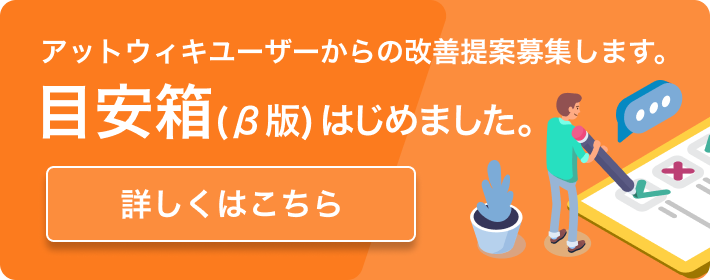あかねと百合
図書館の勉強机にて、演劇部所属の1年生・黒咲あかねは真っ白なノートを目の前にして、自分の才能に疑問を感じていた。
「久遠はどうしてあんなにきれいな脚本が書けるんだろう」
机の端に重ねられた資料は未だ乱れることなくきっちりと並び、買ったばかりの消しゴムも角を保ったまま、ノートと同じように眩しかった。
プロットを迫先輩から任された。こんなに嬉しいことはない。迫先輩のためなら、部員みんなのためなら、劇を見てくれる人のためなら、
誰もが劇を見た後にちょっと幸せになれるような、ささやかなストーリーが書きたい。だけど、幸せの糸を紡ぐことは苦しいこと。
言葉の糸車の針があかねの指にずきりと突き刺さる。痛いと言っていても、無情にも糸は何も織り成すことはない。
あかねの前の真っ白なノートにみんなの笑顔が浮かんでは消えてゆく。『期待』という言葉から耳を塞ぎたくなる。
放課後の時間だけが時計の音ともに削られてゆき、締め切りに徐々に近づいてゆくことに、大人しいあかねは焦りを隠せなかった。
髪の毛を摘む回数が増えてきた。
「久遠はどうしてあんなにきれいな脚本が書けるんだろう」
机の端に重ねられた資料は未だ乱れることなくきっちりと並び、買ったばかりの消しゴムも角を保ったまま、ノートと同じように眩しかった。
プロットを迫先輩から任された。こんなに嬉しいことはない。迫先輩のためなら、部員みんなのためなら、劇を見てくれる人のためなら、
誰もが劇を見た後にちょっと幸せになれるような、ささやかなストーリーが書きたい。だけど、幸せの糸を紡ぐことは苦しいこと。
言葉の糸車の針があかねの指にずきりと突き刺さる。痛いと言っていても、無情にも糸は何も織り成すことはない。
あかねの前の真っ白なノートにみんなの笑顔が浮かんでは消えてゆく。『期待』という言葉から耳を塞ぎたくなる。
放課後の時間だけが時計の音ともに削られてゆき、締め切りに徐々に近づいてゆくことに、大人しいあかねは焦りを隠せなかった。
髪の毛を摘む回数が増えてきた。
「久遠がここにいたらなぁ」
あかねは同じ演劇部1年生・久遠荵と共に、演劇部の先輩から次に発表する劇のプロットを練ってくるように宿題を出されていた。
ゼロから物を作り出す苦しみに耐えて、魅力あるプロットを組み立てることは一日二日で出来るものではないということ。
1年生ながら文才を買われたあかねと荵は、始めはノリノリで書きはじめたものの、ふとしたことで全く筆が動かなくなってしまった。
演劇に携わる者でなくても何となくお分かりであろう。さらに残念なことに、相方である荵はあかねがきょうの作業へと誘う前に
どこかへと消えてしまったのだ。子リスのような荵を捕まえるのは、文章を書くより骨が折れると、あかねは悩む。
あかねは同じ演劇部1年生・久遠荵と共に、演劇部の先輩から次に発表する劇のプロットを練ってくるように宿題を出されていた。
ゼロから物を作り出す苦しみに耐えて、魅力あるプロットを組み立てることは一日二日で出来るものではないということ。
1年生ながら文才を買われたあかねと荵は、始めはノリノリで書きはじめたものの、ふとしたことで全く筆が動かなくなってしまった。
演劇に携わる者でなくても何となくお分かりであろう。さらに残念なことに、相方である荵はあかねがきょうの作業へと誘う前に
どこかへと消えてしまったのだ。子リスのような荵を捕まえるのは、文章を書くより骨が折れると、あかねは悩む。
長いみどりの黒髪が窓から通り抜ける冬の日差しで照らされ、学園を去る生徒たちの歓声が外から楽しそうに聞こえてくる。
静かな図書館の中では、あかねが物語をあれやこれやとひねっては消してと、苦悶していた。
校庭では太陽のような暖かい明るさが輝き、図書館では星のような冷たい光があかねを凍てつかせる。
「どうしたら、部員のみんなが引き立つ本が書けるんだろう」
いつの間にかシャープペンでノートを叩く音が、秒針の音と重なっていたことにあかねは気付かない。
あかねが時計を見ようと顔を上げると、一つ先の机で描いては消して、描いては消してとノートと格闘する女子学生の姿があかねの瞳に映った。
静かな図書館の中では、あかねが物語をあれやこれやとひねっては消してと、苦悶していた。
校庭では太陽のような暖かい明るさが輝き、図書館では星のような冷たい光があかねを凍てつかせる。
「どうしたら、部員のみんなが引き立つ本が書けるんだろう」
いつの間にかシャープペンでノートを叩く音が、秒針の音と重なっていたことにあかねは気付かない。
あかねが時計を見ようと顔を上げると、一つ先の机で描いては消して、描いては消してとノートと格闘する女子学生の姿があかねの瞳に映った。
「あたしの才能はこんなもんじゃない!やに、イメージ通りのデッサンができんきぃ!」
静かな図書館に聞きなれない訛りを響かせ、彼女は消しゴムをノートの上で擦り付けていると、
勢い余って消しゴムを床に落とした。我に返ったその少女は今の言動を少し後悔していたようにあかねに見えた。
図書委員から口にチャックのジェスチャーをされた彼女は、しゅんと縮こまる。
静かな図書館に聞きなれない訛りを響かせ、彼女は消しゴムをノートの上で擦り付けていると、
勢い余って消しゴムを床に落とした。我に返ったその少女は今の言動を少し後悔していたようにあかねに見えた。
図書委員から口にチャックのジェスチャーをされた彼女は、しゅんと縮こまる。
あかねはイスから立ち上がり、少女が落とした消しゴムを拾い上げると、殆ど球状になり黒くすすけた消しゴムを見て自分を恥じる。
(こんなになるまで使ってたんだ。わたしも頑張ってプロット書かなきゃ)
丸い消しゴムは頑張りに正直者だ、とあかねが消しゴムを摘んで見つめていると、聞き慣れない訛りの少女の声があかねに飛び込む。
「ありがと!たすかるきぃ!」
「は、はいっ」
彼女を避けるようにあかねは返事だけを返し、そそくさと自分の席へと戻ったのだが、消しゴムを落とした少女は
あかねに興味が湧いたのか、そっと側に立って机の上の本を見つめていた。
「ね、ちょっと!あなた。その詩集って?」
「これですか。わたしの本ですが」
「そうそう!これって崇人が探しちょったのと同じやん」
(こんなになるまで使ってたんだ。わたしも頑張ってプロット書かなきゃ)
丸い消しゴムは頑張りに正直者だ、とあかねが消しゴムを摘んで見つめていると、聞き慣れない訛りの少女の声があかねに飛び込む。
「ありがと!たすかるきぃ!」
「は、はいっ」
彼女を避けるようにあかねは返事だけを返し、そそくさと自分の席へと戻ったのだが、消しゴムを落とした少女は
あかねに興味が湧いたのか、そっと側に立って机の上の本を見つめていた。
「ね、ちょっと!あなた。その詩集って?」
「これですか。わたしの本ですが」
「そうそう!これって崇人が探しちょったのと同じやん」
あかねが「創作の参考に」と自分の家から持ち込んだとある詩集。
自分が好きな詩集を学園のどこかの誰かが探すほど好きでいてくれる人がいるなんて、ちょっと嬉しいじゃないか。
少女のいう『崇人』という人物とは、誰なのだろう。あかねは少し見知らぬ『崇人』という人物に興味が湧いた。
訛りの少女は、あかねの詩集を手にして瞳を輝かせていた。
「出来ればでいがやけど、お手すきになったら崇人に見せに行きたいんがや」
「今、とてもお手すきですっ」
用事はある。だけど、書こうとするから書けないのだ。だったら少し手を離してお話に乗ればいい。あかねの決断は早かった。
未だに文字が書かれることの無いノートを閉じると、あかねは目の前の少女の後を付いて行くことにした。
胸に詩集と未知なる興奮を抱えて。
自分が好きな詩集を学園のどこかの誰かが探すほど好きでいてくれる人がいるなんて、ちょっと嬉しいじゃないか。
少女のいう『崇人』という人物とは、誰なのだろう。あかねは少し見知らぬ『崇人』という人物に興味が湧いた。
訛りの少女は、あかねの詩集を手にして瞳を輝かせていた。
「出来ればでいがやけど、お手すきになったら崇人に見せに行きたいんがや」
「今、とてもお手すきですっ」
用事はある。だけど、書こうとするから書けないのだ。だったら少し手を離してお話に乗ればいい。あかねの決断は早かった。
未だに文字が書かれることの無いノートを閉じると、あかねは目の前の少女の後を付いて行くことにした。
胸に詩集と未知なる興奮を抱えて。
人前に出る部活の癖に、恥ずかしがり屋というところを突っ込まれやしないか、とあかねは手に汗を握っていたが杞憂に終わる。
素朴な香り漂う垢抜けない訛りで士乃は、妹のような先輩振りであかねの気持ちを和らげる。
「ちょっと、あたしたちの部室に寄っていかん?創作部っち言ってなあ」
「創作。そうさく。……何かを作るんですか?」
「そうな。そうそう、自己紹介まだじゃったね。あたしは浅野士乃。よろしゅう」
「……わ、わ、わたしは。黒咲あかねですっ。演劇部の1年生ですっ」
「それじゃあ、あたしはあかねちゃんの先輩やん」
士乃の横顔を見るだけで精一杯のあかねは、見せるのが恥かしいくらい頬が赤くなっていた。
素朴な香り漂う垢抜けない訛りで士乃は、妹のような先輩振りであかねの気持ちを和らげる。
「ちょっと、あたしたちの部室に寄っていかん?創作部っち言ってなあ」
「創作。そうさく。……何かを作るんですか?」
「そうな。そうそう、自己紹介まだじゃったね。あたしは浅野士乃。よろしゅう」
「……わ、わ、わたしは。黒咲あかねですっ。演劇部の1年生ですっ」
「それじゃあ、あたしはあかねちゃんの先輩やん」
士乃の横顔を見るだけで精一杯のあかねは、見せるのが恥かしいくらい頬が赤くなっていた。
―――「先輩!あそこにも初々しいカップルが並んでます!なんと一人は頬が真っ赤です!」
「ほんとだね!男の子の方は、女の子の横顔を見るだけで精一杯なんだ!この!恋愛仮免講習受講者め!」
演劇部部室では、久遠荵と近森ととろが窓から仁科学園から帰り行く『恋愛若葉』を観察していた。
カップルの幸せを見せていただきながら、幸せをご相伴にあずかるととろは「下校する生徒がよく見えるから」と言って、
演劇部部室に放課後から入り浸っている。この日は先輩たちが部室に来る予定はないので、勝手気ままに部屋を使えるわけだ。
「人物観察は演技の練習の基本のキ!勉強になります!!迫先輩も熱弁していたことですの!」と、
荵は小さな身体をめい一杯使って、ととろの訪問を歓迎していたが、迫先輩からのプロットの宿題のことなどすっかり忘れていたのだった。
「ほんとだね!男の子の方は、女の子の横顔を見るだけで精一杯なんだ!この!恋愛仮免講習受講者め!」
演劇部部室では、久遠荵と近森ととろが窓から仁科学園から帰り行く『恋愛若葉』を観察していた。
カップルの幸せを見せていただきながら、幸せをご相伴にあずかるととろは「下校する生徒がよく見えるから」と言って、
演劇部部室に放課後から入り浸っている。この日は先輩たちが部室に来る予定はないので、勝手気ままに部屋を使えるわけだ。
「人物観察は演技の練習の基本のキ!勉強になります!!迫先輩も熱弁していたことですの!」と、
荵は小さな身体をめい一杯使って、ととろの訪問を歓迎していたが、迫先輩からのプロットの宿題のことなどすっかり忘れていたのだった。
「ととろ先輩!いつでもここを使っていいから、これからもわたしにも金平糖のような甘くて刺々しい恋の蜜を味あわせてくらさい!」
「そ、そうね。荵ちゃんって……やっぱり演劇部向きだね」
「でも、わたしが芸事の道を選んだのは、あかねちゃんの姿を見たからですよ。わたしはあかねちゃんになりたい!
大人びた性格に、すらりと伸びた長身!何故、芸能の神・アメノウズメは、わたしにこんな試練を与えたのか!」
子どもっぽい容姿に、ちっこい背丈の荵は、声を大にして叫んだ。
中庭で先輩たちとエチュード(即興の演劇練習)をしているあかねの演技に惚れたからだと、荵は語る。
芝生だらけの中庭に茜の花が咲き誇っていたと、荵は語る。
「そ、そうね。荵ちゃんって……やっぱり演劇部向きだね」
「でも、わたしが芸事の道を選んだのは、あかねちゃんの姿を見たからですよ。わたしはあかねちゃんになりたい!
大人びた性格に、すらりと伸びた長身!何故、芸能の神・アメノウズメは、わたしにこんな試練を与えたのか!」
子どもっぽい容姿に、ちっこい背丈の荵は、声を大にして叫んだ。
中庭で先輩たちとエチュード(即興の演劇練習)をしているあかねの演技に惚れたからだと、荵は語る。
芝生だらけの中庭に茜の花が咲き誇っていたと、荵は語る。
「でも、負けないもん!わたしは先輩の後ろにある棚の百合の花でさえ、笑顔にしてみせるよ!!百合の花よ、咲き誇れ!」
花瓶に生けられた百合の花は、荵に呆れたように静かに二人を見つめていた。
花瓶に生けられた百合の花は、荵に呆れたように静かに二人を見つめていた。
「ところで、ととろ先輩。ソレ、何の格好です?」
荵が気にするのも無理は無い。ケモノ耳のようなものが付いたヘルメットにハート型のアイシールド。
制服の上には勇者のようなマント、そして純白の手袋。おまけに魔法のステッキを手にしたととろは、瞳を輝かせ腕を振り上げる。
「良くぞ聞いてくれた!他人の恋路を邪魔するものは、ウマに蹴られて地獄に落ちろ!謎の美少女戦士カップルウォッチャー、ここにあり!」
決め台詞のようなものを一通り叫ぶと、ととろはひょいとマントをなびかせてイスに飛び乗る。
そして、ここには居もしないカップルを探すように、きょろきょろと心躍らせた様子で周りを見渡したのだった。
「しあわせゲージMAXなカップルはどこだ!?」
荵が気にするのも無理は無い。ケモノ耳のようなものが付いたヘルメットにハート型のアイシールド。
制服の上には勇者のようなマント、そして純白の手袋。おまけに魔法のステッキを手にしたととろは、瞳を輝かせ腕を振り上げる。
「良くぞ聞いてくれた!他人の恋路を邪魔するものは、ウマに蹴られて地獄に落ちろ!謎の美少女戦士カップルウォッチャー、ここにあり!」
決め台詞のようなものを一通り叫ぶと、ととろはひょいとマントをなびかせてイスに飛び乗る。
そして、ここには居もしないカップルを探すように、きょろきょろと心躍らせた様子で周りを見渡したのだった。
「しあわせゲージMAXなカップルはどこだ!?」
―――「ここやち。ここやきん」
士乃があかねを連れて仁科学園創作部の部室を紹介すると、あかねはきょろきょろと落ち着かない様子で周りを見渡した。
通い慣れたいつもの校舎の中だというのに、行ったこともない土地に放り出されたような気持ちに包まれるあかねの頬は赤い。
「まあ、お茶でも飲んでいってん」
人懐っこい士乃の笑顔があかねにとっての救い。薄っぺらい扉を開くと、物の数だけの匂いがふんわりと二人を包んだ。
士乃があかねを連れて仁科学園創作部の部室を紹介すると、あかねはきょろきょろと落ち着かない様子で周りを見渡した。
通い慣れたいつもの校舎の中だというのに、行ったこともない土地に放り出されたような気持ちに包まれるあかねの頬は赤い。
「まあ、お茶でも飲んでいってん」
人懐っこい士乃の笑顔があかねにとっての救い。薄っぺらい扉を開くと、物の数だけの匂いがふんわりと二人を包んだ。
「りっちゃん、こんちはー」
「士乃ちゃん、お客さん?」
「うん。初々しいお嬢ちゃんじゃの!なのに、崇人が居らんき!どこに行ったー」
ぐっと両手を握った士乃は、部屋一杯に声を響かせながら崇人という男子生徒の名を叫んでいた。
同輩に呆れている『りっちゃん』と呼ばれた少女は、士乃に隠れるように立つあかねに気が付くと、手にしていた雑誌を静かに閉じた。
初めての場所に戸惑うあかねは、右手で左の腕を握り締めて肩をすぼめて自分を落ち着けと言い聞かせる。
脚をぶらぶらとさせながら、軋む木のイスに座る『りっちゃん』は創作部の部員。士乃は彼女の両肩にぽんと手をかける。
「ま、ちっちゃいけどお気楽に。この子がりっちゃん、あたしと同じ2年」
「金城葎です。よろしくねー、って誰がちっちゃいねん!!」
葎が士乃の言葉に反応してイスから飛び上げる。事実、葎が立ち上がっても彼女の目線は、あかねの胸ほどの高さしかない。
士乃は「ちっちゃいのは、部室ち言ったんやん」と士乃のブレザーを引っ張る葎をなだめるが、
あかねの目にはどうしても士乃が葎のことを『ちっちゃい』と言ったようにしか見えなかった。
「士乃ちゃん、お客さん?」
「うん。初々しいお嬢ちゃんじゃの!なのに、崇人が居らんき!どこに行ったー」
ぐっと両手を握った士乃は、部屋一杯に声を響かせながら崇人という男子生徒の名を叫んでいた。
同輩に呆れている『りっちゃん』と呼ばれた少女は、士乃に隠れるように立つあかねに気が付くと、手にしていた雑誌を静かに閉じた。
初めての場所に戸惑うあかねは、右手で左の腕を握り締めて肩をすぼめて自分を落ち着けと言い聞かせる。
脚をぶらぶらとさせながら、軋む木のイスに座る『りっちゃん』は創作部の部員。士乃は彼女の両肩にぽんと手をかける。
「ま、ちっちゃいけどお気楽に。この子がりっちゃん、あたしと同じ2年」
「金城葎です。よろしくねー、って誰がちっちゃいねん!!」
葎が士乃の言葉に反応してイスから飛び上げる。事実、葎が立ち上がっても彼女の目線は、あかねの胸ほどの高さしかない。
士乃は「ちっちゃいのは、部室ち言ったんやん」と士乃のブレザーを引っ張る葎をなだめるが、
あかねの目にはどうしても士乃が葎のことを『ちっちゃい』と言ったようにしか見えなかった。
「はいはい、りっちゃんは席に戻って。新しいお友達が自己紹介するきい」
あかねは舞台に立ったつもりで黒タイツの脚をそろえお辞儀をする。長く伸ばした黒髪が一緒に揺れる。
ここが舞台なら怖いものは無い。舞台はみんなで作るもの。先輩たちも一緒だから怖くない。
先輩たちは舞台を見に来たお客さんと思えばいいじゃないか。舞台仕込みのよく通った声で自分の名前を伝える。
色白の頬を牡丹のように赤く染めながら、堂々と自己紹介を終えたあかねは立派な『役者』だった。
挨拶を終えると、演劇部に居ながら恥ずかしがり屋であるあかねは、創作部の二人に目を合わせようとすることはなかった。
あかねは舞台に立ったつもりで黒タイツの脚をそろえお辞儀をする。長く伸ばした黒髪が一緒に揺れる。
ここが舞台なら怖いものは無い。舞台はみんなで作るもの。先輩たちも一緒だから怖くない。
先輩たちは舞台を見に来たお客さんと思えばいいじゃないか。舞台仕込みのよく通った声で自分の名前を伝える。
色白の頬を牡丹のように赤く染めながら、堂々と自己紹介を終えたあかねは立派な『役者』だった。
挨拶を終えると、演劇部に居ながら恥ずかしがり屋であるあかねは、創作部の二人に目を合わせようとすることはなかった。
「……よろしくね。あかねちゃん」
「まさか、ここで『あーちゃん』と会うとは思わんかったけんなあ」
葎の雑誌をちらりと覗き込んだ士乃の言葉は、あかねをますます赤くさせてゆく。
自分のことを知っている人がいる。しかも、かなり前から……。
「まさか、ここで『あーちゃん』と会うとは思わんかったけんなあ」
葎の雑誌をちらりと覗き込んだ士乃の言葉は、あかねをますます赤くさせてゆく。
自分のことを知っている人がいる。しかも、かなり前から……。
「読者モデルを辞めてから、どうしちょるのかなあって思っとったら、奇跡の巡り合いやん。あたし高知で毎月読んでたき!」
「そうね!もしかして、どこかで見たことあると思ったら『プチ・ポップ』に出てた『あーちゃん』?」
「そうね!もしかして、どこかで見たことあると思ったら『プチ・ポップ』に出てた『あーちゃん』?」
××××××××××××××××××
小学生時代、黒咲あかねは『あーちゃん』と呼ばれていた。
実際に呼ばれていたのは、雑誌の上でのこと。『あーちゃん』は毎月きれいな服を着て、大人びたメイクを体験して、
そして日本中の読者から羨望の眼差しを受けながら、限られた紙面を華やかに飾っていた。
そう。黒咲あかねは、小中学生向けのファッション雑誌『プチ・ポップ』の読者モデルであったのだ。
ファッション誌に出ることになったのは、クラスメイトの推薦からであった。「あかねはきっと人気出るよ」と。
その言葉はうそではなかった。人気も出た。誰もがちやほやしてくれた。クラスメイトも一目置いてくれた。
でも、それは『あーちゃん』に向けてだ。『あーちゃん』は『黒咲あかね』なんて子は知りません。何処の誰ですか。
『あーちゃん』は『あーちゃん』の場所でしか生きることができない、花壇の花のような存在だったのだ。
実際に呼ばれていたのは、雑誌の上でのこと。『あーちゃん』は毎月きれいな服を着て、大人びたメイクを体験して、
そして日本中の読者から羨望の眼差しを受けながら、限られた紙面を華やかに飾っていた。
そう。黒咲あかねは、小中学生向けのファッション雑誌『プチ・ポップ』の読者モデルであったのだ。
ファッション誌に出ることになったのは、クラスメイトの推薦からであった。「あかねはきっと人気出るよ」と。
その言葉はうそではなかった。人気も出た。誰もがちやほやしてくれた。クラスメイトも一目置いてくれた。
でも、それは『あーちゃん』に向けてだ。『あーちゃん』は『黒咲あかね』なんて子は知りません。何処の誰ですか。
『あーちゃん』は『あーちゃん』の場所でしか生きることができない、花壇の花のような存在だったのだ。
「あーちゃん、こんなに読者からのハガキが来てるよ」
「う、うん。ありがとう」
「いいなあ、あーちゃん。わたしにはこんなに来ないんだもん。超羨ましいなあ」
「カラーページ独り占めだもんね」
「はは……。やめてよ」
うそばっかり。他の子は自分がもっと目立ちたいんだ、って思っているんだ。
読者モデル仲間からの言葉を薄っすらと鋭い瞳で見抜く『黒咲あかね』は『あーちゃん』ではない。
仲間が太陽のような笑顔になればなるほど、分かり易いウソをかばう氷がゆっくり雫をたらす。
「う、うん。ありがとう」
「いいなあ、あーちゃん。わたしにはこんなに来ないんだもん。超羨ましいなあ」
「カラーページ独り占めだもんね」
「はは……。やめてよ」
うそばっかり。他の子は自分がもっと目立ちたいんだ、って思っているんだ。
読者モデル仲間からの言葉を薄っすらと鋭い瞳で見抜く『黒咲あかね』は『あーちゃん』ではない。
仲間が太陽のような笑顔になればなるほど、分かり易いウソをかばう氷がゆっくり雫をたらす。
「人気いちばんだからね。『あーちゃん』は」
「わたしも『あーちゃん』みたいに、カラーページを独り占めしたいな。あ!このバッグかわいい」
出来ることなら何もかも砕く金槌で、あかねの手を冷やす氷を砕きたい。あかねは氷を持ち続けながら、
『あーちゃん』にしか出来ない、妙に大人びたウソ笑いを一緒に読モ仲間と分け合うだけだった。
お遊びの仲間だなんて、誰に何の得になる。たまたま同じ雑誌に載っているだけじゃないか。
「わたしも『あーちゃん』みたいに、カラーページを独り占めしたいな。あ!このバッグかわいい」
出来ることなら何もかも砕く金槌で、あかねの手を冷やす氷を砕きたい。あかねは氷を持ち続けながら、
『あーちゃん』にしか出来ない、妙に大人びたウソ笑いを一緒に読モ仲間と分け合うだけだった。
お遊びの仲間だなんて、誰に何の得になる。たまたま同じ雑誌に載っているだけじゃないか。
わたし『黒咲あかね』は『あーちゃん』なんて子は知りません。何処の誰ですか。いっそのこと、無視してくださいな。
『黒咲あかね』は『あーちゃん』を一人ぼっちにしたかった。
『黒咲あかね』は『あーちゃん』を一人ぼっちにしたかった。
××××××××××××××××××
創作部の部室では、雑誌を読み飽きた葎が何やら図面を真っ白いケント紙に起していた。
「おっ。りっちゃん、きょうもペンの調子がいいやん」
「思い付いたときに図面を起さないと、すぐに忘れちゃう」
「おお、そうや。あたしも新作のデザインをしちょるところやった」
ぽんと手を鳴らした士乃は、くるりと周りスカートを揺らす。
あかねは部屋の中にはたくさんの本、焼き物、そして玩具に視線を奪われていた。
「おっ。りっちゃん、きょうもペンの調子がいいやん」
「思い付いたときに図面を起さないと、すぐに忘れちゃう」
「おお、そうや。あたしも新作のデザインをしちょるところやった」
ぽんと手を鳴らした士乃は、くるりと周りスカートを揺らす。
あかねは部屋の中にはたくさんの本、焼き物、そして玩具に視線を奪われていた。
「あかねちゃん!ここはね『創作部』だから、何でも作るのよ」
「そうなんですね。あの……金城さんは……」
「りっちゃんはね、玩具ばっかり作りよるよ。鉄砲とか鉄砲とか……」
葎の目の前の紙に、士乃は手にしていたシャープペンでうずまき落書きの攻撃をする。
「し、士乃ちゃん!わたしの傑作が渦に巻き込まれたよ!」
あはは、と笑う士乃に対して葎は困ったような、笑っているような顔をしていた。
どうしたらいいのか分からず立ちすくむあかねは、とりあえずエチュードで学んだ「何でもいいから、話を途中で切らすな」の教えを思い出し、
思い切って士乃に話を振ってみる。士乃なら何か答えを返してくれると微かな期待を抱いたからだ。
「あの、士乃さんは……何を作っているんですかっ」
「あたしは焼き物をやってるよ。でも」
士乃の背後に並んだ作品たちが、光に照らされて誇らしげに見えた。自己主張もせず、ただたたずむだけの花瓶に皿たちは、
どれもこれも美しい。しかし、急に真面目な顔になった士乃は、ダンボールに乱雑に入れられた花瓶を手にする。
「……やっぱり、これ」
花瓶には『審議中』の付箋紙が付けられていた。
「そうなんですね。あの……金城さんは……」
「りっちゃんはね、玩具ばっかり作りよるよ。鉄砲とか鉄砲とか……」
葎の目の前の紙に、士乃は手にしていたシャープペンでうずまき落書きの攻撃をする。
「し、士乃ちゃん!わたしの傑作が渦に巻き込まれたよ!」
あはは、と笑う士乃に対して葎は困ったような、笑っているような顔をしていた。
どうしたらいいのか分からず立ちすくむあかねは、とりあえずエチュードで学んだ「何でもいいから、話を途中で切らすな」の教えを思い出し、
思い切って士乃に話を振ってみる。士乃なら何か答えを返してくれると微かな期待を抱いたからだ。
「あの、士乃さんは……何を作っているんですかっ」
「あたしは焼き物をやってるよ。でも」
士乃の背後に並んだ作品たちが、光に照らされて誇らしげに見えた。自己主張もせず、ただたたずむだけの花瓶に皿たちは、
どれもこれも美しい。しかし、急に真面目な顔になった士乃は、ダンボールに乱雑に入れられた花瓶を手にする。
「……やっぱり、これ」
花瓶には『審議中』の付箋紙が付けられていた。
「女の子と焼き物は同じやきん。みんなに見られれば見られるほど綺麗になってゆく。でも、そればかりがやない。
ダメなものはダメじゃったりする。いちばんタチが悪りいのは、自分がダメなことに気付かんこと。
もっとダメなもんはダメなもんでも、周りからおだてられて自分がダメなことに気付かんこと。
いちばん大事なのはそれが分かっちょる人が、いつも側にいちあげることやと思うの。大切なことやけん」
手にしていた一枚の陶製の花瓶を士乃が天に向かって持ち上げる。
「この子もこうしてダメっち気付かせちゃる方が、幸せじゃったりするがかも。って、なーんちね」
誰だって、自分が作ったものは愛しい。だけど士乃はそれを見切ることも一つの愛情だと、静かに自分を抑えながら語り、
テラスへの扉を静かに開いた。コンクリートの床はあかねには冷徹に見えた。温厚な空は裏腹に青い。
士乃の振り上げられた腕には士乃が作った白い花瓶。「やけに青空に映える白さやん」と士乃は花瓶を見つめていた。
己の行く末を悟った花瓶は、生みの親の教えに逆らうことなく地面に飛び込む覚悟であった。
ダメなものはダメじゃったりする。いちばんタチが悪りいのは、自分がダメなことに気付かんこと。
もっとダメなもんはダメなもんでも、周りからおだてられて自分がダメなことに気付かんこと。
いちばん大事なのはそれが分かっちょる人が、いつも側にいちあげることやと思うの。大切なことやけん」
手にしていた一枚の陶製の花瓶を士乃が天に向かって持ち上げる。
「この子もこうしてダメっち気付かせちゃる方が、幸せじゃったりするがかも。って、なーんちね」
誰だって、自分が作ったものは愛しい。だけど士乃はそれを見切ることも一つの愛情だと、静かに自分を抑えながら語り、
テラスへの扉を静かに開いた。コンクリートの床はあかねには冷徹に見えた。温厚な空は裏腹に青い。
士乃の振り上げられた腕には士乃が作った白い花瓶。「やけに青空に映える白さやん」と士乃は花瓶を見つめていた。
己の行く末を悟った花瓶は、生みの親の教えに逆らうことなく地面に飛び込む覚悟であった。
―――陶器の割れる音が部室に響く。居合わせたものの視線をひきつける。粉々に散った破片が力なく横たわる。
そして静寂だけが二人を包み込む。
「……どうするの」
「わたし?ちょ、ちょっと!ととろせんぱーい!」
ちょっとはしゃいだつもりだった。ちょっと調子に乗ったつもりだった。荵のちょっとが騒ぎになるとはととろも思っていなかった。
荵はととろから『カップルウォッチャー』の衣装をちょっと借りて、自分もととろになった気になっていた。
ととろがイスから飛び降りたなら、わたしは机から飛んでやる。上靴を脱ぎ、小柄な身体で机に飛び乗る。
「カップルウォッチャーしのぶ、ここにありー!」
「ちょ、ちょ?易々とカップルウォッチャーの座を渡してたまるものかあ!」
そして静寂だけが二人を包み込む。
「……どうするの」
「わたし?ちょ、ちょっと!ととろせんぱーい!」
ちょっとはしゃいだつもりだった。ちょっと調子に乗ったつもりだった。荵のちょっとが騒ぎになるとはととろも思っていなかった。
荵はととろから『カップルウォッチャー』の衣装をちょっと借りて、自分もととろになった気になっていた。
ととろがイスから飛び降りたなら、わたしは机から飛んでやる。上靴を脱ぎ、小柄な身体で机に飛び乗る。
「カップルウォッチャーしのぶ、ここにありー!」
「ちょ、ちょ?易々とカップルウォッチャーの座を渡してたまるものかあ!」
ととろを真似て、机から飛ぶ降りる。荵には長すぎる長いマントがゆっくりと捲り上げる。
が、荵が机から飛び降りるものの、着地に失敗。紺色ハイソの足で床を滑る。両手をぶんぶんと振りながら
足をふらつかせて壁に向かって体勢を立て直すものの、運悪く棚の上の百合の花が生けられた花瓶をピンク色のステッキでジャストミート。
魔法のステッキで一撃された花瓶と百合の花は、床を目掛けてまっ逆さまに床に吸い込まれた。そして、大きな音を立てて百合の花は黙り込む。
百合の花を拾い上げようと荵は床にしゃがむが「役者が手を怪我したら危ないよ!」と、ととろから手を掴まれた。
が、荵が机から飛び降りるものの、着地に失敗。紺色ハイソの足で床を滑る。両手をぶんぶんと振りながら
足をふらつかせて壁に向かって体勢を立て直すものの、運悪く棚の上の百合の花が生けられた花瓶をピンク色のステッキでジャストミート。
魔法のステッキで一撃された花瓶と百合の花は、床を目掛けてまっ逆さまに床に吸い込まれた。そして、大きな音を立てて百合の花は黙り込む。
百合の花を拾い上げようと荵は床にしゃがむが「役者が手を怪我したら危ないよ!」と、ととろから手を掴まれた。
―――あかねは士乃の振り上げた花瓶を持った手を掴んでいた。抱えていた詩集が花瓶の代わりにテラスに落ちた。
「この子だって、どこか光る場所があるはずです!」
「……」
「みんなで作る……、みんなで育てる…。そして、みんなで気付いてあげる、ってわたし、生意気すぎましたね。ごめんなさい」
静かに士乃の腕から手を離し、いつもの恥かしがり屋さんに戻ったあかねの背中をポンと叩くのは葎だった。
葎の小さな体は、あかねには自分を包み込む『アネキ』に見えた。
「この子だって、どこか光る場所があるはずです!」
「……」
「みんなで作る……、みんなで育てる…。そして、みんなで気付いてあげる、ってわたし、生意気すぎましたね。ごめんなさい」
静かに士乃の腕から手を離し、いつもの恥かしがり屋さんに戻ったあかねの背中をポンと叩くのは葎だった。
葎の小さな体は、あかねには自分を包み込む『アネキ』に見えた。
「ははは!あかねちゃん!よく言ったね。士乃にはいいクスリだよ。いっつもガッチャンガッチャン割ってこっちはうるさくて」
「りっちゃん!あたしは芸術家としてこだわりを通したきぃ!!でも……」
「でも?」
「何て言えばいいんだろう。あかねちゃん、ありがとう。よかったらいいんやけど、この花瓶、演劇部で使ってくれる……かえ」
士乃の言葉にこれまで以上にあかねが頬を赤らめていると、メガネを光らせる男子生徒が部室に入ってきた。
「士乃ー?聞いたぞ、聞いたぞ。何時になくお姉さん振っているな!後輩を見るとすぐこれだ」
「崇人!!あたしは、この仁科学園の先輩としてあかねちゃんに……崇人!!崇人が『このデザインがいい』っち言うたけん、
あたしは全身全霊をかけて仕上げたんやに!それに、なんじゃ?崇人の作った詩は、みんなが喜んでもわたしは響かんきい!」
「士乃ったら。きのうさ、こっそりと崇人の詩を何度も口ずさんでたくせにね」
「う、うるさいっ。りっちゃんは、早く自分の玩具を仕上げる!やないと、また『ぐるぐる攻撃』しちゃるきん!」
あかねは創作部のみんなで作品を作ってみんなで語り合うという、創作マインドに心打たれ、
先輩たちの持つ作品への愛情に自分の創作意欲を沸き立たせていたのであった。だが、あかねの脳裏に蘇ったのは、迫先輩からの宿題だった。
「りっちゃん!あたしは芸術家としてこだわりを通したきぃ!!でも……」
「でも?」
「何て言えばいいんだろう。あかねちゃん、ありがとう。よかったらいいんやけど、この花瓶、演劇部で使ってくれる……かえ」
士乃の言葉にこれまで以上にあかねが頬を赤らめていると、メガネを光らせる男子生徒が部室に入ってきた。
「士乃ー?聞いたぞ、聞いたぞ。何時になくお姉さん振っているな!後輩を見るとすぐこれだ」
「崇人!!あたしは、この仁科学園の先輩としてあかねちゃんに……崇人!!崇人が『このデザインがいい』っち言うたけん、
あたしは全身全霊をかけて仕上げたんやに!それに、なんじゃ?崇人の作った詩は、みんなが喜んでもわたしは響かんきい!」
「士乃ったら。きのうさ、こっそりと崇人の詩を何度も口ずさんでたくせにね」
「う、うるさいっ。りっちゃんは、早く自分の玩具を仕上げる!やないと、また『ぐるぐる攻撃』しちゃるきん!」
あかねは創作部のみんなで作品を作ってみんなで語り合うという、創作マインドに心打たれ、
先輩たちの持つ作品への愛情に自分の創作意欲を沸き立たせていたのであった。だが、あかねの脳裏に蘇ったのは、迫先輩からの宿題だった。
「そうだ!プロット!!」
あかねは、白紙のノートを抱えて恥かしそうに廊下側の扉に向い、創作部の面々に深々とお辞儀をする。
「創作部にまた遊びに来てね」と、葎から見送られたあかねは、再びこの部屋へ来ることを誓い、演劇部の部室に戻る。
士乃が一度は投げようとした花瓶を大事そうに抱えて……。
あかねは、白紙のノートを抱えて恥かしそうに廊下側の扉に向い、創作部の面々に深々とお辞儀をする。
「創作部にまた遊びに来てね」と、葎から見送られたあかねは、再びこの部屋へ来ることを誓い、演劇部の部室に戻る。
士乃が一度は投げようとした花瓶を大事そうに抱えて……。
あかねが演劇部部室に入ると、人影は全くなかった。
魔法少女の衣装のようなマントにヘルメットが残されていたが、あかねは「初等部向けの劇でもするのかな」程度に思っていた。
そして、他にあるのもと言えば、暇を持て余した机とイス。そして、水の張ったバケツに生けられた百合の花。
折角の百合の花がこのままではかわいそうと哀れんだあかねは、バケツから士乃から譲り受けた花瓶に水を差し、
百合の花を生けることにした。士乃は始め気に入らなかったものの、やはり花瓶は花をいけると、
水を得た魚のようにいきいきと見えてくるのは、花瓶に感情があるからなのだろうか。
魔法少女の衣装のようなマントにヘルメットが残されていたが、あかねは「初等部向けの劇でもするのかな」程度に思っていた。
そして、他にあるのもと言えば、暇を持て余した机とイス。そして、水の張ったバケツに生けられた百合の花。
折角の百合の花がこのままではかわいそうと哀れんだあかねは、バケツから士乃から譲り受けた花瓶に水を差し、
百合の花を生けることにした。士乃は始め気に入らなかったものの、やはり花瓶は花をいけると、
水を得た魚のようにいきいきと見えてくるのは、花瓶に感情があるからなのだろうか。
「……よしっ」
部室の棚に、一輪の花を置く。たったそれだけなのに、まるで美しいクラシック音楽に浸るような贅沢な気分になる。
じっくり百合の花を観賞しようとあかねは、一歩一歩後ずさり。開けっ放しの窓からの風は冷たかったが、美しい花を見ていると心地よく感じる。
しかし、静かに花を愛でていたあかねの時間は、荵の声で閉ざされた。あかねは同時に頬を赤らめる。
何故なら、荵と共に部屋にやって来たのはととろと、そして迫だったのだから。
迫の腕にコアラのようにしがみ付きながら、わめきたてる荵はどう見てもお子ちゃまであった。
部室の棚に、一輪の花を置く。たったそれだけなのに、まるで美しいクラシック音楽に浸るような贅沢な気分になる。
じっくり百合の花を観賞しようとあかねは、一歩一歩後ずさり。開けっ放しの窓からの風は冷たかったが、美しい花を見ていると心地よく感じる。
しかし、静かに花を愛でていたあかねの時間は、荵の声で閉ざされた。あかねは同時に頬を赤らめる。
何故なら、荵と共に部屋にやって来たのはととろと、そして迫だったのだから。
迫の腕にコアラのようにしがみ付きながら、わめきたてる荵はどう見てもお子ちゃまであった。
「さこせんぱぁーい!わたし、花瓶を割っちゃったんですぅ!!わたしはなんて愚かな子羊なんでしょう!」
「荵ちゃん!泣かないで!!荵が泣くならわたしも泣くよ!恋に破れた乙女を癒すのは、同じく恋に破れた乙女だけだからね!」
荵の後から付いて来るととろを気恥ずかしそうに眺めるあかねは、右手で左の腕を握り締めて肩をすぼめていた。
ところが、と言うより当然なのだが、あかねが生けた百合の花をじっと見つめた迫は、メガネを光らせて目を細める。
「久遠、子羊に謝れ。ウソをつくのもいい加減にしろよ」
「もしかして、奇跡が起こった?!天上界の神々はわたしたち子羊を見捨ててなかったのですの!ねえ!あかねちゃん……っていない!」
百合の花が生けられた花瓶を目にした荵は、あかねが生けたことを知らずに目を輝かせていた。
「荵ちゃん!泣かないで!!荵が泣くならわたしも泣くよ!恋に破れた乙女を癒すのは、同じく恋に破れた乙女だけだからね!」
荵の後から付いて来るととろを気恥ずかしそうに眺めるあかねは、右手で左の腕を握り締めて肩をすぼめていた。
ところが、と言うより当然なのだが、あかねが生けた百合の花をじっと見つめた迫は、メガネを光らせて目を細める。
「久遠、子羊に謝れ。ウソをつくのもいい加減にしろよ」
「もしかして、奇跡が起こった?!天上界の神々はわたしたち子羊を見捨ててなかったのですの!ねえ!あかねちゃん……っていない!」
百合の花が生けられた花瓶を目にした荵は、あかねが生けたことを知らずに目を輝かせていた。
―――その頃、創作部部室にて。
崇人が詩を書き連ねていると、横で士乃の焼き物を光に当てて眺めていた葎が呟く。
「あかねちゃん、また来てくれるかなあ」
葎と背中合わせの士乃が、自分の作品を我が子のように抱きしめながら質問に答える。
崇人が詩を書き連ねていると、横で士乃の焼き物を光に当てて眺めていた葎が呟く。
「あかねちゃん、また来てくれるかなあ」
葎と背中合わせの士乃が、自分の作品を我が子のように抱きしめながら質問に答える。
「来るよ、きっと。今度はあたしの最高傑作をあかねちゃんに見せちゃるき!」
「はいはい。それじゃ、今度あかねちゃんが来るまでに、幾つ焼き物が割られるか……崇人、ジュース賭けない?わたしは8個!」
「おれ、10個」
「ななな?あたしの才能を見くびっちゃいかんちや!一発で……」
士乃が両手を握って部室一杯に声を上げると、扉を叩く音がする。訪ねた者の声を聞いて瞳を輝かせたのは士乃だった。
「あのー、演劇部の黒咲あかねです。確か、詩集を……」
「はいはい。それじゃ、今度あかねちゃんが来るまでに、幾つ焼き物が割られるか……崇人、ジュース賭けない?わたしは8個!」
「おれ、10個」
「ななな?あたしの才能を見くびっちゃいかんちや!一発で……」
士乃が両手を握って部室一杯に声を上げると、扉を叩く音がする。訪ねた者の声を聞いて瞳を輝かせたのは士乃だった。
「あのー、演劇部の黒咲あかねです。確か、詩集を……」
おしまい。