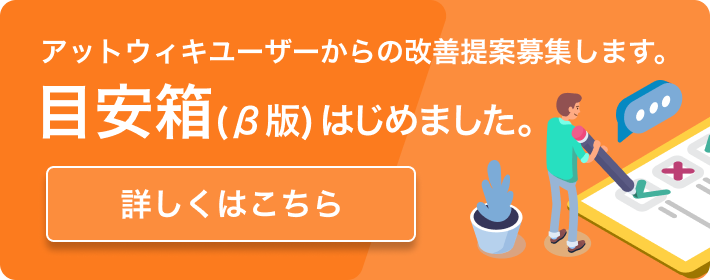責任転嫁。
自分の罪・責任などを他になすりつけること。
責任を転嫁する。
つまり、責任転嫁。
空から舞い降りる無数の白。
白い、何処までも真っ白な花。
花ではないのに、花の名を冠する存在。
六花。
儚い花。
眼にした次の瞬間には消えてしまう、切ない花。
けれどそれは確実に存在していて。
この世界を、真っ白に染めていた。
暦は如月。
冷え込みが最も厳しくなる季節。
昨日の夜から降り始めた雪は、日付が変わった今も、変わることなく降っていた。
友人の話によれば、ここ一番の大雪になるそうだ。
そのため、村の連中は朝から忙しげに大雪対策に勤しんでいる。
そんな中。
「……」
俺は炎に焦がされていた。
朝から部屋の真ん中で大の字になって倒れたまま。
全身を憤怒という名の紅蓮が覆いつくしている。
視界には、少しボロが目立つ我が家の天井。
雪の重みで壊れないだろうか?
ふとそう思ったが、雪卸しをする気は起きなかった。
何故だろう。
雪の日はとても静かだ。
まるで世界から音が消えたかのよう。
この無音が恐ろしいという人も居るが、今の自分にはそれがとても心地良かった。
しんとした静寂が、己が身を焦がすほどの業火を少しだけ沈めてくれる……そんな気がした。
そんなこと、あるワケがないのに。
自嘲気味に笑って、溜息。
そして再び憤怒の炎が俺を焦がした。
顔が歪み、頬が引き攣る。
くそ……
怒りに下唇を噛んだ。
くそっ!
唇に鈍い痛み。
最悪だ……
だがそんなものはどうでもいい。
ああ最悪だ。
脳裏に浮かぶは只一つ。
あいつめ。
鬼。
あいつのせいで俺は……
最強の力を持つ種。
俺は……
そして。
俺は。
その鬼が持つ……
事の発端は、一人の幼女の言葉だった。
大晦日の大決戦から数日後、いつものように俺は博麗神社に足を運んでいた。
目的は言うまでもなく博麗の巫女。
正確には彼女の所有物。
空は晴天。
冬だというのに、頭上には澄んだ青空が広がっている。
ずっと眺めているとそのまま吸い込まれそうな、真っ青な蒼。
今天地が逆さまになったとしても、人はそれを巨大な湖と勘違いをして泳ぎに行ってしまいそうなほどの、蒼い空。
その青空の下、俺は駆け足で階段を上っていた。
時たま吹く風が、火照った身体を冷やしてくれて、とても気持ち良い。
だがそれも一瞬のこと。
すぐさま身体は熱を持ち、早く早くと両足を急かしてくる。
それに素直に従って、俺は更に速度を上げた。
今日はいつもより上る速度が速い。
新年だからだろうか。
うん、関係ないな。
新年だろうがお盆だろうが年末だろうが。
神社に行く時、俺の気分はハッピーなんだ!
なんでかって?
言わなくてもわかんだろ?
アレだよアレ。
あ、わかんねぇ?
じゃあちょっと待ってろ、もう少ししたら分かるから。
と、誰に対するでもなく答えながら階段を勢い良く駆け上がる。
踏み出す足は、一段毎に強く。
弾む心は一呼吸毎に熱く。
求めしは愛しの少女と、その少女の持つ神秘の……
「待ってろよーーーーーっ!!」
叫びは幻想郷の空に遠く響いた。
そんなこんなで数分後、神社に到着。
すぐさま境内を見回す。
ほどなくして、掃除している彼女を発見。
その瞬間。
がち、と。
錆び付いた鉄の歯車が動き出す。
ごう、と。
巨大な炉の中で、炎が勢いよく燃え上がる。
ぱちん、と。
軽快な音を立てて切り替わる、回路。
ぎし、と。
千切れそうな程の軋みをあげて、全力が両足に収束する。
今か今かと解き放たれる瞬間を待つ様は、まるで限界まで引っ張られたゴムのよう。
そして次の瞬間……
「イ~~~~……」
魅惑のお宝目掛けて。
突撃した。
「ヤッフーーーーーーーーーッ!」
「ぅきゃあああああああああっ!」
一つに重なる、異なった叫び声。
そして開かれる楽園への扉。
俺はその扉を全速力で潜り抜け、そして……
精巧な硝子細工で出来た装飾品を扱うように優しく。
飢えた獣が極上の餌を貪るが如く獰猛に頬を摺り寄せる。
スベスベ。
頬から伝わる、羽衣のような滑らかな肌触り。
ぷにぷに。
熟すか熟さないかの間際の、若々しい瑞々しさをもった弾力。
瞬く間にして、頬の神経が侵された。
そのまま頬が落ちそうな錯覚を覚える。
大きく鼻で空気を吸い込む。
ソレは鼻腔から脳へ、そして全身へと回る。
微かに柑橘類の混じった、濃厚なミルクのような香り。
あまりの濃厚さに頭の容積庫がパンクしそう。
だがそれが良い。
それが良いんだ!
心の中で高らかにそう叫んで、ひたすら行為に没頭する。
スベスベぷにぷにスベスベぷにぷに。
香りを吸い込む、吸い込む、吸い込む。
一摺りごとに触覚が麻痺していく。
一呼吸ごとに、脳と嗅覚が壊されていく。
それでも衝動は止まらない。
ああ……
満たされなかった部分が満たされていく感覚。
補われる充足感。
そしてその後は……
「ア、アンタねぇ……」
お決まりのように。
「本当に……」
ド派手に吹っ飛ばされる……
と、思った瞬間だった。
突然、摺り寄せていた頭を後ろから押される。
何事かと思った瞬間……
首元に伝わる感触で一気に身体から力が抜けた。
なんだこれ。
身体が動かない。
まるでそんなことに使うなと抗議しているように。
全身に力が入らない。
まるで今使うのはそんなものでは無いと言わんばかりに。
そんな中浮かぶ、一つの言葉。
柔らかい。
それと同時に、口元が緩んだ。
弛緩している身体。
それとは対称的に、一点に集中しだす神経。
「え?」
こちらの変化に戸惑った様子の声。
だが、今はそんなものに構っている余裕は無い。
最速で全神経・全感覚を首回りに集結させる。
そして全力でその感触を堪能した。
うはぁ……
言葉に出来ない声が出る。
今の感触を言葉で表現するなら、ふにゅ、だろうか。
否。
ふにゅぅ、が正しいか。
柔らかくも適度な温度と弾力。
ソレは例えるなら、高級マシュマロのような弾力。
ソレは喩えるなら、太陽の温かな日差しを満遍なく浴びたような錯覚。
神と自然の作り出した奇跡の巻き布。
ソレが今、俺の首回りを包み込んでいる。
あったけぇ……
ソレはとても温かかった。
まるで心まで温かくなるようだ。
冬にマフラーを巻く人は多い。
しかし、俺は首に何かを巻くことがあんまり好みじゃない。
だが。
コレなら毎日でも巻きたい。
そう、思った。
出来ることなら四六時中。
起きる時も、顔を洗う時も、着替える時も飯を食う時も、働く時も風呂に入る時も寝る時も!
コレには、それだけの価値があった。
頭の中で誰かが言った。
『腋マフラー、そういうのもあるのか!』
そうだよ、あったんだよ。
俺達が知らなかっただけだったんだよ。
知らなかったことの己が愚かさに腹を立てつつ、頭の中の誰かに答える。
ああ、俺はなんて無知だったんだ。
こんな味わい方もあったなんて……
「この……」
もっと。
もっと堪能したい。
そう思った俺は、もっと強く挟もうと彼女の腕に手を掛けようと……した次の瞬間。
世界が半転した。
「え?」
違和感が俺を襲う。
先程まで境内の方を向いていた筈の両眼。
それが今は鳥居の方を向いていた。
違和感はそれだけではない。
視界に移るは逆さまの鳥居。
何で、鳥居が逆さまになって……
「大馬鹿っ!!」
その罵声を最後に、俺の意識は途絶えた。
「起きろ~」
誰かの声。
幼さを残した声が耳に届く。
続いて頬に軽い振動と衝撃。
どうやら叩かれたみたいだった。
それを引き金に、意識が反転して戻ってくる。
薄ぼんやりとした闇を抜けた、その先に。
そして目蓋を開いた。
目の前には……
「あ、起きた?」
幼女が居た。
「おはよ~○○」
「お~……」
微笑む幼女に返事を返す。
まだ意識が完全に覚醒していないのか、間抜けな声だった。
胸が少し苦しい。
何故かと思ったが、原因はすぐに判明した。
目の前の幼女に視線を向ける。
「なあ萃香」
「なに?」
「どいてくれ」
「え~~~」
こっちの要望に、何故か不満気な顔を見せる幼女。
「え~~、じゃねえ。お前がどかないと起き上がれねえだろうが」
「まだ起き上がらない方が良いと思うけど?」
にこやかにそう返す幼女。
俺は反論しようとして……
「っ!?」
首からの鈍痛に声を漏らした。
思わず顔を顰める。
なんだ、この痛みは?
そっと首に手を当てる。
そして手を添えたまま、ゆっくりと首を動かした。
動かすと同時に、首筋に鈍い痛みが走る。
更に顔が険しくなるのが分かった。
「いって~……」
余りの痛さに、思わず呻き声が出る。
一体なんだってんだ?
寝違えたか?
つーか、俺なんで寝てたんだ?
湧き上がる、疑問の数々。
「あ~あ、だから言ったのに~」
その様を見て、目の前の幼女は少し呆れながら笑った。
「どうゆうことだ?」
痛みに耐えつつ尋ねる。
先の言葉から察するに、事情を知っているようだ。
彼女は呆れ半分に笑いながら問いに答えた。
「霊夢に頭から落とされたの、覚えてないの?」
その言葉を聞いた瞬間、忘却された記憶が甦った。
いつもの強襲。
訪れる至福の時。
新たな未開の地の発見。
狂喜する思考。
そして、反転する視界。
「ああ……」
疑問は氷解した。
何故寝ていたのかも。
何故首が痛むのかも。
「思い出した?」
「おう、思い出した」
「私の言葉の意味も、理解出来た?」
「お~~~」
返事を返しつつ、首を擦る。
少し動かしただけでもこれだ。
あんまり動かない方が良いな……
「しゃあねえ、もう少しこのままでいるか」
「そうそう、安静にしときなって!」
返答に満足したのか、萃香は嬉しそうに笑って。
俺の胸に倒れ込んできた。
「おいおい、なんだよ急に」
「別に良いじゃん、暫くこのままなんでしょう?」
俺の抗議など気にしていない風に言いながら、胸元に頬を摺り寄せた。
「ん~……」
途端に漏れ出る、嬉しそうな声。
……あ~、こりゃ駄目だ。言っても聞かねえわ。
「……ったく」
早々に諦めた俺は、仕方なくそのままでいることに。
……ま、いいか。
いつものことだしな。
「むぅ~……」
全身で俺にしがみつく。
小さな手が俺の服を、ぎゅと掴んでいた。
その様はまるで子猫が母猫に甘えるよう。
微笑ましくなって、頭を撫でた。
気持ち良い手触りが掌から伝わってくる。
「うにぃ……」
撫でられるのが嬉しいのか、萃香は目を細くする。
ホントに猫みたいだな……
もし彼女に尻尾があったなら、ぱたぱたと左右に振っていることだろう。
そんなことを思いながら彼女を見る。
小さな身体。
村の子供達と同じくらいの体躯。
身体の成長度合だけを見れば、年齢は十にも満たないだろう。
だが彼女は人ではない。
その証拠に、彼女の頭には不釣合いな程の大きさの二本の角があった。
鬼。
最強の一つとして語られる種族。
その強大な力は月をも砕き、大地を裂く。
絶対的な、畏怖。
ひ弱な人間達からすれば恐怖でしかない存在。
……の、筈なのだが。
「ふにぃ……」
甘ったるい声が漏れた。
ふと、胸元から感じる力が弱まっていることに気付く。
見ると彼女は、だらしなく全身を弛緩させていた。
安心しきった顔。
その姿を見て、自然と笑みが零れる。
「やれやれ」
幼子をあやすように、逆の手でポンポンと背中を叩く。
全く、諏訪子といいコイツといい、何でこうなんだろうな?
神と鬼。
敬意はされど、決して親愛は湧かない存在。
その筈なのに……
「ぅにゃ……」
こいつらときたら、どちらも甘えん坊で困る。
「もっとカリスマ持てよなぁ……」
そのうち、何処ぞの吸血鬼みたいになっちまうぞ?
そう呟きながらも、心の端っこでは、現状で良いと思っている自分が居た。
心を温かな感情が占拠していく。
空間に穏やかない時間が流れた。
「ふぁ~あ……」
穏やかさに当てられたのか思わず欠伸が出た。
欠伸を噛み殺していると、ある変化に気付く。
「すぅ……すぅ……」
聴こえる寝息。
どうやら、彼女もこの穏やかさに当てられたようだった。
「寝付きの良いことで……」
寝顔はとても幸せそうだった。
こりゃ起こすのも可哀想かな?
そう思っていると……
「お?」
ぎゅ、と。
たどたどしい動きで、抱き締められた。
多分無意識的だろう、小さな腕で身体を抱き締められる。
まるで親に甘える子供のようだ。
ホントにもう、コイツは……
やれやれと溜息。
そして、お返しにとばかりに抱き締め返した。
頭と背中を優しく撫でる。
一定のリズムで行われる呼吸。
腕の中に感じる、確かな温かさ。
「ふあぁ……」
二度目の欠伸。
どうやら睡魔の本格的な攻撃が始まったみたいだ。
このままだと、あと十数秒で落ちるだろう。
今の俺に、それを拒む理由は無い。
なので……
「おやすみ~」
ゆっくりと眼を閉じた。
この季節にしては珍しく温かい日差しと。
腕の中で気持ちよさそうに眠る鬼娘を感じつつ。
俺は眠りに落ちていった。
……その数分後、鬼のような形相をした巫女に起こされるとも知らずに。
「全く……」
不機嫌そうな言葉を発しながら湯呑みに口をつける紅白の巫女。
俺達を起こした後、お茶の間に場所を変えてから数分。
彼女はその数分の間、その言葉しか発していない。
場の空気はピリピリと痛かった。
う~~ん……
俺は少女を眺めながら考える。
コイツ、何でこんなに機嫌が悪いんだ?
さっきからずっとこの調子。
一目で分かる機嫌の悪さ。
でも理由が分からない。
一体、何が不満なのだろうか?
不思議に思いながら、ゆっくりと首を動かした。
うん、痛みはもう無いな。
先程安静にしていたお陰か、首はすっかり完治したみたいだった。
ホント、我ながら大した回復力になったモンだよ。
成長というモノを実感しつつ、俺はもう一つの痛みに意識を向ける。
頭頂部に感じるズキズキとした痛み。
痛みの発生源をそっと触ると、其処には大きなたんこぶがあった。
眠る前には無かった筈のたんこぶが、どうして出来ているのか?
答えは単純にして簡単。
起こす時に殴られたからだ。
いやもう、あん時は目の前に星が散ったね。
流星群っていうの?
もう、一発で眼が覚めたわ。
そんで目の前には威圧感たっぷりに腕組みをしたコイツだろ?
誰だって覚醒するって。
正に鬼腋巫女。
触らぬ腋に祟りなし……っと、閑話休題。
そんなことはどうでもいいんだよ。
今現在、重要なのは……
「ねえ霊夢~。なんでそんなに機嫌悪いの~?」
自身の疑問を代弁するかのように萃香が尋ねた。
そう、それだ。
何故機嫌が悪いのか?
それが今、最も重要な問題だ。
その疑問に対し、彼女はこちらに一瞥をくれると……
「別に」
たった一言。
そっけなく返して視線を戻し、再び沈黙した。
別にって……んなわけねえだろ~。
「変な霊夢~」
「別に、いつもと同じよ」
「そうかな~? おかしいよね○○~?」
萃香はそう聞きながらもたれ掛かってくる。
そして少し身体をずらして、こちらに顔を向けた。
彼女は現在、炬燵と俺に挟まれた状態で座っている。
簡単に言うと、俺の膝の上に居るわけだ。
理由は炬燵に入る際にせがまれたため。
……ま、これもいつものことなんだけどな。
可愛らしく首を傾け同意を求めるその姿を見て、思わず頭をくしゃくしゃと撫で回したい衝動に襲われる。
……が、今回は我慢した。
何故ならば。
視線を彼女の後頭部に向ける。
其処には、俺のと同じくらい大きなたんこぶ。
当然ながら犯人は、現在不機嫌街道まっしぐらの紅白巫女。
二人仲良く拳骨を戴いたってワケだ。
痛々しいたんこぶが存在するその頭を撫でるのは、若干躊躇われた。
なので……
「まあなぁ」
曖昧な返事を返しつつ、彼女の額に手を置く。
そしてそのまま、軽く撫でた。
掌から伝わるサラサラとした髪の感触が気持ち良い。
「えへへ~」
その動作に、目の前の幼女は顔を綻ばせた。
嬉しいような照れたような表情。
彼女はそれを隠すように胸元に頭を埋める。
その時だった。
ばきん。
何かが砕ける音が耳に届いた。
何事かと思い、音のした方向に眼を向ける。
音のした方向。
其処には、俯いて拳を握る紅白の少女。
拳の周辺には大小様々な破片が飛び散っている。
多分、彼女が壊したのは湯呑みだろう。
その証拠に、さっきまで彼女が飲んでいた湯呑みが無い。
ぎりっ。
何かが軋む音が聴こえた。
「れ、霊夢?」
突然の行動に驚いた萃香が、おそるおそるといった風に尋ねる。
その呼び掛けに、彼女は無言で返した。
静寂が世界を支配する。
沈黙に耐えかねたのか、萃香はこちらを見つめてくる。
その顔は、見て取れる程の不安に満ちていた。
それもそうだろう。
訳もわからないまま、いきなり険悪な雰囲気になったら誰だって困惑する。
その点で言うならば、彼女の反応は正しいと言えよう。
俺も同じく、彼女と一緒に困惑する……筈だったのだが。
気分は妙にスッキリとしていた。
凍っていた答が解凍されていく。
映し出される場面。
萃香と一緒に寝ていた、十数分前。
そして萃香を膝の上に乗せている今。
起こした時から、不機嫌な紅白の巫女。
そして先程の湯呑み破壊。
その全てが繋がって、一本の線になる。
判ってみると、実に簡単な問題だった。
つまり……
「萃香、ちょっと退いてくれ」
「え、急にどうしたの?」
「まあいいから」
困惑する萃香を膝の上から退かす。
そして立ち上がった俺は、霊夢の後ろに回った。
「霊夢」
声を掛ける。
「なによ」
彼女は湯呑み破壊をした時の状態のまま。
こちらを向かずに返事を返す。
取り付く島も無い態度。
だが。
あ、やば……
答えを知っているに俺にとって、その態度は正直……反則だった。
彼女の後ろに座り込む。
そして目の前の少女を強く抱き締めた。
「!?」
抱き締めた瞬間。
両腕から、少女特有の柔らかな感触が伝わった。
「ちょ、ちょっと!? いきなり何すんのよ!?」
予想外の事態に狼狽する少女。
じたばたと腕の中でもがく。
後ろから抱き付いているため顔は伺えないが、多分真っ赤になっていることだろう。
「何って……お前の希望していたことだが?」
「だ、誰がいつ希望したっていうのよ!?」
全力で否定。
いや、まるわかりだっての。
そう。
これが、さっきまで彼女が不機嫌だった理由。
湯呑みを粉砕した理由。
つまり……
「お前さん、萃香が羨ましかったんだろ?」
その言葉に少女はぴたりと動きを止める。
つまり。
博麗霊夢は伊吹萃香に、嫉妬していたのだ。
無邪気に甘える萃香が羨ましかったのだろう。
こういうことを自分から言い出せない性格だからなぁ……
まあ、気付けなかった自分にも責はあるのだが。
「違うか?」
「そ、そんなことないわよっ!」
問い掛けに、腕の中の少女は続けて否定。
再度じたばたともがき始める。
ああは言われたが、嘘だということは明白だった。
その証拠に、彼女はさっきから腕の中でもがいてはいるが、抜け出そうとはしていなかった。
やれやれ、全く以って素直じゃない。
心の中で溜息を吐く。
その時、ピンと閃いた。
……少し意地悪してみるか。
「そうか~……なら仕方ない、離れるわ」
「え……」
その言葉に、少女は動きを止めた。
不安の篭った声。
うは、困ってる困ってる。
想定した通りの反応に、自身の口元が僅かに攣り上がるのが分かった。
「御所望じゃないなら仕方ないよな。いや、もがく程嫌がることをしてスマンかった」
表面上、深く詫びる。
勿論反省はしていない。
そして腕を解こうとして……
袖を掴まれた。
「なんだ? これ以上嫌がることはしたくないんだが?」
言葉の上では、平静を保って問う。
その問いに、霊夢はぎゅっと袖を握って……
「……嫌とは、言ってないじゃない」
こちらを横目で見ながら、そう答えた。
ああ、ホントにコイツはもう……
もう我慢は出来なかった。
「そうか……じゃあ」
彼女の身体を軽く持ち上げ。
「きゃっ!?」
勢い良く反転。
そして前回より強く、抱き締めた。
さっきは腕のみだった柔らかさを、今度は胸元で感じる。
突然の出来事に硬直する霊夢。
その首筋は、茹蛸のように真っ赤に染まっていた。
「少しは素直になろうな?」
「……るさい」
耳元に届く、蚊の鳴くような声。
本当に素直じゃない。
俺は苦笑しながらその背中を、優しく撫でた。
「むぅ~……」
徐々に緊張が解けていく彼女の身体。
ゆっくりとこちらに体重を預けてくる。
と、肩に重みを感じた。
顎を乗せたのだろう。
今の彼女の顔は、きっと緩みきっているに違いない。
素直じゃない彼女が、自身に身を委ねてくれる。
そのことが単純に嬉しかった。
惜しむらくは、彼女の緩んだ顔を見ることが出来ないことなのだが。
ま、今でも充分。
萃香にした時のように、背中をポンポンと叩く。
「んぅ……」
霊夢は気持ち良さそうに、身動ぎする。
うむ、愛いやつ愛いやつ。
満足した俺は、暫くその状態に浸ることにした。
どれくらいそうしていただろう?
愛しさと穏やかさの混じった、とても温かな時間。
とても心地よい時間。
その時間を破ったのは……
「うぅ~~~~……」
可愛らしい唸り声だった。
その声で、ふと我に返る。
声のした方を見ると、其処にはむくれ顔でこちらを見ている萃香の姿。
見るからに、かなり御不満の様子だ。
「霊夢ずるい~~~……」
ぷくっとした顔でそう告げる。
どうやら今の状態が気に入らないらしい。
「私と代われ~~~!」
抗議の声を上げる幼女。
その対象となった人物は。
「嫌よ」
そちらを見ないままに。
放たれた言葉を、一太刀で切って捨てた。
「ずるいぞ~~!」
「五月蝿い」
抱き合ったままの状態で返す紅白の巫女。
どうやら、この場所を譲る気は毛の先程も無いようだ。
いやはや……可愛いわ~。
「私も○○に甘える~!」
あっさりと断られたことにもめげない鬼娘。
お前、まだ甘えたりんのか……
糖分過剰要求の鬼娘に呆れていると、霊夢が俺の肩から顎を外し、萃香に視線を向けた。
そして……
「此処は私の場所よ」
一言。
顔は林檎の様に真っ赤だった。
彼女は言うべきことは言ったとばかりに。
その顔を俺に見られないよう、再び肩に顎を置く。
抱き締める腕の力が、ほんの少しだけ強くなった。
目の前には、ぽかんと口を開けた萃香の姿。
どうやらかなり面食らった様子だ。
そりゃそうだろう。
正直、俺も驚いている。
あの霊夢が。
もし素直じゃない選手権が開催されたのなら、確実にトップ争いをする程素直じゃない霊夢が。
まさかこんなことを言うとは。
素直になれとは言ったが……こりゃ、明日は嵐か?
萃香はまだ呆然としている。
まだショックから立ち直れていないようだった。
ありゃ暫くあのままだな……
そう思いながら、口を大きく開けたまま固まっている鬼娘を見つめる。
が、立ち直りは思ったよりも早かったようで。
放心状態から戻ってきた萃香は、ブンブンと頭が取れそうな勢いで頭を振る。
そしてひとしきり振った後、こちらを睨みつけ……
「こうなったら実力行使だ!」
言いながら、彼女は一枚の札を取り出した。
それはとても見覚えのある札だった。
これまでに幾度と無く見た札。
その札が出されると、決まって身体に損傷を受けていた札。
スペルカード。
弾幕ごっこの基盤ともいうべき札。
彼女の手にはそのスペルカードが一枚、確かに握られていた。
「鬼符!」
高らかに宣言をする。
宣言に共鳴するように、大気が震えた。
「ちょ、待て萃香!」
反射的に静止の声が出た。
室内でスペルカードとか……冗談じゃねえぞ!
背中から冷や汗が出るのが分かる。
だが、彼女は発動を止めなかった。
「ミッシング……」
静止の声空しく、彼女はスペルカードを発動させる。
否、させようとしたのだが……
突如発生した風切音と。
すこん、という小気味良い音に、発動は阻止された。
「パぶあっ!?」
蛙が潰れた様な声を出して倒れる幼女。
「~~~っ!」
額を抑えながら畳の上をのた打ち回る。
彼女の額には、大きな針(玉櫛だっけか?)が突き刺さっていた。
その針の持ち主。
紅白の少女は俺の腕の中、左腕を突き出しながらその光景を見つめていた。
「邪魔するな」
悶える幼女に冷たくそう言って、彼女は再び俺に抱きついた。
もぞもぞと動く。
どうやら居心地の良い体勢を作っているようだった。
暫くして、しっくりとした姿勢になったのか。
彼女は動きを止め、再び無言になって状況を堪能しはじめた。
むふ~、と息を吐く音が耳に伝わる。
……いや、有り難いんだけどな。
余りの容赦の無さに、俺は苦笑いしか出来なかった。
いやはや、甘えたいという欲求は此処まで人を変えるものなのか。
「う~~~~っ!」
萃香は依然として畳の上で悶えている……と思ったら勢い良く跳ね起き。
涙目で恨めしそうにこちらを、正確には霊夢を見た。
頬は餅のように剥れている。
あ~……なんか餅が食べたくなってきたな~。
涙を消すように、ごしごしと目を擦る鬼娘。
「こうなったら……」
きらりと、その眼が光った。
「最終手段だ!」
再度大きな声で宣言する。
どうやら彼女はまだ諦めていないようだった。
「いや、いい加減諦めろよ……」
その根性に、つい突っ込んでしまう。
いやホントもう、無理じゃね?
「ふっふっふ……」
俺の思いとは裏腹に、萃香は不敵に笑う。
そして。
「ていっ!」
掛け声と共に、左拳を天に向けて突き出した。
左拳に注目する。
今度は何が起こるのかと思ったが、数秒待っても何も起こらなかった。
幼女は不敵に笑ったまま。
「……どう?」
俺に問う。
いや、どうと言われても……
何も起こっていないので反応のしようがない。
「いや、どうって……何が?」
なので素直に聞くことにした。
途端、彼女の不敵は驚愕に変化する。
「腋よ腋っ! 私の腋はどうだって聞いてるの!」
ああ、そういうこと。
振り上げた腕の意味を理解した俺は、目の前の幼女の腋を観察する。
眼前に広がる腋。
それは例えるならば、若すぎる樹木。
故にその腋は、未成熟な青い果実。
食べるにはあまりにも早すぎる、作り始めの蜜。
イコール……
「襲いたかったら襲っても良いんだよ~?」
観察する様を見ながら、にやにやと笑う幼女。
誘う言葉に、ぴくんと、腕の中の少女が反応した。
ん?
身体が強張る。
……もしかして、心配してるのか?
予想は的中したらしく、抱き締める腕の力がきつくなった。
う~~ん、素直で実に宜しい。
けどな、心配はいらんのだよ。
「どう?」
ふりふりと腋を見せ付ける萃香。
そんなの、答えは決まってる。
「遠慮しとくわ」
その言葉を口にした瞬間。
ぴた、と。
ゼンマイが切れた人形の様に、見せ付ける動きが止まった。
「な……」
ぱくぱくと、金魚のように口を動かす鬼娘。
「なんで!?」
俺はその問いに、紅白巫女の右腕を掴んだ。
「えっ?」
突然腕を掴まれ、久方ぶりに声を発する霊夢。
その声を無視して、俺は目線を萃香に向け……
「俺はコレが良いんだ!」
その腕を自身の首に回した。
「あーーーーーっ!!」
「っ!?」
二つの声が重なる。
刹那。
思考回路が吹っ飛んだ。
ふっくらもちもちの、新米のような首触り。
ほんわかぽかぽかの、春の陽気を凝縮して詰め込んだかのような温もり。
奇跡の二重奏が首元に展開された。
その二重奏は俺の首元を、痛んだ竜骨を癒すように優しく包み込む。
「ほわぁぁ……」
情け無い声が声帯から喉を伝って口外に漏れ出た。
「ちょっと、○○……」
当惑した声。
構わずに、俺は首を摺り寄せる。
「くぅ……んっ」
切なげに喘ぐ声と。
ふっくらつやつやで、ほんわかぬくぬくの、普通では絶対に味わえない感覚。
笑い出したくなるような狂気と、天使の羽で包み込まれるような癒し。
デリシャス。
アンビリーバボーだ!
高らかに心の声を張り上げる。
そして感触を増幅させるため、俺は眼を瞑った。
余計な感覚を遮断することによって、首元に感じる恩恵を更に鋭敏にするためだ。
うわぁ、もっちもちのぽっかぽかだぁ……
今の俺の顔は、ふにゃふにゃに緩みきっていることだろう。
頭の片隅で、赤いライトが点滅する。
そろそろくるぞ。
身の危険をしらせる信号。
無視した。
知るか。
この感触を味わえるのなら閻魔にだって挨拶に行ってやるわ!
威勢良く啖呵を切って、一層のめり込む。
幸福の奔流が、首筋から全身へと巡っていく。
ああ、幸せだ~。
そして……
「この……」
終わりを告げる声が聴こえた。
これから数秒もしないうちに、俺の意識は途絶えるだろう。
もう終わりなのか。
もう、終わってしまうのか。
極楽の終わりに、悔しさと切なさが入り混じる。
さようなら。
別れの言葉と。
また今度。
再会を願う言葉。
そして俺の意識は暗黒へと落ちていく……筈だったのだが。
来る筈の終末は、一向に訪れなかった。
あれ?
頭に疑問符が浮かぶ。
この後、いつもなら容赦無く俺をブッ飛ばす筈の彼女は……
「馬鹿……」
俺の頭を撫でてきた。
予想外の彼女の行動に脳がパニックになる。
どういうことだ?
ブッ飛ばすんじゃないのか?
無数に湧く、頭に何故と付いた疑問符。
けど。
優しい声が。
撫でる手が。
とても優しくて。
何故か、無性に泣きたくなった。
泣きそうな笑顔で少女の腕の間から顔を出す男と。
その男を優しく抱き締める少女。
傍から見たら、さぞかし滑稽に映ることだろう。
けれど、今の俺はそんな外聞はどうでも良くて。
ただ、この時間が永遠に続けば良いと思った。
両腕で、力一杯抱き締める。
この少女を離したくない。
そう、強く思った。
…………強く思ったのだが。
その時間は、意外な人物によって終わりを告げた。
「○○の……」
少女の声とは違う声。
聴こえてくる、何かを回転させる音。
それが気になって眼を開く。
自身の眼と鼻の先には。
誰かがいつも持っている瓢箪が。
「馬鹿ぁぁぁぁあああああああっ!」
ぐちゃりと。
顔面の潰れる音を、俺は聴いた。
そして悲劇は、この一週間後に起きた。
休暇の日を迎えた俺は現在、ルンルン気分で博麗神社の階段を駆け上っていた。
「ふんふふ~ん、ふ~ん」
鼻唄混じりに階段を駆ける。
萃香にやられた傷も癒え、体調もバッチリ。
気合はもう、はちきれんばかりだ。
いつもの三倍に届かんくらい。
何故そんなに張り切っているのか?
理由は三日前の夕方に遡る。
「おっしゃ、これで良し!」
「おう○○!」
「あ、親方!」
「今日も気合充分だな!」
「もちろんッスよ親方! やることしっかりやっておかないと、ゆっくりアイツ等に会いに行けないッスから!」
「アイツ等って……博麗の巫女と守矢の巫女のことか? 随分とまあ熱心だな!」
「当たり前ッス! あの二人は俺の活力源ッスから!」
「活力源とは言ってくれるじゃねえか!」
「へへっ、その通りッスからね!」
「お熱いことで結構だな! その調子で頑張って落としてみせろよ!」
「ウイッス! あ、そーいや何か用ッスか?」
「ん、ああ。お前の休みのことなんだがな」
「休み…………まさか、無しとか!?」
「そうあからさまに嫌そうな顔をするな、逆だ逆!」
「逆?」
「次の休暇を少し豪勢にしてやろうと思ってな!」
「豪勢にって……」
「次の休みは三連休にしてやる!」
「さっ!?」
「お前は皆の中でも、特に頑張っているからな!」
「で、でもそんな……」
「なんだ? もしかして嫌なのか?」
「嫌じゃないッス! けど、今は一番工程が忙しい時期じゃないッスか。なのに自分だけそんなに休むなんて……」
「勿論、連中も同意の上だ。皆、二つ返事でOKしてくれたぞ?」
「え?」
「良い仲間を持ったな!」
「……」
「だから遠慮なく休め! とは言っても、どうせお前は神社に行くんだろ?」
「…………」
「まあ、巫女さん達に宜しく言っといてくれや……って、○○?」
「………………」
「急に黙り込んでどうした?」
「……………………」
「○○?」
「…………………………」
「おい、○……」
「…………………………しゃっ!」
「あ?」
「おっしゃあああああああああああああああああああああっ!!」
「おわっ!?」
「三連休は腋巫女尽くしじゃあああああああああああああああああああっ!!」
「ま、○○?」
「待ってろよ霊夢ううううううううううっ!! そして早苗ええええええええええええええっ!!」
以上、回想終了。
その後の同僚達の反応は省略させて貰おう。
まあ、ぶっちゃけドン引きだった。
妙に余所余所しい同僚達の態度が目蓋に浮かぶ。
あの居心地の悪さは、暫く忘れられそうにねえなぁ……
少し心に影が出来た。
でも、まあ……いっか!
折角の三連休、腐っても仕方が無い。
今はこれから訪れる、幸せのことだけを考えよう。
曇りかけた思考回路の電源を落とし、別の回路を立ち上げる。
立ち上げたのは、三連休の予定。
気紛れに舞い降りた天からの恵み、有効に使わなくては損だ。
階段を上る足を止め、顎に手を当て思案する。
今日は博麗神社に行って、明日は守矢神社……
此処までは良い。
だが問題は……
「明後日、どうするかだよなぁ……」
休みは三日。
交互に行った場合、最後の一日が余る。
どちらに行くべきか、それが問題だった。
巡る思考。
紅腋巫女。
緑腋巫女。
どちらも甲乙つけ難い、至高の逸品。
それ故、俺の頭を大いに悩ませる。
……いっそのこと、両方でいくか?
ぽつりと飛び出した発案。
……それ、良いね。
ニヤリと口元が攣りあがる。
速攻でゴーサインを出した。
そうだよな、両方頂けば良いだけの話だよな。
簡単な話だ。
なによりあの時、そう言ったじゃないか。
脳裏に、去年の年末のある出来事が思い出される。
年も押し迫った師走。
二人の巫女を腕の中に抱いて……
<俺は両方頂く>
確かに言った。
その誓いを破るわけにはいかない。
「そうと決まればこうしちゃいられねえ!」
思考を中断し、止まっていた両脚を再起動させ、階段を二段飛ばしで上る。
今日は紅腋巫女、明日は緑腋巫女。
そして明後日は……
「紅緑入り混じっての腋巫女どんぶりじゃーーーーーーっ!」
熱い咆哮は、山彦の様に辺りに響き渡った。
……ちなみにその叫びは、付近の村にまで届いたらしい。
けれど物事はそう上手くは行かないみたいで。
ハイテンションで神社に到着した俺を迎えたのは、がらんとした境内だった。
「あれ~?」
首を傾げつつ、境内に足を踏み入れる。
おかしいな。この時間だと、大概掃除中の筈なんだが……
境内に見回しつつ、歩を進める。
居ない。
部屋の中か?
そう思い、戸を開ける……と其処には。
「あ~○○だ~」
酔っ払った幼女が居た。
「なんだ萃香か」
「なんだとはなんだよ~ぅ」
発言が気に入らなかったのか、幼女は真っ赤な頬を膨らます。
間延びした声。
酔っ払い特有の喋り方だ。
……ったく、真昼間から酒呑むなっつーの。
言ってもどうせ聞かないので、聞きたいことを聞くことにする。
「なあ、霊夢は?」
「居ないよ~ぅ?」
なにい?
居ないだとう?
「居ないって……買い物にでも行ったのか?」
「違うよ~ん」
にゃはははと、何がおかしいのか笑う鬼娘。
嫌な予感がした。
「じゃあ、何処に行ったんだ?」
「吸血鬼のところ~」
「吸血鬼のところって……」
紅魔館か。
掌を胸の前に置いた、変な吸血鬼が頭に浮かぶ。
あんのロリロリヴァンパイア。
人のモン勝手に持ってくなっつーの。
お前はパッド疑惑のメイド長とでもにゃんにゃんしてろ!
「はぁ、じゃあ帰ってくるまで待つかな……」
心の中で悪態を吐きつつ、部屋に入る。
そんな俺に返ってきたのは、絶望的な言葉だった。
「今日は帰ってこないんじゃないかな~?」
「は?」
炬燵に入ろうと屈んだ体が固まる。
「ランチとディナー付き宿泊コースに御招待~……って、メイドが言ってたから~」
なん……だと?
動揺する頭で、先の言葉の意味を翻訳する。
ランチとディナー。
つまり飯。
宿泊。
すなわち泊まり。
博麗の巫女。
イコール貧乏巫女。
この三つの意味するものは……
アイツは今日、確実に帰ってこない。
「お、終わった……」
がくりと膝が折れる。
三連休腋巫女尽くしプロジェクト ~紅と緑の巫女どんぶり、ポロリもあるよ極楽地獄変~
綿密に練られた計画。
それが音を立てて崩れ落ちていく。
なんてことだ。
計画は初日から頓挫した。
終わりだ……
俺は今日、どうやって過ごしたら良いんだっ!
頭を抱えて嘆く。
どうしようもない現実と見つからない答え。
今にも叫び出しそうだった。
……だがしかし。
ん?
絶望に拉ぐ俺の脳裏を、一筋の光が照らした。
待てよ?
それは徐々に広がって鮮明に答えを照らし出す。
霊夢に会えないんだったら……
照らし出された答え。それは……
早苗ちゃんに会いに行けば良いんじゃね?
守矢神社。
妖怪の山にある神社。
其処には……
もう一人の腋巫女が居る。
折れた膝を立て直す。
消えかかった炎が再燃する。
答えは出た。
守矢神社に行こう。
今から全速力で向かえば、堪能する時間は充分にある。
予定は狂ったが……順番が入れ替わっただけだ、問題ない。
そうと決まればこうしちゃいられない、一刻も早く向かわなければ!
「邪魔したな萃香! じゃあな!」
呑んだくれている鬼娘にそう言って背中を向ける。
そして足の先を外に向け、歩き出そうとしたところで……
「えいっ」
「へぶっ!」
盛大にすっころんだ。
「いってぇ~……」
突然のアクシデントにわけもわからず、打った鼻に手を当てる。
「何処行くのよぅ○○~」
咎めるような幼女の声。
足に違和感。
見ると、足首に鎖が絡みついていた。
こけた原因はコレか。
「一緒に呑もうよ~ぅ」
笑いながら鎖をじゃらじゃらと小刻みに振る幼女。
冗談じゃない。
復活した計画を邪魔されて堪るかっ!
「また今度な!」
キッパリと誘いを断って、絡みついた鎖を解きにかかる。
くっそ、かってえなコレ!
異常に固く絡みつく鎖にてこずっていると……
「今度じゃなくて今呑みたいの~」
「おわあっ!」
勢い良く引っ張られた。
「つかまえた~」
腕をつかまれる。
うわあ、捕まっちゃったぁ。
「って、離さんかい!」
「一緒に呑むの~」
へらへらと笑いながら腕にしがみつく幼女。
こっちの話など、これっぽっちも聞いちゃいない。
正に酔っ払い。
腕を離そうとしたが、いかんせん鬼の力。
俺程度の力じゃ離れるわけもなく。
「わ~い! ○○と宴会だ~!」
「ちょ、緑腋巫女おおおおおおおおおっ!!」
半ば強制的に、俺は鬼と酒を酌み交わすこととなった。
「ふぅ、やっぱり外は寒いです……」
境内の掃除を終えた彼女は、居間に入りながらそう言った。
いそいそと炬燵に入る。
「やっぱり、炬燵は暖かいですねぇ……」
幸せそうに顔の筋肉を弛緩させ、台に頬をつける緑白の巫女。
外に居たためか、彼女の肌は寒さで赤くなっていた。
彼女の身体を温めるために、俺は炬燵に入っている緑白の少女を後ろから抱き締める。
「え、えっ!?」
驚く彼女。
瞬く間に、弛緩が緊張に変わってゆく。
構わず抱き締める力を強くした。
「ひゃっ!?」
抱き締める強さの変化に、少女は再び驚きの声を発する。
だが、それも一瞬のことだった。
「ん……」
状況を理解したのか。
おずおずといった具合で、こちらに身を委ねてくる少女。
「○○、さん……」
甘えるような声。
抱き締める腕に触れられた手。
もう緊張は解けたようだ。
そのことを理解した俺は、本来の目的を遂行することにした。
外気に当てられたためか、彼女の肌は赤くなっている。
勿論、彼女の『腋』も。
口元が愉快気に歪む。
出てくるのは狂った情愛。
温めなくっちゃなぁ。
そして俺は……
自身の首を彼女の腋に。
光の速さで突っ込んだ。
腋マフラー。
一週間前に、紅腋巫女から体感した新たなる奇跡。
それを今度は緑腋巫女で体感する……っ!
「にゃはははは~」
筈だったのになぁ……
馬鹿みたいに楽しそうな笑い声。
その笑い声によって、霞みのような幻想は掻き消され、分かりたくもない現実が戻ってくる。
目の前には、第二の腋マフラーを持つ緑白の巫女……ではなく。
「にゃはははは~」
楽しそうに笑う、酔っ払い。
「んくっんくっ……ぷっはーーーーーっ! やっぱりお酒は最高だね~!」
酒を呑んで満足気に幼女は明るく笑う。
「……はぁ」
反対に、こちらの気分は果てしなく暗かった。
そのうちブルーを通り越してブラックになりそう。
気分を色で見ることが出来たのならば、この部屋は黄色と濃い藍色の二色に分かれていることだろう。
「な~に溜息吐いてんのよ○○~。溜息吐くと、福が逃げるんだぞ~?」
笑う鬼娘。
「はぁ」
その姿を見て再度溜息。
自分では吐くつもりはないのだが、出るものは仕方がない。
「あ、また福が逃げた~」
おかしそうに笑う酔っ払い。
うっせえ、福ならもう逃げたっつーの。
本当なら俺は今頃、守矢神社に居た筈なのに……
幻想の中に居た少女が再度浮かぶ。
正しくは、彼女の『腋』が。
先の幻想の中でも、一際輝いていた幻想。
自身が求めた、二つしかない至高の逸品。
そのうちの一つを所有する奇跡の巫女。
「緑腋巫女ぉ~……」
意識せずその言葉が口に出た。
それほどまでに自身の心と身体が求めていたのだろう。
だが、それはもう届かない。
「うぅ……」
切ない現実に涙が出そうになった。
「なぁに暗くなってんのよ~。お酒は楽しく呑むもんだよ~」
心中を知ってか知らずか、励ますように俺の肩を叩く酔っ払い。
無配慮な発言に、少しだけ怒りが湧いた。
誰のせいだと思ってんだこの野郎。
「うるせいチクショウ。今の俺を明るくしたかったら大至急、紅腋もしくは緑腋を持って来やがれ」
若干の不満を込めて言い放つ。
幼女はその言葉に対して……
「な~んだ。腋が見たいんだったら、私のを見れば良いじゃな~い」
腕を振り上げた。
上げた腕の根元には、腋。
酒気を帯びている為か、ほんのりと紅く染まっている。
「ほれほれ~い。どお~?」
楽しそうに見せ付ける鬼娘。
だがそれとは裏腹に、俺のテンションは更に下降した。
俺の目の前には、腋。
腋だ。
ああ腋だ。
確かに腋だ。
間違いなく腋だ。
誰が何と言おうと腋だ。
腋………………なんだけど。
やっぱりというかなんというか。
何の感情も湧かなかった。
「はぁ」
代わりに何度目かの溜息が湧く。
「なにそのリアクショ~ン!」
剥れる幼女。
態度がえらく御不満だったらしい。
「少しは興奮しないの~? 好きなんでしょ、腋~?」
言いながら、しつこく見せ付ける。
彼女の腋は、鼻から数センチ先にあった。
これが紅白の巫女か緑白の巫女の『腋』であったならば、俺は迷うことなくダイブしていたことだろう。
だが、コレは彼女達の『腋』ではない。
眼を閉じる。
そして……
「無理」
ハッキリと言った。
うん、やっぱり無理。
やっぱ俺はアイツ等の『腋』じゃないと興奮出来ない。
いや萃香のも悪い訳じゃないのよ?
けど……やっぱ、まだまだ青い果実なんだよなぁ。
もう少し熟したら、そん時はどうなるか知らんけど。
「○○のいけず~!」
幼女は喚きながら一升瓶を口につけ、中に入った液体を嚥下していく。
瞬く間に、一升瓶の中身は空になった。
「ぷっはーーーっ!」
酒臭い息がこちらにまで臭ってくる。
思わず鼻を摘まんだ。
「にゃははははははは~!」
盛大に笑う。
悩みなど何も無い。
そう思わせるような、心底からの笑い。
既に誘いを断られたことなど忘れているに違いない。
無邪気な笑顔。
だからだろうか。
こんな言葉が出たのは。
「ったく、お前は楽しそうで良いねぇ…………これなら、別に俺が居なくても良かったんじゃねえか?」
愚痴を漏らしつつ、近くにあった酒瓶を手に取る。
少量を口に含み、ゆっくりと味を確かめ、そして呑み込んだ。
喉がきゅっと熱くなる。
っか~……結構キツイなぁ。
でも旨い。
癖になる旨さだ。
もう一口呑もう。
そう思い、再び口をつけうようとした時だった。
「……からだよ」
「ん?」
小さな声が耳に届いた。
吹けば飛んでしまうような、小さな声。
俺はその声に気付き、声のした方を向く。
声の主。
萃香は、泣きそうな顔をこちらに向けていた。
さっきまで陽気に笑っていたのが嘘のように、その眼には涙を滲ませている。
幼女の突然の変化に、俺の心中はみっともなく焦った。
え、なに、どしたの急に!?
ついさっきまで笑っていたのに、なんで泣きそうになってんの!?
「私が……」
前触れもなく発生した急展開に驚く俺を放置したまま、彼女は言葉を発する。
「私が楽しそうに見えるのは、○○と一緒だから……だよ?」
折れそうな声で。
彼女はそう言った。
その言葉に。
ズキンと。
胸に鋭い痛みが走った。
「○○と一緒だから、こんなに嬉しくて、こんなにも楽しいんだよ……?」
少女は言葉を紡ぐ。
「一人なんて、ちっとも楽しくない……」
泣きそうな顔のままで。
「○○と一緒だから、今、私は笑ってるんだ……」
明るい笑顔に秘められた、自身の胸のうちを明かしていく。
一筋の涙が、頬を伝ってぽたりと落ちた。
雫は畳に滲んで広がる。
その事実を隠すように、彼女は顔を俯かせた。
ああ。
今、理解した。
だからコイツは……
鬼。
最強の一つとして語られる種族。
人に恐れられ、人に語られた種族。
今はもういない、忘れられた種族。
幻想郷に彼女一人だけの……種族。
ひとりぼっちの、鬼。
俺は馬鹿だ。
陽気な面ばかりに囚われて、彼女の本質を理解していなかった。
何故いつも俺に甘えてくるのか?
今はその理由が良く判る。
だから俺は……
「なあ萃香」
彼女の名を呼んだ。
自分の名を呼ばれ、彼女は顔を上げる。
顔は涙でぐちゃぐちゃだった。
「お前の酒、注いでくれねえか?」
それには触れずに、指を差す。
差した先は、彼女の瓢箪。
彼女は予期せぬ発言に少しの戸惑い見せつつも、黙って従った。
差し出した湯呑みに、おずおずと酒を注ぐ。
程無くして湯呑みは酒で満たされた。
「サンキュー……じゃあ、お返しに」
瓢箪を彼女の手から奪う。
代わりに彼女の手には湯呑みを。
「え?」
「溢すなよ~?」
驚く声を無視して、彼女の持つ湯呑みに酒を注ぐ。
数秒と経たずに湯呑みは酒で満タンになった。
「よっしゃ、それじゃあ……」
瓢箪を傍に置いて、自分の湯呑みを持つ。
そして……
「かんぱーーーいっ!!」
かきん、と互いの湯呑みを軽くぶつけ合った。
湯呑みの中身を一息で喉の奥に流し込む。
一気に呑んだ為か、かっと身体が熱くなった。
「っぷはーーーーーっ!」
空になった湯呑みを叩きつけるように台に置く。
萃香は、ぽかんとした様子でこちらを見ていた。
両手に持った湯呑みには、まだ酒が波々と入ったままだ。
「なんだ、まだ呑んでねえのか?」
「え?」
「乾杯の時は一気飲みが恒例だろ。早く呑めい!」
「え、え?」
急変したこちらの態度に、おろおろと慌てる萃香。
これはこれは、中々珍しいモンが見れたな。
萃香は手に持った湯呑みと俺を交互に見つめる。
そんな萃香に向けて俺は……
「時化たツラしてんじゃねえ、酒は楽しく呑むモンだ」
笑って言ってやった。
「あ……」
彼女の口から言葉にならない声が漏れる。
酒は楽しく呑むもの。
それは彼女自身が言った言葉。
だからこそ、その意味が良く分かった。
腕で眼をごしごしと擦る。
そして湯呑みに注がれた酒を一気に呑んだ。
「ぷはあっ!」
「お~良い呑みっぷりだ!」
呑みっぷりの良さを称える。
萃香は呑み終えた湯呑みを台に置き……
「うわ~~ん○○ーーーーーっ!!」
飛びついてきた。
「どわっ!?」
不意を突かれた俺は、そのまま後ろに倒れ込む。
「嬉しいよ~~~!」
倒れたことも構わずに、萃香はすりすりと頬に頬を摺り寄せる。
「もう○○好き~~~っ!」
彼女は何かのスイッチが入ったらしく。
「大好きだよ~~~っ!!」
かなりテンションが上がっていた。
「好き好き好き~~~っ!! ○○大好き~~~っ!!」
テンションに倣って、摺り寄せる速度も加速度的に上がっていく。
……って、いや、これすりすりってレベルじゃねえぞ!
なんか頬がすんげえ熱いんですけど!?
「わかった、わかった!」
このままじゃ頬が焦げる。
直感した俺は、制止に入った。
「嬉しいのは充分わかったから、早く呑もう!」
その言葉に、ピタリと頬を摺り寄せる動きが止まる。
そして萃香は勢い良く上体を起こし……
「そうだね! 呑もう呑もう!」
笑った。
それを見て、安堵の息を漏らす。
ふぅ、助かった。
「今日は朝まで飲み明かすぞ~~~っ!!」
萃香はそう言って瓢箪の酒をラッパ呑みする。
「ちょ、人の体の上で呑むなっ!」
零れてるっつーの!
彼女の口からあぶれた酒の雫が、ポタポタと顔に落ちてくる。
「にゃはははは、気にしない気にしな~い」
こちらの苦情など、気にしてない風に笑う鬼娘。
その顔は、心底楽しそうだった。
やれやれ。
笑う萃香を見て安堵する。
明るい笑顔。
やっぱりコイツには笑顔が似合う。
出来れば、ずっと笑っていて欲しい。
その点で言えば、今回の出来事は俺的には収穫だった。
笑顔に隠された孤独。
明るく見える彼女の、寂しがり屋な一面。
そういえば……
アイツと似ているな。
大切な二人の少女。
そのうちの一人が脳裏に浮かび上がる。
紅白の巫女服に身を纏った少女。
素っ気無く見えて、その実甘えたがり。
うん、良く似ている。
障子から漏れる陽の光はオレンジ色。
もうそんな時間なのか。
紅魔館はそろそろディナーの時間だろう。
豪勢な食事が並べられる様を、涎を垂らしながら見つめる極貧巫女。
同情の涙を流しながらその様子を見守る、館の住人達。
……やべえ、素で想像出来るわ。
館の住人達の心情を悟りつつ、切なくなっていると……
「こら~○○~。何ボーっとしてんの~、○○も呑もうよ~!」
可愛らしい不満の声が聞こえた。
萃香はアヒル口でこちらを見つめている。
巡らせていた思考をストップさせた。
そうだな。
今はお前と呑んでるんだもんな。
今夜の相手は紅白の巫女でも緑白の巫女でもない。
誰もが恐れおののく強大な力を持った、寂しがり屋の鬼娘。
余計な思考は無用。
今は彼女との酒を楽しもう。
「よっしゃ、じゃあ……」
答えつつ、視線を彼女に移したその時。
世界が、止まった。
「……っ!?」
衝撃に言葉が詰まらせた。
ドクン。
心臓が大きく跳ねる。
目の前には、酒を呑む幼女。
だが其処に俺の意識は向いていない。
注目はそれより僅かばかり下の部分。
口から滴り落ちた液体によって身体に描かれる濡れた糸。
その終着地点に、ソレはあった。
ソレは生まれたばかりの穢れを知らない無垢な蕾。
ソレは未成熟故に、稀有な甘さを持つ極上の甘露。
ソレは酒池に溺れし者を更なる底へと誘う極楽の器。
ソレハ……
遠くで獣の声が聴こえた。
腋。
世界を作った神が、地上に落とした一粒の奇跡。
この世に唯一つ残された希望の楽園。
今、その楽園が扉を開けて俺の前に佇んでいた。
ごくりと、唾を飲み込む音。
その音にハッとする。
何を考えているんだ俺は!?
そして急速に意識をソレから逸らした。
青い果実。
そう、青い果実だ。
だから興味無い。
前にそう思った筈だろ!?
自身を問い質す。
けれど……
目の前にある、腋。
それ単体では、只の青い果実。
だが今は……
腋に艶かしく線を引く、透明な液体。
熟成されたその雫が未成熟な器と混じり合い、隠匿された神秘へと姿を変える。
ソレは極上の愉悦。
再び喉が鳴る。
夕陽がソレを照らした。
照らされたソレは、きらきらと眩い光りを放つ。
まるで雨の後の蜘蛛の巣のよう。
自身の身を滅ぼすことを理解して尚、飛び込みたくなる妖しさ。
先程よりも近くで、獣の雄叫びが響いた。
五月蝿い!
獣に言う。
俺は……俺は誓ったんだ!
俺は両方頂く。
アイツ等の『腋』しか、俺は求めない。
そう、自身に誓ったんだ。
その誓いを破るワケにはいかない。
獣に惑わされぬよう、キツく歯を食い縛る。
『馬鹿が』
侮蔑の声が、耳に届いた。
気が付くと、俺は真っ暗な空間に居た。
漆黒の闇が何処までも続く空間。
生命の存在を拒絶したような黒。
その空間を、俺は知っていた。
スポットライトが、ある一点を照らす。
照らされた先には巨大な獣……ではなく。
見知らぬ男が居た。
武道着のような服を着込んだ、屈強な男。
微かに、獣臭がした。
『よう』
男はそう言って、俺に向かって軽く手を上げる。
そしてゆっくりと近づき、三歩程の距離を置いて立ち止まった。
一瞬の静寂。
気まずさに耐えかねた俺は、何か喋ろうとして……
胸倉を掴まれた。
「なっ!?」
何するんだ、とは言えなかった。
男の身体から、見て取れる程の殺気が出ていたからだ。
『何故、あの鬼を喰らわない?』
男は問う。
何故そんなことを、とは聞くまでもなかった。
「アイツ等の腋じゃないからだ」
答えた瞬間、胸倉を掴む力が強くなる。
そして……
『馬鹿がッッッ!!』
勢い良く投げ飛ばされた。
数秒の空中飛行の後、地面を転がる。
三回転程して、ようやく俺の身体はストップした。
衝撃に息が詰まる。
『忘れてるんじゃねえッッッ!!』
倒れている俺に向けて、男は言う。
忘れている?
何を?
男の言葉を理解出来ない。
一体、何を忘れているっていうんだ?
分からないでいる俺に、男は言い放った。
『あの鬼は、お前になんと言った?』
萃香が俺に言ったこと?
思考を巡らせる。
答えは直ぐに出た。
<襲いたかったら襲っても良いんだよ~?>
……あ。
言った。
そうだ、確かに彼女はそう言った。
『思い出したみてえだな』
俺の様子を見て、男は口元を歪ませる。
「ああ」
それに頷いて返す。
だが……
だからと言って、そう簡単に割り切れるモノではない。
『考えるな』
悩む俺に、男は言った。
『お前のそれは、侮辱だ』
吐き捨てるように言葉を放つ。
『目の前の神秘だけを見ろ』
その言葉に、心が反応した。
顔を上げて男を見る。
「目の前の神秘だけを、見る?」
『そうだ』
反芻した言葉を、男は肯定する。
男の瞳が、言葉が、とても熱かった。
そうか。
身を縛る鎖が解ける音が聴こえる。
俺は……
頭の中はとてもクリアだ。
俺は何を悩んでいたんだろう。
何も悩む必要なんてなかったのに。
其処に、自身の欲する『腋』があるのならば。
『そうだ』
まるで頭の中を読んだかのように彼は二度目の肯定をする。
『ただ……』
彼は言葉を紡ぐ。
ああ。
今、俺がするべきことは唯一つ。
「美味い料理を喰らうが如く」
『美味い料理を喰らうが如くだ』
重なる言葉に男は笑った。
それは本来の意味の、笑顔。
迷いはもう無かった。
『行け』
もう用は無いと言わんばかりに。
男はこちらに背を向ける。
ああ、言われなくても行くさ。
大きく空気を吸い込む。
そして……
「オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオッッッ!!」
獣のような叫びが、暗闇を切り裂いた。
「どうしたの○○~?」
様子を伺う彼女の声。
だがその声は、耳には届いても脳には届いていない。
今の俺の頭には、もう何も届かない。
「○○?」
返事が無いことを不思議に思ったのか、彼女は首を傾ける。
「お酒呑まないの~?」
そう言って、萃香は瓢箪を見せる。
酒?
ああ、酒なら呑むさ。
「ね……」
「そうだな、じゃあ貰おうか」
言葉を遮って言う。
「そう? じゃあ注ぐね~?」
萃香は不思議そうな顔をしながら、自身の手を台に置いてある俺の湯呑みに伸ばす。
その腕を、掴んだ。
隠された秘境が顔を覗かせる。
口元が醜く歪むのが分かった。
「え?」
突然腕を掴まれたことに戸惑う萃香。
その声を無視して俺は。
その秘境に……
しゃぶりついた。
「うひゃあ!?」
驚きの声が上がる。
しかし、今の俺にはそんなものどうでもいい。
口の中を神秘が蹂躙してゆく。
な。
舌先をビリビリと刺激する未曾有の味。
甘く濃厚なソレは、所狭しと口内を暴れ回る。
なんだ。
鼻腔を強烈に刺激する、芳醇な香り。
甘酸っぱい、聖母のような、生まれたての生命のような、神秘的な匂い。
なんだコレは。
唇を包み込む、スライムのように柔らかな感触。
吸い込む勢いによって様々に形を変えるソレは、逆にこちらが吸い込まれるような錯覚を感じさせた。
それらが一体となって、味覚を、嗅覚を、触覚を犯していく。
「ひゃ、あ……」
うお……
余りの刺激に、堪らなくなって飲み込む。
原始の炎のような熱が、俺の喉を焼いた。
神々が居た太古の時代。
其処に確かに存在した、極上の醸成酒。
禁断の果実のみで精製された、禁忌の美酒。
ソレが今、自身の中に流れ込んでいる。
美味い。
なんという美味さだ。
先程呑んだ酒など足元にも及ばない。
禁断とされるに相応しい味。
想像を遥かに上回るソレに、気が狂いそう。
神は、こんな名酒を呑んでいたのか。
飲み込んだことによって、口の中が空になる。
いつの間にか呼吸は荒くなっていた。
もっと。
もっとだ。
掴んだ腕を上げる。
腕を上げたことにより、更に呑みやすくなった。
さあ二口目だ。
「な、なにを……」
怯えたような声。
構わずむしゃぶりついた。
「ひゃっ」
一口目と変わらない衝撃が俺を襲う。
再度口内に侵入した美酒が、舌の感覚を、脳の機能を。
唇を優しくも荒々しく包み込む器が、唇の感覚を。
徹底的に破壊していく。
霞んでいく思考。
薄れていく自我。
そんな中でも鮮明に浮かぶ、たった一つの言葉。
美味い。
美味いっ。
美味すぎるっ!
それしか浮かばない。
心が、体が、神の生み出した奇跡の酒を求めていた。
「ぁあぁぁ……」
もっと。
もっと呑ませろ……っ!
荒々しく腕を固定する。
「も、ゃめ……ぇ」
懇願する声を無視して、むしゃぶりつく。
じゅるじゅると音が鳴った。
口元から、涎とも酒ともつかない液体が溢れる。
それらを拭うこともせずに、がむしゃらに酒を呑んだ。
じゅるじゅる、じゅるじゅる。
響く音。
それさえも己の精神を犯していく。
「ゃ……ぁぁ」
喘ぐ様な声。
構うものか。
今はこの酒を呑むことだけに神経を集中させろ。
壊れかけの脳に、伝令を送る。
繰り返すように、酒を啜る。
止まらない欲求。
鳴り響く狂騒。
全身を支配するカタルシス。
そして意識が崩壊する直前。
何かが爆発した。
轟音が辺りに響き渡る。
「な、なんだ?」
その音で我に返った俺は、急変した状況に辺りを見回す。
吹き飛ぶ戸。
反響する轟音。
揺らぐ煙。
猛烈に熱を奪う寒波。
そんな中、俺は見た。
吹き飛んだ戸があった場所。
その奥に陽炎のように佇む、大きな袋を手に持った少女。
心臓が凍る音が、聴こえた。
そして疑問。
何故?
何故彼女が此処に?
その疑問が解ける前に。
少女は姿を消した。
あれ、と思った時にはもう手遅れ。
後ろから感じる強烈な殺気。
それとともに発生した膨大な……熱。
「ちょ、ま……」
制止の言葉。
その全てを言い終わる前に。
「こんの浮気者おおおおおおおおおおおおおっ!!」
俺の意識は根こそぎ刈り取られた。
意識の途絶えるほんの僅かな瞬間。
紅い吸血鬼の嘲笑う声が聴こえたような気が、した。
ふと辺りの暗さに気付く。
見ると、外には夜の帳が下りていた。
ぶるりと身震いが起こる。
寒さが増していることに、今更になって気付く。
もうそんな時間か……
暗闇の中、手探りで灯りを点す。
ほどなくして、暗い室内を照らす光が現れた。
灯りを見つめる。
囲炉裏に火は点けない。
今、熱は欲しくなかった。
そして俺は、それからのことを思い出す。
あの後。
目を覚ますと、全身包帯まみれで自宅の布団に寝かされていた。
自身のしでかしたことを理解した俺は次の日、無理を押して再度博麗神社に向かった。
そんな俺を待っていたのは。
夥しい量の弾幕だった。
もう有無を言わさん程の。
仕方無く博麗神社に行くのを諦めた俺はそのまた次の日、守矢神社に向かった。
そして俺を待っていたのは。
凄惨な弾幕だった。
それはもう、殺す気満々の。
実践同然の本気の弾幕。
どちらも逃げ帰れたのはラッキーとしか言いようがなかった。
そこでふと疑問が湧いた。
霊夢はともかく、何故早苗ちゃんまで怒っているのか?
その疑問は、知り合いの烏天狗に聞くことで解決した。
曰く、守矢神社を紅魔館の主が訪れたとのこと。
それを聞いた瞬間、疑問は怒りに変わった。
同時に、霊夢が紅魔館から早く帰宅した理由も理解する。
永遠に紅い幼き月。
彼女の持つ能力は、運命を操る程度の能力。
その能力は、先の運命さえも見通すことが可能だと言われている。
ということは。
視えた運命のうちの『どれか』を選択することも、彼女にとっては朝飯前ということだ。
すなわち。
俺はあの吸血鬼に嵌められたということになる。
その事実に俺は怒り狂った。
が、今となってはどうしようもないこと。
正直言って、かなりのダメージだった。
火が揺れる。
去年の大晦日のように、彼女達が此処を訪れることもない。
来るのは、村の友人達と……
「やっほ~~~~!」
鬼だけだった。
「遊びに来たよ~~~~!」
「おう」
突如目の前に現れた幼女。
それに驚くこともなく返事を返す。
伊吹萃香。
あの件以来、彼女は頻繁に我が家を訪れるようになっていた。
落ち込む俺を見兼ねたのか、はたまた只の気まぐれか。
彼女は足繁く此処に通っている。
そのことが、今の俺にとって唯一の救いだった。
だが、今回は更に特別。
「それで、どうだった?」
彼女に尋ねる。
「駄目だった」
彼女は肩を大きく落としてそう言った。
「やっぱりかぁ~……」
釣られるようにこちらの肩も落ちる。
「そんな気はしてたんだがなぁ……」
特別の理由。
それは……
「もう全然駄目。霊夢は○○のことを口に出すと何も喋らなくなるし、
早苗は早苗で、『○○さんなんて知りません!』の一点張りだし……あ、諏訪子と神奈子は○○に会いたがってたよ!」
萃香は結果を報告する。
そう、俺は萃香に彼女達の心情調査を依頼していたのだった。
そこから何か現状を変える糸口でも見つけ出せればと思ったのだが……
結果は言わずもがな。
聞くのも耐えがたい現実が俺を痛めつけてくる。
せめてもの朗報は、諏訪子と神奈子さんくらいのものか。
でもまあ、あの二人は事情を知らないだろうし。
当然と言えば当然か……あ~あ。
「はぁ」
自然と溜息が出た。
天井を見上げる。
「○○?」
「いつまで続くんだろうな……」
そんな言葉が口に出た。
出したことによって、それは厳しい現実となって心を締め付ける。
今でも変わらず、休みの日には両方の神社に顔を出している。
けれど変わらないのはそこまで。
声を掛けようとすると、弾幕。
触れようとすると、弾幕。
弾幕。
弾幕。
弾幕。
まるでそれ以外は不要とばかりに。
あれ以来。
俺は彼女達と一言も言葉を交わしていなかった。
「はぁ」
また溜息。
あれから約一ヶ月。
一ヶ月だ。
一ヶ月も彼女達の『腋』に触れていない。
触りてえ。
切なさと苦しさで、胸が破裂しそう。
でもそれは叶わぬ願い。
そして湧き上がる一つの感情。
それは真っ赤な真っ赤な。
鮮血のように紅い炎。
あの……
歯がぎしりと鳴る。
あの吸血鬼め。
脳裏に移るは、紅魔。
全部。
紅い、悪魔。
全部アイツのせいだ。
身を焦がすほどの紅蓮が己を包む。
アイツのせいで、俺は……
自身の許容量を遥かに上回る怒りに溺れる。
……と。
突然。
萃香が背中に圧し掛かってきた。
柔らかい感触と確かな温度が背中から伝わる。
「○○、怖い顔してる~」
窘めるようにそう言いながら、首に手を回してきた。
「してねえ」
「してるよ~」
「してねえって」
「してる」
…………してただろうな。
「考えてたのは、あの吸血鬼のこと?」
「ああ」
全部、アイツのせいだからな。
「こうなったのも、あの野郎のせいだからな」
アイツだけは絶対許さん。
呪う様に、そう呟いた。
「そう。じゃあ……」
俺の言葉に、萃香は身体を摺り寄せ……
「私のことも、許さない?」
そう、言った。
「は?」
思わず聞き返す。
なんで?
なんで俺が萃香を?
あの吸血鬼は当然としてしばくが、俺が萃香を恨む理由はどこにも無い。
俺の動揺を無視して、萃香は言う。
「だって……私にあんなことしたせいで、こんなことになったんだよ?」
許しを乞うような口調だった。
首に回された萃香の腕は、微かに震えていた。
ああそういうこと。
彼女は、悔やんでいるのか。
自身と関わったために、こんな事態を引き起こしたと。
そう思っているのか。
そうかもしれない。
起こった事実だけを見るならば……確かに、そうかもしれない。
でも、コイツは大事なことを忘れている。
それはとても大切で、最も重要な……
一つの、信念。
回された腕を外し、自身の身体を反転させる。
そして幼女を胸の中に抱き入れた。
「な、なにする……」
わけもわからず腕の中でもがく幼女。
俺はそいつに向かって……
「ば~か」
言ってやった。
「なっ!?」
「俺がお前を恨む? 馬鹿言ってんじゃねえぞ? 感謝するならともかく、恨むワケねえだろ」
「だ、だって……」
「あれは俺が望んでやったんだ。そのことに関しては、後悔なんか微塵も無い」
そうだ、後悔なんてあるもんか。
秘境に隠された神の酒。
暴かれた、新たなる神秘。
其処に至れたことに感謝こそすれ、恨むなど有り得ない。
「俺は後悔なんてない」
強く言い切る。
「わかったか?」
そして、呆然とした顔でこちらを見つめる幼女に笑いかけた。
彼女の顔は一瞬の後。
「……うぁ」
ぐしゃぐしゃに崩壊した。
「ぅぇあっ、ひぐっ……っ」
堰を切ったように流れ出した涙が顔を濡らす。
「っ、ぅぁっ……ひっ、えぅ」
零れる涙が、俺の服に染みを作った。
嬉しさから出たためだろうか。
溢れ出した涙は、とても温かかった。
「ょ……か、った……っ…………ょか、っった、よぅ」
しゃっくり交じりの声。
良かったと。
涙声で何度も繰り返す。
きっと彼女は怖かったのだろう。
このことで、俺との繋がりが絶たれるかもしれないということが。
関わりが無くなることが。
嫌われることが。
どうしようもなく、不安だったのだろう。
馬鹿なヤツ。
そんなことあるワケねえのに。
宥めすかすように、優しく背中を擦る。
最強の鬼。
人に恐れられる存在。
その身体が、今はとても小さく、そして愛おしく感じた。
「あ~もう、泣くなって……」
赤子をあやすように背中を擦る。
心配するな。
誰もお前を一人になんかしない。
大丈夫。
ずっとずっと。
皆、一緒だ。
想いが手から伝わるよう願いながら、その背中を優しく撫で続けた。
さて。
突然ながら、此処で諺の問題だ。
泣きっ面に蜂、という言葉を御存知だろうか?
悪い状況の中、更に悪いことが起きる様を表す言葉だ。
これを俺に当て嵌めてみると……
泣き面とは、今。
つまり、巫女達に無視され続けて泣きそうな現状だ。
じゃあ蜂は?
それは今から起こるんだよ。
正確には蜂じゃなくて……
「ひっ……ひっ、うぅ」
未だ腕の中で泣き続ける萃香。
胸元を握ったまま離さない。
それを愛しげに眺めつつ、宥めていると唐突に。
「っ!!」
背中を大きな何かで突き刺された。
否、正確には刺されてはいない。
それは視線。
見るだけで人を殺すような、視線。
明確な意味を持った、殺意。
ぎちぎちと。
錆びた滑車を回すように首を後ろに向ける。
首を向けた先。
玄関。
其処には雪の寒さよりなお寒い、絶対零度を従えた……
二人の修羅が、居た。
「~~~っ!!」
予想だにしない、しかしある意味予想通りの展開に、俺の頭は恐慌状態に陥る。
そして飛び出す、様々な疑問。
な、なんで!?
どうして霊夢達が此処に!?
今までちっとも来なかったのに!!
何故今になって突然の来訪!?
なにがなんだか分からない。
混乱する脳機能。
慌てる俺を、二人は無表情で見つめている。
無機質な、鉄仮面のような顔。
ぞくりと、背筋が凍った。
ちょっと待て。
俺、なんでこんなに殺気を向けられてんの!?
その解を求め、ぐるぐると焼き切れんばかりに脳を働かせる。
今の俺の状態。
泣いている萃香を抱き締めている、以上。
つまり、それが答え。
それが導き出す結果は……
「な、なんで?」
震える声で少女達に問う。
何故、今になって此処を尋ねたのか?
これから自身に訪れる結末は分かっている。
でもだからこそ、来訪の理由を知りたかった。
俺の問い掛けに、少女達は透明な声で答えた。
「今日ぐらいに仲直りしてきたらって。そうレミリアに言われたから、来たんだけど……」
「私は霊夢さんに一緒に行こうって誘われて来たんですが……」
あのロリめえええええええええええっ!!
やりやがったなああああああああああああっ!!
高笑いする吸血鬼の姿が、浮かんで消える。
「でも……」
「ですが……」
激昂は二人の修羅の言葉で掻き消され。
それぞれの手に持つは、無数の御札と御払い棒。
「そんな必要は無かったみたいね……」
「そんな必要は無かったみたいですね……」
莫大な霊力が収束していく。
世界を破壊出来そうな程の、暴力。
それが二人の元に集まっていく。
「ちょ、ちょっと待て! これにはワケが……」
「問答無用」
「問答無用です」
説得の言葉は、一刃の元に消え失せる。
ああ、これはもう、駄目かも知れんね……
どうしようもない現実に、諦めと絶望が心を支配していった。
「○○の……」
「○○さんの……」
集まった霊力は臨界に達し……そして。
「「スケこましいいいいいいいいいいいいいいいいっ!!」」
俺は我が家もろとも、盛大にブッ飛ばされた。
この後、家が直るまで一週間。
身体の傷が全快するまで二週間。
巫女達と仲直りするのに一ヶ月掛かった。
全快してから巫女達と仲直りするまでの間の、とある日に。
萃香と諏訪子、神奈子さんを引き連れて紅魔館を襲撃したのは言うまでもない。
おまけ ~ある日の紅魔館~
「くっくっくっ……」
「お嬢様、お茶が入りました」
「ありがとう咲夜」
「最近、機嫌が宜しいですね」
「わかる?」
「はい」
「そう……」
「理由はやはり、あの男でしょうか?」
「ええ。こういうの、目の上のたんこぶが取れたっていうのかしら? とても爽やかな気分だわ」
「それは喜ばしいことですね」
「全くよ。只の人間が私の霊夢に手を出そうだなんて、百年早いわ。
あまつさえ、他の女にも手を出しているだなんて、舐めてるとしか言いようがない」
「その点については同意します」
「しかも近づいた目的が、腋よ腋? ふざけるにも程があるわ」
「まあ、人の趣味嗜好はそれぞれですから」
「そうだとしても、ふざけてるわ。霊夢も霊夢よ、あんな馬鹿と関わりを持つだなんて……」
「ですが、霊夢の方はそれほど嫌ではないみたいですね。むしろ彼の話をしている時の霊夢は、どことなく嬉しそうな……」
「咲夜」
「なんでしょう?」
「その続きは言わなくて良いわ」
「畏まりました」
「とにかく、これで邪魔者は消えたわ。後は霊夢をモノにするだけ……」
「そう上手くいくでしょうか?」
「いくわよ。先日、追い討ちも掛けておいたしね」
「追い討ち?」
「そう、追い討ち。もう完膚なきまでの」
「はぁ」
「さてと、アイツを再起不能にしたことだし……今から霊夢の処に行こうかしら?」
「それでは傘を御用意致します」
「助かるわ」
「いえ、これも務めですか……」
「さ、さ、さ、咲夜さあああああああんっ!!」
「騒々しいわよ美鈴」
「あ、すいません……って、それどころじゃないんです!」
「どうしたの中国?」
「あ、お嬢様もいらっしゃたのですか!?」
「居たら悪い?」
「いえ、そんなことはありません! 寧ろ好都合です!」
「あそう」
「で、何があったの?」
「侵入者です!」
「侵入者って……また魔理沙ね。全く、普通に入ってきなさいって言ってあるのにアイツったら」
「まあ良いじゃない、フランの良い遊び相手が出来たわ」
「ああ、それもそうですね」
「違います! 黒白じゃありません!」
「あら、じゃあ誰かしら?」
「人間です!」
「人間?」
「もしかして霊夢かしら?
ああん、折角会いに行こうと思ってたのに…………でも、会いに来てくれるなんて嬉しいわっ!」
「お嬢様……」
「紅白でもないんですっ!」
「なんだ。じゃあ誰なのよ?」
「ですから人間です! 人間の男です!」
「人間の男って……まさか」
「○○か。御礼参りでもしにきたのかしら?」
「かもしれませんね。でも、それくらいなら貴女一人でも十分じゃないの」
「それがその……鬼も一緒なんです。あと背中に柱を背負った女の人と、蛙の帽子を被った女の子が……」
「へぇ……」
「お嬢様」
「面白い……咲夜、中国」
「はい」
「は、はい!」
「迎え撃つわよ」
「わかりました」
「わ、わかりました!」
「咲夜と中国は柱を背負った女と蛙の帽子の相手をしなさい。どうせ雑魚よ、一瞬でカタをつけなさい」
「了解」
「了解です!」
「私は○○と、鬼の相手をするわ。
くっくっくっ……あの鬼め。どちらが本当に優れた種か、今度こそハッキリと分からせてあげるわ。
それと○○、貴方には地獄を見せてあげる。霊夢に手をかけた報いをその身に受けるが良いわ!」
「お嬢様、怖いです……」
「因縁の相手が一気に二人ですもの、当然よ」
「そうなんですかぁ……」
「そうなの。さ、貴女も気合入れなさい。足手まといにならないでよ?」
「はい、頑張ります!」
「宜しい。ではお嬢様……」
「ええ……出撃よ!!」
そして決戦の火蓋は落とされた。
紅魔館を攻めるは、一人の人間と三人の人外。
たった四人の侵入者。
誰がどう見ても、紅魔館の勝利は確実。
館の者達はそう信じて疑わなかった。
疑いようがなかった。
……だが。
彼女達は知らなかったのだ。
レミリアが雑魚だと罵った二人。
その二人が、高位の神だということを。
数時間後、紅魔館は壊滅的な打撃を受けることになる。
屈辱的な敗北を喫した紅魔館の主、レミリア・スカーレット。
彼女はこの後、丸三日間を掛け、『○○の素晴らしき腋講座』を受けさせられることとなるのだが……
そのことを、彼女とその従者達は知る由も無かった。
───────────
幻想郷に暖かな日差しが降り注ぐ。
全てを包み込むような柔らかな光。
それはまるで、新たに生まれる生命を祝福するかのよう。
轟と、嵐のように一際強い風が吹いた。
春一番。
春の訪れを告げる風。
始まりを意味する、旋風。
人々は新たな始まりを喜び、生活に一層の精を出す。
春とはそんな季節だ。
誰もが春の訪れを喜び、心を躍らせる。
そんな季節。
だというのに。
「はぁ……」
境内を掃除する私の気分は時化っていた。
まるで霧雨のように。
雲が心を覆っている。
今の天気とは正反対。
どんよりとした大きな雲が光を遮断し、心に影を作っている。
その理由は二つあった。
一つは、ある行事を逃したこと。
バレンタイン。
女性が想いを寄せる男性にチョコレートと共に、精一杯の愛を伝える行事。
女の子の一大イベントとも言えるその日を……
どういうわけか、私はすっかり忘れていたのだった。
まあ、忘れるに値する理由はあったのだが。
……って、別に誰かにあげるつもりじゃなかったのよ?
好きな相手なんていないし……まあ、気になるヤツなら居るけど。
いやそれも嘘っ! 冗談だから!
あんな変態のことなんて気にも留めてないわ!
ホントよ! ホントにどうでもいいの!
変態で馬鹿な男なんて、こっちからお断りよ!
……私、誰に言い訳してるのかしら。
「はぁ」
知らずと溜息が出た。
まあ、過ぎてしまったものを悔やんでも仕方が無い。
気持ちを切り替える。
実を言うと、そちらの方はまだ大した問題じゃない。
重大なのは、もう一つの方だった。
それは……
階段の方に視線を向ける。
今の時刻は、昼を少し過ぎた頃。
そろそろ、階段を上り終えたアイツが満面の笑みで。
私に飛び付いてくる。
筈なのだが……
階段からはそんな空気は感じられなかった。
苛立つ気持ちと、諦めにも似た気持ちが交互に浮上する。
いつもならこの時間帯に来る筈のアイツ。
ちょっと、いやかなりの変態で、大が付くくらい馬鹿な青年。
その彼は、今日も姿を見せない。
なんで来ないのよ。
心の中で愚痴った。
約二ヶ月前。
私はアイツと喧嘩をした。
いや、あれは喧嘩というより、一方的な暴力だろうか。
あの時、アイツは少女を求めていた。
私でも早苗でもない、別の少女。
伊吹萃香。
幻想郷で唯一人の鬼。
彼女を求めていたアイツに向けて、暴威ともいえる弾幕の嵐を叩き込んだ時の光景が思い出される。
後ろから渾身の弾幕を撃ち込まれて、夜空に飛んでいったアイツ。
……あの時は少し、やりすぎたかしら。
今更になって反省してみたが、悪いのはあっちの方なので良しとしておいた。
ともかく。
それから約二ヶ月、私はアイツと一切口を利かなかった。
アイツはブッ飛ばされた翌日も翌々日も、足繁く神社に通ってきたけど。
私は頑なに無視を決め込んだ。
代わりに、来る度にありったけの弾幕をお見舞いした。
今思うとかなり酷いことをしたと思う。
日を追うごとに怪我を増しながらも必死になって神社に訪れる彼の姿は、思い出すだけで胸が痛んだ。
でも、あの時はそれほどまでに腹が立っていたのだ。
怒り狂う自分を抑え切れなかったのだ。
一応手加減はしておいた……と、思う。
多分……きっと。
ま、まあ、それは置いときましょう。
早苗の方も同じようなことをしてたみたいだし、おあいこよおあいこ!
意味が違う?
五月蝿い、良いのよ別に。
悪いのはアイツなんだから。
……私、さっきから誰に言い訳してるのかしら。
と、とにかく。
それから二ヶ月の後、私はアイツと仲直りをした。
勿論、平謝りをするアイツを、私と早苗が許す形で。
もう怒っていないと言った時のアイツの顔はまだ覚えている。
なんというか、神を称えるような顔だった。
まあ、その後お約束の様に例の病気が始まったのでブッ飛ばしてやったのだけれども。
その次の日、アイツは夕方近くに息を切らせてやってきた。
アイツがこんな遅くにやってきたのは珍しいことだった。
理由を尋ねると、アイツは苦しそうな顔を笑顔に変えて。
『いや、二ヶ月も会えなかったから……その分を補給しようと思って』
そんなことを言ってきた。
突然の不意打ちに、不覚にも顔に熱が集まるのを実感した。
あの時感じた感情は多分、嬉しい、だったと思う。
会えなかったのはこちらも同じだったから。
二ヶ月。
言葉にすれば短く感じるが、体感するとなれば気が遠くなる程に長い時間。
その間、私の中に空白があったのは確かだった。
だから多分、あの時の私は嬉しかったんだと思う。
止まることなく紅く染まっていく頬。
アイツはそれをどう勘違いしたのか、いきなり抱きついてきた。
当然、腋に。
勿論ブッ飛ばした。
盛大に飛ばされた後、アイツはこう言った。
『明日も来るからな!』
眩しいくらいの笑顔で。
迷いも無くハッキリと。
確かにそう言った。
だというのに……
次の日、アイツは姿を見せなかった。
急な仕事が入ったのだろう。
何気なくそう思った。
けど。
その瞬間、私の心の底に何かが溜まったのが分かった。
次の日も、アイツは来なかった。
ポタリと、また何かが溜まる。
そしてその次の日も、そのまた次の日も。
アイツは来なかった。
そうして一週間が経った今日も。
アイツは姿を見せない。
ぼちゃん。
また何かが、容積を増やす。
得体の知れない何か。
それは日を追うごとに量を増して。
着実に、私の心に溜まっていった。
気が付けば辺りは紅く染まっていた。
煌々と紅く煌く夕陽に私は眼を細める。
もうそんな時間なのか。
あれからずっと境内の掃除を続けたままだったことに今更ながらに気付く。
結局、今日もアイツは来なかった。
紅く染まった空を見上げる。
そして私は思案した。
あの時。
二ヶ月前の、あの日。
萃香を襲っていた○○を目にした時。
間欠泉の様に噴き出した怒りと、もう一つの……あのいいようのない感情。
あれは一体何だったんだろう?
どろどろとした……けどそれだけじゃない、濁り。
その感情が湧いたのは、あの時で四度目だった。
それを最初に感じたのは、神社騒動で妖怪の山に殴り込みに行った時だった。
弾幕ごっこに敗れた早苗を襲う、アイツの姿を見た時。
その感情が、芽を出した。
気が付くと私はアイツに弾幕を放っていた。
二度目は私の神社。
アイツが大晦日をどちらの神社で過ごすかを決めるを早苗と勝負をして、負けた時。
落ち込む私を他所に、アイツとにこやかに話す早苗が放った一言が原因だった。
『いつも博麗神社から貰い損ねている分の御利益もプラスしちゃいますねっ!』
普段の私なら気にもしない台詞。
なのに、あの時はその言葉が凄く痛くて。
何故か、涙が止まらなかった。
三度目も私の神社。
大喧嘩をする少し前、お茶の間でアイツに甘える萃香を見た時。
突如として現れたその感情は、私の心を一瞬で支配した。
気付けば、私は湯呑みを握り潰していた。
あれは何なのだろう?
考えても考えても、答えは靄々としたものに隠されて、決して明かされない。
あれは一体、何なのだろう?
その得体の知れない感情は現れる度に大きくなって。
私の心を、じわじわと侵食していった。
それはまるで、私の心を糧にして成長するかのように。
不意にアイツの言った言葉が思い出された。
甘える萃香を眼にし、その感情に侵されていた私にアイツが言った言葉。
『お前さん、萃香が羨ましかったんだろ?』
したり顔で笑うアイツの顔が浮かぶ。
馬鹿馬鹿しい。
私は否定する。
なんで私が萃香を羨ましがらきゃいけないのよ。
ホント馬鹿じゃない?
私が萃香を羨む?
そんなこと、あるわけないじゃない。
けれど、その後自分がした行動は……
離れようとしたアイツの袖を掴んだ自分。
その後に訪れた、温かな抱擁感と。
揺り籠のような安らぎ。
ハッとして、その光景を消し去るように首を振った。
覚えてないわ。
そして私は過去を否定した。
あれは……そう、一種の気の迷いよ。
そう、気の迷い。
あの時の自分は、きっとどうかしていたのだ。
だから、ちっともおかしくない。
去年の暮れにあったことだって、気の迷いだ。
全力で過去の失態を否定する。
眼に映る夕陽がとても眩しかった。
馬鹿なこと考えちゃったわね……
無駄なことに時間を使ったことに後悔する。
そして視線を空から外し、階段に向けた。
鳥居の奥からは、誰も訪れる気配は無い。
今日はもう来ないだろう。
そう判断した私は、部屋に戻ろうと踵を返した。
その時だった。
「ん?」
唐突に、後ろから人の気配を感じた。
○○?
やっと来たのかしら。
久しぶりの来訪に、ほんの少し、気持ちが昂ぶった。
心臓が音を立てて脈動する。
けれどそれを悟られないよう、表面上はいつもどおり冷静に。
来訪をなんとも思っていないかのように振り向いた。
其処には。
○○ではなく……
「おっす霊夢!」
黒白の魔女が、居た。
箒を持った手とは逆の手を挙げ、こちらに声を掛ける少女。
顔には人懐っこい笑みを浮かべている。
それは夕陽との相乗効果で、とても眩しかった。
「魔理沙?」
予想とは違う人物の登場に、私は若干肩を落とす。
落とした瞬間、はたと気付いた。
なんでがっかりしてるのよ!?
驚きは自分に。
○○じゃなかったことが、そんなに……
巡る思考。
そんなに、落ち込むこと……なの?
動揺する精神。
疑問を裏付けるように、昂ぶっていた感情は徐々に静かになっていった。
「ああ、私だけど……どうした? なんか問題あったか?」
魔理沙は頭にハテナマークを浮かべながらこちらを見やる。
悟られてはいけない。
何故かそう思った私は、急いで思考を中断させた。
できるだけいつもどおりに言葉を返す。
「別に? なんの問題も無いわ」
「そうか、なら良かったぜ」
「こんな夕方にどうしたの?」
「いや、今紅魔館に寄った帰りでな? 近くを通ったから晩飯でも御馳走になろうかと思って……」
にしし、と彼女は明け透けも無くそう告げる。
その様子にホッとした。
どうやら気付かれていないようだ。
危ないところだった。
彼女に悟られたら、何を言われるか分かったもんじゃない。
胸を撫で下ろす。
この思考さえ不自然ということに、今の私は気付いていなかった。
「全く、材料もタダじゃないんだからね?」
「まあまあ、この借りは気が向いたら返すぜ」
渋るように言う私に、魔理沙は笑う。
「はいはい、じゃあ今から作りますか」
「おう、今夜の献立は何だ?」
「今夜は……そうね、寒いから鍋にしましょうか?」
「うっひょー! 鍋とはまた豪勢だな! なんか良いことでもあったのか?」
言葉に、思考が止まった。
良いこと?
また、どろりとした何かが。
良いことなんて……
這い上がり、心を覆う。
良いことなんて、一つも……
「霊夢?」
「え、あ、なに魔理沙?」
様子を伺う声に、驚いて返事を返す。
「いや、なにって……今日の霊夢、何か変だぞ?」
心配そうな顔。
いけないいけない、しっかりしなきゃ。
大急ぎで体面を整える。
「別にこれといって良いことなんて無いわ。寒いからなんとなく、よ」
「ならいいんだけど……」
魔理沙は納得行かない顔をする。
こちらの様子から何かを感じ取ったのだろう。
全く、変なところで勘が鋭いんだから……
「さ、早く準備するわよ。アンタも手伝いなさい、じゃないと食べさせてあげないわよ?」
考えを逸らすためにそう言って、歩き出す。
「へいへ~い」
魔理沙もそれに習って歩き出した。
これで一安心。
そう思った矢先だった。
「そういえば、今日○○を見たぜ」
そんな言葉が耳に届いたのは。
突如魔理沙の口から現れたアイツの名前に、思考は急停止する。
鼓動が早まるのが分かった。
魔理沙の方を振り返る。
○○を?
いつ?
何処で?
止め処なく溢れる疑問。
けれどそれらは、言葉にはならなかった。
「……え?」
震える喉から代わりに出たのは、その一言だけ。
心臓の早鐘は加速度的に速度を上げている。
「ど……」
何処で?
再度試みたが、最後まで続かない。
何故。
何故私の声は、こんなにも震えているのだろう?
まるで聞くことを拒むかのようだ。
聞いてはいけない。
頭の隅から、そんな言葉が聞こえた。
彼女はこちらの変化に気付かずに。
未完成の言葉の意味を理解したのかしていないのか分からぬまま……
「湖の上を飛んでた時にチラリと見かけただけだから、ハッキリそうだとは言えないんだが……
確か、萃香と居たな~。なんか二人共、やけに楽しそうだったな」
答えた瞬間。
頭の中で何かが壊れる音が、聴こえた。
彼女の口からでた言葉の意味を、麻痺した脳で咀嚼する。
萃香と居た。
魔理沙は確かにそう言った。
なんで?
なんで萃香と居るの?
私の所には一度も来ないくせに。
楽しそうだった。
どうして?
どうして萃香と楽しそうにしているの?
私はこんなに……
ぎしりと。
胸の奥が悲鳴を上げるように軋んだ。
そして這い上がる、二つの感情。
疑惑と……これは悲しみだろうか?
それらが私の心をじわじわと蝕み始める。
何故悲しいの?
答えは見つからなかった。
「只の人間の癖に鬼と親交があるとは……○○もやるねえ」
何も知らない魔理沙は言葉を続ける。
無知な言葉が、棘となって心に突き刺さる。
もういい。
「でも良い感じの雰囲気だったな~……もしかして、アイツ等そーゆう関係とか?」
ずぶりと。
無自覚の槍が、深々と突き刺さった。
もういいから。
心の中で叫んでも、それは彼女には決して届かない。
もうやめて。
私は魔理沙に気付かれぬよう、俯いて。
小さく、唇を噛んだ。
いつの間にか箒を持つ手は小刻みに震えていた。
お願いだから。
響く心の声。
その声は無慈悲にも。
唐突に現れた更なる悲報によって……
残酷に掻き消された。
「○○なら私も見たわよ?」
突如出現した新たな声。
私は苦痛を表に出さぬよう、精一杯の努力をしながら顔を上げる。
その声の主は、自分の良く知っている人物だった。
「こんばんは、霊夢」
目の前には、上品に礼をする少女。
レミリア・スカーレット。
紅魔館の主。
彼女がこんな時間に此処を訪れることは珍しいことだ。
けれど、今はそんなことに頭を使っている余裕は私には無かった。
頭の中では、まだレミリアの言った言葉が響いている。
「レミリアがこんな時間に神社に来るなんて、珍しいこともあるもんだな」
「それはお互い様よ、魔理沙。貴女こそ、珍しいじゃない?」
「そうか? 普通だぜ?」
「なにが普通なんだか……」
「まあ気にするな。ところで、お前も○○を見たのか?」
「ええ、昨日会ったわ」
会った?
一体何処で?
急かす思いで二人の話に耳を傾ける。
「へえ……何処で?」
「散歩中に、森の中で」
「森の中? また珍しい処であったな」
「全くよ。逃げようと思ったんだけど……」
一端区切って、レミリアは顔を曇らせる。
苦虫を噛み潰した様に顔を顰めるレミリアを見て、魔理沙は続きを促せた。
「逃げるって……お前が?」
「……ええ」
「なんでまた?」
「五月蝿いわね、貴女には関係無いでしょうに」
「ふ~ん……まあ良いや。でも会ったってことは、結局捕まったってことか?」
「ええ、目ざとく見つけられたわ……」
「ほほう、それで?」
「一時間」
「一時間?」
「説教の時間よ」
「説教? なんの?」
「関係無いわ」
「またかよ」
二度目の黙秘に魔理沙は呆れ顔で返した。
関係無い。
確かに、私には関係無い。
私が知りたいのはそんなことじゃない。
そんなことはどうでもいい。
どうでもいいから、早く……
急かすような気持ちは、更に強くなる。
『本当に聞いていいの?』
囁くような声を、私は無視した。
「五月蝿いわね。で、その後開放されたんだけど……釘を刺されたわ」
「ほほう、なんて?」
「今から守矢神社に行くから邪魔をするなよ、って」
ビクンと。
身体が跳ねた。
耳元で反響する言霊。
やがてそれは形を持って脳裏に鮮明に映し出される。
守矢神社。
その場所が導き出す答えはつまり。
早苗の……とこ、ろ?
口元が引き攣った。
東風谷早苗。
アイツが良く通っている、もう一つの神社に居る巫女。
アイツが好きな、少女。
混乱は極みに達する。
神社に来ないアイツ。
萃香と居たアイツ。
早苗に会いに行ったアイツ。
全てを繋げた瞬間。
ぱきん。
大切な何かが、割れた。
そして私の心身は急速に熱を失っていった。
「守矢神社? なんでまたそんな処に?」
「あら、貴女知らないの? ○○って、守矢の巫女に御執心なのよ?」
「うっそ!? マジで!?」
「マジもマジ、大マジよ。まあ、随分と特殊な感情なんだけど……」
他愛も無い話を二人は続けている。
けれど私にはそれが良く聞こえなかった。
既に私の心は、氷のように熱を失くしていたから。
「ん? そこでなんで霊夢を見るんだ?」
「へっ!? い、いや深い意味は無いのよ?」
「怪しいぜ」
「うぅ……あ、そういえば」
「なんだ?」
「○○のヤツ、この間紅魔館に来てたらしいわ」
「紅魔館に?」
「ええ。詳しいことは知らないけど、厨房に用があったみたい……」
「厨房にねえ……飯でもたかりに来たとか?」
「さあ? 何か作って、持って帰ったとは聞いたけど……」
「晩飯でも作りに来たのかね? 私ならそのまま食べて帰るけど……」
「貴女は例外も例外よ。一緒にしちゃ、他の人間が可哀想ね」
「言ってくれるじゃないか……っと。あ~、私も思い出したぜ」
「何を?」
「いやな? この間、アリスんとこに遊びに行ったら断られたんだよ。
で、理由を問いただしたらなんと……」
「なんと?」
「○○に付き合ってて寝てないの、ときたもんだ!」
「うわ~、それって……」
「怪しいよな?」
「怪しいわね。一体、二人で何をしてたのかしら?」
「さあな~……粘っても、そこだけは教えてくれないんだよ。
なんか、○○との約束だから無理、とかなんとか……」
「それは更に怪しいわね~……」
「だろだろ?」
楽しそうに話をする二人。
その会話の中で、拾った言葉を分析する。
凍った心でも言葉は届くのか。
自嘲気味に笑いつつ、言葉の意味をのろのろと理解する。
理解した意味はとても冷徹で、冷酷だった。
そうなんだ。
無自覚な悪意。
アイツは、早苗と萃香だけじゃなくて。
無邪気な刃。
他にも、色んな人と会ってるんだ。
無遠慮な痛み。
色んな人に……親しまれてるんだ。
無知という名の暴力。
けれど……
そして残酷な。
私は其処に、含まれていない。
一つの事実。
それらが私の心を粉々に打ち砕く。
それは容赦無く、無慈悲に。
悲鳴の声は瓦礫の音に掻き消され。
私の中で変わらずに残ったのは、仮面の様に変わらない顔だけだった。
「いや~。まさかアリスにそんなヤツが出来るとはなぁ……」
「まさかあの人形遣いがねぇ……奥手だと思ってたけど、驚きだわ」
「だよな……ん? そーいや○○って、早苗に随分と入れ込んでるって、お前さっき言ってなかったか?」
「ええ、そう言ったわ」
「つまりそれって、二股ってことじゃないのか?」
「いいえ、二股じゃないわよ?」
二人は会話に華を咲かせている。
何処にでもあるような内容。
けれど、それは私にとって、無数の牙に見えた。
牙が私の心身の残骸を無造作に喰い漁る。
貪る様を人事のように見つめながら、ふと思う。
これは本当に自分なのだろうか?
疑問に、答えは返ってこなかった。
甦るアイツの言葉。
『明日も来るからな!』
あの時、確かに言った言葉。
その言葉に対し私は……
嘘吐き。
搾り出す様に、そう吐き捨てた。
「なんでだよ、早苗のことも好きなんだろ? だったら……」
「正確には四股になるわ」
「よっ!? ちょ、ちょっと待て! 四股って……他に誰が居るっていうんだ?」
「あの鬼も、○○に御執心みたいよ?」
「鬼って……萃香のことか?」
「それ以外に居る?」
「嘘だろ……何処まで節操無しなんだアイツは」
「まあ、アイツは特殊だから……」
「特殊っていっても限度ってモンがあるだろ……」
「同感ね。全く、霊夢もあんなヤツの何処が良いのかしら……少しだけ理解しかねるわ」
「こっちは少しどころじゃないんだが……って、なにい!? もしかして、霊夢もなのか!?」
「貴女、それも知らなかったの?」
「知らないもなにも……初耳だぜ。まさか霊夢と○○がそんな仲だったとは……」
魔理沙が予想外といった声を上げる。
『大丈夫よ、もう終わりだから』
誰かが答えた。
そうね、もう……
「今日の魔理沙は、知らないことが多いわね」
「正直言って、今日は驚きの連続だぜ。まさか○○が女たらしだったとはなぁ……」
「女たらしというよりは、只の変態ね」
「それ、悪くなってないか?」
「良いのよ別に、本当のことなんだから」
「なんだか良く分からんが……」
「は~あ。霊夢もあんな無節操なヤツなんて放って置いて、私と愛し合いましょうよ~…………っ!?」
「ん? どうしたレミリア? 霊夢がどうかし…………なっ!?」
突然、会話が途切れた。
静寂が場を支配する。
どうしたのだろう。
不意に生まれた静寂が気になった私は、切れかけの意識を視界に集中させる。
意識が途切れ掛けているためか、目の前は滲んでいた。
二人は私の方を見つめている。
何故か二人の顔には、驚愕と困惑が貼り付いていた。
「れ、霊夢……?」
動揺を詰め込んだ声でレミリアが尋ねる。
「なに?」
辛うじて声帯は機能してくれた。
いつもと同じ抑揚の声が、意味を持った音となって口から発せられる。
だが、それも彼女達の動揺を促す結果にしかならなかった。
「何って……急にどうしたんだよ?」
今度の声は魔理沙から。
彼女は不安そうな声で尋ねた。
一体何のことだろう?
良く分からない。
「別に、どうもしないけど?」
同じ抑揚の声で返す。
返事に、魔理沙は吃驚したようだった。
何をそんなに驚いているんだろう。
「まさか、お前……」
不思議に思っている私に、魔理沙は言いにくそうに……けれどハッキリとした声で。
「自分が泣いていることに、気付いてないのか?」
そう、言った。
「え?」
疑問の声は自分の口から。
泣いている?
私が?
そんな筈は無い。
ズタボロになった心身の中、唯一まともに残っている仮面。
いつもと変わらない無表情。
その筈だ。
事実を確かめるために、私はゆっくりと頬に手を当てる。
温かな液体が指先を伝った。
熱い。
涙。
なんで?
なんで私は泣いているんだろう?
不思議に思いつつ、何度も目元を擦る。
擦っても擦っても。
その度に涙は溢れ出して、頬を濡らす。
わからない。
何故こんなにも涙が出るのか。
わからない。
何故こんなにも胸が苦しいのか。
わからない。
何故こんなにも寂しいのか。
え?
突然飛び出した予期せぬ言葉。
その言葉に私は驚愕した。
寂しい?
先程自分の中から現れた、確かな想い。
それを私は……
そんな筈は無い。
否定した。
そうだ、そんな筈は無い。
寂しいなんて有り得ない。
ずっと前から、私はこの神社に一人で生きてきた。
生まれてから、今までずっと一人で。
けれど、それを寂しいとは思ったことなど一度も無かった。
だって、それが当たり前だったから。
博麗の巫女。
人外を討ち、人外から恐れられ、そして人からも恐れられる。
誰に対しても平等で、誰に対しても無関心。
誰にも無情で、誰にも不干渉。
全てにおいて中立の存在。
それが私。
それが博麗。
だから私は一人で生きていく。
今までも、そしてこれからも。
たった一人で。
生きていける……筈だったのに。
ああそうか。
そんな私の前に。
アイツが現れたんだった。
只の人間の癖に、暇を見付けては神社に来る変わり者。
特殊な性癖を持つド変態で。
どうしようもない程の馬鹿。
呆れるくらいの愚か者。
でも……
本当はとても優しくて、とても温かな人。
素直じゃない私を優しく包み込んでくれる人。
博麗の巫女としてでなく、一人の少女として私を見てくれる……唯一人の存在。
いつも見ていたアイツの笑顔。
それが今は……
何かが胸に去来する。
どろどろとした……けれど、それだけではない想い。
ああ、私は……
それが何なのか、私はようやく理解した。
私は……
早苗を襲うアイツを目撃した時に生まれた感情。
早苗と楽しげに語らうアイツを見た時に感じた気持ち。
アイツに甘える萃香に犯された欲望。
萃香を襲うアイツを眼にした時の情操。
二ヶ月の空白と、一週間の今。
誰も居ない境内と、訪れることの無い待ち人。
そうか、そうだったんだ。
それらが導き出す、一つの感情。
寂しい。
そうだ、私は寂しかったんだ。
アイツが居ないことが。
アイツの笑顔を見れないことが。
アイツが私を見てくれないことが
アイツの温もりを感じられないことが。
どうしようもなく。
どうしようもなく、寂しかったんだ。
その事実を認識した時……
許容は限界に達した。
「うぁ……」
声が漏れる。
決壊は喉から出たそれを引き金にして。
「っく、うぇ……ぁぁっ」
溜まった全てが溢れ出した。
ごちゃまぜになった感情が、津波のように押し寄せる。
理解した今、もう止めることは出来なかった。
「れ、霊夢っ!?」
「なんだなんだ!?」
二人の驚く声が聞こえる。
けれどそれに返す言葉は思い浮かばず。
「うぇっ……ひっ、く…………ひっ、うぁぁっ」
ただ鳴咽が喉から漏れ出す。
止め処なく溢れる涙は、頬を伝って次々と地面に落下する。
大地に落ちた雫達は、様々な形の染みを作っていった。
「……ひっ、ぐ……うぁ、っ…………ぅぇぇっ」
止まらない感情の波。
それらは一つとなって、私の心を攫っていく。
そんな中、目蓋に浮かぶアイツの笑顔。
そして紡がれる、一つの言葉。
「ちょ……どうするのよ魔理沙!?」
「どうするもこうするも……私に聞くなっ!」
喧騒の中でもハッキリと響く、確かな想い。
それは……
「……ぃっ……」
「え?」
「ん?」
それは。
「……ったぃ……○○、にッ…………ぁい、たぃ……っ!」
会いたい。
○○に会いたい。
アイツの笑顔を見たい。
アイツの温もりを感じたい。
アイツの傍に、居たい。
心が、その想いで弾けそうだった。
「霊夢……」
「お前……」
戸惑うような、微かに理解したような声。
「……ぅ、ぅえっ…………ぁぃ……たぃ、よ…………っ!」
想いは消えることなく。
叫びは夜のカーテンが降り始めた空に。
哀しく、響いた。
障子から暖かな陽光を瞼に受けて、私は目を覚ました。
ゆっくりと上体を起き上がらせ、障子から透ける日差しを見る。
「朝……か」
そこでやっと、朝だということを私の脳は理解した。
寝間着のまま裏の井戸に向かう。
汲んだ水を桶に溜め、それを勢い良く頭から被った。
春だといってもまだ初春。
水は凍えるように冷たかった。
しかし、その冷たさを以ってしても、私の頭には靄が掛かったままだった。
依然としてはっきりとしない頭で、昨日の出来事を思い返す。
あの後。
泣きじゃくっている私を、魔理沙とレミリアが必死になって慰めてくれた。
二人の言葉を記憶から引き起こす。
『そんなに気にするなって。アイツのことだ、そのうち、ひょっこり顔を出すさ!』
『そ、そうよ! アイツが霊夢に会いに来ないワケないじゃない!』
おろおろとしながら、私を慰める二人の顔。
余りの必死さに微笑ましくなる。
そこでふと気付いた。
もしかして私は、とんでもない醜態を二人に晒したのではないだろうかと。
昨日の光景。
人目を憚らず、子供のように泣きじゃくる自分。
涙声で、○○会いたいと何度も言った自分。
「…………」
今更になって、とてつもない恥ずかしさが襲ってきた。
後悔と自己の脆弱さに引き篭もりそう。
出来ることなら、今すぐにでも記憶を抹消したかった。
けれど。
もう忘れることなど出来ない。
自分の気持ちに気付いてしまったから。
明るみに出た感情。
寂しい。
泣きながら言った言葉。
会いたい。
あの時言った言葉と、感じた想いは……きっと私の本心の筈だから。
水滴が前髪を伝って落ちていく。
それを意に介さず、私は空を見上げた。
雲一つ無い、真っ青な空。
あるのは眩しいくらいに明るい太陽のみ。
まるで今の私の心を移したかのよう。
頭の靄は、いつの間にか綺麗に消え去っていた。
そうだ。
陽の光を全身に受ける。
会いに来ないのなら……
光が、私の身体に力を注いでゆく。
会いに行こう。
決意は固まった。
そうと決まれば話は早い。
私は視線を空から下ろして、神社に歩みを進める。
脳裏に浮かぶはアイツの顔。
こんな時間に行っても大丈夫かしら?
一寸思ったが、時間を遅らせるつもりは毛頭無かった。
歩く速度は、次第に早足に。
早く、早く。
心が急かしてくる。
そして裏手の戸に手を掛けたその時。
ちゃりーん。
小気味良い金属音が神社に響き渡った。
続いて、がらがらと鐘を鳴らす音。
次に、二拍。
そして、静寂が辺りに広がった。
……参拝客?
珍しいこともあるものだ。
この神社に御参り来る人が居るなんて。
参拝してくれことに対し、若干の感謝をする。
けれど……
今はそんなことに気を回している暇は無い。
そして再び戸に手を掛けようとして……
私は状況を理解した。
理解すると同時に、本堂目掛けて走り出す。
なに間抜けなことを思ってるのよ私は!
叱責は自分に。
ウチの神社に参拝客なんて来る筈ないじゃない!
間の抜けた思考を叱咤する。
そうだ、この神社に参拝客が訪れることは無い。
それは自分が一番理解している。
来るんだったら、今頃生活は困窮していない。
ウチの神社に参拝客は来ない。
それは悲しいけれど事実だった。
そう……
唯一つの例外を除いては。
果たして其処に居たのは。
神社の本堂。
賽銭箱の前。
其処には神妙な顔で眼を瞑って、手を合わせている……
アイツが、居た。
「っ!!」
息が詰まった。
鼓動が早鐘を打ち始める。
体中の熱が、顔面に集まっていくのを実感する。
歓喜が、全身を廻った。
来て……くれたんだ。
その事実が嬉しくて、彼に歩み寄ろうとした。
……が。
意に反して、体は石のように動かなかった。
ど、どうして?
戸惑いながらも、懸命に体を動かそうするけれど。
どうして動いてくれないの?
鉛の様に重くなった私の体は、ぴくりとも動いてくれなかった。
どうして……
戸惑いに答えるように、声が聞こえた。
『彼は本当に貴女に会いに来たのかしら?』
あ……
闇が、再び私の心を覆った。
もしかしたら、アイツは単純に御参りに来ただけなのかもしれない。
そんな有り得ない不安が私を襲う。
でもそんなこと……
私は声に反論する。
『本当に? 本当にそうじゃないと言い切れる?』
あれ以来、一度も此処を訪ねていない○○。
その間、色んな少女達と会った○○。
可能性が無いとは、言い切れなかった。
今更になって、此処を訪れる理由なんてあるのだろうか?
わからない。
私には、わからない。
底無し沼に落ちていくような感覚が私を襲う。
それでも。
ずぶずぶと沈む体。
それでも、私はアイツに……
沼の中で私は足掻く。
アイツに会いたいのよ。
声を聞きたいの。
笑顔を見たいの。
アイツの温もりを、感じたいのよ。
言いながら必死に足掻いた。
けれど……
『そう。でも……』
私の叫びに、声は嫌らしそうに一端区切って。
『まだ彼が貴女を求めていると……貴女、自信を持って言える?』
容赦の無い言葉を浴びせ掛けてきた。
その問い掛けに、私は放心した。
それは……
先刻までの輝きは形を潜め。
わからない。
代わりに生まれた真っ黒な泥が、私に執拗に絡み付き、思考の自由を奪う。
私はまだ……アイツに求められているのだろうか?
声が私の心を闇に沈めていく。
わからない。
もしかしたらもう……
一面に広がるドス黒い闇。
体を侵食する、負。
そんな暗黒を掃ったのは。
「会いたかったぜ腋巫女ーーーーーーーーーーーっ!!」
待ち望んでいた彼の声だった。
いつの間にこちらに来たのか。
気が付くと彼は、私の目の前に居た。
両腕で私の腰回りを抱き締める。
あ……
抱き締められた瞬間。
ドクンと、心臓が一際激しく脈打った。
ああ……
腕から伝わってくる彼の温もりに渇いた心が満たされてゆく。
干乾びた私が潤っていく。
彼はこちらのそんな様子に全く気付かないまま。
いつもどおり、私の腋に頬を摺り寄せた。
「ほへぇ~~~……」
程無くして漏れ出る、だらしのない声。
満足感たっぷりの幸せそうな顔。
久しぶりに会った彼は、相変わらずの変態っぷりだった。
その顔を私は見つめた。
○○だ。
堰を切ったように溢れ出す、温かな感情。
やっと……
熱い、想い。
やっと会えた……
それらが全身を駆け巡る。
嬉しさの余り、抱き締めたい衝動に駆られた。
従順に従い、彼の背中に腕を回そうとして……
何故か上空に振り上げた。
そしてそのまま勢いをつけ。
肘先を彼の脳天目掛けて……
叩き付けた。
「べぶあっ!?」
潰れた蛙のような声。
その声に気付いた時、彼は地面にへばり付いていた。
……あれ?
驚きは自分に対して。
なんでこんなことに?
彼は不規則にぴくぴくと、小刻みに痙攣している。
私はその様を呆然としながら、眺めていた。
やがて彼は顔を上げた。
「いって~……」
どくどくと流れ出る鼻血。
彼の顔は、鼻から下が真っ赤に染まっていた。
「あ~……」
呻きながら首筋をトントンと叩く。
暫くして鼻血が止まったことを実感した彼は、こちらを見て……
「久しぶりだな霊夢!」
ニカッと。
血塗れの顔で笑った。
やっぱり。
目の前の彼は、ちっとも変わっていなかった。
「相変わらず容赦無えなあ!」
彼は笑いながら言う。
その顔は自分の求めた笑顔過ぎて。
無性に、泣きたくなった。
アイツだ。
会いたかったアイツだ。
さっきまで私を覆いつくそうとしていた闇は。
跡形も無く、消え去っていた。
「ん? お~い霊夢~?」
黙ったままの自分を不思議に思ったのか、彼はこちらを覗き込む。
いけない。
何か喋らないと……
でも何を?
言葉を捜す。
会いたかった?
寂しかった?
どうして来てくれなかったの?
言いたい言葉は数知れず。
かしゃかしゃと頭の中で最良の答えを検索する。
そして出てきた言葉は……
「こんな朝早くに、ウチに何の用?」
そんな素っ気無い言葉だった。
違う。
こんなことを言いたいんじゃない。
必死に喚く。
けれど言葉は無情で。
「御参りに来たの? なら一応感謝しておくわ」
心とは裏腹に、冷たい言葉が発せられる。
馬鹿。
意地っ張り。
どうして自分はこんなにも素直じゃないのだろう?
さっきとは別の意味で泣きそうになった。
後悔の波が押し寄せる。
そんな私に向けて、彼はニヤリと笑った。
「ふっふっふ……甘いな霊夢!
そんなモン、おまけもおまけ! 俺の目的はいつも一つ! それは……」
彼は高らかにそう叫びながら。
「お前に会うことだああああああああっ!!」
ビシッという効果音が付きそうな程、強く。
私を指差した。
阿呆みたいな啖呵。
普段の私なら呆れるところ、なのだが。
今日の私は違った。
奥底に芽吹く。
そうなんだ。
私に会いに来てくれたんだ。
この春の様に温かな花。
嬉しい。
本当に嬉しい。
この気持ちを貴方に伝えたい。
会いに来てくれて本当に嬉しいのって言いたい。
そう想っているのに……
「……そう」
やっぱり、そんな言葉しか返せなかった。
ホントにもう、私は筋金入りだ。
なんで。
なんで伝えられないのよ!?
自分の不甲斐無さに憤る。
素直じゃない自分。
嘘吐きな自分。
そんな自分とは対照的に……
「おうよ!」
彼は親指を立ててこちらに見せ付ける。
彼は自分に正直だ。
愚直な程に。
その正直さが、とても羨ましかった。
どうしてコイツはこんなに自分の望みに忠実なんだろう?
どうして私はコイツみたいになれないんだろう?
急に自分が嫌になった。
不意に、この場から逃げ出したい衝動に駆られる。
……その時だった。
私の体に、ぶるりと身震いが起きた。
そして突然襲い掛かる、冷気。
余りの寒気に身を固くする。
肌を見ると、少し青白くなっていた。
足の先端部分に至っては紫に近い。
春と言っても、まだ初春。
早朝の冷え込みは、まだ冬のそれに近い。
流石に寝間着のままじゃキツイわね。
……丁度良い。
「ちょっと待ってなさい。何か羽織るものを取ってくるわ」
私は彼にそう告げて、逃げるように境内に向かう。
「お? ……ちょっと待てい」
そんな私を彼は止めた。
なんで、止めるのよ。
気持ちを整理する絶好の機会だったのに。
制止の声を不満に思いつつ、彼の方を向く。
彼はその場にしゃがみ込んで、持参した袋の中を探っていた。
「え~と…………お、あったあった」
ほどなくして御目当ての品が見つかったのか、彼は腰を上げる。
あれは……なにかしら?
紅い、布のような何か。
彼はそれを胸に抱えて、こちらに近付く。
顔には何か企む様な笑顔を携えて。
そしてお互いの体がくっつくまで、あと一歩というところで止まり……
手に持ったそれを。
ふわりと。
私の首に巻いた。
「……え?」
突然首回りに発生した柔らかな感触に、私は戸惑った。
巻かれたそれを触る。
ふかふかとした生地の、紅と白の長い布。
これは……マフラー?
「へっへ~…………巻き心地はどうだ?」
彼はしてやったりという顔でこちらを伺っている。
私の首には、ふかふかのマフラー。
それは少々雑な造りで。
所々解れ掛けていて、少し不恰好。
でも。
それはとても温かくて。
まるで彼に抱かれているみたいだった。
「その顔を見ると良いみたいだな。良かった良かった、頑張って編んだ甲斐もあったってモンだ! あとは……」
彼は破顔した後、再びごそごそと袋を漁りだす。
「霊夢、手ぇ出してくれるか?」
言われるまま掌を上に向ける。
彼は其処に、可愛らしく装飾された小さな袋を置いた。
「開けてみ?」
素直に袋を開ける。
中には雪のように真っ白なマシュマロが詰まっていた。
「これ……」
「俺の手作りだ! さ、食べてみてくれい!」
「あ、うん……」
促されるまま、一つ手に取って口に放り込む。
口の中に入ったマシュマロは、瞬く間に溶けていく。
滲み出た糖分が、舌を軽く刺激した。
甘い。
羊羹やお饅頭のような、強烈な砂糖の甘さではなく。
なんというか、優しい甘さだった。
「味の方は、どうよ?」
少し不安そうに、彼は問う。
「……美味しい」
正直にそう答えた。
「そっか~…………へへっ!」
不安が晴れた彼は、嬉しそうに鼻を擦る。
その手を見て気付く。
彼の手は、火傷でボロボロだった。
なんで……
顔も良く見ると、目元に大きなくまが出来ている。
なんでそんなに……
『今日は何の日かしら?』
脳裏に響く声。
あ……
瞬間。
私は全てを悟った。
アリスの家に行った○○。
不恰好なマフラー。
目元の大きなくま。
紅魔館に厨房を借りた理由。
マシュマロ。
火傷が痛々しい彼の両手。
その全てが今、目の前にある。
そうか。
今日は……
気が付けば、彼の手を握り締めていた。
「うおっ! ど、どうした霊夢?」
私の突然の行動に焦る彼。
答えを返さずに、私は彼の手を撫でる。
傷に塗れた無骨な、けれど温かな手。
「あ、これか? いや、慣れないことをしたからさ~……見た目だけで、実は大したことないんだぞ?」
心配させないように。
笑いながらバレバレの嘘を言う。
なんて馬鹿なんだろう。
なんて純粋なんだろう。
なんて……愛おしいのだろう。
もう止まらなかった。
握っていた手を離し、彼の胸元に飛び込む。
そして両腕に、ありったけの力と想いを込めて。
彼の体を抱き締めた。
伝わる温もりと、彼の重み。
「おわっ」
軽い動揺の声。
それを無視して私は胸元に頬を摺り寄せる。
彼の匂いが、した。
少し汗臭い、けれど落ち着く匂い。
私の全てを包み込んでくれる、彼の匂い。
『 』な人の、匂い。
体が弛緩して、今にも膝が折れそうだ。
思う間も無く、崩れ落ちそうになる体。
その体を彼は抱き締めてくれた。
強く激しく、けれど繊細に優しく。
私の体を抱き締める。
「ぁ……」
息が漏れた。
彼の両腕が、私の全身を温かく包み込む。
それは、ただただ温かくて……
だからこそ、自分を呪いたくなった。
自責の念が私を襲う。
私は最低だ。
呪いの言葉を自分自身に向けて吐き捨てる。
私は疑ってばかりで……
彼のことを、これっぽっちも信じていなかった。
最低だ。
最低も最低、下の下だ。
ごめん。
言葉は声にはならず。
ごめんなさい。
ただ、胸の中で反響した。
後悔と罪悪感で、体が震える。
ごめん、なさい。
泣きそうになる感情をがむしゃらになって抑えつける。
そんな中届く……
「なあ、霊夢」
優しい彼の声。
「……何よ」
ぶっきらぼうに返してしまう。
止めてよ。
そんな風に優しい声、出さないでよ。
私なんて……
暗く沈む思考。
けれど彼は、こちらの想いなどお構い無しに。
「来年のバレンタインは、期待してるからな!」
そんな、わけのわからないことを言ってきた。
「……え?」
予期せぬ発言に、私は彼を見上げる。
「いやさ、今年は色々あって貰えなかっただろ?」
困った様な顔で彼は言う。
色々……そうね、色々あってあげれなかったわ。
あげたかったのよ?
そう、貴方に本当はあげたかった。
でも、あげなくて正解だったのかもしないわね。
今の私には、貴方にあげる資格なんて……
影を振り払うかの様に、彼は困った顔を太陽に変える。
「だから来年は絶対貰う! 楽しみにしてるからな!」
そして気合十分に言い放った。
余りの勢いに、私は一瞬呆気に取られた。
一瞬の呆然の後で思う。
やっぱりコイツは馬鹿だ。
こんな最低な自分に、まだそんな言葉が吐けるのだから。
アンタ、わかってんの?
私は最低な女なのよ?
私はアンタのことを信じられなかったのよ?
信じようともしなかったのよ?
それなのに、なんでそんなこと言えるの?
なんで……
もう、限界だった。
「……っ」
崩れる顔。
瞳に溜まりだす、涙。
喜び。
懺悔。
涙。
それら全てを隠すように彼の胸元に顔を埋めた。
「馬鹿……」
胸元で呟く。
「馬鹿で結構。お前から貰えるんなら、こちとら馬鹿にでも阿呆にでもなる覚悟だぜ!」
彼は迷い無く、そう啖呵を切った。
馬鹿。
馬鹿、ばか、バカ。
次々に生まれる、罵声の言葉。
しかしそれらは音には成らず、内に溜まる。
ホント馬鹿。
でも、一番の馬鹿は……
私だった。
素直じゃない上に、勝手な勘違い。
こんなにも自分を想ってくれるコイツを疑った私。
本当に、本当に、愚か者だ。
出来ることなら、今すぐ自分を罰したかった。
けれど、それは自分では出来ない。
だから。
だから私は。
彼の体を……
強く、強く抱き締めた。
「おお?」
現象に驚きの声。
構わず抱き締める。
そして言った。
「……不味くても、知らないからね」
ああ、自分は何処まで小心なのだろう。
こんな時に、こんな言い方しか出来ないのか。
本当に素直じゃない。
けれど彼はその答えに満足したようで。
「おう! 楽しみにしてるぜ!」
本当に嬉しそうに言って。
より一層強く、抱き締め返してきた。
馬鹿な人。
あんな言い方なのに。
そんなに喜んで。
ホント馬鹿。
でも私の胸は高鳴って。
余りの嬉しさに、破裂しそうだった。
その会話を最後にして、お互いに黙り込む。
優しくて穏やかな、時間。
感じるのは彼の温もりと……確かな鼓動。
とくん、とくん。
彼の生命を感じる。
ああ生きている。
その事実が、無性に嬉しかった。
抱き合っているうち、不意に溶け出しそうな錯覚に襲われた。
二人重なりあったまま、ぐにゃぐにゃに溶けていく。
そんな、錯覚……けど。
彼とならそうなっても良い。
寧ろ、このまま一緒に溶けてしまいたい。
そう、切に思った。
蕩ける様に甘い時間。
二人だけの空間。
それを破ったのは……
お決まりのように、アイツだった。
……ん?
彼の温もりを甘受している私は、不意に腕の辺りにもぞもぞとした異物感を感じた。
なにかしら?
疑問に思っている間にも、それは二の腕の外側から内側に。
そして腋下に行った直後。
勢い良く這い上がってきた。
「うひゃあっ!?」
突如発生した違和感に悲鳴を上げる。
その悲鳴にも、我関せずといった具合にもぞもぞと何かは動く。
擽ったさに似た感覚。
それは私の腋を中心にして無遠慮に動き回った。
耐えかねた私は、原因に眼を向ける。
私の腋元から、手が生えていた。
もぞもぞと愉快気に蠢く手と……
「はふ~ん……」
痴呆の様な声。
その声で私は理解した。
手の持ち主を見る。
彼は、とても御満悦な表情をしていた。
「うはぁ~……腋手袋~……」
愉悦に浸った顔で変な単語を口走る。
その顔を見て、私の中で何かが切り替わった。
先刻までの甘い空気は形を潜め、代わりにメラメラと怒りの炎が私を包み始める。
こんの馬鹿……
胸元から取り出したるは、一枚の札。
いつも、いつも思うことだけどねぇ……
その札に霊力を叩き込む。
少しだけ、少しだけで良いから……
そしてそれを彼の前に突き出して。
「空気読め馬鹿ああああああああああああああっ!!」
ためらいなく発動させた。
「どふおっ!?」
吐くような呻き声。
彼は声と共に、地面と平行になって飛んでゆく。
そして鳥居を越え、階段の下に消える刹那。
「腋巫女ばんざあああああああああああああああああいっ!!」
そんな間抜けな悲鳴が、聞こえた。
幻想郷に暖かな日差しが降り注ぐ。
全てを包み込むような柔らかな光。
それはまるで、新たに生まれる生命を祝福するかのよう。
轟と、嵐のように一際強い風が吹いた。
春一番。
春の訪れを告げる風。
始まりを意味する、旋風。
人々は新たな始まりを喜び、生活に一層の精を出す。
春とは、そんな季節だ。
誰もが春の訪れを喜び、心を躍らせる。
暖かな、春の日差し。
その下で、私はいつものように境内の掃除をしている。
首には少し不恰好な、紅白のマフラー。
時刻はお昼を回ってすぐ。
腹ごなしに始めた掃除は、もう少しで終わりそうだ。
うーんと背伸びをして、掃除で凝った体を解す。
そして階段の方に眼を向けた。
そろそろかしら?
予感はどうやら当たったようで。
階段から聴こえてくる、荒い息遣い。
その息遣いと共に現れたのは……
自身の求めた、一人の青年。
胸が弾む。
彼は自分を見つけると、嬉しそうに顔を綻ばせ駆け寄ってきた。
そして今日もまた。
どうしようもなく馬鹿で。
どうしようもなく変態で。
「会いたかったぜ腋巫女おおおおおおおおおおおおおおおっ!!」
「だから腋巫女言うなって言ってるでしょうがあああああっ!!」
そしてどうしようもなく愛しい日が、始まる。
おまけ ~紅茶談義~
「おっす」
「あら、魔理沙じゃない」
「邪魔しに来たぜ~」
「別に構わないけど……こっちに来るなんて、珍しいわね?」
「別に普通だぜ」
「そう? まあ、良いけど」
「よいっしょ、っと。……なぁ、あれから霊夢のところに行ったか?」
「いいえ、行ってないわ……あんなの見せられたら、気軽に行けないわよ」
「そうかそうか、だったらこっちに来て正解だったな」
「? どうゆう意味?」
「いやな? 昨日、霊夢ん処に行ってきたんだよ」
「貴女、度胸あるわね……」
「まあ、ほっとけないってのもあるがな……で、だ。霊夢のヤツ、どうしてたと思う?」
「それはまあ……まだ、落ち込んでたでしょう。あれから三日しか経ってないし……」
「残念ながら、不正解だぜ」
「え? じゃあ……」
「ああ、元に戻ってた」
「そう……なの。吹っ切れたのかしら……」
「いやいや、その逆だ」
「どうゆうこと?」
「私も最初、元通りになった霊夢を見た時はそう思ったんだが……良く見ると一部が違ってたんだよ」
「一部って?」
「マフラー」
「マフラー?」
「そ、マフラーしてたんだ。しかも御世辞にも綺麗とは言えない、不細工な。言った瞬間、ブッ飛ばされたけど……」
「それってつまり……」
「そーゆうことだな。いや~○○もやるね~」
「そうなの……良かったわ」
「お? なんだなんだ、霊夢が元気になったていうのに落ち込んでいるじゃないか。嬉しくないのか?」
「嬉しいわよ。けど……」
「なんだよ?」
「私には、無理ってことが分かったから……」
「……あ~」
「少し、嫉妬しちゃうわね」
「そうか。まあ、その、なんだ。気にするなって! お前にもいつか良いヤツが見つかる筈さ!」
「霊夢じゃなきゃ、駄目なのよ……」
「レミリア……」
「そう……霊夢の腋じゃないと……」
「あ?」
「あの若葉のように瑞々しくて、神話に出てくる聖杯のように神々しい……」
「お、おい……」
「成熟と未成熟の狭間にのみ存在する、蕩けるような甘さを持った、霊夢の腋じゃないと……」
「おいレミリア! さっきから何おかしなこと言ってんだよ!」
「あの特上のシルクのような肌触り。何処までも沈み込んでいくような、けれど確かな弾力をもった霊夢の腋じゃないと私は……」
「レミリアっ!!」
「ハッ!?」
「やっと正気に戻ったか……」
「あ、あれ? 私、どうしたのかしら?」
「それはこっちが聞きたいぜ」
「御免なさい。ちょっと前から、私おかしくって……」
「そうみたいだな」
「理由は分かってるんだけど……」
「一体どうしたってんだ?」
「それは……言えないわ」
「またかよ……そういえば、この間霊夢の処に行った時もお前……」
「!?」
「その反応……まさか……」
「な、何を勘違いしてるのかしら?」
「お前も……」
「お嬢様、お茶が入りました」
「あ、ありがとう咲夜! 魔理沙、貴女も呑むでしょう?」
「ちぇっ、まあいいや……有り難く頂くぜ」
「ほっ…………助かったわ咲夜」
「いえ、これも務めですので」
「それじゃあ、頂きましょうか?」
「おう、頂くぜ」
「ねえねえ、私のは~~~?」
「お? 萃香じゃないか」
「やっほ~」
「……貴女、一体何処から入って来たのかしら」
「普通に入り口から入ってきたよ~?」
「中国め……ホント使えないわね」
「ね~私の分は~?」
「無いわよ」
「え~なんで~?」
「五月蝿い。鬼に出すお茶なんて、この紅魔館には無いわ。さっさと出て行きなさい」
「ふ~ん、そーゆーこと言っちゃうんだ~? 良いのかな~?」
「……どうゆう意味?」
「別に~……ねえ、魔理沙」
「あん?」
「さっき、レミリアが変なこと言ってたでしょう?」
「っ!?」
「ああ、言ってたな」
「その理由、知りたくない?」
「ちょ、ちょっと!」
「知ってるのか?」
「勿論、当事者の一人だしね」
「ちょ、ちょっと待ちなさい……!」
「是非、教えてくれ」
「良いよ~。あ~でも、ワインとか飲んだら忘れそうだな~」
「……っ!!」
「無いかな~極上のワイン~?」
「くっ……咲夜」
「はいお嬢様」
「交渉成立! ごめんね魔理沙、やっぱり無理~」
「おいおい、そりゃないぜ~」
「ごめんね~」
「……まあいいや。ところでお前の巻いてるそれって、もしかして……」
「このマフラーのこと? 良いでしょ~。○○が編んでくれたんだ~」
「だと思ったぜ」
「えへへ~」
「部屋の中に居るんだから外したらどうなの?」
「無理~」
「なんでよ?」
「これしてると○○に抱かれてる気がしてとってもあったかいんだ~」
「はぁん? 何言ってんだお前? 遂に呆けたか?」
「呆けてなんかないよ~。う~ん、○○あったか~い」
「うはぁ……こっちは甘くて死にそうだぜ…………でも、やっば不細工だな」
「愛情が篭ってるから良いんだも~ん」
「そ、そうか……でもアイツ、マフラーなんて編めたんだな?」
「人形師に習ったみたいだよ?」
「アリスに? あ~……納得だぜ」
「何が?」
「いんや、こっちの話しだ。にしても二つも編むとは……頑張ったんだなアイツ」
「多分、五つよ」
「へ? なんでまたそんなに?」
「忘れたの? ○○、守矢神社に行ってるでしょう?」
「あ~……早苗か。でも、それなら三つじゃないのか?」
「多分、神連中にもあげてるわ。あの男、アイツ等に借りがあるし……」
「諏訪子と神奈子か。そーゆうとこは義理堅いよなぁ、アイツ……ん?
そーいやお前、なんであの二人のことを知ってるんだ?」
「……そのことに関しては、黙秘させて貰うわ」
「にっしっし~」
「なんだよ萃香、その意味深な笑いは?」
「べっつに~……ねえ吸血鬼?」
「……五月蝿いわね」
「いや~愉快愉快」
「くっ…………いつか覚えてなさい」
「? なんなんだ?」
「まあいいからいいから。あ~、○○マフラーあったかいよ~」
「そんなに良いのか、それ?」
「うん! もう最高だよっ!」
「じゃあ、ちょっと貸してくれ」
「それは嫌」
「なんでだよ」
「魔理沙の匂いが付いたら困るから~」
「私の匂いが付くと、何か問題でもあるのか?」
「ある」
「何だよ」
「○○の匂いが消えちゃう」
「○○の匂い? そんなモン付いてるのか?」
「付いてるの」
「それは流石に嘘だろ」
「嘘じゃないってば」
「だって……なぁ?」
「そこでなんで私に振るのかしら?」
「いや、なんとなく」
「嘘だと思うんなら、霊夢にでも聞いてみれば?」
「霊夢に?」
「うん、多分同じこと言うと思うよ?」
「ふむ……丁度良い。レミリア、確認ついでに霊夢ん処に様子見に行こうぜ」
「それ良いわね、行きましょうか」
「それじゃあ霊夢のところに……」
「「「「レッツゴー!」」」
「ふぅ、掃除終わりっと」
「今日はアイツ、仕事で来れないって言ってたわよね……」
「…………はぁ」
「………………くんくん」
「…………」
「…………ちょっとだけ」
「すぅ……はぁ…………ぁ」
「…………もうちょっとだけ」
「すぅぅ…………はあっ…………」
「…………あといっかいだけ」
「すぅ~…………っはぁ。ふぅ…………もいっかいだけ…………すぅ」
「お~い霊夢~」
「遊びに来たわよ~」
「あれ~? いないの~?」
「うえっ!? ちょ! ま……」
「「「あ」」」
その日、博麗神社は眩い光で覆い尽くされた。
そして博麗神社を訪れた三人は、共に最上級のトラウマを植え付けられた。
光を目撃した烏天狗は、自前の好奇心を押さえ切れず、三人を直撃取材した。
しかしそのことについて、三人は決して口を割ることはなかった。
何を聞いてもガタガタと震えている様を見て、彼女達が壮絶な何かを体験したことだけは分かったのだが。
それ以外は一切が闇に包まれたままだった。
神社で何を見たのか?
彼女達が神社で見たある光景。
それは春先の青空と、燦々と煌く太陽だけが知っていた。
10スレ目>>49 11スレ目>>843 13スレ目>>115、511
うpろだ740、741、947、1003
───────────────────────────────────────────────────────────
自分の罪・責任などを他になすりつけること。
責任を転嫁する。
つまり、責任転嫁。
空から舞い降りる無数の白。
白い、何処までも真っ白な花。
花ではないのに、花の名を冠する存在。
六花。
儚い花。
眼にした次の瞬間には消えてしまう、切ない花。
けれどそれは確実に存在していて。
この世界を、真っ白に染めていた。
暦は如月。
冷え込みが最も厳しくなる季節。
昨日の夜から降り始めた雪は、日付が変わった今も、変わることなく降っていた。
友人の話によれば、ここ一番の大雪になるそうだ。
そのため、村の連中は朝から忙しげに大雪対策に勤しんでいる。
そんな中。
「……」
俺は炎に焦がされていた。
朝から部屋の真ん中で大の字になって倒れたまま。
全身を憤怒という名の紅蓮が覆いつくしている。
視界には、少しボロが目立つ我が家の天井。
雪の重みで壊れないだろうか?
ふとそう思ったが、雪卸しをする気は起きなかった。
何故だろう。
雪の日はとても静かだ。
まるで世界から音が消えたかのよう。
この無音が恐ろしいという人も居るが、今の自分にはそれがとても心地良かった。
しんとした静寂が、己が身を焦がすほどの業火を少しだけ沈めてくれる……そんな気がした。
そんなこと、あるワケがないのに。
自嘲気味に笑って、溜息。
そして再び憤怒の炎が俺を焦がした。
顔が歪み、頬が引き攣る。
くそ……
怒りに下唇を噛んだ。
くそっ!
唇に鈍い痛み。
最悪だ……
だがそんなものはどうでもいい。
ああ最悪だ。
脳裏に浮かぶは只一つ。
あいつめ。
鬼。
あいつのせいで俺は……
最強の力を持つ種。
俺は……
そして。
俺は。
その鬼が持つ……
事の発端は、一人の幼女の言葉だった。
大晦日の大決戦から数日後、いつものように俺は博麗神社に足を運んでいた。
目的は言うまでもなく博麗の巫女。
正確には彼女の所有物。
空は晴天。
冬だというのに、頭上には澄んだ青空が広がっている。
ずっと眺めているとそのまま吸い込まれそうな、真っ青な蒼。
今天地が逆さまになったとしても、人はそれを巨大な湖と勘違いをして泳ぎに行ってしまいそうなほどの、蒼い空。
その青空の下、俺は駆け足で階段を上っていた。
時たま吹く風が、火照った身体を冷やしてくれて、とても気持ち良い。
だがそれも一瞬のこと。
すぐさま身体は熱を持ち、早く早くと両足を急かしてくる。
それに素直に従って、俺は更に速度を上げた。
今日はいつもより上る速度が速い。
新年だからだろうか。
うん、関係ないな。
新年だろうがお盆だろうが年末だろうが。
神社に行く時、俺の気分はハッピーなんだ!
なんでかって?
言わなくてもわかんだろ?
アレだよアレ。
あ、わかんねぇ?
じゃあちょっと待ってろ、もう少ししたら分かるから。
と、誰に対するでもなく答えながら階段を勢い良く駆け上がる。
踏み出す足は、一段毎に強く。
弾む心は一呼吸毎に熱く。
求めしは愛しの少女と、その少女の持つ神秘の……
「待ってろよーーーーーっ!!」
叫びは幻想郷の空に遠く響いた。
そんなこんなで数分後、神社に到着。
すぐさま境内を見回す。
ほどなくして、掃除している彼女を発見。
その瞬間。
がち、と。
錆び付いた鉄の歯車が動き出す。
ごう、と。
巨大な炉の中で、炎が勢いよく燃え上がる。
ぱちん、と。
軽快な音を立てて切り替わる、回路。
ぎし、と。
千切れそうな程の軋みをあげて、全力が両足に収束する。
今か今かと解き放たれる瞬間を待つ様は、まるで限界まで引っ張られたゴムのよう。
そして次の瞬間……
「イ~~~~……」
魅惑のお宝目掛けて。
突撃した。
「ヤッフーーーーーーーーーッ!」
「ぅきゃあああああああああっ!」
一つに重なる、異なった叫び声。
そして開かれる楽園への扉。
俺はその扉を全速力で潜り抜け、そして……
精巧な硝子細工で出来た装飾品を扱うように優しく。
飢えた獣が極上の餌を貪るが如く獰猛に頬を摺り寄せる。
スベスベ。
頬から伝わる、羽衣のような滑らかな肌触り。
ぷにぷに。
熟すか熟さないかの間際の、若々しい瑞々しさをもった弾力。
瞬く間にして、頬の神経が侵された。
そのまま頬が落ちそうな錯覚を覚える。
大きく鼻で空気を吸い込む。
ソレは鼻腔から脳へ、そして全身へと回る。
微かに柑橘類の混じった、濃厚なミルクのような香り。
あまりの濃厚さに頭の容積庫がパンクしそう。
だがそれが良い。
それが良いんだ!
心の中で高らかにそう叫んで、ひたすら行為に没頭する。
スベスベぷにぷにスベスベぷにぷに。
香りを吸い込む、吸い込む、吸い込む。
一摺りごとに触覚が麻痺していく。
一呼吸ごとに、脳と嗅覚が壊されていく。
それでも衝動は止まらない。
ああ……
満たされなかった部分が満たされていく感覚。
補われる充足感。
そしてその後は……
「ア、アンタねぇ……」
お決まりのように。
「本当に……」
ド派手に吹っ飛ばされる……
と、思った瞬間だった。
突然、摺り寄せていた頭を後ろから押される。
何事かと思った瞬間……
首元に伝わる感触で一気に身体から力が抜けた。
なんだこれ。
身体が動かない。
まるでそんなことに使うなと抗議しているように。
全身に力が入らない。
まるで今使うのはそんなものでは無いと言わんばかりに。
そんな中浮かぶ、一つの言葉。
柔らかい。
それと同時に、口元が緩んだ。
弛緩している身体。
それとは対称的に、一点に集中しだす神経。
「え?」
こちらの変化に戸惑った様子の声。
だが、今はそんなものに構っている余裕は無い。
最速で全神経・全感覚を首回りに集結させる。
そして全力でその感触を堪能した。
うはぁ……
言葉に出来ない声が出る。
今の感触を言葉で表現するなら、ふにゅ、だろうか。
否。
ふにゅぅ、が正しいか。
柔らかくも適度な温度と弾力。
ソレは例えるなら、高級マシュマロのような弾力。
ソレは喩えるなら、太陽の温かな日差しを満遍なく浴びたような錯覚。
神と自然の作り出した奇跡の巻き布。
ソレが今、俺の首回りを包み込んでいる。
あったけぇ……
ソレはとても温かかった。
まるで心まで温かくなるようだ。
冬にマフラーを巻く人は多い。
しかし、俺は首に何かを巻くことがあんまり好みじゃない。
だが。
コレなら毎日でも巻きたい。
そう、思った。
出来ることなら四六時中。
起きる時も、顔を洗う時も、着替える時も飯を食う時も、働く時も風呂に入る時も寝る時も!
コレには、それだけの価値があった。
頭の中で誰かが言った。
『腋マフラー、そういうのもあるのか!』
そうだよ、あったんだよ。
俺達が知らなかっただけだったんだよ。
知らなかったことの己が愚かさに腹を立てつつ、頭の中の誰かに答える。
ああ、俺はなんて無知だったんだ。
こんな味わい方もあったなんて……
「この……」
もっと。
もっと堪能したい。
そう思った俺は、もっと強く挟もうと彼女の腕に手を掛けようと……した次の瞬間。
世界が半転した。
「え?」
違和感が俺を襲う。
先程まで境内の方を向いていた筈の両眼。
それが今は鳥居の方を向いていた。
違和感はそれだけではない。
視界に移るは逆さまの鳥居。
何で、鳥居が逆さまになって……
「大馬鹿っ!!」
その罵声を最後に、俺の意識は途絶えた。
「起きろ~」
誰かの声。
幼さを残した声が耳に届く。
続いて頬に軽い振動と衝撃。
どうやら叩かれたみたいだった。
それを引き金に、意識が反転して戻ってくる。
薄ぼんやりとした闇を抜けた、その先に。
そして目蓋を開いた。
目の前には……
「あ、起きた?」
幼女が居た。
「おはよ~○○」
「お~……」
微笑む幼女に返事を返す。
まだ意識が完全に覚醒していないのか、間抜けな声だった。
胸が少し苦しい。
何故かと思ったが、原因はすぐに判明した。
目の前の幼女に視線を向ける。
「なあ萃香」
「なに?」
「どいてくれ」
「え~~~」
こっちの要望に、何故か不満気な顔を見せる幼女。
「え~~、じゃねえ。お前がどかないと起き上がれねえだろうが」
「まだ起き上がらない方が良いと思うけど?」
にこやかにそう返す幼女。
俺は反論しようとして……
「っ!?」
首からの鈍痛に声を漏らした。
思わず顔を顰める。
なんだ、この痛みは?
そっと首に手を当てる。
そして手を添えたまま、ゆっくりと首を動かした。
動かすと同時に、首筋に鈍い痛みが走る。
更に顔が険しくなるのが分かった。
「いって~……」
余りの痛さに、思わず呻き声が出る。
一体なんだってんだ?
寝違えたか?
つーか、俺なんで寝てたんだ?
湧き上がる、疑問の数々。
「あ~あ、だから言ったのに~」
その様を見て、目の前の幼女は少し呆れながら笑った。
「どうゆうことだ?」
痛みに耐えつつ尋ねる。
先の言葉から察するに、事情を知っているようだ。
彼女は呆れ半分に笑いながら問いに答えた。
「霊夢に頭から落とされたの、覚えてないの?」
その言葉を聞いた瞬間、忘却された記憶が甦った。
いつもの強襲。
訪れる至福の時。
新たな未開の地の発見。
狂喜する思考。
そして、反転する視界。
「ああ……」
疑問は氷解した。
何故寝ていたのかも。
何故首が痛むのかも。
「思い出した?」
「おう、思い出した」
「私の言葉の意味も、理解出来た?」
「お~~~」
返事を返しつつ、首を擦る。
少し動かしただけでもこれだ。
あんまり動かない方が良いな……
「しゃあねえ、もう少しこのままでいるか」
「そうそう、安静にしときなって!」
返答に満足したのか、萃香は嬉しそうに笑って。
俺の胸に倒れ込んできた。
「おいおい、なんだよ急に」
「別に良いじゃん、暫くこのままなんでしょう?」
俺の抗議など気にしていない風に言いながら、胸元に頬を摺り寄せた。
「ん~……」
途端に漏れ出る、嬉しそうな声。
……あ~、こりゃ駄目だ。言っても聞かねえわ。
「……ったく」
早々に諦めた俺は、仕方なくそのままでいることに。
……ま、いいか。
いつものことだしな。
「むぅ~……」
全身で俺にしがみつく。
小さな手が俺の服を、ぎゅと掴んでいた。
その様はまるで子猫が母猫に甘えるよう。
微笑ましくなって、頭を撫でた。
気持ち良い手触りが掌から伝わってくる。
「うにぃ……」
撫でられるのが嬉しいのか、萃香は目を細くする。
ホントに猫みたいだな……
もし彼女に尻尾があったなら、ぱたぱたと左右に振っていることだろう。
そんなことを思いながら彼女を見る。
小さな身体。
村の子供達と同じくらいの体躯。
身体の成長度合だけを見れば、年齢は十にも満たないだろう。
だが彼女は人ではない。
その証拠に、彼女の頭には不釣合いな程の大きさの二本の角があった。
鬼。
最強の一つとして語られる種族。
その強大な力は月をも砕き、大地を裂く。
絶対的な、畏怖。
ひ弱な人間達からすれば恐怖でしかない存在。
……の、筈なのだが。
「ふにぃ……」
甘ったるい声が漏れた。
ふと、胸元から感じる力が弱まっていることに気付く。
見ると彼女は、だらしなく全身を弛緩させていた。
安心しきった顔。
その姿を見て、自然と笑みが零れる。
「やれやれ」
幼子をあやすように、逆の手でポンポンと背中を叩く。
全く、諏訪子といいコイツといい、何でこうなんだろうな?
神と鬼。
敬意はされど、決して親愛は湧かない存在。
その筈なのに……
「ぅにゃ……」
こいつらときたら、どちらも甘えん坊で困る。
「もっとカリスマ持てよなぁ……」
そのうち、何処ぞの吸血鬼みたいになっちまうぞ?
そう呟きながらも、心の端っこでは、現状で良いと思っている自分が居た。
心を温かな感情が占拠していく。
空間に穏やかない時間が流れた。
「ふぁ~あ……」
穏やかさに当てられたのか思わず欠伸が出た。
欠伸を噛み殺していると、ある変化に気付く。
「すぅ……すぅ……」
聴こえる寝息。
どうやら、彼女もこの穏やかさに当てられたようだった。
「寝付きの良いことで……」
寝顔はとても幸せそうだった。
こりゃ起こすのも可哀想かな?
そう思っていると……
「お?」
ぎゅ、と。
たどたどしい動きで、抱き締められた。
多分無意識的だろう、小さな腕で身体を抱き締められる。
まるで親に甘える子供のようだ。
ホントにもう、コイツは……
やれやれと溜息。
そして、お返しにとばかりに抱き締め返した。
頭と背中を優しく撫でる。
一定のリズムで行われる呼吸。
腕の中に感じる、確かな温かさ。
「ふあぁ……」
二度目の欠伸。
どうやら睡魔の本格的な攻撃が始まったみたいだ。
このままだと、あと十数秒で落ちるだろう。
今の俺に、それを拒む理由は無い。
なので……
「おやすみ~」
ゆっくりと眼を閉じた。
この季節にしては珍しく温かい日差しと。
腕の中で気持ちよさそうに眠る鬼娘を感じつつ。
俺は眠りに落ちていった。
……その数分後、鬼のような形相をした巫女に起こされるとも知らずに。
「全く……」
不機嫌そうな言葉を発しながら湯呑みに口をつける紅白の巫女。
俺達を起こした後、お茶の間に場所を変えてから数分。
彼女はその数分の間、その言葉しか発していない。
場の空気はピリピリと痛かった。
う~~ん……
俺は少女を眺めながら考える。
コイツ、何でこんなに機嫌が悪いんだ?
さっきからずっとこの調子。
一目で分かる機嫌の悪さ。
でも理由が分からない。
一体、何が不満なのだろうか?
不思議に思いながら、ゆっくりと首を動かした。
うん、痛みはもう無いな。
先程安静にしていたお陰か、首はすっかり完治したみたいだった。
ホント、我ながら大した回復力になったモンだよ。
成長というモノを実感しつつ、俺はもう一つの痛みに意識を向ける。
頭頂部に感じるズキズキとした痛み。
痛みの発生源をそっと触ると、其処には大きなたんこぶがあった。
眠る前には無かった筈のたんこぶが、どうして出来ているのか?
答えは単純にして簡単。
起こす時に殴られたからだ。
いやもう、あん時は目の前に星が散ったね。
流星群っていうの?
もう、一発で眼が覚めたわ。
そんで目の前には威圧感たっぷりに腕組みをしたコイツだろ?
誰だって覚醒するって。
正に鬼腋巫女。
触らぬ腋に祟りなし……っと、閑話休題。
そんなことはどうでもいいんだよ。
今現在、重要なのは……
「ねえ霊夢~。なんでそんなに機嫌悪いの~?」
自身の疑問を代弁するかのように萃香が尋ねた。
そう、それだ。
何故機嫌が悪いのか?
それが今、最も重要な問題だ。
その疑問に対し、彼女はこちらに一瞥をくれると……
「別に」
たった一言。
そっけなく返して視線を戻し、再び沈黙した。
別にって……んなわけねえだろ~。
「変な霊夢~」
「別に、いつもと同じよ」
「そうかな~? おかしいよね○○~?」
萃香はそう聞きながらもたれ掛かってくる。
そして少し身体をずらして、こちらに顔を向けた。
彼女は現在、炬燵と俺に挟まれた状態で座っている。
簡単に言うと、俺の膝の上に居るわけだ。
理由は炬燵に入る際にせがまれたため。
……ま、これもいつものことなんだけどな。
可愛らしく首を傾け同意を求めるその姿を見て、思わず頭をくしゃくしゃと撫で回したい衝動に襲われる。
……が、今回は我慢した。
何故ならば。
視線を彼女の後頭部に向ける。
其処には、俺のと同じくらい大きなたんこぶ。
当然ながら犯人は、現在不機嫌街道まっしぐらの紅白巫女。
二人仲良く拳骨を戴いたってワケだ。
痛々しいたんこぶが存在するその頭を撫でるのは、若干躊躇われた。
なので……
「まあなぁ」
曖昧な返事を返しつつ、彼女の額に手を置く。
そしてそのまま、軽く撫でた。
掌から伝わるサラサラとした髪の感触が気持ち良い。
「えへへ~」
その動作に、目の前の幼女は顔を綻ばせた。
嬉しいような照れたような表情。
彼女はそれを隠すように胸元に頭を埋める。
その時だった。
ばきん。
何かが砕ける音が耳に届いた。
何事かと思い、音のした方向に眼を向ける。
音のした方向。
其処には、俯いて拳を握る紅白の少女。
拳の周辺には大小様々な破片が飛び散っている。
多分、彼女が壊したのは湯呑みだろう。
その証拠に、さっきまで彼女が飲んでいた湯呑みが無い。
ぎりっ。
何かが軋む音が聴こえた。
「れ、霊夢?」
突然の行動に驚いた萃香が、おそるおそるといった風に尋ねる。
その呼び掛けに、彼女は無言で返した。
静寂が世界を支配する。
沈黙に耐えかねたのか、萃香はこちらを見つめてくる。
その顔は、見て取れる程の不安に満ちていた。
それもそうだろう。
訳もわからないまま、いきなり険悪な雰囲気になったら誰だって困惑する。
その点で言うならば、彼女の反応は正しいと言えよう。
俺も同じく、彼女と一緒に困惑する……筈だったのだが。
気分は妙にスッキリとしていた。
凍っていた答が解凍されていく。
映し出される場面。
萃香と一緒に寝ていた、十数分前。
そして萃香を膝の上に乗せている今。
起こした時から、不機嫌な紅白の巫女。
そして先程の湯呑み破壊。
その全てが繋がって、一本の線になる。
判ってみると、実に簡単な問題だった。
つまり……
「萃香、ちょっと退いてくれ」
「え、急にどうしたの?」
「まあいいから」
困惑する萃香を膝の上から退かす。
そして立ち上がった俺は、霊夢の後ろに回った。
「霊夢」
声を掛ける。
「なによ」
彼女は湯呑み破壊をした時の状態のまま。
こちらを向かずに返事を返す。
取り付く島も無い態度。
だが。
あ、やば……
答えを知っているに俺にとって、その態度は正直……反則だった。
彼女の後ろに座り込む。
そして目の前の少女を強く抱き締めた。
「!?」
抱き締めた瞬間。
両腕から、少女特有の柔らかな感触が伝わった。
「ちょ、ちょっと!? いきなり何すんのよ!?」
予想外の事態に狼狽する少女。
じたばたと腕の中でもがく。
後ろから抱き付いているため顔は伺えないが、多分真っ赤になっていることだろう。
「何って……お前の希望していたことだが?」
「だ、誰がいつ希望したっていうのよ!?」
全力で否定。
いや、まるわかりだっての。
そう。
これが、さっきまで彼女が不機嫌だった理由。
湯呑みを粉砕した理由。
つまり……
「お前さん、萃香が羨ましかったんだろ?」
その言葉に少女はぴたりと動きを止める。
つまり。
博麗霊夢は伊吹萃香に、嫉妬していたのだ。
無邪気に甘える萃香が羨ましかったのだろう。
こういうことを自分から言い出せない性格だからなぁ……
まあ、気付けなかった自分にも責はあるのだが。
「違うか?」
「そ、そんなことないわよっ!」
問い掛けに、腕の中の少女は続けて否定。
再度じたばたともがき始める。
ああは言われたが、嘘だということは明白だった。
その証拠に、彼女はさっきから腕の中でもがいてはいるが、抜け出そうとはしていなかった。
やれやれ、全く以って素直じゃない。
心の中で溜息を吐く。
その時、ピンと閃いた。
……少し意地悪してみるか。
「そうか~……なら仕方ない、離れるわ」
「え……」
その言葉に、少女は動きを止めた。
不安の篭った声。
うは、困ってる困ってる。
想定した通りの反応に、自身の口元が僅かに攣り上がるのが分かった。
「御所望じゃないなら仕方ないよな。いや、もがく程嫌がることをしてスマンかった」
表面上、深く詫びる。
勿論反省はしていない。
そして腕を解こうとして……
袖を掴まれた。
「なんだ? これ以上嫌がることはしたくないんだが?」
言葉の上では、平静を保って問う。
その問いに、霊夢はぎゅっと袖を握って……
「……嫌とは、言ってないじゃない」
こちらを横目で見ながら、そう答えた。
ああ、ホントにコイツはもう……
もう我慢は出来なかった。
「そうか……じゃあ」
彼女の身体を軽く持ち上げ。
「きゃっ!?」
勢い良く反転。
そして前回より強く、抱き締めた。
さっきは腕のみだった柔らかさを、今度は胸元で感じる。
突然の出来事に硬直する霊夢。
その首筋は、茹蛸のように真っ赤に染まっていた。
「少しは素直になろうな?」
「……るさい」
耳元に届く、蚊の鳴くような声。
本当に素直じゃない。
俺は苦笑しながらその背中を、優しく撫でた。
「むぅ~……」
徐々に緊張が解けていく彼女の身体。
ゆっくりとこちらに体重を預けてくる。
と、肩に重みを感じた。
顎を乗せたのだろう。
今の彼女の顔は、きっと緩みきっているに違いない。
素直じゃない彼女が、自身に身を委ねてくれる。
そのことが単純に嬉しかった。
惜しむらくは、彼女の緩んだ顔を見ることが出来ないことなのだが。
ま、今でも充分。
萃香にした時のように、背中をポンポンと叩く。
「んぅ……」
霊夢は気持ち良さそうに、身動ぎする。
うむ、愛いやつ愛いやつ。
満足した俺は、暫くその状態に浸ることにした。
どれくらいそうしていただろう?
愛しさと穏やかさの混じった、とても温かな時間。
とても心地よい時間。
その時間を破ったのは……
「うぅ~~~~……」
可愛らしい唸り声だった。
その声で、ふと我に返る。
声のした方を見ると、其処にはむくれ顔でこちらを見ている萃香の姿。
見るからに、かなり御不満の様子だ。
「霊夢ずるい~~~……」
ぷくっとした顔でそう告げる。
どうやら今の状態が気に入らないらしい。
「私と代われ~~~!」
抗議の声を上げる幼女。
その対象となった人物は。
「嫌よ」
そちらを見ないままに。
放たれた言葉を、一太刀で切って捨てた。
「ずるいぞ~~!」
「五月蝿い」
抱き合ったままの状態で返す紅白の巫女。
どうやら、この場所を譲る気は毛の先程も無いようだ。
いやはや……可愛いわ~。
「私も○○に甘える~!」
あっさりと断られたことにもめげない鬼娘。
お前、まだ甘えたりんのか……
糖分過剰要求の鬼娘に呆れていると、霊夢が俺の肩から顎を外し、萃香に視線を向けた。
そして……
「此処は私の場所よ」
一言。
顔は林檎の様に真っ赤だった。
彼女は言うべきことは言ったとばかりに。
その顔を俺に見られないよう、再び肩に顎を置く。
抱き締める腕の力が、ほんの少しだけ強くなった。
目の前には、ぽかんと口を開けた萃香の姿。
どうやらかなり面食らった様子だ。
そりゃそうだろう。
正直、俺も驚いている。
あの霊夢が。
もし素直じゃない選手権が開催されたのなら、確実にトップ争いをする程素直じゃない霊夢が。
まさかこんなことを言うとは。
素直になれとは言ったが……こりゃ、明日は嵐か?
萃香はまだ呆然としている。
まだショックから立ち直れていないようだった。
ありゃ暫くあのままだな……
そう思いながら、口を大きく開けたまま固まっている鬼娘を見つめる。
が、立ち直りは思ったよりも早かったようで。
放心状態から戻ってきた萃香は、ブンブンと頭が取れそうな勢いで頭を振る。
そしてひとしきり振った後、こちらを睨みつけ……
「こうなったら実力行使だ!」
言いながら、彼女は一枚の札を取り出した。
それはとても見覚えのある札だった。
これまでに幾度と無く見た札。
その札が出されると、決まって身体に損傷を受けていた札。
スペルカード。
弾幕ごっこの基盤ともいうべき札。
彼女の手にはそのスペルカードが一枚、確かに握られていた。
「鬼符!」
高らかに宣言をする。
宣言に共鳴するように、大気が震えた。
「ちょ、待て萃香!」
反射的に静止の声が出た。
室内でスペルカードとか……冗談じゃねえぞ!
背中から冷や汗が出るのが分かる。
だが、彼女は発動を止めなかった。
「ミッシング……」
静止の声空しく、彼女はスペルカードを発動させる。
否、させようとしたのだが……
突如発生した風切音と。
すこん、という小気味良い音に、発動は阻止された。
「パぶあっ!?」
蛙が潰れた様な声を出して倒れる幼女。
「~~~っ!」
額を抑えながら畳の上をのた打ち回る。
彼女の額には、大きな針(玉櫛だっけか?)が突き刺さっていた。
その針の持ち主。
紅白の少女は俺の腕の中、左腕を突き出しながらその光景を見つめていた。
「邪魔するな」
悶える幼女に冷たくそう言って、彼女は再び俺に抱きついた。
もぞもぞと動く。
どうやら居心地の良い体勢を作っているようだった。
暫くして、しっくりとした姿勢になったのか。
彼女は動きを止め、再び無言になって状況を堪能しはじめた。
むふ~、と息を吐く音が耳に伝わる。
……いや、有り難いんだけどな。
余りの容赦の無さに、俺は苦笑いしか出来なかった。
いやはや、甘えたいという欲求は此処まで人を変えるものなのか。
「う~~~~っ!」
萃香は依然として畳の上で悶えている……と思ったら勢い良く跳ね起き。
涙目で恨めしそうにこちらを、正確には霊夢を見た。
頬は餅のように剥れている。
あ~……なんか餅が食べたくなってきたな~。
涙を消すように、ごしごしと目を擦る鬼娘。
「こうなったら……」
きらりと、その眼が光った。
「最終手段だ!」
再度大きな声で宣言する。
どうやら彼女はまだ諦めていないようだった。
「いや、いい加減諦めろよ……」
その根性に、つい突っ込んでしまう。
いやホントもう、無理じゃね?
「ふっふっふ……」
俺の思いとは裏腹に、萃香は不敵に笑う。
そして。
「ていっ!」
掛け声と共に、左拳を天に向けて突き出した。
左拳に注目する。
今度は何が起こるのかと思ったが、数秒待っても何も起こらなかった。
幼女は不敵に笑ったまま。
「……どう?」
俺に問う。
いや、どうと言われても……
何も起こっていないので反応のしようがない。
「いや、どうって……何が?」
なので素直に聞くことにした。
途端、彼女の不敵は驚愕に変化する。
「腋よ腋っ! 私の腋はどうだって聞いてるの!」
ああ、そういうこと。
振り上げた腕の意味を理解した俺は、目の前の幼女の腋を観察する。
眼前に広がる腋。
それは例えるならば、若すぎる樹木。
故にその腋は、未成熟な青い果実。
食べるにはあまりにも早すぎる、作り始めの蜜。
イコール……
「襲いたかったら襲っても良いんだよ~?」
観察する様を見ながら、にやにやと笑う幼女。
誘う言葉に、ぴくんと、腕の中の少女が反応した。
ん?
身体が強張る。
……もしかして、心配してるのか?
予想は的中したらしく、抱き締める腕の力がきつくなった。
う~~ん、素直で実に宜しい。
けどな、心配はいらんのだよ。
「どう?」
ふりふりと腋を見せ付ける萃香。
そんなの、答えは決まってる。
「遠慮しとくわ」
その言葉を口にした瞬間。
ぴた、と。
ゼンマイが切れた人形の様に、見せ付ける動きが止まった。
「な……」
ぱくぱくと、金魚のように口を動かす鬼娘。
「なんで!?」
俺はその問いに、紅白巫女の右腕を掴んだ。
「えっ?」
突然腕を掴まれ、久方ぶりに声を発する霊夢。
その声を無視して、俺は目線を萃香に向け……
「俺はコレが良いんだ!」
その腕を自身の首に回した。
「あーーーーーっ!!」
「っ!?」
二つの声が重なる。
刹那。
思考回路が吹っ飛んだ。
ふっくらもちもちの、新米のような首触り。
ほんわかぽかぽかの、春の陽気を凝縮して詰め込んだかのような温もり。
奇跡の二重奏が首元に展開された。
その二重奏は俺の首元を、痛んだ竜骨を癒すように優しく包み込む。
「ほわぁぁ……」
情け無い声が声帯から喉を伝って口外に漏れ出た。
「ちょっと、○○……」
当惑した声。
構わずに、俺は首を摺り寄せる。
「くぅ……んっ」
切なげに喘ぐ声と。
ふっくらつやつやで、ほんわかぬくぬくの、普通では絶対に味わえない感覚。
笑い出したくなるような狂気と、天使の羽で包み込まれるような癒し。
デリシャス。
アンビリーバボーだ!
高らかに心の声を張り上げる。
そして感触を増幅させるため、俺は眼を瞑った。
余計な感覚を遮断することによって、首元に感じる恩恵を更に鋭敏にするためだ。
うわぁ、もっちもちのぽっかぽかだぁ……
今の俺の顔は、ふにゃふにゃに緩みきっていることだろう。
頭の片隅で、赤いライトが点滅する。
そろそろくるぞ。
身の危険をしらせる信号。
無視した。
知るか。
この感触を味わえるのなら閻魔にだって挨拶に行ってやるわ!
威勢良く啖呵を切って、一層のめり込む。
幸福の奔流が、首筋から全身へと巡っていく。
ああ、幸せだ~。
そして……
「この……」
終わりを告げる声が聴こえた。
これから数秒もしないうちに、俺の意識は途絶えるだろう。
もう終わりなのか。
もう、終わってしまうのか。
極楽の終わりに、悔しさと切なさが入り混じる。
さようなら。
別れの言葉と。
また今度。
再会を願う言葉。
そして俺の意識は暗黒へと落ちていく……筈だったのだが。
来る筈の終末は、一向に訪れなかった。
あれ?
頭に疑問符が浮かぶ。
この後、いつもなら容赦無く俺をブッ飛ばす筈の彼女は……
「馬鹿……」
俺の頭を撫でてきた。
予想外の彼女の行動に脳がパニックになる。
どういうことだ?
ブッ飛ばすんじゃないのか?
無数に湧く、頭に何故と付いた疑問符。
けど。
優しい声が。
撫でる手が。
とても優しくて。
何故か、無性に泣きたくなった。
泣きそうな笑顔で少女の腕の間から顔を出す男と。
その男を優しく抱き締める少女。
傍から見たら、さぞかし滑稽に映ることだろう。
けれど、今の俺はそんな外聞はどうでも良くて。
ただ、この時間が永遠に続けば良いと思った。
両腕で、力一杯抱き締める。
この少女を離したくない。
そう、強く思った。
…………強く思ったのだが。
その時間は、意外な人物によって終わりを告げた。
「○○の……」
少女の声とは違う声。
聴こえてくる、何かを回転させる音。
それが気になって眼を開く。
自身の眼と鼻の先には。
誰かがいつも持っている瓢箪が。
「馬鹿ぁぁぁぁあああああああっ!」
ぐちゃりと。
顔面の潰れる音を、俺は聴いた。
そして悲劇は、この一週間後に起きた。
休暇の日を迎えた俺は現在、ルンルン気分で博麗神社の階段を駆け上っていた。
「ふんふふ~ん、ふ~ん」
鼻唄混じりに階段を駆ける。
萃香にやられた傷も癒え、体調もバッチリ。
気合はもう、はちきれんばかりだ。
いつもの三倍に届かんくらい。
何故そんなに張り切っているのか?
理由は三日前の夕方に遡る。
「おっしゃ、これで良し!」
「おう○○!」
「あ、親方!」
「今日も気合充分だな!」
「もちろんッスよ親方! やることしっかりやっておかないと、ゆっくりアイツ等に会いに行けないッスから!」
「アイツ等って……博麗の巫女と守矢の巫女のことか? 随分とまあ熱心だな!」
「当たり前ッス! あの二人は俺の活力源ッスから!」
「活力源とは言ってくれるじゃねえか!」
「へへっ、その通りッスからね!」
「お熱いことで結構だな! その調子で頑張って落としてみせろよ!」
「ウイッス! あ、そーいや何か用ッスか?」
「ん、ああ。お前の休みのことなんだがな」
「休み…………まさか、無しとか!?」
「そうあからさまに嫌そうな顔をするな、逆だ逆!」
「逆?」
「次の休暇を少し豪勢にしてやろうと思ってな!」
「豪勢にって……」
「次の休みは三連休にしてやる!」
「さっ!?」
「お前は皆の中でも、特に頑張っているからな!」
「で、でもそんな……」
「なんだ? もしかして嫌なのか?」
「嫌じゃないッス! けど、今は一番工程が忙しい時期じゃないッスか。なのに自分だけそんなに休むなんて……」
「勿論、連中も同意の上だ。皆、二つ返事でOKしてくれたぞ?」
「え?」
「良い仲間を持ったな!」
「……」
「だから遠慮なく休め! とは言っても、どうせお前は神社に行くんだろ?」
「…………」
「まあ、巫女さん達に宜しく言っといてくれや……って、○○?」
「………………」
「急に黙り込んでどうした?」
「……………………」
「○○?」
「…………………………」
「おい、○……」
「…………………………しゃっ!」
「あ?」
「おっしゃあああああああああああああああああああああっ!!」
「おわっ!?」
「三連休は腋巫女尽くしじゃあああああああああああああああああああっ!!」
「ま、○○?」
「待ってろよ霊夢ううううううううううっ!! そして早苗ええええええええええええええっ!!」
以上、回想終了。
その後の同僚達の反応は省略させて貰おう。
まあ、ぶっちゃけドン引きだった。
妙に余所余所しい同僚達の態度が目蓋に浮かぶ。
あの居心地の悪さは、暫く忘れられそうにねえなぁ……
少し心に影が出来た。
でも、まあ……いっか!
折角の三連休、腐っても仕方が無い。
今はこれから訪れる、幸せのことだけを考えよう。
曇りかけた思考回路の電源を落とし、別の回路を立ち上げる。
立ち上げたのは、三連休の予定。
気紛れに舞い降りた天からの恵み、有効に使わなくては損だ。
階段を上る足を止め、顎に手を当て思案する。
今日は博麗神社に行って、明日は守矢神社……
此処までは良い。
だが問題は……
「明後日、どうするかだよなぁ……」
休みは三日。
交互に行った場合、最後の一日が余る。
どちらに行くべきか、それが問題だった。
巡る思考。
紅腋巫女。
緑腋巫女。
どちらも甲乙つけ難い、至高の逸品。
それ故、俺の頭を大いに悩ませる。
……いっそのこと、両方でいくか?
ぽつりと飛び出した発案。
……それ、良いね。
ニヤリと口元が攣りあがる。
速攻でゴーサインを出した。
そうだよな、両方頂けば良いだけの話だよな。
簡単な話だ。
なによりあの時、そう言ったじゃないか。
脳裏に、去年の年末のある出来事が思い出される。
年も押し迫った師走。
二人の巫女を腕の中に抱いて……
<俺は両方頂く>
確かに言った。
その誓いを破るわけにはいかない。
「そうと決まればこうしちゃいられねえ!」
思考を中断し、止まっていた両脚を再起動させ、階段を二段飛ばしで上る。
今日は紅腋巫女、明日は緑腋巫女。
そして明後日は……
「紅緑入り混じっての腋巫女どんぶりじゃーーーーーーっ!」
熱い咆哮は、山彦の様に辺りに響き渡った。
……ちなみにその叫びは、付近の村にまで届いたらしい。
けれど物事はそう上手くは行かないみたいで。
ハイテンションで神社に到着した俺を迎えたのは、がらんとした境内だった。
「あれ~?」
首を傾げつつ、境内に足を踏み入れる。
おかしいな。この時間だと、大概掃除中の筈なんだが……
境内に見回しつつ、歩を進める。
居ない。
部屋の中か?
そう思い、戸を開ける……と其処には。
「あ~○○だ~」
酔っ払った幼女が居た。
「なんだ萃香か」
「なんだとはなんだよ~ぅ」
発言が気に入らなかったのか、幼女は真っ赤な頬を膨らます。
間延びした声。
酔っ払い特有の喋り方だ。
……ったく、真昼間から酒呑むなっつーの。
言ってもどうせ聞かないので、聞きたいことを聞くことにする。
「なあ、霊夢は?」
「居ないよ~ぅ?」
なにい?
居ないだとう?
「居ないって……買い物にでも行ったのか?」
「違うよ~ん」
にゃはははと、何がおかしいのか笑う鬼娘。
嫌な予感がした。
「じゃあ、何処に行ったんだ?」
「吸血鬼のところ~」
「吸血鬼のところって……」
紅魔館か。
掌を胸の前に置いた、変な吸血鬼が頭に浮かぶ。
あんのロリロリヴァンパイア。
人のモン勝手に持ってくなっつーの。
お前はパッド疑惑のメイド長とでもにゃんにゃんしてろ!
「はぁ、じゃあ帰ってくるまで待つかな……」
心の中で悪態を吐きつつ、部屋に入る。
そんな俺に返ってきたのは、絶望的な言葉だった。
「今日は帰ってこないんじゃないかな~?」
「は?」
炬燵に入ろうと屈んだ体が固まる。
「ランチとディナー付き宿泊コースに御招待~……って、メイドが言ってたから~」
なん……だと?
動揺する頭で、先の言葉の意味を翻訳する。
ランチとディナー。
つまり飯。
宿泊。
すなわち泊まり。
博麗の巫女。
イコール貧乏巫女。
この三つの意味するものは……
アイツは今日、確実に帰ってこない。
「お、終わった……」
がくりと膝が折れる。
三連休腋巫女尽くしプロジェクト ~紅と緑の巫女どんぶり、ポロリもあるよ極楽地獄変~
綿密に練られた計画。
それが音を立てて崩れ落ちていく。
なんてことだ。
計画は初日から頓挫した。
終わりだ……
俺は今日、どうやって過ごしたら良いんだっ!
頭を抱えて嘆く。
どうしようもない現実と見つからない答え。
今にも叫び出しそうだった。
……だがしかし。
ん?
絶望に拉ぐ俺の脳裏を、一筋の光が照らした。
待てよ?
それは徐々に広がって鮮明に答えを照らし出す。
霊夢に会えないんだったら……
照らし出された答え。それは……
早苗ちゃんに会いに行けば良いんじゃね?
守矢神社。
妖怪の山にある神社。
其処には……
もう一人の腋巫女が居る。
折れた膝を立て直す。
消えかかった炎が再燃する。
答えは出た。
守矢神社に行こう。
今から全速力で向かえば、堪能する時間は充分にある。
予定は狂ったが……順番が入れ替わっただけだ、問題ない。
そうと決まればこうしちゃいられない、一刻も早く向かわなければ!
「邪魔したな萃香! じゃあな!」
呑んだくれている鬼娘にそう言って背中を向ける。
そして足の先を外に向け、歩き出そうとしたところで……
「えいっ」
「へぶっ!」
盛大にすっころんだ。
「いってぇ~……」
突然のアクシデントにわけもわからず、打った鼻に手を当てる。
「何処行くのよぅ○○~」
咎めるような幼女の声。
足に違和感。
見ると、足首に鎖が絡みついていた。
こけた原因はコレか。
「一緒に呑もうよ~ぅ」
笑いながら鎖をじゃらじゃらと小刻みに振る幼女。
冗談じゃない。
復活した計画を邪魔されて堪るかっ!
「また今度な!」
キッパリと誘いを断って、絡みついた鎖を解きにかかる。
くっそ、かってえなコレ!
異常に固く絡みつく鎖にてこずっていると……
「今度じゃなくて今呑みたいの~」
「おわあっ!」
勢い良く引っ張られた。
「つかまえた~」
腕をつかまれる。
うわあ、捕まっちゃったぁ。
「って、離さんかい!」
「一緒に呑むの~」
へらへらと笑いながら腕にしがみつく幼女。
こっちの話など、これっぽっちも聞いちゃいない。
正に酔っ払い。
腕を離そうとしたが、いかんせん鬼の力。
俺程度の力じゃ離れるわけもなく。
「わ~い! ○○と宴会だ~!」
「ちょ、緑腋巫女おおおおおおおおおっ!!」
半ば強制的に、俺は鬼と酒を酌み交わすこととなった。
「ふぅ、やっぱり外は寒いです……」
境内の掃除を終えた彼女は、居間に入りながらそう言った。
いそいそと炬燵に入る。
「やっぱり、炬燵は暖かいですねぇ……」
幸せそうに顔の筋肉を弛緩させ、台に頬をつける緑白の巫女。
外に居たためか、彼女の肌は寒さで赤くなっていた。
彼女の身体を温めるために、俺は炬燵に入っている緑白の少女を後ろから抱き締める。
「え、えっ!?」
驚く彼女。
瞬く間に、弛緩が緊張に変わってゆく。
構わず抱き締める力を強くした。
「ひゃっ!?」
抱き締める強さの変化に、少女は再び驚きの声を発する。
だが、それも一瞬のことだった。
「ん……」
状況を理解したのか。
おずおずといった具合で、こちらに身を委ねてくる少女。
「○○、さん……」
甘えるような声。
抱き締める腕に触れられた手。
もう緊張は解けたようだ。
そのことを理解した俺は、本来の目的を遂行することにした。
外気に当てられたためか、彼女の肌は赤くなっている。
勿論、彼女の『腋』も。
口元が愉快気に歪む。
出てくるのは狂った情愛。
温めなくっちゃなぁ。
そして俺は……
自身の首を彼女の腋に。
光の速さで突っ込んだ。
腋マフラー。
一週間前に、紅腋巫女から体感した新たなる奇跡。
それを今度は緑腋巫女で体感する……っ!
「にゃはははは~」
筈だったのになぁ……
馬鹿みたいに楽しそうな笑い声。
その笑い声によって、霞みのような幻想は掻き消され、分かりたくもない現実が戻ってくる。
目の前には、第二の腋マフラーを持つ緑白の巫女……ではなく。
「にゃはははは~」
楽しそうに笑う、酔っ払い。
「んくっんくっ……ぷっはーーーーーっ! やっぱりお酒は最高だね~!」
酒を呑んで満足気に幼女は明るく笑う。
「……はぁ」
反対に、こちらの気分は果てしなく暗かった。
そのうちブルーを通り越してブラックになりそう。
気分を色で見ることが出来たのならば、この部屋は黄色と濃い藍色の二色に分かれていることだろう。
「な~に溜息吐いてんのよ○○~。溜息吐くと、福が逃げるんだぞ~?」
笑う鬼娘。
「はぁ」
その姿を見て再度溜息。
自分では吐くつもりはないのだが、出るものは仕方がない。
「あ、また福が逃げた~」
おかしそうに笑う酔っ払い。
うっせえ、福ならもう逃げたっつーの。
本当なら俺は今頃、守矢神社に居た筈なのに……
幻想の中に居た少女が再度浮かぶ。
正しくは、彼女の『腋』が。
先の幻想の中でも、一際輝いていた幻想。
自身が求めた、二つしかない至高の逸品。
そのうちの一つを所有する奇跡の巫女。
「緑腋巫女ぉ~……」
意識せずその言葉が口に出た。
それほどまでに自身の心と身体が求めていたのだろう。
だが、それはもう届かない。
「うぅ……」
切ない現実に涙が出そうになった。
「なぁに暗くなってんのよ~。お酒は楽しく呑むもんだよ~」
心中を知ってか知らずか、励ますように俺の肩を叩く酔っ払い。
無配慮な発言に、少しだけ怒りが湧いた。
誰のせいだと思ってんだこの野郎。
「うるせいチクショウ。今の俺を明るくしたかったら大至急、紅腋もしくは緑腋を持って来やがれ」
若干の不満を込めて言い放つ。
幼女はその言葉に対して……
「な~んだ。腋が見たいんだったら、私のを見れば良いじゃな~い」
腕を振り上げた。
上げた腕の根元には、腋。
酒気を帯びている為か、ほんのりと紅く染まっている。
「ほれほれ~い。どお~?」
楽しそうに見せ付ける鬼娘。
だがそれとは裏腹に、俺のテンションは更に下降した。
俺の目の前には、腋。
腋だ。
ああ腋だ。
確かに腋だ。
間違いなく腋だ。
誰が何と言おうと腋だ。
腋………………なんだけど。
やっぱりというかなんというか。
何の感情も湧かなかった。
「はぁ」
代わりに何度目かの溜息が湧く。
「なにそのリアクショ~ン!」
剥れる幼女。
態度がえらく御不満だったらしい。
「少しは興奮しないの~? 好きなんでしょ、腋~?」
言いながら、しつこく見せ付ける。
彼女の腋は、鼻から数センチ先にあった。
これが紅白の巫女か緑白の巫女の『腋』であったならば、俺は迷うことなくダイブしていたことだろう。
だが、コレは彼女達の『腋』ではない。
眼を閉じる。
そして……
「無理」
ハッキリと言った。
うん、やっぱり無理。
やっぱ俺はアイツ等の『腋』じゃないと興奮出来ない。
いや萃香のも悪い訳じゃないのよ?
けど……やっぱ、まだまだ青い果実なんだよなぁ。
もう少し熟したら、そん時はどうなるか知らんけど。
「○○のいけず~!」
幼女は喚きながら一升瓶を口につけ、中に入った液体を嚥下していく。
瞬く間に、一升瓶の中身は空になった。
「ぷっはーーーっ!」
酒臭い息がこちらにまで臭ってくる。
思わず鼻を摘まんだ。
「にゃははははははは~!」
盛大に笑う。
悩みなど何も無い。
そう思わせるような、心底からの笑い。
既に誘いを断られたことなど忘れているに違いない。
無邪気な笑顔。
だからだろうか。
こんな言葉が出たのは。
「ったく、お前は楽しそうで良いねぇ…………これなら、別に俺が居なくても良かったんじゃねえか?」
愚痴を漏らしつつ、近くにあった酒瓶を手に取る。
少量を口に含み、ゆっくりと味を確かめ、そして呑み込んだ。
喉がきゅっと熱くなる。
っか~……結構キツイなぁ。
でも旨い。
癖になる旨さだ。
もう一口呑もう。
そう思い、再び口をつけうようとした時だった。
「……からだよ」
「ん?」
小さな声が耳に届いた。
吹けば飛んでしまうような、小さな声。
俺はその声に気付き、声のした方を向く。
声の主。
萃香は、泣きそうな顔をこちらに向けていた。
さっきまで陽気に笑っていたのが嘘のように、その眼には涙を滲ませている。
幼女の突然の変化に、俺の心中はみっともなく焦った。
え、なに、どしたの急に!?
ついさっきまで笑っていたのに、なんで泣きそうになってんの!?
「私が……」
前触れもなく発生した急展開に驚く俺を放置したまま、彼女は言葉を発する。
「私が楽しそうに見えるのは、○○と一緒だから……だよ?」
折れそうな声で。
彼女はそう言った。
その言葉に。
ズキンと。
胸に鋭い痛みが走った。
「○○と一緒だから、こんなに嬉しくて、こんなにも楽しいんだよ……?」
少女は言葉を紡ぐ。
「一人なんて、ちっとも楽しくない……」
泣きそうな顔のままで。
「○○と一緒だから、今、私は笑ってるんだ……」
明るい笑顔に秘められた、自身の胸のうちを明かしていく。
一筋の涙が、頬を伝ってぽたりと落ちた。
雫は畳に滲んで広がる。
その事実を隠すように、彼女は顔を俯かせた。
ああ。
今、理解した。
だからコイツは……
鬼。
最強の一つとして語られる種族。
人に恐れられ、人に語られた種族。
今はもういない、忘れられた種族。
幻想郷に彼女一人だけの……種族。
ひとりぼっちの、鬼。
俺は馬鹿だ。
陽気な面ばかりに囚われて、彼女の本質を理解していなかった。
何故いつも俺に甘えてくるのか?
今はその理由が良く判る。
だから俺は……
「なあ萃香」
彼女の名を呼んだ。
自分の名を呼ばれ、彼女は顔を上げる。
顔は涙でぐちゃぐちゃだった。
「お前の酒、注いでくれねえか?」
それには触れずに、指を差す。
差した先は、彼女の瓢箪。
彼女は予期せぬ発言に少しの戸惑い見せつつも、黙って従った。
差し出した湯呑みに、おずおずと酒を注ぐ。
程無くして湯呑みは酒で満たされた。
「サンキュー……じゃあ、お返しに」
瓢箪を彼女の手から奪う。
代わりに彼女の手には湯呑みを。
「え?」
「溢すなよ~?」
驚く声を無視して、彼女の持つ湯呑みに酒を注ぐ。
数秒と経たずに湯呑みは酒で満タンになった。
「よっしゃ、それじゃあ……」
瓢箪を傍に置いて、自分の湯呑みを持つ。
そして……
「かんぱーーーいっ!!」
かきん、と互いの湯呑みを軽くぶつけ合った。
湯呑みの中身を一息で喉の奥に流し込む。
一気に呑んだ為か、かっと身体が熱くなった。
「っぷはーーーーーっ!」
空になった湯呑みを叩きつけるように台に置く。
萃香は、ぽかんとした様子でこちらを見ていた。
両手に持った湯呑みには、まだ酒が波々と入ったままだ。
「なんだ、まだ呑んでねえのか?」
「え?」
「乾杯の時は一気飲みが恒例だろ。早く呑めい!」
「え、え?」
急変したこちらの態度に、おろおろと慌てる萃香。
これはこれは、中々珍しいモンが見れたな。
萃香は手に持った湯呑みと俺を交互に見つめる。
そんな萃香に向けて俺は……
「時化たツラしてんじゃねえ、酒は楽しく呑むモンだ」
笑って言ってやった。
「あ……」
彼女の口から言葉にならない声が漏れる。
酒は楽しく呑むもの。
それは彼女自身が言った言葉。
だからこそ、その意味が良く分かった。
腕で眼をごしごしと擦る。
そして湯呑みに注がれた酒を一気に呑んだ。
「ぷはあっ!」
「お~良い呑みっぷりだ!」
呑みっぷりの良さを称える。
萃香は呑み終えた湯呑みを台に置き……
「うわ~~ん○○ーーーーーっ!!」
飛びついてきた。
「どわっ!?」
不意を突かれた俺は、そのまま後ろに倒れ込む。
「嬉しいよ~~~!」
倒れたことも構わずに、萃香はすりすりと頬に頬を摺り寄せる。
「もう○○好き~~~っ!」
彼女は何かのスイッチが入ったらしく。
「大好きだよ~~~っ!!」
かなりテンションが上がっていた。
「好き好き好き~~~っ!! ○○大好き~~~っ!!」
テンションに倣って、摺り寄せる速度も加速度的に上がっていく。
……って、いや、これすりすりってレベルじゃねえぞ!
なんか頬がすんげえ熱いんですけど!?
「わかった、わかった!」
このままじゃ頬が焦げる。
直感した俺は、制止に入った。
「嬉しいのは充分わかったから、早く呑もう!」
その言葉に、ピタリと頬を摺り寄せる動きが止まる。
そして萃香は勢い良く上体を起こし……
「そうだね! 呑もう呑もう!」
笑った。
それを見て、安堵の息を漏らす。
ふぅ、助かった。
「今日は朝まで飲み明かすぞ~~~っ!!」
萃香はそう言って瓢箪の酒をラッパ呑みする。
「ちょ、人の体の上で呑むなっ!」
零れてるっつーの!
彼女の口からあぶれた酒の雫が、ポタポタと顔に落ちてくる。
「にゃはははは、気にしない気にしな~い」
こちらの苦情など、気にしてない風に笑う鬼娘。
その顔は、心底楽しそうだった。
やれやれ。
笑う萃香を見て安堵する。
明るい笑顔。
やっぱりコイツには笑顔が似合う。
出来れば、ずっと笑っていて欲しい。
その点で言えば、今回の出来事は俺的には収穫だった。
笑顔に隠された孤独。
明るく見える彼女の、寂しがり屋な一面。
そういえば……
アイツと似ているな。
大切な二人の少女。
そのうちの一人が脳裏に浮かび上がる。
紅白の巫女服に身を纏った少女。
素っ気無く見えて、その実甘えたがり。
うん、良く似ている。
障子から漏れる陽の光はオレンジ色。
もうそんな時間なのか。
紅魔館はそろそろディナーの時間だろう。
豪勢な食事が並べられる様を、涎を垂らしながら見つめる極貧巫女。
同情の涙を流しながらその様子を見守る、館の住人達。
……やべえ、素で想像出来るわ。
館の住人達の心情を悟りつつ、切なくなっていると……
「こら~○○~。何ボーっとしてんの~、○○も呑もうよ~!」
可愛らしい不満の声が聞こえた。
萃香はアヒル口でこちらを見つめている。
巡らせていた思考をストップさせた。
そうだな。
今はお前と呑んでるんだもんな。
今夜の相手は紅白の巫女でも緑白の巫女でもない。
誰もが恐れおののく強大な力を持った、寂しがり屋の鬼娘。
余計な思考は無用。
今は彼女との酒を楽しもう。
「よっしゃ、じゃあ……」
答えつつ、視線を彼女に移したその時。
世界が、止まった。
「……っ!?」
衝撃に言葉が詰まらせた。
ドクン。
心臓が大きく跳ねる。
目の前には、酒を呑む幼女。
だが其処に俺の意識は向いていない。
注目はそれより僅かばかり下の部分。
口から滴り落ちた液体によって身体に描かれる濡れた糸。
その終着地点に、ソレはあった。
ソレは生まれたばかりの穢れを知らない無垢な蕾。
ソレは未成熟故に、稀有な甘さを持つ極上の甘露。
ソレは酒池に溺れし者を更なる底へと誘う極楽の器。
ソレハ……
遠くで獣の声が聴こえた。
腋。
世界を作った神が、地上に落とした一粒の奇跡。
この世に唯一つ残された希望の楽園。
今、その楽園が扉を開けて俺の前に佇んでいた。
ごくりと、唾を飲み込む音。
その音にハッとする。
何を考えているんだ俺は!?
そして急速に意識をソレから逸らした。
青い果実。
そう、青い果実だ。
だから興味無い。
前にそう思った筈だろ!?
自身を問い質す。
けれど……
目の前にある、腋。
それ単体では、只の青い果実。
だが今は……
腋に艶かしく線を引く、透明な液体。
熟成されたその雫が未成熟な器と混じり合い、隠匿された神秘へと姿を変える。
ソレは極上の愉悦。
再び喉が鳴る。
夕陽がソレを照らした。
照らされたソレは、きらきらと眩い光りを放つ。
まるで雨の後の蜘蛛の巣のよう。
自身の身を滅ぼすことを理解して尚、飛び込みたくなる妖しさ。
先程よりも近くで、獣の雄叫びが響いた。
五月蝿い!
獣に言う。
俺は……俺は誓ったんだ!
俺は両方頂く。
アイツ等の『腋』しか、俺は求めない。
そう、自身に誓ったんだ。
その誓いを破るワケにはいかない。
獣に惑わされぬよう、キツく歯を食い縛る。
『馬鹿が』
侮蔑の声が、耳に届いた。
気が付くと、俺は真っ暗な空間に居た。
漆黒の闇が何処までも続く空間。
生命の存在を拒絶したような黒。
その空間を、俺は知っていた。
スポットライトが、ある一点を照らす。
照らされた先には巨大な獣……ではなく。
見知らぬ男が居た。
武道着のような服を着込んだ、屈強な男。
微かに、獣臭がした。
『よう』
男はそう言って、俺に向かって軽く手を上げる。
そしてゆっくりと近づき、三歩程の距離を置いて立ち止まった。
一瞬の静寂。
気まずさに耐えかねた俺は、何か喋ろうとして……
胸倉を掴まれた。
「なっ!?」
何するんだ、とは言えなかった。
男の身体から、見て取れる程の殺気が出ていたからだ。
『何故、あの鬼を喰らわない?』
男は問う。
何故そんなことを、とは聞くまでもなかった。
「アイツ等の腋じゃないからだ」
答えた瞬間、胸倉を掴む力が強くなる。
そして……
『馬鹿がッッッ!!』
勢い良く投げ飛ばされた。
数秒の空中飛行の後、地面を転がる。
三回転程して、ようやく俺の身体はストップした。
衝撃に息が詰まる。
『忘れてるんじゃねえッッッ!!』
倒れている俺に向けて、男は言う。
忘れている?
何を?
男の言葉を理解出来ない。
一体、何を忘れているっていうんだ?
分からないでいる俺に、男は言い放った。
『あの鬼は、お前になんと言った?』
萃香が俺に言ったこと?
思考を巡らせる。
答えは直ぐに出た。
<襲いたかったら襲っても良いんだよ~?>
……あ。
言った。
そうだ、確かに彼女はそう言った。
『思い出したみてえだな』
俺の様子を見て、男は口元を歪ませる。
「ああ」
それに頷いて返す。
だが……
だからと言って、そう簡単に割り切れるモノではない。
『考えるな』
悩む俺に、男は言った。
『お前のそれは、侮辱だ』
吐き捨てるように言葉を放つ。
『目の前の神秘だけを見ろ』
その言葉に、心が反応した。
顔を上げて男を見る。
「目の前の神秘だけを、見る?」
『そうだ』
反芻した言葉を、男は肯定する。
男の瞳が、言葉が、とても熱かった。
そうか。
身を縛る鎖が解ける音が聴こえる。
俺は……
頭の中はとてもクリアだ。
俺は何を悩んでいたんだろう。
何も悩む必要なんてなかったのに。
其処に、自身の欲する『腋』があるのならば。
『そうだ』
まるで頭の中を読んだかのように彼は二度目の肯定をする。
『ただ……』
彼は言葉を紡ぐ。
ああ。
今、俺がするべきことは唯一つ。
「美味い料理を喰らうが如く」
『美味い料理を喰らうが如くだ』
重なる言葉に男は笑った。
それは本来の意味の、笑顔。
迷いはもう無かった。
『行け』
もう用は無いと言わんばかりに。
男はこちらに背を向ける。
ああ、言われなくても行くさ。
大きく空気を吸い込む。
そして……
「オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオッッッ!!」
獣のような叫びが、暗闇を切り裂いた。
「どうしたの○○~?」
様子を伺う彼女の声。
だがその声は、耳には届いても脳には届いていない。
今の俺の頭には、もう何も届かない。
「○○?」
返事が無いことを不思議に思ったのか、彼女は首を傾ける。
「お酒呑まないの~?」
そう言って、萃香は瓢箪を見せる。
酒?
ああ、酒なら呑むさ。
「ね……」
「そうだな、じゃあ貰おうか」
言葉を遮って言う。
「そう? じゃあ注ぐね~?」
萃香は不思議そうな顔をしながら、自身の手を台に置いてある俺の湯呑みに伸ばす。
その腕を、掴んだ。
隠された秘境が顔を覗かせる。
口元が醜く歪むのが分かった。
「え?」
突然腕を掴まれたことに戸惑う萃香。
その声を無視して俺は。
その秘境に……
しゃぶりついた。
「うひゃあ!?」
驚きの声が上がる。
しかし、今の俺にはそんなものどうでもいい。
口の中を神秘が蹂躙してゆく。
な。
舌先をビリビリと刺激する未曾有の味。
甘く濃厚なソレは、所狭しと口内を暴れ回る。
なんだ。
鼻腔を強烈に刺激する、芳醇な香り。
甘酸っぱい、聖母のような、生まれたての生命のような、神秘的な匂い。
なんだコレは。
唇を包み込む、スライムのように柔らかな感触。
吸い込む勢いによって様々に形を変えるソレは、逆にこちらが吸い込まれるような錯覚を感じさせた。
それらが一体となって、味覚を、嗅覚を、触覚を犯していく。
「ひゃ、あ……」
うお……
余りの刺激に、堪らなくなって飲み込む。
原始の炎のような熱が、俺の喉を焼いた。
神々が居た太古の時代。
其処に確かに存在した、極上の醸成酒。
禁断の果実のみで精製された、禁忌の美酒。
ソレが今、自身の中に流れ込んでいる。
美味い。
なんという美味さだ。
先程呑んだ酒など足元にも及ばない。
禁断とされるに相応しい味。
想像を遥かに上回るソレに、気が狂いそう。
神は、こんな名酒を呑んでいたのか。
飲み込んだことによって、口の中が空になる。
いつの間にか呼吸は荒くなっていた。
もっと。
もっとだ。
掴んだ腕を上げる。
腕を上げたことにより、更に呑みやすくなった。
さあ二口目だ。
「な、なにを……」
怯えたような声。
構わずむしゃぶりついた。
「ひゃっ」
一口目と変わらない衝撃が俺を襲う。
再度口内に侵入した美酒が、舌の感覚を、脳の機能を。
唇を優しくも荒々しく包み込む器が、唇の感覚を。
徹底的に破壊していく。
霞んでいく思考。
薄れていく自我。
そんな中でも鮮明に浮かぶ、たった一つの言葉。
美味い。
美味いっ。
美味すぎるっ!
それしか浮かばない。
心が、体が、神の生み出した奇跡の酒を求めていた。
「ぁあぁぁ……」
もっと。
もっと呑ませろ……っ!
荒々しく腕を固定する。
「も、ゃめ……ぇ」
懇願する声を無視して、むしゃぶりつく。
じゅるじゅると音が鳴った。
口元から、涎とも酒ともつかない液体が溢れる。
それらを拭うこともせずに、がむしゃらに酒を呑んだ。
じゅるじゅる、じゅるじゅる。
響く音。
それさえも己の精神を犯していく。
「ゃ……ぁぁ」
喘ぐ様な声。
構うものか。
今はこの酒を呑むことだけに神経を集中させろ。
壊れかけの脳に、伝令を送る。
繰り返すように、酒を啜る。
止まらない欲求。
鳴り響く狂騒。
全身を支配するカタルシス。
そして意識が崩壊する直前。
何かが爆発した。
轟音が辺りに響き渡る。
「な、なんだ?」
その音で我に返った俺は、急変した状況に辺りを見回す。
吹き飛ぶ戸。
反響する轟音。
揺らぐ煙。
猛烈に熱を奪う寒波。
そんな中、俺は見た。
吹き飛んだ戸があった場所。
その奥に陽炎のように佇む、大きな袋を手に持った少女。
心臓が凍る音が、聴こえた。
そして疑問。
何故?
何故彼女が此処に?
その疑問が解ける前に。
少女は姿を消した。
あれ、と思った時にはもう手遅れ。
後ろから感じる強烈な殺気。
それとともに発生した膨大な……熱。
「ちょ、ま……」
制止の言葉。
その全てを言い終わる前に。
「こんの浮気者おおおおおおおおおおおおおっ!!」
俺の意識は根こそぎ刈り取られた。
意識の途絶えるほんの僅かな瞬間。
紅い吸血鬼の嘲笑う声が聴こえたような気が、した。
ふと辺りの暗さに気付く。
見ると、外には夜の帳が下りていた。
ぶるりと身震いが起こる。
寒さが増していることに、今更になって気付く。
もうそんな時間か……
暗闇の中、手探りで灯りを点す。
ほどなくして、暗い室内を照らす光が現れた。
灯りを見つめる。
囲炉裏に火は点けない。
今、熱は欲しくなかった。
そして俺は、それからのことを思い出す。
あの後。
目を覚ますと、全身包帯まみれで自宅の布団に寝かされていた。
自身のしでかしたことを理解した俺は次の日、無理を押して再度博麗神社に向かった。
そんな俺を待っていたのは。
夥しい量の弾幕だった。
もう有無を言わさん程の。
仕方無く博麗神社に行くのを諦めた俺はそのまた次の日、守矢神社に向かった。
そして俺を待っていたのは。
凄惨な弾幕だった。
それはもう、殺す気満々の。
実践同然の本気の弾幕。
どちらも逃げ帰れたのはラッキーとしか言いようがなかった。
そこでふと疑問が湧いた。
霊夢はともかく、何故早苗ちゃんまで怒っているのか?
その疑問は、知り合いの烏天狗に聞くことで解決した。
曰く、守矢神社を紅魔館の主が訪れたとのこと。
それを聞いた瞬間、疑問は怒りに変わった。
同時に、霊夢が紅魔館から早く帰宅した理由も理解する。
永遠に紅い幼き月。
彼女の持つ能力は、運命を操る程度の能力。
その能力は、先の運命さえも見通すことが可能だと言われている。
ということは。
視えた運命のうちの『どれか』を選択することも、彼女にとっては朝飯前ということだ。
すなわち。
俺はあの吸血鬼に嵌められたということになる。
その事実に俺は怒り狂った。
が、今となってはどうしようもないこと。
正直言って、かなりのダメージだった。
火が揺れる。
去年の大晦日のように、彼女達が此処を訪れることもない。
来るのは、村の友人達と……
「やっほ~~~~!」
鬼だけだった。
「遊びに来たよ~~~~!」
「おう」
突如目の前に現れた幼女。
それに驚くこともなく返事を返す。
伊吹萃香。
あの件以来、彼女は頻繁に我が家を訪れるようになっていた。
落ち込む俺を見兼ねたのか、はたまた只の気まぐれか。
彼女は足繁く此処に通っている。
そのことが、今の俺にとって唯一の救いだった。
だが、今回は更に特別。
「それで、どうだった?」
彼女に尋ねる。
「駄目だった」
彼女は肩を大きく落としてそう言った。
「やっぱりかぁ~……」
釣られるようにこちらの肩も落ちる。
「そんな気はしてたんだがなぁ……」
特別の理由。
それは……
「もう全然駄目。霊夢は○○のことを口に出すと何も喋らなくなるし、
早苗は早苗で、『○○さんなんて知りません!』の一点張りだし……あ、諏訪子と神奈子は○○に会いたがってたよ!」
萃香は結果を報告する。
そう、俺は萃香に彼女達の心情調査を依頼していたのだった。
そこから何か現状を変える糸口でも見つけ出せればと思ったのだが……
結果は言わずもがな。
聞くのも耐えがたい現実が俺を痛めつけてくる。
せめてもの朗報は、諏訪子と神奈子さんくらいのものか。
でもまあ、あの二人は事情を知らないだろうし。
当然と言えば当然か……あ~あ。
「はぁ」
自然と溜息が出た。
天井を見上げる。
「○○?」
「いつまで続くんだろうな……」
そんな言葉が口に出た。
出したことによって、それは厳しい現実となって心を締め付ける。
今でも変わらず、休みの日には両方の神社に顔を出している。
けれど変わらないのはそこまで。
声を掛けようとすると、弾幕。
触れようとすると、弾幕。
弾幕。
弾幕。
弾幕。
まるでそれ以外は不要とばかりに。
あれ以来。
俺は彼女達と一言も言葉を交わしていなかった。
「はぁ」
また溜息。
あれから約一ヶ月。
一ヶ月だ。
一ヶ月も彼女達の『腋』に触れていない。
触りてえ。
切なさと苦しさで、胸が破裂しそう。
でもそれは叶わぬ願い。
そして湧き上がる一つの感情。
それは真っ赤な真っ赤な。
鮮血のように紅い炎。
あの……
歯がぎしりと鳴る。
あの吸血鬼め。
脳裏に移るは、紅魔。
全部。
紅い、悪魔。
全部アイツのせいだ。
身を焦がすほどの紅蓮が己を包む。
アイツのせいで、俺は……
自身の許容量を遥かに上回る怒りに溺れる。
……と。
突然。
萃香が背中に圧し掛かってきた。
柔らかい感触と確かな温度が背中から伝わる。
「○○、怖い顔してる~」
窘めるようにそう言いながら、首に手を回してきた。
「してねえ」
「してるよ~」
「してねえって」
「してる」
…………してただろうな。
「考えてたのは、あの吸血鬼のこと?」
「ああ」
全部、アイツのせいだからな。
「こうなったのも、あの野郎のせいだからな」
アイツだけは絶対許さん。
呪う様に、そう呟いた。
「そう。じゃあ……」
俺の言葉に、萃香は身体を摺り寄せ……
「私のことも、許さない?」
そう、言った。
「は?」
思わず聞き返す。
なんで?
なんで俺が萃香を?
あの吸血鬼は当然としてしばくが、俺が萃香を恨む理由はどこにも無い。
俺の動揺を無視して、萃香は言う。
「だって……私にあんなことしたせいで、こんなことになったんだよ?」
許しを乞うような口調だった。
首に回された萃香の腕は、微かに震えていた。
ああそういうこと。
彼女は、悔やんでいるのか。
自身と関わったために、こんな事態を引き起こしたと。
そう思っているのか。
そうかもしれない。
起こった事実だけを見るならば……確かに、そうかもしれない。
でも、コイツは大事なことを忘れている。
それはとても大切で、最も重要な……
一つの、信念。
回された腕を外し、自身の身体を反転させる。
そして幼女を胸の中に抱き入れた。
「な、なにする……」
わけもわからず腕の中でもがく幼女。
俺はそいつに向かって……
「ば~か」
言ってやった。
「なっ!?」
「俺がお前を恨む? 馬鹿言ってんじゃねえぞ? 感謝するならともかく、恨むワケねえだろ」
「だ、だって……」
「あれは俺が望んでやったんだ。そのことに関しては、後悔なんか微塵も無い」
そうだ、後悔なんてあるもんか。
秘境に隠された神の酒。
暴かれた、新たなる神秘。
其処に至れたことに感謝こそすれ、恨むなど有り得ない。
「俺は後悔なんてない」
強く言い切る。
「わかったか?」
そして、呆然とした顔でこちらを見つめる幼女に笑いかけた。
彼女の顔は一瞬の後。
「……うぁ」
ぐしゃぐしゃに崩壊した。
「ぅぇあっ、ひぐっ……っ」
堰を切ったように流れ出した涙が顔を濡らす。
「っ、ぅぁっ……ひっ、えぅ」
零れる涙が、俺の服に染みを作った。
嬉しさから出たためだろうか。
溢れ出した涙は、とても温かかった。
「ょ……か、った……っ…………ょか、っった、よぅ」
しゃっくり交じりの声。
良かったと。
涙声で何度も繰り返す。
きっと彼女は怖かったのだろう。
このことで、俺との繋がりが絶たれるかもしれないということが。
関わりが無くなることが。
嫌われることが。
どうしようもなく、不安だったのだろう。
馬鹿なヤツ。
そんなことあるワケねえのに。
宥めすかすように、優しく背中を擦る。
最強の鬼。
人に恐れられる存在。
その身体が、今はとても小さく、そして愛おしく感じた。
「あ~もう、泣くなって……」
赤子をあやすように背中を擦る。
心配するな。
誰もお前を一人になんかしない。
大丈夫。
ずっとずっと。
皆、一緒だ。
想いが手から伝わるよう願いながら、その背中を優しく撫で続けた。
さて。
突然ながら、此処で諺の問題だ。
泣きっ面に蜂、という言葉を御存知だろうか?
悪い状況の中、更に悪いことが起きる様を表す言葉だ。
これを俺に当て嵌めてみると……
泣き面とは、今。
つまり、巫女達に無視され続けて泣きそうな現状だ。
じゃあ蜂は?
それは今から起こるんだよ。
正確には蜂じゃなくて……
「ひっ……ひっ、うぅ」
未だ腕の中で泣き続ける萃香。
胸元を握ったまま離さない。
それを愛しげに眺めつつ、宥めていると唐突に。
「っ!!」
背中を大きな何かで突き刺された。
否、正確には刺されてはいない。
それは視線。
見るだけで人を殺すような、視線。
明確な意味を持った、殺意。
ぎちぎちと。
錆びた滑車を回すように首を後ろに向ける。
首を向けた先。
玄関。
其処には雪の寒さよりなお寒い、絶対零度を従えた……
二人の修羅が、居た。
「~~~っ!!」
予想だにしない、しかしある意味予想通りの展開に、俺の頭は恐慌状態に陥る。
そして飛び出す、様々な疑問。
な、なんで!?
どうして霊夢達が此処に!?
今までちっとも来なかったのに!!
何故今になって突然の来訪!?
なにがなんだか分からない。
混乱する脳機能。
慌てる俺を、二人は無表情で見つめている。
無機質な、鉄仮面のような顔。
ぞくりと、背筋が凍った。
ちょっと待て。
俺、なんでこんなに殺気を向けられてんの!?
その解を求め、ぐるぐると焼き切れんばかりに脳を働かせる。
今の俺の状態。
泣いている萃香を抱き締めている、以上。
つまり、それが答え。
それが導き出す結果は……
「な、なんで?」
震える声で少女達に問う。
何故、今になって此処を尋ねたのか?
これから自身に訪れる結末は分かっている。
でもだからこそ、来訪の理由を知りたかった。
俺の問い掛けに、少女達は透明な声で答えた。
「今日ぐらいに仲直りしてきたらって。そうレミリアに言われたから、来たんだけど……」
「私は霊夢さんに一緒に行こうって誘われて来たんですが……」
あのロリめえええええええええええっ!!
やりやがったなああああああああああああっ!!
高笑いする吸血鬼の姿が、浮かんで消える。
「でも……」
「ですが……」
激昂は二人の修羅の言葉で掻き消され。
それぞれの手に持つは、無数の御札と御払い棒。
「そんな必要は無かったみたいね……」
「そんな必要は無かったみたいですね……」
莫大な霊力が収束していく。
世界を破壊出来そうな程の、暴力。
それが二人の元に集まっていく。
「ちょ、ちょっと待て! これにはワケが……」
「問答無用」
「問答無用です」
説得の言葉は、一刃の元に消え失せる。
ああ、これはもう、駄目かも知れんね……
どうしようもない現実に、諦めと絶望が心を支配していった。
「○○の……」
「○○さんの……」
集まった霊力は臨界に達し……そして。
「「スケこましいいいいいいいいいいいいいいいいっ!!」」
俺は我が家もろとも、盛大にブッ飛ばされた。
この後、家が直るまで一週間。
身体の傷が全快するまで二週間。
巫女達と仲直りするのに一ヶ月掛かった。
全快してから巫女達と仲直りするまでの間の、とある日に。
萃香と諏訪子、神奈子さんを引き連れて紅魔館を襲撃したのは言うまでもない。
おまけ ~ある日の紅魔館~
「くっくっくっ……」
「お嬢様、お茶が入りました」
「ありがとう咲夜」
「最近、機嫌が宜しいですね」
「わかる?」
「はい」
「そう……」
「理由はやはり、あの男でしょうか?」
「ええ。こういうの、目の上のたんこぶが取れたっていうのかしら? とても爽やかな気分だわ」
「それは喜ばしいことですね」
「全くよ。只の人間が私の霊夢に手を出そうだなんて、百年早いわ。
あまつさえ、他の女にも手を出しているだなんて、舐めてるとしか言いようがない」
「その点については同意します」
「しかも近づいた目的が、腋よ腋? ふざけるにも程があるわ」
「まあ、人の趣味嗜好はそれぞれですから」
「そうだとしても、ふざけてるわ。霊夢も霊夢よ、あんな馬鹿と関わりを持つだなんて……」
「ですが、霊夢の方はそれほど嫌ではないみたいですね。むしろ彼の話をしている時の霊夢は、どことなく嬉しそうな……」
「咲夜」
「なんでしょう?」
「その続きは言わなくて良いわ」
「畏まりました」
「とにかく、これで邪魔者は消えたわ。後は霊夢をモノにするだけ……」
「そう上手くいくでしょうか?」
「いくわよ。先日、追い討ちも掛けておいたしね」
「追い討ち?」
「そう、追い討ち。もう完膚なきまでの」
「はぁ」
「さてと、アイツを再起不能にしたことだし……今から霊夢の処に行こうかしら?」
「それでは傘を御用意致します」
「助かるわ」
「いえ、これも務めですか……」
「さ、さ、さ、咲夜さあああああああんっ!!」
「騒々しいわよ美鈴」
「あ、すいません……って、それどころじゃないんです!」
「どうしたの中国?」
「あ、お嬢様もいらっしゃたのですか!?」
「居たら悪い?」
「いえ、そんなことはありません! 寧ろ好都合です!」
「あそう」
「で、何があったの?」
「侵入者です!」
「侵入者って……また魔理沙ね。全く、普通に入ってきなさいって言ってあるのにアイツったら」
「まあ良いじゃない、フランの良い遊び相手が出来たわ」
「ああ、それもそうですね」
「違います! 黒白じゃありません!」
「あら、じゃあ誰かしら?」
「人間です!」
「人間?」
「もしかして霊夢かしら?
ああん、折角会いに行こうと思ってたのに…………でも、会いに来てくれるなんて嬉しいわっ!」
「お嬢様……」
「紅白でもないんですっ!」
「なんだ。じゃあ誰なのよ?」
「ですから人間です! 人間の男です!」
「人間の男って……まさか」
「○○か。御礼参りでもしにきたのかしら?」
「かもしれませんね。でも、それくらいなら貴女一人でも十分じゃないの」
「それがその……鬼も一緒なんです。あと背中に柱を背負った女の人と、蛙の帽子を被った女の子が……」
「へぇ……」
「お嬢様」
「面白い……咲夜、中国」
「はい」
「は、はい!」
「迎え撃つわよ」
「わかりました」
「わ、わかりました!」
「咲夜と中国は柱を背負った女と蛙の帽子の相手をしなさい。どうせ雑魚よ、一瞬でカタをつけなさい」
「了解」
「了解です!」
「私は○○と、鬼の相手をするわ。
くっくっくっ……あの鬼め。どちらが本当に優れた種か、今度こそハッキリと分からせてあげるわ。
それと○○、貴方には地獄を見せてあげる。霊夢に手をかけた報いをその身に受けるが良いわ!」
「お嬢様、怖いです……」
「因縁の相手が一気に二人ですもの、当然よ」
「そうなんですかぁ……」
「そうなの。さ、貴女も気合入れなさい。足手まといにならないでよ?」
「はい、頑張ります!」
「宜しい。ではお嬢様……」
「ええ……出撃よ!!」
そして決戦の火蓋は落とされた。
紅魔館を攻めるは、一人の人間と三人の人外。
たった四人の侵入者。
誰がどう見ても、紅魔館の勝利は確実。
館の者達はそう信じて疑わなかった。
疑いようがなかった。
……だが。
彼女達は知らなかったのだ。
レミリアが雑魚だと罵った二人。
その二人が、高位の神だということを。
数時間後、紅魔館は壊滅的な打撃を受けることになる。
屈辱的な敗北を喫した紅魔館の主、レミリア・スカーレット。
彼女はこの後、丸三日間を掛け、『○○の素晴らしき腋講座』を受けさせられることとなるのだが……
そのことを、彼女とその従者達は知る由も無かった。
───────────
幻想郷に暖かな日差しが降り注ぐ。
全てを包み込むような柔らかな光。
それはまるで、新たに生まれる生命を祝福するかのよう。
轟と、嵐のように一際強い風が吹いた。
春一番。
春の訪れを告げる風。
始まりを意味する、旋風。
人々は新たな始まりを喜び、生活に一層の精を出す。
春とはそんな季節だ。
誰もが春の訪れを喜び、心を躍らせる。
そんな季節。
だというのに。
「はぁ……」
境内を掃除する私の気分は時化っていた。
まるで霧雨のように。
雲が心を覆っている。
今の天気とは正反対。
どんよりとした大きな雲が光を遮断し、心に影を作っている。
その理由は二つあった。
一つは、ある行事を逃したこと。
バレンタイン。
女性が想いを寄せる男性にチョコレートと共に、精一杯の愛を伝える行事。
女の子の一大イベントとも言えるその日を……
どういうわけか、私はすっかり忘れていたのだった。
まあ、忘れるに値する理由はあったのだが。
……って、別に誰かにあげるつもりじゃなかったのよ?
好きな相手なんていないし……まあ、気になるヤツなら居るけど。
いやそれも嘘っ! 冗談だから!
あんな変態のことなんて気にも留めてないわ!
ホントよ! ホントにどうでもいいの!
変態で馬鹿な男なんて、こっちからお断りよ!
……私、誰に言い訳してるのかしら。
「はぁ」
知らずと溜息が出た。
まあ、過ぎてしまったものを悔やんでも仕方が無い。
気持ちを切り替える。
実を言うと、そちらの方はまだ大した問題じゃない。
重大なのは、もう一つの方だった。
それは……
階段の方に視線を向ける。
今の時刻は、昼を少し過ぎた頃。
そろそろ、階段を上り終えたアイツが満面の笑みで。
私に飛び付いてくる。
筈なのだが……
階段からはそんな空気は感じられなかった。
苛立つ気持ちと、諦めにも似た気持ちが交互に浮上する。
いつもならこの時間帯に来る筈のアイツ。
ちょっと、いやかなりの変態で、大が付くくらい馬鹿な青年。
その彼は、今日も姿を見せない。
なんで来ないのよ。
心の中で愚痴った。
約二ヶ月前。
私はアイツと喧嘩をした。
いや、あれは喧嘩というより、一方的な暴力だろうか。
あの時、アイツは少女を求めていた。
私でも早苗でもない、別の少女。
伊吹萃香。
幻想郷で唯一人の鬼。
彼女を求めていたアイツに向けて、暴威ともいえる弾幕の嵐を叩き込んだ時の光景が思い出される。
後ろから渾身の弾幕を撃ち込まれて、夜空に飛んでいったアイツ。
……あの時は少し、やりすぎたかしら。
今更になって反省してみたが、悪いのはあっちの方なので良しとしておいた。
ともかく。
それから約二ヶ月、私はアイツと一切口を利かなかった。
アイツはブッ飛ばされた翌日も翌々日も、足繁く神社に通ってきたけど。
私は頑なに無視を決め込んだ。
代わりに、来る度にありったけの弾幕をお見舞いした。
今思うとかなり酷いことをしたと思う。
日を追うごとに怪我を増しながらも必死になって神社に訪れる彼の姿は、思い出すだけで胸が痛んだ。
でも、あの時はそれほどまでに腹が立っていたのだ。
怒り狂う自分を抑え切れなかったのだ。
一応手加減はしておいた……と、思う。
多分……きっと。
ま、まあ、それは置いときましょう。
早苗の方も同じようなことをしてたみたいだし、おあいこよおあいこ!
意味が違う?
五月蝿い、良いのよ別に。
悪いのはアイツなんだから。
……私、さっきから誰に言い訳してるのかしら。
と、とにかく。
それから二ヶ月の後、私はアイツと仲直りをした。
勿論、平謝りをするアイツを、私と早苗が許す形で。
もう怒っていないと言った時のアイツの顔はまだ覚えている。
なんというか、神を称えるような顔だった。
まあ、その後お約束の様に例の病気が始まったのでブッ飛ばしてやったのだけれども。
その次の日、アイツは夕方近くに息を切らせてやってきた。
アイツがこんな遅くにやってきたのは珍しいことだった。
理由を尋ねると、アイツは苦しそうな顔を笑顔に変えて。
『いや、二ヶ月も会えなかったから……その分を補給しようと思って』
そんなことを言ってきた。
突然の不意打ちに、不覚にも顔に熱が集まるのを実感した。
あの時感じた感情は多分、嬉しい、だったと思う。
会えなかったのはこちらも同じだったから。
二ヶ月。
言葉にすれば短く感じるが、体感するとなれば気が遠くなる程に長い時間。
その間、私の中に空白があったのは確かだった。
だから多分、あの時の私は嬉しかったんだと思う。
止まることなく紅く染まっていく頬。
アイツはそれをどう勘違いしたのか、いきなり抱きついてきた。
当然、腋に。
勿論ブッ飛ばした。
盛大に飛ばされた後、アイツはこう言った。
『明日も来るからな!』
眩しいくらいの笑顔で。
迷いも無くハッキリと。
確かにそう言った。
だというのに……
次の日、アイツは姿を見せなかった。
急な仕事が入ったのだろう。
何気なくそう思った。
けど。
その瞬間、私の心の底に何かが溜まったのが分かった。
次の日も、アイツは来なかった。
ポタリと、また何かが溜まる。
そしてその次の日も、そのまた次の日も。
アイツは来なかった。
そうして一週間が経った今日も。
アイツは姿を見せない。
ぼちゃん。
また何かが、容積を増やす。
得体の知れない何か。
それは日を追うごとに量を増して。
着実に、私の心に溜まっていった。
気が付けば辺りは紅く染まっていた。
煌々と紅く煌く夕陽に私は眼を細める。
もうそんな時間なのか。
あれからずっと境内の掃除を続けたままだったことに今更ながらに気付く。
結局、今日もアイツは来なかった。
紅く染まった空を見上げる。
そして私は思案した。
あの時。
二ヶ月前の、あの日。
萃香を襲っていた○○を目にした時。
間欠泉の様に噴き出した怒りと、もう一つの……あのいいようのない感情。
あれは一体何だったんだろう?
どろどろとした……けどそれだけじゃない、濁り。
その感情が湧いたのは、あの時で四度目だった。
それを最初に感じたのは、神社騒動で妖怪の山に殴り込みに行った時だった。
弾幕ごっこに敗れた早苗を襲う、アイツの姿を見た時。
その感情が、芽を出した。
気が付くと私はアイツに弾幕を放っていた。
二度目は私の神社。
アイツが大晦日をどちらの神社で過ごすかを決めるを早苗と勝負をして、負けた時。
落ち込む私を他所に、アイツとにこやかに話す早苗が放った一言が原因だった。
『いつも博麗神社から貰い損ねている分の御利益もプラスしちゃいますねっ!』
普段の私なら気にもしない台詞。
なのに、あの時はその言葉が凄く痛くて。
何故か、涙が止まらなかった。
三度目も私の神社。
大喧嘩をする少し前、お茶の間でアイツに甘える萃香を見た時。
突如として現れたその感情は、私の心を一瞬で支配した。
気付けば、私は湯呑みを握り潰していた。
あれは何なのだろう?
考えても考えても、答えは靄々としたものに隠されて、決して明かされない。
あれは一体、何なのだろう?
その得体の知れない感情は現れる度に大きくなって。
私の心を、じわじわと侵食していった。
それはまるで、私の心を糧にして成長するかのように。
不意にアイツの言った言葉が思い出された。
甘える萃香を眼にし、その感情に侵されていた私にアイツが言った言葉。
『お前さん、萃香が羨ましかったんだろ?』
したり顔で笑うアイツの顔が浮かぶ。
馬鹿馬鹿しい。
私は否定する。
なんで私が萃香を羨ましがらきゃいけないのよ。
ホント馬鹿じゃない?
私が萃香を羨む?
そんなこと、あるわけないじゃない。
けれど、その後自分がした行動は……
離れようとしたアイツの袖を掴んだ自分。
その後に訪れた、温かな抱擁感と。
揺り籠のような安らぎ。
ハッとして、その光景を消し去るように首を振った。
覚えてないわ。
そして私は過去を否定した。
あれは……そう、一種の気の迷いよ。
そう、気の迷い。
あの時の自分は、きっとどうかしていたのだ。
だから、ちっともおかしくない。
去年の暮れにあったことだって、気の迷いだ。
全力で過去の失態を否定する。
眼に映る夕陽がとても眩しかった。
馬鹿なこと考えちゃったわね……
無駄なことに時間を使ったことに後悔する。
そして視線を空から外し、階段に向けた。
鳥居の奥からは、誰も訪れる気配は無い。
今日はもう来ないだろう。
そう判断した私は、部屋に戻ろうと踵を返した。
その時だった。
「ん?」
唐突に、後ろから人の気配を感じた。
○○?
やっと来たのかしら。
久しぶりの来訪に、ほんの少し、気持ちが昂ぶった。
心臓が音を立てて脈動する。
けれどそれを悟られないよう、表面上はいつもどおり冷静に。
来訪をなんとも思っていないかのように振り向いた。
其処には。
○○ではなく……
「おっす霊夢!」
黒白の魔女が、居た。
箒を持った手とは逆の手を挙げ、こちらに声を掛ける少女。
顔には人懐っこい笑みを浮かべている。
それは夕陽との相乗効果で、とても眩しかった。
「魔理沙?」
予想とは違う人物の登場に、私は若干肩を落とす。
落とした瞬間、はたと気付いた。
なんでがっかりしてるのよ!?
驚きは自分に。
○○じゃなかったことが、そんなに……
巡る思考。
そんなに、落ち込むこと……なの?
動揺する精神。
疑問を裏付けるように、昂ぶっていた感情は徐々に静かになっていった。
「ああ、私だけど……どうした? なんか問題あったか?」
魔理沙は頭にハテナマークを浮かべながらこちらを見やる。
悟られてはいけない。
何故かそう思った私は、急いで思考を中断させた。
できるだけいつもどおりに言葉を返す。
「別に? なんの問題も無いわ」
「そうか、なら良かったぜ」
「こんな夕方にどうしたの?」
「いや、今紅魔館に寄った帰りでな? 近くを通ったから晩飯でも御馳走になろうかと思って……」
にしし、と彼女は明け透けも無くそう告げる。
その様子にホッとした。
どうやら気付かれていないようだ。
危ないところだった。
彼女に悟られたら、何を言われるか分かったもんじゃない。
胸を撫で下ろす。
この思考さえ不自然ということに、今の私は気付いていなかった。
「全く、材料もタダじゃないんだからね?」
「まあまあ、この借りは気が向いたら返すぜ」
渋るように言う私に、魔理沙は笑う。
「はいはい、じゃあ今から作りますか」
「おう、今夜の献立は何だ?」
「今夜は……そうね、寒いから鍋にしましょうか?」
「うっひょー! 鍋とはまた豪勢だな! なんか良いことでもあったのか?」
言葉に、思考が止まった。
良いこと?
また、どろりとした何かが。
良いことなんて……
這い上がり、心を覆う。
良いことなんて、一つも……
「霊夢?」
「え、あ、なに魔理沙?」
様子を伺う声に、驚いて返事を返す。
「いや、なにって……今日の霊夢、何か変だぞ?」
心配そうな顔。
いけないいけない、しっかりしなきゃ。
大急ぎで体面を整える。
「別にこれといって良いことなんて無いわ。寒いからなんとなく、よ」
「ならいいんだけど……」
魔理沙は納得行かない顔をする。
こちらの様子から何かを感じ取ったのだろう。
全く、変なところで勘が鋭いんだから……
「さ、早く準備するわよ。アンタも手伝いなさい、じゃないと食べさせてあげないわよ?」
考えを逸らすためにそう言って、歩き出す。
「へいへ~い」
魔理沙もそれに習って歩き出した。
これで一安心。
そう思った矢先だった。
「そういえば、今日○○を見たぜ」
そんな言葉が耳に届いたのは。
突如魔理沙の口から現れたアイツの名前に、思考は急停止する。
鼓動が早まるのが分かった。
魔理沙の方を振り返る。
○○を?
いつ?
何処で?
止め処なく溢れる疑問。
けれどそれらは、言葉にはならなかった。
「……え?」
震える喉から代わりに出たのは、その一言だけ。
心臓の早鐘は加速度的に速度を上げている。
「ど……」
何処で?
再度試みたが、最後まで続かない。
何故。
何故私の声は、こんなにも震えているのだろう?
まるで聞くことを拒むかのようだ。
聞いてはいけない。
頭の隅から、そんな言葉が聞こえた。
彼女はこちらの変化に気付かずに。
未完成の言葉の意味を理解したのかしていないのか分からぬまま……
「湖の上を飛んでた時にチラリと見かけただけだから、ハッキリそうだとは言えないんだが……
確か、萃香と居たな~。なんか二人共、やけに楽しそうだったな」
答えた瞬間。
頭の中で何かが壊れる音が、聴こえた。
彼女の口からでた言葉の意味を、麻痺した脳で咀嚼する。
萃香と居た。
魔理沙は確かにそう言った。
なんで?
なんで萃香と居るの?
私の所には一度も来ないくせに。
楽しそうだった。
どうして?
どうして萃香と楽しそうにしているの?
私はこんなに……
ぎしりと。
胸の奥が悲鳴を上げるように軋んだ。
そして這い上がる、二つの感情。
疑惑と……これは悲しみだろうか?
それらが私の心をじわじわと蝕み始める。
何故悲しいの?
答えは見つからなかった。
「只の人間の癖に鬼と親交があるとは……○○もやるねえ」
何も知らない魔理沙は言葉を続ける。
無知な言葉が、棘となって心に突き刺さる。
もういい。
「でも良い感じの雰囲気だったな~……もしかして、アイツ等そーゆう関係とか?」
ずぶりと。
無自覚の槍が、深々と突き刺さった。
もういいから。
心の中で叫んでも、それは彼女には決して届かない。
もうやめて。
私は魔理沙に気付かれぬよう、俯いて。
小さく、唇を噛んだ。
いつの間にか箒を持つ手は小刻みに震えていた。
お願いだから。
響く心の声。
その声は無慈悲にも。
唐突に現れた更なる悲報によって……
残酷に掻き消された。
「○○なら私も見たわよ?」
突如出現した新たな声。
私は苦痛を表に出さぬよう、精一杯の努力をしながら顔を上げる。
その声の主は、自分の良く知っている人物だった。
「こんばんは、霊夢」
目の前には、上品に礼をする少女。
レミリア・スカーレット。
紅魔館の主。
彼女がこんな時間に此処を訪れることは珍しいことだ。
けれど、今はそんなことに頭を使っている余裕は私には無かった。
頭の中では、まだレミリアの言った言葉が響いている。
「レミリアがこんな時間に神社に来るなんて、珍しいこともあるもんだな」
「それはお互い様よ、魔理沙。貴女こそ、珍しいじゃない?」
「そうか? 普通だぜ?」
「なにが普通なんだか……」
「まあ気にするな。ところで、お前も○○を見たのか?」
「ええ、昨日会ったわ」
会った?
一体何処で?
急かす思いで二人の話に耳を傾ける。
「へえ……何処で?」
「散歩中に、森の中で」
「森の中? また珍しい処であったな」
「全くよ。逃げようと思ったんだけど……」
一端区切って、レミリアは顔を曇らせる。
苦虫を噛み潰した様に顔を顰めるレミリアを見て、魔理沙は続きを促せた。
「逃げるって……お前が?」
「……ええ」
「なんでまた?」
「五月蝿いわね、貴女には関係無いでしょうに」
「ふ~ん……まあ良いや。でも会ったってことは、結局捕まったってことか?」
「ええ、目ざとく見つけられたわ……」
「ほほう、それで?」
「一時間」
「一時間?」
「説教の時間よ」
「説教? なんの?」
「関係無いわ」
「またかよ」
二度目の黙秘に魔理沙は呆れ顔で返した。
関係無い。
確かに、私には関係無い。
私が知りたいのはそんなことじゃない。
そんなことはどうでもいい。
どうでもいいから、早く……
急かすような気持ちは、更に強くなる。
『本当に聞いていいの?』
囁くような声を、私は無視した。
「五月蝿いわね。で、その後開放されたんだけど……釘を刺されたわ」
「ほほう、なんて?」
「今から守矢神社に行くから邪魔をするなよ、って」
ビクンと。
身体が跳ねた。
耳元で反響する言霊。
やがてそれは形を持って脳裏に鮮明に映し出される。
守矢神社。
その場所が導き出す答えはつまり。
早苗の……とこ、ろ?
口元が引き攣った。
東風谷早苗。
アイツが良く通っている、もう一つの神社に居る巫女。
アイツが好きな、少女。
混乱は極みに達する。
神社に来ないアイツ。
萃香と居たアイツ。
早苗に会いに行ったアイツ。
全てを繋げた瞬間。
ぱきん。
大切な何かが、割れた。
そして私の心身は急速に熱を失っていった。
「守矢神社? なんでまたそんな処に?」
「あら、貴女知らないの? ○○って、守矢の巫女に御執心なのよ?」
「うっそ!? マジで!?」
「マジもマジ、大マジよ。まあ、随分と特殊な感情なんだけど……」
他愛も無い話を二人は続けている。
けれど私にはそれが良く聞こえなかった。
既に私の心は、氷のように熱を失くしていたから。
「ん? そこでなんで霊夢を見るんだ?」
「へっ!? い、いや深い意味は無いのよ?」
「怪しいぜ」
「うぅ……あ、そういえば」
「なんだ?」
「○○のヤツ、この間紅魔館に来てたらしいわ」
「紅魔館に?」
「ええ。詳しいことは知らないけど、厨房に用があったみたい……」
「厨房にねえ……飯でもたかりに来たとか?」
「さあ? 何か作って、持って帰ったとは聞いたけど……」
「晩飯でも作りに来たのかね? 私ならそのまま食べて帰るけど……」
「貴女は例外も例外よ。一緒にしちゃ、他の人間が可哀想ね」
「言ってくれるじゃないか……っと。あ~、私も思い出したぜ」
「何を?」
「いやな? この間、アリスんとこに遊びに行ったら断られたんだよ。
で、理由を問いただしたらなんと……」
「なんと?」
「○○に付き合ってて寝てないの、ときたもんだ!」
「うわ~、それって……」
「怪しいよな?」
「怪しいわね。一体、二人で何をしてたのかしら?」
「さあな~……粘っても、そこだけは教えてくれないんだよ。
なんか、○○との約束だから無理、とかなんとか……」
「それは更に怪しいわね~……」
「だろだろ?」
楽しそうに話をする二人。
その会話の中で、拾った言葉を分析する。
凍った心でも言葉は届くのか。
自嘲気味に笑いつつ、言葉の意味をのろのろと理解する。
理解した意味はとても冷徹で、冷酷だった。
そうなんだ。
無自覚な悪意。
アイツは、早苗と萃香だけじゃなくて。
無邪気な刃。
他にも、色んな人と会ってるんだ。
無遠慮な痛み。
色んな人に……親しまれてるんだ。
無知という名の暴力。
けれど……
そして残酷な。
私は其処に、含まれていない。
一つの事実。
それらが私の心を粉々に打ち砕く。
それは容赦無く、無慈悲に。
悲鳴の声は瓦礫の音に掻き消され。
私の中で変わらずに残ったのは、仮面の様に変わらない顔だけだった。
「いや~。まさかアリスにそんなヤツが出来るとはなぁ……」
「まさかあの人形遣いがねぇ……奥手だと思ってたけど、驚きだわ」
「だよな……ん? そーいや○○って、早苗に随分と入れ込んでるって、お前さっき言ってなかったか?」
「ええ、そう言ったわ」
「つまりそれって、二股ってことじゃないのか?」
「いいえ、二股じゃないわよ?」
二人は会話に華を咲かせている。
何処にでもあるような内容。
けれど、それは私にとって、無数の牙に見えた。
牙が私の心身の残骸を無造作に喰い漁る。
貪る様を人事のように見つめながら、ふと思う。
これは本当に自分なのだろうか?
疑問に、答えは返ってこなかった。
甦るアイツの言葉。
『明日も来るからな!』
あの時、確かに言った言葉。
その言葉に対し私は……
嘘吐き。
搾り出す様に、そう吐き捨てた。
「なんでだよ、早苗のことも好きなんだろ? だったら……」
「正確には四股になるわ」
「よっ!? ちょ、ちょっと待て! 四股って……他に誰が居るっていうんだ?」
「あの鬼も、○○に御執心みたいよ?」
「鬼って……萃香のことか?」
「それ以外に居る?」
「嘘だろ……何処まで節操無しなんだアイツは」
「まあ、アイツは特殊だから……」
「特殊っていっても限度ってモンがあるだろ……」
「同感ね。全く、霊夢もあんなヤツの何処が良いのかしら……少しだけ理解しかねるわ」
「こっちは少しどころじゃないんだが……って、なにい!? もしかして、霊夢もなのか!?」
「貴女、それも知らなかったの?」
「知らないもなにも……初耳だぜ。まさか霊夢と○○がそんな仲だったとは……」
魔理沙が予想外といった声を上げる。
『大丈夫よ、もう終わりだから』
誰かが答えた。
そうね、もう……
「今日の魔理沙は、知らないことが多いわね」
「正直言って、今日は驚きの連続だぜ。まさか○○が女たらしだったとはなぁ……」
「女たらしというよりは、只の変態ね」
「それ、悪くなってないか?」
「良いのよ別に、本当のことなんだから」
「なんだか良く分からんが……」
「は~あ。霊夢もあんな無節操なヤツなんて放って置いて、私と愛し合いましょうよ~…………っ!?」
「ん? どうしたレミリア? 霊夢がどうかし…………なっ!?」
突然、会話が途切れた。
静寂が場を支配する。
どうしたのだろう。
不意に生まれた静寂が気になった私は、切れかけの意識を視界に集中させる。
意識が途切れ掛けているためか、目の前は滲んでいた。
二人は私の方を見つめている。
何故か二人の顔には、驚愕と困惑が貼り付いていた。
「れ、霊夢……?」
動揺を詰め込んだ声でレミリアが尋ねる。
「なに?」
辛うじて声帯は機能してくれた。
いつもと同じ抑揚の声が、意味を持った音となって口から発せられる。
だが、それも彼女達の動揺を促す結果にしかならなかった。
「何って……急にどうしたんだよ?」
今度の声は魔理沙から。
彼女は不安そうな声で尋ねた。
一体何のことだろう?
良く分からない。
「別に、どうもしないけど?」
同じ抑揚の声で返す。
返事に、魔理沙は吃驚したようだった。
何をそんなに驚いているんだろう。
「まさか、お前……」
不思議に思っている私に、魔理沙は言いにくそうに……けれどハッキリとした声で。
「自分が泣いていることに、気付いてないのか?」
そう、言った。
「え?」
疑問の声は自分の口から。
泣いている?
私が?
そんな筈は無い。
ズタボロになった心身の中、唯一まともに残っている仮面。
いつもと変わらない無表情。
その筈だ。
事実を確かめるために、私はゆっくりと頬に手を当てる。
温かな液体が指先を伝った。
熱い。
涙。
なんで?
なんで私は泣いているんだろう?
不思議に思いつつ、何度も目元を擦る。
擦っても擦っても。
その度に涙は溢れ出して、頬を濡らす。
わからない。
何故こんなにも涙が出るのか。
わからない。
何故こんなにも胸が苦しいのか。
わからない。
何故こんなにも寂しいのか。
え?
突然飛び出した予期せぬ言葉。
その言葉に私は驚愕した。
寂しい?
先程自分の中から現れた、確かな想い。
それを私は……
そんな筈は無い。
否定した。
そうだ、そんな筈は無い。
寂しいなんて有り得ない。
ずっと前から、私はこの神社に一人で生きてきた。
生まれてから、今までずっと一人で。
けれど、それを寂しいとは思ったことなど一度も無かった。
だって、それが当たり前だったから。
博麗の巫女。
人外を討ち、人外から恐れられ、そして人からも恐れられる。
誰に対しても平等で、誰に対しても無関心。
誰にも無情で、誰にも不干渉。
全てにおいて中立の存在。
それが私。
それが博麗。
だから私は一人で生きていく。
今までも、そしてこれからも。
たった一人で。
生きていける……筈だったのに。
ああそうか。
そんな私の前に。
アイツが現れたんだった。
只の人間の癖に、暇を見付けては神社に来る変わり者。
特殊な性癖を持つド変態で。
どうしようもない程の馬鹿。
呆れるくらいの愚か者。
でも……
本当はとても優しくて、とても温かな人。
素直じゃない私を優しく包み込んでくれる人。
博麗の巫女としてでなく、一人の少女として私を見てくれる……唯一人の存在。
いつも見ていたアイツの笑顔。
それが今は……
何かが胸に去来する。
どろどろとした……けれど、それだけではない想い。
ああ、私は……
それが何なのか、私はようやく理解した。
私は……
早苗を襲うアイツを目撃した時に生まれた感情。
早苗と楽しげに語らうアイツを見た時に感じた気持ち。
アイツに甘える萃香に犯された欲望。
萃香を襲うアイツを眼にした時の情操。
二ヶ月の空白と、一週間の今。
誰も居ない境内と、訪れることの無い待ち人。
そうか、そうだったんだ。
それらが導き出す、一つの感情。
寂しい。
そうだ、私は寂しかったんだ。
アイツが居ないことが。
アイツの笑顔を見れないことが。
アイツが私を見てくれないことが
アイツの温もりを感じられないことが。
どうしようもなく。
どうしようもなく、寂しかったんだ。
その事実を認識した時……
許容は限界に達した。
「うぁ……」
声が漏れる。
決壊は喉から出たそれを引き金にして。
「っく、うぇ……ぁぁっ」
溜まった全てが溢れ出した。
ごちゃまぜになった感情が、津波のように押し寄せる。
理解した今、もう止めることは出来なかった。
「れ、霊夢っ!?」
「なんだなんだ!?」
二人の驚く声が聞こえる。
けれどそれに返す言葉は思い浮かばず。
「うぇっ……ひっ、く…………ひっ、うぁぁっ」
ただ鳴咽が喉から漏れ出す。
止め処なく溢れる涙は、頬を伝って次々と地面に落下する。
大地に落ちた雫達は、様々な形の染みを作っていった。
「……ひっ、ぐ……うぁ、っ…………ぅぇぇっ」
止まらない感情の波。
それらは一つとなって、私の心を攫っていく。
そんな中、目蓋に浮かぶアイツの笑顔。
そして紡がれる、一つの言葉。
「ちょ……どうするのよ魔理沙!?」
「どうするもこうするも……私に聞くなっ!」
喧騒の中でもハッキリと響く、確かな想い。
それは……
「……ぃっ……」
「え?」
「ん?」
それは。
「……ったぃ……○○、にッ…………ぁい、たぃ……っ!」
会いたい。
○○に会いたい。
アイツの笑顔を見たい。
アイツの温もりを感じたい。
アイツの傍に、居たい。
心が、その想いで弾けそうだった。
「霊夢……」
「お前……」
戸惑うような、微かに理解したような声。
「……ぅ、ぅえっ…………ぁぃ……たぃ、よ…………っ!」
想いは消えることなく。
叫びは夜のカーテンが降り始めた空に。
哀しく、響いた。
障子から暖かな陽光を瞼に受けて、私は目を覚ました。
ゆっくりと上体を起き上がらせ、障子から透ける日差しを見る。
「朝……か」
そこでやっと、朝だということを私の脳は理解した。
寝間着のまま裏の井戸に向かう。
汲んだ水を桶に溜め、それを勢い良く頭から被った。
春だといってもまだ初春。
水は凍えるように冷たかった。
しかし、その冷たさを以ってしても、私の頭には靄が掛かったままだった。
依然としてはっきりとしない頭で、昨日の出来事を思い返す。
あの後。
泣きじゃくっている私を、魔理沙とレミリアが必死になって慰めてくれた。
二人の言葉を記憶から引き起こす。
『そんなに気にするなって。アイツのことだ、そのうち、ひょっこり顔を出すさ!』
『そ、そうよ! アイツが霊夢に会いに来ないワケないじゃない!』
おろおろとしながら、私を慰める二人の顔。
余りの必死さに微笑ましくなる。
そこでふと気付いた。
もしかして私は、とんでもない醜態を二人に晒したのではないだろうかと。
昨日の光景。
人目を憚らず、子供のように泣きじゃくる自分。
涙声で、○○会いたいと何度も言った自分。
「…………」
今更になって、とてつもない恥ずかしさが襲ってきた。
後悔と自己の脆弱さに引き篭もりそう。
出来ることなら、今すぐにでも記憶を抹消したかった。
けれど。
もう忘れることなど出来ない。
自分の気持ちに気付いてしまったから。
明るみに出た感情。
寂しい。
泣きながら言った言葉。
会いたい。
あの時言った言葉と、感じた想いは……きっと私の本心の筈だから。
水滴が前髪を伝って落ちていく。
それを意に介さず、私は空を見上げた。
雲一つ無い、真っ青な空。
あるのは眩しいくらいに明るい太陽のみ。
まるで今の私の心を移したかのよう。
頭の靄は、いつの間にか綺麗に消え去っていた。
そうだ。
陽の光を全身に受ける。
会いに来ないのなら……
光が、私の身体に力を注いでゆく。
会いに行こう。
決意は固まった。
そうと決まれば話は早い。
私は視線を空から下ろして、神社に歩みを進める。
脳裏に浮かぶはアイツの顔。
こんな時間に行っても大丈夫かしら?
一寸思ったが、時間を遅らせるつもりは毛頭無かった。
歩く速度は、次第に早足に。
早く、早く。
心が急かしてくる。
そして裏手の戸に手を掛けたその時。
ちゃりーん。
小気味良い金属音が神社に響き渡った。
続いて、がらがらと鐘を鳴らす音。
次に、二拍。
そして、静寂が辺りに広がった。
……参拝客?
珍しいこともあるものだ。
この神社に御参り来る人が居るなんて。
参拝してくれことに対し、若干の感謝をする。
けれど……
今はそんなことに気を回している暇は無い。
そして再び戸に手を掛けようとして……
私は状況を理解した。
理解すると同時に、本堂目掛けて走り出す。
なに間抜けなことを思ってるのよ私は!
叱責は自分に。
ウチの神社に参拝客なんて来る筈ないじゃない!
間の抜けた思考を叱咤する。
そうだ、この神社に参拝客が訪れることは無い。
それは自分が一番理解している。
来るんだったら、今頃生活は困窮していない。
ウチの神社に参拝客は来ない。
それは悲しいけれど事実だった。
そう……
唯一つの例外を除いては。
果たして其処に居たのは。
神社の本堂。
賽銭箱の前。
其処には神妙な顔で眼を瞑って、手を合わせている……
アイツが、居た。
「っ!!」
息が詰まった。
鼓動が早鐘を打ち始める。
体中の熱が、顔面に集まっていくのを実感する。
歓喜が、全身を廻った。
来て……くれたんだ。
その事実が嬉しくて、彼に歩み寄ろうとした。
……が。
意に反して、体は石のように動かなかった。
ど、どうして?
戸惑いながらも、懸命に体を動かそうするけれど。
どうして動いてくれないの?
鉛の様に重くなった私の体は、ぴくりとも動いてくれなかった。
どうして……
戸惑いに答えるように、声が聞こえた。
『彼は本当に貴女に会いに来たのかしら?』
あ……
闇が、再び私の心を覆った。
もしかしたら、アイツは単純に御参りに来ただけなのかもしれない。
そんな有り得ない不安が私を襲う。
でもそんなこと……
私は声に反論する。
『本当に? 本当にそうじゃないと言い切れる?』
あれ以来、一度も此処を訪ねていない○○。
その間、色んな少女達と会った○○。
可能性が無いとは、言い切れなかった。
今更になって、此処を訪れる理由なんてあるのだろうか?
わからない。
私には、わからない。
底無し沼に落ちていくような感覚が私を襲う。
それでも。
ずぶずぶと沈む体。
それでも、私はアイツに……
沼の中で私は足掻く。
アイツに会いたいのよ。
声を聞きたいの。
笑顔を見たいの。
アイツの温もりを、感じたいのよ。
言いながら必死に足掻いた。
けれど……
『そう。でも……』
私の叫びに、声は嫌らしそうに一端区切って。
『まだ彼が貴女を求めていると……貴女、自信を持って言える?』
容赦の無い言葉を浴びせ掛けてきた。
その問い掛けに、私は放心した。
それは……
先刻までの輝きは形を潜め。
わからない。
代わりに生まれた真っ黒な泥が、私に執拗に絡み付き、思考の自由を奪う。
私はまだ……アイツに求められているのだろうか?
声が私の心を闇に沈めていく。
わからない。
もしかしたらもう……
一面に広がるドス黒い闇。
体を侵食する、負。
そんな暗黒を掃ったのは。
「会いたかったぜ腋巫女ーーーーーーーーーーーっ!!」
待ち望んでいた彼の声だった。
いつの間にこちらに来たのか。
気が付くと彼は、私の目の前に居た。
両腕で私の腰回りを抱き締める。
あ……
抱き締められた瞬間。
ドクンと、心臓が一際激しく脈打った。
ああ……
腕から伝わってくる彼の温もりに渇いた心が満たされてゆく。
干乾びた私が潤っていく。
彼はこちらのそんな様子に全く気付かないまま。
いつもどおり、私の腋に頬を摺り寄せた。
「ほへぇ~~~……」
程無くして漏れ出る、だらしのない声。
満足感たっぷりの幸せそうな顔。
久しぶりに会った彼は、相変わらずの変態っぷりだった。
その顔を私は見つめた。
○○だ。
堰を切ったように溢れ出す、温かな感情。
やっと……
熱い、想い。
やっと会えた……
それらが全身を駆け巡る。
嬉しさの余り、抱き締めたい衝動に駆られた。
従順に従い、彼の背中に腕を回そうとして……
何故か上空に振り上げた。
そしてそのまま勢いをつけ。
肘先を彼の脳天目掛けて……
叩き付けた。
「べぶあっ!?」
潰れた蛙のような声。
その声に気付いた時、彼は地面にへばり付いていた。
……あれ?
驚きは自分に対して。
なんでこんなことに?
彼は不規則にぴくぴくと、小刻みに痙攣している。
私はその様を呆然としながら、眺めていた。
やがて彼は顔を上げた。
「いって~……」
どくどくと流れ出る鼻血。
彼の顔は、鼻から下が真っ赤に染まっていた。
「あ~……」
呻きながら首筋をトントンと叩く。
暫くして鼻血が止まったことを実感した彼は、こちらを見て……
「久しぶりだな霊夢!」
ニカッと。
血塗れの顔で笑った。
やっぱり。
目の前の彼は、ちっとも変わっていなかった。
「相変わらず容赦無えなあ!」
彼は笑いながら言う。
その顔は自分の求めた笑顔過ぎて。
無性に、泣きたくなった。
アイツだ。
会いたかったアイツだ。
さっきまで私を覆いつくそうとしていた闇は。
跡形も無く、消え去っていた。
「ん? お~い霊夢~?」
黙ったままの自分を不思議に思ったのか、彼はこちらを覗き込む。
いけない。
何か喋らないと……
でも何を?
言葉を捜す。
会いたかった?
寂しかった?
どうして来てくれなかったの?
言いたい言葉は数知れず。
かしゃかしゃと頭の中で最良の答えを検索する。
そして出てきた言葉は……
「こんな朝早くに、ウチに何の用?」
そんな素っ気無い言葉だった。
違う。
こんなことを言いたいんじゃない。
必死に喚く。
けれど言葉は無情で。
「御参りに来たの? なら一応感謝しておくわ」
心とは裏腹に、冷たい言葉が発せられる。
馬鹿。
意地っ張り。
どうして自分はこんなにも素直じゃないのだろう?
さっきとは別の意味で泣きそうになった。
後悔の波が押し寄せる。
そんな私に向けて、彼はニヤリと笑った。
「ふっふっふ……甘いな霊夢!
そんなモン、おまけもおまけ! 俺の目的はいつも一つ! それは……」
彼は高らかにそう叫びながら。
「お前に会うことだああああああああっ!!」
ビシッという効果音が付きそうな程、強く。
私を指差した。
阿呆みたいな啖呵。
普段の私なら呆れるところ、なのだが。
今日の私は違った。
奥底に芽吹く。
そうなんだ。
私に会いに来てくれたんだ。
この春の様に温かな花。
嬉しい。
本当に嬉しい。
この気持ちを貴方に伝えたい。
会いに来てくれて本当に嬉しいのって言いたい。
そう想っているのに……
「……そう」
やっぱり、そんな言葉しか返せなかった。
ホントにもう、私は筋金入りだ。
なんで。
なんで伝えられないのよ!?
自分の不甲斐無さに憤る。
素直じゃない自分。
嘘吐きな自分。
そんな自分とは対照的に……
「おうよ!」
彼は親指を立ててこちらに見せ付ける。
彼は自分に正直だ。
愚直な程に。
その正直さが、とても羨ましかった。
どうしてコイツはこんなに自分の望みに忠実なんだろう?
どうして私はコイツみたいになれないんだろう?
急に自分が嫌になった。
不意に、この場から逃げ出したい衝動に駆られる。
……その時だった。
私の体に、ぶるりと身震いが起きた。
そして突然襲い掛かる、冷気。
余りの寒気に身を固くする。
肌を見ると、少し青白くなっていた。
足の先端部分に至っては紫に近い。
春と言っても、まだ初春。
早朝の冷え込みは、まだ冬のそれに近い。
流石に寝間着のままじゃキツイわね。
……丁度良い。
「ちょっと待ってなさい。何か羽織るものを取ってくるわ」
私は彼にそう告げて、逃げるように境内に向かう。
「お? ……ちょっと待てい」
そんな私を彼は止めた。
なんで、止めるのよ。
気持ちを整理する絶好の機会だったのに。
制止の声を不満に思いつつ、彼の方を向く。
彼はその場にしゃがみ込んで、持参した袋の中を探っていた。
「え~と…………お、あったあった」
ほどなくして御目当ての品が見つかったのか、彼は腰を上げる。
あれは……なにかしら?
紅い、布のような何か。
彼はそれを胸に抱えて、こちらに近付く。
顔には何か企む様な笑顔を携えて。
そしてお互いの体がくっつくまで、あと一歩というところで止まり……
手に持ったそれを。
ふわりと。
私の首に巻いた。
「……え?」
突然首回りに発生した柔らかな感触に、私は戸惑った。
巻かれたそれを触る。
ふかふかとした生地の、紅と白の長い布。
これは……マフラー?
「へっへ~…………巻き心地はどうだ?」
彼はしてやったりという顔でこちらを伺っている。
私の首には、ふかふかのマフラー。
それは少々雑な造りで。
所々解れ掛けていて、少し不恰好。
でも。
それはとても温かくて。
まるで彼に抱かれているみたいだった。
「その顔を見ると良いみたいだな。良かった良かった、頑張って編んだ甲斐もあったってモンだ! あとは……」
彼は破顔した後、再びごそごそと袋を漁りだす。
「霊夢、手ぇ出してくれるか?」
言われるまま掌を上に向ける。
彼は其処に、可愛らしく装飾された小さな袋を置いた。
「開けてみ?」
素直に袋を開ける。
中には雪のように真っ白なマシュマロが詰まっていた。
「これ……」
「俺の手作りだ! さ、食べてみてくれい!」
「あ、うん……」
促されるまま、一つ手に取って口に放り込む。
口の中に入ったマシュマロは、瞬く間に溶けていく。
滲み出た糖分が、舌を軽く刺激した。
甘い。
羊羹やお饅頭のような、強烈な砂糖の甘さではなく。
なんというか、優しい甘さだった。
「味の方は、どうよ?」
少し不安そうに、彼は問う。
「……美味しい」
正直にそう答えた。
「そっか~…………へへっ!」
不安が晴れた彼は、嬉しそうに鼻を擦る。
その手を見て気付く。
彼の手は、火傷でボロボロだった。
なんで……
顔も良く見ると、目元に大きなくまが出来ている。
なんでそんなに……
『今日は何の日かしら?』
脳裏に響く声。
あ……
瞬間。
私は全てを悟った。
アリスの家に行った○○。
不恰好なマフラー。
目元の大きなくま。
紅魔館に厨房を借りた理由。
マシュマロ。
火傷が痛々しい彼の両手。
その全てが今、目の前にある。
そうか。
今日は……
気が付けば、彼の手を握り締めていた。
「うおっ! ど、どうした霊夢?」
私の突然の行動に焦る彼。
答えを返さずに、私は彼の手を撫でる。
傷に塗れた無骨な、けれど温かな手。
「あ、これか? いや、慣れないことをしたからさ~……見た目だけで、実は大したことないんだぞ?」
心配させないように。
笑いながらバレバレの嘘を言う。
なんて馬鹿なんだろう。
なんて純粋なんだろう。
なんて……愛おしいのだろう。
もう止まらなかった。
握っていた手を離し、彼の胸元に飛び込む。
そして両腕に、ありったけの力と想いを込めて。
彼の体を抱き締めた。
伝わる温もりと、彼の重み。
「おわっ」
軽い動揺の声。
それを無視して私は胸元に頬を摺り寄せる。
彼の匂いが、した。
少し汗臭い、けれど落ち着く匂い。
私の全てを包み込んでくれる、彼の匂い。
『 』な人の、匂い。
体が弛緩して、今にも膝が折れそうだ。
思う間も無く、崩れ落ちそうになる体。
その体を彼は抱き締めてくれた。
強く激しく、けれど繊細に優しく。
私の体を抱き締める。
「ぁ……」
息が漏れた。
彼の両腕が、私の全身を温かく包み込む。
それは、ただただ温かくて……
だからこそ、自分を呪いたくなった。
自責の念が私を襲う。
私は最低だ。
呪いの言葉を自分自身に向けて吐き捨てる。
私は疑ってばかりで……
彼のことを、これっぽっちも信じていなかった。
最低だ。
最低も最低、下の下だ。
ごめん。
言葉は声にはならず。
ごめんなさい。
ただ、胸の中で反響した。
後悔と罪悪感で、体が震える。
ごめん、なさい。
泣きそうになる感情をがむしゃらになって抑えつける。
そんな中届く……
「なあ、霊夢」
優しい彼の声。
「……何よ」
ぶっきらぼうに返してしまう。
止めてよ。
そんな風に優しい声、出さないでよ。
私なんて……
暗く沈む思考。
けれど彼は、こちらの想いなどお構い無しに。
「来年のバレンタインは、期待してるからな!」
そんな、わけのわからないことを言ってきた。
「……え?」
予期せぬ発言に、私は彼を見上げる。
「いやさ、今年は色々あって貰えなかっただろ?」
困った様な顔で彼は言う。
色々……そうね、色々あってあげれなかったわ。
あげたかったのよ?
そう、貴方に本当はあげたかった。
でも、あげなくて正解だったのかもしないわね。
今の私には、貴方にあげる資格なんて……
影を振り払うかの様に、彼は困った顔を太陽に変える。
「だから来年は絶対貰う! 楽しみにしてるからな!」
そして気合十分に言い放った。
余りの勢いに、私は一瞬呆気に取られた。
一瞬の呆然の後で思う。
やっぱりコイツは馬鹿だ。
こんな最低な自分に、まだそんな言葉が吐けるのだから。
アンタ、わかってんの?
私は最低な女なのよ?
私はアンタのことを信じられなかったのよ?
信じようともしなかったのよ?
それなのに、なんでそんなこと言えるの?
なんで……
もう、限界だった。
「……っ」
崩れる顔。
瞳に溜まりだす、涙。
喜び。
懺悔。
涙。
それら全てを隠すように彼の胸元に顔を埋めた。
「馬鹿……」
胸元で呟く。
「馬鹿で結構。お前から貰えるんなら、こちとら馬鹿にでも阿呆にでもなる覚悟だぜ!」
彼は迷い無く、そう啖呵を切った。
馬鹿。
馬鹿、ばか、バカ。
次々に生まれる、罵声の言葉。
しかしそれらは音には成らず、内に溜まる。
ホント馬鹿。
でも、一番の馬鹿は……
私だった。
素直じゃない上に、勝手な勘違い。
こんなにも自分を想ってくれるコイツを疑った私。
本当に、本当に、愚か者だ。
出来ることなら、今すぐ自分を罰したかった。
けれど、それは自分では出来ない。
だから。
だから私は。
彼の体を……
強く、強く抱き締めた。
「おお?」
現象に驚きの声。
構わず抱き締める。
そして言った。
「……不味くても、知らないからね」
ああ、自分は何処まで小心なのだろう。
こんな時に、こんな言い方しか出来ないのか。
本当に素直じゃない。
けれど彼はその答えに満足したようで。
「おう! 楽しみにしてるぜ!」
本当に嬉しそうに言って。
より一層強く、抱き締め返してきた。
馬鹿な人。
あんな言い方なのに。
そんなに喜んで。
ホント馬鹿。
でも私の胸は高鳴って。
余りの嬉しさに、破裂しそうだった。
その会話を最後にして、お互いに黙り込む。
優しくて穏やかな、時間。
感じるのは彼の温もりと……確かな鼓動。
とくん、とくん。
彼の生命を感じる。
ああ生きている。
その事実が、無性に嬉しかった。
抱き合っているうち、不意に溶け出しそうな錯覚に襲われた。
二人重なりあったまま、ぐにゃぐにゃに溶けていく。
そんな、錯覚……けど。
彼とならそうなっても良い。
寧ろ、このまま一緒に溶けてしまいたい。
そう、切に思った。
蕩ける様に甘い時間。
二人だけの空間。
それを破ったのは……
お決まりのように、アイツだった。
……ん?
彼の温もりを甘受している私は、不意に腕の辺りにもぞもぞとした異物感を感じた。
なにかしら?
疑問に思っている間にも、それは二の腕の外側から内側に。
そして腋下に行った直後。
勢い良く這い上がってきた。
「うひゃあっ!?」
突如発生した違和感に悲鳴を上げる。
その悲鳴にも、我関せずといった具合にもぞもぞと何かは動く。
擽ったさに似た感覚。
それは私の腋を中心にして無遠慮に動き回った。
耐えかねた私は、原因に眼を向ける。
私の腋元から、手が生えていた。
もぞもぞと愉快気に蠢く手と……
「はふ~ん……」
痴呆の様な声。
その声で私は理解した。
手の持ち主を見る。
彼は、とても御満悦な表情をしていた。
「うはぁ~……腋手袋~……」
愉悦に浸った顔で変な単語を口走る。
その顔を見て、私の中で何かが切り替わった。
先刻までの甘い空気は形を潜め、代わりにメラメラと怒りの炎が私を包み始める。
こんの馬鹿……
胸元から取り出したるは、一枚の札。
いつも、いつも思うことだけどねぇ……
その札に霊力を叩き込む。
少しだけ、少しだけで良いから……
そしてそれを彼の前に突き出して。
「空気読め馬鹿ああああああああああああああっ!!」
ためらいなく発動させた。
「どふおっ!?」
吐くような呻き声。
彼は声と共に、地面と平行になって飛んでゆく。
そして鳥居を越え、階段の下に消える刹那。
「腋巫女ばんざあああああああああああああああああいっ!!」
そんな間抜けな悲鳴が、聞こえた。
幻想郷に暖かな日差しが降り注ぐ。
全てを包み込むような柔らかな光。
それはまるで、新たに生まれる生命を祝福するかのよう。
轟と、嵐のように一際強い風が吹いた。
春一番。
春の訪れを告げる風。
始まりを意味する、旋風。
人々は新たな始まりを喜び、生活に一層の精を出す。
春とは、そんな季節だ。
誰もが春の訪れを喜び、心を躍らせる。
暖かな、春の日差し。
その下で、私はいつものように境内の掃除をしている。
首には少し不恰好な、紅白のマフラー。
時刻はお昼を回ってすぐ。
腹ごなしに始めた掃除は、もう少しで終わりそうだ。
うーんと背伸びをして、掃除で凝った体を解す。
そして階段の方に眼を向けた。
そろそろかしら?
予感はどうやら当たったようで。
階段から聴こえてくる、荒い息遣い。
その息遣いと共に現れたのは……
自身の求めた、一人の青年。
胸が弾む。
彼は自分を見つけると、嬉しそうに顔を綻ばせ駆け寄ってきた。
そして今日もまた。
どうしようもなく馬鹿で。
どうしようもなく変態で。
「会いたかったぜ腋巫女おおおおおおおおおおおおおおおっ!!」
「だから腋巫女言うなって言ってるでしょうがあああああっ!!」
そしてどうしようもなく愛しい日が、始まる。
おまけ ~紅茶談義~
「おっす」
「あら、魔理沙じゃない」
「邪魔しに来たぜ~」
「別に構わないけど……こっちに来るなんて、珍しいわね?」
「別に普通だぜ」
「そう? まあ、良いけど」
「よいっしょ、っと。……なぁ、あれから霊夢のところに行ったか?」
「いいえ、行ってないわ……あんなの見せられたら、気軽に行けないわよ」
「そうかそうか、だったらこっちに来て正解だったな」
「? どうゆう意味?」
「いやな? 昨日、霊夢ん処に行ってきたんだよ」
「貴女、度胸あるわね……」
「まあ、ほっとけないってのもあるがな……で、だ。霊夢のヤツ、どうしてたと思う?」
「それはまあ……まだ、落ち込んでたでしょう。あれから三日しか経ってないし……」
「残念ながら、不正解だぜ」
「え? じゃあ……」
「ああ、元に戻ってた」
「そう……なの。吹っ切れたのかしら……」
「いやいや、その逆だ」
「どうゆうこと?」
「私も最初、元通りになった霊夢を見た時はそう思ったんだが……良く見ると一部が違ってたんだよ」
「一部って?」
「マフラー」
「マフラー?」
「そ、マフラーしてたんだ。しかも御世辞にも綺麗とは言えない、不細工な。言った瞬間、ブッ飛ばされたけど……」
「それってつまり……」
「そーゆうことだな。いや~○○もやるね~」
「そうなの……良かったわ」
「お? なんだなんだ、霊夢が元気になったていうのに落ち込んでいるじゃないか。嬉しくないのか?」
「嬉しいわよ。けど……」
「なんだよ?」
「私には、無理ってことが分かったから……」
「……あ~」
「少し、嫉妬しちゃうわね」
「そうか。まあ、その、なんだ。気にするなって! お前にもいつか良いヤツが見つかる筈さ!」
「霊夢じゃなきゃ、駄目なのよ……」
「レミリア……」
「そう……霊夢の腋じゃないと……」
「あ?」
「あの若葉のように瑞々しくて、神話に出てくる聖杯のように神々しい……」
「お、おい……」
「成熟と未成熟の狭間にのみ存在する、蕩けるような甘さを持った、霊夢の腋じゃないと……」
「おいレミリア! さっきから何おかしなこと言ってんだよ!」
「あの特上のシルクのような肌触り。何処までも沈み込んでいくような、けれど確かな弾力をもった霊夢の腋じゃないと私は……」
「レミリアっ!!」
「ハッ!?」
「やっと正気に戻ったか……」
「あ、あれ? 私、どうしたのかしら?」
「それはこっちが聞きたいぜ」
「御免なさい。ちょっと前から、私おかしくって……」
「そうみたいだな」
「理由は分かってるんだけど……」
「一体どうしたってんだ?」
「それは……言えないわ」
「またかよ……そういえば、この間霊夢の処に行った時もお前……」
「!?」
「その反応……まさか……」
「な、何を勘違いしてるのかしら?」
「お前も……」
「お嬢様、お茶が入りました」
「あ、ありがとう咲夜! 魔理沙、貴女も呑むでしょう?」
「ちぇっ、まあいいや……有り難く頂くぜ」
「ほっ…………助かったわ咲夜」
「いえ、これも務めですので」
「それじゃあ、頂きましょうか?」
「おう、頂くぜ」
「ねえねえ、私のは~~~?」
「お? 萃香じゃないか」
「やっほ~」
「……貴女、一体何処から入って来たのかしら」
「普通に入り口から入ってきたよ~?」
「中国め……ホント使えないわね」
「ね~私の分は~?」
「無いわよ」
「え~なんで~?」
「五月蝿い。鬼に出すお茶なんて、この紅魔館には無いわ。さっさと出て行きなさい」
「ふ~ん、そーゆーこと言っちゃうんだ~? 良いのかな~?」
「……どうゆう意味?」
「別に~……ねえ、魔理沙」
「あん?」
「さっき、レミリアが変なこと言ってたでしょう?」
「っ!?」
「ああ、言ってたな」
「その理由、知りたくない?」
「ちょ、ちょっと!」
「知ってるのか?」
「勿論、当事者の一人だしね」
「ちょ、ちょっと待ちなさい……!」
「是非、教えてくれ」
「良いよ~。あ~でも、ワインとか飲んだら忘れそうだな~」
「……っ!!」
「無いかな~極上のワイン~?」
「くっ……咲夜」
「はいお嬢様」
「交渉成立! ごめんね魔理沙、やっぱり無理~」
「おいおい、そりゃないぜ~」
「ごめんね~」
「……まあいいや。ところでお前の巻いてるそれって、もしかして……」
「このマフラーのこと? 良いでしょ~。○○が編んでくれたんだ~」
「だと思ったぜ」
「えへへ~」
「部屋の中に居るんだから外したらどうなの?」
「無理~」
「なんでよ?」
「これしてると○○に抱かれてる気がしてとってもあったかいんだ~」
「はぁん? 何言ってんだお前? 遂に呆けたか?」
「呆けてなんかないよ~。う~ん、○○あったか~い」
「うはぁ……こっちは甘くて死にそうだぜ…………でも、やっば不細工だな」
「愛情が篭ってるから良いんだも~ん」
「そ、そうか……でもアイツ、マフラーなんて編めたんだな?」
「人形師に習ったみたいだよ?」
「アリスに? あ~……納得だぜ」
「何が?」
「いんや、こっちの話しだ。にしても二つも編むとは……頑張ったんだなアイツ」
「多分、五つよ」
「へ? なんでまたそんなに?」
「忘れたの? ○○、守矢神社に行ってるでしょう?」
「あ~……早苗か。でも、それなら三つじゃないのか?」
「多分、神連中にもあげてるわ。あの男、アイツ等に借りがあるし……」
「諏訪子と神奈子か。そーゆうとこは義理堅いよなぁ、アイツ……ん?
そーいやお前、なんであの二人のことを知ってるんだ?」
「……そのことに関しては、黙秘させて貰うわ」
「にっしっし~」
「なんだよ萃香、その意味深な笑いは?」
「べっつに~……ねえ吸血鬼?」
「……五月蝿いわね」
「いや~愉快愉快」
「くっ…………いつか覚えてなさい」
「? なんなんだ?」
「まあいいからいいから。あ~、○○マフラーあったかいよ~」
「そんなに良いのか、それ?」
「うん! もう最高だよっ!」
「じゃあ、ちょっと貸してくれ」
「それは嫌」
「なんでだよ」
「魔理沙の匂いが付いたら困るから~」
「私の匂いが付くと、何か問題でもあるのか?」
「ある」
「何だよ」
「○○の匂いが消えちゃう」
「○○の匂い? そんなモン付いてるのか?」
「付いてるの」
「それは流石に嘘だろ」
「嘘じゃないってば」
「だって……なぁ?」
「そこでなんで私に振るのかしら?」
「いや、なんとなく」
「嘘だと思うんなら、霊夢にでも聞いてみれば?」
「霊夢に?」
「うん、多分同じこと言うと思うよ?」
「ふむ……丁度良い。レミリア、確認ついでに霊夢ん処に様子見に行こうぜ」
「それ良いわね、行きましょうか」
「それじゃあ霊夢のところに……」
「「「「レッツゴー!」」」
「ふぅ、掃除終わりっと」
「今日はアイツ、仕事で来れないって言ってたわよね……」
「…………はぁ」
「………………くんくん」
「…………」
「…………ちょっとだけ」
「すぅ……はぁ…………ぁ」
「…………もうちょっとだけ」
「すぅぅ…………はあっ…………」
「…………あといっかいだけ」
「すぅ~…………っはぁ。ふぅ…………もいっかいだけ…………すぅ」
「お~い霊夢~」
「遊びに来たわよ~」
「あれ~? いないの~?」
「うえっ!? ちょ! ま……」
「「「あ」」」
その日、博麗神社は眩い光で覆い尽くされた。
そして博麗神社を訪れた三人は、共に最上級のトラウマを植え付けられた。
光を目撃した烏天狗は、自前の好奇心を押さえ切れず、三人を直撃取材した。
しかしそのことについて、三人は決して口を割ることはなかった。
何を聞いてもガタガタと震えている様を見て、彼女達が壮絶な何かを体験したことだけは分かったのだが。
それ以外は一切が闇に包まれたままだった。
神社で何を見たのか?
彼女達が神社で見たある光景。
それは春先の青空と、燦々と煌く太陽だけが知っていた。
10スレ目>>49 11スレ目>>843 13スレ目>>115、511
うpろだ740、741、947、1003
───────────────────────────────────────────────────────────