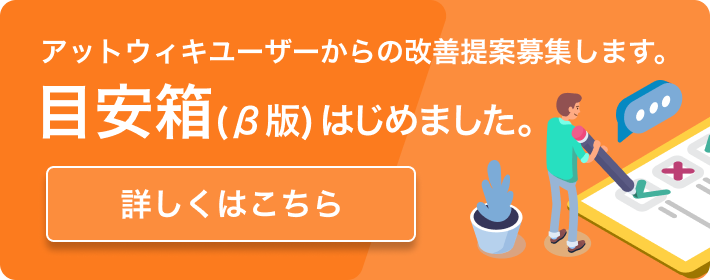無題
「迫先輩から演劇を奪い去ったらどうなりますかっ」
どうする。迫文彦・演劇部部長をつとめる高等部三年生。
考えたこともないシチュエーションだ。だから咄嗟に答えは出ない。
目の前は真っ暗だ。
考えたこともないシチュエーションだ。だから咄嗟に答えは出ない。
目の前は真っ暗だ。
「黒咲、前が見えない」
演劇部の部長だからこそ、そんなイマジネーションを働かさせるスキルは必要じゃないかと後悔しても、
あまりにも迫にとってはありえない世界。マフラーを巻いて、学園前の停留所にてバスの到着を待ち続ける放課後。
黒咲あかねは迫の背後に廻って、両手で迫の視界を遮り続けていた。
あまりにも迫にとってはありえない世界。マフラーを巻いて、学園前の停留所にてバスの到着を待ち続ける放課後。
黒咲あかねは迫の背後に廻って、両手で迫の視界を遮り続けていた。
ひんやりとするオンナノコの手のひらが、迫のまぶたを塞ぎ続け、ほのかにオトコノコの頬を赤くする。
メガネを愛用している迫が、ふとレンズを拭こうとメガネを外した瞬間にあかねに羽交い締めされた上、
あろうことにも視界を遮られた。小娘ごときに身柄をほしいままにされるとはこのことか。
メガネが役割を失って暇をもて余していた。
メガネを愛用している迫が、ふとレンズを拭こうとメガネを外した瞬間にあかねに羽交い締めされた上、
あろうことにも視界を遮られた。小娘ごときに身柄をほしいままにされるとはこのことか。
メガネが役割を失って暇をもて余していた。
「どうなると思う?黒咲わかるか?」
「わかりませんっ」
「わかりませんっ」
真っ暗だからあかねの声がよく聞こえる。五感のうちの一つの自由が奪われただけで、鼓膜のスキルが加速する。
あかねの表情を伺えないのは悔しい。冷静さを保ちつつ、先輩の面目をも保つ。冬の夕暮れの無理ゲーだ。クリアしても得はない。
意図もせずに迫はあかねを十分にじらした上に端的に答えをまとめた。
あかねの表情を伺えないのは悔しい。冷静さを保ちつつ、先輩の面目をも保つ。冬の夕暮れの無理ゲーだ。クリアしても得はない。
意図もせずに迫はあかねを十分にじらした上に端的に答えをまとめた。
「それでもおれは演劇を追い続けるな」
あかねの表情が変わった。勿論、迫は知る由もない。
「止められてもですか」
「ああ。知ってるだろ。おれの性格を」
「どんなに尊敬する人物から咎められてもですか?」
「ああ」
「わたしのような若輩者が拝み倒してもですか」
「ああ。知ってるだろ。おれの性格を」
「どんなに尊敬する人物から咎められてもですか?」
「ああ」
「わたしのような若輩者が拝み倒してもですか」
自他共に認める演劇バカ。
だからこそ、演劇部の部長をつとめているんだと、迫は自負していた。
そう言えば、演技指導に力を入れるあまりに声が大きくなっていた。
そう言えば、脚本にこだわるあまりに議論を重ねに重ね、先輩と対立してしまった。
だからこそ、演劇部の部長をつとめているんだと、迫は自負していた。
そう言えば、演技指導に力を入れるあまりに声が大きくなっていた。
そう言えば、脚本にこだわるあまりに議論を重ねに重ね、先輩と対立してしまった。
それ故、公演を無事に終えた喜びは文字にすら書き表すことも困難なぐらい。贅沢過ぎる一瞬の為。
「一秒たりとも部のこと、演劇のこと、部のことを忘れたことないぞ」
「部のことが恋人みたいですねっ」
「……」
「わたしのこともですかっ」
「部のことが恋人みたいですねっ」
「……」
「わたしのこともですかっ」
あかねの白い息が迫の後頭部に吹きかかった。迫よりも背が高いあかねだから。
先輩の襟首がマフラーで見えないことが、どうしようもできないもどかしさであかねは眉を吊り上げる。
迫の返事が続かないこともあかねの心中を濁す原因の一つでもあった。
先輩の襟首がマフラーで見えないことが、どうしようもできないもどかしさであかねは眉を吊り上げる。
迫の返事が続かないこともあかねの心中を濁す原因の一つでもあった。
「今、わたし。台本書いてるんですっ。まだ、部員の誰にも見せてない書き下ろしですっ」
「おれにも見せてくれ」
「まだですっ。だからこうして目隠ししてますっ」
「どんな話かぐらいは教えてくれ」
「おれにも見せてくれ」
「まだですっ。だからこうして目隠ししてますっ」
「どんな話かぐらいは教えてくれ」
初めてあかねは笑みを見せた。ただ、迫には見えないが。
先輩の肌は優しい。無駄に潤いがある。いつまでも迫の顔を塞いでいたいとう邪心があかねを揺さぶる。
こんなにすべすべとした体で、どうしてあんなに厳しい鬼のような言葉を投げつけられるのか。
演劇に魂を売りつくしてしまった故か。
先輩の肌は優しい。無駄に潤いがある。いつまでも迫の顔を塞いでいたいとう邪心があかねを揺さぶる。
こんなにすべすべとした体で、どうしてあんなに厳しい鬼のような言葉を投げつけられるのか。
演劇に魂を売りつくしてしまった故か。
「笑わないで下さいっ」
くすりとも頬を緩ませることのない迫に、あかねがぽつんと呟いて中指に力を入れていた。
あかねの書いたストーリーは単純だった。
高校生同士のごく普通の恋愛。
ありふれて、風の流れに吹き飛ばされそうなぐらい。恥ずかしくも、初々しくもある、男女のすれ違い。
恋愛なんかあまたの数存在するだろうに、思春期のころの恋愛がまるで一生かけて稼ぐ金でも買うことが出来ない値が付くような。
だからこそ、誰もがよってたかって物語にしようとするのだろう。
高校生同士のごく普通の恋愛。
ありふれて、風の流れに吹き飛ばされそうなぐらい。恥ずかしくも、初々しくもある、男女のすれ違い。
恋愛なんかあまたの数存在するだろうに、思春期のころの恋愛がまるで一生かけて稼ぐ金でも買うことが出来ない値が付くような。
だからこそ、誰もがよってたかって物語にしようとするのだろう。
「でも、途中で書けなくなりましたっ。どうしてでしょう」
迫を包んだ黒の世界が灰色に染まる。
ぱぁっと、あかねが手を離したからだ。途端に迫の顔が冷される。全ては冬の空気のせい。迫が振り返りメガネをかけると、
既にあかねの表情から笑みが消えていた。あかねの演技について迫が一言二言鞭打っているときに見せる顔だった。
ぱぁっと、あかねが手を離したからだ。途端に迫の顔が冷される。全ては冬の空気のせい。迫が振り返りメガネをかけると、
既にあかねの表情から笑みが消えていた。あかねの演技について迫が一言二言鞭打っているときに見せる顔だった。
「失恋がどういうものか分からないからですっ」
誰かを好きになっても、傷付くことに怯えていた。
遠くから花を眺めていることで、自分自身を守っていた。
誰かのコイバナを傍で聞いていて、「わー」「きゃー」騒ぐだけの存在でいることが楽しかった。
失うことの価値すら知らずに、桜の木々をやり過ごし、海の恩恵も得ず、一雨ごとに冷たくなる通学路を通り抜け、
そして雨後の夕焼けの美しい季節を無駄にしていた。
遠くから花を眺めていることで、自分自身を守っていた。
誰かのコイバナを傍で聞いていて、「わー」「きゃー」騒ぐだけの存在でいることが楽しかった。
失うことの価値すら知らずに、桜の木々をやり過ごし、海の恩恵も得ず、一雨ごとに冷たくなる通学路を通り抜け、
そして雨後の夕焼けの美しい季節を無駄にしていた。
「主人公の男子が失恋することから物語は始まります。でも、書き出しが書けないんですっ」
「なにも書けてないんじゃないのか」
「なにも書けてないんじゃないのか」
演劇部の端くれだと自負しているだけに、そこは強く否定した。
「でも、大丈夫です。迫先輩の言葉で救われましたっ」
迫の乗るバスが停留所に到着した。ブザーの音で扉が開き家路へと誘う。
お乗り間違えがございませんように。
だが、迫には今やバスなど家路などどうでもよくなっていた。丁寧に、そしてそれを悟られないようにあかねの指先を観察する。
お乗り間違えがございませんように。
だが、迫には今やバスなど家路などどうでもよくなっていた。丁寧に、そしてそれを悟られないようにあかねの指先を観察する。
あれはあかねがホンキで話している匂いだ。
くんかくんかと嗅いでみてもいい。
きっと、ウソをつく香りはしないはず。
くんかくんかと嗅いでみてもいい。
きっと、ウソをつく香りはしないはず。
「恋人から振られても、振られても、その子のことはずっと忘れない。迫先輩って、男の子ですっ」
「待て。そんなこと言ってないし、未練がましいなどもってのほかだ」
「恋人にしたいぐらい演劇、演劇部のことが好きなんですよねっ。迫先輩のお陰で、いい台本が書けそうですっ」
「待て。そんなこと言ってないし、未練がましいなどもってのほかだ」
「恋人にしたいぐらい演劇、演劇部のことが好きなんですよねっ。迫先輩のお陰で、いい台本が書けそうですっ」
紅潮したあかねはぐっと拳を作り、ぐるりと踵を返した。長い黒髪がふわりと木枯らしの歩道に舞った。
走り去るバスを追いかけるように、あかねは小走りする。
すたすたと黒タイツに包まれた脚を学園へと走らせているあかねを呼ぶ声が響いた。
走り去るバスを追いかけるように、あかねは小走りする。
すたすたと黒タイツに包まれた脚を学園へと走らせているあかねを呼ぶ声が響いた。
迫だ。
演劇部部長・迫文彦。
人呼んで『演劇バカ』。
演劇部部長・迫文彦。
人呼んで『演劇バカ』。
「今から書くつもりだろ」
その一言で救われる。
言葉と言う文字は、武器にもなり、薬草にもなる。おいそれ使うわけにはいかないし、軽んじてはいけない。
言葉の偉大な力を良く知るあかねは、頷くことによって返事に代えた。
言葉と言う文字は、武器にもなり、薬草にもなる。おいそれ使うわけにはいかないし、軽んじてはいけない。
言葉の偉大な力を良く知るあかねは、頷くことによって返事に代えた。
「おれも力になる」
「わたしが書きたいんですっ」
「演劇部でやるんだろ。おれの目を信じろ。悪いようにはしない」
「そうするつもりですけど、お断りしますっ」
「わたしが書きたいんですっ」
「演劇部でやるんだろ。おれの目を信じろ。悪いようにはしない」
「そうするつもりですけど、お断りしますっ」
乗るはずだったバスをやり過ごし、迫はマフラーを巻き直し大きく息を吐いた。
恋人がどんどん遠ざかる。恋人が他人に戻るなんて、どんなにあがいても忘れられるわけないし。
恋人がどんどん遠ざかる。恋人が他人に戻るなんて、どんなにあがいても忘れられるわけないし。
「とことん見てやるから、黒咲は書け」
振られても、振られても、恋人のことを忘れられない迫のことだ。
頷くことによって返事に代えたあかねは、迫の恋人との間を取り持つことにした。
頷くことによって返事に代えたあかねは、迫の恋人との間を取り持つことにした。
おしまい。
前:無題 次:先輩!バレンタインまで一週間です!