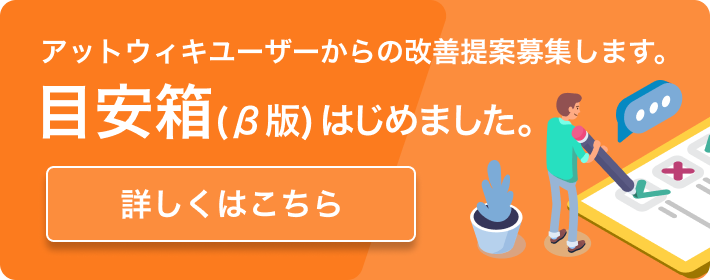プロポスレ@Wiki
永琳2
最終更新:
orz1414
-
view
■永琳2
芽生え、花が咲き、そして散ってゆく。
朽ちて、風に融け、そして空に昇る。
やがて雨が降り、大地を潤し、新しい生命を芽吹かせる。
繰り返し、繰り返し。
周る星々と同じように、命もまた巡るものなのだ。
・
・
~ January ~ ――最初から結果を知っているのなら、誰も間違いは起こさない。
元日からの三ヶ日もそれなりに平坦に過ぎ、年越しの浮かれた空気もやや薄れ始めた永遠亭。
その日、珍しく自ら材料の採取に出ていた私の師匠こと八意永琳は、ロクでもない拾い物をして帰って来た。
「……どうしたんですか師匠。それ」
ホクホク顔で帰って来た師匠の背中に、一人の人間の青年がグッタリと負ぶわれていた。
「ちょっとそこで拾ってね。折角だから持って帰って来ちゃった。
まあ、薬の実験台くらいにはなってくれるでしょ」
「は、はぁ……」
青年の出で立ちはこの幻想郷ではまず見られないもので、外からの迷い人である事を窺わせる。
(……可哀相に)
よりにもよって師匠に拾われてしまうとは。
これなら、気絶している間にそこらの妖怪に喰われでもした方が、まだマシと言うものだ。
私は毒蜘蛛の獄糸に囚われた哀れな羽虫に、僅かな同情の念を抱いて視線を送り、そして、
「……なっ!?」
眼前のおぞましい光景に、言葉を失った。
「? どうしたの、ウドンゲ」
「い、いえ……な、何でもありませんよ。あ゛、あははは……」
……何という事だ。
男は、気絶した振りをしながら師匠の髪の香りを嗅いで、幸せそうに鼻の下を伸ばしていた。
「?……変な子ねぇ。まあいいわ、まだお昼の残り物があるわよね?
取り敢えず、疲労と空腹意外におかしな所は無いみたいだから、叩き起こして食べさせてあげましょう」
「……はい」
脳の調子もおかしいのではないかと思ったが、混ぜっ返すのも面倒なので、大人しく師匠に従う事にした。
――彼は哀れな羽虫などではなく、飛び切り性質の悪い毒虫だった。
後々私達――特に師匠は、それをある種の痛みとともに思い知る事になる。
屋敷に運び込まれた彼は、程無く師匠の高速往復ビンタ(秒間16連打)で目を見開いた。
残り物のご飯を振舞いながら、双方簡潔に自己紹介を済ませる。
話を聞くに、やはり外の住人だったらしく、此処にいる心当たりもまるで無く、このところ数日の記憶も酷く曖昧らしい。
……スキマ妖怪の餌狩りから、漏れ出しでもしたのだろうか。
「ムシャムシャどうにか帰れないかなあガツガツ、ああ美味いゴクゴク、ありがとう助かったよモグモグ」
食べるか尋ねるか礼を言うか、どれか一つにして欲しい。
健啖そのものの彼の様子に師匠は満足そうに笑うと、いつもと変わり無い、平坦な声で答えた。
「心当たりはあるにはあるのだけど、冬の内はどうにも出来ないわね。
時期が来れば手は打ってあげるから、それまではウチで過ごしなさいな。
それなりの扶持と仕事は与えてあげるわ」
「……そっか、ありがとう。まあ、世話になった分はしっかり体で返すよ」
「…………『体で返す』……言ったわね、言ったわね、フフフ……」
彼の快諾を得た師匠が、唇の端を妖しく吊り上げた。
(……つくづく、可哀相に……)
口は災いの元とは、よく言ったものだ。
哀れ、実験台&隷属労働が確定した彼の表情をちらりと窺い見ると、師匠に負けじと妖しく笑っていた。
「ふふ……そうとも、『体で返す』……むふふ……ぐふっ」
取り敢えず、一発殴っておいた。
…………
何が何やら分からぬまま流れ着いて来た、魍魎住まう幻想郷。
『行動力のある方向音痴』という非常に迷惑な性質を持つ俺が、曖昧に色の移ろう竹林を独力で抜けられる筈も無く、
手を打てる妖怪が居るには居るらしいが、現在冬眠中で、春が来るまでは当てには出来ないらしい。
人型の妖怪の癖に冬眠だのと言うくらいだから、さぞかし熊チックな大女なのだろう。
熊殺しは男の浪漫だ。会う日を楽しみにしておこう。
当然ながら行く宛てなど無いロンリーシングルな俺は、お言葉に甘えてこの永遠亭の人たちの世話になる事にした。
昨日あの後、この屋敷の姫様とやらをはじめ、ある程度の顔見せは済ませてある。
――さて、今日は実質初日だ。俺が出来るナイスガイである事を、一発見せ付けてやるとしよう。
長い廊下を歩きながら、擦れ違う子たちに自己紹介のついでに道を聞き、永琳の部屋を訪ねた。
「おはよう、永琳」
「あら、おはよう。そっちの方から来るとは良い気構えね。体調はどうかしら?」
「元気ビンビン大事無い。……ところで、指し当たって俺は何をすればいいんだ?」
「そうね……いきなり大仕事になって悪いのだけど、今日は年末の大掃除で出たゴミを庭で燃やそうと思うのよ。
裏口に全部積んであるから、それをリヤカーで庭まで運び出してちょうだい」
「分かった、あつらえ向きの力仕事だな。任せてくれよ」
「まあ、頼もしい限りね……ふふ」
と、意気揚々と臨んだ初仕事だったのだが、裏口に出るなりいきなり挫けそうになった。
「…………何じゃこりゃ」
山のようなゴミ袋や家財道具、果てにはごっついボロ箪笥がまるまる一台。
横に鎮座している、幅だけでゆうに六尺は超えていそうな特大リヤカーが、随分可愛らしく見えた。
「え~っと……これを、俺一人で?」
「そうよ。まさか、嫌とは言わないでしょうね?」
「ぐ……」
確かに、タダ飯喰らいの店子である俺にはそんな強い事を言える立場も無い。
「仕方が無い、やってやるさ。お嬢さん、あまりの頼もしさに惚れるなよ?」
「ふふ、期待はしないでおくわ」
冗談めかした淑やかな笑顔に、それなりのやる気と、頬に少々の赤みが湧いてきた。
愚痴を垂れたところで荷が減る訳でもない。まあ頑張ろう。
…………
――それからおおよそ二時間弱。
「え~んやこ~ら、せっと」
幸い裏口から庭までそう大層な距離がある訳ではなかったので、一度に運ぶ量を少なめにして、足を細かく動かす事にした。
「ほら、頑張りなさいな。もう少しで終わるわよ」
「ぐ……」
永琳は何か手伝ってくれる訳でもなく、細かな指示を出しながら、俺の横をただついて歩いていた。
妙な居心地の悪さに囚われながらも、何とかあと一往復、という位までゴミの山を切り崩したところだ。
そもそも元のゴミの量が半端ではなく、リヤカーそのものの重量もある。
いい加減限界を訴える両の腕に、これで最後と喝を入れた。
「ふふ、大丈夫? 随分辛そうに見えるけど、ここに来て降参かしら?」
小馬鹿にしたような嫌味ったらしい物言いが、俺の闘魂の炎を激しく揺さぶり上げた。
「あんまり馬鹿言うなよ。やっと準備運動が終わったところだ。
ヘイヘイ小粋なお嬢さん! 俺の愛車に乗って行くかい?」
頭をノリノリで振り回しながら、峠の田舎ヤンキーっぽく強がってみた。
「あらいいの? それじゃ、お言葉に甘えちゃおうかしら」
……どうやらこの畜生鬼には、俺の限界を慮り、可愛く遠慮する程度の優しさも無いらしい。
「あ~まあいいよ。ほら、乗りな」
足を止め、顎で指して永琳に荷台を勧めた。
今更女性一人程度の荷が増えたところで、大した違いは無いだろう。
それに少し想像を逞しくすれば、自転車の後ろに女の子を載せるようで、萌えるシチュだと言えなくもない。
「ふふ。では、遠慮なく。……よいしょ、と」
断りを入れると、永琳はリヤカーの縁に両手を掛け、ふわりと軽く跳んで、腰を荷台に落としてきた。
底板が軽くたわみ、パイプを震わせ両手に彼女の重みを伝えてくる。
「うっ! ……おも」
「ま、さ、か、『重い』だなんて言わないでしょうね?」
「……さを感じないくらい軽くてビックリしちゃう!!」
「よろしい」
まだ死にたくないので、余計な冗談は言わない事にした。
「さ、面舵いっぱ~~い」
向こうを指差しながら視せられた悪戯っぽい笑顔に、不覚にも胸が高鳴る。
「はいはい、月の向こうまででも行ってみせますよ、お客さん」
「う~ん……折角だけど、月は遠慮しておくわ。代わりに庭までよろしくね」
…………
――ごとん、ごとん、ごとん。
のんびりと最後の往路を闊歩していると、行く先に人影が一つ見えたので、そこで一旦足を止めた。
鴉の濡れ羽色鮮やかな長髪が目を惹く、この屋敷の首魁、蓬莱山輝夜姫だった。
「あら、姫。おはようございます。もういい加減お昼ですけど」
「ん、おはようございます、姫様」
「おはよう二人とも。精が出るわね」
姫様は俺達の挨拶に軽く笑って応えると、荷台の上でニコニコとお姫様チックに鎮座している永琳に視線を送り、
「……永琳、歳を考えなさい。見てられないわ」
きっつい一言を浴びせかけた。
恐る恐る永琳の表情を覗い見ると、表面上は先程までと変わらぬ笑顔のままではあったが、奥歯がギリギリ軋む音がしてめっちゃ怖い。
「あらあら姫、お戯れを。精神にまで若々しさを亡くしてしまったら、女はお仕舞いですよ?」
「m9(^Д^)プギャーwwwwちょっwwwwwww若々しさとかwwwテwラwワwロwスwww自分の実年齢考えろってのwwwwwwwwっうぇ」
姫様、お願いだから日本語で話して下さい。
と言うか、トップの主従が朝からこんなアホな諍い起こしてて、大丈夫なのかこの屋敷。
「ほらほら貴方も言ってやりなさいよ。××年以上も生きてる因業ババアが男の後ろで少女座りとか恥ずかしくないのか、って」
具体的な数字を伏せたのは、俺のなけなしの良心からです。
さて、姫様が俺に話を振りやがりになられたので、極力角の立たない素敵な言い回しを考えてみた。
「いやそんな、俺は可愛いと思いますよ?」
「えっ?」
「なっ……ば、馬鹿言わないの!」
――ごすっ。
「痛でっ」
場に角は立たなかったが、永琳が投げつけてきた木箱の角が俺の鼻っ柱に突き立った。
「な、何すんだよ! せっかく人が褒めたってのに!」
「いいからっ、早く進む!」
何故か永琳が顔を真っ赤にしてプリプリ怒っているので、仕方なく従う事にした。
「ったく……それじゃ姫様、また後で」
「え、ええ……」
呆然と手を振る姫様を尻目に、再びリヤカーを漕ぎ出した。
…………
「…………驚いた」
永琳って、あんなに初心だったかしら。
……そう言えば、永琳の事を『綺麗だ』と褒める奴は、男女問わず今までにも掃いて捨てる程居たが、
初見で『可愛い』と表現した奴は、ちょっと記憶に無い。
以前、弟子のイナバが同じような言い回しで永琳の服を褒めて、照れ隠しの張り手で十メートルくらい地面と平行にブッ飛んで行った事があった。
「……うん、気に入った」
少々退屈していたところに、見所のある玩具が増えたのかもしれない。
ひ弱な人間、それも外からの異分子の癖に、彼は私たちを畏れず、大した気負いも無く環境の変化に順応している。
余程の馬鹿なのか、はたまた余程の大物なのか。
この泥の大海に揺られるような永い航路に、少しは波を立ててはくれるのだろうか。
…………
「鈴仙様~~、鈴仙様の分も焼けましたよ~」
「ん、ありがとう」
イナバの子から、ほかほかと湯気を立てるサツマイモを受け取った。
「熱つつっ」
手の中で転がしながら、ぺりぺりと芋の皮を剥き上げる。
紫色の皮の下から姿を現した黄金色の実に、少しはしたなく齧り付いた。
甘味を孕んだ熱の塊が咽喉を滑って腑を流れ、喉元に残った温かな薫りが鼻孔を抜けた。
「ふふ、美味しい」
やはり、焚き火と言えばこれが無いと始まらない。
庭のど真ん中で、集めた廃棄家具が火にくべられ、轟々と煙と炎を巻き上げている。
イナバの子達がワイワイと楽しそうに周りを囲み、暖を取ったり、棒で中を突付いて芋の焼け具合を確かめたりしていた。
火を畏れない獣というのはどうかという気もしなくは無いが、まあ些細な事だ。
――少し向こうの方で、師匠と姫、それに居候の彼を加えた三人が、焼き芋を肴に歓談している。
今日これまでの半日で、随分と仲が良くなったみたいだ。
「う~ん、美味しいわ永琳。ね、もう一個いいかしら」
「構いませんけど、注意はして下さいね。引き篭もりで肥満体質な姫なんて、私は嫌ですよ」
「う゛……」
乙女心の軟らかい所を鋭く抉る師匠の一言に、姫様は一歩たじろいだ。
和装なので分かり辛いが、正月太りの兆候でも顕れているのかも知れない。
……私も気をつけよう。
「なあ永琳。悪いけど、俺はもう一個貰えないかな。流石に腹が減って」
「いいわよ。今日は頑張ってくれたから、特別に私が密かに栽培していた、滋養たっぷりの取って置きをあげる」
控え目にお替りを要求する彼に師匠は軽く笑いかけ、焚き火から木串を一本引っ張り出した。
――ずいっっ。
「うっ」
「おわっ……こ、これは……」
姫様と彼が、揃って顔を顰めて変な声を上げた。
随分と摩擦係数の小さそうな、ツルツルと真ん丸いサツマイモ色の球体が、師匠の掲げた木串に刺さっていた。
「いかがかしら? 永琳印特製の遺伝子超絶組み換え芋、『グリーングローブ』よ」
「……突っ込み所がいささか多過ぎる気もするが、オラすっげえわくわくしてきたぞ」
……それでいいのか、か弱き人間。
そんな私の危惧を余所に、彼は師匠から受け取った母なる大地に、大口開けて勢い良く齧り付いた。
「……モグモグ。……うはっ、美味ええぇぇ!! どうですか、姫様も」
「そ、そうなの? それじゃ私も一口…………ぶはあぁぁー――ッッ!!!
ななな何これすっごい不味い!! おのれ謀ったわねこの下郎!! おえっぷ」
「ぶははははっ、かかったなアホが! こんな不味いモン、俺一人で食ってられるか!! ぐえっぷ」
「あら、喧嘩はダメですよ、二人とも」
「「アンタが言うな!!」」
「…………はは」
二人同時に師匠に指を突き付ける姫様と彼の姿に、思わず苦笑が漏れた。
周りを囲むイナバの子達からも、どっと笑いが起こっている。
この屋敷にこれだけの大声が飛び交うのは、去年の永夜事変以来ではないだろうか。
「ま、みんな楽しそうだからいいか……」
師匠も姫様もイナバの子達も、彼の事をなかなかに気に入ったようだ。
現前でゆらゆらと棚引く炎と背後のドンチャン騒ぎを肴に、もう一口芋に齧り付いた。
…………
どうにかこうにか一月弱の日々を経て、この永遠亭での生活にも少しは馴染んできただろうか。
粗相を仕出かして即お肉、という危惧もまあ当初は無かった訳でもないが、今の所そのような気配は無い。
永琳は、俺の事を容赦無く扱き使い、悶死クラスの人体実験を平気でやらかしたりするが、根本的には優しい人……だよね?
姫様は、きっつい揶揄を浴びせてきたり難題を吹っ掛けてきたり、香霖堂でwebマネーを買って来いだのと何かとサドい人だが、
全ては親愛の裏返しである、と俺の常夏トロピカル脳が告げているので、概ね問題は無い。
イナバの子達も幸い俺と楽しそうに接してくれているし、鈴仙の短いスカートから伸びる白い脚は、まさしく月が生み出した奇跡だ。
俺の方も、ここでの生活が楽しいと思える程度には、永遠亭の人達の事を好きになっていた。
さて、今日は昨晩から降り出した雪が猛威を振るいまくりで、暴れ回る白雪が屋敷とその周辺一帯を真っ白に染め上げている。
イナバの子達は部屋にこもって布団で丸くなり、薬師師弟と姫様、俺を含めた四名は、居間の掘り炬燵を囲んで丸くなっていた。
「さ、寒い……」
炬燵に深々と潜り込みながらも、なおガチガチと歯を鳴らす鈴仙の姿が哀れを誘う。
まあ、寒さに強い兎というのも、あまり耳に入る話では無いが。
「うぅ……寒い……時が……時が視えるわ……」
どてらを二重に着込んで目を虚ろに泳がせている姫様に関しては、極力視界に入れない事で対処する事にした。
「だらしないですよ姫。それにウドンゲ、この程度で音を上げるような情けない弟子を持った覚えは無いわよ、私は」
「全くだ。炬燵の中で実はパンツ一丁になっている元気な俺を見習え」
「……居住まいを直すのと素っ裸で庭に放り出されるのと、どちらがお好みかしら?」
「ご、ごめんよぅ」
永琳の爽やかな笑顔が恐ろしかったので、慌てて倒錯露出プレイを中止し、炬燵の中でもぞもぞとズボンを上げる。
一人平気な顔をしている永琳に、鈴仙が恨めしそうに頬を膨らませた。
「ふんだ、師匠はいいですよね。胸にいっぱい脂肪が詰まってるから、寒くも何ともぎゃあああっっ!!!
痛い痛いっっ、足の指とは到底思えないこの握力!!」
炬燵の中で執行された制裁に、鈴仙が面白い顔をしながらギブアップを訴える。
程無く足指アイアンクローを解くと、永琳は硬く閉じた障子の向こう、外の景色を幻視するかのように、少し遠い目をした。
「確かに寒いのは難儀ではあるけど、雪っていうのは綺麗なものね。
月が地上に適わない、数少ない現象の一つだわ」
「……そう、ですね」
「…………」
相槌を打った鈴仙が一つ息を吐き、場に少し神妙な懐古の空気が流れる。
ここに居る三人は元来月の住人で、止む無き事情でこの幻想郷に移り住んで来たのだと言う。
三者三様に抱えているであろう胸の傷は、所詮他人である俺が触れて良い類のものでは無い。
要らぬ傷をうっかり抉らぬよう、大人しく黙り込んだ俺に、永琳は何事も無かったかのように笑いかけてきた。
「この分だと、明日は一日雪掻きね。頼りにしてるわよ」
「うへぇ……」
凡人であり他人である俺には、彼女の笑顔の裏にどのような感情が隠されているのかなど、分かりようも無い。
それを寂しい事だと感じてしまうのは、春にはここから姿を消す俺にとって、良くない兆候だと思った。
…………
昨夜の内に降りしきる雪は勢いを無くし、夜が明ける頃には粉雪がぱらつく程度に天候も落ち着いていた。
とは言え、丸一日暴れ回った雪たちは屋根だの周辺だのにどっさりと鎮座し、屋敷の骨を密やかに軋ませている。
昨日の永琳の言葉どおり、今日はイナバの子達と協力して雪掻きだ。
「あれ? 随分と集まりが悪い気がするが」
「そうなのよ……昨日の寒波で、殆どの子が風邪を引いちゃって」
俺の疑問に、鈴仙が頭を掻きながら苦笑交じりに答えた。
「そっか、可哀相に。具合は大丈夫そうなのか?」
「今師匠が診て廻ってるけど、まあ大丈夫でしょ」
まあ体調を崩してしまったのでは仕方が無い。こういう時にこそ俺のような居候がしっかり働くべきだろう。
「さ、始めましょ。動ける私達が頑張らないと」
「「「は~~い!!」」」
鈴仙の音頭に、イナバの子達に混じって大声を上げた。
…………
「おっ嬢さ~~ん、山男には惚れるなよ~~、っと」
作業を始めてから、どの位の時間が経っただろうか。
どっかと屋根に根を下ろした雪の山を延々とこそぎ落とし、ようやく屋根の上の雪を粗方降ろす事が出来た。
参加してくれたイナバの子達の体調も万全には程遠く、へばった子には作業を切り上げさせて屋敷に帰らせていく内に、
何時の間にか俺と鈴仙を含めて、両手で足りる程度まで頭数が減っていた。
少し目を放した隙に無断で居なくなっていたてゐは、かつて全米を震撼させたジャックハマーで雪の中に串刺しにしてやろうと思う。
「ふ~~、あとは落とした雪を固めて終了、ね」
長い髪を後ろに縛った鈴仙が、息を整えながら歩いて来る。
彼女も人手不足を補おうと懸命に動いてくれていたが、大体が雪掻きなんて、女の子にさせるような作業ではない。
表情にも疲労の色が濃く、普段は水饅頭のように艶やかな唇が、見る影無く青褪めてしまっていた。
「……いいよ鈴仙。後は俺一人でどうにでも出来るから、他の子達を連れて先に戻ってな」
「何言ってるのよ。私はまだまだ大丈夫」
「そんな真っ青な唇して何言ってやがる。大体君のその格好は、見ているだけでこっちの体温が一度下がる」
この銀世界に関わらずいつものミニスカートって、一体どこの世界のワカメちゃんだ。
「しょ、しょうがないでしょ。ズボンを穿こうとしたら、何故か師匠が怒るんだから」
「何と。……う~む……鈴仙も苦労してるんだな……」
俺の脳内で、永琳の宇宙人的セクハラに憤怒する天使を、大喝采を送る悪魔が一瞬で誅殺した。
「もういいから、今すぐ戻って風呂にでも入って、しっかり暖まりなさい。
俺の方もさっさと終わらせて、君の風呂を覗く事にするから」
「ばっ、馬鹿言ってるんじゃなー――――ックシュン!!!」
――べちょべちょべちょっっ。
「…………」
いきなり間近で思いっ切りクシャミをかましてくれるものだから、俺の顔面に唾だの鼻水だのがかかりまくった。
「あっ、あああっ、ご、ごめんなさー――――ックシュン!!!」
――べちょべちょべちょちょっっっ。
はい、もう一発追加~~。
「あわわっ、ほ、本当にごめんなさい……」
「…………う~む……」
こんな仕打ちを受けて興奮している俺は、人としては間違っているが、男としては間違っていないと思う。
「ちょっとジッとしてて。すぐ拭くから」
鈴仙は慌ててポケットからハンカチを取り出し、俺の顔面に刻まれた聖なる液痕を拭い取ろうとした。
「バカタレ!! 勿体無いから拭くんじゃありません!!」
「私がイヤなの!!」
ごもっともです。
…………
結局は鈴仙の方が折れ、イナバの子達と共に屋敷に引っ込み、最後の仕上げは俺一人で行う事となった。
腕っ節にはそれなりに自信はあるし、残った作業も落とした雪を叩いて固めるのみ、という単純な力仕事。
時間は掛かりつつも屋敷の周りを何とか一周し終え、現在はもう一度屋根に上がって不備が無いか確認中、といったところだ。
「ん~~~~……問題無し、かな」
屋根の淵を一周して見回してみた分には、大きな問題は無いように視える。
今日のお勤め完了、という事だ。
「ふぅ」
一つ大きく息を吐き、梯子を降りようとして……少し、心変わりした。
下に落ちないように軒先に足を引っ掛け、その場に腰を落とし、顎を上げてぐるりと周辺を見回してみた。
永遠亭の近辺を万遍無く、雪にまみれた竹が埋め尽くしている。
ここの人達が外を行き来する為に拓いた獣道が僅かに覗く程度で、その景観は竹で出来た固牢じみていた。
「……」
あながち間違った表現でも無いと思う。
この永遠亭は、かつて姫様と永琳が追っ手の目を眩ます為にこしらえた、不可視の鳥籠だ。
今でこそ鈴仙やてゐ、イナバの子達が共に住まい、時折り来訪者も訪れて来るという比較的開かれた環境ではあるが、
この幻想郷に来た当初……たった二人きりだった頃、彼女達はどのような心境で日々を過ごしていたのだろうか……
「…………やめとこ」
二人がこの場に到った事情を知らない以上、何をどう考えても下衆の勘繰りにしかならない。
それが話して良いような理由なら、俺がそれを聞くに値する存在なら、いつか彼女達の方から話してくれるだろう。
「あら、そんな所にいたのね」
「ん?」
不意に下方からかけられた声に視線を落とすと、永琳が小さな籐製のバスケットを両手にぶら下げてこちらを見上げていた。
「ああ永琳、お疲れ様。こっちはさっき終わったよ。イナバの子達はもう大丈夫なのか?」
「ええ、お陰様で。……ちょっと待ってなさい、私もそっちに行くから」
そう言って永琳は籐籠を右手に持ち替え、器用に体のバネを遣いながら、片手で梯子を昇って来た。
「……よいしょっと。隣、失礼するわね」
断りを入れてくると、籐籠を間に挟んで、俺と同じような体勢で隣に腰掛けた。
「ん~~冷たいっ。よく平気で座ってられるわね」
「ここまで冷えると、立ってても変わらんよ」
もうその辺の感覚は、とうの昔に麻痺してしまっている。
「まったく無理しちゃって。そんな可哀相な頑張り屋さんに、永琳お姉さんから素敵な差し入れよ」
永琳は苦笑いを浮かべると、いそいそと籠の蓋を開いた。
箱の中に敷かれていた蝋紙の上に、中華まんが三つ、ほかほかと湯気を立てている。
「おぉっ、ありがたい! ちょうどお腹も減っていたところでさ」
「喜んで頂けて何より。一つは私が頂くから、二つはご自由にどうぞ」
「ん。ありがたくいただきます」
「はい、いただきます」
二人で冗談めかして両手を合わせ、早速中華まんに齧り付く。
程好く張りのある皮とふかふかの生地の中に、熱々の餡子がぎっしりと詰まっていた。
「あ~~こりゃ美味いや。極楽極楽」
心地よい熱と糖分が四肢を巡り、凍えた体に再び力を与えてくれる。
「ふふ。お口に合ったみたいで良かったわ。自分で料理するだなんて、随分久し振りだったから」
「それはそれは、重畳の至り。この状況での錯覚を差し引いても、本当に美味いよ」
「ありがとう。日頃縁の無い手間をかけた甲斐があったわ」
俺の言葉が世辞ではない事を感じ取ってくれたようで、永琳は満足そうに相好を崩した。
「……ね、何でイナバの子達を帰したの? 皆結構気にしてたわよ」
「何でも何も無いよ。女の子に無茶をさせて体を壊しでもされた日には、男の立つ瀬が無い」
女性の体は、子を宿し未来を託す為の、大切な世界の宝だ。
こんな詰まらない事で台無しにして良いような粗末なものでは無い。
「あらあらご立派。でもね、外で働くのは男の役目だなんて言うのは、フェミニズムでも何でも無く、単なる男尊女卑よ」
「……酷い事言うなあ……」
「うふふ、冗談よ。……ありがとう。貴方のお陰で、あの子達に無理をさせずに済んだわ」
ふわりとした笑みを見せてから視線を前方に移した永琳に、俺も倣う。
変わり映えの無い竹の群れが、緩やかな風に煽られ、ゆらゆらと棚引いていた。
「……ねえ。此処での暮らしは、退屈じゃないかしら?」
視線を前方に向けたまま、永琳がそんな事を訊いてきた。
「そんな事無いよ。みんな良くしてくれるし、外に居た頃には出来なかった、新鮮な体験ばかりだ」
――それと……
「そう」
少し強い風が吹き、厚く束ねられた永琳の髪を軽く浮かせる。
――出逢ってから共にした日々は、一月にも満たない程度の須臾でしか無いけれど、多分俺は……この人の事を。
「その感性、大切にしなさい。それは定命ある者にのみ赦された、とても貴いもの。
私みたいな、天の理に背いて左道に外れた外道には、酷く遠い揺らぎだわ。
あまり死の陰の無い生活が長くなるとね、どんどん感情の振れ幅が小さくなってくるのよ。
日の移ろい、四季の移ろい程度の変化では、ちっとも心が揺れてくれない。……悪い暮らしでは無いのだけどね。
『死が無い』と言う状態を、果たして『生きている』と表現して良いものなのやら」
そこまで詠うようにゆったりと語り上げると、竹林の更に遠くを見据えるように、眼差しを細くした。
憂いを孕んだ薄い笑みに滲んでいたのは何処か自虐めいた達観で、彼女の言葉どおり、俺に理解できる類のものでは無かった。
「……自分の事を外道だとか、あんまり悪く言うもんじゃないよ。
君を慕っている鈴仙やイナバの子達に失礼だし、俺だって悲しくなる」
そんな気の利かない事しか言えず、食べかけの中華まんを一気に口に放り込んだ。
それでも、しっかりと感情を込めた取り繕いでない言葉は、ちゃんと相手に届くもので。
「……そうね……ごめんなさい、少し軽率だった」
そう柔らかく微笑んだ彼女の頬が少し赤く視えたのは、寒気のせいか、はたまた俺の自惚れだろうか。
「それじゃ、嬉しい事言ってくれた色男さんに、出血大サービス」
一転悪戯っぽく笑うと、永琳は籐籠から最後の中華まんを取り出し、俺の方に差し出してきた。
「はい、あ~ん」
「…………マジで?」
「大マジです。それとも、姫やウドンゲじゃないと嫌だとか?」
「断じてそんな事は無い」
金メダル級のロケット即答。自分に正直なのは良い事だ。
「あら嬉しい。それなら遠慮しないで、はい」
「わ、分かったよ…………んぐ」
彼女の手の中の中華まんに齧り付いた瞬間、
――パシャパシャ!
幻想郷に来て以来、初めて耳にしたシャッター音に振り向くと、
見慣れた頭部と初めて見る頭部の計二つが、大棟の向こう側からひょっこり覗いていた。
『凄いです!! とんでもない写真が撮れました!』
『ね、言ったとおりでしょ? 最近ちょっと怪しい雰囲気だったのよね~』
『うんうん、これはいい記事が書けそうです。
天才薬師と異邦人の、銀色のロマンス……あぁ、痺れるわ……』
『うんうん、でしょでしょ? それで、リークのお代の方は……』
『人里の激ウマ人参二十本でしたよね。それは後日必ず』
『ウササササ、お主もワルよのう、越後屋』
『いえいえいえ、御代官様には遠く及びませぬ。むふふふふ』
「…………殺るか」
「…………ええ」
――ひゅんっ。
無言のままに永琳の手首が唸り、何処からとも無く取り出された鍼が放たれ、
――すととんっっ。
二つの頭に、同時に突き刺さった。
「「う゛っっ」」
間の抜けた呻き声が二つ同時に上がる。
「うっ……動けない? い、一体何を……」
「ぬ、ぬかったわ……!」
身動き一つ取れない状態でもがく人影二つに、永琳と並んで詰め寄っていく。
「あらあら記者さん。何時から貴方の新聞は五流ゴシップ誌に成り下がっちゃったのかしら?」
「い、いや~、これは、その……」
「おやおやてゐ。みんなに仕事を押し付けて、一体何処で何をしていたのかな?」
「ひっっ、あの……か、堪忍して、ね?」
「ん~~? 最近の詐欺師は、性格だけじゃなく往生際も悪いのかい?」
いやいやと目を潤ませるてゐの体を抱え上げ、屋根の端の方につかつかと移動する。
「実はさ、昔から一度試してみたい技があったんだよなぁ……」
そして屋根の端まで辿り着き、てゐのお尻を高々と抱え上げる形で、変型パワーボムの体勢に入る。
(ttp://www.sumire.sakura.ne.jp/~ruriruri/nazenani/aoi/image/ore/last%20ride.jpg※例によって、良い子は絶対に真似しないで下さい)
「ちょっ! タンマ、それセクハラっっ」
「はっはっはっ!! 喰らえ男の憧れ、屋根からラストライド!!」
そのままの高さから、先程作り上げた雪垣の向こう側目掛けて、渾身の力で叩きつけた。
「てっ、ていかああああああああっっ!!?」
――ぼすんっっっ。
くぐもった音を立てて、深く積もった雪の層に兎型の大穴が出来上がった。
「……ふっ、上がったり大明神。……Rest in peace……」
格好良くキメて後ろを振り向くと、あちらの方もまたどえらい事になっていた。
「ほら文、これで全部じゃないでしょう? 隠したフィルムとネガ、全部耳を揃えて出しなさい」
「そ、それだけは出来ま」
ぷすっ。
「ふああっっ!!?」
文と呼ばれた記者さんの抗弁が終わらない内に、これまた何処から出したのか彼女の腕に注射器の針が捻じ込まれ、一気にアンプルの中身が流し込まれる。
「あっ、あっ、あぁ…………」
「…………さぁて文、もう一度訊くわ。隠したフィルムとネガは?」
「ハイ、コレデ全部デス。ゴメンナサイ、永琳サマ。文ハ、イケナイ子デス」
……おいおい。
瞳孔をだだっ開きにして、壊れたロボットのような抑揚の無い声を出す文に、永琳は素敵過ぎて目を背けたくなるような笑顔を見せた。
「よろしい。でも、これだけじゃ私の気が済まないから、貴方も飛んで逝きなさい」
そう宣言すると、文の体を飛行機投げの要領で担ぎ上げ、俺が先程てゐを投げた位置までのっしのっしと歩く。
「…………はっ? わ、私は一体!?……って、何この体勢!! ちょ、永琳さん、待っ」
正気に戻った文が拘束から逃れようと必死に体を捻るが、先程の鍼や薬が効いているのか、まるで力が入らない様子だ。
「いいえ待たない。その糜爛した出歯亀根性、真っ白な雪で洗い流して来なさい!」
口上をキメた永琳は、その体勢から下半身のうねりを加え、プロペラ回転をつけて文の体を放り出した。
な、投げっ放しバーディクト(旧F5)……!!
「れっ、れすなああああああああっっ!!?」
――ぼすんっっっ。
俺がてゐを叩きつけた三メートル程向こうに、鴉天狗型の大穴が出来上がった。
流石は月の頭脳……惚れ惚れするほどに美しい、力学と腕力の結合技だ。
「……ふっ、天網恢恢疎にして漏らさず。さ、掃除も済んだし、戻りましょうか」
雪山に開いた大穴二つに背を向け、永琳と二人、勝者として花道を悠々と歩く。
※メインイベント:時間無制限 雪中生き埋めデスマッチ TAG
アンダー俺カー 5分18秒 ● 射命丸 文
バーディクトによる
八意 永琳 ○ 生き埋め葬 因幡 てゐ
――来週の新永遠亭プロレスも、どうぞお楽しみに!
…………んで、その日の夕飯。
「本当に何でも無いんですか? 結構いい雰囲気だと思ったんだけどなぁ……」
生き埋めの状態から不死鳥の如く復活した文が、蕎麦を勢い良く啜りながらしつこく食い下がってくる。
今日の晩ご飯はイナバの子達の不調もあって、多く作るのも簡単でさらに食べやすい、質素な山菜蕎麦だ。
暖を取るにはちょうど良く、消化にも良い、賢明な献立だと言えよう。
「と言うか、何で文まで一緒に食べてるのさ……」
今宵夕餉を共にしているのは、姫様に永琳、鈴仙にてゐという定番のピラミッドに、俺と文、加えて比較的元気なイナバの子数名、といった感じだ。
ダウン中のイナバの子達は、可哀相だとは思うが別室に隔離中である。
「細かい事を気にする男性はモテませんよ。それよりも、ね、ね、どうなんです? お二人さん」
「……まったく、貴方も大概しつこいわね。何でも無いって、何度も言っているでしょう?
昼間のアレは、頑張った労働階級に、雇い主からのちょっとしたご褒美」
……そう即座に上手い事否定されるのも、男として悲しいものがある。
少しムカついたので、この澄ました顔をギャフンと言わせてやる事にした。
「何だよ、誤魔化す事無いじゃないか。あの二人で熱く燃え上がった夜を忘れたのかい? 俺のラブリーナース」
「「ぶふぅぅー――――ッッ!!!」」
永琳と鈴仙が同時に吹き出した蕎麦が俺の顔面を直撃した。
……永琳は初めてだから兎も角、鈴仙は俺の顔に物を吹き付けるのが趣味なのだろうか。
「何するんだ二人とも、勿体無い」
食べ物を粗末にするなんてのは、犬畜生でもしないような愚劣極まる所業だ。
顔面にこびり付きまくった蕎麦を、手で掬って美味しくいただいた。
「なっ!? そ、そんなの食べるんじゃありません!!」
「し、師匠っ、落ち着いて下さい! 鼻からお蕎麦が出ています!……と言うか、二人とも何時の間にそんな破廉恥なっ」
無様に慌てまくる師弟の姿に溜飲を下げていると、唖然としていた文が我に返り、俺の袖をぐいぐい引っ張ってきた。
「ちょっと、やっぱりそういう関係なんじゃないですか!! 詳しい話、聞かせて貰いますよ?」
「いいよ。隠すような話でもない」
そっと目を閉じ、あの忘れられない夜を回想する。
「あれは先週、永琳の新薬の実験に付き合った晩の事だった……」
「……(わくわく)」
『え、永琳……熱い……苦しい……後生だから、解熱剤を……』
『あら駄目よ。他の薬とチャンポンにしてたら、実験の意味が無いわ。
……あぁ……凄い……貴方の体、どんどん熱くなってるわ……』
『なあ……五十度ってのは、人間が出していい体温なのか……?』
『ふふ、まだまだ。夜は永いわよ、ふ、ふふっ、うふふふふ…………』
「まったくもって、熱い夜だった……」
あの時の永琳の素敵な笑顔は、ちょっとやそっとの事では忘れられそうに無い。
熱帯夜の回想にうっとりとマゾい笑みを浮かべていると、文がプリプリ怒り出した。
「色気もへったくれも無い話じゃないですか!! 馬鹿っ、騙されたっ、私のわくわく返してっ!!」
「はっはっは可愛い奴め。別に最初から嘘はついていなかった筈だが」
「紛らわし過ぎます!」
からかい甲斐のあるパパラッチ天狗とギャースカ騒いでいると、永琳が冷たい瞳に怒りを孕ませながら俺の事を睨んでいた。
「……姫……彼を、この場で縊り殺しても構わないでしょうか」
「駄目よ。貴方が拾ってきたんだから、ちゃんと最後まで面倒見なさい。
……そんな怖い事言いながら、実のところ貴方も満更じゃないんでしょう?」
そう切り返して姫様は袖を口元に当てて、意地悪そうにほくそ笑んだ。
と言うか、犬扱いか俺は。
「なっ!……わ、私はそのような……」
無二の味方である筈の主君の裏切りに、うろたえた永琳の頬が一瞬で赤く染まる。
「……あらら、結構奥手なんですね。天才薬師の意外な弱点発見です」
「そうなのよそうなのよ。いい歳してみっともないったら」
「ははは、あの良さが分からんとは、お子様だなぁてゐは。そこがまた可愛いんじゃないか」
「そうですよねぇ。ギャップが新鮮です」
――がたんっ!!
文とてゐと三人で言いたい放題うんうん頷き合っていると、突然猛烈に立ち上がった永琳に、まとめて襟首を掴まれた。
「……ふ、ふふ……ここまでの屈辱、ちょっと記憶に無いわ…………貴方達、ちょぉっとお仕置きが必要なようね?」
顔は笑っているが、目から殺気光線が迸りまくっている。
「……あ~、永琳さん? 暴力反対ですよ?」
「そうよそうよ。図星指されたからって大人気無ぐふっっ!」
懲りないてゐの鳩尾に、容赦無く永琳の爪先がめり込んだ。
「……こ、怖ぇ……」
――ずるずるずるずる。
蟹のように口から泡を吹いているてゐと文と三人、ズルズルと部屋の外へ引き摺り出される。
「……さあ貴方達……特別に、馬鹿につける薬を処方してあげるわ!」
屋上 アポロ三発
――ちゅどどどどどどどどー―――んっっっ。
「「「うっひゃああああああっっ!!?」」」
「……平和ねぇ……」
「平和ですねぇ……」
「それにしても永琳ったら、あんなにムキにならなくてもねぇ……」
「結構お似合いだと思うんですけどねぇ……」
そんな姫様と鈴仙ののどかなやり取りが、弾幕飛び交う修羅道に投げ出された俺達の耳に届くような事は無かった……
…………
~ February ~ ――だけど、全ての人は迷い迷い、心の欠けを補う何かを探しながら、その命の旅路を半ばにして終える。
暦は如月。一頃よりは大分過ごし易くなったとは言え、まだまだ厳寒真っ盛りといったところだ。
つい先日、八雲藍と名乗る、スキマ妖怪の式とか言うお狐様と初めて顔を合わせた。
「来月には目を覚ますと思うから、申し訳無いが、もうほんの少し辛抱してくれ」
そう謝りながらしきりに頭を下げてきた藍さんに、永琳がそっと胃薬を差し出す風景は、実に感動的なものだった。
しかしよくよく考えてみると、もし何の紛れも起きなければ、俺はとうの昔にスキマ妖怪とやらの肥やしになっていた筈で……
こうして無事に生き延びて、多くの人達に助けられながら楽しく暮らせているのは、僥倖だとしか言い様が無い。
……藍さんの「来月には目を覚ます」という言葉が、不快を伴った靄となって胸中を満たす。
あと一月。
あと一月で、この奇跡のような生活ともお別れなのだ。
取り敢えず、餌にされそうになった事については断じて許す訳にいかなかったので、
藍さんにお土産として渡した散らし寿司を、俺のボロパンツを繋ぎ合わせて作った風呂敷で包んでおいた。
いい事をした後は、やはり気分がいい。
一月先の別れを今から思い悩むよりも、まずは今日が良い一日になる努力をするべきなのだ。
今日も一日、頑張ろう。
「永琳、今日は久々に妹紅で遊んでくるわ」
朝食を終えて箸を置くなり、姫様がそんな事を言い出した。
「あら。それならお供しますよ」
「要らない。何気に今年の初顔合わせだし、偶には一人で羽を伸ばしたいわ。お昼には戻るつもり」
これは珍しい……と言うか、姫様が単独で行動しているところを、少なくとも今日まで俺は見た事が無い。
「そうですか……くれぐれも、お気を付けて下さいね」
「もうっ、つくづく思うけど、永琳は心配性ね。……大丈夫よ、私達何があっても死にはしないんだから」
何だか姫様の物言いに引っ掛かるものを感じたが、それよりも気になる事があったので訊いてみた。
「あの、『もこう』って?」
「友達よ、友達。それはそれは永い腐れ縁」
「…………」
からからと笑う姫様に、無言で湯呑みを傾ける永琳。
食器の片付けをしている鈴仙やイナバの子達が、不安げに視線を俺達の方に彷徨わせている。
……何だろう、この変な雰囲気。
後方で、てゐが食後の腹ごなしに太極拳を舞っているが、多分それは関係無い。
「姫、少し不用意ですよ」
「別にいいじゃない。私はこの人ともう少し仲良くなりたい。
だと言うのにこの馬鹿、普段は何かと慇懃無礼な癖に、こういう美味しい肝には絶対自分から食い付いて来ないんだもの」
「……それは当たり前でしょう」
無理矢理他人の傷み腹を突付くような趣味は無い。
そんな俺の及び腰な返答に、姫様はお得意の意地悪な微笑を見せた。
「そうね、そのメリハリの利いた距離感は貴方の美点でもある。
……でもね、そうして地を這っているだけじゃ、雲の彼方に浮かぶ宝物は永遠に手に入らないわよ」
「む……」
それは一理ある。
何時までも気を使って腰を引かせていては、確かに深く相手を知る事は出来ない。
……構わないから、もう少し踏み込んで来い、という事か。
先程の会話から察するに、姫様の台詞に何か糸口があったようなので、検証してみる事にした。
「むむむ……そうか!!」
「ど、どうしたのよ。急に大声出して」
お茶のお替りを用意してくれていた鈴仙が、俺の大声にビクリと体を震わせた。
「どうやら俺達はとんでもない思い違いをしていたようだ……鈴仙、先程の姫様の台詞を思い出してみてくれ」
「? ええっと、確か……」
『もうっ、つくづく思うけど、永琳は心配性ね。……大丈夫よ、私達何があっても死にはしないんだから』
↓
『 っ く く 、永琳は …… 私 が も んだから』
↓
『っくく、永琳は……私がもんだから』
「つまり、永琳の胸は姫様が揉んであそこまで大きくしたという事だったんだよ!!」
「「「な、なんだってー!!」」」
イナバの子達から一斉に驚愕の声が上がり、
「んな訳無いでしょう!!!」
――どごんっっ!!!
永琳の蹴りが俺の延髄をブチ抜く音が、それを上回る大音量で響き渡った。
「かっ……」
体の髄を打ち抜く大衝撃に、目の前に大銀河が展開される。
「あ~らら……それじゃ、私は行って来るからね~~」
「……ボ、ボン・ヴォヤージュ……」
姫様の声を遥か遠くに捉えながら、あっと言う間に俺の意識は成層圏の彼方へと旅立って行った。
…………
さて、お昼までには戻るとか言っていた筈の姫様が、昼食の支度が終わったにも拘らず帰って来ない。
「どうしたんだ、姫様は? 今更反抗期とか言う歳でもあるまいし」
「万年反抗期と言う気もしなくは無いけど……」
俺の危惧に、鈴仙がなかなかに的を射た返事を寄越してきた。
「う~ん、大丈夫かな? 永琳」
「そうねぇ……」
人差し指でこめかみを叩きながら生返事をすると、永琳は一つ力の無いため息をついた。
「……いいわ、迎えに行きましょう。貴方も付いて来なさい」
「俺も?」
「ええ。……最初から、こうなりそうな気はしていたのよねぇ……」
…………
永琳に襟首を掴まれた状態で竹林の上空を吊られ漂う事数分、程無く非常に分かり易い異常地帯を発見した。
視界の限りを埋める竹林に、クレーターのようにごっそりと抉られた一角があった。
「あれか。存外近かったわね」
「よ゛……よ゛か゛っ゛た゛……」
いい加減脳への酸素の供給が不足してきており、もう少しで首吊り人形に成り果てるところだった。
「うわ……酷いなこりゃあ」
降り立った場所の有り様を表現するのは、その一言に尽きた。
辺りの竹はぼろぼろに焼け落ち、露霜の名残を受けて湿っていた筈の土壌は、乾いた焼け土と化していた。
「ええっと、姫様は何処だ?」
「この辺りに居る筈だけど……」
きょろきょろと二人で辺りを見回していると、永琳がある一角を指差した。
「あ、居たわ。……ふむ、今日は姫様の勝ちかしらね」
永琳の指差した方に、確かに人影が二つ転がっていたのだが……
「げっ!!? な、何だよアレ!!」
「何だよって言われても……姫様と妹紅だ、としか言い様が無いわね」
上半身の右半分を無くした姫様が、地べたに座りながら、俺達に向かって笑顔で残った左手を振っていた。
「お~~い、こっちこっち~~……」
「ふむ、自分で動ける程度には元気みたいね。何よりだわ」
「……アレは元気と呼んでいいのか……よく見たら、左足も膝から下辺りから無くなってないか?」
遊びに行ってあんな風になるとは、どんなダイハードごっこだ一体。
「細かい事は気にしないの。妹紅のあの姿に比べれば大分良心的でしょう」
永琳の指し示す先に、下半身だけになったモンペ姿が転がっていた。
「う~ん……これ、夢じゃないよねぇ……」
「夢も現も、所詮は何処かの誰かのちっぽけな妄想に過ぎないのよ。ほら、行きましょう」
「あ、ああ……」
俺達が辿り着くと、姫様は血の気の失せた蒼い顔をしながらも、容態にそぐわぬあっけらかんとした顔で笑った。
右肩から先は焼け落ちたような感じで無くなっていて、傷口の周辺や頬が、ケロイド状に焼け爛れている。
「遅くなっちゃって御免なさいね。蘇生に廻せる余力が無くて、動けなくなっちゃった」
「どうせそんな事だろうと思ってましたよ。さ、帰りましょう」
永琳は苦笑と共に姫様の手を取り、ぼろ切れのようになった体をそっと背負った。
……月人の生命力って、凄いのなあ……
「……ねえ姫様? 帰るって言っても、アレはどうするんですか?」
血まみれでスッ転がっている下半身を、恐る恐る指差す。
葬式以外の場で死体を生で見るのは初めての体験だが、顔が無い分、まだ恐怖感は軽かった。
「放っておいて構わないわよ。時間が経てば、勝手に元に戻るわ」
「げ。これで生きてるのかよ」
脳も無くし、心臓も無くしたような状態で死んでいないって、妖怪ってのはつくづく恐ろしいものだ。
「誤解しないで。私達も妹紅も、間違い無く人間よ。
朝にも言ったでしょう? 何があっても死ねないのよ、私達」
姫様が、俺の率直な感想をからからと笑い飛ばしながら、何だかとんでもない事を言ってきた。
「はい? 死ねない?」
まるで噛み合わない、俺と姫様の何処か滑稽な問答に、それまで黙っていた永琳が、観念したようなため息をついた。
「……帰ったら詳しい話を聞かせてあげるわ。まずは屋敷に戻りましょう」
「そうして貰えると助かるわ。ここは地脈が悪いのか、いまいち力の戻りが悪い」
「分かった……その前に、これだけ」
結局顔を見る事の叶わなかった妹紅さんの亡骸の傍らに、お土産として持って来ていた冥菓・揉み痔饅頭を置いておいた。
現在人里の一部で大ブレイク中の、極悪スパイスぎっしり血便間違い無しのニクい奴だ。
「何かしら、それは」
「いや、姫様の友人に失礼があってはいかんと、用意して来たんだよ」
俺としては、この姫様の友人という希少種がこの銘菓を食べてどんな顔をするのか、是非とも拝見したかったのだが。
「律儀なものね。……ありがとう、私の顔を立ててくれて」
……姫様のこんな毒の無い優しい笑顔を、俺は初めて視た。
…………
「♪そ~ら~を自由に、飛~びた~いな~♪」
「……はいはい、胡蝶夢丸~~♪」
「♪アン、アン、アァン とっても上手ね エリえ~もん~~♪」
「…………ツッコみませんよ、俺は」
右肩から先と左足の無い姫様と、彼女を背負って飛ぶ永琳の楽しそうな歌声。
そして、永琳の両腕からぶら下がっているのは、相変わらず襟首から吊るされている俺。
こんな所を文にでも見られたら、さぞ面白い事になるだろうねぇ……
肌を刺すような寒空の下、正午より少し遅れて真上に昇った太陽の光が、瀕死でアンニュイな俺を慰めるかのように緩く照らしつけていた。
…………
屋敷に戻るなり、出迎えてくれたイナバの子達が、スムーズな連携で姫様を寝室に運び込んだ。
誰も慌てた様子がないという事は、今日みたいなケースはそう珍しい事でも無いと言う訳か。
姫様の事をイナバの子達に一任して、永琳は俺を自室に呼び入れた。
「いらっしゃい。座って楽にして頂戴」
「ん」
勧められるままに簡素な木製のスツールに腰掛け、永琳が作業机に背を向ける形で、二人向かい合う。
「……さて、何処から話したものかしら」
「どうせなら、全部聞きたい。永琳が俺に話しても良いと思う範囲で構わないから」
遠回しにとは言え、折角姫様から許しを頂いたのだ。
いい機会だから、この永遠亭の人達の事をもっと深く知りたい。
「そう……分かったわ、聞かせてあげる。
あの子が永遠亭に流れ着いて来てから、私が今日まで一日欠かさずつけて来た、『ウドンゲ赤裸々観察日記』の全てを!」
そう力強く宣言すると、棚から百科事典と見紛うばかりの極厚日記帳が取り出された。
「いや、その……今は君の劣情猥雑師弟愛列伝を聞きに来た訳ではないのだが……」
ある意味、激しく興味を惹く内容ではあるが。
「冗談よ、冗談。……さ、本当に長くて厭な話になるから、覚悟して聞いてね」
「任せろ。詰まらん話なら、俺は容赦無く寝る」
「そしてそのまま目覚める事はありませんでした、と…………さて」
軽口を叩き合うのを合図に、月と地球と幻想郷を跨いで幾重にも刻み込まれた傷痕が、永琳の口から謳い上げられた。
・
・
「…………というお話だったとさ…………ん~~~~~~っ」
本当に、本当に長い話を終え、永琳は可愛らしい唸り声を上げながら背を反らして、凝り固まった上体をほぐした。
聞かされた過去の重さに嘆息しつつも、俺は彼女の胸元が強調されるのをバッチリ見逃さなかった。
「さて、ご感想は?」
「おっぱ……じゃなかった、みんな苦労してるんだなぁ、と」
「……随分あっさりと片付けてくれるわねぇ……」
永琳ががく、と肩を落として苦笑を浮かべる。
「あぁ、違う違う。軽く言っているんじゃなくてさ。
昔苦労してきたから、今こんなに優しいんだろうなって思ったんだよ」
慌てて付け足した俺の弁明に、永琳はぱちぱちと、二回大きな瞬きをした。
「優しい? 私達が?」
「うん、永琳も姫様も鈴仙も、みんな優しい」
犯した罪の重さに悩み、痛みや悲しみに苛まれながら、こんな辺鄙な所まで流れ着いて。
それでもなお悩み、痛み、苦しみながら優しくなる事を選んだ、この永遠亭の強い人達が、俺は大好きだ。
「……呆れた。怖くなったとか、軽蔑したとか、少しは思わないの?
今貴方の目の前に居るのは不死身の化け物で、おまけに大量殺人犯よ?」
「思わない。そりゃ犯した罪は何を以っても贖えない、死ぬまで背負って行くべき十字架だろうさ。
でも、同じ過ちを二度繰り返すような馬鹿は、ここには居ないだろ?
今俺の目の前に居るのは命の恩人で、おまけにとても優しい素敵な人だ」
「……」
――すっ。
俺の言葉を詭弁と咎めるかのように、永琳のたおやかな人差し指が、音も無く隙の無い所作で俺の喉元に突きつけられる。
「分からないわよ? 貴方が私達にとっての不具合になれば、今すぐにでもこの指が貴方の首を掻き切るかも知れない」
眼前の厚顔無恥な人間を嘲るように吊り上げられた唇から、おおよそ感情の覗えない淡々とした音が漏れた。
「姫様を逃がした時と同じように?」
「そう。月の使者達を謀り陥れ、鏖殺した時のように」
……馬鹿馬鹿しい。
永琳が見せる外敵に対する容赦の無さは、身内への愛情の何よりの証なのだろう。
それなら、俺が彼女を恐れなければならない理由など、微塵も無い。
「いい加減にしろ馬鹿。俺は何があっても永遠亭の、君の味方だ」
出来る限りに強く言葉を放ち、突きつけられた彼女の手を、右手で強く掴んだ。
「っ…………何を……」
先月の雪掻きの時、永琳は自分の事を『左道に外れた外道』と評し、
また、自分が『生きている』と表現して良いか分からない、という風な事も言っていた。
「なあ永琳。ある程度自覚しているとは思うけど、あまり自責が過ぎるのも良くないぞ。
顔を合わせて一月程度しか経っていない、しかも今日初めて事情を知った俺がこんな事を言うのもアレだけど、
もう姫様も永琳も、十分に罰を受けたと思うんだ」
鈴仙もてゐもイナバの子達も、やがて時間の波に呑まれて永琳や姫様ら蓬莱人を追い越し、彼女達を残して朽ち消えていく。
得たものを時間と共に亡くし置いて行かれて、新しい思い出を手に入れる度に心太のように古い思い出はこぼれ落ちて。
それをただ眺めるしか出来ず、成長する事も退化する事も出来ず、永遠にその場に留まり続ける事しか出来ない、魂結びの牢獄。
この人達は、気が違いそうな程の永い間、こんな自壊してしまいそうな悲しい在り方を強いられてきたのか。
……あんまりじゃないか。
「ちょ、ちょっとどうしたの。いきなり泣いたりして」
「はい?」
永琳に言われて自分の頬に手を当ててみて、初めて気付いた。
……何だよ、俺、泣いてたのか。
残った左手で、慌てて目元を拭い取る。
「…………」
「あ~、悪い。こりゃみっともないや」
「……馬鹿ね。みっともなくなんて無いわよ」
永琳は初めて聞くような優しい声色でふんわりと微笑むと、
先程からずっと握ったままの右手はそのままに、残った左手を俺の頬に添えてきた。
「ありがとう。私の為に泣いてくれたのは、ウドンゲに続いて貴方が二人目。
……でもほら、私の手、ちゃんと温かいでしょう?」
「…………ああ」
寒気に中てられ冷えた手の平の内から、確かな命のぬくもりが沁みてくる。
「貴方が心配してくれなくても、ちゃんと私は自分が生きているのを実感している。
……そうね、以前使った表現は適切じゃなかったわ。
私達は道を外れてしまったのでは無くて、ただ蓬莱の薬に縛られて時間の渦に乗れないだけ」
「そうだな。永琳も姫様も妹紅さんも、俺達と同じだ」
昼間に姫様が言っていた事を思い出す。
『私達も妹紅も、間違い無く人間よ』
同感だ。
左道に住まう畜生鬼の手の平が、こんなに温かい訳あるものか。
「それにね? 確かに淵源は自責の念だったけれど、私は何もそれだけを理由に今の生活を選んだ訳じゃない。
姫様と此処に来てから過ごした、今日までの時間を切り出せば、私は間違い無く幸せだったと言えるわ」
「……そっか」
「ええ。……いい機会だから、もう一つぶっちゃけちゃいましょうか。
皆が私を慕ってくれているのと同じ程度には、私もこの永遠亭の人々を愛してる」
「…………そっか」
良かった。
全面的に鵜呑みにして良い言葉では無いが、少なくとも偽りでない事は、目の前の柔らかな笑顔を視れば分かる。
本人が幸せだと言っているのだから、ただの客分でしかない俺がこれ以上言える事は無い。
んで、気が緩んだ拍子に悪戯心が芽生え、
「じゃあさ、俺の事は?」
……うっかりこんな事を口走ってしまった。
「へっ?」
素っ頓狂な声を上げると、永琳は穏やかな笑顔から一転、目を見開いて白黒させた。
「そっ、そそそそう来るとは思わなかったわ……」
先程の優しいお姉さんチックな出来た風格は何処へやら、顔を真っ赤にしておろおろと狼狽している。
これはこれで可愛いと思うので、俺としては何ら問題は無い。
「あ、あのね? 貴方の事もそれなりには気に入ってますけど、それはその、ね。……あぁ、困ったわ……」
どうでも良いが、未だに繋いだままの手をブンブン振り回すのは、俺の肩が今にも外れそうなので勘弁して頂きたいと思う。
周りの雰囲気が何時の間にやら平時の緩いものに戻っているのを感じ、体の力を抜くと、
――ぎしっっ。
「「?」」
襖の向こうから、床板が軋む音と、幽かな話し声が聞こえた。
永琳と二人、耳を傾けてみる。
『あーもうっ、何やってるのよ永琳は! 薬学や術理ばかり達者で、自分の色恋沙汰にはてんで空っ下手なんだから』
『姫様ぁ、やっぱり良くないですよ、こんな覗き見だなんて……』
『黙らっしゃい! 折角私がこんな痛い目見てまで切っ掛け作ってやったってのに、何よあのヘタレ薬師!
大体彼の方も、何でそこで一気に押し倒さないのっ!! ひょっとして、EDか性病持ちなんじゃないの?』
『ちよっと姫、何言ってるんですか! イナバの子達も居る前で、そんな下劣な……』
『……ねぇねぇてゐちゃん、EDって何?』
『それはね、あいつの×××が××で×××だから役立たずって事でね、
永琳様の×××に××して×××××したりするには不適切って事なの』
『子供に詳細な説明をするな馬鹿てゐ! あ、貴方もそんな事不用意に訊かないのっ』
『え~っ、私子供じゃないもん。大人の魅力で、お兄ちゃんの事メロメロにするんだもん』
『あらあらあら、これは強敵出現ね。彼も隅に置けないこと。永琳も前途多難だわ』
『……あ、頭痛くなってきた……』
『そんな事より、二人ともこっちの方を見ている気がするんですが』
『あら、ひょっとしなくてもバレちゃったみたいね。みんな、退散よ!』
「…………殺るか」
「…………ええ」
永琳は作業机の引き出しを開くと、中に隠されていたスイッチを、
「ポチッとな」
――ぶしゅうううううううううっっっ。
スイッチが軽く鳴った瞬間、廊下の方から激しいスチームの噴射音が聞こえた。
『ぐっ、げほっげほっ、一体何なの、これっ』
『な、何だか気が遠く……』
――ばたばたばたっっ。
『ちょっ、ちょっとみんな!?
くっ、恐るべし月の頭脳。何時の間にこんな仕掛けを……
しかし詰めが甘いわね。私達蓬莱人に毒は効かないっていう初歩をお忘れかしら?』
――わらわらわらわらっっ。
『あら? イナバたち、もう起きたの?……って、きゃああああっっ!!?
なっ、何でみんなそんな紫色の肌で私に詰め寄って来るのっっ!!?』
『『ガ、ギ……ヒ、ヒメサマ……ヒギル……』』
――ぐちゃっ。ぬちゃっ。めりめりめりっっっ。
『ひっ、ひぎいいいいぃぃぃぃぃっっ!!?』
『『『らっせーらっ、らっせーらっ』』』
「うわぁ……」
襖に映る姫様やイナバの子達の影絵が、何やら生物学的にあり得ない形状になっているが、
基本的に自業自得なので気にしてはいけない。
「……あぁ、滅多に聞けない、姫様の珠玉の悲鳴……優曇華の花待ち得たる心地とは、まさにこの事ね……」
「月人の愛情って、随分歪んでるのなぁ……」
※メインイベント:時間無制限 永遠亭内変則タッグタシーロマッチ
ED性病男爵 1時間53分48秒 ● 蓬莱山 輝夜
バイオハザードによる with
八意 永琳 ○ イナバーズの裏切り イナバーズ
――来週の新永遠亭プロレスも、どうぞお楽しみに!
…………
「……と言う訳で、私は永琳と彼を是非くっつけたいと思います」
あの思い出したくも無い馬鹿騒ぎの後、姫様は珍しく私だけを自室に呼びつけて、そんな事を言ってきた。
「姫様も、懲りませんね……」
今私の眼前に在らせられる麗しの姫様は、全身をぞんざいな継ぎ接ぎと包帯まみれにして、ミイラの出来損ないみたいになっていた。
「これしきで懲りてなんかいられますか。大体永琳は、自責と自戒が強すぎる。
昔っからこうなのよ。何に於いても私より上にあってはいけない、私より幸せになっちゃいけない、って」
「……そうですね」
それは、端から二人の関係を見ていてもよく分かる。
師匠は常に己を抑え、後方から姫様を立てる事しか考えていない。
「ありがたい気構えではあるけど、度が過ぎると私が足枷になっているみたいでいい気はしないわ。
今回だってそう。折角いい拾い物したんだから、逃がす手は無いって言うのに」
「姫様は、また随分彼の事を気に入られたのですね」
「そうね。相当極まった変質者ではあるけど、肝は据わっているし、何より懐が深い。
イナバ達の彼への懐きようったら、無いでしょう?」
「はい。子供達なんかは、もうベッタリですね」
最近は『ぷろれすごっこ』とやらが主流らしく、この前庭で遊んでいるのを見かけた時には、
彼がてゐにせがまれて肩車をしようとした所を、見事にフランケンシュタイナーで返されていた。
あの後、怒り狂った彼がアックスボンバーでてゐの体を一回転させたシーンは、ちょっと忘れられそうに無い。
「……確かに、本能で動く彼と理屈で動く師匠、って言うのは良いバランスですよね。
二人とも何気に行動力は抜群なんで、手が付けられなさそうです」
「そうそう。永琳みたいな理屈屋には、あれ位奔放な馬鹿がちょうどいいのよ」
ここ最近というもの、師匠は今までに私が見た事の無かった表情を幾つも見せている。
それは間違い無く、外から来た彼が引き出したものだ。
「……うん、師匠と彼がそういう仲になってくれたら、私も嬉しいです」
「でしょう? まったく誰から見ても丸分かりだって言うのに、永琳も何を意固地になって否定しているのやら」
……それは、貴方やてゐが面白がって弄繰り回すからではないかと……
心の中でツッコミを入れた私を尻目に、すっかり姫様は盛り上がってしまっている。
「もうこのまま放っておいたら、春まで何事も無く彼は外の世界に帰ってしまうわ。
ここは私達で何か手を打ちましょう」
「はぁ、それは良いのですが……具体的にはどのような?」
「それは、貴方が考えなさい」
こ、このグータラ姫は……!
肝心な所で役に立たないダメ主君に憤ってみたが、すぐにそれを打ち飛ばす妙案が浮かんでくれた。
……今月は二月。
もうほんの数日経てば、こういう色事に打って付けのイベントがあるではないか。
つい最近まで隠れて生活していた事、それに女所帯という事もあって通年は歯牙にも掛けなかったイベントだけど、今年はそうは言っていられない。
思い立ったが吉日、こんな所で姫様とチンタラ遊んでいる場合ではない。
「頑張ってね~~」
「うるさい、働け!!」
ニコニコと手を振る竹取ミイラ姫にうっかり本音を浴びせつつ、私は師匠の部屋に急いだ。
…………
――すぱー―――んっっ!!!
「師匠ッッ!!!」
「わっ。……ウドンゲ? 驚いた、声くらいかけなさいな」
「そんな悠長な事言ってる場合じゃありません!
……はい師匠、問題です。二月十四日は何の日ですか?」
「何よいきなり、変な子ね。…………う~ん、二月十四日ねぇ……」
何処ぞの捻くれトンチ坊主のように、師匠は指でポクポク頭を叩きながらしばし瞑目すると、
「あぁ、はいはい。ジェームズ・クックが航海中、ハワイの原住民に殺害された日ね」
ダ、ダメだこの人。
「なっ、何でわざわざそんなキツい所を引き出すんですか!」
「冗談よ、冗談。バレンタインでしょ、聖バレンタインデー。
……それがどうかしたの?」
「どうかしたの、って……師匠は、彼に何かあげないんですか?」
「…………そういう事か。……私個人からは何かを贈るつもりは無いわよ」
「ええっ!? そ、そんなっ。チョコにお得意の薬を混ぜて篭絡したり、
全裸にリボンを巻いて『うっふん、プレゼントはワ・タ・シ』とかやる大チャンスじゃないですか!!」
「ウドンゲ……いい物あげるから、少し落ち着きなさい」
――ぷすっ。
「うっ」
首元に痛みも無く注射針が刺さり、一瞬で中の液体が流し込まれる。
「あっ……あぁ……」
「……落ち着いたかしら?」
「う、うぅ……ごめんなさい師匠……鈴仙は……鈴仙は、悪い子です…………」
「ありゃ、効き過ぎたわね。……ふむふむ要改良、と」
何とも抗い難い憂鬱な気分に襲われ涙をはらはらと流していると、師匠が私の額を人差し指で軽く小突いてきた。
「あ痛っ」
「馬鹿ね。私個人からは、って言ったでしょう?
……当日は皆でね、イナバの子達も全員入れて食べられる位のケーキを作ろうと思っているのよ」
「ケーキ、ですか?」
「ええ。その方が彼も喜ぶんじゃないかしら」
「……はぁ……」
卑怯な逃げ方だ、と一瞬思ったけど、そうかも知れない、とも思った。
以前、食事中に彼とした会話を思い出す。
…………
『モグモグゴクゴク、あ~今日も美味いやムシャムシャ』
『……ホント貴方って美味しそうに食べるわね……そんなにここのご飯は美味しい?』
『ああ、最高だ。こんな沢山の人達と一緒に笑いながら食べるご飯が、不味い訳が無い』
『……そう』
『そうなの。モグモグ……ぶはああぁぁぁっっ!!! 不味うううううっっっ!!!
だ、誰だこの餃子作ったの!! この死臭漂う大珍味は、流石の俺にもフォロー不可能!!』
『あら、私特製のワサビ納豆蜂蜜餃子はお気に召さなかったかしら』
『またアンタか姫様!! 折角いい腕してるんだから、ネタに走るの止めて下さいよ!』
『オホホホお断りよ。あぁ、これだから人の幸せをぶち壊しにするのは止められないわぁ~~』
『ぐっ、主君の過ちを糺すのも臣下の務め! その大外道、最早捨てては置けぬ!!』
『あらら、私に是非を問おうと言うのね、賤しき地の民が。面白い、表に出なさい!!』
『望むところ!! 当方に人間の尊厳あり!!』
―ーちゅどー―――んっっ。
…………
「…………」
随分と不要な事まで思い出してしまったけど、確かに彼には、団欒を非常に貴ぶ気質がある。
……私達と同じように、彼にもそれなりの過去や思想があると言う事かな。
「……そうですね。いい案だと思います」
私達外野があれこれ手を焼いてみたところで、結局どういう道を選ぶのかは師匠と彼、当人達次第だ。
今回の事だって、師匠なりに彼の事を想ってこういう選択をしたのだろう。
「そう……それじゃウドンゲ、明日は一緒に里や紅魔館に行きましょうか。
材料の買出しと、あと調理器具を借りないとね」
「はいっ。みんなで飛び切り美味しいケーキを作りましょう!」
私の自慢の師匠と、その師匠の眼鏡に適った人だ。
心配なんてしなくても、きっと最高の選択をしてくれるだろう。…………多分。
…………
さて、今日は二月十四日。
俺の敬愛する、藤島親方(元大関・武双山)の誕生日だ。
聖バレンタインデーとか言う行事など、見た事も無いし聞いた事も無い。
昨晩悶々としてしまってなかなか寝付けず、うっかり昼前まで豪快に寝過ごしてしまったのは、
『ひょっとして今年は』などと期待に胸を躍らせていたという惰弱な理由からでは断じて無い。
……ホントだよ? ホントだよ?
…………さあ今日も一日、張り切って行こう!
――すぱー――んっっ!!!
「おはようみんなっっ!! 今日って何月何日だったっけ!!?」
勢い良く大広間の襖を開いたが、珍しく中はもぬけの空だった。
「……あれ? 誰も居ない?」
どでかい広間に、俺の物であろう朝食の残りらしき膳が一つ、ぽつんと置かれている。
そう言えば、俺の部屋からここに来る間も、誰とも顔を合わせる事が無かった。
「……ふむ」
まあこればかりは寝坊した俺が悪いので、膳の前に腰を落とし、遅い朝食を頂く事にした。
「…………」
齧り付いた卵焼きは、今日も複雑に味の染みた良い出来だったが、いつもと比べてどうにも味気無かった。
…………
「……で、一体何なんだこれは」
一人寂しく朝食を終えた後、人影を求めて屋敷を彷徨っていた訳だが。
調理場に差し掛かる廊下に掲げられたバカでかい看板を前に、俺は立ち往生していた。
『男子この場より先に足を踏み入れるべからず』
「……」
廊下の向こう、調理場の中から、何やらわいわいとイナバの子達が楽しそうに騒ぐ声が聞こえる。
要するに、今日は永遠亭のみんなで何かを催していて、俺は除け者にされている訳か。
ムカついたので、看板の頭に『美』の文字を入れておいた。
『美男子この場より先に足を踏み入れるべからず』
「……そこまで言われちゃ、仕方が無いな」
まあ、こういう日もあるだろう。一人で燻ぶっていても仕方が無い。
この時間、屋敷の近辺なら危険も無いだろうし、たまには外へ羽を伸ばすとした。
…………
「う~~、寒い。それにしてもこの辺りって、本当に竹や野草しか無いんだな」
それなりに長い距離を歩いた気がするが、基本的にある程度拓けた一本道しか通っていないので、帰りに迷う事も無いだろう。
竹の葉の隙間から降り注ぐ暖かみを孕んだ陽光に、来たる春の兆しを感じる。
……もうすぐ冬が終わり、春が来る。
「…………はぁ」
一つ、気だるく白い息を吐く。
本来なら歓迎すべき新たな季節の訪れを、どうにも快く迎える事が出来ない。
何時の間にか、この幻想郷で……否、永遠亭で過ごしたほんの短い日々は、
二十数余の年月を過ごした外での暮らしと天秤に掛けても遜色が無い程に、俺の中で掛け替えの無い物になっていた。
ここには、甘えを叱責し、生きる糧を与えてくれる主君が居る。
ここには、孤独を埋めて胸を満たしてくれる優しい人達が居る。
……ここには、誰より傍に居て欲しい、何より愛しい人が居る。
何をとって考えても、外の世界では手に入らなかったものばかりだ。
こちらを選んでしまうのが、一番良い選択肢のように思える。
だけど、今日まで幻想郷で得た物は、全て客人として得た物であって、あくまで俺は『外から来たお客様』に過ぎない。
家族との絆、過ごした時間、沁み付いた習性。
そうした外の世界との繋がりに当たるような何かが、今の俺と幻想郷との間には無かった。
「……何がしたいのか、何が欲しいのかね、俺は……」
宛ても無く一人ごちて、空から前方に落とした視線の先に、一人の少女がこちらの方に歩いて来る姿を捉えた。
……まずいかも知れない。
妖怪の見た目からその能力、性質を判断出来ないというのは、何処より永遠亭で思い知らされている。
万一の事態に備えて持ち出しておいた発炎筒を、そっと懐から取り出した。
少女の方もこちらの方に気付いたらしく、気負った風も無く、悠々とこちらに歩みを進めて来ている。
「……南無三っ」
発炎筒のフックに指をかけ、力を込めた。
軽い抵抗と共に、火付けのフックが一気に引っ張り出され、
――ばっっ。
「んなあっ!!?」
発炎筒からフックに伸びた紐に色鮮やかな万国旗が姿を現し、辺り一帯を紙吹雪が舞う。
万国旗の中の一枚に、可愛らしい兎のイラストと共に、こんな事が書かれていた。
『かかったなアホが! byプリチーお宇佐様』
「ふっ、ふざけるな馬鹿野郎!!!」
何の役にも立たなかった発炎筒もどきを思い切り地面に叩きつけて憤慨していると、すぐ傍まで来ていた少女が呆れた声を出した。
「……何やってるのさ、アンタ」
右手から下がった籠には、食用の野草。
その少女は、何処かで見たようなモンペにサスペンダーという、一風変わった出で立ちをしていた。
…………
「へぇ、外から来たの。大変ねぇアンタも」
先程の醜態から敵意が無いのを感じてくれたのか、あの後妹紅さんは、俺を竹林の中の掘っ立て小屋に案内してくれた。
「まあゆっくりしてよ。何も無い所だけどさ」
「悪いな、お邪魔させて頂くよ、妹紅さん。」
「はは、妹紅でいいよ。……はい、出涸らしだけど」
「……ありがとう。頂きます」
目の前に置かれた湯呑みに手を伸ばし、散歩で乾いた喉を潤した。
最初はもっとおっかない人を想像していたのだが、いざ話してみるとまったく普通の女の子で、少々拍子抜けした感じだ。
「この前はお土産ありがとうね。あれ、アンタでしょ?」
「あぁ、あれか。どうだった?」
「うん、気に入った。お陰様で、私の火力も一割増しってもんよ」
「そうか……」
あの極悪冥菓を喜んで食べるとは、流石は姫様の旧知だけあって、なかなかの変態のようだ。
「……何か失礼な事考えてる?」
掲げられた人差し指に、ぽ、と一つ火の玉が灯る。
「いやいや滅相も」
慌ててもう一度湯呑みを啜ると、誰かが入り口の引き戸を開く音が響いた。
「――妹紅、居るか?」
「あぁ慧音、いらっしゃい。入りなよ」
慧音と呼ばれた来訪者の顔には、見覚えがあった。
向こうの方も俺の事を覚えてくれていたらしく、俺の姿を視止めて目を丸くした。
「あれ、お前は確か、永遠亭の……」
「覚えていてくれたんだ。あの後どうだった?」
彼女は先月の半ばに一度、永遠亭を訪れて大量の風邪薬を買って行った事があった。
「あぁ、お陰で助かったよ。
まったく、一人罹ってしまえば拡がるのはあっと言う間だから、風邪と言うものは困る」
「何だ、二人とも知り合いだったの。……ね、慧音。その袋、何?」
「これか? 森の古道具屋に寄ったら、何やらチョコレートの駄菓子が沢山置いてあってな。
お茶請けに良いと思って、少し多めに買って来た」
そう言ってその場に置かれた袋の中には、懐かしの天使vs悪魔なシール入りウェハースチョコがぎっしりと詰まっていた。
……あぁ……遂にこのチョコも幻想郷送りになったのか……
「じゃあお茶請けが増えた所で、仕切り直そうか。アンタも一緒するでしょ?」
「ふむ……それじゃ、遠慮無く」
立ち上がった妹紅に空になった湯呑みを渡し、袋の中のチョコに手を伸ばした所で、
「「そのチョコレート、待ったあああああ!!!」」
――どがああああんんっっ!!!
入り口の戸をショルダータックルで粉々に吹き飛ばしながら、突然姫様とてゐが乱入して来た。
「な、何事だ!?」
「げっ! か、輝夜っ!? アンタわざわざ私の家まで、何しに来たのよ!!」
「お黙りなさいこの泥棒もこ!! 貧相な芋娘の分際でウチの客分を誑かそうとはいい度胸ねぇ。
生憎そいつはウチの薬師に売約済みよ」
「そうよそうよ。千年経っても脳味噌に皺一つ増えない炎上馬鹿と、牛乳臭いハクタクは引っ込んでなさい!
…………って、そこの彼も言ってるわよ」
「言ってねえ!!」
暴言の責任を俺に擦り付けようとするてゐを、思いっ切り一喝した。
「……一体何を言っているのか分からないけどアンタ達、人の家を壊した責任くらいは取って貰うわよ?」
先程までの穏やかな雰囲気から一転、妹紅は殺意のこもった赤い瞳で、姫様とてゐを睨み付けた。
「責任なんて面倒なもの、誰が取るもんですか!! 喰らえ先手必勝!!」
不意を突き、腰を落とした低い体勢で突っ込んだ姫様が妹紅の腰に食らい付き、テイクダウンを奪った。
「なっ……!」
そのまま蜘蛛の如く隙の無い動きで妹紅の背後から足と首を絡め取り、一気に絞り上げる。
「存分に味わいなさい! イナバ達と編み出した対蓬莱人最終奥義、
STF(ステップオーバー・てるよ・フェイスロック)!!!」
「ぐっ!?……ぎゃああああああっっ!!!
痛い痛いっっ、死なない程度に痛いいいいっっ!!!」
……まさに蓬莱殺し!
姫様の陰険な性格がよく滲み出た、非常に嫌らしい技だった。
妹紅の悲鳴に気を良くした姫様は、うっとりと無茶苦茶いい笑顔をしている。
「も、妹紅っ」
慧音さんが妹紅を助けに入ろうとするが、てゐが巧みに進路を妨害していた。
「ほらほら、あんたの相手は私、私」
「くっ……お前らっ……!」
姫様の極悪奥義を逃れようの無い角度で受けた妹紅が、涙目で苦しげな声を漏らす。
「……た、助けて、慧音……」
「!!」
――どくんっっ。
外まで聞こえるような確かな音で、一つ心臓を強く鳴らした慧音さんの頭から……
――めきめきめきっっ。
……二本の禍々しい角が生えてきた。
「げっ!?」
「呼ばれて飛び出て満月フォー――――ッッ!!」
まるで妖怪のような姿に成り果てた慧音さんが、両腕を高々と上げ、両足をクロスさせて、見事なXポーズをキメた。
「なっ!? な、何でこんな真っ昼間にその姿にっっ!!?」
姫様の驚愕の声に、慧音さんは不敵な笑みを浮かべる。
「よくぞ聞いた! 妹紅が私を求めて流した一粒の涙が、偶然にも満月光線と同じ光を放ったのだ!!」
「んなアホな……」
もうグダグダだった。
「お前に恨みは無いが、私の妹紅を救う為! そこを空けて貰うぞ白因幡!!」
「ひっっ!?」
――ぞぶっっ!!
神速のタックルにより、慧音さんの角がてゐの臀部を深々と貫き、その小さな体躯を高々と吊り上げた。
「ふ、ぐ、ぐぶぶ……」
見事に一本釣りにされたてゐが、白目を剥いてぶくぶくと口から泡を吹いている。
「う、うわ……えげつなぁ……」
「くっ、これは誤算だわ……ほら貴方っ、走りなさい!!」
「えっ? あ、ああ」
指示を受けた俺が外へ走り出したのを確認すると、姫様は妹紅を解放して飛び上がり、てゐを回収して脱兎の如く逃げ出した。
程無く俺に追い着いて襟首を掴むと、
「そぅれっっ、逃げるわよおおお~~~~!!」
ばびゅー―――んっっ。
そのまま高々と青空目掛けて飛び上がる。
「「に、二度と来るなああああ!!」」
下から大声で呪詛を上げる妹紅と慧音さんの姿が、みるみる小さく遠ざかっていく。
「…………ねえ姫様。俺を迎えに来てくれたのは分かるんですけど、もう少しこう、穏便には……」
「ふん、人が争うのに、大した理由なんて必要無いのよ」
「当人がそれを言うなよ……」
幻想郷で生きていくと言うのは、かくも厳しいものなのであった……
…………
――すぱー―――んっっ!!
「ただいま~。ちゃんと連れて帰って来たわよ」
「「ただいま~」」
元気良く襖を開いた姫様にてゐと二人で続くと、大広間の中からカカオとクリームの噎せ返るような甘い香りが漂ってきた。
「あら、お帰りなさい。どうしたの、てゐ。そんな変な歩き方して」
「いや、その、大丈夫だから、あはははは……」
「変な子ねぇ……」
俺達を迎えてくれた永琳は、いつもの服の上に薄ピンク色のエプロンという完璧な若奥様ルックをしていた。
「まあいいわ。ほら、準備はもう出来てますから、早く始めましょう」
「了解。ほら皆、今日の主役のお帰りよ~」
永琳と姫様の背中を押された先、広間の中央にホール型のケーキが五つ、どんと鎮座していた。
「……なあ、これって」
「ふふ、今日が何の日か、知らない訳じゃ無いでしょう?
永遠亭の一同から日頃の感謝をこめて、貴方にプレゼント」
「……そうだったのか…………ありがとう」
少し照れくさそうな永琳の言葉が、じわりと胸に沁みる。
俺は、除け者にされたなどと詰まらない事を考えた自分の心の貧しさを、猛烈に恥じた。
辺りを見回すと、イナバの子達が小皿とフォークを手に、ケーキの周りをそわそわと取り囲んでいる。
「お兄ちゃん遅~い!」
「何処行ってたのバカ! ノロマ!」
「もうこんな鈍亀放っておいて早く食べようよ~」
みんなありがとう! 俺嬉しいよ('A`)
今日って確か『ケーキ食べ放題の日』じゃ無くて、『女性が大切な男性にチョコを贈る日』だった筈だよね……
がっくりと肩を落としていると、永琳が苦笑いを浮かべながら手を叩いた。
「はいはい、皆待ち切れないみたいだから、始めましょう。
ウドンゲ、切り分けるから手伝って頂戴ね」
「はい。ほらみんな、並んで並んで。順番順番」
「「「は~~~い」」」
結局ホール五つ分のケーキはものの見事に分配され、みんなで仲良く分け合う事となった。
俺の知っているバレンタインとはこんなイベントでは無かった筈だが、
美味しそうにケーキを頬張るみんなの幸せそうな笑顔を見ていると、そんな些細な疑問はどうでも良くなる。
辺りいっぱいの笑顔を肴にケーキを頂いていると、ふと横合いから袖を軽く引っ張られた。
「ん?……何だ、どうしたチビ助」
俺の肘を摘んでいたのはイナバの最年少で、特に俺によく懐いてくれている子だった。
「ね、お兄ちゃん。美味しい?」
「ああ、美味しいよ。……ありがとう。みんなで頑張って作ってくれたんだろ?」
「うん……よかった」
頭をわしわしと撫でてやると、彼女は幸せそうに頬を緩ませた。
「えへへ……ね、お兄ちゃん」
「何だ?」
「ずっと……ずっと、ここにいてくれる?」
――ぴしっっっ。
場の空気が、一瞬にして凍りついた。
「「「……………………」」」
鈴仙や他のイナバの子達はフォークを咥えたままで瞬きさえ忘れて固まり、永琳は無表情でお茶を啜っている。
そもそもケーキに夢中で話を聞いていなかった姫様は、一人ご満悦な表情を浮かべていた。
自分の一言で周りの雰囲気が一変してしまったのを感じ取り、チビ助があたふた慌て出す。
「あ、あれれ? ねえ、私、何かおかしな事言ったかなあ?」
「…………いや、何もおかしな事は言ってないよ」
まったく、ありがたい話だ。
この程度の事で場がおかしくなる程度には、皆俺の事を気に掛けてくれているのだ。
「そうだな……ずっと居られたらいいな」
それこそ息を吐くような自然さで、そんな言葉が口を衝いて出てきていた。
「ホント? わぁ、嬉しい!」
無邪気に喜んで走り回るチビ助の姿に、ようやくみんなの口から安堵の息が漏れる。
……ずっと居られたら、か。
方便などではない、自分の胸底から自然に出た、偽りの無い言葉だった。
胸の内の天秤は、とうの昔にこの永遠亭の方に傾き切っている。
あとは、秤を今の位置で縛り付ける為の、俺と幻想郷を繋げる絆が欲しい。
「……色々な事を考える必要があるな」
「例えば、今日の永琳様のエプロン姿について、とか?」
俺の独り言に、てゐが横から茶々を入れてきた。
「ああ。エプロン一枚衣服が増えたのに、何でいつもよりエロく視えるんだろうな……」
「知ったこっちゃ無いわよ……」
思考の切り替えの圧倒的な速さが、俺の自慢の一つだった。
…………
~ March ~ ――だから、私が生きた世界のぬくもりを、思い出と言う慰めで良いから、私の胸に抱き留めていたい。
三月。
冬と呼べる程の寒気はとうに失せ、庭に聳える一本の桜の蕾も、随分と柔らかくなってきた。
――春が来た。
その日の晩ご飯も、いつもと同じように賑々しく進んでいた。
「ねえ居候、ちょっと醤油取ってくれない?」
「あーはいはいどうぞ。姫様、たまには自分で動いて下さいよ……」
「嫌よ。他に動いてくれる人が居る内は、私が動く必要なんて無いじゃない」
「もう、姫様。怠け癖がつくのは良くないですよ?」
甘ったれまくりの姫様に、永琳が思わず苦笑を漏らした瞬間、
――カラン、カラン。
永遠亭周囲に張り巡られた結界が反応し、来訪者を報せる柝の音が響いた。
「あら、お客様ね。イナバ、お願い」
「あ、はい。私が行きます」
率先して席を立った鈴仙に、イナバの子達が数名、ぱたぱたと後をついて行った。
…………
鈴仙達の姿が消えてから数分して、姫様がぽつりと呟いた。
「来ちゃった、か……」
「…………はい」
苦笑いを浮かべる姫様と、何故か重々しく視線を落とす永琳。
「?」
お茶を一口啜り、どうかしたのかと口を開きかけた瞬間、鈴仙が神妙な顔付きをして戻って来た。
「……あの、姫様、師匠。来ました……スキマ妖怪が」
「呼ばれてないけどジャジャジャジャー―――ンッッ!!!」
「うおおっっ!!?」
鈴仙の台詞が終わるか終わらないかというタイミングで、俺の湯呑みから突然人影が飛び出してきた。
「ほっ、と」
軽やかに畳に降り立ったその金髪の貴婦人風味な女性は、和洋折衷だか中華風だか、よく分からない服装をしていた。
「はいはい皆さんお久し振りね、藍から話は聞いたわよ。
……って、アレ? な、何でみんな私の事そんな白い目で見てるの?」
「普通に登場出来ないのかしら、貴方は……」
ええと、ひょっとして、この人が……
「あら、貴方が藍の言っていた外の方ね。初めまして、八雲紫と申します」
「ああ、初めまして。……なあ永琳、想像していたのより、全然熊っぽくないんだが……」
「油断したら駄目よ。こう見えても人は喰うし、長い冬眠で腹の肉も増えているに違いないんだから」
「そ、それは怖いな……」
まったく、妖怪と女は見た目で判断する事が出来ない。熊さえ可愛く見える恐ろしさだった。
「……初見で随分失礼な人ねぇ。お腹の肉なんて、肥満と細身の境界を弄ればどうって事無いわ」
「そっ、そんなのズルイわっ!!」
何故か、姫様が憤慨していた。
「……さて、本題に入りましょうか。貴方、心の準備は出来ていて?」
「……あー、その……」
「だめっ!!」
ちょっと待って、と言いかけたところで、突然イナバの子達が数人俺の前に割り込み、両手を広げて紫さんの前に立ち塞がった。
「……お兄ちゃんを、連れて行っちゃダメ」
「あらあら、可愛いらしい騎士様達だこと」
チビ助達に睨みつけられた紫さんが、淡い苦笑いを浮かべる。
「……しょうがないわね。おチビちゃん達と、そこで怖い顔をしている薬師さんに免じて、今日のところは退散するわ」
扇子が振るわれた軌道に沿って、一拍遅れて空間に裂け目が生まれた。
「明日また来るから、そこで答えを頂戴。その次はもう無いわよ」
ウィンクを一つ残して、紫さんの体が裂け目の中に消えていく。
「それでは皆さん、良き選択を」
彼女の姿を呑み込むと裂け目は閉じて、その跡形全てをそこから無くした。
「……………………」
神妙な沈黙が、背中に重く圧し掛かってきた。
…………
あの後、味がよく分からなくなった晩ご飯を片付け、一人自室に篭もって思案に耽っていた。
バレンタインの日からずっと考えてきて、自分がどうしたいのか、結論はとっくに出ている。
だけどそれを実行に移すには、やはりそれなりの覚悟が必要だった。
何処に、絆を求める?
決まってる。この永遠亭に。
誰に、絆を求める?
決まってる。一目視た時から恋焦がれてきた、大好きな人に。
「…………よしっ」
頬を張って気合を入れ、勢い良く腰を上げた。
…………そして次の日。
~ Last Note ~ ――誕まれて、生きて、死んでいく。
「…………」
「師匠」
「…………」
「師匠?」
「…………」
「……師匠!!」
「きゃあっ!? ちょ、ちょっと、驚かさないでよウドンゲ……」
「何言ってるんですか。私、ずっと呼んでたんですよ?」
昨日の晩から自室に篭もり、半日以上瞑目していたせいか、まるで気がつかなかった。
「そ、そう……」
「もう、一体どうしたんですか?
昨日からずっと引き篭もっていたかと思えば、朝食にも昼食にも出て来ないで」
「……何でもないわよ」
「嘘ばっかり。昨日あれから、彼と二人で話してましたよね。それ絡みじゃないんですか?」
「…………そうなのよねえ……」
もう取り繕っても仕方が無い。弟子の指摘を、己の未熟と併せて素直に認める事にした。
「……彼は、何て?」
ウドンゲの催促に、昨晩彼から受けた言葉を思い出す。
『君の事が好きだ。だから、俺がここに残るか外に帰るかを、君に決めて欲しい』
そう私に告げてきた彼の眼差しから感じたのは、
己の道さえ決められぬ弱さなどではなく、自分の未来を委ねても構わないと言う、私に向けられた強い愛情だった。
「まったく、女冥利に尽きるわ……」
「ふふ、いい話じゃないですか。で、師匠は何て返事したんですか?」
「……保留中」
「えっ? な、何でですか? あの、師匠も彼の事……」
「私は蓬莱人だからね」
「それはそうですけど……でも、彼はそんな事」
「そうね……きっとあの人はそういう事情まで考慮した上で、私を好いてくれているのでしょう」
間違い無く、彼は私や永遠亭の人達を幸せにしてくれるだろう。
……問題は、私の方にある。
彼と接するようになってから、何時の間にか私の中に一つの恐れが芽生えていた。
長い時間を経て身についた、生きる上で必要な知識や習性、そして姫との経緯は、
どれ程の時間をかけても決して失われる事の無い、私を形作る原型と呼べるものだろう。
だけど、かつての月での生活や、この永遠亭に来てからの出来事……所謂『思い出』というものに関しては、その限りではない。
ある記憶は時間と共に風化して朽ち落ち、ある記憶は新たな出来事によって塗り替え抹消されて……
ふと自分の足跡を顧みて、思い出と呼べるものの大半が最早輪郭さえ留めず、私の中から失われている事に気付いたのだ。
ならば果たして、現在私を取り巻く永遠亭の人々……このウドンゲやイナバの子達、それに、彼の事はどうだろうか。
今となっては月で共に過ごした同胞の顔をまるで思い出せないように、
やがて天寿を全うし消えていく彼等を、私は新たな思い出を塗り重ねる事で無くしてしまうのだろうか。
…………嫌だ。
亡くしても、無くしたくない。
この幸せさえ擦り減らしやがて無くして、なおのうのうと笑っているであろう未来の自分が、酷く醜い生き物に視えてしまう。
……改めて思い知らされる。
私は深い思慮も無く、こんな酷い生き方をあの二人に与えてしまったのか。
「ねぇウドンゲ……永く生きるっていうのは、こんなに悲しいものだったのね。
今こうして目の前に居る貴方の事も、私はやがて無くしてしまうのでしょう」
苦笑の表情を作ったつもりだが、実際にはどんな酷い顔をしているのか、自分でも分からない。
だと言うのに、目の前の不肖者の弟子は、
「何言ってるんですか師匠。私は、居なくなったりしませんよ」
そんな馬鹿な事を言いながら、私の鬱屈を笑い飛ばすかのような笑顔を視せた。
「……あのね。私の話、聞いてた?」
「はい、一語一句漏らさず。……私は確かにただの兎で、やがて師匠を置いて死んでしまうでしょう。
でも、子供が出来たら師匠に教えて頂いた事をその子に伝えます。
もし子供が出来なくても、私が残したものはイナバの子達が受け継ぎ、やがて子供達にも伝えてくれるでしょう」
そこまで一気に言って、彼女は一つ、大きく息を吸った。
「師匠が忘れてしまっても、気付かなくても、私はずっと……ずっと、師匠の傍に居ますから」
「…………」
――眼前の風景が、目映く歪む。
三千年に一度しか開花しないと言われる、金輪王と如来の花。
戯れで名付けた筈のその幻想の花が、私の眼前で白く眩しく咲いている。
「……ウドンゲ」
そっと手を伸ばし、彼女の頭を胸元に抱き抱えた。
「わぷっ。……し、師匠? 苦し……」
「ねぇウドンゲ。……一度しか言わないから、よく聞きなさい」
私の胸に埋もれた小さな頭を、柔らかく撫でる。
――今の私のこんな顔を、弟子になんて見せられるものか。
「…………はい」
「……ありがとう。貴方に逢えて、よかった」
――決めた。
昨日からずっと考え、一つ辿り着いた私の望むもの。
私は、今ここにある幸せを、もう薄れさせたくは無い。
……あの人が私に思いの丈を伝えてくれたように、私も全霊を以って伝えよう。
彼の真っ直ぐな情念とは比べるべくも無い、醜くおぞましい欲望ではあるが。
…………
ウドンゲと別れ、眦を決して彼の部屋へと向かう途中、縁側に姫の姿を視止めた。
姫は一人で縁側に腰掛け、齷齪と庭の手入れに勤しむイナバの子達を眺めていた。
視線を庭の方に向けたまま、鈴を鳴らすような声が静かに響く。
「…………腹は決まったかしら?」
「はい」
「そう。……それじゃ、私から言う事はあまり無いわね」
詠うように気負いの無い、だけど力ある荘厳な声で、姫は続けた。
「今までありがとう、永琳。
私は、貴方のどのような決断も受け入れる。
言いたい事は、ただ一つだけ…………」
「はい」
「……幸せになりなさい、八意永琳。
臣の幸せは、私の幸せでもあるのだから」
「…………はい」
…………
「……入るわよ」
「ああ」
断りを入れて、襖を開く。
何も様子の変わらない部屋の真ん中で、彼はただ寝転がって天井を眺めていた。
何一つ部屋の片付けが行われていない事に小さな安堵を覚え、改めて彼からの信頼の深さを感じた。
「話があるの。少し表に出ましょう」
…………
――ざっぱああああんっっ!!
「こんにちはお姫様~~。たまにはお昼に顔を出してみたのだけど、いかがお過ごしかしら? ……クシュン!」
「昨日は湯呑みからで、今日は池から、か。まったく、普通に玄関から来なさい、玄関から」
「う~~冷たい、今後考慮するわ。それよりも……あの人間は?」
「いないわ、お出掛け中」
「あらあら、逃げられちゃったか。
残念ねえ……外に帰るとか言うのなら、こっそり頂いちゃおうかと思ってたのに」
「やっぱりそんな所だったか。彼はもう此処の住人だから、これから手を出すのなら容赦はしないわよ」
「流石にそんな野暮はしないわよ。そう言えば、薬師も居ないみたいだけど……やっぱりそういう事?」
そう言っていやらしい笑みを浮かべると、紫は親指と人差し指で輪っかを作った。
「むっふっふ。そういう事、そういう事」
その輪っかに、人差し指をズボズボと突き入れてやった。
「「むふ、むふ、むふふふふ…………」」
「「「……………………」」」
周りのイナバの子達の視線が、とても痛かった。
…………
「いい天気ねぇ」
そろそろ夕刻に差し掛かろうという頃合、僅かに茜の差した空を、
彼を初めて拾ったあの日のように、背中に負いながらゆるりと飛んでいる。
「痛いよ~~、痛いよ~~」
道中、体勢を直す振りをして私の胸を触ろうとした不届き者を、両肩の関節を外す事で制裁した。
竹林をとうに過ぎ、初夏から何度か行き来している鈴蘭畑を通り過ぎて、
やがて私達は、かつて彼岸の花に溢れていた、無縁の塚に降り立った。
…………
『……ありゃ。これはまた珍しいお客さんだこと』
『ちょっと小町! またサボってる!』
『きゃんっ!? ちょ、ちょっと映姫様、いきなり後ろに立たないで下さいよ』
『何言ってるの。こんな所で一体、何をコソコソ……ゲエェー―ッ!!
あ、あれは蓬莱人! こここ小町!! 塩っ、塩撒いて追っ払って来なさい!』
『まあまあ映姫様。……それよりも、一杯どうです?
あの二人、いい肴になりそうですよ?』
…………
「何とも辛気臭い場所だな。立ってるだけで気が鬱ぎそうだ」
入れ直した肩をぐるぐる慣らしながら、彼は呟いた。
「そうね……でも、ここじゃないと駄目なの」
天命を終えた人の魂、想いの逝きつく孤高の丘。
今の私には縁の無いこの塚こそ、始まりのテープを切るに相応しい場だと思ったのだ。
「……それじゃあ、聞かせてくれる? 永琳の話」
「……ええ」
もはや取り繕う必要も、余分な言葉で意味をぼかす必要も無い。
私の出した答えを、簡潔に彼に伝えよう。
――私が彼に与える、一つの難題。
「実は……ね」
「うん」
「蓬莱を殺す薬を、作ろうと思うの」
「……………………そうか」
「ええ。だから……ね」
怖い。
怖い。
私の次の言の葉を受けた後、彼は一体どのような顔をするだろうか……
「だから?」
「だから…………貴方に、蓬莱の薬を、飲んで欲しいの」
「…………」
「…………」
言葉として形にする事で、自分の出した答えのおぞましさ、浅ましさに、改めて痛烈な嫌気を覚えた。
私は、彼にこう言っているのだ。
……一緒に地獄に堕ちてくれ、と。
禁忌である蓬莱の薬を殺すという事は、更にもう一つ先の禁忌を犯すという事だ。
これから着手するとして、どれ程の時間や犠牲を払う事になるのか、見当もつかない。
果たして薬を完成させ、再び時間の歯車を軋ませるその瞬間に、この人が隣に居ないのでは、まるで意味が無いのだ。
「…………」
「…………」
一瞬とも万年とも思える、凍ったような沈黙。
彼は私の言葉の裏、私の胸の内までを咀嚼するように暫し瞑目し、そして……
「うん、分かった」
……先刻のウドンゲを彷彿とさせるような、眩しい笑顔を視せてきた。
「……………………いいの?」
「ああ。日本男児に、二言は無い」
いつもの爛漫な笑顔そのままに、彼の手が私の方にそっと伸びて……
「あっ」
……引き寄せられるままに、私の身体が彼の腕の中に収まる。
「……いいの? 私、貴方が思っているより、ずっと怖い女よ?」
「怖くなんてあるもんか。俺を選んでくれた、誰より大切な人だ」
「…………きっと、永く辛い道になるわよ?」
「大丈夫だよ。姫様も居るし、妹紅も居る。鈴仙やイナバの子達も居るし……俺だって、ずっとついてる。
きっと、地獄だって楽しめるさ」
かつての私は、知っていたのだろうか。
――人の腕の中が、こんなにあたたかいものだという事を。
「永琳」
彼の指が、私の顎をそっと上を向かせる。
「あ……」
少なくとも幻想郷に来てからは覚えの無かった潤みを目元に感じながら、私はそっと瞳を閉じた。
…………
――矢を、放とう。
永い射線に迷い、切り裂く風の冷たさに凍て付き、林檎に刺さる頃には、朽ちてぼろぼろになってしまうかも知れないけど。
偕老同穴の誓いを乗せて、再び歯車を動かす為の、決して折れる事の無い命の矢を、二人で放とう。
・
・
・
・
・
・
・
「ウィ~ッ、こここ小町のヴワッキャロォォオオオオイっ。
クソッタレ蓬莱人でさえあんにゃに幸せそうにイチャイチャしてんのに、
ぬわぁぁんで私はお前みたいな阿婆擦れと酒なんて飲んでんだああああああっっ!!?」
「あ、あの、映姫様? 落ち着いて……」
「ああああたしゃ落ち着いてるってんだよこのパープリンがああああああ!!
いいからとっとと酒追加しろってんだよおおおおぉぉぉ!!」
「ひいいぃぃっっ、しまったあぁ、あたいとした事がああああぁぁ~~~~……」
>>454
芽生え、花が咲き、そして散ってゆく。
朽ちて、風に融け、そして空に昇る。
やがて雨が降り、大地を潤し、新しい生命を芽吹かせる。
繰り返し、繰り返し。
周る星々と同じように、命もまた巡るものなのだ。
・
・
~ January ~ ――最初から結果を知っているのなら、誰も間違いは起こさない。
元日からの三ヶ日もそれなりに平坦に過ぎ、年越しの浮かれた空気もやや薄れ始めた永遠亭。
その日、珍しく自ら材料の採取に出ていた私の師匠こと八意永琳は、ロクでもない拾い物をして帰って来た。
「……どうしたんですか師匠。それ」
ホクホク顔で帰って来た師匠の背中に、一人の人間の青年がグッタリと負ぶわれていた。
「ちょっとそこで拾ってね。折角だから持って帰って来ちゃった。
まあ、薬の実験台くらいにはなってくれるでしょ」
「は、はぁ……」
青年の出で立ちはこの幻想郷ではまず見られないもので、外からの迷い人である事を窺わせる。
(……可哀相に)
よりにもよって師匠に拾われてしまうとは。
これなら、気絶している間にそこらの妖怪に喰われでもした方が、まだマシと言うものだ。
私は毒蜘蛛の獄糸に囚われた哀れな羽虫に、僅かな同情の念を抱いて視線を送り、そして、
「……なっ!?」
眼前のおぞましい光景に、言葉を失った。
「? どうしたの、ウドンゲ」
「い、いえ……な、何でもありませんよ。あ゛、あははは……」
……何という事だ。
男は、気絶した振りをしながら師匠の髪の香りを嗅いで、幸せそうに鼻の下を伸ばしていた。
「?……変な子ねぇ。まあいいわ、まだお昼の残り物があるわよね?
取り敢えず、疲労と空腹意外におかしな所は無いみたいだから、叩き起こして食べさせてあげましょう」
「……はい」
脳の調子もおかしいのではないかと思ったが、混ぜっ返すのも面倒なので、大人しく師匠に従う事にした。
――彼は哀れな羽虫などではなく、飛び切り性質の悪い毒虫だった。
後々私達――特に師匠は、それをある種の痛みとともに思い知る事になる。
屋敷に運び込まれた彼は、程無く師匠の高速往復ビンタ(秒間16連打)で目を見開いた。
残り物のご飯を振舞いながら、双方簡潔に自己紹介を済ませる。
話を聞くに、やはり外の住人だったらしく、此処にいる心当たりもまるで無く、このところ数日の記憶も酷く曖昧らしい。
……スキマ妖怪の餌狩りから、漏れ出しでもしたのだろうか。
「ムシャムシャどうにか帰れないかなあガツガツ、ああ美味いゴクゴク、ありがとう助かったよモグモグ」
食べるか尋ねるか礼を言うか、どれか一つにして欲しい。
健啖そのものの彼の様子に師匠は満足そうに笑うと、いつもと変わり無い、平坦な声で答えた。
「心当たりはあるにはあるのだけど、冬の内はどうにも出来ないわね。
時期が来れば手は打ってあげるから、それまではウチで過ごしなさいな。
それなりの扶持と仕事は与えてあげるわ」
「……そっか、ありがとう。まあ、世話になった分はしっかり体で返すよ」
「…………『体で返す』……言ったわね、言ったわね、フフフ……」
彼の快諾を得た師匠が、唇の端を妖しく吊り上げた。
(……つくづく、可哀相に……)
口は災いの元とは、よく言ったものだ。
哀れ、実験台&隷属労働が確定した彼の表情をちらりと窺い見ると、師匠に負けじと妖しく笑っていた。
「ふふ……そうとも、『体で返す』……むふふ……ぐふっ」
取り敢えず、一発殴っておいた。
…………
何が何やら分からぬまま流れ着いて来た、魍魎住まう幻想郷。
『行動力のある方向音痴』という非常に迷惑な性質を持つ俺が、曖昧に色の移ろう竹林を独力で抜けられる筈も無く、
手を打てる妖怪が居るには居るらしいが、現在冬眠中で、春が来るまでは当てには出来ないらしい。
人型の妖怪の癖に冬眠だのと言うくらいだから、さぞかし熊チックな大女なのだろう。
熊殺しは男の浪漫だ。会う日を楽しみにしておこう。
当然ながら行く宛てなど無いロンリーシングルな俺は、お言葉に甘えてこの永遠亭の人たちの世話になる事にした。
昨日あの後、この屋敷の姫様とやらをはじめ、ある程度の顔見せは済ませてある。
――さて、今日は実質初日だ。俺が出来るナイスガイである事を、一発見せ付けてやるとしよう。
長い廊下を歩きながら、擦れ違う子たちに自己紹介のついでに道を聞き、永琳の部屋を訪ねた。
「おはよう、永琳」
「あら、おはよう。そっちの方から来るとは良い気構えね。体調はどうかしら?」
「元気ビンビン大事無い。……ところで、指し当たって俺は何をすればいいんだ?」
「そうね……いきなり大仕事になって悪いのだけど、今日は年末の大掃除で出たゴミを庭で燃やそうと思うのよ。
裏口に全部積んであるから、それをリヤカーで庭まで運び出してちょうだい」
「分かった、あつらえ向きの力仕事だな。任せてくれよ」
「まあ、頼もしい限りね……ふふ」
と、意気揚々と臨んだ初仕事だったのだが、裏口に出るなりいきなり挫けそうになった。
「…………何じゃこりゃ」
山のようなゴミ袋や家財道具、果てにはごっついボロ箪笥がまるまる一台。
横に鎮座している、幅だけでゆうに六尺は超えていそうな特大リヤカーが、随分可愛らしく見えた。
「え~っと……これを、俺一人で?」
「そうよ。まさか、嫌とは言わないでしょうね?」
「ぐ……」
確かに、タダ飯喰らいの店子である俺にはそんな強い事を言える立場も無い。
「仕方が無い、やってやるさ。お嬢さん、あまりの頼もしさに惚れるなよ?」
「ふふ、期待はしないでおくわ」
冗談めかした淑やかな笑顔に、それなりのやる気と、頬に少々の赤みが湧いてきた。
愚痴を垂れたところで荷が減る訳でもない。まあ頑張ろう。
…………
――それからおおよそ二時間弱。
「え~んやこ~ら、せっと」
幸い裏口から庭までそう大層な距離がある訳ではなかったので、一度に運ぶ量を少なめにして、足を細かく動かす事にした。
「ほら、頑張りなさいな。もう少しで終わるわよ」
「ぐ……」
永琳は何か手伝ってくれる訳でもなく、細かな指示を出しながら、俺の横をただついて歩いていた。
妙な居心地の悪さに囚われながらも、何とかあと一往復、という位までゴミの山を切り崩したところだ。
そもそも元のゴミの量が半端ではなく、リヤカーそのものの重量もある。
いい加減限界を訴える両の腕に、これで最後と喝を入れた。
「ふふ、大丈夫? 随分辛そうに見えるけど、ここに来て降参かしら?」
小馬鹿にしたような嫌味ったらしい物言いが、俺の闘魂の炎を激しく揺さぶり上げた。
「あんまり馬鹿言うなよ。やっと準備運動が終わったところだ。
ヘイヘイ小粋なお嬢さん! 俺の愛車に乗って行くかい?」
頭をノリノリで振り回しながら、峠の田舎ヤンキーっぽく強がってみた。
「あらいいの? それじゃ、お言葉に甘えちゃおうかしら」
……どうやらこの畜生鬼には、俺の限界を慮り、可愛く遠慮する程度の優しさも無いらしい。
「あ~まあいいよ。ほら、乗りな」
足を止め、顎で指して永琳に荷台を勧めた。
今更女性一人程度の荷が増えたところで、大した違いは無いだろう。
それに少し想像を逞しくすれば、自転車の後ろに女の子を載せるようで、萌えるシチュだと言えなくもない。
「ふふ。では、遠慮なく。……よいしょ、と」
断りを入れると、永琳はリヤカーの縁に両手を掛け、ふわりと軽く跳んで、腰を荷台に落としてきた。
底板が軽くたわみ、パイプを震わせ両手に彼女の重みを伝えてくる。
「うっ! ……おも」
「ま、さ、か、『重い』だなんて言わないでしょうね?」
「……さを感じないくらい軽くてビックリしちゃう!!」
「よろしい」
まだ死にたくないので、余計な冗談は言わない事にした。
「さ、面舵いっぱ~~い」
向こうを指差しながら視せられた悪戯っぽい笑顔に、不覚にも胸が高鳴る。
「はいはい、月の向こうまででも行ってみせますよ、お客さん」
「う~ん……折角だけど、月は遠慮しておくわ。代わりに庭までよろしくね」
…………
――ごとん、ごとん、ごとん。
のんびりと最後の往路を闊歩していると、行く先に人影が一つ見えたので、そこで一旦足を止めた。
鴉の濡れ羽色鮮やかな長髪が目を惹く、この屋敷の首魁、蓬莱山輝夜姫だった。
「あら、姫。おはようございます。もういい加減お昼ですけど」
「ん、おはようございます、姫様」
「おはよう二人とも。精が出るわね」
姫様は俺達の挨拶に軽く笑って応えると、荷台の上でニコニコとお姫様チックに鎮座している永琳に視線を送り、
「……永琳、歳を考えなさい。見てられないわ」
きっつい一言を浴びせかけた。
恐る恐る永琳の表情を覗い見ると、表面上は先程までと変わらぬ笑顔のままではあったが、奥歯がギリギリ軋む音がしてめっちゃ怖い。
「あらあら姫、お戯れを。精神にまで若々しさを亡くしてしまったら、女はお仕舞いですよ?」
「m9(^Д^)プギャーwwwwちょっwwwwwww若々しさとかwwwテwラwワwロwスwww自分の実年齢考えろってのwwwwwwwwっうぇ」
姫様、お願いだから日本語で話して下さい。
と言うか、トップの主従が朝からこんなアホな諍い起こしてて、大丈夫なのかこの屋敷。
「ほらほら貴方も言ってやりなさいよ。××年以上も生きてる因業ババアが男の後ろで少女座りとか恥ずかしくないのか、って」
具体的な数字を伏せたのは、俺のなけなしの良心からです。
さて、姫様が俺に話を振りやがりになられたので、極力角の立たない素敵な言い回しを考えてみた。
「いやそんな、俺は可愛いと思いますよ?」
「えっ?」
「なっ……ば、馬鹿言わないの!」
――ごすっ。
「痛でっ」
場に角は立たなかったが、永琳が投げつけてきた木箱の角が俺の鼻っ柱に突き立った。
「な、何すんだよ! せっかく人が褒めたってのに!」
「いいからっ、早く進む!」
何故か永琳が顔を真っ赤にしてプリプリ怒っているので、仕方なく従う事にした。
「ったく……それじゃ姫様、また後で」
「え、ええ……」
呆然と手を振る姫様を尻目に、再びリヤカーを漕ぎ出した。
…………
「…………驚いた」
永琳って、あんなに初心だったかしら。
……そう言えば、永琳の事を『綺麗だ』と褒める奴は、男女問わず今までにも掃いて捨てる程居たが、
初見で『可愛い』と表現した奴は、ちょっと記憶に無い。
以前、弟子のイナバが同じような言い回しで永琳の服を褒めて、照れ隠しの張り手で十メートルくらい地面と平行にブッ飛んで行った事があった。
「……うん、気に入った」
少々退屈していたところに、見所のある玩具が増えたのかもしれない。
ひ弱な人間、それも外からの異分子の癖に、彼は私たちを畏れず、大した気負いも無く環境の変化に順応している。
余程の馬鹿なのか、はたまた余程の大物なのか。
この泥の大海に揺られるような永い航路に、少しは波を立ててはくれるのだろうか。
…………
「鈴仙様~~、鈴仙様の分も焼けましたよ~」
「ん、ありがとう」
イナバの子から、ほかほかと湯気を立てるサツマイモを受け取った。
「熱つつっ」
手の中で転がしながら、ぺりぺりと芋の皮を剥き上げる。
紫色の皮の下から姿を現した黄金色の実に、少しはしたなく齧り付いた。
甘味を孕んだ熱の塊が咽喉を滑って腑を流れ、喉元に残った温かな薫りが鼻孔を抜けた。
「ふふ、美味しい」
やはり、焚き火と言えばこれが無いと始まらない。
庭のど真ん中で、集めた廃棄家具が火にくべられ、轟々と煙と炎を巻き上げている。
イナバの子達がワイワイと楽しそうに周りを囲み、暖を取ったり、棒で中を突付いて芋の焼け具合を確かめたりしていた。
火を畏れない獣というのはどうかという気もしなくは無いが、まあ些細な事だ。
――少し向こうの方で、師匠と姫、それに居候の彼を加えた三人が、焼き芋を肴に歓談している。
今日これまでの半日で、随分と仲が良くなったみたいだ。
「う~ん、美味しいわ永琳。ね、もう一個いいかしら」
「構いませんけど、注意はして下さいね。引き篭もりで肥満体質な姫なんて、私は嫌ですよ」
「う゛……」
乙女心の軟らかい所を鋭く抉る師匠の一言に、姫様は一歩たじろいだ。
和装なので分かり辛いが、正月太りの兆候でも顕れているのかも知れない。
……私も気をつけよう。
「なあ永琳。悪いけど、俺はもう一個貰えないかな。流石に腹が減って」
「いいわよ。今日は頑張ってくれたから、特別に私が密かに栽培していた、滋養たっぷりの取って置きをあげる」
控え目にお替りを要求する彼に師匠は軽く笑いかけ、焚き火から木串を一本引っ張り出した。
――ずいっっ。
「うっ」
「おわっ……こ、これは……」
姫様と彼が、揃って顔を顰めて変な声を上げた。
随分と摩擦係数の小さそうな、ツルツルと真ん丸いサツマイモ色の球体が、師匠の掲げた木串に刺さっていた。
「いかがかしら? 永琳印特製の遺伝子超絶組み換え芋、『グリーングローブ』よ」
「……突っ込み所がいささか多過ぎる気もするが、オラすっげえわくわくしてきたぞ」
……それでいいのか、か弱き人間。
そんな私の危惧を余所に、彼は師匠から受け取った母なる大地に、大口開けて勢い良く齧り付いた。
「……モグモグ。……うはっ、美味ええぇぇ!! どうですか、姫様も」
「そ、そうなの? それじゃ私も一口…………ぶはあぁぁー――ッッ!!!
ななな何これすっごい不味い!! おのれ謀ったわねこの下郎!! おえっぷ」
「ぶははははっ、かかったなアホが! こんな不味いモン、俺一人で食ってられるか!! ぐえっぷ」
「あら、喧嘩はダメですよ、二人とも」
「「アンタが言うな!!」」
「…………はは」
二人同時に師匠に指を突き付ける姫様と彼の姿に、思わず苦笑が漏れた。
周りを囲むイナバの子達からも、どっと笑いが起こっている。
この屋敷にこれだけの大声が飛び交うのは、去年の永夜事変以来ではないだろうか。
「ま、みんな楽しそうだからいいか……」
師匠も姫様もイナバの子達も、彼の事をなかなかに気に入ったようだ。
現前でゆらゆらと棚引く炎と背後のドンチャン騒ぎを肴に、もう一口芋に齧り付いた。
…………
どうにかこうにか一月弱の日々を経て、この永遠亭での生活にも少しは馴染んできただろうか。
粗相を仕出かして即お肉、という危惧もまあ当初は無かった訳でもないが、今の所そのような気配は無い。
永琳は、俺の事を容赦無く扱き使い、悶死クラスの人体実験を平気でやらかしたりするが、根本的には優しい人……だよね?
姫様は、きっつい揶揄を浴びせてきたり難題を吹っ掛けてきたり、香霖堂でwebマネーを買って来いだのと何かとサドい人だが、
全ては親愛の裏返しである、と俺の常夏トロピカル脳が告げているので、概ね問題は無い。
イナバの子達も幸い俺と楽しそうに接してくれているし、鈴仙の短いスカートから伸びる白い脚は、まさしく月が生み出した奇跡だ。
俺の方も、ここでの生活が楽しいと思える程度には、永遠亭の人達の事を好きになっていた。
さて、今日は昨晩から降り出した雪が猛威を振るいまくりで、暴れ回る白雪が屋敷とその周辺一帯を真っ白に染め上げている。
イナバの子達は部屋にこもって布団で丸くなり、薬師師弟と姫様、俺を含めた四名は、居間の掘り炬燵を囲んで丸くなっていた。
「さ、寒い……」
炬燵に深々と潜り込みながらも、なおガチガチと歯を鳴らす鈴仙の姿が哀れを誘う。
まあ、寒さに強い兎というのも、あまり耳に入る話では無いが。
「うぅ……寒い……時が……時が視えるわ……」
どてらを二重に着込んで目を虚ろに泳がせている姫様に関しては、極力視界に入れない事で対処する事にした。
「だらしないですよ姫。それにウドンゲ、この程度で音を上げるような情けない弟子を持った覚えは無いわよ、私は」
「全くだ。炬燵の中で実はパンツ一丁になっている元気な俺を見習え」
「……居住まいを直すのと素っ裸で庭に放り出されるのと、どちらがお好みかしら?」
「ご、ごめんよぅ」
永琳の爽やかな笑顔が恐ろしかったので、慌てて倒錯露出プレイを中止し、炬燵の中でもぞもぞとズボンを上げる。
一人平気な顔をしている永琳に、鈴仙が恨めしそうに頬を膨らませた。
「ふんだ、師匠はいいですよね。胸にいっぱい脂肪が詰まってるから、寒くも何ともぎゃあああっっ!!!
痛い痛いっっ、足の指とは到底思えないこの握力!!」
炬燵の中で執行された制裁に、鈴仙が面白い顔をしながらギブアップを訴える。
程無く足指アイアンクローを解くと、永琳は硬く閉じた障子の向こう、外の景色を幻視するかのように、少し遠い目をした。
「確かに寒いのは難儀ではあるけど、雪っていうのは綺麗なものね。
月が地上に適わない、数少ない現象の一つだわ」
「……そう、ですね」
「…………」
相槌を打った鈴仙が一つ息を吐き、場に少し神妙な懐古の空気が流れる。
ここに居る三人は元来月の住人で、止む無き事情でこの幻想郷に移り住んで来たのだと言う。
三者三様に抱えているであろう胸の傷は、所詮他人である俺が触れて良い類のものでは無い。
要らぬ傷をうっかり抉らぬよう、大人しく黙り込んだ俺に、永琳は何事も無かったかのように笑いかけてきた。
「この分だと、明日は一日雪掻きね。頼りにしてるわよ」
「うへぇ……」
凡人であり他人である俺には、彼女の笑顔の裏にどのような感情が隠されているのかなど、分かりようも無い。
それを寂しい事だと感じてしまうのは、春にはここから姿を消す俺にとって、良くない兆候だと思った。
…………
昨夜の内に降りしきる雪は勢いを無くし、夜が明ける頃には粉雪がぱらつく程度に天候も落ち着いていた。
とは言え、丸一日暴れ回った雪たちは屋根だの周辺だのにどっさりと鎮座し、屋敷の骨を密やかに軋ませている。
昨日の永琳の言葉どおり、今日はイナバの子達と協力して雪掻きだ。
「あれ? 随分と集まりが悪い気がするが」
「そうなのよ……昨日の寒波で、殆どの子が風邪を引いちゃって」
俺の疑問に、鈴仙が頭を掻きながら苦笑交じりに答えた。
「そっか、可哀相に。具合は大丈夫そうなのか?」
「今師匠が診て廻ってるけど、まあ大丈夫でしょ」
まあ体調を崩してしまったのでは仕方が無い。こういう時にこそ俺のような居候がしっかり働くべきだろう。
「さ、始めましょ。動ける私達が頑張らないと」
「「「は~~い!!」」」
鈴仙の音頭に、イナバの子達に混じって大声を上げた。
…………
「おっ嬢さ~~ん、山男には惚れるなよ~~、っと」
作業を始めてから、どの位の時間が経っただろうか。
どっかと屋根に根を下ろした雪の山を延々とこそぎ落とし、ようやく屋根の上の雪を粗方降ろす事が出来た。
参加してくれたイナバの子達の体調も万全には程遠く、へばった子には作業を切り上げさせて屋敷に帰らせていく内に、
何時の間にか俺と鈴仙を含めて、両手で足りる程度まで頭数が減っていた。
少し目を放した隙に無断で居なくなっていたてゐは、かつて全米を震撼させたジャックハマーで雪の中に串刺しにしてやろうと思う。
「ふ~~、あとは落とした雪を固めて終了、ね」
長い髪を後ろに縛った鈴仙が、息を整えながら歩いて来る。
彼女も人手不足を補おうと懸命に動いてくれていたが、大体が雪掻きなんて、女の子にさせるような作業ではない。
表情にも疲労の色が濃く、普段は水饅頭のように艶やかな唇が、見る影無く青褪めてしまっていた。
「……いいよ鈴仙。後は俺一人でどうにでも出来るから、他の子達を連れて先に戻ってな」
「何言ってるのよ。私はまだまだ大丈夫」
「そんな真っ青な唇して何言ってやがる。大体君のその格好は、見ているだけでこっちの体温が一度下がる」
この銀世界に関わらずいつものミニスカートって、一体どこの世界のワカメちゃんだ。
「しょ、しょうがないでしょ。ズボンを穿こうとしたら、何故か師匠が怒るんだから」
「何と。……う~む……鈴仙も苦労してるんだな……」
俺の脳内で、永琳の宇宙人的セクハラに憤怒する天使を、大喝采を送る悪魔が一瞬で誅殺した。
「もういいから、今すぐ戻って風呂にでも入って、しっかり暖まりなさい。
俺の方もさっさと終わらせて、君の風呂を覗く事にするから」
「ばっ、馬鹿言ってるんじゃなー――――ックシュン!!!」
――べちょべちょべちょっっ。
「…………」
いきなり間近で思いっ切りクシャミをかましてくれるものだから、俺の顔面に唾だの鼻水だのがかかりまくった。
「あっ、あああっ、ご、ごめんなさー――――ックシュン!!!」
――べちょべちょべちょちょっっっ。
はい、もう一発追加~~。
「あわわっ、ほ、本当にごめんなさい……」
「…………う~む……」
こんな仕打ちを受けて興奮している俺は、人としては間違っているが、男としては間違っていないと思う。
「ちょっとジッとしてて。すぐ拭くから」
鈴仙は慌ててポケットからハンカチを取り出し、俺の顔面に刻まれた聖なる液痕を拭い取ろうとした。
「バカタレ!! 勿体無いから拭くんじゃありません!!」
「私がイヤなの!!」
ごもっともです。
…………
結局は鈴仙の方が折れ、イナバの子達と共に屋敷に引っ込み、最後の仕上げは俺一人で行う事となった。
腕っ節にはそれなりに自信はあるし、残った作業も落とした雪を叩いて固めるのみ、という単純な力仕事。
時間は掛かりつつも屋敷の周りを何とか一周し終え、現在はもう一度屋根に上がって不備が無いか確認中、といったところだ。
「ん~~~~……問題無し、かな」
屋根の淵を一周して見回してみた分には、大きな問題は無いように視える。
今日のお勤め完了、という事だ。
「ふぅ」
一つ大きく息を吐き、梯子を降りようとして……少し、心変わりした。
下に落ちないように軒先に足を引っ掛け、その場に腰を落とし、顎を上げてぐるりと周辺を見回してみた。
永遠亭の近辺を万遍無く、雪にまみれた竹が埋め尽くしている。
ここの人達が外を行き来する為に拓いた獣道が僅かに覗く程度で、その景観は竹で出来た固牢じみていた。
「……」
あながち間違った表現でも無いと思う。
この永遠亭は、かつて姫様と永琳が追っ手の目を眩ます為にこしらえた、不可視の鳥籠だ。
今でこそ鈴仙やてゐ、イナバの子達が共に住まい、時折り来訪者も訪れて来るという比較的開かれた環境ではあるが、
この幻想郷に来た当初……たった二人きりだった頃、彼女達はどのような心境で日々を過ごしていたのだろうか……
「…………やめとこ」
二人がこの場に到った事情を知らない以上、何をどう考えても下衆の勘繰りにしかならない。
それが話して良いような理由なら、俺がそれを聞くに値する存在なら、いつか彼女達の方から話してくれるだろう。
「あら、そんな所にいたのね」
「ん?」
不意に下方からかけられた声に視線を落とすと、永琳が小さな籐製のバスケットを両手にぶら下げてこちらを見上げていた。
「ああ永琳、お疲れ様。こっちはさっき終わったよ。イナバの子達はもう大丈夫なのか?」
「ええ、お陰様で。……ちょっと待ってなさい、私もそっちに行くから」
そう言って永琳は籐籠を右手に持ち替え、器用に体のバネを遣いながら、片手で梯子を昇って来た。
「……よいしょっと。隣、失礼するわね」
断りを入れてくると、籐籠を間に挟んで、俺と同じような体勢で隣に腰掛けた。
「ん~~冷たいっ。よく平気で座ってられるわね」
「ここまで冷えると、立ってても変わらんよ」
もうその辺の感覚は、とうの昔に麻痺してしまっている。
「まったく無理しちゃって。そんな可哀相な頑張り屋さんに、永琳お姉さんから素敵な差し入れよ」
永琳は苦笑いを浮かべると、いそいそと籠の蓋を開いた。
箱の中に敷かれていた蝋紙の上に、中華まんが三つ、ほかほかと湯気を立てている。
「おぉっ、ありがたい! ちょうどお腹も減っていたところでさ」
「喜んで頂けて何より。一つは私が頂くから、二つはご自由にどうぞ」
「ん。ありがたくいただきます」
「はい、いただきます」
二人で冗談めかして両手を合わせ、早速中華まんに齧り付く。
程好く張りのある皮とふかふかの生地の中に、熱々の餡子がぎっしりと詰まっていた。
「あ~~こりゃ美味いや。極楽極楽」
心地よい熱と糖分が四肢を巡り、凍えた体に再び力を与えてくれる。
「ふふ。お口に合ったみたいで良かったわ。自分で料理するだなんて、随分久し振りだったから」
「それはそれは、重畳の至り。この状況での錯覚を差し引いても、本当に美味いよ」
「ありがとう。日頃縁の無い手間をかけた甲斐があったわ」
俺の言葉が世辞ではない事を感じ取ってくれたようで、永琳は満足そうに相好を崩した。
「……ね、何でイナバの子達を帰したの? 皆結構気にしてたわよ」
「何でも何も無いよ。女の子に無茶をさせて体を壊しでもされた日には、男の立つ瀬が無い」
女性の体は、子を宿し未来を託す為の、大切な世界の宝だ。
こんな詰まらない事で台無しにして良いような粗末なものでは無い。
「あらあらご立派。でもね、外で働くのは男の役目だなんて言うのは、フェミニズムでも何でも無く、単なる男尊女卑よ」
「……酷い事言うなあ……」
「うふふ、冗談よ。……ありがとう。貴方のお陰で、あの子達に無理をさせずに済んだわ」
ふわりとした笑みを見せてから視線を前方に移した永琳に、俺も倣う。
変わり映えの無い竹の群れが、緩やかな風に煽られ、ゆらゆらと棚引いていた。
「……ねえ。此処での暮らしは、退屈じゃないかしら?」
視線を前方に向けたまま、永琳がそんな事を訊いてきた。
「そんな事無いよ。みんな良くしてくれるし、外に居た頃には出来なかった、新鮮な体験ばかりだ」
――それと……
「そう」
少し強い風が吹き、厚く束ねられた永琳の髪を軽く浮かせる。
――出逢ってから共にした日々は、一月にも満たない程度の須臾でしか無いけれど、多分俺は……この人の事を。
「その感性、大切にしなさい。それは定命ある者にのみ赦された、とても貴いもの。
私みたいな、天の理に背いて左道に外れた外道には、酷く遠い揺らぎだわ。
あまり死の陰の無い生活が長くなるとね、どんどん感情の振れ幅が小さくなってくるのよ。
日の移ろい、四季の移ろい程度の変化では、ちっとも心が揺れてくれない。……悪い暮らしでは無いのだけどね。
『死が無い』と言う状態を、果たして『生きている』と表現して良いものなのやら」
そこまで詠うようにゆったりと語り上げると、竹林の更に遠くを見据えるように、眼差しを細くした。
憂いを孕んだ薄い笑みに滲んでいたのは何処か自虐めいた達観で、彼女の言葉どおり、俺に理解できる類のものでは無かった。
「……自分の事を外道だとか、あんまり悪く言うもんじゃないよ。
君を慕っている鈴仙やイナバの子達に失礼だし、俺だって悲しくなる」
そんな気の利かない事しか言えず、食べかけの中華まんを一気に口に放り込んだ。
それでも、しっかりと感情を込めた取り繕いでない言葉は、ちゃんと相手に届くもので。
「……そうね……ごめんなさい、少し軽率だった」
そう柔らかく微笑んだ彼女の頬が少し赤く視えたのは、寒気のせいか、はたまた俺の自惚れだろうか。
「それじゃ、嬉しい事言ってくれた色男さんに、出血大サービス」
一転悪戯っぽく笑うと、永琳は籐籠から最後の中華まんを取り出し、俺の方に差し出してきた。
「はい、あ~ん」
「…………マジで?」
「大マジです。それとも、姫やウドンゲじゃないと嫌だとか?」
「断じてそんな事は無い」
金メダル級のロケット即答。自分に正直なのは良い事だ。
「あら嬉しい。それなら遠慮しないで、はい」
「わ、分かったよ…………んぐ」
彼女の手の中の中華まんに齧り付いた瞬間、
――パシャパシャ!
幻想郷に来て以来、初めて耳にしたシャッター音に振り向くと、
見慣れた頭部と初めて見る頭部の計二つが、大棟の向こう側からひょっこり覗いていた。
『凄いです!! とんでもない写真が撮れました!』
『ね、言ったとおりでしょ? 最近ちょっと怪しい雰囲気だったのよね~』
『うんうん、これはいい記事が書けそうです。
天才薬師と異邦人の、銀色のロマンス……あぁ、痺れるわ……』
『うんうん、でしょでしょ? それで、リークのお代の方は……』
『人里の激ウマ人参二十本でしたよね。それは後日必ず』
『ウササササ、お主もワルよのう、越後屋』
『いえいえいえ、御代官様には遠く及びませぬ。むふふふふ』
「…………殺るか」
「…………ええ」
――ひゅんっ。
無言のままに永琳の手首が唸り、何処からとも無く取り出された鍼が放たれ、
――すととんっっ。
二つの頭に、同時に突き刺さった。
「「う゛っっ」」
間の抜けた呻き声が二つ同時に上がる。
「うっ……動けない? い、一体何を……」
「ぬ、ぬかったわ……!」
身動き一つ取れない状態でもがく人影二つに、永琳と並んで詰め寄っていく。
「あらあら記者さん。何時から貴方の新聞は五流ゴシップ誌に成り下がっちゃったのかしら?」
「い、いや~、これは、その……」
「おやおやてゐ。みんなに仕事を押し付けて、一体何処で何をしていたのかな?」
「ひっっ、あの……か、堪忍して、ね?」
「ん~~? 最近の詐欺師は、性格だけじゃなく往生際も悪いのかい?」
いやいやと目を潤ませるてゐの体を抱え上げ、屋根の端の方につかつかと移動する。
「実はさ、昔から一度試してみたい技があったんだよなぁ……」
そして屋根の端まで辿り着き、てゐのお尻を高々と抱え上げる形で、変型パワーボムの体勢に入る。
(ttp://www.sumire.sakura.ne.jp/~ruriruri/nazenani/aoi/image/ore/last%20ride.jpg※例によって、良い子は絶対に真似しないで下さい)
「ちょっ! タンマ、それセクハラっっ」
「はっはっはっ!! 喰らえ男の憧れ、屋根からラストライド!!」
そのままの高さから、先程作り上げた雪垣の向こう側目掛けて、渾身の力で叩きつけた。
「てっ、ていかああああああああっっ!!?」
――ぼすんっっっ。
くぐもった音を立てて、深く積もった雪の層に兎型の大穴が出来上がった。
「……ふっ、上がったり大明神。……Rest in peace……」
格好良くキメて後ろを振り向くと、あちらの方もまたどえらい事になっていた。
「ほら文、これで全部じゃないでしょう? 隠したフィルムとネガ、全部耳を揃えて出しなさい」
「そ、それだけは出来ま」
ぷすっ。
「ふああっっ!!?」
文と呼ばれた記者さんの抗弁が終わらない内に、これまた何処から出したのか彼女の腕に注射器の針が捻じ込まれ、一気にアンプルの中身が流し込まれる。
「あっ、あっ、あぁ…………」
「…………さぁて文、もう一度訊くわ。隠したフィルムとネガは?」
「ハイ、コレデ全部デス。ゴメンナサイ、永琳サマ。文ハ、イケナイ子デス」
……おいおい。
瞳孔をだだっ開きにして、壊れたロボットのような抑揚の無い声を出す文に、永琳は素敵過ぎて目を背けたくなるような笑顔を見せた。
「よろしい。でも、これだけじゃ私の気が済まないから、貴方も飛んで逝きなさい」
そう宣言すると、文の体を飛行機投げの要領で担ぎ上げ、俺が先程てゐを投げた位置までのっしのっしと歩く。
「…………はっ? わ、私は一体!?……って、何この体勢!! ちょ、永琳さん、待っ」
正気に戻った文が拘束から逃れようと必死に体を捻るが、先程の鍼や薬が効いているのか、まるで力が入らない様子だ。
「いいえ待たない。その糜爛した出歯亀根性、真っ白な雪で洗い流して来なさい!」
口上をキメた永琳は、その体勢から下半身のうねりを加え、プロペラ回転をつけて文の体を放り出した。
な、投げっ放しバーディクト(旧F5)……!!
「れっ、れすなああああああああっっ!!?」
――ぼすんっっっ。
俺がてゐを叩きつけた三メートル程向こうに、鴉天狗型の大穴が出来上がった。
流石は月の頭脳……惚れ惚れするほどに美しい、力学と腕力の結合技だ。
「……ふっ、天網恢恢疎にして漏らさず。さ、掃除も済んだし、戻りましょうか」
雪山に開いた大穴二つに背を向け、永琳と二人、勝者として花道を悠々と歩く。
※メインイベント:時間無制限 雪中生き埋めデスマッチ TAG
アンダー俺カー 5分18秒 ● 射命丸 文
バーディクトによる
八意 永琳 ○ 生き埋め葬 因幡 てゐ
――来週の新永遠亭プロレスも、どうぞお楽しみに!
…………んで、その日の夕飯。
「本当に何でも無いんですか? 結構いい雰囲気だと思ったんだけどなぁ……」
生き埋めの状態から不死鳥の如く復活した文が、蕎麦を勢い良く啜りながらしつこく食い下がってくる。
今日の晩ご飯はイナバの子達の不調もあって、多く作るのも簡単でさらに食べやすい、質素な山菜蕎麦だ。
暖を取るにはちょうど良く、消化にも良い、賢明な献立だと言えよう。
「と言うか、何で文まで一緒に食べてるのさ……」
今宵夕餉を共にしているのは、姫様に永琳、鈴仙にてゐという定番のピラミッドに、俺と文、加えて比較的元気なイナバの子数名、といった感じだ。
ダウン中のイナバの子達は、可哀相だとは思うが別室に隔離中である。
「細かい事を気にする男性はモテませんよ。それよりも、ね、ね、どうなんです? お二人さん」
「……まったく、貴方も大概しつこいわね。何でも無いって、何度も言っているでしょう?
昼間のアレは、頑張った労働階級に、雇い主からのちょっとしたご褒美」
……そう即座に上手い事否定されるのも、男として悲しいものがある。
少しムカついたので、この澄ました顔をギャフンと言わせてやる事にした。
「何だよ、誤魔化す事無いじゃないか。あの二人で熱く燃え上がった夜を忘れたのかい? 俺のラブリーナース」
「「ぶふぅぅー――――ッッ!!!」」
永琳と鈴仙が同時に吹き出した蕎麦が俺の顔面を直撃した。
……永琳は初めてだから兎も角、鈴仙は俺の顔に物を吹き付けるのが趣味なのだろうか。
「何するんだ二人とも、勿体無い」
食べ物を粗末にするなんてのは、犬畜生でもしないような愚劣極まる所業だ。
顔面にこびり付きまくった蕎麦を、手で掬って美味しくいただいた。
「なっ!? そ、そんなの食べるんじゃありません!!」
「し、師匠っ、落ち着いて下さい! 鼻からお蕎麦が出ています!……と言うか、二人とも何時の間にそんな破廉恥なっ」
無様に慌てまくる師弟の姿に溜飲を下げていると、唖然としていた文が我に返り、俺の袖をぐいぐい引っ張ってきた。
「ちょっと、やっぱりそういう関係なんじゃないですか!! 詳しい話、聞かせて貰いますよ?」
「いいよ。隠すような話でもない」
そっと目を閉じ、あの忘れられない夜を回想する。
「あれは先週、永琳の新薬の実験に付き合った晩の事だった……」
「……(わくわく)」
『え、永琳……熱い……苦しい……後生だから、解熱剤を……』
『あら駄目よ。他の薬とチャンポンにしてたら、実験の意味が無いわ。
……あぁ……凄い……貴方の体、どんどん熱くなってるわ……』
『なあ……五十度ってのは、人間が出していい体温なのか……?』
『ふふ、まだまだ。夜は永いわよ、ふ、ふふっ、うふふふふ…………』
「まったくもって、熱い夜だった……」
あの時の永琳の素敵な笑顔は、ちょっとやそっとの事では忘れられそうに無い。
熱帯夜の回想にうっとりとマゾい笑みを浮かべていると、文がプリプリ怒り出した。
「色気もへったくれも無い話じゃないですか!! 馬鹿っ、騙されたっ、私のわくわく返してっ!!」
「はっはっは可愛い奴め。別に最初から嘘はついていなかった筈だが」
「紛らわし過ぎます!」
からかい甲斐のあるパパラッチ天狗とギャースカ騒いでいると、永琳が冷たい瞳に怒りを孕ませながら俺の事を睨んでいた。
「……姫……彼を、この場で縊り殺しても構わないでしょうか」
「駄目よ。貴方が拾ってきたんだから、ちゃんと最後まで面倒見なさい。
……そんな怖い事言いながら、実のところ貴方も満更じゃないんでしょう?」
そう切り返して姫様は袖を口元に当てて、意地悪そうにほくそ笑んだ。
と言うか、犬扱いか俺は。
「なっ!……わ、私はそのような……」
無二の味方である筈の主君の裏切りに、うろたえた永琳の頬が一瞬で赤く染まる。
「……あらら、結構奥手なんですね。天才薬師の意外な弱点発見です」
「そうなのよそうなのよ。いい歳してみっともないったら」
「ははは、あの良さが分からんとは、お子様だなぁてゐは。そこがまた可愛いんじゃないか」
「そうですよねぇ。ギャップが新鮮です」
――がたんっ!!
文とてゐと三人で言いたい放題うんうん頷き合っていると、突然猛烈に立ち上がった永琳に、まとめて襟首を掴まれた。
「……ふ、ふふ……ここまでの屈辱、ちょっと記憶に無いわ…………貴方達、ちょぉっとお仕置きが必要なようね?」
顔は笑っているが、目から殺気光線が迸りまくっている。
「……あ~、永琳さん? 暴力反対ですよ?」
「そうよそうよ。図星指されたからって大人気無ぐふっっ!」
懲りないてゐの鳩尾に、容赦無く永琳の爪先がめり込んだ。
「……こ、怖ぇ……」
――ずるずるずるずる。
蟹のように口から泡を吹いているてゐと文と三人、ズルズルと部屋の外へ引き摺り出される。
「……さあ貴方達……特別に、馬鹿につける薬を処方してあげるわ!」
屋上 アポロ三発
――ちゅどどどどどどどどー―――んっっっ。
「「「うっひゃああああああっっ!!?」」」
「……平和ねぇ……」
「平和ですねぇ……」
「それにしても永琳ったら、あんなにムキにならなくてもねぇ……」
「結構お似合いだと思うんですけどねぇ……」
そんな姫様と鈴仙ののどかなやり取りが、弾幕飛び交う修羅道に投げ出された俺達の耳に届くような事は無かった……
…………
~ February ~ ――だけど、全ての人は迷い迷い、心の欠けを補う何かを探しながら、その命の旅路を半ばにして終える。
暦は如月。一頃よりは大分過ごし易くなったとは言え、まだまだ厳寒真っ盛りといったところだ。
つい先日、八雲藍と名乗る、スキマ妖怪の式とか言うお狐様と初めて顔を合わせた。
「来月には目を覚ますと思うから、申し訳無いが、もうほんの少し辛抱してくれ」
そう謝りながらしきりに頭を下げてきた藍さんに、永琳がそっと胃薬を差し出す風景は、実に感動的なものだった。
しかしよくよく考えてみると、もし何の紛れも起きなければ、俺はとうの昔にスキマ妖怪とやらの肥やしになっていた筈で……
こうして無事に生き延びて、多くの人達に助けられながら楽しく暮らせているのは、僥倖だとしか言い様が無い。
……藍さんの「来月には目を覚ます」という言葉が、不快を伴った靄となって胸中を満たす。
あと一月。
あと一月で、この奇跡のような生活ともお別れなのだ。
取り敢えず、餌にされそうになった事については断じて許す訳にいかなかったので、
藍さんにお土産として渡した散らし寿司を、俺のボロパンツを繋ぎ合わせて作った風呂敷で包んでおいた。
いい事をした後は、やはり気分がいい。
一月先の別れを今から思い悩むよりも、まずは今日が良い一日になる努力をするべきなのだ。
今日も一日、頑張ろう。
「永琳、今日は久々に妹紅で遊んでくるわ」
朝食を終えて箸を置くなり、姫様がそんな事を言い出した。
「あら。それならお供しますよ」
「要らない。何気に今年の初顔合わせだし、偶には一人で羽を伸ばしたいわ。お昼には戻るつもり」
これは珍しい……と言うか、姫様が単独で行動しているところを、少なくとも今日まで俺は見た事が無い。
「そうですか……くれぐれも、お気を付けて下さいね」
「もうっ、つくづく思うけど、永琳は心配性ね。……大丈夫よ、私達何があっても死にはしないんだから」
何だか姫様の物言いに引っ掛かるものを感じたが、それよりも気になる事があったので訊いてみた。
「あの、『もこう』って?」
「友達よ、友達。それはそれは永い腐れ縁」
「…………」
からからと笑う姫様に、無言で湯呑みを傾ける永琳。
食器の片付けをしている鈴仙やイナバの子達が、不安げに視線を俺達の方に彷徨わせている。
……何だろう、この変な雰囲気。
後方で、てゐが食後の腹ごなしに太極拳を舞っているが、多分それは関係無い。
「姫、少し不用意ですよ」
「別にいいじゃない。私はこの人ともう少し仲良くなりたい。
だと言うのにこの馬鹿、普段は何かと慇懃無礼な癖に、こういう美味しい肝には絶対自分から食い付いて来ないんだもの」
「……それは当たり前でしょう」
無理矢理他人の傷み腹を突付くような趣味は無い。
そんな俺の及び腰な返答に、姫様はお得意の意地悪な微笑を見せた。
「そうね、そのメリハリの利いた距離感は貴方の美点でもある。
……でもね、そうして地を這っているだけじゃ、雲の彼方に浮かぶ宝物は永遠に手に入らないわよ」
「む……」
それは一理ある。
何時までも気を使って腰を引かせていては、確かに深く相手を知る事は出来ない。
……構わないから、もう少し踏み込んで来い、という事か。
先程の会話から察するに、姫様の台詞に何か糸口があったようなので、検証してみる事にした。
「むむむ……そうか!!」
「ど、どうしたのよ。急に大声出して」
お茶のお替りを用意してくれていた鈴仙が、俺の大声にビクリと体を震わせた。
「どうやら俺達はとんでもない思い違いをしていたようだ……鈴仙、先程の姫様の台詞を思い出してみてくれ」
「? ええっと、確か……」
『もうっ、つくづく思うけど、永琳は心配性ね。……大丈夫よ、私達何があっても死にはしないんだから』
↓
『 っ く く 、永琳は …… 私 が も んだから』
↓
『っくく、永琳は……私がもんだから』
「つまり、永琳の胸は姫様が揉んであそこまで大きくしたという事だったんだよ!!」
「「「な、なんだってー!!」」」
イナバの子達から一斉に驚愕の声が上がり、
「んな訳無いでしょう!!!」
――どごんっっ!!!
永琳の蹴りが俺の延髄をブチ抜く音が、それを上回る大音量で響き渡った。
「かっ……」
体の髄を打ち抜く大衝撃に、目の前に大銀河が展開される。
「あ~らら……それじゃ、私は行って来るからね~~」
「……ボ、ボン・ヴォヤージュ……」
姫様の声を遥か遠くに捉えながら、あっと言う間に俺の意識は成層圏の彼方へと旅立って行った。
…………
さて、お昼までには戻るとか言っていた筈の姫様が、昼食の支度が終わったにも拘らず帰って来ない。
「どうしたんだ、姫様は? 今更反抗期とか言う歳でもあるまいし」
「万年反抗期と言う気もしなくは無いけど……」
俺の危惧に、鈴仙がなかなかに的を射た返事を寄越してきた。
「う~ん、大丈夫かな? 永琳」
「そうねぇ……」
人差し指でこめかみを叩きながら生返事をすると、永琳は一つ力の無いため息をついた。
「……いいわ、迎えに行きましょう。貴方も付いて来なさい」
「俺も?」
「ええ。……最初から、こうなりそうな気はしていたのよねぇ……」
…………
永琳に襟首を掴まれた状態で竹林の上空を吊られ漂う事数分、程無く非常に分かり易い異常地帯を発見した。
視界の限りを埋める竹林に、クレーターのようにごっそりと抉られた一角があった。
「あれか。存外近かったわね」
「よ゛……よ゛か゛っ゛た゛……」
いい加減脳への酸素の供給が不足してきており、もう少しで首吊り人形に成り果てるところだった。
「うわ……酷いなこりゃあ」
降り立った場所の有り様を表現するのは、その一言に尽きた。
辺りの竹はぼろぼろに焼け落ち、露霜の名残を受けて湿っていた筈の土壌は、乾いた焼け土と化していた。
「ええっと、姫様は何処だ?」
「この辺りに居る筈だけど……」
きょろきょろと二人で辺りを見回していると、永琳がある一角を指差した。
「あ、居たわ。……ふむ、今日は姫様の勝ちかしらね」
永琳の指差した方に、確かに人影が二つ転がっていたのだが……
「げっ!!? な、何だよアレ!!」
「何だよって言われても……姫様と妹紅だ、としか言い様が無いわね」
上半身の右半分を無くした姫様が、地べたに座りながら、俺達に向かって笑顔で残った左手を振っていた。
「お~~い、こっちこっち~~……」
「ふむ、自分で動ける程度には元気みたいね。何よりだわ」
「……アレは元気と呼んでいいのか……よく見たら、左足も膝から下辺りから無くなってないか?」
遊びに行ってあんな風になるとは、どんなダイハードごっこだ一体。
「細かい事は気にしないの。妹紅のあの姿に比べれば大分良心的でしょう」
永琳の指し示す先に、下半身だけになったモンペ姿が転がっていた。
「う~ん……これ、夢じゃないよねぇ……」
「夢も現も、所詮は何処かの誰かのちっぽけな妄想に過ぎないのよ。ほら、行きましょう」
「あ、ああ……」
俺達が辿り着くと、姫様は血の気の失せた蒼い顔をしながらも、容態にそぐわぬあっけらかんとした顔で笑った。
右肩から先は焼け落ちたような感じで無くなっていて、傷口の周辺や頬が、ケロイド状に焼け爛れている。
「遅くなっちゃって御免なさいね。蘇生に廻せる余力が無くて、動けなくなっちゃった」
「どうせそんな事だろうと思ってましたよ。さ、帰りましょう」
永琳は苦笑と共に姫様の手を取り、ぼろ切れのようになった体をそっと背負った。
……月人の生命力って、凄いのなあ……
「……ねえ姫様? 帰るって言っても、アレはどうするんですか?」
血まみれでスッ転がっている下半身を、恐る恐る指差す。
葬式以外の場で死体を生で見るのは初めての体験だが、顔が無い分、まだ恐怖感は軽かった。
「放っておいて構わないわよ。時間が経てば、勝手に元に戻るわ」
「げ。これで生きてるのかよ」
脳も無くし、心臓も無くしたような状態で死んでいないって、妖怪ってのはつくづく恐ろしいものだ。
「誤解しないで。私達も妹紅も、間違い無く人間よ。
朝にも言ったでしょう? 何があっても死ねないのよ、私達」
姫様が、俺の率直な感想をからからと笑い飛ばしながら、何だかとんでもない事を言ってきた。
「はい? 死ねない?」
まるで噛み合わない、俺と姫様の何処か滑稽な問答に、それまで黙っていた永琳が、観念したようなため息をついた。
「……帰ったら詳しい話を聞かせてあげるわ。まずは屋敷に戻りましょう」
「そうして貰えると助かるわ。ここは地脈が悪いのか、いまいち力の戻りが悪い」
「分かった……その前に、これだけ」
結局顔を見る事の叶わなかった妹紅さんの亡骸の傍らに、お土産として持って来ていた冥菓・揉み痔饅頭を置いておいた。
現在人里の一部で大ブレイク中の、極悪スパイスぎっしり血便間違い無しのニクい奴だ。
「何かしら、それは」
「いや、姫様の友人に失礼があってはいかんと、用意して来たんだよ」
俺としては、この姫様の友人という希少種がこの銘菓を食べてどんな顔をするのか、是非とも拝見したかったのだが。
「律儀なものね。……ありがとう、私の顔を立ててくれて」
……姫様のこんな毒の無い優しい笑顔を、俺は初めて視た。
…………
「♪そ~ら~を自由に、飛~びた~いな~♪」
「……はいはい、胡蝶夢丸~~♪」
「♪アン、アン、アァン とっても上手ね エリえ~もん~~♪」
「…………ツッコみませんよ、俺は」
右肩から先と左足の無い姫様と、彼女を背負って飛ぶ永琳の楽しそうな歌声。
そして、永琳の両腕からぶら下がっているのは、相変わらず襟首から吊るされている俺。
こんな所を文にでも見られたら、さぞ面白い事になるだろうねぇ……
肌を刺すような寒空の下、正午より少し遅れて真上に昇った太陽の光が、瀕死でアンニュイな俺を慰めるかのように緩く照らしつけていた。
…………
屋敷に戻るなり、出迎えてくれたイナバの子達が、スムーズな連携で姫様を寝室に運び込んだ。
誰も慌てた様子がないという事は、今日みたいなケースはそう珍しい事でも無いと言う訳か。
姫様の事をイナバの子達に一任して、永琳は俺を自室に呼び入れた。
「いらっしゃい。座って楽にして頂戴」
「ん」
勧められるままに簡素な木製のスツールに腰掛け、永琳が作業机に背を向ける形で、二人向かい合う。
「……さて、何処から話したものかしら」
「どうせなら、全部聞きたい。永琳が俺に話しても良いと思う範囲で構わないから」
遠回しにとは言え、折角姫様から許しを頂いたのだ。
いい機会だから、この永遠亭の人達の事をもっと深く知りたい。
「そう……分かったわ、聞かせてあげる。
あの子が永遠亭に流れ着いて来てから、私が今日まで一日欠かさずつけて来た、『ウドンゲ赤裸々観察日記』の全てを!」
そう力強く宣言すると、棚から百科事典と見紛うばかりの極厚日記帳が取り出された。
「いや、その……今は君の劣情猥雑師弟愛列伝を聞きに来た訳ではないのだが……」
ある意味、激しく興味を惹く内容ではあるが。
「冗談よ、冗談。……さ、本当に長くて厭な話になるから、覚悟して聞いてね」
「任せろ。詰まらん話なら、俺は容赦無く寝る」
「そしてそのまま目覚める事はありませんでした、と…………さて」
軽口を叩き合うのを合図に、月と地球と幻想郷を跨いで幾重にも刻み込まれた傷痕が、永琳の口から謳い上げられた。
・
・
「…………というお話だったとさ…………ん~~~~~~っ」
本当に、本当に長い話を終え、永琳は可愛らしい唸り声を上げながら背を反らして、凝り固まった上体をほぐした。
聞かされた過去の重さに嘆息しつつも、俺は彼女の胸元が強調されるのをバッチリ見逃さなかった。
「さて、ご感想は?」
「おっぱ……じゃなかった、みんな苦労してるんだなぁ、と」
「……随分あっさりと片付けてくれるわねぇ……」
永琳ががく、と肩を落として苦笑を浮かべる。
「あぁ、違う違う。軽く言っているんじゃなくてさ。
昔苦労してきたから、今こんなに優しいんだろうなって思ったんだよ」
慌てて付け足した俺の弁明に、永琳はぱちぱちと、二回大きな瞬きをした。
「優しい? 私達が?」
「うん、永琳も姫様も鈴仙も、みんな優しい」
犯した罪の重さに悩み、痛みや悲しみに苛まれながら、こんな辺鄙な所まで流れ着いて。
それでもなお悩み、痛み、苦しみながら優しくなる事を選んだ、この永遠亭の強い人達が、俺は大好きだ。
「……呆れた。怖くなったとか、軽蔑したとか、少しは思わないの?
今貴方の目の前に居るのは不死身の化け物で、おまけに大量殺人犯よ?」
「思わない。そりゃ犯した罪は何を以っても贖えない、死ぬまで背負って行くべき十字架だろうさ。
でも、同じ過ちを二度繰り返すような馬鹿は、ここには居ないだろ?
今俺の目の前に居るのは命の恩人で、おまけにとても優しい素敵な人だ」
「……」
――すっ。
俺の言葉を詭弁と咎めるかのように、永琳のたおやかな人差し指が、音も無く隙の無い所作で俺の喉元に突きつけられる。
「分からないわよ? 貴方が私達にとっての不具合になれば、今すぐにでもこの指が貴方の首を掻き切るかも知れない」
眼前の厚顔無恥な人間を嘲るように吊り上げられた唇から、おおよそ感情の覗えない淡々とした音が漏れた。
「姫様を逃がした時と同じように?」
「そう。月の使者達を謀り陥れ、鏖殺した時のように」
……馬鹿馬鹿しい。
永琳が見せる外敵に対する容赦の無さは、身内への愛情の何よりの証なのだろう。
それなら、俺が彼女を恐れなければならない理由など、微塵も無い。
「いい加減にしろ馬鹿。俺は何があっても永遠亭の、君の味方だ」
出来る限りに強く言葉を放ち、突きつけられた彼女の手を、右手で強く掴んだ。
「っ…………何を……」
先月の雪掻きの時、永琳は自分の事を『左道に外れた外道』と評し、
また、自分が『生きている』と表現して良いか分からない、という風な事も言っていた。
「なあ永琳。ある程度自覚しているとは思うけど、あまり自責が過ぎるのも良くないぞ。
顔を合わせて一月程度しか経っていない、しかも今日初めて事情を知った俺がこんな事を言うのもアレだけど、
もう姫様も永琳も、十分に罰を受けたと思うんだ」
鈴仙もてゐもイナバの子達も、やがて時間の波に呑まれて永琳や姫様ら蓬莱人を追い越し、彼女達を残して朽ち消えていく。
得たものを時間と共に亡くし置いて行かれて、新しい思い出を手に入れる度に心太のように古い思い出はこぼれ落ちて。
それをただ眺めるしか出来ず、成長する事も退化する事も出来ず、永遠にその場に留まり続ける事しか出来ない、魂結びの牢獄。
この人達は、気が違いそうな程の永い間、こんな自壊してしまいそうな悲しい在り方を強いられてきたのか。
……あんまりじゃないか。
「ちょ、ちょっとどうしたの。いきなり泣いたりして」
「はい?」
永琳に言われて自分の頬に手を当ててみて、初めて気付いた。
……何だよ、俺、泣いてたのか。
残った左手で、慌てて目元を拭い取る。
「…………」
「あ~、悪い。こりゃみっともないや」
「……馬鹿ね。みっともなくなんて無いわよ」
永琳は初めて聞くような優しい声色でふんわりと微笑むと、
先程からずっと握ったままの右手はそのままに、残った左手を俺の頬に添えてきた。
「ありがとう。私の為に泣いてくれたのは、ウドンゲに続いて貴方が二人目。
……でもほら、私の手、ちゃんと温かいでしょう?」
「…………ああ」
寒気に中てられ冷えた手の平の内から、確かな命のぬくもりが沁みてくる。
「貴方が心配してくれなくても、ちゃんと私は自分が生きているのを実感している。
……そうね、以前使った表現は適切じゃなかったわ。
私達は道を外れてしまったのでは無くて、ただ蓬莱の薬に縛られて時間の渦に乗れないだけ」
「そうだな。永琳も姫様も妹紅さんも、俺達と同じだ」
昼間に姫様が言っていた事を思い出す。
『私達も妹紅も、間違い無く人間よ』
同感だ。
左道に住まう畜生鬼の手の平が、こんなに温かい訳あるものか。
「それにね? 確かに淵源は自責の念だったけれど、私は何もそれだけを理由に今の生活を選んだ訳じゃない。
姫様と此処に来てから過ごした、今日までの時間を切り出せば、私は間違い無く幸せだったと言えるわ」
「……そっか」
「ええ。……いい機会だから、もう一つぶっちゃけちゃいましょうか。
皆が私を慕ってくれているのと同じ程度には、私もこの永遠亭の人々を愛してる」
「…………そっか」
良かった。
全面的に鵜呑みにして良い言葉では無いが、少なくとも偽りでない事は、目の前の柔らかな笑顔を視れば分かる。
本人が幸せだと言っているのだから、ただの客分でしかない俺がこれ以上言える事は無い。
んで、気が緩んだ拍子に悪戯心が芽生え、
「じゃあさ、俺の事は?」
……うっかりこんな事を口走ってしまった。
「へっ?」
素っ頓狂な声を上げると、永琳は穏やかな笑顔から一転、目を見開いて白黒させた。
「そっ、そそそそう来るとは思わなかったわ……」
先程の優しいお姉さんチックな出来た風格は何処へやら、顔を真っ赤にしておろおろと狼狽している。
これはこれで可愛いと思うので、俺としては何ら問題は無い。
「あ、あのね? 貴方の事もそれなりには気に入ってますけど、それはその、ね。……あぁ、困ったわ……」
どうでも良いが、未だに繋いだままの手をブンブン振り回すのは、俺の肩が今にも外れそうなので勘弁して頂きたいと思う。
周りの雰囲気が何時の間にやら平時の緩いものに戻っているのを感じ、体の力を抜くと、
――ぎしっっ。
「「?」」
襖の向こうから、床板が軋む音と、幽かな話し声が聞こえた。
永琳と二人、耳を傾けてみる。
『あーもうっ、何やってるのよ永琳は! 薬学や術理ばかり達者で、自分の色恋沙汰にはてんで空っ下手なんだから』
『姫様ぁ、やっぱり良くないですよ、こんな覗き見だなんて……』
『黙らっしゃい! 折角私がこんな痛い目見てまで切っ掛け作ってやったってのに、何よあのヘタレ薬師!
大体彼の方も、何でそこで一気に押し倒さないのっ!! ひょっとして、EDか性病持ちなんじゃないの?』
『ちよっと姫、何言ってるんですか! イナバの子達も居る前で、そんな下劣な……』
『……ねぇねぇてゐちゃん、EDって何?』
『それはね、あいつの×××が××で×××だから役立たずって事でね、
永琳様の×××に××して×××××したりするには不適切って事なの』
『子供に詳細な説明をするな馬鹿てゐ! あ、貴方もそんな事不用意に訊かないのっ』
『え~っ、私子供じゃないもん。大人の魅力で、お兄ちゃんの事メロメロにするんだもん』
『あらあらあら、これは強敵出現ね。彼も隅に置けないこと。永琳も前途多難だわ』
『……あ、頭痛くなってきた……』
『そんな事より、二人ともこっちの方を見ている気がするんですが』
『あら、ひょっとしなくてもバレちゃったみたいね。みんな、退散よ!』
「…………殺るか」
「…………ええ」
永琳は作業机の引き出しを開くと、中に隠されていたスイッチを、
「ポチッとな」
――ぶしゅうううううううううっっっ。
スイッチが軽く鳴った瞬間、廊下の方から激しいスチームの噴射音が聞こえた。
『ぐっ、げほっげほっ、一体何なの、これっ』
『な、何だか気が遠く……』
――ばたばたばたっっ。
『ちょっ、ちょっとみんな!?
くっ、恐るべし月の頭脳。何時の間にこんな仕掛けを……
しかし詰めが甘いわね。私達蓬莱人に毒は効かないっていう初歩をお忘れかしら?』
――わらわらわらわらっっ。
『あら? イナバたち、もう起きたの?……って、きゃああああっっ!!?
なっ、何でみんなそんな紫色の肌で私に詰め寄って来るのっっ!!?』
『『ガ、ギ……ヒ、ヒメサマ……ヒギル……』』
――ぐちゃっ。ぬちゃっ。めりめりめりっっっ。
『ひっ、ひぎいいいいぃぃぃぃぃっっ!!?』
『『『らっせーらっ、らっせーらっ』』』
「うわぁ……」
襖に映る姫様やイナバの子達の影絵が、何やら生物学的にあり得ない形状になっているが、
基本的に自業自得なので気にしてはいけない。
「……あぁ、滅多に聞けない、姫様の珠玉の悲鳴……優曇華の花待ち得たる心地とは、まさにこの事ね……」
「月人の愛情って、随分歪んでるのなぁ……」
※メインイベント:時間無制限 永遠亭内変則タッグタシーロマッチ
ED性病男爵 1時間53分48秒 ● 蓬莱山 輝夜
バイオハザードによる with
八意 永琳 ○ イナバーズの裏切り イナバーズ
――来週の新永遠亭プロレスも、どうぞお楽しみに!
…………
「……と言う訳で、私は永琳と彼を是非くっつけたいと思います」
あの思い出したくも無い馬鹿騒ぎの後、姫様は珍しく私だけを自室に呼びつけて、そんな事を言ってきた。
「姫様も、懲りませんね……」
今私の眼前に在らせられる麗しの姫様は、全身をぞんざいな継ぎ接ぎと包帯まみれにして、ミイラの出来損ないみたいになっていた。
「これしきで懲りてなんかいられますか。大体永琳は、自責と自戒が強すぎる。
昔っからこうなのよ。何に於いても私より上にあってはいけない、私より幸せになっちゃいけない、って」
「……そうですね」
それは、端から二人の関係を見ていてもよく分かる。
師匠は常に己を抑え、後方から姫様を立てる事しか考えていない。
「ありがたい気構えではあるけど、度が過ぎると私が足枷になっているみたいでいい気はしないわ。
今回だってそう。折角いい拾い物したんだから、逃がす手は無いって言うのに」
「姫様は、また随分彼の事を気に入られたのですね」
「そうね。相当極まった変質者ではあるけど、肝は据わっているし、何より懐が深い。
イナバ達の彼への懐きようったら、無いでしょう?」
「はい。子供達なんかは、もうベッタリですね」
最近は『ぷろれすごっこ』とやらが主流らしく、この前庭で遊んでいるのを見かけた時には、
彼がてゐにせがまれて肩車をしようとした所を、見事にフランケンシュタイナーで返されていた。
あの後、怒り狂った彼がアックスボンバーでてゐの体を一回転させたシーンは、ちょっと忘れられそうに無い。
「……確かに、本能で動く彼と理屈で動く師匠、って言うのは良いバランスですよね。
二人とも何気に行動力は抜群なんで、手が付けられなさそうです」
「そうそう。永琳みたいな理屈屋には、あれ位奔放な馬鹿がちょうどいいのよ」
ここ最近というもの、師匠は今までに私が見た事の無かった表情を幾つも見せている。
それは間違い無く、外から来た彼が引き出したものだ。
「……うん、師匠と彼がそういう仲になってくれたら、私も嬉しいです」
「でしょう? まったく誰から見ても丸分かりだって言うのに、永琳も何を意固地になって否定しているのやら」
……それは、貴方やてゐが面白がって弄繰り回すからではないかと……
心の中でツッコミを入れた私を尻目に、すっかり姫様は盛り上がってしまっている。
「もうこのまま放っておいたら、春まで何事も無く彼は外の世界に帰ってしまうわ。
ここは私達で何か手を打ちましょう」
「はぁ、それは良いのですが……具体的にはどのような?」
「それは、貴方が考えなさい」
こ、このグータラ姫は……!
肝心な所で役に立たないダメ主君に憤ってみたが、すぐにそれを打ち飛ばす妙案が浮かんでくれた。
……今月は二月。
もうほんの数日経てば、こういう色事に打って付けのイベントがあるではないか。
つい最近まで隠れて生活していた事、それに女所帯という事もあって通年は歯牙にも掛けなかったイベントだけど、今年はそうは言っていられない。
思い立ったが吉日、こんな所で姫様とチンタラ遊んでいる場合ではない。
「頑張ってね~~」
「うるさい、働け!!」
ニコニコと手を振る竹取ミイラ姫にうっかり本音を浴びせつつ、私は師匠の部屋に急いだ。
…………
――すぱー―――んっっ!!!
「師匠ッッ!!!」
「わっ。……ウドンゲ? 驚いた、声くらいかけなさいな」
「そんな悠長な事言ってる場合じゃありません!
……はい師匠、問題です。二月十四日は何の日ですか?」
「何よいきなり、変な子ね。…………う~ん、二月十四日ねぇ……」
何処ぞの捻くれトンチ坊主のように、師匠は指でポクポク頭を叩きながらしばし瞑目すると、
「あぁ、はいはい。ジェームズ・クックが航海中、ハワイの原住民に殺害された日ね」
ダ、ダメだこの人。
「なっ、何でわざわざそんなキツい所を引き出すんですか!」
「冗談よ、冗談。バレンタインでしょ、聖バレンタインデー。
……それがどうかしたの?」
「どうかしたの、って……師匠は、彼に何かあげないんですか?」
「…………そういう事か。……私個人からは何かを贈るつもりは無いわよ」
「ええっ!? そ、そんなっ。チョコにお得意の薬を混ぜて篭絡したり、
全裸にリボンを巻いて『うっふん、プレゼントはワ・タ・シ』とかやる大チャンスじゃないですか!!」
「ウドンゲ……いい物あげるから、少し落ち着きなさい」
――ぷすっ。
「うっ」
首元に痛みも無く注射針が刺さり、一瞬で中の液体が流し込まれる。
「あっ……あぁ……」
「……落ち着いたかしら?」
「う、うぅ……ごめんなさい師匠……鈴仙は……鈴仙は、悪い子です…………」
「ありゃ、効き過ぎたわね。……ふむふむ要改良、と」
何とも抗い難い憂鬱な気分に襲われ涙をはらはらと流していると、師匠が私の額を人差し指で軽く小突いてきた。
「あ痛っ」
「馬鹿ね。私個人からは、って言ったでしょう?
……当日は皆でね、イナバの子達も全員入れて食べられる位のケーキを作ろうと思っているのよ」
「ケーキ、ですか?」
「ええ。その方が彼も喜ぶんじゃないかしら」
「……はぁ……」
卑怯な逃げ方だ、と一瞬思ったけど、そうかも知れない、とも思った。
以前、食事中に彼とした会話を思い出す。
…………
『モグモグゴクゴク、あ~今日も美味いやムシャムシャ』
『……ホント貴方って美味しそうに食べるわね……そんなにここのご飯は美味しい?』
『ああ、最高だ。こんな沢山の人達と一緒に笑いながら食べるご飯が、不味い訳が無い』
『……そう』
『そうなの。モグモグ……ぶはああぁぁぁっっ!!! 不味うううううっっっ!!!
だ、誰だこの餃子作ったの!! この死臭漂う大珍味は、流石の俺にもフォロー不可能!!』
『あら、私特製のワサビ納豆蜂蜜餃子はお気に召さなかったかしら』
『またアンタか姫様!! 折角いい腕してるんだから、ネタに走るの止めて下さいよ!』
『オホホホお断りよ。あぁ、これだから人の幸せをぶち壊しにするのは止められないわぁ~~』
『ぐっ、主君の過ちを糺すのも臣下の務め! その大外道、最早捨てては置けぬ!!』
『あらら、私に是非を問おうと言うのね、賤しき地の民が。面白い、表に出なさい!!』
『望むところ!! 当方に人間の尊厳あり!!』
―ーちゅどー―――んっっ。
…………
「…………」
随分と不要な事まで思い出してしまったけど、確かに彼には、団欒を非常に貴ぶ気質がある。
……私達と同じように、彼にもそれなりの過去や思想があると言う事かな。
「……そうですね。いい案だと思います」
私達外野があれこれ手を焼いてみたところで、結局どういう道を選ぶのかは師匠と彼、当人達次第だ。
今回の事だって、師匠なりに彼の事を想ってこういう選択をしたのだろう。
「そう……それじゃウドンゲ、明日は一緒に里や紅魔館に行きましょうか。
材料の買出しと、あと調理器具を借りないとね」
「はいっ。みんなで飛び切り美味しいケーキを作りましょう!」
私の自慢の師匠と、その師匠の眼鏡に適った人だ。
心配なんてしなくても、きっと最高の選択をしてくれるだろう。…………多分。
…………
さて、今日は二月十四日。
俺の敬愛する、藤島親方(元大関・武双山)の誕生日だ。
聖バレンタインデーとか言う行事など、見た事も無いし聞いた事も無い。
昨晩悶々としてしまってなかなか寝付けず、うっかり昼前まで豪快に寝過ごしてしまったのは、
『ひょっとして今年は』などと期待に胸を躍らせていたという惰弱な理由からでは断じて無い。
……ホントだよ? ホントだよ?
…………さあ今日も一日、張り切って行こう!
――すぱー――んっっ!!!
「おはようみんなっっ!! 今日って何月何日だったっけ!!?」
勢い良く大広間の襖を開いたが、珍しく中はもぬけの空だった。
「……あれ? 誰も居ない?」
どでかい広間に、俺の物であろう朝食の残りらしき膳が一つ、ぽつんと置かれている。
そう言えば、俺の部屋からここに来る間も、誰とも顔を合わせる事が無かった。
「……ふむ」
まあこればかりは寝坊した俺が悪いので、膳の前に腰を落とし、遅い朝食を頂く事にした。
「…………」
齧り付いた卵焼きは、今日も複雑に味の染みた良い出来だったが、いつもと比べてどうにも味気無かった。
…………
「……で、一体何なんだこれは」
一人寂しく朝食を終えた後、人影を求めて屋敷を彷徨っていた訳だが。
調理場に差し掛かる廊下に掲げられたバカでかい看板を前に、俺は立ち往生していた。
『男子この場より先に足を踏み入れるべからず』
「……」
廊下の向こう、調理場の中から、何やらわいわいとイナバの子達が楽しそうに騒ぐ声が聞こえる。
要するに、今日は永遠亭のみんなで何かを催していて、俺は除け者にされている訳か。
ムカついたので、看板の頭に『美』の文字を入れておいた。
『美男子この場より先に足を踏み入れるべからず』
「……そこまで言われちゃ、仕方が無いな」
まあ、こういう日もあるだろう。一人で燻ぶっていても仕方が無い。
この時間、屋敷の近辺なら危険も無いだろうし、たまには外へ羽を伸ばすとした。
…………
「う~~、寒い。それにしてもこの辺りって、本当に竹や野草しか無いんだな」
それなりに長い距離を歩いた気がするが、基本的にある程度拓けた一本道しか通っていないので、帰りに迷う事も無いだろう。
竹の葉の隙間から降り注ぐ暖かみを孕んだ陽光に、来たる春の兆しを感じる。
……もうすぐ冬が終わり、春が来る。
「…………はぁ」
一つ、気だるく白い息を吐く。
本来なら歓迎すべき新たな季節の訪れを、どうにも快く迎える事が出来ない。
何時の間にか、この幻想郷で……否、永遠亭で過ごしたほんの短い日々は、
二十数余の年月を過ごした外での暮らしと天秤に掛けても遜色が無い程に、俺の中で掛け替えの無い物になっていた。
ここには、甘えを叱責し、生きる糧を与えてくれる主君が居る。
ここには、孤独を埋めて胸を満たしてくれる優しい人達が居る。
……ここには、誰より傍に居て欲しい、何より愛しい人が居る。
何をとって考えても、外の世界では手に入らなかったものばかりだ。
こちらを選んでしまうのが、一番良い選択肢のように思える。
だけど、今日まで幻想郷で得た物は、全て客人として得た物であって、あくまで俺は『外から来たお客様』に過ぎない。
家族との絆、過ごした時間、沁み付いた習性。
そうした外の世界との繋がりに当たるような何かが、今の俺と幻想郷との間には無かった。
「……何がしたいのか、何が欲しいのかね、俺は……」
宛ても無く一人ごちて、空から前方に落とした視線の先に、一人の少女がこちらの方に歩いて来る姿を捉えた。
……まずいかも知れない。
妖怪の見た目からその能力、性質を判断出来ないというのは、何処より永遠亭で思い知らされている。
万一の事態に備えて持ち出しておいた発炎筒を、そっと懐から取り出した。
少女の方もこちらの方に気付いたらしく、気負った風も無く、悠々とこちらに歩みを進めて来ている。
「……南無三っ」
発炎筒のフックに指をかけ、力を込めた。
軽い抵抗と共に、火付けのフックが一気に引っ張り出され、
――ばっっ。
「んなあっ!!?」
発炎筒からフックに伸びた紐に色鮮やかな万国旗が姿を現し、辺り一帯を紙吹雪が舞う。
万国旗の中の一枚に、可愛らしい兎のイラストと共に、こんな事が書かれていた。
『かかったなアホが! byプリチーお宇佐様』
「ふっ、ふざけるな馬鹿野郎!!!」
何の役にも立たなかった発炎筒もどきを思い切り地面に叩きつけて憤慨していると、すぐ傍まで来ていた少女が呆れた声を出した。
「……何やってるのさ、アンタ」
右手から下がった籠には、食用の野草。
その少女は、何処かで見たようなモンペにサスペンダーという、一風変わった出で立ちをしていた。
…………
「へぇ、外から来たの。大変ねぇアンタも」
先程の醜態から敵意が無いのを感じてくれたのか、あの後妹紅さんは、俺を竹林の中の掘っ立て小屋に案内してくれた。
「まあゆっくりしてよ。何も無い所だけどさ」
「悪いな、お邪魔させて頂くよ、妹紅さん。」
「はは、妹紅でいいよ。……はい、出涸らしだけど」
「……ありがとう。頂きます」
目の前に置かれた湯呑みに手を伸ばし、散歩で乾いた喉を潤した。
最初はもっとおっかない人を想像していたのだが、いざ話してみるとまったく普通の女の子で、少々拍子抜けした感じだ。
「この前はお土産ありがとうね。あれ、アンタでしょ?」
「あぁ、あれか。どうだった?」
「うん、気に入った。お陰様で、私の火力も一割増しってもんよ」
「そうか……」
あの極悪冥菓を喜んで食べるとは、流石は姫様の旧知だけあって、なかなかの変態のようだ。
「……何か失礼な事考えてる?」
掲げられた人差し指に、ぽ、と一つ火の玉が灯る。
「いやいや滅相も」
慌ててもう一度湯呑みを啜ると、誰かが入り口の引き戸を開く音が響いた。
「――妹紅、居るか?」
「あぁ慧音、いらっしゃい。入りなよ」
慧音と呼ばれた来訪者の顔には、見覚えがあった。
向こうの方も俺の事を覚えてくれていたらしく、俺の姿を視止めて目を丸くした。
「あれ、お前は確か、永遠亭の……」
「覚えていてくれたんだ。あの後どうだった?」
彼女は先月の半ばに一度、永遠亭を訪れて大量の風邪薬を買って行った事があった。
「あぁ、お陰で助かったよ。
まったく、一人罹ってしまえば拡がるのはあっと言う間だから、風邪と言うものは困る」
「何だ、二人とも知り合いだったの。……ね、慧音。その袋、何?」
「これか? 森の古道具屋に寄ったら、何やらチョコレートの駄菓子が沢山置いてあってな。
お茶請けに良いと思って、少し多めに買って来た」
そう言ってその場に置かれた袋の中には、懐かしの天使vs悪魔なシール入りウェハースチョコがぎっしりと詰まっていた。
……あぁ……遂にこのチョコも幻想郷送りになったのか……
「じゃあお茶請けが増えた所で、仕切り直そうか。アンタも一緒するでしょ?」
「ふむ……それじゃ、遠慮無く」
立ち上がった妹紅に空になった湯呑みを渡し、袋の中のチョコに手を伸ばした所で、
「「そのチョコレート、待ったあああああ!!!」」
――どがああああんんっっ!!!
入り口の戸をショルダータックルで粉々に吹き飛ばしながら、突然姫様とてゐが乱入して来た。
「な、何事だ!?」
「げっ! か、輝夜っ!? アンタわざわざ私の家まで、何しに来たのよ!!」
「お黙りなさいこの泥棒もこ!! 貧相な芋娘の分際でウチの客分を誑かそうとはいい度胸ねぇ。
生憎そいつはウチの薬師に売約済みよ」
「そうよそうよ。千年経っても脳味噌に皺一つ増えない炎上馬鹿と、牛乳臭いハクタクは引っ込んでなさい!
…………って、そこの彼も言ってるわよ」
「言ってねえ!!」
暴言の責任を俺に擦り付けようとするてゐを、思いっ切り一喝した。
「……一体何を言っているのか分からないけどアンタ達、人の家を壊した責任くらいは取って貰うわよ?」
先程までの穏やかな雰囲気から一転、妹紅は殺意のこもった赤い瞳で、姫様とてゐを睨み付けた。
「責任なんて面倒なもの、誰が取るもんですか!! 喰らえ先手必勝!!」
不意を突き、腰を落とした低い体勢で突っ込んだ姫様が妹紅の腰に食らい付き、テイクダウンを奪った。
「なっ……!」
そのまま蜘蛛の如く隙の無い動きで妹紅の背後から足と首を絡め取り、一気に絞り上げる。
「存分に味わいなさい! イナバ達と編み出した対蓬莱人最終奥義、
STF(ステップオーバー・てるよ・フェイスロック)!!!」
「ぐっ!?……ぎゃああああああっっ!!!
痛い痛いっっ、死なない程度に痛いいいいっっ!!!」
……まさに蓬莱殺し!
姫様の陰険な性格がよく滲み出た、非常に嫌らしい技だった。
妹紅の悲鳴に気を良くした姫様は、うっとりと無茶苦茶いい笑顔をしている。
「も、妹紅っ」
慧音さんが妹紅を助けに入ろうとするが、てゐが巧みに進路を妨害していた。
「ほらほら、あんたの相手は私、私」
「くっ……お前らっ……!」
姫様の極悪奥義を逃れようの無い角度で受けた妹紅が、涙目で苦しげな声を漏らす。
「……た、助けて、慧音……」
「!!」
――どくんっっ。
外まで聞こえるような確かな音で、一つ心臓を強く鳴らした慧音さんの頭から……
――めきめきめきっっ。
……二本の禍々しい角が生えてきた。
「げっ!?」
「呼ばれて飛び出て満月フォー――――ッッ!!」
まるで妖怪のような姿に成り果てた慧音さんが、両腕を高々と上げ、両足をクロスさせて、見事なXポーズをキメた。
「なっ!? な、何でこんな真っ昼間にその姿にっっ!!?」
姫様の驚愕の声に、慧音さんは不敵な笑みを浮かべる。
「よくぞ聞いた! 妹紅が私を求めて流した一粒の涙が、偶然にも満月光線と同じ光を放ったのだ!!」
「んなアホな……」
もうグダグダだった。
「お前に恨みは無いが、私の妹紅を救う為! そこを空けて貰うぞ白因幡!!」
「ひっっ!?」
――ぞぶっっ!!
神速のタックルにより、慧音さんの角がてゐの臀部を深々と貫き、その小さな体躯を高々と吊り上げた。
「ふ、ぐ、ぐぶぶ……」
見事に一本釣りにされたてゐが、白目を剥いてぶくぶくと口から泡を吹いている。
「う、うわ……えげつなぁ……」
「くっ、これは誤算だわ……ほら貴方っ、走りなさい!!」
「えっ? あ、ああ」
指示を受けた俺が外へ走り出したのを確認すると、姫様は妹紅を解放して飛び上がり、てゐを回収して脱兎の如く逃げ出した。
程無く俺に追い着いて襟首を掴むと、
「そぅれっっ、逃げるわよおおお~~~~!!」
ばびゅー―――んっっ。
そのまま高々と青空目掛けて飛び上がる。
「「に、二度と来るなああああ!!」」
下から大声で呪詛を上げる妹紅と慧音さんの姿が、みるみる小さく遠ざかっていく。
「…………ねえ姫様。俺を迎えに来てくれたのは分かるんですけど、もう少しこう、穏便には……」
「ふん、人が争うのに、大した理由なんて必要無いのよ」
「当人がそれを言うなよ……」
幻想郷で生きていくと言うのは、かくも厳しいものなのであった……
…………
――すぱー―――んっっ!!
「ただいま~。ちゃんと連れて帰って来たわよ」
「「ただいま~」」
元気良く襖を開いた姫様にてゐと二人で続くと、大広間の中からカカオとクリームの噎せ返るような甘い香りが漂ってきた。
「あら、お帰りなさい。どうしたの、てゐ。そんな変な歩き方して」
「いや、その、大丈夫だから、あはははは……」
「変な子ねぇ……」
俺達を迎えてくれた永琳は、いつもの服の上に薄ピンク色のエプロンという完璧な若奥様ルックをしていた。
「まあいいわ。ほら、準備はもう出来てますから、早く始めましょう」
「了解。ほら皆、今日の主役のお帰りよ~」
永琳と姫様の背中を押された先、広間の中央にホール型のケーキが五つ、どんと鎮座していた。
「……なあ、これって」
「ふふ、今日が何の日か、知らない訳じゃ無いでしょう?
永遠亭の一同から日頃の感謝をこめて、貴方にプレゼント」
「……そうだったのか…………ありがとう」
少し照れくさそうな永琳の言葉が、じわりと胸に沁みる。
俺は、除け者にされたなどと詰まらない事を考えた自分の心の貧しさを、猛烈に恥じた。
辺りを見回すと、イナバの子達が小皿とフォークを手に、ケーキの周りをそわそわと取り囲んでいる。
「お兄ちゃん遅~い!」
「何処行ってたのバカ! ノロマ!」
「もうこんな鈍亀放っておいて早く食べようよ~」
みんなありがとう! 俺嬉しいよ('A`)
今日って確か『ケーキ食べ放題の日』じゃ無くて、『女性が大切な男性にチョコを贈る日』だった筈だよね……
がっくりと肩を落としていると、永琳が苦笑いを浮かべながら手を叩いた。
「はいはい、皆待ち切れないみたいだから、始めましょう。
ウドンゲ、切り分けるから手伝って頂戴ね」
「はい。ほらみんな、並んで並んで。順番順番」
「「「は~~~い」」」
結局ホール五つ分のケーキはものの見事に分配され、みんなで仲良く分け合う事となった。
俺の知っているバレンタインとはこんなイベントでは無かった筈だが、
美味しそうにケーキを頬張るみんなの幸せそうな笑顔を見ていると、そんな些細な疑問はどうでも良くなる。
辺りいっぱいの笑顔を肴にケーキを頂いていると、ふと横合いから袖を軽く引っ張られた。
「ん?……何だ、どうしたチビ助」
俺の肘を摘んでいたのはイナバの最年少で、特に俺によく懐いてくれている子だった。
「ね、お兄ちゃん。美味しい?」
「ああ、美味しいよ。……ありがとう。みんなで頑張って作ってくれたんだろ?」
「うん……よかった」
頭をわしわしと撫でてやると、彼女は幸せそうに頬を緩ませた。
「えへへ……ね、お兄ちゃん」
「何だ?」
「ずっと……ずっと、ここにいてくれる?」
――ぴしっっっ。
場の空気が、一瞬にして凍りついた。
「「「……………………」」」
鈴仙や他のイナバの子達はフォークを咥えたままで瞬きさえ忘れて固まり、永琳は無表情でお茶を啜っている。
そもそもケーキに夢中で話を聞いていなかった姫様は、一人ご満悦な表情を浮かべていた。
自分の一言で周りの雰囲気が一変してしまったのを感じ取り、チビ助があたふた慌て出す。
「あ、あれれ? ねえ、私、何かおかしな事言ったかなあ?」
「…………いや、何もおかしな事は言ってないよ」
まったく、ありがたい話だ。
この程度の事で場がおかしくなる程度には、皆俺の事を気に掛けてくれているのだ。
「そうだな……ずっと居られたらいいな」
それこそ息を吐くような自然さで、そんな言葉が口を衝いて出てきていた。
「ホント? わぁ、嬉しい!」
無邪気に喜んで走り回るチビ助の姿に、ようやくみんなの口から安堵の息が漏れる。
……ずっと居られたら、か。
方便などではない、自分の胸底から自然に出た、偽りの無い言葉だった。
胸の内の天秤は、とうの昔にこの永遠亭の方に傾き切っている。
あとは、秤を今の位置で縛り付ける為の、俺と幻想郷を繋げる絆が欲しい。
「……色々な事を考える必要があるな」
「例えば、今日の永琳様のエプロン姿について、とか?」
俺の独り言に、てゐが横から茶々を入れてきた。
「ああ。エプロン一枚衣服が増えたのに、何でいつもよりエロく視えるんだろうな……」
「知ったこっちゃ無いわよ……」
思考の切り替えの圧倒的な速さが、俺の自慢の一つだった。
…………
~ March ~ ――だから、私が生きた世界のぬくもりを、思い出と言う慰めで良いから、私の胸に抱き留めていたい。
三月。
冬と呼べる程の寒気はとうに失せ、庭に聳える一本の桜の蕾も、随分と柔らかくなってきた。
――春が来た。
その日の晩ご飯も、いつもと同じように賑々しく進んでいた。
「ねえ居候、ちょっと醤油取ってくれない?」
「あーはいはいどうぞ。姫様、たまには自分で動いて下さいよ……」
「嫌よ。他に動いてくれる人が居る内は、私が動く必要なんて無いじゃない」
「もう、姫様。怠け癖がつくのは良くないですよ?」
甘ったれまくりの姫様に、永琳が思わず苦笑を漏らした瞬間、
――カラン、カラン。
永遠亭周囲に張り巡られた結界が反応し、来訪者を報せる柝の音が響いた。
「あら、お客様ね。イナバ、お願い」
「あ、はい。私が行きます」
率先して席を立った鈴仙に、イナバの子達が数名、ぱたぱたと後をついて行った。
…………
鈴仙達の姿が消えてから数分して、姫様がぽつりと呟いた。
「来ちゃった、か……」
「…………はい」
苦笑いを浮かべる姫様と、何故か重々しく視線を落とす永琳。
「?」
お茶を一口啜り、どうかしたのかと口を開きかけた瞬間、鈴仙が神妙な顔付きをして戻って来た。
「……あの、姫様、師匠。来ました……スキマ妖怪が」
「呼ばれてないけどジャジャジャジャー―――ンッッ!!!」
「うおおっっ!!?」
鈴仙の台詞が終わるか終わらないかというタイミングで、俺の湯呑みから突然人影が飛び出してきた。
「ほっ、と」
軽やかに畳に降り立ったその金髪の貴婦人風味な女性は、和洋折衷だか中華風だか、よく分からない服装をしていた。
「はいはい皆さんお久し振りね、藍から話は聞いたわよ。
……って、アレ? な、何でみんな私の事そんな白い目で見てるの?」
「普通に登場出来ないのかしら、貴方は……」
ええと、ひょっとして、この人が……
「あら、貴方が藍の言っていた外の方ね。初めまして、八雲紫と申します」
「ああ、初めまして。……なあ永琳、想像していたのより、全然熊っぽくないんだが……」
「油断したら駄目よ。こう見えても人は喰うし、長い冬眠で腹の肉も増えているに違いないんだから」
「そ、それは怖いな……」
まったく、妖怪と女は見た目で判断する事が出来ない。熊さえ可愛く見える恐ろしさだった。
「……初見で随分失礼な人ねぇ。お腹の肉なんて、肥満と細身の境界を弄ればどうって事無いわ」
「そっ、そんなのズルイわっ!!」
何故か、姫様が憤慨していた。
「……さて、本題に入りましょうか。貴方、心の準備は出来ていて?」
「……あー、その……」
「だめっ!!」
ちょっと待って、と言いかけたところで、突然イナバの子達が数人俺の前に割り込み、両手を広げて紫さんの前に立ち塞がった。
「……お兄ちゃんを、連れて行っちゃダメ」
「あらあら、可愛いらしい騎士様達だこと」
チビ助達に睨みつけられた紫さんが、淡い苦笑いを浮かべる。
「……しょうがないわね。おチビちゃん達と、そこで怖い顔をしている薬師さんに免じて、今日のところは退散するわ」
扇子が振るわれた軌道に沿って、一拍遅れて空間に裂け目が生まれた。
「明日また来るから、そこで答えを頂戴。その次はもう無いわよ」
ウィンクを一つ残して、紫さんの体が裂け目の中に消えていく。
「それでは皆さん、良き選択を」
彼女の姿を呑み込むと裂け目は閉じて、その跡形全てをそこから無くした。
「……………………」
神妙な沈黙が、背中に重く圧し掛かってきた。
…………
あの後、味がよく分からなくなった晩ご飯を片付け、一人自室に篭もって思案に耽っていた。
バレンタインの日からずっと考えてきて、自分がどうしたいのか、結論はとっくに出ている。
だけどそれを実行に移すには、やはりそれなりの覚悟が必要だった。
何処に、絆を求める?
決まってる。この永遠亭に。
誰に、絆を求める?
決まってる。一目視た時から恋焦がれてきた、大好きな人に。
「…………よしっ」
頬を張って気合を入れ、勢い良く腰を上げた。
…………そして次の日。
~ Last Note ~ ――誕まれて、生きて、死んでいく。
「…………」
「師匠」
「…………」
「師匠?」
「…………」
「……師匠!!」
「きゃあっ!? ちょ、ちょっと、驚かさないでよウドンゲ……」
「何言ってるんですか。私、ずっと呼んでたんですよ?」
昨日の晩から自室に篭もり、半日以上瞑目していたせいか、まるで気がつかなかった。
「そ、そう……」
「もう、一体どうしたんですか?
昨日からずっと引き篭もっていたかと思えば、朝食にも昼食にも出て来ないで」
「……何でもないわよ」
「嘘ばっかり。昨日あれから、彼と二人で話してましたよね。それ絡みじゃないんですか?」
「…………そうなのよねえ……」
もう取り繕っても仕方が無い。弟子の指摘を、己の未熟と併せて素直に認める事にした。
「……彼は、何て?」
ウドンゲの催促に、昨晩彼から受けた言葉を思い出す。
『君の事が好きだ。だから、俺がここに残るか外に帰るかを、君に決めて欲しい』
そう私に告げてきた彼の眼差しから感じたのは、
己の道さえ決められぬ弱さなどではなく、自分の未来を委ねても構わないと言う、私に向けられた強い愛情だった。
「まったく、女冥利に尽きるわ……」
「ふふ、いい話じゃないですか。で、師匠は何て返事したんですか?」
「……保留中」
「えっ? な、何でですか? あの、師匠も彼の事……」
「私は蓬莱人だからね」
「それはそうですけど……でも、彼はそんな事」
「そうね……きっとあの人はそういう事情まで考慮した上で、私を好いてくれているのでしょう」
間違い無く、彼は私や永遠亭の人達を幸せにしてくれるだろう。
……問題は、私の方にある。
彼と接するようになってから、何時の間にか私の中に一つの恐れが芽生えていた。
長い時間を経て身についた、生きる上で必要な知識や習性、そして姫との経緯は、
どれ程の時間をかけても決して失われる事の無い、私を形作る原型と呼べるものだろう。
だけど、かつての月での生活や、この永遠亭に来てからの出来事……所謂『思い出』というものに関しては、その限りではない。
ある記憶は時間と共に風化して朽ち落ち、ある記憶は新たな出来事によって塗り替え抹消されて……
ふと自分の足跡を顧みて、思い出と呼べるものの大半が最早輪郭さえ留めず、私の中から失われている事に気付いたのだ。
ならば果たして、現在私を取り巻く永遠亭の人々……このウドンゲやイナバの子達、それに、彼の事はどうだろうか。
今となっては月で共に過ごした同胞の顔をまるで思い出せないように、
やがて天寿を全うし消えていく彼等を、私は新たな思い出を塗り重ねる事で無くしてしまうのだろうか。
…………嫌だ。
亡くしても、無くしたくない。
この幸せさえ擦り減らしやがて無くして、なおのうのうと笑っているであろう未来の自分が、酷く醜い生き物に視えてしまう。
……改めて思い知らされる。
私は深い思慮も無く、こんな酷い生き方をあの二人に与えてしまったのか。
「ねぇウドンゲ……永く生きるっていうのは、こんなに悲しいものだったのね。
今こうして目の前に居る貴方の事も、私はやがて無くしてしまうのでしょう」
苦笑の表情を作ったつもりだが、実際にはどんな酷い顔をしているのか、自分でも分からない。
だと言うのに、目の前の不肖者の弟子は、
「何言ってるんですか師匠。私は、居なくなったりしませんよ」
そんな馬鹿な事を言いながら、私の鬱屈を笑い飛ばすかのような笑顔を視せた。
「……あのね。私の話、聞いてた?」
「はい、一語一句漏らさず。……私は確かにただの兎で、やがて師匠を置いて死んでしまうでしょう。
でも、子供が出来たら師匠に教えて頂いた事をその子に伝えます。
もし子供が出来なくても、私が残したものはイナバの子達が受け継ぎ、やがて子供達にも伝えてくれるでしょう」
そこまで一気に言って、彼女は一つ、大きく息を吸った。
「師匠が忘れてしまっても、気付かなくても、私はずっと……ずっと、師匠の傍に居ますから」
「…………」
――眼前の風景が、目映く歪む。
三千年に一度しか開花しないと言われる、金輪王と如来の花。
戯れで名付けた筈のその幻想の花が、私の眼前で白く眩しく咲いている。
「……ウドンゲ」
そっと手を伸ばし、彼女の頭を胸元に抱き抱えた。
「わぷっ。……し、師匠? 苦し……」
「ねぇウドンゲ。……一度しか言わないから、よく聞きなさい」
私の胸に埋もれた小さな頭を、柔らかく撫でる。
――今の私のこんな顔を、弟子になんて見せられるものか。
「…………はい」
「……ありがとう。貴方に逢えて、よかった」
――決めた。
昨日からずっと考え、一つ辿り着いた私の望むもの。
私は、今ここにある幸せを、もう薄れさせたくは無い。
……あの人が私に思いの丈を伝えてくれたように、私も全霊を以って伝えよう。
彼の真っ直ぐな情念とは比べるべくも無い、醜くおぞましい欲望ではあるが。
…………
ウドンゲと別れ、眦を決して彼の部屋へと向かう途中、縁側に姫の姿を視止めた。
姫は一人で縁側に腰掛け、齷齪と庭の手入れに勤しむイナバの子達を眺めていた。
視線を庭の方に向けたまま、鈴を鳴らすような声が静かに響く。
「…………腹は決まったかしら?」
「はい」
「そう。……それじゃ、私から言う事はあまり無いわね」
詠うように気負いの無い、だけど力ある荘厳な声で、姫は続けた。
「今までありがとう、永琳。
私は、貴方のどのような決断も受け入れる。
言いたい事は、ただ一つだけ…………」
「はい」
「……幸せになりなさい、八意永琳。
臣の幸せは、私の幸せでもあるのだから」
「…………はい」
…………
「……入るわよ」
「ああ」
断りを入れて、襖を開く。
何も様子の変わらない部屋の真ん中で、彼はただ寝転がって天井を眺めていた。
何一つ部屋の片付けが行われていない事に小さな安堵を覚え、改めて彼からの信頼の深さを感じた。
「話があるの。少し表に出ましょう」
…………
――ざっぱああああんっっ!!
「こんにちはお姫様~~。たまにはお昼に顔を出してみたのだけど、いかがお過ごしかしら? ……クシュン!」
「昨日は湯呑みからで、今日は池から、か。まったく、普通に玄関から来なさい、玄関から」
「う~~冷たい、今後考慮するわ。それよりも……あの人間は?」
「いないわ、お出掛け中」
「あらあら、逃げられちゃったか。
残念ねえ……外に帰るとか言うのなら、こっそり頂いちゃおうかと思ってたのに」
「やっぱりそんな所だったか。彼はもう此処の住人だから、これから手を出すのなら容赦はしないわよ」
「流石にそんな野暮はしないわよ。そう言えば、薬師も居ないみたいだけど……やっぱりそういう事?」
そう言っていやらしい笑みを浮かべると、紫は親指と人差し指で輪っかを作った。
「むっふっふ。そういう事、そういう事」
その輪っかに、人差し指をズボズボと突き入れてやった。
「「むふ、むふ、むふふふふ…………」」
「「「……………………」」」
周りのイナバの子達の視線が、とても痛かった。
…………
「いい天気ねぇ」
そろそろ夕刻に差し掛かろうという頃合、僅かに茜の差した空を、
彼を初めて拾ったあの日のように、背中に負いながらゆるりと飛んでいる。
「痛いよ~~、痛いよ~~」
道中、体勢を直す振りをして私の胸を触ろうとした不届き者を、両肩の関節を外す事で制裁した。
竹林をとうに過ぎ、初夏から何度か行き来している鈴蘭畑を通り過ぎて、
やがて私達は、かつて彼岸の花に溢れていた、無縁の塚に降り立った。
…………
『……ありゃ。これはまた珍しいお客さんだこと』
『ちょっと小町! またサボってる!』
『きゃんっ!? ちょ、ちょっと映姫様、いきなり後ろに立たないで下さいよ』
『何言ってるの。こんな所で一体、何をコソコソ……ゲエェー―ッ!!
あ、あれは蓬莱人! こここ小町!! 塩っ、塩撒いて追っ払って来なさい!』
『まあまあ映姫様。……それよりも、一杯どうです?
あの二人、いい肴になりそうですよ?』
…………
「何とも辛気臭い場所だな。立ってるだけで気が鬱ぎそうだ」
入れ直した肩をぐるぐる慣らしながら、彼は呟いた。
「そうね……でも、ここじゃないと駄目なの」
天命を終えた人の魂、想いの逝きつく孤高の丘。
今の私には縁の無いこの塚こそ、始まりのテープを切るに相応しい場だと思ったのだ。
「……それじゃあ、聞かせてくれる? 永琳の話」
「……ええ」
もはや取り繕う必要も、余分な言葉で意味をぼかす必要も無い。
私の出した答えを、簡潔に彼に伝えよう。
――私が彼に与える、一つの難題。
「実は……ね」
「うん」
「蓬莱を殺す薬を、作ろうと思うの」
「……………………そうか」
「ええ。だから……ね」
怖い。
怖い。
私の次の言の葉を受けた後、彼は一体どのような顔をするだろうか……
「だから?」
「だから…………貴方に、蓬莱の薬を、飲んで欲しいの」
「…………」
「…………」
言葉として形にする事で、自分の出した答えのおぞましさ、浅ましさに、改めて痛烈な嫌気を覚えた。
私は、彼にこう言っているのだ。
……一緒に地獄に堕ちてくれ、と。
禁忌である蓬莱の薬を殺すという事は、更にもう一つ先の禁忌を犯すという事だ。
これから着手するとして、どれ程の時間や犠牲を払う事になるのか、見当もつかない。
果たして薬を完成させ、再び時間の歯車を軋ませるその瞬間に、この人が隣に居ないのでは、まるで意味が無いのだ。
「…………」
「…………」
一瞬とも万年とも思える、凍ったような沈黙。
彼は私の言葉の裏、私の胸の内までを咀嚼するように暫し瞑目し、そして……
「うん、分かった」
……先刻のウドンゲを彷彿とさせるような、眩しい笑顔を視せてきた。
「……………………いいの?」
「ああ。日本男児に、二言は無い」
いつもの爛漫な笑顔そのままに、彼の手が私の方にそっと伸びて……
「あっ」
……引き寄せられるままに、私の身体が彼の腕の中に収まる。
「……いいの? 私、貴方が思っているより、ずっと怖い女よ?」
「怖くなんてあるもんか。俺を選んでくれた、誰より大切な人だ」
「…………きっと、永く辛い道になるわよ?」
「大丈夫だよ。姫様も居るし、妹紅も居る。鈴仙やイナバの子達も居るし……俺だって、ずっとついてる。
きっと、地獄だって楽しめるさ」
かつての私は、知っていたのだろうか。
――人の腕の中が、こんなにあたたかいものだという事を。
「永琳」
彼の指が、私の顎をそっと上を向かせる。
「あ……」
少なくとも幻想郷に来てからは覚えの無かった潤みを目元に感じながら、私はそっと瞳を閉じた。
…………
――矢を、放とう。
永い射線に迷い、切り裂く風の冷たさに凍て付き、林檎に刺さる頃には、朽ちてぼろぼろになってしまうかも知れないけど。
偕老同穴の誓いを乗せて、再び歯車を動かす為の、決して折れる事の無い命の矢を、二人で放とう。
・
・
・
・
・
・
・
「ウィ~ッ、こここ小町のヴワッキャロォォオオオオイっ。
クソッタレ蓬莱人でさえあんにゃに幸せそうにイチャイチャしてんのに、
ぬわぁぁんで私はお前みたいな阿婆擦れと酒なんて飲んでんだああああああっっ!!?」
「あ、あの、映姫様? 落ち着いて……」
「ああああたしゃ落ち着いてるってんだよこのパープリンがああああああ!!
いいからとっとと酒追加しろってんだよおおおおぉぉぉ!!」
「ひいいぃぃっっ、しまったあぁ、あたいとした事がああああぁぁ~~~~……」
>>454