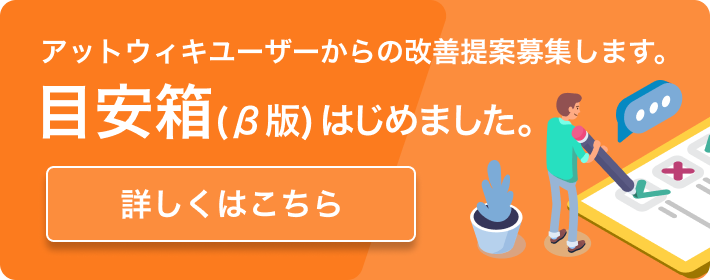プロポスレ@Wiki
パチュリー3
最終更新:
orz1414
-
view
■パチュリー3
紅魔館地下に設けられた書斎は、大量に収められた本の匂いで満たされている。
その中にたまに紛れ込むのは、紅茶の香りであったり、コーヒーの香りであったり、弾幕の衝撃であったり。
「うーん…………」
ぺらり、と音を立てて、新たなページが知識を運んでいく。
今日も今日とて、その書斎の主、パチュリーは調べ物に余念がない。
彼女が読む本に、ジャンルの壁などは存在しない。
魔女らしく魔術書を読むこともあれば、外界の歴史書や雑誌を読むことだってある。
だが、幻想郷に外界の本が来ることはごく稀で、当然ながら外界の知識は限られたものになってしまう。
最近彼女が求めているのは、とある外界の知識である。
「ねえ小悪魔。そっちは?」
「あまり、芳しくありません……」
普段は自分だけで読んでいる彼女だが、今日は小悪魔も動員しているようだ。
広い机の上には十数冊もの本が散らばり、後でこれを片付けることになるであろう小悪魔は、既にげんなりしていた。
「やっぱり向こう側の常識は、本に記されることが少ないのかしら?」
「パチュリー様。やっぱり○○さんに聞いてみれば……」
「何度も言っているでしょ。今回ばかりは、それじゃ駄目なのよ」
小悪魔の提案は、即座に却下された。
パチュリーの恋人である○○は、元は外界から来た人間である。
本ではどうしても調べられない知識は、彼に聞いて得ることが出来たのだ。
もちろん、彼が知っている範囲の知識に限られるのだが、外界の常識として浸透しているはずの知識なら、彼が知らないはずがない。
それでもパチュリーは、その方法を選ばなかった。
「内緒にしなきゃ……駄目なのよ」
夜の霧雨亭。
魔法の森の奥に建っているその家は、静かではあるのだが、その主に至ってはその限りではない。
それでも弟子を迎えてからは、以前に比べれば大人しくなった方である。
「そうだ、○○。ちょっと思い出したんだが」
「……師匠が言うと、とんでもなく不穏当に聞こえるんですけど」
そんな霧雨亭での夕食の席。
彼は魔理沙の茶碗にご飯をよそいながら、眉を寄せた。
魔法の稽古はつけてもらっているが、今の彼を見る限り、とても弟子には見えない。
エプロンと言う名の、薄いブルーの戦闘服に身を包み、頭には純白の三角巾。
それはまさに、家庭を預かる戦士の姿だった。
「おいおい、恐い顔するなって。
そんな顔してると、パチュリーに嫌われるぞ」
「……師匠。自分の胸に手を当てて、心辺りがないか思い返してみません?」
彼とて、伊達に長らく魔理沙の弟子をやっているわけではない。
彼女が切り出す話は、彼にとって危ない橋を渡らせる類のものであることが多かった。
もちろん、それは悪意あってのものではなく、結果が吉と出ることもあるのだ。
例えば、以前彼がパチュリーを紅魔館まで送って行った時のように……。
「もちろんないぜ。なんにもないからな。
大したことじゃないから、そんな顔しないでまず聞け」
「……それならいいんですけど。
なんにもないなら、話自体なかったことになりません?」
「師匠の教えは聞くもんだぜ」
一抹の不安を抱えながら、彼は魔理沙に茶碗を手渡し、向かいの席につく。
「お、ありがとな。んじゃ早速頂きます」
「師匠……話があるんじゃないんですか?
あるなら、食べるか話すかどっちがでお願いします」
「面倒だから食べながら話すぜ。人の一生は短いんだ」
魔理沙の話を簡単に要約すると、休日をやると言うことだった。
魔理沙は久し振りに魔法薬の実験をやりたいのだが、危険性が高く、相当集中しなければならない。
そのため、家はなるべく静かな方が好ましく……。
「……つまり、ここ以外で時間を潰してろ、ってことですか」
「そんなところだぜ。
お前なら、迷わずパチュリーの所に行くんだろうけどな」
的を射た彼女の言葉に、彼はやっとのことで、
「べ、別に……いいじゃないですか」
とだけ返した。
「ああ、別にいいぜ。パチュリーもああ見えて、意外と寂しがりやだからな」
「そうねぇ。あの娘も最初は、対応こそツンツンしてたのに、今はもうすっかりあんな調子だしね」
そっぽを向く彼に、前と下から連携した冷やかしが飛ぶ。
視線を落とせば、彼の空っぽの茶碗から、顔だけにょきっと生えたスキマ妖怪が。
「○○。寂しがらせたなら、ちゃんと慰めてあげなさいな。
ああいった内気な娘は、少し強引に押し倒して……」
ぐわしっ!!
「まあ、師匠が昼夜抜く覚悟なら、俺は別に構いませんが」
「うわ、紫を手掴みか。やるようになったな、お前も」
茶碗から湧いて出た紫を、○○はアイアンクローで迎え撃つ。
「あらあら、あの娘に続いて私かしら?こういうのも『手が早い』って……」
ぎりぎりぎり……。
「お、おい。何か頭の形が変形してないか?」
「気のせいです」(キッパリ)
少し慌てた様子の魔理沙に、彼は動じる事なく断言する。
加えて、紫のことは完全に無視である。
以前なら律義に『口より先に手が出る、の間違いです』とでも返したものだが。
彼も慣れたということだろうか。
「ふふっ。その程度じゃ、まだまだ私は倒せないわよー♪」
「……藍の奴も、苦労してるんだろうな」
「そうですね。師匠に拾われて、本当に助かりました」
「あらあら。今度は魔理沙かしら? 全く、呆れるくらいのプレイボーイなんだから……」
ガタンっ!!
倒れる椅子には目もくれず、彼は立ち上がると近くの窓を開け放つ。
「あ、あら?」
「とりあえず……紫さん」
「私の魔砲で、白玉楼まで送ってやるぜっ!」
茶碗ごと、彼は全力投球で紫を夜空へ放り投げる。
そして――
魔砲『ファイナルスパーク』
――夜空を切り裂く光芒が、魔法の森の上空に弾けた。
恐れるべきは魔理沙の狙撃力か破壊力か、師弟のコンビネーションか。
夜空に向けられたはずの魔砲は、あまりの威力に森の一部も巻き込んで……。
「あれ、師匠。あっちって、アリスさんの工房じゃ……?」
「知らないぜ」
「……まあ、明日は俺もいませんし、何かあっても師匠の仕業ですから、いいんですけどね」
「ああ、飯の作り置きだけは頼むぜ」
「はいはい、了解了解」
ぺらりぺらりと、ページがめくられていく。
探しても探しても、目当ての知識は見つからない。
あるのは、断片的な情報ばかり。
それでも、その僅かな情報を手掛かりに、パチュリーは探し続けていた。
それは、甘い物だということ。
それは、黒い色をしていること。
それは、主に四角い形をしていること。
それは、砂糖や豆を材料にして作ること。
「……なるほど、ね」
パタン、と彼女は本を閉じる。
「見つかったんですか?」
「いいえ。でも、それが何を指しているのかは、やっと解ったわ。
これは多分、呼び方が変わっているだけで、私達がよく知っている物だったのよ」
小悪魔の問いに、自信を持って断言するパチュリー。
それなら後は片付けて、ゆっくり休もう……そう思っていた小悪魔に、パチュリーからメモが渡される。
「はい、これが材料よ。支度して厨房に行くから、先に集めておいてね」
「は、はいぃ……」
紅魔館の夜は長い。
未だ寒さの残る幻想郷の空には、煌々と輝く紅い月。
「月もこんなに紅いしね。今夜は、作るわよ……!」
(パチュリー様……そんなだから、お身体もよくならないんじゃ……?)
紅魔館は吸血鬼の治める館。
夜こそが、活動時間なのだ。
小悪魔が眠れるのは、まだ当分先の事になりそうである。
翌日、昼前の紅魔館――
「…………」
彼は、言葉を失って立ち尽くしていた。
いつも見慣れた彼女の書斎が、今日ばかりは異空間に見えていたのだ。
小悪魔が頑張って整理し、魔理沙が荒らした後以外は、常に整然としている本棚が、所々乱雑になっていた。
それだけではない。
机には、栞がはさまったままの本が数冊、開きっぱなしの本が十数冊散らばっていた。
後者に関しては、パチュリーの性格からして、有り得ない状態である。
「参ったな……」
広い紅魔館内でも、ようやく迷わずに移動出来るようになり、先日から案内を断った矢先の出来事なのだ。
彼以外には誰もいない。
少なくとも、見える範囲にはであるが。
「あ、れ――?」
不意に訪れた既知感。
見慣れないはずの、この状況を知っているという、矛盾。
目を凝らしても、見えるものは変わらない。目を向けるべきは、彼が何故そう感じたか――。
(ああ――そうか)
彼は気付いた。
程度の差こそあれ、散らかった部屋なら、見慣れている。
魔理沙の蒐集物で圧迫された部屋も、またしかりである。
そして、そんな部屋に対して、彼がやるべきことと言えば、もはや1つしかない。
「……片付けよう」
原因が解った所で、現状が改善される訳ではない。
そんな理屈を抜きにして、まずは目の前の惨状をどうにかするべく、彼は手近な本を手に取る。
(これは……料理の本?それに、あっち側の……?)
幻想郷にある本と外界の本は、様々な違いがある。
紙質もその1つではあるが、外界の本は比較的カラフルである。
彼が手にした本も、そうだった。
机に散らばっている本も、見た感じでは、大低が外界の本らしい。
幸いにも、外界の本が纏められている本棚は、彼も知っていた。
小悪魔ほどの効率ではないにせよ、丁寧に確実に、あるべき場所へ納めていく。
そして彼は、いつもと違うもう一つの点に気付いた。
微かに感じる、甘い香り。
僅かではあるものの、紅茶やコーヒーなどとは違う風味。
「お菓子……かな」
何となくではあるが、彼はそう感じていた。
他ならともかく、紅魔館なら十分な材料があってもおかしくない。
だが、仮に今誰かが作っていたとしても、この場所までその香りが漂うとは考えにくい。
カチャリ。
彼が首を傾げると、答えはドアを開けて、自らやって来た。
「あ、○○……来てたのね」
「おはよう、パチェ。
勝手に片付けさせてもらってるよ」
近くのドアが開き、現れたパチュリーの手には、あまり見映えはよくないものの、一生懸命にラッピングされた箱が握られていた。
「で、この大きな箱は何なのよ?」
「あいつの作り置きだぜ。一人じゃこんなに食べ切れないからな」
正午過ぎの博霊神社。
珍しく手土産を持参した魔理沙は、縁側でそれを開ける。
中には、クッキーやら大福餅やら、茶菓子の類が所狭しと詰まっていた。
「彼の作り置き……ねぇ」
「以心伝心ってやつだろ。私の弟子なんだからな」
彼が作り過ぎたという可能性は、既に魔理沙の頭にはない。
師の気遣いは、しっかり弟子に気付かれていたのである。
霊夢は、箱の中に無造作に手を突っ込むと、苺大福を取り出した。
「パチュリーじゃなくて、魔理沙が相手だったら面倒がなくて済みそうよね。
……あ、美味しい」
「よせやい。私はそんな目的で、あいつを拾った訳じゃないぜ。それに……」
大福を頬張る霊夢の横で、魔理沙は煎餅をかじり、空を見上げる。
珍しく晴れた、冬の幻想郷の青空は、彼女には少し眩しく映った。
「……端から見てて、やきもきすることもあるけどな。
あいつらが幸せそうに笑ってるの見ちまうと、割って入る気もなくなっちまうぜ」
帽子のつばを下げ、彼女はぐいと茶を煽る。燻した香りが目に染みた。
「まあ、魔理沙だしね。あんなに集めてるんだし、いずれ人まで拾うとは思ってたけど。
牡丹餅も美味しいわよ。食べる?」
「ああ、頂くぜ。残さず頂いてやるぜ」
「それじゃあ幽々子みたいじゃないの……って、言ってるそばから来そうよね」
茶菓子に限った話ではないが、食べ物が大量にある所に、冥界のフードファイターは現れる。
茶菓子は2人でも十分な量なのだが、幽々子の食欲の前には風前の灯だろう。
加えて、紫と組んでスキマを抜け、至る所に現れることまであるので、余計にタチが悪い。
「あいつが死んだら、幽々子の所で菓子職人になりそうだな」
「作るのは……桜餅かしらね」
「そうだな、私に似て和食派だし」
幻想郷の青空に1つ、星が流れる。
それを目にしたのは、霊夢だけだった。
「チョコレート、作ってみたんだけど……」
あらかた片付け終わり、一息ついた所でパチュリーは切り出した。
料理書を片手に、一晩中かかって作り上げたのだ。
もちろん一人で出来ない作業は、小悪魔にも若干手伝わせたものの、彼女自身に料理の心得はあまりない。
場慣れしていないせいもあるのだろう。差し出す彼女の白い手は、所々赤くなっている部分があった。
「確か、バレンタイン……って言うのよね」
「そうなんだけど……何だか、食べるのが勿体ない気がするよ」
世界的には、男性から女性へあげるケースが大半で、逆なのは日本くらい----。
思わずツッコミそうになるのを押さえ、彼は差し出された箱を見つめる。
向こうでも、ラッピングは人の手で行われているが、どれも見栄えよく画一的なものだ。
それに比べると、見劣りこそするものの、適度に崩れた部分が手作りであることを強く思わせる。
手の赤みもだが、書斎がこんなになるまで調べ、作ったことを考えれば、確かに食べてしまうことも躊躇われる。
「あまり、日保ちしないと思うわよ?
その……出来れば、美味しいうちに食べて欲しいし、感想とかも……」
「そっか……それもそうだね」
食べて欲しいから作る。
これは、料理をする彼にも解る気持ちだ。
勿体ないからといって、駄目にしてしまっては、それこそ本末転倒だろう。
彼はパチュリーから箱を受け取り、もう一度しっかり見詰める。記憶に刻み込むように。
「術式展開スペルセット・対象解析アナライズ・接合解除リンクカット……」
テープの代わりに、魔力で接着されたラッピングを、一箇所ずつ丁寧に切り離していく。
全ての接着箇所を切り離すと、花が開くように、ふわりとラッピングがほどけた。
「綺麗だな……」
後に残るのは、シンプルな白い箱。
彼の隣で、パチュリーは固唾を飲んで見詰めている。
蓋を開ければ、甘い香りが周囲に溢れ出す。
(これは……)
それは、彼がずっと感じていた香りである。その源が、パチュリーの渾身の一作なのだ。
「どう……?」
「よく出来てると思うよ。まあ、見た目はだけど……」
「……意地悪」
食べずに彼が言えるのはそれくらいなのだが、やはり彼の一言は余計だろう。
「味見はしたから、失敗じゃないとは思うわよ?」
「ごめんごめん。それじゃ頂きます」
怒ったようなパチュリーをかわして、彼は一切れ口に運んだ。
角を引っ込めたパチュリーは、黙って彼の反応を伺っている。
料理書を何度も確認しながら作り、何度も味見しているとはいえ、不安は拭えない。
念には念をということで、小悪魔やレミリアにも味見してもらったのだが、味覚というのは十人十色である。
それは、人も魔女も妖怪も悪魔も、変わりはない。
「……パチェ、そんな顔しなくていいよ。普通に美味しいから」
「ほ、本当?」
彼の言葉に、パチュリーは――珍しいことに――驚きの表情も隠すことなく、身を乗り出して尋ねた。
「自信持って。何なら、パチェも食べる?」
「う、ううん……貴方に食べて欲しくて作ったから、私はいいわ」
「でも、独り占めするのもちょっと……」
そう言って彼は、箱に視線を落とす。
次に彼が聞いた囁くような声は、とても近くから聞こえた。
「じゃあ……一口だけ、ね」
「え……?」
普段の彼ならば、咄嗟に反応することも出来ただろう。
だが、油断していたためか、安心しきっていたためか、彼は動くことさえも出来なかった。
それは、完全な不意打ちで、直撃だった。
零距離からの、恋の魔法――
「ご……ごちそうさま」
どちらともなく身体を離した時、仕掛けた側も直撃した側も、顔を赤く染めていた。
結果を見れば、相打ちだろうか。
「……パチェの方が、美味しいな」
「馬鹿……チョコも、ちゃんと食べてよね」
「そりゃ食べるけどさ……」
彼が返す言葉は、少し歯切れが悪い。
言うべきか、言わざるべきか迷っていたのだ。
だが、根本的な間違いなら、やはり指摘するのは早い方がいい。
まだ顔は赤かったが、彼は意を決して、口を開いた。
「パチェ、チョコレートと羊羹は別な物だからね」
「え……チョコレートって、羊羹の別名じゃなかったの!?」
―――後書きの原材料は、小豆と砂糖と、ほんの少しの糸寒天―――
性格も積極的な方ではなく、常に我が道を行く。ただ、好奇心は高く
知識に関しては積極的に取り入れる。全て本に依る物だが間違いも多い。
東方萃夢想の上海アリス通信、パチュリーの項目より抜粋。
つまり、知識に関してはパーフェクトだと思われがちなパチュリーも、実は間違った知識を?
それがオチでもあり、今回の動機です。前の続きというか、補完も兼ねてますが。
バレンタインとチョコレートが、幻想郷行きになる日はいつになるんでしょうね。
>>530
───────────────────────────────────────────────────────────
今日も俺は図書館にやってきた。
外は雪がちらつく空模様。図書館の中もすこし肌寒い。
暖炉の近くの安楽椅子に深く腰掛け、読みかけの本を手に取る。
「今日も来たのね」
――うん、いろいろと読んでみたい本が多いしね。
「好きにしていいとは言ったけど、来たなら一言あってもいいんじゃない?」
――邪魔しちゃ悪いと思ってさ。
「気遣いするような性格じゃないでしょ」
――確かにね。
パチェの手を引いて膝の上に座らせ、そのまま抱えるように抱き寄せる。
「ちょ、ちょっと!」
――本の解説してほしいんだけど、寒いから風邪ひかせたくないし。
「こんな体勢じゃなくても解説するわよ。それに暖炉があるから大丈夫っ…」
――パチェは温かいな。
「な、何を言って…」
――この温かみを感じられる奴は幸せだな」
「………………ッ、(………貴方だけよ)」
パチンッ!
パチェの呟きに暖炉の薪の爆ぜる音が被った。
――もう一回。
「……聞こえてたくせに…」
うらめしそうな顔で睨んでくるパチェ。
今夜はまだまだ冷え込みそうだ。
3スレ目 >>383
───────────────────────────────────────────────────────────
パチュリーの隣で、図書館の奥魔法の本を読んでいる。
借りていこうとして席を立つと、そっと袖を掴まれた。
「たまには……ここで読んでいかない?忙しいなら、無理にとは言わないけど………」
袖を引っ張っりつつ、向こうを向きながらもじもじしているパチェ。
3スレ目 >>461
───────────────────────────────────────────────────────────
読書中
「なあ」
「・・・・・・・・」(読書中)
「なあって」
「・・・・・・・・」(読書中)
「もしもーし」
「・・・・・・・何か用?」(顔を上げる)
「いや・・別に用事は無いけど」
「用が無いなら話しかけないで・・・・・」(読書に戻る)
一転してデレ状態
「なあ」
「・・・・・・・・」(読書中)
「なあって」
「・・・・・・・・」(読書中)
「もしもーし」
「・・・・・・・何か用?」(顔を上げる)
「いや・・別に用事は無いけど」
「・・・・・・・・・・・・そう」(読書に戻る)
ああパチュリーに後ろ向いてから振り返りながら「大好き」って言わせてEEEE!!
3スレ目 >>844
───────────────────────────────────────────────────────────
時々騒がしくなるが、普段は薄暗く静かな図書館
俺がここに来てからかなりの月日が立っていた。
「なあ」
「なに?」
「俺がここに来てから結構立つよな」
「そうね」
「なんかお祝いみたいのってないのか?」
「ないわ」
「即答かよ・・・」
「必要ないもの。費用もかかるし、大体何に対して祝うのよ」
「俺が今まで幻想郷で生きてこれたことに対して」
「・・・まあ、確かに稀ではあるわね」
「じゃあさ、二人で祝わないか」
「・・・何で私なの」
「他に祝ってくれるような人がいるか?」
「その祝う人の中に私が入っているのが疑問なんだけど」
「まあ、それは捨て犬のような俺を拾ってくれたご主人様なわけだし」
「人間の使い魔を持った覚えはないわ。それに、あれは捨て犬じゃなくて半死体よ」
「・・・ところで、喋っている時ぐらい本から顔を上げないか?」
「必要ないわ」
「・・・外でピクニックなんかいいな」
「まだやるなんて言っていないわよ。それに如何してわざわざ外なんかに」
「普段、日陰にいるんだからたまにはいいだろ?それに日向に出ないと健康に悪いぞ」
「いいのよ、知識と日陰の少女だから。健康に関しては否定できないけど・・・」
「それなら丁度いいだろ。今やっている研究もないみたいだし」
「それはそうだけど・・・ 何で研究がないことを知っているの」
「いつも見ているからな。それに、ほとんど実験体のようなものだろ?俺」
「そう、そうね。 まあ、いいわ祝ってあげましょう。」
「おっし。じゃあ明日は・・・多分、というか絶対黒白が来るだろうから明後日だな。」
「そうね」
「弁当は任せておけ!今までで最高な物を作って見せる」
「それは楽しみね。あなたの料理美味しくて食べやすいから、でも普通私が祝うんじゃないの?」
「細かいことは気にしない!それと、あ~なんだ、その・・・ ピクニックのときに大事な話がある」
「大事な話?」
「ああ」
「そう・・・」
「・・・気に成らないのか」
「明後日になったら聞けるのでしょう?」
「そりゃ、まあ」
「だったら待っているわ。楽しみにしてね」
「そう、待っているわ。」
「貴方が言ってくれるまで、いつまでも いつまでも・・・ね」
薄暗く静かな図書館
されど少女の声は誰にも聞こえず、届かず・・・
ただ、少女の読んでいる本だけがそれを見ていた。
顔を朱に染めとても幸せそうに微笑んでいるその顔を・・・
執筆、投稿ともに二回目!初執筆の物と似ているところが多いな~と自分で思うが
直せる腕がない罠!ただ、言えることは私の中のパチュはこんな子です。ということだけです。
ちなみに、料理の感想は実際の言われたことのある言葉です。作った相手は男だったけどね!
避難所 >>9
───────────────────────────────────────────────────────────
ええと、効率よく仮眠をとる方法は……。
――○○、ちょうどいい所に、ちょっとここに座って頂戴。
……何で警戒してるのよ。失礼ね、実験なんかじゃないわ。
普通に座ってていいのよ。私の方じゃなくて、テーブルの方向いてて。
……別に失礼でも何でもないから、気にしなくていいのよ。変な所で律義なんだから。
そうそう、そんな感じよ。後は動かないで、目を閉じて楽にしてなさい。
よい……しょっと。
……緊張することないじゃない。心地いいんだから、誇ってもいいくらいよ。
そうね、レミィが起きる辺りに起こしてくれるかしら。
――変な事、しないでよね。
…………。
………。
○○さん、何をなさってるんですか?
枕……ですか。
ふふ、やっぱり恥ずかしいですよね。
でも、パチュリー様がそんな風に甘えられるのって、○○さんくらいなんですよ?
まぁ、甘えてるようには見えませんけど……素直じゃないんですよ。
……ええ、それを聞いて安心しました。私は仕事が残ってますから、向こうにいますので。
――あ、はい。そうですよね、毛布でしたらすぐお持ちします。
ない物はセルフで補給すればいいってことでパチェ分補給。
4スレ目 >>420
───────────────────────────────────────────────────────────
……そう言えば貴方、毎回どうやって入ってくるのよ。
逆立ちしたって、貴方じゃ小悪魔にも敵わないでしょう?
はぁ……呆れたわね。そんな方法があったなんて。
ええと、それって何て言ったかしら……食糧責め?
……買収って、流石に言い方が悪くないかしら。
まあ、別に邪魔じゃないからいいけど。
でも、貴方も変わり者ね。わざわざこんな所まで来るなんて。
……確かに本は沢山あるけど、それだけで来るような場所でもないでしょ。
――本当に、それだけ?
…………。
………。
――な、何?借りていくの?
……本の管理は小悪魔の仕事だから、一声掛ければ大丈夫よ。
貸出期限?……別に、ちゃんと返しに来るならせっかちなことは言わないわ。
ええ、それじゃ、またね。
…………はぁ。
最後のパチュリーのため息が誰に向けられたかで、脳内補完の方向が変わりそうですが。
4スレ目 >>616
───────────────────────────────────────────────────────────
怒ると危ないお嬢様とメイド長の人にやっと放してもらえた僕は、美鈴さんに会いたくて門に向かう
元の服に着替えたけど、メイド長の人に渡された鞄の中に巫女服とメイドさん達が着る服が入ってる
メイドさん達が着ている服は返そうとしたら、メイド長の人がまた着させようとしたので受け取った
着ないのに、洗って美鈴さんから返してもらおう
「美鈴さん! 」
「あれ? 遅かったわね」
「あ、ごめんなさい」
「別に怒ってるわけじゃないんだけど、どうしたの? 」
僕は、何故か美鈴さんに聞いて欲しくてさっきまでの事を話した
美鈴さんは驚いたような顔をした後、苦笑しながら僕の頭をなでてくれた
「あちゃー、私の部屋に置いて行ったのは不味かったわね」
「えっと、その」
「それより、どうだった? 」
「え? 」
美鈴さんが、突然ニマニマと変な顔をして僕に聞く
僕の胸を軽く指で突付きながら、美鈴さんはムフフーと言う
「お嬢様と咲夜さん、あのお二人の事だから相当凄かったでしょう? 」
「あ、う」
「照れない照れない、それよりどんな風にしたの? やっぱり巫女服で? 」
美鈴さんの言葉に、僕は怒りを覚えた
何で?
理由は分からないけど、それしか思いつかないぐらい怒っていた
「美鈴さんの馬鹿ー! 」
「ほへ? 」
これ以上美鈴さんと話ていたくない
僕は美鈴さんから逃げる為に、出てきた館に逃げ込んだ
「はぁ」
僕は溜息を止めないで館の中を歩いている
美鈴さんに、馬鹿なんて言っちゃった
それに時々立ち止まって後ろを振り返っても、美鈴さんは居ない
やっぱり馬鹿なんて言ったから追いかけてくれなかったんだ
「うぅ」
何でだろう、涙が出てきた
涙が眼から零れ落ちようとしたとき、僕の視界に長くて紅い髪が眼に入る
「美鈴さん? 」
紅い髪が、一つの扉に吸い込まれるように消えるのを僕は呆然と見ていた
慌てて追いかける
その扉に急いで僕も入ろうとしたら、扉を開けた途端に僕は暗い場所に吸い込まれた
吸い込まれる前に紅い髪の人が見えたけど、美鈴さんじゃなかった
あぁ、僕は美鈴さんに謝らなきゃいけない
何も見えない暗い中、僕は柔らかい何かの上に落ちた
驚いて立ち上がっても、暗くてなにも見えない
だけど本当に暗いわけでもなかった見たいで、眼が慣れてくると普通に見えるようになった
「むきゅー」
「うわ! 大丈夫ですか!? 」
多分、僕が落ちたときに下敷きにしてしまった人が倒れていた
倒れたままなのが心配になって上半身を起こしてみたけど、特に怪我は見当たらない事に安心する
少し顔色が悪いのは暗いからじゃないと思って、なんとか引き摺らないよう近くにあった椅子に座らせた
でも、どうしよう?
あたりを見渡しても誰もいないみたいで、本が一杯あることに僕は気づいた
「図書館、かな? 」
「う、うぅ」
気絶した人をどうすれば良いのか書いてある本を探しに行こうとしたら、下敷きにしてしまった人の眼が醒めたみたいだ
「痛い、ゴホッ」
「大丈夫ですか? 」
僕が話しかけると、その人が僕を見て急に苦しみ始めた
「うぅ、苦しい! 死んでしまう! 」
「えぇ!? ど、どうすれば!? 」
慌てる僕が誰か呼びに行こうとしたら、その人に腕を凄い力で掴まれた
「私を助けなさい! 」
「ど、どうすれば良いんですか!? 」
「これ、これをつけて! むしろ私がつける! 」
掴まれた腕を引っ張られて、その人に抱きかかえられた
それで頭に変なのが乗せられた気がする
「えっと? 」
「後はコレとコレとコレ! 」
「うわぁ!? 」
その人は僕を凄い勢いで動かして、僕はそれに眼を回した
手と足に変なのがつけられた感じがする
「か、完璧よ。あぁ、なんて高い猫度なのかしら」
「猫度? 」
「見なさい」
その人が何処から取り出したのか、僕の全身が映るぐらい大きな鏡を目の前に置いた
其処に映っていた僕は、変な格好をしていた
手と変な手袋みたいなのをつけて、足にも似たような物をつけてる
頭の上に猫の耳と同じ形をした耳がつけられてる、意識してみると何でかピクピク動いた
こんな変な格好をさせた人は、僕の方を見詰めながら元気そうにしてる
さっきまで、苦しそうにしてなかったっけ?
「えっと、これは? 」
「最後は、これをつければ完成よ」
そう言ってその人は、先っぽに細長い棒の付いた猫の尻尾みたいのを持って僕をまた引っ張る
驚いている僕に(隙間による検閲が入りました。見るには『パチェ萌え』と絶叫してください
4スレ目 >>781
───────────────────────────────────────────────────────────
某国際展示場駅前で約4時間待ってる間に妄想してた恋愛シミュレーション的パチェ。
頭悪いが今更なのでキニシナイ。
「痛っ!」
「どうしたの?」
「本の金具で指切ったみたいだ。おーいてぇ」
血ぃ出てきたー、とぼやきながら切れた人差し指をパチュリーに見せる。
するとパチュリーは、
# 好感度16以上の場合
「そう。本が汚れてないなら良いわ」
と呟くと、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度32以上の場合
「そう。そんなことで一々騒がないで」
と不機嫌そうに言うと、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度48以上の場合
「そう。ほっとけば治るわ」
と言うと、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度64以上の場合
「そう。大丈夫?」
と聞いてきた。
ああ、と返事をすると、そう、と一つうなずいて、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度80以上の場合
「あら、大丈夫? 中には血を吸ったりする本もあるから、注意してね」
「レミリアみたいな本だな」
「違いないわね」
そう言ってクスッと笑うと、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度96以上の場合
「大丈夫? すぐに手当てした方が良いわね小悪魔すぐに包帯持ってきて」
「や、そんなたいした傷じゃないんだけd
「えいっ」
ぐるぐるぐるぐるぐる
「ふぅ、これで安心ね。○○、怪我には気を付けなさいね」
「あ、ああ……ありがとう」
「うわ! ○○どうしたのその包帯? 骨折でもしたの?」
「……レミリアか。いや、指の先っちょ切っただけ」
「……怪我したのは頭なのかしら?」
「俺にも分からん」
# 好感度128の場合
「大丈夫? 治そうか?」
「ああ、ま、これくらないなら舐めてりゃ治るかな」
「ええっ!?
あ、ああ、貴方が舐めるのね」
「? なんだと思ったんだ?」
「なななななんでもないっ! な、なんでもないわっ!」
顔を真っ赤にして手をわたわたとさせながら言うと、読んでいた本に顔を隠すかのように、ばばっとうずめ
た。
(省略されました。小悪魔を登場させるには小悪魔合同誌のP126を踊りきってください)
4スレ目 >>915
───────────────────────────────────────────────────────────
# パチェ好感度128かつ小悪魔イベントを二つ以上こなしている場合
「大丈夫!? 痛くない?」
「ああ、ま、これくらないなら舐めてりゃ治るかな」
「ええっ!?
あ、ああ、貴方が舐めるのね」
「え…なんだと思ったんだ?」
「なななななんでもないっ! な、なんでもないわっ!」
顔を真っ赤にして手をわたわたとさせながら言うと、読んでいた本に顔を隠すかのように、ばばっとうずめた。
と、
「あら何でもないんですか? 残念ですぅ」
「うおっ、小悪魔!? どっから現れた?」
いきなり背後から声をかけられびっくりする。さすが紅魔館にいるだけあって神出鬼没な司書さんだ。
後ろから肩口を覗きこむように抱きつかれ、ケガした指を両手で包み込んでくれる。
「ふふっ、パチュリー様がやらないのでしたら私が代わりに舐めてさしあげましょうか?」
「ダッ!? ダメ! ダメよ! 何言ってるのよこの子!」
「あの。どゆこと? 何の話?」
一人話の流れについて行けてないぞ俺っ。
しかしそんな俺はステキにスルーされるのであった。おおっとルーミアくんのナイトバード!
「えぇ~、どうしてダメなんですかぁ?」
「ダメったらダメ! え~と、ほら、図書館倫理規定に引っかかってるからよ! 今作ったけど」
「図書館倫理規定の例外なんですよ」
「大体! そのっ…恥ずかしいじゃない!」
「あら、私は○○さん好きですから、恥ずかしくないですよ?」
んあ? 小悪魔さん?
しかし瞬間、パチュリーの顔から色が消える。
「私もっ! 私だって、好きだったのに!!」
え、とその言葉の意味を理解するより速く、詠唱無しで撃たれた火の玉が足下に着弾していた。
巻き起こる爆風、烈風、熱風。
「小悪魔と○○の、莫迦ーーーーーーーッッッッッッ!!!」
ヽ/ ひぇぇ、と情けない悲鳴を上げる小悪魔もろともに吹き飛ばされる視界の隅で、
本棚の角を曲がって走り去るパチュリーの姿が見えた。
「……っ、パチュリーっ」
瞳を潤ませていたように見えたのは、気の所為では、きっと、ない。
「あいたたた…はぅぅ、ひ~ど~ぃ~」
「小悪魔」
煤を払って、立ち上がる。とたんに小悪魔が、げっとした表情に変わり、しりもちをついたままで手をすりあわせる。
「あ、あのあの、ごめんなさぁ~い。えーと、その、ちょっとしたアレのつもりだったんですけど……」
「行ってくる」
短く、しかしはっきりと。意志を込めた一言を告げる。それで、通じてくれる。
ぱぁ、と小悪魔の表情が明るくなる。
「はい! パチュリー様をよろしくお願いしますね!」
向日葵のような笑顔を背に受けて、パチュリーを追う。
もしあの笑顔が俺一人に向けられていたなら――また別の物語があったかもしれない。
そういう意味でも、ごめん、そしてありがとう。そう心の中で小悪魔に感謝しながら俺は本棚の谷を走った。
走り去ったパチェは驚くほどあっさりと見つかった。
と言うのも、本棚を二つ曲がったところで倒れていたからだ。
「パチュリー!? パチュリー! どうした、大丈夫か!?」
慌てて抱き起こすと、ゼィゼィと荒い呼吸を繰り返すパチュリーは
「ぜ、喘息が……ゲホゲホゲホッ、ハァ、ハァ」
……ま、そりゃ普段運動しないわ魔法で移動するわのところをいきなり全力疾走すりゃあなぁ。
安心したような、気が抜けたような。
「ど……して…」
「え?」
「どう、して、来たの? 小悪魔の、こと、好きだっ、た、んじゃ、ケホッ、ないの?」
あーー。何か知らんが勘違いされっぱなしか。どう説明したものか。
俺は空いている方の手でぽりぽりと頬を掻くと、ぼんやりと見つめてくる滲んだ紫色の瞳を避けて視線を彷徨わせる。
ちょっと考えたが、口だけで説明するのも面倒だ。
体中を奮い立たせて一つ決心をすると、いまだに半開きでヒューヒューと音を立てて苦しそうに息を吐いているパチュリーの口に自分の唇をすっと重ねた。
「――――。!?!?!!?」
「うわ、ちょっ」
パチュリーは一瞬呆けた目をした後、俺の腕の中でバタバタと暴れだし、胸を突き飛ばして立ち上がる。
「パチュリー!」
がし! と、また逃げようとした肩をつかんで無理矢理振り向かせ、そのまま真っ直ぐにパチュリーを見つめる。
細い肩。細い身体。濡れた瞳。不安そうな眼。上気した頬。――俺が濡らした、形の良い唇。
「全てが――お前の全てが好きだッ! 小悪魔よりもずっとずっとお前の方が好きだッッッ!!!」
言った! 言い切った!
と、つぅ、とパチュリーの頬を涙が伝ったかと思うとそのまましゃくり上げ始めた。
「…っっぐっ………っぇぐ…っく……」
「パチュリー……」
今さらじゃ、遅かった、の、か?
不安という耐えきれない重圧だけが襲いかかってくる。
「…がぃ、…って」
「え?」
「も゛っかい゛、言っ゛て…?」
後から思い出すに、このとき滑稽なほどぶんぶんとうなずいていた記憶がある。
「何回でも言う! 好きだ、パチュリー好きだ、大好きだ、誰よりも誰よりも誰よりも愛してる!」
パチュリーは。しばらくぼーっとしていたが、やがて
うん、うん、と涙と鼻水でぐしゃぐしゃになった顔をふっと笑顔に変えてうなずくと、胸の中に飛び込んできてくれた。
それを、壊れ物を扱うようにやさしく抱きしめる。体全体で、愛する人を感じる。
薬草の臭いがパチュリーを余計に近く感じる。
「ねぇ、もう一回。もう一回言って」
「好きだ。ずっとずっと、愛してる。きっと出会ったときから、愛してた」
「もう一回」
「いつでもどこにいても誰よりも愛してる」
「……ありがとう。
うん、ありがとう。
もう、口滑らせちゃったけど。あなたが好き。大好き。どんな本より愛してるわ」
潤んだ瞳が俺を見つめる。
そうして、ゆっくりと二人の唇と唇が距離を縮めてゆく。
一度目は、お姫様を解き放つキスだった。
「んっ……」
「あむっ……ん………」
二度目からは、ゆっくりと。お互いを感じ合うためのキス。
「ん…ぷはっ……あ…ねぇ、○○、もっと…もっとして……」
「うん、俺もしたい。ちゅ…ん…」
「うん…んぐ…ちゅっ……」
「んむ……むぁ……」
「はぁっ……んっ……ちゅろっ…」
「んぅっ!? …ん、ん。じゅろっ…………」
……………
………
…
長い間、ずっとそうして二人でお互いを、そして幸せを感じあっていた。
「あ~あ。咲夜さぁん、見事に○○さんパチュリー様に取られちゃいました」
「奥手なパチュリー様を焚き付けて本音を引き出すきっかけを作る、かぁ。
何て言うのかしらこれ? 雨降って縁固まる、だったかしら」
くっくっ、と喉の奥で笑うと、まさに小悪魔、と呟いて二つ手を叩くメイド長。
円卓に置いた水晶で成り行きを見守っていた二人は、軽口をたたき合って紅茶のカップを一つ啜る。
「めでたしめでたし……と、言いたいところだけど」
「はい?」
「冗談っぽく言ってるけど。あなたも、結構本気で○○のこと好きだったんじゃないの?」
心の奥を見透かそうとするようなメイドの視線を受けて、もう一口、小悪魔は紅茶を口にして言った。
「咲夜さんは…レミリア様の幸せとご自分の幸せと、どちらを選ばれますか?」
「両方。私がお嬢様を幸せにして差し上げれば良いのですわ」
「こぁぁー、残念。その手がありましたねぇ」
「あなたぜんっぜん残念そうじゃないわね。むしろ幸せそう」
あついわぁ、と半分苦笑の半分あきれ顔になって手をぱたぱたと泳がせる。
きっともうすぐ二人で帰ってくるだろう。
今日も、そしてこれからも。笑顔で二人を「おかえりなさい」と迎える権利は自分にしかないのだと考えると、
小悪魔はとろけるような幸福感に満たされるのだった。
パチュリーGoodエンド01
(お読み頂きありがとうございました。もし“別の物語”も読んでやろうという方は花映塚MatchLunaで3分間粘って下さい)
4スレ目 >>948(うpろだ >>0050)
紅魔館地下に設けられた書斎は、大量に収められた本の匂いで満たされている。
その中にたまに紛れ込むのは、紅茶の香りであったり、コーヒーの香りであったり、弾幕の衝撃であったり。
「うーん…………」
ぺらり、と音を立てて、新たなページが知識を運んでいく。
今日も今日とて、その書斎の主、パチュリーは調べ物に余念がない。
彼女が読む本に、ジャンルの壁などは存在しない。
魔女らしく魔術書を読むこともあれば、外界の歴史書や雑誌を読むことだってある。
だが、幻想郷に外界の本が来ることはごく稀で、当然ながら外界の知識は限られたものになってしまう。
最近彼女が求めているのは、とある外界の知識である。
「ねえ小悪魔。そっちは?」
「あまり、芳しくありません……」
普段は自分だけで読んでいる彼女だが、今日は小悪魔も動員しているようだ。
広い机の上には十数冊もの本が散らばり、後でこれを片付けることになるであろう小悪魔は、既にげんなりしていた。
「やっぱり向こう側の常識は、本に記されることが少ないのかしら?」
「パチュリー様。やっぱり○○さんに聞いてみれば……」
「何度も言っているでしょ。今回ばかりは、それじゃ駄目なのよ」
小悪魔の提案は、即座に却下された。
パチュリーの恋人である○○は、元は外界から来た人間である。
本ではどうしても調べられない知識は、彼に聞いて得ることが出来たのだ。
もちろん、彼が知っている範囲の知識に限られるのだが、外界の常識として浸透しているはずの知識なら、彼が知らないはずがない。
それでもパチュリーは、その方法を選ばなかった。
「内緒にしなきゃ……駄目なのよ」
夜の霧雨亭。
魔法の森の奥に建っているその家は、静かではあるのだが、その主に至ってはその限りではない。
それでも弟子を迎えてからは、以前に比べれば大人しくなった方である。
「そうだ、○○。ちょっと思い出したんだが」
「……師匠が言うと、とんでもなく不穏当に聞こえるんですけど」
そんな霧雨亭での夕食の席。
彼は魔理沙の茶碗にご飯をよそいながら、眉を寄せた。
魔法の稽古はつけてもらっているが、今の彼を見る限り、とても弟子には見えない。
エプロンと言う名の、薄いブルーの戦闘服に身を包み、頭には純白の三角巾。
それはまさに、家庭を預かる戦士の姿だった。
「おいおい、恐い顔するなって。
そんな顔してると、パチュリーに嫌われるぞ」
「……師匠。自分の胸に手を当てて、心辺りがないか思い返してみません?」
彼とて、伊達に長らく魔理沙の弟子をやっているわけではない。
彼女が切り出す話は、彼にとって危ない橋を渡らせる類のものであることが多かった。
もちろん、それは悪意あってのものではなく、結果が吉と出ることもあるのだ。
例えば、以前彼がパチュリーを紅魔館まで送って行った時のように……。
「もちろんないぜ。なんにもないからな。
大したことじゃないから、そんな顔しないでまず聞け」
「……それならいいんですけど。
なんにもないなら、話自体なかったことになりません?」
「師匠の教えは聞くもんだぜ」
一抹の不安を抱えながら、彼は魔理沙に茶碗を手渡し、向かいの席につく。
「お、ありがとな。んじゃ早速頂きます」
「師匠……話があるんじゃないんですか?
あるなら、食べるか話すかどっちがでお願いします」
「面倒だから食べながら話すぜ。人の一生は短いんだ」
魔理沙の話を簡単に要約すると、休日をやると言うことだった。
魔理沙は久し振りに魔法薬の実験をやりたいのだが、危険性が高く、相当集中しなければならない。
そのため、家はなるべく静かな方が好ましく……。
「……つまり、ここ以外で時間を潰してろ、ってことですか」
「そんなところだぜ。
お前なら、迷わずパチュリーの所に行くんだろうけどな」
的を射た彼女の言葉に、彼はやっとのことで、
「べ、別に……いいじゃないですか」
とだけ返した。
「ああ、別にいいぜ。パチュリーもああ見えて、意外と寂しがりやだからな」
「そうねぇ。あの娘も最初は、対応こそツンツンしてたのに、今はもうすっかりあんな調子だしね」
そっぽを向く彼に、前と下から連携した冷やかしが飛ぶ。
視線を落とせば、彼の空っぽの茶碗から、顔だけにょきっと生えたスキマ妖怪が。
「○○。寂しがらせたなら、ちゃんと慰めてあげなさいな。
ああいった内気な娘は、少し強引に押し倒して……」
ぐわしっ!!
「まあ、師匠が昼夜抜く覚悟なら、俺は別に構いませんが」
「うわ、紫を手掴みか。やるようになったな、お前も」
茶碗から湧いて出た紫を、○○はアイアンクローで迎え撃つ。
「あらあら、あの娘に続いて私かしら?こういうのも『手が早い』って……」
ぎりぎりぎり……。
「お、おい。何か頭の形が変形してないか?」
「気のせいです」(キッパリ)
少し慌てた様子の魔理沙に、彼は動じる事なく断言する。
加えて、紫のことは完全に無視である。
以前なら律義に『口より先に手が出る、の間違いです』とでも返したものだが。
彼も慣れたということだろうか。
「ふふっ。その程度じゃ、まだまだ私は倒せないわよー♪」
「……藍の奴も、苦労してるんだろうな」
「そうですね。師匠に拾われて、本当に助かりました」
「あらあら。今度は魔理沙かしら? 全く、呆れるくらいのプレイボーイなんだから……」
ガタンっ!!
倒れる椅子には目もくれず、彼は立ち上がると近くの窓を開け放つ。
「あ、あら?」
「とりあえず……紫さん」
「私の魔砲で、白玉楼まで送ってやるぜっ!」
茶碗ごと、彼は全力投球で紫を夜空へ放り投げる。
そして――
魔砲『ファイナルスパーク』
――夜空を切り裂く光芒が、魔法の森の上空に弾けた。
恐れるべきは魔理沙の狙撃力か破壊力か、師弟のコンビネーションか。
夜空に向けられたはずの魔砲は、あまりの威力に森の一部も巻き込んで……。
「あれ、師匠。あっちって、アリスさんの工房じゃ……?」
「知らないぜ」
「……まあ、明日は俺もいませんし、何かあっても師匠の仕業ですから、いいんですけどね」
「ああ、飯の作り置きだけは頼むぜ」
「はいはい、了解了解」
ぺらりぺらりと、ページがめくられていく。
探しても探しても、目当ての知識は見つからない。
あるのは、断片的な情報ばかり。
それでも、その僅かな情報を手掛かりに、パチュリーは探し続けていた。
それは、甘い物だということ。
それは、黒い色をしていること。
それは、主に四角い形をしていること。
それは、砂糖や豆を材料にして作ること。
「……なるほど、ね」
パタン、と彼女は本を閉じる。
「見つかったんですか?」
「いいえ。でも、それが何を指しているのかは、やっと解ったわ。
これは多分、呼び方が変わっているだけで、私達がよく知っている物だったのよ」
小悪魔の問いに、自信を持って断言するパチュリー。
それなら後は片付けて、ゆっくり休もう……そう思っていた小悪魔に、パチュリーからメモが渡される。
「はい、これが材料よ。支度して厨房に行くから、先に集めておいてね」
「は、はいぃ……」
紅魔館の夜は長い。
未だ寒さの残る幻想郷の空には、煌々と輝く紅い月。
「月もこんなに紅いしね。今夜は、作るわよ……!」
(パチュリー様……そんなだから、お身体もよくならないんじゃ……?)
紅魔館は吸血鬼の治める館。
夜こそが、活動時間なのだ。
小悪魔が眠れるのは、まだ当分先の事になりそうである。
翌日、昼前の紅魔館――
「…………」
彼は、言葉を失って立ち尽くしていた。
いつも見慣れた彼女の書斎が、今日ばかりは異空間に見えていたのだ。
小悪魔が頑張って整理し、魔理沙が荒らした後以外は、常に整然としている本棚が、所々乱雑になっていた。
それだけではない。
机には、栞がはさまったままの本が数冊、開きっぱなしの本が十数冊散らばっていた。
後者に関しては、パチュリーの性格からして、有り得ない状態である。
「参ったな……」
広い紅魔館内でも、ようやく迷わずに移動出来るようになり、先日から案内を断った矢先の出来事なのだ。
彼以外には誰もいない。
少なくとも、見える範囲にはであるが。
「あ、れ――?」
不意に訪れた既知感。
見慣れないはずの、この状況を知っているという、矛盾。
目を凝らしても、見えるものは変わらない。目を向けるべきは、彼が何故そう感じたか――。
(ああ――そうか)
彼は気付いた。
程度の差こそあれ、散らかった部屋なら、見慣れている。
魔理沙の蒐集物で圧迫された部屋も、またしかりである。
そして、そんな部屋に対して、彼がやるべきことと言えば、もはや1つしかない。
「……片付けよう」
原因が解った所で、現状が改善される訳ではない。
そんな理屈を抜きにして、まずは目の前の惨状をどうにかするべく、彼は手近な本を手に取る。
(これは……料理の本?それに、あっち側の……?)
幻想郷にある本と外界の本は、様々な違いがある。
紙質もその1つではあるが、外界の本は比較的カラフルである。
彼が手にした本も、そうだった。
机に散らばっている本も、見た感じでは、大低が外界の本らしい。
幸いにも、外界の本が纏められている本棚は、彼も知っていた。
小悪魔ほどの効率ではないにせよ、丁寧に確実に、あるべき場所へ納めていく。
そして彼は、いつもと違うもう一つの点に気付いた。
微かに感じる、甘い香り。
僅かではあるものの、紅茶やコーヒーなどとは違う風味。
「お菓子……かな」
何となくではあるが、彼はそう感じていた。
他ならともかく、紅魔館なら十分な材料があってもおかしくない。
だが、仮に今誰かが作っていたとしても、この場所までその香りが漂うとは考えにくい。
カチャリ。
彼が首を傾げると、答えはドアを開けて、自らやって来た。
「あ、○○……来てたのね」
「おはよう、パチェ。
勝手に片付けさせてもらってるよ」
近くのドアが開き、現れたパチュリーの手には、あまり見映えはよくないものの、一生懸命にラッピングされた箱が握られていた。
「で、この大きな箱は何なのよ?」
「あいつの作り置きだぜ。一人じゃこんなに食べ切れないからな」
正午過ぎの博霊神社。
珍しく手土産を持参した魔理沙は、縁側でそれを開ける。
中には、クッキーやら大福餅やら、茶菓子の類が所狭しと詰まっていた。
「彼の作り置き……ねぇ」
「以心伝心ってやつだろ。私の弟子なんだからな」
彼が作り過ぎたという可能性は、既に魔理沙の頭にはない。
師の気遣いは、しっかり弟子に気付かれていたのである。
霊夢は、箱の中に無造作に手を突っ込むと、苺大福を取り出した。
「パチュリーじゃなくて、魔理沙が相手だったら面倒がなくて済みそうよね。
……あ、美味しい」
「よせやい。私はそんな目的で、あいつを拾った訳じゃないぜ。それに……」
大福を頬張る霊夢の横で、魔理沙は煎餅をかじり、空を見上げる。
珍しく晴れた、冬の幻想郷の青空は、彼女には少し眩しく映った。
「……端から見てて、やきもきすることもあるけどな。
あいつらが幸せそうに笑ってるの見ちまうと、割って入る気もなくなっちまうぜ」
帽子のつばを下げ、彼女はぐいと茶を煽る。燻した香りが目に染みた。
「まあ、魔理沙だしね。あんなに集めてるんだし、いずれ人まで拾うとは思ってたけど。
牡丹餅も美味しいわよ。食べる?」
「ああ、頂くぜ。残さず頂いてやるぜ」
「それじゃあ幽々子みたいじゃないの……って、言ってるそばから来そうよね」
茶菓子に限った話ではないが、食べ物が大量にある所に、冥界のフードファイターは現れる。
茶菓子は2人でも十分な量なのだが、幽々子の食欲の前には風前の灯だろう。
加えて、紫と組んでスキマを抜け、至る所に現れることまであるので、余計にタチが悪い。
「あいつが死んだら、幽々子の所で菓子職人になりそうだな」
「作るのは……桜餅かしらね」
「そうだな、私に似て和食派だし」
幻想郷の青空に1つ、星が流れる。
それを目にしたのは、霊夢だけだった。
「チョコレート、作ってみたんだけど……」
あらかた片付け終わり、一息ついた所でパチュリーは切り出した。
料理書を片手に、一晩中かかって作り上げたのだ。
もちろん一人で出来ない作業は、小悪魔にも若干手伝わせたものの、彼女自身に料理の心得はあまりない。
場慣れしていないせいもあるのだろう。差し出す彼女の白い手は、所々赤くなっている部分があった。
「確か、バレンタイン……って言うのよね」
「そうなんだけど……何だか、食べるのが勿体ない気がするよ」
世界的には、男性から女性へあげるケースが大半で、逆なのは日本くらい----。
思わずツッコミそうになるのを押さえ、彼は差し出された箱を見つめる。
向こうでも、ラッピングは人の手で行われているが、どれも見栄えよく画一的なものだ。
それに比べると、見劣りこそするものの、適度に崩れた部分が手作りであることを強く思わせる。
手の赤みもだが、書斎がこんなになるまで調べ、作ったことを考えれば、確かに食べてしまうことも躊躇われる。
「あまり、日保ちしないと思うわよ?
その……出来れば、美味しいうちに食べて欲しいし、感想とかも……」
「そっか……それもそうだね」
食べて欲しいから作る。
これは、料理をする彼にも解る気持ちだ。
勿体ないからといって、駄目にしてしまっては、それこそ本末転倒だろう。
彼はパチュリーから箱を受け取り、もう一度しっかり見詰める。記憶に刻み込むように。
「術式展開スペルセット・対象解析アナライズ・接合解除リンクカット……」
テープの代わりに、魔力で接着されたラッピングを、一箇所ずつ丁寧に切り離していく。
全ての接着箇所を切り離すと、花が開くように、ふわりとラッピングがほどけた。
「綺麗だな……」
後に残るのは、シンプルな白い箱。
彼の隣で、パチュリーは固唾を飲んで見詰めている。
蓋を開ければ、甘い香りが周囲に溢れ出す。
(これは……)
それは、彼がずっと感じていた香りである。その源が、パチュリーの渾身の一作なのだ。
「どう……?」
「よく出来てると思うよ。まあ、見た目はだけど……」
「……意地悪」
食べずに彼が言えるのはそれくらいなのだが、やはり彼の一言は余計だろう。
「味見はしたから、失敗じゃないとは思うわよ?」
「ごめんごめん。それじゃ頂きます」
怒ったようなパチュリーをかわして、彼は一切れ口に運んだ。
角を引っ込めたパチュリーは、黙って彼の反応を伺っている。
料理書を何度も確認しながら作り、何度も味見しているとはいえ、不安は拭えない。
念には念をということで、小悪魔やレミリアにも味見してもらったのだが、味覚というのは十人十色である。
それは、人も魔女も妖怪も悪魔も、変わりはない。
「……パチェ、そんな顔しなくていいよ。普通に美味しいから」
「ほ、本当?」
彼の言葉に、パチュリーは――珍しいことに――驚きの表情も隠すことなく、身を乗り出して尋ねた。
「自信持って。何なら、パチェも食べる?」
「う、ううん……貴方に食べて欲しくて作ったから、私はいいわ」
「でも、独り占めするのもちょっと……」
そう言って彼は、箱に視線を落とす。
次に彼が聞いた囁くような声は、とても近くから聞こえた。
「じゃあ……一口だけ、ね」
「え……?」
普段の彼ならば、咄嗟に反応することも出来ただろう。
だが、油断していたためか、安心しきっていたためか、彼は動くことさえも出来なかった。
それは、完全な不意打ちで、直撃だった。
零距離からの、恋の魔法――
「ご……ごちそうさま」
どちらともなく身体を離した時、仕掛けた側も直撃した側も、顔を赤く染めていた。
結果を見れば、相打ちだろうか。
「……パチェの方が、美味しいな」
「馬鹿……チョコも、ちゃんと食べてよね」
「そりゃ食べるけどさ……」
彼が返す言葉は、少し歯切れが悪い。
言うべきか、言わざるべきか迷っていたのだ。
だが、根本的な間違いなら、やはり指摘するのは早い方がいい。
まだ顔は赤かったが、彼は意を決して、口を開いた。
「パチェ、チョコレートと羊羹は別な物だからね」
「え……チョコレートって、羊羹の別名じゃなかったの!?」
―――後書きの原材料は、小豆と砂糖と、ほんの少しの糸寒天―――
性格も積極的な方ではなく、常に我が道を行く。ただ、好奇心は高く
知識に関しては積極的に取り入れる。全て本に依る物だが間違いも多い。
東方萃夢想の上海アリス通信、パチュリーの項目より抜粋。
つまり、知識に関してはパーフェクトだと思われがちなパチュリーも、実は間違った知識を?
それがオチでもあり、今回の動機です。前の続きというか、補完も兼ねてますが。
バレンタインとチョコレートが、幻想郷行きになる日はいつになるんでしょうね。
>>530
───────────────────────────────────────────────────────────
今日も俺は図書館にやってきた。
外は雪がちらつく空模様。図書館の中もすこし肌寒い。
暖炉の近くの安楽椅子に深く腰掛け、読みかけの本を手に取る。
「今日も来たのね」
――うん、いろいろと読んでみたい本が多いしね。
「好きにしていいとは言ったけど、来たなら一言あってもいいんじゃない?」
――邪魔しちゃ悪いと思ってさ。
「気遣いするような性格じゃないでしょ」
――確かにね。
パチェの手を引いて膝の上に座らせ、そのまま抱えるように抱き寄せる。
「ちょ、ちょっと!」
――本の解説してほしいんだけど、寒いから風邪ひかせたくないし。
「こんな体勢じゃなくても解説するわよ。それに暖炉があるから大丈夫っ…」
――パチェは温かいな。
「な、何を言って…」
――この温かみを感じられる奴は幸せだな」
「………………ッ、(………貴方だけよ)」
パチンッ!
パチェの呟きに暖炉の薪の爆ぜる音が被った。
――もう一回。
「……聞こえてたくせに…」
うらめしそうな顔で睨んでくるパチェ。
今夜はまだまだ冷え込みそうだ。
3スレ目 >>383
───────────────────────────────────────────────────────────
パチュリーの隣で、図書館の奥魔法の本を読んでいる。
借りていこうとして席を立つと、そっと袖を掴まれた。
「たまには……ここで読んでいかない?忙しいなら、無理にとは言わないけど………」
袖を引っ張っりつつ、向こうを向きながらもじもじしているパチェ。
3スレ目 >>461
───────────────────────────────────────────────────────────
読書中
「なあ」
「・・・・・・・・」(読書中)
「なあって」
「・・・・・・・・」(読書中)
「もしもーし」
「・・・・・・・何か用?」(顔を上げる)
「いや・・別に用事は無いけど」
「用が無いなら話しかけないで・・・・・」(読書に戻る)
一転してデレ状態
「なあ」
「・・・・・・・・」(読書中)
「なあって」
「・・・・・・・・」(読書中)
「もしもーし」
「・・・・・・・何か用?」(顔を上げる)
「いや・・別に用事は無いけど」
「・・・・・・・・・・・・そう」(読書に戻る)
ああパチュリーに後ろ向いてから振り返りながら「大好き」って言わせてEEEE!!
3スレ目 >>844
───────────────────────────────────────────────────────────
時々騒がしくなるが、普段は薄暗く静かな図書館
俺がここに来てからかなりの月日が立っていた。
「なあ」
「なに?」
「俺がここに来てから結構立つよな」
「そうね」
「なんかお祝いみたいのってないのか?」
「ないわ」
「即答かよ・・・」
「必要ないもの。費用もかかるし、大体何に対して祝うのよ」
「俺が今まで幻想郷で生きてこれたことに対して」
「・・・まあ、確かに稀ではあるわね」
「じゃあさ、二人で祝わないか」
「・・・何で私なの」
「他に祝ってくれるような人がいるか?」
「その祝う人の中に私が入っているのが疑問なんだけど」
「まあ、それは捨て犬のような俺を拾ってくれたご主人様なわけだし」
「人間の使い魔を持った覚えはないわ。それに、あれは捨て犬じゃなくて半死体よ」
「・・・ところで、喋っている時ぐらい本から顔を上げないか?」
「必要ないわ」
「・・・外でピクニックなんかいいな」
「まだやるなんて言っていないわよ。それに如何してわざわざ外なんかに」
「普段、日陰にいるんだからたまにはいいだろ?それに日向に出ないと健康に悪いぞ」
「いいのよ、知識と日陰の少女だから。健康に関しては否定できないけど・・・」
「それなら丁度いいだろ。今やっている研究もないみたいだし」
「それはそうだけど・・・ 何で研究がないことを知っているの」
「いつも見ているからな。それに、ほとんど実験体のようなものだろ?俺」
「そう、そうね。 まあ、いいわ祝ってあげましょう。」
「おっし。じゃあ明日は・・・多分、というか絶対黒白が来るだろうから明後日だな。」
「そうね」
「弁当は任せておけ!今までで最高な物を作って見せる」
「それは楽しみね。あなたの料理美味しくて食べやすいから、でも普通私が祝うんじゃないの?」
「細かいことは気にしない!それと、あ~なんだ、その・・・ ピクニックのときに大事な話がある」
「大事な話?」
「ああ」
「そう・・・」
「・・・気に成らないのか」
「明後日になったら聞けるのでしょう?」
「そりゃ、まあ」
「だったら待っているわ。楽しみにしてね」
「そう、待っているわ。」
「貴方が言ってくれるまで、いつまでも いつまでも・・・ね」
薄暗く静かな図書館
されど少女の声は誰にも聞こえず、届かず・・・
ただ、少女の読んでいる本だけがそれを見ていた。
顔を朱に染めとても幸せそうに微笑んでいるその顔を・・・
執筆、投稿ともに二回目!初執筆の物と似ているところが多いな~と自分で思うが
直せる腕がない罠!ただ、言えることは私の中のパチュはこんな子です。ということだけです。
ちなみに、料理の感想は実際の言われたことのある言葉です。作った相手は男だったけどね!
避難所 >>9
───────────────────────────────────────────────────────────
ええと、効率よく仮眠をとる方法は……。
――○○、ちょうどいい所に、ちょっとここに座って頂戴。
……何で警戒してるのよ。失礼ね、実験なんかじゃないわ。
普通に座ってていいのよ。私の方じゃなくて、テーブルの方向いてて。
……別に失礼でも何でもないから、気にしなくていいのよ。変な所で律義なんだから。
そうそう、そんな感じよ。後は動かないで、目を閉じて楽にしてなさい。
よい……しょっと。
……緊張することないじゃない。心地いいんだから、誇ってもいいくらいよ。
そうね、レミィが起きる辺りに起こしてくれるかしら。
――変な事、しないでよね。
…………。
………。
○○さん、何をなさってるんですか?
枕……ですか。
ふふ、やっぱり恥ずかしいですよね。
でも、パチュリー様がそんな風に甘えられるのって、○○さんくらいなんですよ?
まぁ、甘えてるようには見えませんけど……素直じゃないんですよ。
……ええ、それを聞いて安心しました。私は仕事が残ってますから、向こうにいますので。
――あ、はい。そうですよね、毛布でしたらすぐお持ちします。
ない物はセルフで補給すればいいってことでパチェ分補給。
4スレ目 >>420
───────────────────────────────────────────────────────────
……そう言えば貴方、毎回どうやって入ってくるのよ。
逆立ちしたって、貴方じゃ小悪魔にも敵わないでしょう?
はぁ……呆れたわね。そんな方法があったなんて。
ええと、それって何て言ったかしら……食糧責め?
……買収って、流石に言い方が悪くないかしら。
まあ、別に邪魔じゃないからいいけど。
でも、貴方も変わり者ね。わざわざこんな所まで来るなんて。
……確かに本は沢山あるけど、それだけで来るような場所でもないでしょ。
――本当に、それだけ?
…………。
………。
――な、何?借りていくの?
……本の管理は小悪魔の仕事だから、一声掛ければ大丈夫よ。
貸出期限?……別に、ちゃんと返しに来るならせっかちなことは言わないわ。
ええ、それじゃ、またね。
…………はぁ。
最後のパチュリーのため息が誰に向けられたかで、脳内補完の方向が変わりそうですが。
4スレ目 >>616
───────────────────────────────────────────────────────────
怒ると危ないお嬢様とメイド長の人にやっと放してもらえた僕は、美鈴さんに会いたくて門に向かう
元の服に着替えたけど、メイド長の人に渡された鞄の中に巫女服とメイドさん達が着る服が入ってる
メイドさん達が着ている服は返そうとしたら、メイド長の人がまた着させようとしたので受け取った
着ないのに、洗って美鈴さんから返してもらおう
「美鈴さん! 」
「あれ? 遅かったわね」
「あ、ごめんなさい」
「別に怒ってるわけじゃないんだけど、どうしたの? 」
僕は、何故か美鈴さんに聞いて欲しくてさっきまでの事を話した
美鈴さんは驚いたような顔をした後、苦笑しながら僕の頭をなでてくれた
「あちゃー、私の部屋に置いて行ったのは不味かったわね」
「えっと、その」
「それより、どうだった? 」
「え? 」
美鈴さんが、突然ニマニマと変な顔をして僕に聞く
僕の胸を軽く指で突付きながら、美鈴さんはムフフーと言う
「お嬢様と咲夜さん、あのお二人の事だから相当凄かったでしょう? 」
「あ、う」
「照れない照れない、それよりどんな風にしたの? やっぱり巫女服で? 」
美鈴さんの言葉に、僕は怒りを覚えた
何で?
理由は分からないけど、それしか思いつかないぐらい怒っていた
「美鈴さんの馬鹿ー! 」
「ほへ? 」
これ以上美鈴さんと話ていたくない
僕は美鈴さんから逃げる為に、出てきた館に逃げ込んだ
「はぁ」
僕は溜息を止めないで館の中を歩いている
美鈴さんに、馬鹿なんて言っちゃった
それに時々立ち止まって後ろを振り返っても、美鈴さんは居ない
やっぱり馬鹿なんて言ったから追いかけてくれなかったんだ
「うぅ」
何でだろう、涙が出てきた
涙が眼から零れ落ちようとしたとき、僕の視界に長くて紅い髪が眼に入る
「美鈴さん? 」
紅い髪が、一つの扉に吸い込まれるように消えるのを僕は呆然と見ていた
慌てて追いかける
その扉に急いで僕も入ろうとしたら、扉を開けた途端に僕は暗い場所に吸い込まれた
吸い込まれる前に紅い髪の人が見えたけど、美鈴さんじゃなかった
あぁ、僕は美鈴さんに謝らなきゃいけない
何も見えない暗い中、僕は柔らかい何かの上に落ちた
驚いて立ち上がっても、暗くてなにも見えない
だけど本当に暗いわけでもなかった見たいで、眼が慣れてくると普通に見えるようになった
「むきゅー」
「うわ! 大丈夫ですか!? 」
多分、僕が落ちたときに下敷きにしてしまった人が倒れていた
倒れたままなのが心配になって上半身を起こしてみたけど、特に怪我は見当たらない事に安心する
少し顔色が悪いのは暗いからじゃないと思って、なんとか引き摺らないよう近くにあった椅子に座らせた
でも、どうしよう?
あたりを見渡しても誰もいないみたいで、本が一杯あることに僕は気づいた
「図書館、かな? 」
「う、うぅ」
気絶した人をどうすれば良いのか書いてある本を探しに行こうとしたら、下敷きにしてしまった人の眼が醒めたみたいだ
「痛い、ゴホッ」
「大丈夫ですか? 」
僕が話しかけると、その人が僕を見て急に苦しみ始めた
「うぅ、苦しい! 死んでしまう! 」
「えぇ!? ど、どうすれば!? 」
慌てる僕が誰か呼びに行こうとしたら、その人に腕を凄い力で掴まれた
「私を助けなさい! 」
「ど、どうすれば良いんですか!? 」
「これ、これをつけて! むしろ私がつける! 」
掴まれた腕を引っ張られて、その人に抱きかかえられた
それで頭に変なのが乗せられた気がする
「えっと? 」
「後はコレとコレとコレ! 」
「うわぁ!? 」
その人は僕を凄い勢いで動かして、僕はそれに眼を回した
手と足に変なのがつけられた感じがする
「か、完璧よ。あぁ、なんて高い猫度なのかしら」
「猫度? 」
「見なさい」
その人が何処から取り出したのか、僕の全身が映るぐらい大きな鏡を目の前に置いた
其処に映っていた僕は、変な格好をしていた
手と変な手袋みたいなのをつけて、足にも似たような物をつけてる
頭の上に猫の耳と同じ形をした耳がつけられてる、意識してみると何でかピクピク動いた
こんな変な格好をさせた人は、僕の方を見詰めながら元気そうにしてる
さっきまで、苦しそうにしてなかったっけ?
「えっと、これは? 」
「最後は、これをつければ完成よ」
そう言ってその人は、先っぽに細長い棒の付いた猫の尻尾みたいのを持って僕をまた引っ張る
驚いている僕に(隙間による検閲が入りました。見るには『パチェ萌え』と絶叫してください
4スレ目 >>781
───────────────────────────────────────────────────────────
某国際展示場駅前で約4時間待ってる間に妄想してた恋愛シミュレーション的パチェ。
頭悪いが今更なのでキニシナイ。
「痛っ!」
「どうしたの?」
「本の金具で指切ったみたいだ。おーいてぇ」
血ぃ出てきたー、とぼやきながら切れた人差し指をパチュリーに見せる。
するとパチュリーは、
# 好感度16以上の場合
「そう。本が汚れてないなら良いわ」
と呟くと、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度32以上の場合
「そう。そんなことで一々騒がないで」
と不機嫌そうに言うと、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度48以上の場合
「そう。ほっとけば治るわ」
と言うと、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度64以上の場合
「そう。大丈夫?」
と聞いてきた。
ああ、と返事をすると、そう、と一つうなずいて、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度80以上の場合
「あら、大丈夫? 中には血を吸ったりする本もあるから、注意してね」
「レミリアみたいな本だな」
「違いないわね」
そう言ってクスッと笑うと、読んでいた本に再び目を落とした。
# 好感度96以上の場合
「大丈夫? すぐに手当てした方が良いわね小悪魔すぐに包帯持ってきて」
「や、そんなたいした傷じゃないんだけd
「えいっ」
ぐるぐるぐるぐるぐる
「ふぅ、これで安心ね。○○、怪我には気を付けなさいね」
「あ、ああ……ありがとう」
「うわ! ○○どうしたのその包帯? 骨折でもしたの?」
「……レミリアか。いや、指の先っちょ切っただけ」
「……怪我したのは頭なのかしら?」
「俺にも分からん」
# 好感度128の場合
「大丈夫? 治そうか?」
「ああ、ま、これくらないなら舐めてりゃ治るかな」
「ええっ!?
あ、ああ、貴方が舐めるのね」
「? なんだと思ったんだ?」
「なななななんでもないっ! な、なんでもないわっ!」
顔を真っ赤にして手をわたわたとさせながら言うと、読んでいた本に顔を隠すかのように、ばばっとうずめ
た。
(省略されました。小悪魔を登場させるには小悪魔合同誌のP126を踊りきってください)
4スレ目 >>915
───────────────────────────────────────────────────────────
# パチェ好感度128かつ小悪魔イベントを二つ以上こなしている場合
「大丈夫!? 痛くない?」
「ああ、ま、これくらないなら舐めてりゃ治るかな」
「ええっ!?
あ、ああ、貴方が舐めるのね」
「え…なんだと思ったんだ?」
「なななななんでもないっ! な、なんでもないわっ!」
顔を真っ赤にして手をわたわたとさせながら言うと、読んでいた本に顔を隠すかのように、ばばっとうずめた。
と、
「あら何でもないんですか? 残念ですぅ」
「うおっ、小悪魔!? どっから現れた?」
いきなり背後から声をかけられびっくりする。さすが紅魔館にいるだけあって神出鬼没な司書さんだ。
後ろから肩口を覗きこむように抱きつかれ、ケガした指を両手で包み込んでくれる。
「ふふっ、パチュリー様がやらないのでしたら私が代わりに舐めてさしあげましょうか?」
「ダッ!? ダメ! ダメよ! 何言ってるのよこの子!」
「あの。どゆこと? 何の話?」
一人話の流れについて行けてないぞ俺っ。
しかしそんな俺はステキにスルーされるのであった。おおっとルーミアくんのナイトバード!
「えぇ~、どうしてダメなんですかぁ?」
「ダメったらダメ! え~と、ほら、図書館倫理規定に引っかかってるからよ! 今作ったけど」
「図書館倫理規定の例外なんですよ」
「大体! そのっ…恥ずかしいじゃない!」
「あら、私は○○さん好きですから、恥ずかしくないですよ?」
んあ? 小悪魔さん?
しかし瞬間、パチュリーの顔から色が消える。
「私もっ! 私だって、好きだったのに!!」
え、とその言葉の意味を理解するより速く、詠唱無しで撃たれた火の玉が足下に着弾していた。
巻き起こる爆風、烈風、熱風。
「小悪魔と○○の、莫迦ーーーーーーーッッッッッッ!!!」
ヽ/ ひぇぇ、と情けない悲鳴を上げる小悪魔もろともに吹き飛ばされる視界の隅で、
本棚の角を曲がって走り去るパチュリーの姿が見えた。
「……っ、パチュリーっ」
瞳を潤ませていたように見えたのは、気の所為では、きっと、ない。
「あいたたた…はぅぅ、ひ~ど~ぃ~」
「小悪魔」
煤を払って、立ち上がる。とたんに小悪魔が、げっとした表情に変わり、しりもちをついたままで手をすりあわせる。
「あ、あのあの、ごめんなさぁ~い。えーと、その、ちょっとしたアレのつもりだったんですけど……」
「行ってくる」
短く、しかしはっきりと。意志を込めた一言を告げる。それで、通じてくれる。
ぱぁ、と小悪魔の表情が明るくなる。
「はい! パチュリー様をよろしくお願いしますね!」
向日葵のような笑顔を背に受けて、パチュリーを追う。
もしあの笑顔が俺一人に向けられていたなら――また別の物語があったかもしれない。
そういう意味でも、ごめん、そしてありがとう。そう心の中で小悪魔に感謝しながら俺は本棚の谷を走った。
走り去ったパチェは驚くほどあっさりと見つかった。
と言うのも、本棚を二つ曲がったところで倒れていたからだ。
「パチュリー!? パチュリー! どうした、大丈夫か!?」
慌てて抱き起こすと、ゼィゼィと荒い呼吸を繰り返すパチュリーは
「ぜ、喘息が……ゲホゲホゲホッ、ハァ、ハァ」
……ま、そりゃ普段運動しないわ魔法で移動するわのところをいきなり全力疾走すりゃあなぁ。
安心したような、気が抜けたような。
「ど……して…」
「え?」
「どう、して、来たの? 小悪魔の、こと、好きだっ、た、んじゃ、ケホッ、ないの?」
あーー。何か知らんが勘違いされっぱなしか。どう説明したものか。
俺は空いている方の手でぽりぽりと頬を掻くと、ぼんやりと見つめてくる滲んだ紫色の瞳を避けて視線を彷徨わせる。
ちょっと考えたが、口だけで説明するのも面倒だ。
体中を奮い立たせて一つ決心をすると、いまだに半開きでヒューヒューと音を立てて苦しそうに息を吐いているパチュリーの口に自分の唇をすっと重ねた。
「――――。!?!?!!?」
「うわ、ちょっ」
パチュリーは一瞬呆けた目をした後、俺の腕の中でバタバタと暴れだし、胸を突き飛ばして立ち上がる。
「パチュリー!」
がし! と、また逃げようとした肩をつかんで無理矢理振り向かせ、そのまま真っ直ぐにパチュリーを見つめる。
細い肩。細い身体。濡れた瞳。不安そうな眼。上気した頬。――俺が濡らした、形の良い唇。
「全てが――お前の全てが好きだッ! 小悪魔よりもずっとずっとお前の方が好きだッッッ!!!」
言った! 言い切った!
と、つぅ、とパチュリーの頬を涙が伝ったかと思うとそのまましゃくり上げ始めた。
「…っっぐっ………っぇぐ…っく……」
「パチュリー……」
今さらじゃ、遅かった、の、か?
不安という耐えきれない重圧だけが襲いかかってくる。
「…がぃ、…って」
「え?」
「も゛っかい゛、言っ゛て…?」
後から思い出すに、このとき滑稽なほどぶんぶんとうなずいていた記憶がある。
「何回でも言う! 好きだ、パチュリー好きだ、大好きだ、誰よりも誰よりも誰よりも愛してる!」
パチュリーは。しばらくぼーっとしていたが、やがて
うん、うん、と涙と鼻水でぐしゃぐしゃになった顔をふっと笑顔に変えてうなずくと、胸の中に飛び込んできてくれた。
それを、壊れ物を扱うようにやさしく抱きしめる。体全体で、愛する人を感じる。
薬草の臭いがパチュリーを余計に近く感じる。
「ねぇ、もう一回。もう一回言って」
「好きだ。ずっとずっと、愛してる。きっと出会ったときから、愛してた」
「もう一回」
「いつでもどこにいても誰よりも愛してる」
「……ありがとう。
うん、ありがとう。
もう、口滑らせちゃったけど。あなたが好き。大好き。どんな本より愛してるわ」
潤んだ瞳が俺を見つめる。
そうして、ゆっくりと二人の唇と唇が距離を縮めてゆく。
一度目は、お姫様を解き放つキスだった。
「んっ……」
「あむっ……ん………」
二度目からは、ゆっくりと。お互いを感じ合うためのキス。
「ん…ぷはっ……あ…ねぇ、○○、もっと…もっとして……」
「うん、俺もしたい。ちゅ…ん…」
「うん…んぐ…ちゅっ……」
「んむ……むぁ……」
「はぁっ……んっ……ちゅろっ…」
「んぅっ!? …ん、ん。じゅろっ…………」
……………
………
…
長い間、ずっとそうして二人でお互いを、そして幸せを感じあっていた。
「あ~あ。咲夜さぁん、見事に○○さんパチュリー様に取られちゃいました」
「奥手なパチュリー様を焚き付けて本音を引き出すきっかけを作る、かぁ。
何て言うのかしらこれ? 雨降って縁固まる、だったかしら」
くっくっ、と喉の奥で笑うと、まさに小悪魔、と呟いて二つ手を叩くメイド長。
円卓に置いた水晶で成り行きを見守っていた二人は、軽口をたたき合って紅茶のカップを一つ啜る。
「めでたしめでたし……と、言いたいところだけど」
「はい?」
「冗談っぽく言ってるけど。あなたも、結構本気で○○のこと好きだったんじゃないの?」
心の奥を見透かそうとするようなメイドの視線を受けて、もう一口、小悪魔は紅茶を口にして言った。
「咲夜さんは…レミリア様の幸せとご自分の幸せと、どちらを選ばれますか?」
「両方。私がお嬢様を幸せにして差し上げれば良いのですわ」
「こぁぁー、残念。その手がありましたねぇ」
「あなたぜんっぜん残念そうじゃないわね。むしろ幸せそう」
あついわぁ、と半分苦笑の半分あきれ顔になって手をぱたぱたと泳がせる。
きっともうすぐ二人で帰ってくるだろう。
今日も、そしてこれからも。笑顔で二人を「おかえりなさい」と迎える権利は自分にしかないのだと考えると、
小悪魔はとろけるような幸福感に満たされるのだった。
パチュリーGoodエンド01
(お読み頂きありがとうございました。もし“別の物語”も読んでやろうという方は花映塚MatchLunaで3分間粘って下さい)
4スレ目 >>948(うpろだ >>0050)