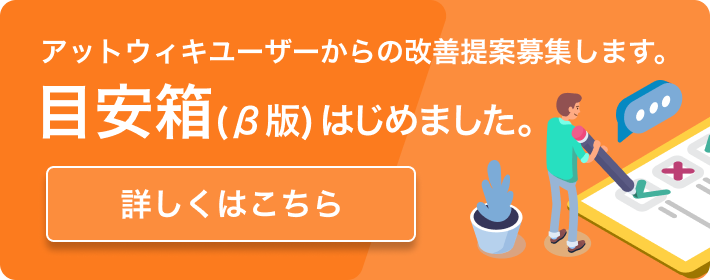■フランドール5
私がこの図書館に寄生するようになって何年が経っただろう。いや、実の所一年も経っていないかもしれない。
村から気違いと蔑まれ、人里を追われ、人間よりもむしろ妖怪相手のほうが何かと面白く会話が出来る事に気づき、湖を渡り、私はこの館に辿り着いた。
今は家事手伝いの十六夜が運んでくる僅かな食事を口にしながら、この愛すべきヴアル魔法図書館の書物たちを少しずつ読み続ける日々が続いている。
ぱたり、と、私は手元の書物を閉じた。
一冊の読書を終えた私の頭に残るのは、ひとつの疑問。心理学的に言えば好奇心とも言うだろうか。
今まで読んだ事のないジャンル「恋愛小説」。その中のいわゆる「愛」の記述の中に、私は少し気になる表現を見つけた。
その表現について尋ねる為、私は親友パチュリー・ノーレッジの姿を探して広い図書館の中を早足で移動する。
お互い口という器官をあまり必要としない性質の生物のため、いざ聞きたい事があると不便だ。
と、そこで私は本棚の影に、見慣れた赤い翼を見つけた。
「小悪魔」
「ひゃわっ!?…あ、○○さんですか。驚かせないでくださいよ~…」
図書館整備担当要因小悪魔。この図書館ではノーレッジに次ぐ知恵者であり、蔵書の位置にも詳しい。
まだ私が来て間もない頃から何かと世話を焼いてくれている。本人曰く、「○○さんはフラフラしてて危なっかしいですから、いつだって目が離せませんよ」だそうだ。
ありがたい事だが、読書中に後ろからじーっと私の事を見つめているのはどうかと思う。以前そのことを指摘すると「きっ…気づいてたんですか!?」と言って赤面とともに逃げた。
私は今自分が抱えている疑問を、彼女にぶつけてみる事にした。
「なあ小悪魔。…キスとはどういう味がするんだ?」
「へ…え?え、え、えええええええええええええっ!?」
そう。私が感じていた疑問はそれ「キスとはどういう味がするのか」というものである。
書物曰く行為の対象の味がするとあったが、どうも小説の類は表現がうやむやな事があって困る。
それだからノーレッジにでも聞けば分かり易く説明してくれるのかと思いやってきた訳だが──
「…小悪魔、風邪か?顔が赤い──「あああああああああ貴方って人は!もう!なんてこと言い出すんですかっ!バカ!バカ!罪な人っ!」
発言を遮られた上に、赤面されたまま力無く胸のあたりを殴られた。
「…キスとは、何かマズいことだったのか?」
「う…えーっと、いや、その…悪くは…ない、です…で、でも、それには順序ってものが…あう…でも…いい…のかな?」
小悪魔が何か慌てた風にしどろもどろになってしまっていたその時───
「そこまでよ、小悪魔」
「おお、来たかノーレッジ」
「パチュリー様!?」
動かない大図書館パチュリー・ノーレッジが宙にいた。
彼女は私と小悪魔の間に割り込むようにふわりと着地し、小悪魔に向き直った
「こぁ、今から私は○○ととても大事な話があるから、貴方は外で門番でもしてなさい、そう、朝まで」
「いっ…嫌です嫌です嫌です!朝までって○○さんに何する気ですかパチュリー様───!?」
彼女は小さく自分のスペルカード名を呟き、色鮮やかな弾幕とともに赤い翼の彼女を屋根の外へと放りだした。
「…スペルカードを使うほどか?」
「ええ。あの子がいると何かと進みにくいから」
そういうと彼女は私に向き直り、薄紫の髪をなびかせた。
彼女こそ私の親友にして屈指の知識人、パチュリー・ノーレッジ。
この図書館の主であり、館の主人レミリア・スカーレットの古き友人でもあるらしい。彼女の知識の深さは私も一目置いている。
…そういえば一度、彼女に「知識を求めるその姿勢は結構だけど、もう少し貴方は他者からの好意に敏感になってもいいんじゃないかしら」
と、唐突に言われた事があった。そりゃ私がここで本を読むために生きているような生活が出来るのも、全て人からのご好意で成り立っておるわけであり、その事に対しての感謝は十分してるはずなのだが。
そう彼女に言うと、「…………そういう所が鈍感だって言うのよ」と言われた。
どうやら、私には彼女にしか見えない欠点があるらしい。
彼女はさて、と前置きして切り出した。
「キスの味が知りたいそうね、○○?」
「話が早くて助かる」
「ここで私が貴方にその行為の味を口頭で説明するのは簡単。けれどそれでは貴方に100%伝わるという保証がない。
五感によって感じられる事を言葉で相手に伝えるのはとても難しい事。…つまり百聞は一見にしかずね」
そこではた、とノーレッジの口が止まる。少し溜めたあと、彼女はゆっくり続けた。
「そこで───私は、実際に私とキスをしてみることを提案するわ」
酒でも飲んでいたのか、彼女の顔はほんのり赤い。
酩酊でもそんな良案が出るとは流石だな、と口の中で呟き、私はその案を肯定した。
「良案だな」
「…決まりね」
私の前に手を差し出すノーレッジ。身長を合わせろと言う事だろう。
私はその場で膝立ちになる。交錯する視線。そして彼女は私の頬に両手を添え、そのまま自分の唇に────
触れる直前、カツンという硬い金属音が静かな図書館にどこからか響く。
何かと思い首を上げると、そこには銀色のワゴンを携えた家事手伝いの主──メイド長だったか──十六夜咲夜が立っていた。
「…紅茶をお持ちしました」
十六夜咲夜。私が最もご好意に甘えさせていただいてる人物は彼女であろう。
人間である私が死なない程度の食を用意し、定時になるとどこからともなく現れては美味な食事を振舞ってくれる。
……しかし、紅茶(嗜好品)を持ってくるとは珍しい。それほどキリの良い時間でもないというのに。
と、そこで私はこういうことが以前にもあったなと思い起こす。
あれは──そう、いつだったか、ふとした事から私がノーレッジの読もうとしていた本を取ってやろうとして転落し、誤ってノーレッジを押し倒した際に一度。
それと私が椅子の上で本を読みながらうっかり寝てしまった時。彼女の声で目を覚ました時、小悪魔が何故か顔をぎりぎりまで接近させていたのが印象的だった。
どこか緊張したような彼女の声に、私はすまないなと言ってワゴンの上のカップを取る。
「待ちなさい、○○」
紅茶を飲むためカップに口をつけようとした私を、ノーレッジが呼び止めた。
「実験がまだ途中よ。すぐに終わるから、こっちが済んでからにしたら?」
ああ、それもそうかと言って私は再び膝をつく。
「すまないが十六夜、紅茶は後で頂くよ」
再び、ノーレッジが頬に手をかける。そして顔を素早く近づけ、私の口に────
瞬間、世界が変わる。
仄暗い図書館から、赤い絨毯に蝋燭の燭台が並べられた図書館前の廊下へと。
私は手早く状況を理解するよう、あたりをキョロキョロと見回す。
目の前にノーレッジの姿が無く、十六夜咲夜が立っていた。
私は辺りの情報を整理し、結論を見つける。
「…つまり、時を止めて連れてきたと言う事か?」
「お早いご理解、助かりますわ」
彼女は美しいという表現ができる笑みを浮かべ、ぺこりと一礼した
私は彼女に対し不満げに口を尖らせ、抗議の意を表する。
「私は実験中だったのだが?」
「ええ。ですから、私はあなたをここに呼んだのです」
少しばかりの疑問符が頭に浮かぶ。私は十六夜に、詳しい説明を求めた。
「説明してくれないか?」
「ええ。…私のこのことが大変な失礼な事であるというのは承知の上。
しかしキスという行為は、そもそも男女間の深い愛情を表すもの。○○さんほどの方ならば、実験とはいえそういう行為をしてしまうのですから───
相手も、それなりの方が必要かと存じまして」
「…つまりノーレッジでは役不足であり、見ていられなくなったから連れ出したと?」
「概ね、そのように解釈して構いませんわ」
成程、と私は筋の通った理屈に頷く。しかしその説明では疑問が残る。
「…では、私が実験するに相応しい相手とは誰か?」
「それは…勿論」
ぽん、と自分の胸を叩く十六夜。
「不肖、紅魔館メイド長十六夜咲夜。これより○○さんのお相手を勤めさせていただきたく存じます」
「…………?」
私はやたらと硬い彼女の口振りに少し疑問を覚える。
これではまるで、嫁入り前の娘ではないだろうか。
「……十六夜、嫁入りの練習か?」
その口調がおかしく、私は柄にもなく冗談を口にした。
彼女はそれに答えるように、無言でただにっこりと微笑んでいた。
やがて会話が途切れ、十六夜は胸に手を当てて二、三度深呼吸を始める。瞳を閉じて、唇を私のほうへ突き出した。
こちらから、という事らしい。私は先ほどノーレッジがそうしたように頬に手を当て、顔を近づけ────
「おっ兄っ様────────っ!!」
廊下右奥より、光の勢いで何かが迫り来る。
それは以上の言葉を述べつつ十六夜を跳ね飛ばし、私の前でぴたりと停止した。
「何か」の正体を確認すればそれは悪魔の妹フランドール・スカーレット嬢。
地下牢に幽閉されし囚われのイカレ姫君だ。
彼女との出会いは非常に衝撃的であった。あくる日、地のそこまで響く轟音と共に私の目の前の床をブチ抜いて現れたのである。
私は突如現れた彼女に押し倒されてそのまま殺されそうになったが、
その時の私は生命の危機よりも読みかけの本を壊された事に腹を立て、その場で彼女の頬を思いっきり張ったのだ。
そのまま小一時間ほど説教を食らわし、今では私の妹のような存在となっている。
彼女は跳ね飛ばした十六夜に蹴りを入れて紅魔館外まで吹っ飛ばすと、私に向き直り幼子特有の太陽のような笑みを見せた。
「ね、お兄様何してるの?お散歩?」
そのまま彼女は私に抱きつき、胸板に顔を埋めた。返答を必要としない自己中心的な会話は、実に彼女らしいと言わざるを得ない。
度重なる出来事の連続で忘れかけていたが、私はそこでふとキスの味についての実験を思い出す。
十六夜も戻ってきそうにないし、いっそ彼女に頼むかと私は考えた。
「…フラン、キスしていいか?」
実験だのなんだの言わない方がより早く実行できるのではないか、と私は考えた。
「ん……え?キス?うん!しよしよ!」
それからの彼女の行動は早いものだった。
埋めていた顔をすぐに離し、私の顔の位置に持っていく。
一瞬だけ互いの視線を交差させ、その後すぐに唇を重ね合わせた。
まさに一瞬。誰から邪魔する隙もない早業だった。
「ん、ちゅ…ぷはっ」
少しして、フランは私から口を離す。
さて、肝心の味だが……正直な所、よくは分からなかった。
予想通り、濡れた唇の感触というか…やはりフィクションの表現は大袈裟だったか。
そこで私は思考を内部から外部に切り替えフランを見る。少し眠たげ(とろんとした、というのだろうか)な目をして、頬を赤く染めて蟲惑的な笑みを浮かべていた。
と、そこでふと思いつく。私はフランにも味を聞いてみる事にした。
「…フラン、キスとはどういう味がした?」
「ん…えーっとね、お兄さまの味…かな?」
えへへ、と、自分の発言が恥ずかしかったのか頬を染めて俯くフラン。やはり彼女もそういう表現をするか。
顎に手を当てしばし考える。以上の結果より導き出される結論は───
・キスとは、行為の対象の味がする
・私にそれを知覚する事はできず、フランには知覚する事ができる。
というところだろうか。後はその味を私がどのようにして知覚する事ができるようにするかの模索だが───
「……………お兄様?」
と、私がそこまで考えた所で不意にフランから声をかけられる。
…困った事に、思案してる間に彼女を置いてけ堀にしてしまっていたらしい。私の悪い癖だ。
「ね、お兄様、もう一回…しよ?」
フランは私に向けて両手を掲げた。恐らく、身長をあわせるために抱っこしろという事なのだろう。
私は両手を取ってフランを抱き上げ、もう一度口づけを交わした。
「……ん…」
相変わらず、何の味もしない。
対してフランの方はというと、口に残った味を噛み締めるように舌で舐っていた。
「……フランは、私が知らないことを知ってるんだな」
それなりに知識人になったつもりでいたが、目の前の少女にすら私の知識は劣るのである。
私は自嘲気味に、羨望の意も込めて彼女にそう言った。
彼女は私に三度目の口づけを交わし、やがて笑顔で言った。
「ん…うん。だから今度は…私がお兄様の知らない事、たーっくさん教えてあげるねっ!」
その言葉を聞いて、私の顔にも自然と笑みが漏れる。
長閑な午後の昼下がり、多くの犠牲を出して為された実験は、こうして幕を閉じた。
>>新ろだ401,402
───────────────────────────────────────────────────────────
帳簿整理も終わり、いざ就寝と言った時の事だった。
廊下から、ザックザックと言うか、ガッシャガッシャと言うか。
そんな、足音のような鈍い金属音が聞こえてきた。
確実に近づいてきているその音は、俺の部屋の前で止まったらしかった。
「○○、いるー?」
聞き慣れた声が扉から聞こえた。
「ん、フラン?」
「うん」
こんな夜更けにどうしたのだろう。
そう思ってから、吸血鬼ってば夜行性だってばよ、という事を思い出した。
まさか、遊んで欲しい、とか言われる訳ではあるまいな。
流石にそれは無いとは思うのだが、仮にもレミリアの妹である。絶対に無いとは言い切れない。
どうやって断ろう、などと考えながら、扉を開けると。
そこには、灯りを反射して光沢を放つ小さなぶたを持った、笑顔の女の子がいた。
背中の羽がぱたぱたと動いている。
「……どうした?」
「これ見て!」
ぶたを俺に差し出してきた。直後、ぶたの体内から、ガション、という豪快な音が聞こえた。
「……ぶただねぇ」
「うん、ぶたさん」
フランは相変わらず笑顔だ。何が嬉しいのだろうか。
ぶたを受け取る事にした。ズッシリとした重みが手に伝わった。
高級感溢れる重みだった。
やはり紅魔館。目の付け所が違う。そして、金の使い方が豪快だ。
そのぶたをよく観察する。
背中に、縦に短く横に長い小さな長方形の穴が開いていた。
「あ、貯金箱か」
「……何だと思ってたの?」
「いや……その……」
よもや、高い骨董品。等とは口が裂けても言えない。
今思えば、動かしたときに内部で音がなる骨董品なんて聞いたこともない。
どうやら、目の付け所が違ったのは俺だったようだ。
廊下で立ち話も何なので、フランを部屋に入れる事にした。
現在、テーブルを挟んで座っている。
そして、そのテーブルの中心に鎮座しておられるのがぶたの貯金箱。
そのつぶらな瞳は、付き合いの長いフランをじっと見つめている。
……いや、まぁ俺が向けたんだけど。
「それで……これがどうした?」
「お金、もう入らない」
フランが硬貨を取り出して、ぶたの体内へ続く唯一の穴に差し込む。
しかし、カチッという金属がぶつかるような音がして、これ以上進まない。
フランが手を離すと、硬貨は半分も入らずに止まっている。
「凄いなぁ、ここまで溜め込んだの初めて見たかも」
「!! でしょ、でしょ!」
俺が言うと、ようやく笑顔が引っ込めたはずのフランが目を輝かせた。
羽の動きがせわしない。
何だ? 何でスイッチが入ったんだ?
「いや、確かに凄いけど……もしかして新しい貯金箱が欲しいのか?」
「ううん、違うよ」
「違うの?」
じゃあ、一体何なんだ。れみりあうー☆って何なんだ。
真意が全く読めない俺に、フランの顔は少しずつむくれていく。
「○○、シラを切ってるの?」
「何でそうなる!?」
「だって、さっきから何も知らないって顔してる」
さっきの笑顔はどこへやら。
明らかな不機嫌顔になってしまった。
確かにここの会計管理を任されている俺が、フランが貯金をしていた事を知らなかった事には非がある。
ただ、フランのそれはどことなく違った。
「いや、実際に何も知らないんだ。フランが貯金箱で金を貯めてた事なんて、さっき初めて知ったんだぞ」
「……ほんとに?」
確かに悪いのは俺だ。そう、俺なんだ。
なのに、どうしてそんなに泣きそうな顔をするんだ?
「もし良かったら、教えてくれないか。別に教えちゃいけないってルールは無いだろ?」
俺の言葉に、俯いたフランがこくんと頷いた。
そして、顔を腕でゴシゴシと拭いながら、言った。
「この貯金箱、一杯にしたら、○○が、喜ぶから、お礼にずっと一緒にいてくれるって」
「俺が?」
「ううん、パチュリーが」
「パチュリーかよっ!?」
何言ってるんだよあの人。
っていうか、当事者無視で勝手に話決めるなよ。
「でも、知らなかったんでしょ?」
「あぁ、全く」
「……そうだよね」
やり取りを静観していたぶたを胸に抱いて、フランは椅子から立ち上がった。
「フラン?」
「お部屋に帰る」
「…………」
「だって、○○知らなかったんだもん。無理に言っちゃ、悪いもん」
あぁ、くそ。反則だろ。
そんな事泣きながら言われて、帰せるかよ。
「良いよ」
「……え?」
「流石に俺も忙しいからずっと、って訳にはいかないが」
「……ほんとに?」
さっきと同じ言葉だ。
しかし、その顔には悲しみは無く、驚きと喜びで満ちていた。
「暇があればフランに会いに行くよ。逆に、暇だったらフランからこっちに来ても良い」
「でも、お仕事が……」
「その時ぐらい、静かにしてくれるだろ?」
「うん……うんっ!」
満面の笑みのフランが飛び込んできた。
ぶたを、放り投げて。
「ちょ、ぶたぁぁぁぁぁぁぁぁ!」
ぶたは、豪快な音を立てて中身をぶちまけた。
俺は、フランに飛び込まれて床に倒れこんだ。
部屋は、凄惨な状態になった。
現在、俺は床にぶちまけられた金を集めていた。
背中には、幸せそうなフラン。
「で、この処理に困る金、どうするの?」
「○○にあげる」
「いや、こんな小銭だらけ、貰っても困るんだけど……」
「でも、お金使わないから」
「……そっか。そう言えばフランは外出ないもんな。なら、ありがたく貰っておくよ」
「これで○○を買ったと思えば良いんだもんね」
「人身売買は犯罪です……」
「えへへ、ずっと一緒にいてね!」
「だから、ずっとは無理だって」
「じゃあ、いっぱい一緒にいてね!」
「うん、まぁ、それなら良いかな?」
今までよりも、もっと忙しくなりそうだった。
>>新ろだ441
───────────────────────────────────────────────────────────
私がこの図書館に寄生するようになって何年が経っただろう。いや、実の所一年も経っていないかもしれない。
村から気違いと蔑まれ、人里を追われ、人間よりもむしろ妖怪相手のほうが何かと面白く会話が出来る事に気づき、湖を渡り、私はこの館に辿り着いた。
今は家事手伝いの十六夜が運んでくる僅かな食事を口にしながら、この愛すべきヴアル魔法図書館の書物たちを少しずつ読み続ける日々が続いている。
ぱたり、と、私は手元の書物を閉じた。
一冊の読書を終えた私の頭に残るのは、ひとつの疑問。心理学的に言えば好奇心とも言うだろうか。
今まで読んだ事のないジャンル「恋愛小説」。その中のいわゆる「愛」の記述の中に、私は少し気になる表現を見つけた。
その表現について尋ねる為、私は親友パチュリー・ノーレッジの姿を探して広い図書館の中を早足で移動する。
お互い口という器官をあまり必要としない性質の生物のため、いざ聞きたい事があると不便だ。
と、そこで私は本棚の影に、見慣れた赤い翼を見つけた。
「小悪魔」
「ひゃわっ!?…あ、○○さんですか。驚かせないでくださいよ~…」
図書館整備担当要因小悪魔。この図書館ではノーレッジに次ぐ知恵者であり、蔵書の位置にも詳しい。
まだ私が来て間もない頃から何かと世話を焼いてくれている。本人曰く、「○○さんはフラフラしてて危なっかしいですから、いつだって目が離せませんよ」だそうだ。
ありがたい事だが、読書中に後ろからじーっと私の事を見つめているのはどうかと思う。以前そのことを指摘すると「きっ…気づいてたんですか!?」と言って赤面とともに逃げた。
私は今自分が抱えている疑問を、彼女にぶつけてみる事にした。
「なあ小悪魔。…キスとはどういう味がするんだ?」
「へ…え?え、え、えええええええええええええっ!?」
そう。私が感じていた疑問はそれ「キスとはどういう味がするのか」というものである。
書物曰く行為の対象の味がするとあったが、どうも小説の類は表現がうやむやな事があって困る。
それだからノーレッジにでも聞けば分かり易く説明してくれるのかと思いやってきた訳だが──
「…小悪魔、風邪か?顔が赤い──「あああああああああ貴方って人は!もう!なんてこと言い出すんですかっ!バカ!バカ!罪な人っ!」
発言を遮られた上に、赤面されたまま力無く胸のあたりを殴られた。
「…キスとは、何かマズいことだったのか?」
「う…えーっと、いや、その…悪くは…ない、です…で、でも、それには順序ってものが…あう…でも…いい…のかな?」
小悪魔が何か慌てた風にしどろもどろになってしまっていたその時───
「そこまでよ、小悪魔」
「おお、来たかノーレッジ」
「パチュリー様!?」
動かない大図書館パチュリー・ノーレッジが宙にいた。
彼女は私と小悪魔の間に割り込むようにふわりと着地し、小悪魔に向き直った
「こぁ、今から私は○○ととても大事な話があるから、貴方は外で門番でもしてなさい、そう、朝まで」
「いっ…嫌です嫌です嫌です!朝までって○○さんに何する気ですかパチュリー様───!?」
彼女は小さく自分のスペルカード名を呟き、色鮮やかな弾幕とともに赤い翼の彼女を屋根の外へと放りだした。
「…スペルカードを使うほどか?」
「ええ。あの子がいると何かと進みにくいから」
そういうと彼女は私に向き直り、薄紫の髪をなびかせた。
彼女こそ私の親友にして屈指の知識人、パチュリー・ノーレッジ。
この図書館の主であり、館の主人レミリア・スカーレットの古き友人でもあるらしい。彼女の知識の深さは私も一目置いている。
…そういえば一度、彼女に「知識を求めるその姿勢は結構だけど、もう少し貴方は他者からの好意に敏感になってもいいんじゃないかしら」
と、唐突に言われた事があった。そりゃ私がここで本を読むために生きているような生活が出来るのも、全て人からのご好意で成り立っておるわけであり、その事に対しての感謝は十分してるはずなのだが。
そう彼女に言うと、「…………そういう所が鈍感だって言うのよ」と言われた。
どうやら、私には彼女にしか見えない欠点があるらしい。
彼女はさて、と前置きして切り出した。
「キスの味が知りたいそうね、○○?」
「話が早くて助かる」
「ここで私が貴方にその行為の味を口頭で説明するのは簡単。けれどそれでは貴方に100%伝わるという保証がない。
五感によって感じられる事を言葉で相手に伝えるのはとても難しい事。…つまり百聞は一見にしかずね」
そこではた、とノーレッジの口が止まる。少し溜めたあと、彼女はゆっくり続けた。
「そこで───私は、実際に私とキスをしてみることを提案するわ」
酒でも飲んでいたのか、彼女の顔はほんのり赤い。
酩酊でもそんな良案が出るとは流石だな、と口の中で呟き、私はその案を肯定した。
「良案だな」
「…決まりね」
私の前に手を差し出すノーレッジ。身長を合わせろと言う事だろう。
私はその場で膝立ちになる。交錯する視線。そして彼女は私の頬に両手を添え、そのまま自分の唇に────
触れる直前、カツンという硬い金属音が静かな図書館にどこからか響く。
何かと思い首を上げると、そこには銀色のワゴンを携えた家事手伝いの主──メイド長だったか──十六夜咲夜が立っていた。
「…紅茶をお持ちしました」
十六夜咲夜。私が最もご好意に甘えさせていただいてる人物は彼女であろう。
人間である私が死なない程度の食を用意し、定時になるとどこからともなく現れては美味な食事を振舞ってくれる。
……しかし、紅茶(嗜好品)を持ってくるとは珍しい。それほどキリの良い時間でもないというのに。
と、そこで私はこういうことが以前にもあったなと思い起こす。
あれは──そう、いつだったか、ふとした事から私がノーレッジの読もうとしていた本を取ってやろうとして転落し、誤ってノーレッジを押し倒した際に一度。
それと私が椅子の上で本を読みながらうっかり寝てしまった時。彼女の声で目を覚ました時、小悪魔が何故か顔をぎりぎりまで接近させていたのが印象的だった。
どこか緊張したような彼女の声に、私はすまないなと言ってワゴンの上のカップを取る。
「待ちなさい、○○」
紅茶を飲むためカップに口をつけようとした私を、ノーレッジが呼び止めた。
「実験がまだ途中よ。すぐに終わるから、こっちが済んでからにしたら?」
ああ、それもそうかと言って私は再び膝をつく。
「すまないが十六夜、紅茶は後で頂くよ」
再び、ノーレッジが頬に手をかける。そして顔を素早く近づけ、私の口に────
瞬間、世界が変わる。
仄暗い図書館から、赤い絨毯に蝋燭の燭台が並べられた図書館前の廊下へと。
私は手早く状況を理解するよう、あたりをキョロキョロと見回す。
目の前にノーレッジの姿が無く、十六夜咲夜が立っていた。
私は辺りの情報を整理し、結論を見つける。
「…つまり、時を止めて連れてきたと言う事か?」
「お早いご理解、助かりますわ」
彼女は美しいという表現ができる笑みを浮かべ、ぺこりと一礼した
私は彼女に対し不満げに口を尖らせ、抗議の意を表する。
「私は実験中だったのだが?」
「ええ。ですから、私はあなたをここに呼んだのです」
少しばかりの疑問符が頭に浮かぶ。私は十六夜に、詳しい説明を求めた。
「説明してくれないか?」
「ええ。…私のこのことが大変な失礼な事であるというのは承知の上。
しかしキスという行為は、そもそも男女間の深い愛情を表すもの。○○さんほどの方ならば、実験とはいえそういう行為をしてしまうのですから───
相手も、それなりの方が必要かと存じまして」
「…つまりノーレッジでは役不足であり、見ていられなくなったから連れ出したと?」
「概ね、そのように解釈して構いませんわ」
成程、と私は筋の通った理屈に頷く。しかしその説明では疑問が残る。
「…では、私が実験するに相応しい相手とは誰か?」
「それは…勿論」
ぽん、と自分の胸を叩く十六夜。
「不肖、紅魔館メイド長十六夜咲夜。これより○○さんのお相手を勤めさせていただきたく存じます」
「…………?」
私はやたらと硬い彼女の口振りに少し疑問を覚える。
これではまるで、嫁入り前の娘ではないだろうか。
「……十六夜、嫁入りの練習か?」
その口調がおかしく、私は柄にもなく冗談を口にした。
彼女はそれに答えるように、無言でただにっこりと微笑んでいた。
やがて会話が途切れ、十六夜は胸に手を当てて二、三度深呼吸を始める。瞳を閉じて、唇を私のほうへ突き出した。
こちらから、という事らしい。私は先ほどノーレッジがそうしたように頬に手を当て、顔を近づけ────
「おっ兄っ様────────っ!!」
廊下右奥より、光の勢いで何かが迫り来る。
それは以上の言葉を述べつつ十六夜を跳ね飛ばし、私の前でぴたりと停止した。
「何か」の正体を確認すればそれは悪魔の妹フランドール・スカーレット嬢。
地下牢に幽閉されし囚われのイカレ姫君だ。
彼女との出会いは非常に衝撃的であった。あくる日、地のそこまで響く轟音と共に私の目の前の床をブチ抜いて現れたのである。
私は突如現れた彼女に押し倒されてそのまま殺されそうになったが、
その時の私は生命の危機よりも読みかけの本を壊された事に腹を立て、その場で彼女の頬を思いっきり張ったのだ。
そのまま小一時間ほど説教を食らわし、今では私の妹のような存在となっている。
彼女は跳ね飛ばした十六夜に蹴りを入れて紅魔館外まで吹っ飛ばすと、私に向き直り幼子特有の太陽のような笑みを見せた。
「ね、お兄様何してるの?お散歩?」
そのまま彼女は私に抱きつき、胸板に顔を埋めた。返答を必要としない自己中心的な会話は、実に彼女らしいと言わざるを得ない。
度重なる出来事の連続で忘れかけていたが、私はそこでふとキスの味についての実験を思い出す。
十六夜も戻ってきそうにないし、いっそ彼女に頼むかと私は考えた。
「…フラン、キスしていいか?」
実験だのなんだの言わない方がより早く実行できるのではないか、と私は考えた。
「ん……え?キス?うん!しよしよ!」
それからの彼女の行動は早いものだった。
埋めていた顔をすぐに離し、私の顔の位置に持っていく。
一瞬だけ互いの視線を交差させ、その後すぐに唇を重ね合わせた。
まさに一瞬。誰から邪魔する隙もない早業だった。
「ん、ちゅ…ぷはっ」
少しして、フランは私から口を離す。
さて、肝心の味だが……正直な所、よくは分からなかった。
予想通り、濡れた唇の感触というか…やはりフィクションの表現は大袈裟だったか。
そこで私は思考を内部から外部に切り替えフランを見る。少し眠たげ(とろんとした、というのだろうか)な目をして、頬を赤く染めて蟲惑的な笑みを浮かべていた。
と、そこでふと思いつく。私はフランにも味を聞いてみる事にした。
「…フラン、キスとはどういう味がした?」
「ん…えーっとね、お兄さまの味…かな?」
えへへ、と、自分の発言が恥ずかしかったのか頬を染めて俯くフラン。やはり彼女もそういう表現をするか。
顎に手を当てしばし考える。以上の結果より導き出される結論は───
・キスとは、行為の対象の味がする
・私にそれを知覚する事はできず、フランには知覚する事ができる。
というところだろうか。後はその味を私がどのようにして知覚する事ができるようにするかの模索だが───
「……………お兄様?」
と、私がそこまで考えた所で不意にフランから声をかけられる。
…困った事に、思案してる間に彼女を置いてけ堀にしてしまっていたらしい。私の悪い癖だ。
「ね、お兄様、もう一回…しよ?」
フランは私に向けて両手を掲げた。恐らく、身長をあわせるために抱っこしろという事なのだろう。
私は両手を取ってフランを抱き上げ、もう一度口づけを交わした。
「……ん…」
相変わらず、何の味もしない。
対してフランの方はというと、口に残った味を噛み締めるように舌で舐っていた。
「……フランは、私が知らないことを知ってるんだな」
それなりに知識人になったつもりでいたが、目の前の少女にすら私の知識は劣るのである。
私は自嘲気味に、羨望の意も込めて彼女にそう言った。
彼女は私に三度目の口づけを交わし、やがて笑顔で言った。
「ん…うん。だから今度は…私がお兄様の知らない事、たーっくさん教えてあげるねっ!」
その言葉を聞いて、私の顔にも自然と笑みが漏れる。
長閑な午後の昼下がり、多くの犠牲を出して為された実験は、こうして幕を閉じた。
>>新ろだ401,402
───────────────────────────────────────────────────────────
帳簿整理も終わり、いざ就寝と言った時の事だった。
廊下から、ザックザックと言うか、ガッシャガッシャと言うか。
そんな、足音のような鈍い金属音が聞こえてきた。
確実に近づいてきているその音は、俺の部屋の前で止まったらしかった。
「○○、いるー?」
聞き慣れた声が扉から聞こえた。
「ん、フラン?」
「うん」
こんな夜更けにどうしたのだろう。
そう思ってから、吸血鬼ってば夜行性だってばよ、という事を思い出した。
まさか、遊んで欲しい、とか言われる訳ではあるまいな。
流石にそれは無いとは思うのだが、仮にもレミリアの妹である。絶対に無いとは言い切れない。
どうやって断ろう、などと考えながら、扉を開けると。
そこには、灯りを反射して光沢を放つ小さなぶたを持った、笑顔の女の子がいた。
背中の羽がぱたぱたと動いている。
「……どうした?」
「これ見て!」
ぶたを俺に差し出してきた。直後、ぶたの体内から、ガション、という豪快な音が聞こえた。
「……ぶただねぇ」
「うん、ぶたさん」
フランは相変わらず笑顔だ。何が嬉しいのだろうか。
ぶたを受け取る事にした。ズッシリとした重みが手に伝わった。
高級感溢れる重みだった。
やはり紅魔館。目の付け所が違う。そして、金の使い方が豪快だ。
そのぶたをよく観察する。
背中に、縦に短く横に長い小さな長方形の穴が開いていた。
「あ、貯金箱か」
「……何だと思ってたの?」
「いや……その……」
よもや、高い骨董品。等とは口が裂けても言えない。
今思えば、動かしたときに内部で音がなる骨董品なんて聞いたこともない。
どうやら、目の付け所が違ったのは俺だったようだ。
廊下で立ち話も何なので、フランを部屋に入れる事にした。
現在、テーブルを挟んで座っている。
そして、そのテーブルの中心に鎮座しておられるのがぶたの貯金箱。
そのつぶらな瞳は、付き合いの長いフランをじっと見つめている。
……いや、まぁ俺が向けたんだけど。
「それで……これがどうした?」
「お金、もう入らない」
フランが硬貨を取り出して、ぶたの体内へ続く唯一の穴に差し込む。
しかし、カチッという金属がぶつかるような音がして、これ以上進まない。
フランが手を離すと、硬貨は半分も入らずに止まっている。
「凄いなぁ、ここまで溜め込んだの初めて見たかも」
「!! でしょ、でしょ!」
俺が言うと、ようやく笑顔が引っ込めたはずのフランが目を輝かせた。
羽の動きがせわしない。
何だ? 何でスイッチが入ったんだ?
「いや、確かに凄いけど……もしかして新しい貯金箱が欲しいのか?」
「ううん、違うよ」
「違うの?」
じゃあ、一体何なんだ。れみりあうー☆って何なんだ。
真意が全く読めない俺に、フランの顔は少しずつむくれていく。
「○○、シラを切ってるの?」
「何でそうなる!?」
「だって、さっきから何も知らないって顔してる」
さっきの笑顔はどこへやら。
明らかな不機嫌顔になってしまった。
確かにここの会計管理を任されている俺が、フランが貯金をしていた事を知らなかった事には非がある。
ただ、フランのそれはどことなく違った。
「いや、実際に何も知らないんだ。フランが貯金箱で金を貯めてた事なんて、さっき初めて知ったんだぞ」
「……ほんとに?」
確かに悪いのは俺だ。そう、俺なんだ。
なのに、どうしてそんなに泣きそうな顔をするんだ?
「もし良かったら、教えてくれないか。別に教えちゃいけないってルールは無いだろ?」
俺の言葉に、俯いたフランがこくんと頷いた。
そして、顔を腕でゴシゴシと拭いながら、言った。
「この貯金箱、一杯にしたら、○○が、喜ぶから、お礼にずっと一緒にいてくれるって」
「俺が?」
「ううん、パチュリーが」
「パチュリーかよっ!?」
何言ってるんだよあの人。
っていうか、当事者無視で勝手に話決めるなよ。
「でも、知らなかったんでしょ?」
「あぁ、全く」
「……そうだよね」
やり取りを静観していたぶたを胸に抱いて、フランは椅子から立ち上がった。
「フラン?」
「お部屋に帰る」
「…………」
「だって、○○知らなかったんだもん。無理に言っちゃ、悪いもん」
あぁ、くそ。反則だろ。
そんな事泣きながら言われて、帰せるかよ。
「良いよ」
「……え?」
「流石に俺も忙しいからずっと、って訳にはいかないが」
「……ほんとに?」
さっきと同じ言葉だ。
しかし、その顔には悲しみは無く、驚きと喜びで満ちていた。
「暇があればフランに会いに行くよ。逆に、暇だったらフランからこっちに来ても良い」
「でも、お仕事が……」
「その時ぐらい、静かにしてくれるだろ?」
「うん……うんっ!」
満面の笑みのフランが飛び込んできた。
ぶたを、放り投げて。
「ちょ、ぶたぁぁぁぁぁぁぁぁ!」
ぶたは、豪快な音を立てて中身をぶちまけた。
俺は、フランに飛び込まれて床に倒れこんだ。
部屋は、凄惨な状態になった。
現在、俺は床にぶちまけられた金を集めていた。
背中には、幸せそうなフラン。
「で、この処理に困る金、どうするの?」
「○○にあげる」
「いや、こんな小銭だらけ、貰っても困るんだけど……」
「でも、お金使わないから」
「……そっか。そう言えばフランは外出ないもんな。なら、ありがたく貰っておくよ」
「これで○○を買ったと思えば良いんだもんね」
「人身売買は犯罪です……」
「えへへ、ずっと一緒にいてね!」
「だから、ずっとは無理だって」
「じゃあ、いっぱい一緒にいてね!」
「うん、まぁ、それなら良いかな?」
今までよりも、もっと忙しくなりそうだった。
>>新ろだ441
───────────────────────────────────────────────────────────