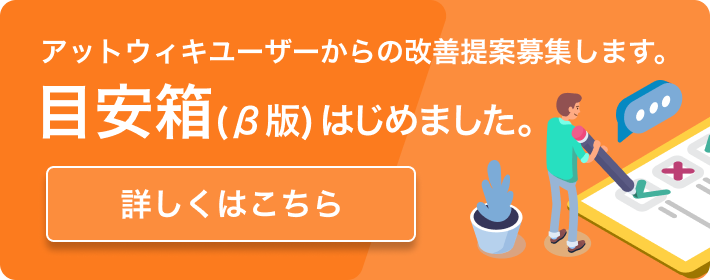プロポスレ@Wiki
阿求1
最終更新:
orz1414
-
view
世間はクリスマス。恋人達があまーい一時を過ごすファッキンな一日。
風の噂によると、紅白の巫女は恋人と質素にニャンニャン。
白黒魔砲使いは白黒魔砲使いで恋人の家に押しかけてケーキを味わいつつニャンニャン。
夜雀もニャンニャン、人形遣いもニャンニャン、閻魔もニャンニャン、妖狐もニャンニャン、兎もニャンニャンと、それはもうピンクな空気らしい。
ニャンニャン鳴くのは猫だけで良いが、その猫も好きな人と読んで字の如くニャンニャンしているのだからたまらない。
正に世は乱世。幻想郷が桃源郷になってしまうのも時間の問題である。
で、そんなピンクな行事が行われている中。自分は何をしているのかと言うと……。
「エフッ!エフッ!ゴフッ!ガハァッ!あー畜生。チーン!」
風邪を拗らせて寝込んでました。
何ですかこのイジメ。何が悲しくてこんな苦しい思いをしなきゃならないのか。
五分ほど考えて止めた。悲しくなってくる。私の名前はザ・ソロー、人の悲しみを知れ……。
まぁそんな訳で、寝たり起きたりを繰り返しながらボーっとしていた。
ドンドンドン
そうしていると、扉を叩く音がする。ちなみに呼び鈴なんて便利なものは付いていない。
ドンドンドン
「誰だよこんな時間に……ったく」
そんな事を呟きながら玄関へと向かう。
ドンドンドン
ガチャリ
「ういー、どちら様ですか、と」
「メリークリスマース!」
「だれてめぇ」
扉を開けるとそこにはおじさん?が居た。
いや、正確に表現するとだ
黄緑っぽいボディ、黄色っぽいアーム、茶色っぽいレッグ、紫っぽいヘッド。
そしてパーティ等に使う鼻眼鏡、三角帽子、片手に一升瓶、片手にコップ。
ああ駄目だ、正確に表現したら余計何なのか分からん。
「む、酷いですね。私の顔を忘れるなんて」
「……とりあえず鼻眼鏡を取ってください、話はそれからだ」
「あ」
急いで鼻眼鏡を取る目の前の人物。どうやら付けていた事をすっかり忘れていたらしい。
鼻眼鏡を取ると、おっさんではなく少女の顔が現れた。
「あぁ、誰かと思ったらあきゅさんですか」
「阿求です。何で『う』だけ省略されてるんですか」
「いやまぁ、何となくノリ……ウゲッホ!ゲホ! 失礼。それでどうかしたんですか」
「せっかく求聞史記が書き終わって打ち上げをやっていたのですが。一人ほど未参加者が居たようなので様子見です」
どうやら自分の様子を見に来てくれたらしい。
「いや、少々風邪を拗らせまして」
「あぁ、それで……。熱はどれくらいあるんですか?」
「さっき測った時は37.6度ってとこです」
「それでは安静にしていた方が良いですね」
「そう言う事です。エホッ!エホッ! それじゃ、うつすと申し訳ないので」
ガチャン
「……」
「……」
「……あの、何で一緒に入って来るのでしょうか?」
「風邪で苦しんでいる人が居るのに私だけ楽しむのも申し訳ありませんから、特別に看病しますよ」
「いやいや大丈夫ですよ、自力で治しますから」
「いやいや遠慮しなくても、美少女が看護してあげると言っているのですよ?」
「いやいやいや」
「いやいやいや」
………
……
…
そんなやり取りが続く事5分。体調不良でスタミナの切れた自分が折れる形で決着と相成った。
「そうですね、それではお粥を……」
「昼に多目に作ったので大丈夫です」
「では水枕……」
「さっき起きたついでに買えたじゃないですか」
「氷嚢……」
「水枕と併用したら駄目だったと思ったんですが」
「それなら私は何をやれば良いんですか!!」
「知るかー!!」
とまぁ、基本的にはこんな感じだったが。
結局、雑談なんかをしているうちに眠くなってきたので、眠る事にした。
夜中、ふと目が覚めた。
しかし、目を開けることができない。開けれない事も無さそうだが、とても辛い。
寝ているにも関わらず、頭がズキズキと痛む。
呼吸は自分が聞いていても分かるほどに荒くなっている。ゆっくりとした呼吸をする事ができない。
毛布等をしっかりとかけているはずなのに、恐ろしいほどに寒い。
どうやら風邪が悪化したらしい。
この状態をどう表現すれば良いのだろうか?
故郷の方言を借りるとするならば『怖い』と表現するのが一番的確だろう。
「○○さん、○○さん、どうしました?大丈夫ですか?」
阿求さんの声が聞こえてくる。
どうやら自分が寝た後も、帰らず居てくれたらしい。
しかし、その問い掛けに答える事が出来ない。
声を出す力すら風邪に奪い取らている。
不意に、首筋と額に冷たい感触がする。
「大分熱が上がってますね……。頭、上げられますか?」
軽く首を横に振ると、自分の頭が宙に浮き、水枕を引き抜かれる。
変わりに普段使う枕を入れられ、そのままゆっくりと頭が降りていく。
暫くすると「頭上げますよ」と声がかかり、先程と同じ要領で枕と水枕が取り替えられた。
そしてまた、首筋に冷たい感触。それと同時に、やっと目が開く。
目の前には、心配そうな顔をした阿求さんの顔があった。
目と鼻の先と言うほどの近さでは無いものの、それなりに近い。
自分の額に冷たい感触。阿求さんの手が自分の額に置かれたのだと把握する。
それを見て、自分は何を思ったのだろうか。動かすのも辛いはずの腕を動かして、阿求さんの頭の後ろに添える。
そのまま、力の入らない腕で阿求さんの頭をこちらに引き寄せる。
そしてそのまま、キスをした。
再び意識が朦朧とし、視界がボヤけてくる。どうやら頭と体、両方が休憩を求めているようだ。
阿求さんの顔が自分から離れていく。その表情は、嬉しそうなようでもあり、呆れているようでもあり、困っているようでもあった。
そのまま、自分の意識は無くなっていった。
6スレ目>>590
──────────────────────────────────────────────────────────────
『見なくたって、私はずっと覚えてますから』
恥ずかしそうに、小さく笑った阿求さん。
精一杯背伸びをして、穏やかに目を閉じて。
――僕が呆然としているその間に、目の前で綺麗なおかっぱの髪が揺れた。
6スレ目>>754
──────────────────────────────────────────────────────────────
迷った。道に、迷った。
何の変哲もない、ただ進むべき道を見失っただけのこと。ちょっとだけ難しく言ったが、簡単に言えば道に迷った。
オーライ、しかし慌ててはいけない。そこらへんの岩にでも腰掛けて、待っていれば、軽い足音。
「もう……○○。いい加減に帰り道くらい覚えて下さい」
な? お迎えが来るのさ。
それも、とびっきりのかわいこちゃん。
腰に手を当てて怒って見せるが、どうしても怖くは無い。それどころか、怒りで粗雑になる仕草でさえ、上品に見える。
「わりぃわりぃ、つい景色に見とれちまってな」
「その言い訳は38回目です」
「この道は迷いやすいんだ」
「それは72回目ですね」
「あ~…………、すまん」
「全く……」
大仰にため息をついて、彼女は俺に背を向ける。そして、小さな歩幅で歩き出した。
彼女は稗田阿求。一度見たものは忘れないという特殊な技能を持っている。俺が前いた世界にも、そんな人がいた。それと同じようなものか。
2年前だったか、3年前だったか。友達とハイキングに来ていた俺は、道に迷い、気がつくとここ――幻想郷にいた。妖に鬼、亡霊に魔法使い。果ては精霊や吸血鬼と、何でもござれのここは、俺が前いた世界とは隔絶されてしまっている、らしい。もう前いた世界には帰れないといわれた日には、正直泣きそうになった。そんな俺を励ましてくれて、支えてくれたのが阿求だ。
この世界、幻想郷の歴史を書き留めていると言う彼女は、俺を自分の屋敷に連れ込んで、「何か面白いお話でもしてくれませんか?」なんて言った。初めて、幻想郷に来て笑った瞬間だった。
「○○っ。早く来て下さい。帰りますよ」
「ほいほいっと」
肩を可愛らしく怒らせて歩く彼女に追いついて、並んで歩いた。もうこれで何度目だろうか。俺と彼女がこうやって一緒の帰り道を行くのは。
さて、帰ったらどんな話をしてやろうか?
◇◆◇
「それでだ、俺はこういってやったんだ。『先生、ヒーローは遅れて登場するもんです』ってな」
「その……『先生』っていうのは、○○の世界での、慧音のようなものなのですね?」
「ああ、そうだ。しかも、それぞれ教えてくれることが違うときてる。めんどくさいったらありゃしない」
「それは……仕方のない事です。私みたいなものでもないと、全部覚えるなんて不可能です」
薄ぼんやりとした灯りの中で、阿求が手を振る。燭台一つの部屋の中で、阿求は布団の中。俺はその枕元に座っていた。いつの頃からか、阿求が寝る前に、俺が外の世界であったことを話すようになっていた。初めは本当の事を話していたのだけど、いずれネタは尽きる。そこで、俺は少しだけ嘘をつくことにした。良心が痛むが、阿求のためなら仕方ない。ちょっとだけ、俺が我慢すればいいだけの事だ。
ふうむ、と阿求が息をつく。
「やはり○○の世界は興味深いですね……いつか行ってみたい」
「その内行けるさ、俺が来れたんだから、出てもいけるはずだろ」
「…………そうですね」
こういう話題になると、いつもいつも阿求は様子が違って見える。それは諦観のような、全てを見透かしたような笑みだった。人生経験というものが違っていると、やっぱり先見性も違ってくるのだろうか?
阿求が布団の中にもぐりこんだ。もう寝る、という合図だ。俺は腰を上げて、「おやすみ」と声をかけて部屋を出る。外はまん丸な月が浮かぶ、宵闇だった。虫の音が、風の音が、趣深い。そういったものは総じて――はかない。
「った! 何不吉なこと考えてんだ、俺は」
ぶるぶる頭を振った。きっと思い違いさ。俺みたいなバカの考えることなんて、大したことじゃない。馬鹿の考え休むに似たりってね。さあ、もう寝よう。明日は、部屋の掃除をしなきゃ。
◇◆◇
はたきを箪笥にかける。その上を雑巾で拭いて…と。
「だから、違いますって! 部屋の掃除は上から下へ、これが基本です」
「ああ~? いいんじゃないのか? 最終的にきれいになればいいわけだしさ、そんな細かいこと」
「どこが細かいのですか。ああもう、貸して御覧なさい。手本を見せてあげます」
そう言って、俺の手からはたきを取り上げた阿求は小鳥のように部屋の中を飛び回る。それを何となく目で追ってるうちに、ついぽろりと本音がこぼれてしまった。が、忙しく走り回る彼女には聞こえなかったようで、安心した。今の言葉が聞こえようものなら、どうなっていたことか。想像するだけで恐ろしい。
「○○っ。少しは手伝いなさ……げほっ!」
「お、おい。大丈夫か、阿求」
「だい……じょうぶ…です。えほっ!」
「全然大丈夫じゃないだろ……ほら、後は俺がやるから、休んでろ」
「申し訳ありません……。でも、きちんとするんですよ。上から下へ、基本に忠実に、いいですね?」
「わかったわかった、わかったから。早く休んでいてくれ」
半ば追い出すように障子を閉める。陰だけになった阿求はまだ、咳き込んでいる。最近、体調があんまり良くないらしい。今みたいに咳き込むだけのこともあれば、何日も部屋から出てこないこともある。本人はどうということは無い、ただの風邪だと言っているが、それが尚更嘘っぽくて、俺は心配だ。何事も無ければいいが……。
だけど、世の中そんなにうまく出来ているわけはなくて。俺が掃除を早々に切り上げて、部屋を出ると外は荒れていた。強い風が吹き付けるのに、それはうだるように熱い。どことなく、気持ち悪い。
「阿求?」
返事は無い。声の届かない所にいるのか?
「お~い、阿求?」
返事はまたも、無い。さっきよりも大きな声を出した。よもや、聞こえていないということはあるまい。どうして返事をしないんだ。少しづつ、ほんの少しづつ、嫌な想像がつのる。
「阿求! 返事をしろ、阿求!」
最早なりふりなど構ってはいられない。乱暴に障子を開いては、足音を鳴らして屋敷の中を歩き回る。早く早く、返事をしてくれ。お茶目に脅かしてくれるのでもいい。彼女がそんな事をしたことは無いけど、今だったらしてもいい。してくれれば、いい。
「阿求! あきゅ……………………阿求!」
見つけた、彼女を見つけた。今まで、夜俺と彼女が夜遅くまで話しをしていた、彼女の寝所。そこに彼女は、うつぶせに、倒れていた。慌てて、その体を抱き上げて、顔を覗き込む。だらしなく半開きになった唇に以前のような張りは無かった。目は開けている。開けているが、その視線はどこを向いているのやら、少なくとも俺を見てはいない。頬を張って、大声を張り上げても、何の反応も示さない。ただ、ただただ、その矮躯を揺らすだけであった。
その時だった。第三者の声が、座敷に這入りこんだ。
「あや~、やっぱり死んじゃったか」
「……あんた、誰だ? やっぱりってなんだよ!? あんた何か知ってるんだな? 知ってるんだろ!? 教えてくれよ、彼女に……阿求に何があったんだ!?」
「何があったって……死んだのさ。ぽっくり逝ったの。……ああ、自己紹介がまだだったね。あたいは、小野塚小町。死神さね。よろしく」
赤い髪の死神は、親しげに右手を差し出してくる。握手でもしようってのか? 生憎、そんな余裕は無い。阿求に何があったのか、そればっかりが気になる。詰め寄るように、俺は言葉も荒く死神にまくし立てた。死神は、ウンザリするように額に手を当ててから、ため息混じりに口を開いた。
「はぁ……めんどくさいなぁ。いいかい、一回しか言わないからよく聞きなよ。彼女は、稗田の女はね、長生きできないようになってるのさ。阿求は一度見たものは忘れなかったろ? その能力があるなら、尚更さ。精々、十年かそこら生きられればいいほうじゃないのかね。あんた、阿求と出会ってから何年一緒にいるんだ?」
「二三年だと思う……。詳しく覚えてないけど……。それより、なんで阿求は死ななきゃならなかったんだよ!?」
「言ったろ、『そういう風にできてる』からさ。彼女の家系は特別でね、とある縁起を書く為に生きてるって言ってもいいくらいさ。ま、彼女はいい人生歩めたんじゃないの? 最後にあんたに会えたわけだしさ」
そういう風にできている。だから、彼女は死んだ。ただ、それだけの簡単で、あまりにも明快な理由。これだけはつらつと言われると、何も反論ができなくなる。
俯いて黙りこくった俺を見て、死神はまたため息をつく。俺の頭をぽんぽんと叩いてから、「泣くんじゃないさ」と言った。
「泣くんじゃないさ。運が良ければ、転生してまた会えるからさ。ま、運が良ければの話だけどね。他に何かあるかい? あたい、こう見えても忙しいんだ。ノルマがたまっててね」
「……………………」
「はぁ、あんたまで死にそうな顔してんな。まあいいさ。それも運命さね。……よっ…と。じゃ、縁があったらまた会おうや。ま、あんたが死んだら絶対会うわけだけどね」
ふわり。そう言って死神は阿求の亡骸を担いで何処かへ飛び去ってしまった。俺は、その場から一歩も動けないで、夜が更けるまでずっとそこに立ち尽くしていた。俺自身、動かない自分を不思議に思ったほどだ。
いい加減にしろよ。自分に言い聞かせても、どうにもならなかった。ふらふらと、幽鬼の様に足を向けたのは、阿求の部屋。後ろ手に障子を閉めて、その場にへたり込む。燭台に火も灯さない。独りごちるように俺は口を開いた。今の今まで自覚しなかった、いや、自覚はしていた。だけど気恥ずかしくていえなかった言葉を、吐き出すように、言った。
「なあ、阿求。ひとつ話をしてやる。お前が憧れた世界から来た、一人の男の話さ。その男は幻想郷に来て、絶望した。男が知ってるものは何も無い。どこを向いても、知らないものばっかりで、怖いものばっかりで、毎日膝を抱えてがたがた震えるばっかりだった。そこへお前が来てくれたんだったな、阿求。俺は狂喜したさ。俺のことを分かってくれる人がいたってな。お前は俺の話を楽しそうに聞いてくれたっけか。あれ、実はほとんど作り話だったんだぜ? 笑っちゃうだろ。それで、その男はな、今、お前を失って初めて気づいたのさ。俺は――お前が好きだ……ってな」
一筋、涙がこぼれた。それだけ、一筋だけ流れた。それ以上は、流れない。俺が、流れさせない。死神は、転生すればまた会えるといった。なら、俺は待つだけだ。いつか、阿求にまた会える日を。その時ばっかりは、絶対に言おう。
「大好き」
この言葉を送ろう。忘れられない少女に、この言葉を。
◇◆◇
文々。新聞より転載。
『九代目阿礼乙女 稗田阿求の手記より一枚の紙が発見される。
それには、彼女が同居していたと思われる男性、○○氏への言葉がつづられていた。内容を明かすことはしないが、阿求氏は○○に対し何らかの好意的な感情を抱いていたと思われる。
○○氏は、阿求氏が亡くなる数年前から彼女と同居を始め、そこで何らかの感情が芽生えていったと思われる。手記に寄れば、彼は博霊大結界の外から来た人間らしい。一緒に道を歩いている姿が、幾度となく見られていた。
なお、○○氏は阿求氏が亡くなった数年後に、死亡が確認されている。発見場所は阿求氏の邸宅。阿求氏の転生を待っていたと見られる。阿礼乙女の転生には百年近くかかると、知らなかったのであろうか?
文責:射命丸 文』
(了)
7スレ目>>289
──────────────────────────────────────────────────────────────
「今日も結構冷えるなあ」
夜半、布団に入って一人言ちる。
もう7月半ばだというのに梅雨も明けず、熱帯夜も少ないことになっている。
薄手の寝巻きと毛布、タオルケット一枚ずつでは、正直少々肌寒い気温である。
「まあいいや。寝よう」
毛布を体に巻きつけ、枕に頭を乗せる。
目を閉じて二息した辺りで障子戸の外からずるずると、
何かを引きずるような音がするのに気づいた。
何の音かと訝しんでいると、ゆっくりと障子を引き開け、毛布を大事そうに抱えた阿求が顔を出す。
声を掛けようかとも思ったが、面倒なので右目だけ明けて様子を見ておく。
すると阿求はこちらを観察するようにじっと見つめ、やおら決心したようにまた動き出す。
障子を閉め、引きずる毛布でつんのめりそうになりながら近寄ってきた。
足元まで寄ってきたら、持っていた毛布を大きく広げ、俺の上に掛ける。
毛布持ってきてくれたのか、と思っていると阿求はそのまま出て行かず、
俺の背後に回り、布団の中に入り込んできた。
頭をぴったりと首裏に付け、左腕を脇から腹に回してくる。
こそばゆいのを堪えてそのままでいると、更に体を寄せて密着してくる。
そのまま幾らかの時間が経ってから、寝返りを打つふりをして阿求の方に向き直った。
両目を明けて阿求の顔を見ると、随分安心したような表情で目を閉じている。
とりあえず枕の端に申し訳程度に乗せている程度だった頭を、深い位置に乗せかえてやり、
頭を2,3度撫でたところで阿求も目を開けた。
「起きて……いたんです、か」
「いや、こっちこそ起こしたか?」
「いえ、私は先刻からずっと……」
どうにも両方起きていたらしい。
「起きていたんなら、目を開けてればいいのに」
まあ、人のことは言えない訳だが。
「え……それは、そのですね……」
「? どしたの?」
「あなたの……匂いをちょっと、覚えようかと……」
頭に疑問符が12個くらい浮かぶ。匂い?
「何で匂い? しかも目を閉じて」
「わ……私は見たものを覚えるのは得意なんですが、そうじゃないものは……」
「苦手なのか」
「はい……」
阿求がこちらから目をそらすように頭を伏せる。
首元に阿求の額が当たる格好になるので、髪の毛が首に当たって大分くすぐったい。
「何でそんなもの覚えようと」
頭を撫で擦りながら言う。
「皆覚えたいんです……あなたのことを……。姿も声も、匂いも」
そう言って阿求が顔を上げる。
「お嫌ですか……?」
そう言う阿求の目は幾らか潤んでいる様にも見える。
「嫌……」
そう言うと阿求は顔色を失った。が、続ける。
「嫌ではないけど……覚えるのはそれだけ?」
「え?」
阿求の顔色は戻ったが、疑問符が浮かんでいる。
「覚えるのは外見とか声とかだけでいいの?」
そう言ってだんだんと顔を近づけ、うっすらと桃色に染まった阿求の
(ここから先を読むには閲覧権限を取得してください)
うpろだ266
───────────────────────────────────────────────────────────
-幻史編纂恋史-
――それはふとした切欠、と言うモノだ。
ここ、幻想郷の人里に住む、幻想郷の「中」では普通な方の人間。名は○○。
強いて挙げるなら、そうだな、「本を読み漁るだけの能力」とでも言っておこうか。
程度でもなく、だけ。勿論、趣味なんてこんな根暗なモンしかなく、
家の畑仕事や寺子屋なんかが済むと行き付けの黴臭い本屋へ向かう訳だ。
いや、友人が居ない訳でもない。ただ、お互い色々仕事がある訳で。まあ、
外の本で目にする限りには自分の歳だとまだ勉学に勤めている時期なのだそうだが、
そこまで深く何かすべき事がある訳でもなく、余った時間を全て趣味に投げ売ってしまう。
最近は、本屋中の本を全て読み漁ってしまい、本を買いもしない俺は
行き付けの本屋から目の敵にされつつある訳だが……。
外の世界に行ってみたい、そんな風に考える事もまま有る。
だが、いかんせん情報量が少なすぎる。何より、外より流れ着いた、それも
ほんの僅かな本如きで手に入る情報など高が知れている。
故に、今日も今日とてこんなボロ臭い本屋に入り浸っている訳だで……。
もはや特等席となった、良く陽の当たる壁際に腰掛けて。
「……○○さん、でしたっけ?」
「は……はぇ?」
唐突に掛けられた声に、俺はまともに反応出来ずに腑抜けた声を漏らしてしまう。
目線を上げると、何処か見覚えのある少女が逆光を背に立っていた。
「……阿求さん、だっけ?」
「はい。お久しぶりです」
稗田阿求。九代目の御阿礼の娘とやらだそうで、時たま寺子屋に資料なんかを持って来て
くれたりする。病弱な家系らしいんだが、幻想郷中を飛び回って色々調べ物してたりするとかで、
案外アクティブな娘なのかもしれないと思ってる。年格好は俺より小さいくらいなのにな。
まあ詳しくは知らないが、本を多く読む関係上、寺子屋で顔を合わせた時なんかに
良く話すんだ。最近はそんなに顔も合わせなかったけど……。
兎角、何故だか分厚い本の山をたくさん抱えて、目だけは興味津々に、俺の読んでいた本、
「妖怪と人間の関係」を覗き込んでいた(どうやら初版らしく、ボロボロだ)。
「……それ、著者分かります?」
「著者ですか? えーと……あれ、稗田?」
目の前で微笑を浮かべる彼女と同姓の人物の名がそこにはあった。
どうやら、前代の稗田家の者がまとめた物らしい。記されている内容をかいつまんで言うとすれば、
殺伐幻想郷ライフ、貴方はこの惨劇から逃れる事が出来るか、みたいな事が書いてある。
……良く分からんのだが、今は八雲さんとこの藍さん辺りに笑顔で挨拶出来る時代です。
「六代目の御阿礼の娘が書いたんですよ」とエヘンプイな阿求。お前さんが書いた訳じゃ無かろうに、
なんて無粋なツッコミを入れようか迷ったが、とりあえず「ふーん」と返しておく。
「……あんまり好反応じゃないですね?」
「あ、すみませっ。いや、別に、えーと……」
上手い反応が思いつかなかったのであたふたしていると、阿求はため息一つの後、抱えていた本の山を
ズドンと俺の目の前に叩き落し、その内の一冊を俺に差し出した。
あんまりな出来事に目を白黒させていると、阿求はニッコリと笑って言うのだった。
「幻想郷縁起! さぁ、私の、いえ、私達の偉業を少しでも多く記憶するのです」
「は……え?」
「……じゃなくて。えーと、あの、幻想郷についてまとめた本です。折角ですから
ここで会ったご縁と言う事で、一冊差し上げます。その様子では、この辺の本にも退屈して来た
トコロのようですし」
え、と呻くと、店主の咳払いが聴こえた。申し訳ないのだが、持ち合わせはあっても大抵の本は
手に取って一時間もあれば読み干してしまうので、買う事が滅多に無いのだ。
「でしょう? ですから、この本をどうぞ。少なくとも、貴方の時間潰しには成ってくれるはずですよ」
「え……と。良いんですか? あの、御代とか」
ポケットをまさぐるも、寺子屋帰りの身では何か入っている訳も無く(置き勉ってヤツか?)、
鞄さえも持ってない自分に持ち合わせがあるはずも無い。両のポケットがまるっきり
空なのを見て、阿求は申し訳無さそうに苦笑した。
「構いませんよ。御代なんかより、見て貰い、記憶して貰う事にこそ価値があるんです。
ここに置いて貰うつもりはありますが、御代は気持ち程度で良いと断ってありますからね」
「そうなんですか……」
ページをめくると、なんとまあ可愛らしいイラスト付きで読みやすさを感じる。おまけに
聞いたことはあれど見た事も無い色々が載っているようで、これは読み耽らざるを得ない……。
と、また一つページをめくろうとした瞬間響く不快そうな咳払い。
「……ちゃんと家で読んで下さいね?」
「あ、えっと、そうですね。あの、何だかわざわざありがとうございましたっ」
阿求に礼を言い、俺は陽射しに目を細めながら立ち上がる。
小脇に幻想郷縁起を抱え、店主に儀礼的に一礼してから店を走り出る。
と思ったら、ワンテンポ遅れて阿求も一緒になって出て来た。抱えていた幻想郷縁起は
手元にもはや無く、小袖を軽快に揺らしてすぐ傍に駆けて来た。
「まあまあ。そう急く事も無いでしょうに」
「いや、別に急いではないですけど……まだ昼下がりですしね」
つい先程昼飯は食べ終え、眠くなる頃合。本に読み耽っていればそんな事も無いのだが、
今日は流れでいつの間にか本屋を出てしまっていた。
「甘味屋にでも行きましょう。ね、どうせ退屈なら」
「え、でも俺持ち合わせ無いですよ?」
「大丈夫」
袖の裏から現われたのは、やたらと重厚感溢れる大きながま口の財布。
「御阿礼の娘を侮るなかれ、です」
そう言って笑う彼女は、何故だか以前よりずっと楽しそうだった。
「おいひいでふゅ」
甘味屋名物の杏仁豆腐を頬張りながら、阿求はうっとりとそう言った。
「口の中はちゃんと空にしてから喋りなよ……」
「……んむっ、えぇ。だって美味しいものですから」
いつの間にか打ち解けていたと言うか何と言うか、俺は既に敬語ではなく普通に友人と
会話するような空気で彼女と話していた。それでも阿求の敬語は癖みたいなものらしく、
俺側が軽くなろうとも、その丁寧な言葉遣いは揺るがなかった。
「んー、こう言う所に来るのも久しぶりかもしれません」
「そうなの? あっ、ちょっ待てそれ俺のさくらんぼ!!」
何気無い動作で即座に掠め取り、皿のさくらんぼはいつの間にか阿求の口中に収まっていた。
「欲ひーのなりゃ取って御覧なしゃいなー、ほへほへー」
「ぬぬぬ……」
阿求の舌先で踊る、淡い紅色の小さな果実。好きな物を最後まで取っておく俺としては、
非常に心苦しい痛手だ。これで彼女と恋仲でもあったなら、無理矢理にでも奪い去ったんだろうが……。
待て待て、何を考えているんだ俺は。
「……んみゅ。御馳走様です!」
「あぁぁぁ、俺の分が……」
そうこうしてる間に、哀れ俺のさくらんぼは阿求に奪われてしまった。卑猥な意味に聞こえるのは気のせい。
ま、奢って貰ってるんだからこれくらい……やっぱり惜しいな、くそぅ。
「……良く来たりしないの?」
「えぇ。自慢じゃないですが、私御阿礼の娘の中でも歴代一番体が強いらしいのですよ。なので、
人里にこもるより散歩してる事の方が多いんです。だから、こう言う機会も少なくて」
またもやエヘンプイ。この動作だけ見れば、裏に隠れた歴史家的な一面なんて見えないんだろうな、
なんて思う。少なくとも、俺の目に映る彼女は、純粋に今を楽しむ少女の姿をしている。
「そっか。じゃあ、暇な時は何してるんだい?」
「そうですね。編纂も大体一段落しましたし……まあ、貴方と同じと言った所でしょうか」
言うと、阿求はテーブルの上に置いてあった幻想郷縁起を手に取る。
「あとは、散歩とかかな。少なくとも、貴方よりは結構外に出てるつもりです」
「失礼な。何だよ、どうせ引きこもりだよ」
「ふふ、本だけでは分からない事だってたくさんあるものですよ。ですから」
阿求は幻想郷縁起を開くと、幻想郷の様々な場所が記されているであろうページを開いた。
「こんな風に、見やすさを追求して絵も入れてみた訳です」
「ふーむ」
それらの絵は、むしろ絵と言うより随分写実的な構図で描かれていて、その割にやたらと
活き活きしていて、何と言うか、分からん!! 要は上手いんだよ、絵が。
「だから、ね。幻想郷にはこんなに美しい自然がある。それに、妖怪と私達の、
人間との関係も良い方向に変わって来ている今がある。だから、知って貰いたいんです。
少しでも多くの人に、幻想郷の素晴らしさを。人妖問わず、ね」
そう言って笑う阿求の笑顔は、何処か儚げに見えた。
何故だろう、なんて首を傾げる間も無く、彼女の笑顔からそんな薄らぼやけた影は消えていた。
……幻想郷か。中に居るのに、何も知ろうとした事が無かった。
外は危ないから。その一言で片付けて、大人達の言いつけを守って、未だにこの本に記されている
ような美しい場所の数々を覗き見た事さえ無い。
「ま、そんな事より。イタダキですっ」
「あ、ちょっ俺の蜜柑うわああぁぁぁぁぁ」
何の脈絡も無く、俺の思考と言う静寂を打ち破って阿求の不意打ちが襲う!!
さくらんぼ<蜜柑の俺に特攻ダメージ!! 話に熱中していた隙を突き、阿求は俺の蜜柑を奪い取った!!
気付けば俺自身何を食ったのか思い出せないほどに虫食い状態の杏仁豆腐が残されていた!!
……あーんにんどーふ。
「わたひがおごってりゅんだから……んくっ、ご馳走様! 良いでしょう?」
「おぅあ、あぁ。そうだけどもね……ひでぇ」
とりあえず残りを虚しくかっ込み、蜜で流し込む。男として、過去は振り返らないのさ……。
むしろそんな事を思う脳内が拘ってるって? あぁ、その通りかも分からんね。
勘定も済み、店を出て昼下がりの人里を二人歩く俺と阿求。
昼も終わりが近いが、まだ仕事に仕事で往来を駆けずり回る人も多いようだ。
仕事……らしい仕事なんて、ここには畑仕事くらいしか無いような。いや、でも
俺の認識してるモノが少ないだけで、実際は違うのかもしれないな。
魚屋の兄ちゃんに「随分不釣合いなカップルだなぁ!」なんて囃し立てられて、
俺と阿求は二人して黙りこくってしまった。
……俺? そうだな、正直あんまり仕事はしてない。本を読んでるせいか、
随分と頭の出来た子供だと思われているらしい。別に、生活や人生に活かしている
訳でもないのに、将来に期待されているという訳だ。
どうせ自宅警備員に……え? 今なんか良く分からん単語がパッと脳内に出て来た。
「あ、あの」
「あ、うん?」
疲れてるのかな、なんて目尻をマッサージしていると、阿求がおずおずと声を掛けて来た。
「どうした?」
「えと、その。忘れないで下さいね」
ビシィ、と効果音が付きそうな動作で、目線少し下から俺を指差す阿求。あーと、いや別に
不快ではないんだが、周りの目はちょっとばかし気にして下さい。
「私が奢ってあげたんだから、今度は貴方の番です」
「あはは、そうだな。御馳走様、また御馳走になってやる」
「んなッ。卑怯です! 次は貴方の番ですよ! ちゃんと奢って貰います、また会うんですからね!」
そんなやり取りをしている内に、いつの間にか俺の家と阿求の家との岐路に辿り着いた。
気付けばもう日も暮れ始めていて、随分と大きな鴉の影が夕陽からこちらまで伸びていた。アレ、
妖怪なんじゃなかろうか。
「あ、そうです」
「ん?」
阿求は、もはや四次元ポケットと化した袖の下から何やら煤けた紙を取り出した。あ、
四次元ポケットとか言うのは、向こうの世界に居るらしい青い狸型機械人形の持ち物だとか。
そんな奇々怪々な物があるなんて、向こうは面白そうで困る。
「真新しい本が欲しいのでしたら、こちらへ行って見ては如何ですか?」
「……香霖、堂?」
何だか長い事倉庫にでも放っておいた紙切れのように古ぼけたそれには、香霖堂と言う、恐らく
雑貨屋? いや、道具屋だろうか。兎に角、初見の店の名と地図らしき物が記されていた。
「えぇ。外界の本もありますし、面白おかしな物もたくさんありますから」
「ほうほう。ありがとう、行ってみるよ」
「それと……」
先程見せた、霞みそうな笑顔と共に、彼女は言葉を続けた。
「また、逢えますか?」
「勿論、会いたい時に会えるさ。今度は奢ってあげるよ」
口元に笑みを浮かべたまま、彼女はやたらと速い動作で振り返り、一時俯いたように見えた。
――が、見間違いだったのかもしれない。振り返った彼女の顔にあの憂いのある陰りは消え、
本当に楽しそうな顔でまた笑ってくれた。
「ありがとう、ございます」
「こちらこそ。んじゃ、また会おうな」
「……えぇ。それじゃ、また――」
手を振り、歳相応の少女の姿で駆けて行く阿求の姿を、夕陽の中俺はただ見つめていた。
……今度は、蜜柑取られないようにしなくちゃ、な。
蜩が鳴いている。距離が近いせいか、あの夕暮れ時に響く
儚げな美しさは、その音色からは感じられなかった。
ただ、単純な音量だけは大きくとも、漂う弱々しさはどんなに
距離が近くとも蜩そのものな気がした。
――その内に事切れた蜩は、最期にジリとも鳴かずに庭へ転がり落ちた。
その様子はまるで、私自身のように見えた。
少しばかり気分が悪くなって、私は優しげな夕陽から逃れるように障子を閉める。
最期に寄り添う伴侶も居らず、孤独に果てた蜩。
子孫を残す、と言う生物の、種としての存在理由さえ果たせなかったこの者は、
終わりのその時に一体何を思っていたのだろう。
私は、こんな風には成りたくない――
机の上には、未だ編纂を待つ未解決、未整理の資料が並んでいる。
だけど、手を付ける気にはなれなかった。良く分からない不安が押し寄せて来て、
この部屋の暗さのように頭の中が真っ暗だ。
……何故、あんな事をしたのだろう?
どうせ、一緒には成れないのに。
成れたとしても、彼よりずっとずっと先に死ぬ事に成るだろうに。
何より、私は彼にそんな辛い想いをさせたくない。
……別に、○○さんは私の事を好きだ、なんて思っては居ないでしょうけど。
けど、私は彼と居たいと想ったんだ。いつの間にか、話している内にだろうか、
寺子屋で会った時には、そんな事思ってなかったのに。
妖怪ならば良い。私が転生して帰って来れば、また知人として、友人として
迎え入れてくれる。だけど、人間の場合そうも行かない。
私は人とは違う。彼や、あるいは他の人間達と同じ時を過ごす事は、
叶わぬ幻想なのだろう。
――独白を書いている内に、普通の人間で在りたい、なんて思ってしまったのだろうか。
ふふ、閻魔様に叱られてしまいますね。私は、そう在るように生まれついた存在じゃないか。
私のような優秀な書記が消えてしまえば、閻魔様も惑乱する事だろう。
こんな事、考えるだけ、行動するだけ無駄なのかもしれないな――
再び、障子を開け放つ。
先程よりほんの少し落ちた陽は、優しさと言うよりは無機質で生命を感じない、
感情の無い光に見えた。
屍と成った蜩は、変わらずに庭先に転がっていた。
……彼の、傍に居たい。
例え、この蝉のように成ってしまう私でも。
――私に、そんな資格はあるのかしら?
「はろう☆」
「ひやあああぁぁぁ!!?」
花屋の娘と遊んだ時、カキ氷の余った氷を背中に注がれた事がある。
そんな夏のある一日を鮮明に思い出してしまうくらい唐突に、背後から
気味の悪いハイトーンボイスが響いた。
「ななッ、なんっ、なんでスか!!」
「あらあら、声が極端に上ずってるわよ。可愛いわねぇ」
驚いた勢いで飛び出した庭の砂利を両手で味わいながら振り返ってみれば、
妖怪の賢者こと八雲紫が、相も変わらず不気味な笑みを浮かべて佇んでいた。
……一応の編纂についての打ち合わせは済んだのに、何の用かしら?
「っう、げふん……えーと、何か御用ですか? 幻想郷縁起の方でしたら、
指摘箇所は直しましたし、現在進行形で編纂も行ってますよ?」
「えぇ、ちょっとね」
起き上がり、居住まいを正しながら紫様を部屋へと招き入れる。
夕陽はついに山向こうへ隠れ、逢魔ヶ刻の空は紫様の金髪を妖しく染めていた。
お茶でもお出ししましょうか、なんて言い出そうと立ち上がりかけた瞬間、
紫様の白魚のような手がそれを制された。
「恋に生きるのは良いことですわ。求聞持の力を持てど、所詮貴方は人間なのだから」
「……えと、気付かれていたのですか?」
従者を呼ぼうとするその手が止まる。
胸中は、いつの間にか行動に現われていたのだろうか。自分では、
いつもと同じように散歩していただけのつもりだったのに、目が人里に、いや、
○○さんに向いていたのだろうか……。
「えぇ。貴方、自分でも気付かない内に里に居る頻度が増えてますわ。意中の子が
居る事くらい嫌でも分かります」
「……私が人間とて、想い人を現世に残せるほど私は強くありません」
――そう、一人に成る恐ろしさは、私が一番知っているから。
「ならば――」
フッ、と目の前から紫様が掻き消え、真後ろから惑わすようなあの声が聴こえる。
「――ならば。成ってみる? 妖怪にでも亡霊にでも、輪廻の輪から外れた存在にでも。
もう恐れる事は無い。妖怪や蓬莱人のような、死から蹴り出された存在がいくらでも居ますわ。
孤独を感じる事なぞ、須臾の間さえ無い」
「――お断り、します」
「どうして? もう幻想郷縁起なんて要らない時代なのに?」
蜘蛛のように絡みつく指先が、私の首元を這い回る。
胃に込み上げるような気持ち悪さがせり上がって来て、いつもは明瞭過ぎて悩ましい
ほどの頭脳が音を立てて凍りついて行く。
「……嫌だと言ったら、嫌です」
ツ、と唇の辺りまで来た白い指先が止まる。まるであの骸と化した蜩のように、
生命の息吹が感じられぬ冷たさがあった。
「……貴方の優秀な思考回路は何処へ行ったのかしら。何故嫌なの? 貴方の
論法に、根拠が欠如しているのはらしくないわ」
「それ、は……」
息を詰まらせたように、言葉が出て来ない。
私の存在意義。幻想郷縁起を纏め上げ、人間と妖怪の橋渡しをする存在に成る事。
今は、確かに妖怪を危険視する時代ではない。独白にも書いたが、私の存在は
もはや要らない物となりつつあるのかもしれない。
……でも、それならば。今居る私自身が私自身たる理由は……?
幻想郷でさえ幻想になった存在は、一体何処へ行き着くのだろう……?
「まあ、『時間』はありますの」
重苦しいその嫌悪感は、速やかに去った。
「……」
「尤も、『考える時間』があるかは分かりませんけどね」
皮肉めいた、そして嘲笑めいた笑みを浮かべて、紫様は暗い空間の切れ目へと
沈むように消えていった。
――時間は、ある。それこそ、私が死んでも永遠に。
うpろだ387・400
───────────────────────────────────────────────────────────
「すごい音だな」
「台風ですから」
「固定してるのに、雨戸もやたら揺れてる」
「台風ですから」
「向こうが騒がしいけど、雨漏りでもしたのかね」
「台風ですから」
先刻から同じ答えしか返ってこない。
「阿求、何でそんな奥のほうにいるの?」
「台風ですから」
「……」
暗がりの奥に阿求はいて、顔は良く見えない。
しかしこれは……。
「あきゅんたいふうこわい?」
「台風dいえ、怖くはありませんよ」
何度も経験しましたし、と声を小さくしながら続けるもそれにまったく説得力は無い。
これは明らかに怖がっている。
「怖いなら怖いって言っていいのよ」
「はい怖いです」
心地良いまでの即答痛み入る。そこまでか。
「別に強い台風って言っても、家が壊れるほどじゃないでしょ」
せいぜい屋根瓦が吹き飛ぶ程度、と付け加えると阿求から笑みがこぼれた。
「そ……そうですね。ここまで怖がることはありませんよね」
「そうそう、伊勢湾やマエミーに比べれば何のことも無い」
比べるものが間違ってる? まあ多少大きいものと比べた方がいいだろう。
「それでは落ち着いたところで、少し書き物などしてきますね」
そう言いながら立ち上がり、書斎へ行こうとする阿求。
外の廊下を使った方が早いだろうに、内の部屋伝いに行くのはやはりまだ怖いからか。
「それじゃ俺は夜に備えて横になってこよう」
夜に何をする気なんですか、と突っ込まれたが何のことは無い、ただの昼寝である。
各々やることをしに動こうとした時に、不意にそれは来た。
ガオンという轟音とともに屋敷が揺れ、遅れて風の吹き込む音が聞こえ始める。
「お。どっかの屋根瓦でもぶつかったか?」
見に行こうとした瞬間、腰をつかまれる。
「いやー。やー」
見れば阿求が泣きながらしがみついている。
「遠くでぶつかっただけで、ここにゃ被害は出んよ」
そう言いながら頭を軽く撫でてやると、幾らか落ち着いたようで泣きはしなくなった。
「じゃ見に行ってみようか」
「うにゃー」
抱きつく力をさらに強める阿求。からかいすぎたろうか。
「っていっても一応俺も少ない男手だし、見に行かんわけにも行くるまいよ」
言うとしがみつく手が少し緩まる。
「じゃあ、書斎に送ってから見に行くから」
もう少し力が弱まる。
「じゃほれ、行くよ」
言うが動かない。膝立ちのまま、じっとこちらの腿に顔を埋めている
「どうしたの。たっちは?」
「子ども扱いしないでください」
顔を上げ、やっとといった風情で阿求が声を出す。
「ん。で、どしたの」
「今ので腰が抜けました……」
「あ、あらら」
さて、どうしたものか。
手の塞がっているだろうから、女中さんらを呼ぶわけには行かない。
なら、ここで休ませておくのが上等だろうか。
「休む? 畳の上でいい? 布団引く?」
といってもこの部屋に布団はないので、持って来る必要があるが。
「いえ、とりあえず書斎に運んでください」
「でも、休んでいた方が良くないか?」
「書斎に行きたいんですっ」
強く言い切られてしまった。
書斎に何かあるのか……そういえばあそこは奥のほうにあったっけ。
「さて立てないんじゃどうするかねえ」
肩を貸すわけにも行かないし、背負っていこうか。
さてそれでは背負い紐を調達してこなければいけない。
「抱っこ」
「そうさね。背負ってえなに?」
「抱っこしてください」
抱っこ。こっちの腰が死ねる。よって却下したい。
だが、両腕広げて待っているのを見捨てるわけにも行かない。
……覚悟を決めるより他あるまいか。
阿求を横座りにさせ、左腋より腕を入れて背側に通し、右腋をつかむようにする。
同時に膝の下にも他方の腕を差し込み持ち上げ、俗に言うお姫様抱っこの状態にする。
「重い。落としそう」
「女の子に重いなんて言っちゃいけません」
そう言って阿求は肩に顎を押し付けてくる。
肩のツボが押されて地味に痛い。
「痛いでしょ。そんなことやってると落とすよ」
「きゃーおとさないでー」
そう言って阿求は腕に力を込め、顔を首筋に寄せてきた。
阿求の吐息が首にかかリ、大分くすぐったい。
「じゃ行くかね」
ふらふらと歩き始める。
普段なら1分、40歩かからない程度の場所に、
途中何度か落としそうになりながら、じっくり5分以上かけて進んでいく。
「はい、着いたよ」
言いながら、座布団の上に降ろす。
「ありがとうございました」
言うと阿求は座りなおし、背筋を伸ばして筆記机に向かう。
「それじゃ見てくるか」
「気をつけてくださいね」
外回りの廊下をのそのそ歩き、破損箇所を探す。
が、特に見つからない。
二週目に突入するがやはり見つからない。
「戸袋にでも当たったのか……?」
まあいい。目に見える被害がないなら、今はそれで上等だ。
「ただいま」
「おかえりなさい。どうでした?」
「何も壊れてないね。添え木なりにでも当たったんじゃなかろうか」
阿求の傍に胡坐をかき、言う。
「見た感じ被害がないようなんで、安心して寝れるわ」
足を伸ばし、敷いていた座布団を除け横になる。
「寝るのは構わないんですが……」
服の上のボタンをはずし、ベルトを少し緩め寝やすくする。
「何でここで寝ようとしているんですか?」
「阿求がいるから」
言いながら阿求の座っている座布団を机の影から、阿求ごと引き摺り出す。
「えっ……それはどういう」
「ん、いい高さ」
問いかけは無視して、膝の上に頭を乗せ幾らか揺り動かす。
「じゃ、おやすみ」
「膝で寝ないでください。重いでしょ」
「じゃあ、膝枕はやめよう」
座りながら言い、座布団を頭を置く方向に放り投げ、阿求を引き倒しながらまた寝転がる。
「何するんですか」
「……添い寝?」
「される方ですか?」
阿求が言っている間にこちらは座布団を二つに折り、頭をのせる。
引き倒した阿求を抱き寄せ、頭の下に左手を差し入れて座布団の上に乗せさせて、
また右手を後頭に当てる。
「まあ、いいじゃないの。台風なんだし」
と、阿求の頭を撫でてやりながら言う。
そのまま阿求の頭頂に顎を乗せる形に、あるいは頭を胸に抱きかかえるように体の位置を変える。
幾らか抜け出そうと阿求はもがいていたが、やがて観念したか、離そうと突っ張っていた左腕をこちらの脇腹にのせると、
「台風ですし、まあいいかもしれませんね」
と言って体を引き付け、やがて双方静かに寝息を立てていった。
<<その後>>
時間経てども台風未だ過ぎず、風雨未だ強し。
さすがに何時間も雨戸が揺れ続けていれば不安になってくるし、
何よりうるさくて眠れやしない。
「寝れん」
そもそも昼間に2時間寝たのが悪かった。
「というか何でこんなに風が強いままなんだ」
台風なんて6時間程度で過ぎるものじゃないのか。
もうそのくらいは経ったはずだ。
「まあ、寝て起きれば晴れてるはずだな」
言いながら毛布をかぶり、寝ようとする。
「やはり寝れん」
人間は寝溜出来ない生き物なので、あまり寝すぎることも出来ない。
本でも読んでいようかと思ったが、そういえば燈油が足りないという話なので、
おいそれとそれも出来ない。
風が幾らか止んでいれば外に出て散歩でもしていればいいのだろうが、
こう風が強くてはそれも出来ない。
(あきゅんの寝顔見物にでも行こうかしらん)
うむ、そうしよう。見つかったらその時だ。
早速足音を消すための厚手の靴下を探そうとした時、外の障子の闇が濃くなった。
かたり、と小さな音を立て障子が開く。現れたのは阿求だった。
「やはり起きてましたか」
近寄ってきた阿求が小声で言う。
「どうしたの? そっちも眠れない?」
こちらも小声で返すと、阿求は小さく頷いた。
本でも読んでいればいいのに、と言うと阿求は燈油が切れたと答えてきた。
「ですから、何か向こうにいた時の話でもしてもらおうかな、と」
さてやこれもなにかのネタにでもするつもりなのか、阿求が言ってくる。
しかし、狭く深くの交友関係だった自分には人に話すような話はさしてない。
とはいえ昔話なんぞやろうものならこっぴどく叱られそうだ。
いっそグリム童話あたり話してしまおうかとも思ったが、そも俺が覚えていない。
あたりは真っ暗。秋口とはいえ、台風の最中で未だ蒸し暑い。
「では覚えているのを幾らか。信じようと、信じまいと―」
翌日、毛布に包まり眠る阿求と、敷布団の下にいる俺がいた。
うpろだ404
───────────────────────────────────────────────────────────
この家の主が息を引き取ろうとしていた。
本当に短い間の命を、ただただ書く事のみに捧げ死んでいく。
それを何代も何代も続けているのだという。
「お世話になりました」
「いえ、このくらいなんでもありません」
「それでもです。お礼を言わせてください」
弱弱しく言う。
あぁ、やはり死ぬのだと再確認する。
もしかしたらちょっと風邪を引いただけなのかも、と望んでいたけれど。
ならば、言わなければいけないことが……
「私は……」
「言わないで下さい」
「…………」
「命短い私に、その言葉は重過ぎます」
「…………」
「泣かないで下さいよ。死にそうで泣きたいのは私なんですから」
「はい」
それでもあふれる涙をとめることは出来なかった。
それから無言でどれほどの時間いたのだろう。
ようやく涙が枯れたときには、沈みかけていた太陽はすでになく月が南の空にかかっていた。
「そろそろ……逝きますね」
「はい」
「これから息災ですごしてください」
死んでしまう。
最愛の人が。
勇気を振り絞る。
「必ずまた会います。そのときは先程の言葉を必ず聞いていただきます」
「急になんですか?
私は数百年単位で転生を繰り返しています。それに私はそのとき男か女かわかりませんよ」
「存じています。でも、必ず会います」
そう、これは強い意思。
「あなたが生まれ変わるとき私は必ずそこにいます。
あなたが女性なら男として、男性なら女として」
「閻魔様が許すとも思えませんけど」
「いいえ、誓って生まれ変わります」
「それは楽しみです」
そういって瞳を閉じ、二度と開かなかった。
その後最愛の人に遅れること数十年、十分に長生きをして死ぬことになる。
「お初お目にかかります。私は○○と申します。
幻想郷の外の出身ではありますが、この度稗田家の使用人頭としてお世話させていただくこととなりました」
「はい、よろしくお願いいたします」
そういって目の前の少女はクスリと笑った。
何か変なこといったかな?
「それにしても、本当に生まれ変わった上にきちんと男性なんですね。○○は」
「はい?」
「いいえ、なんでもありません。
ところで何か言いたいことはありませんか?」
「? いえ、特にはございませんが」
不思議そうな顔をしている俺を見てまたクスクス笑う。
なんだ?
「ちなみに私にはあります。お久しぶりです○○」
「?」
「あのときの言葉を今度こそ聞きたい。必ず言ってくださいね」
「は、はぁ、何のことか良くわかりませんが」
「はい、でもきっと思い出してください」
「? と、とにかくこれからよろしくお願いいたします、阿求さま」
と、これが俺と阿求の出会い。
ちなみに俺がこの時の会話の意味を知るのは、もうしばらく後のことだった。
うpろだ457
───────────────────────────────────────────────────────────
夜の蚊帳が下りた薄暗い林の中を一人進む。
終わらない迷路のように続く林。
聳え立つ暗い木々は寂しく朽ち果て、多いというのにどこか空虚な印象を与える。
そんな冷たい場所の明かりはただ一つ、頭上の満月のみ。
ただ、月が仄かに照らし出そうとも、この場所の陰鬱な雰囲気は変わらない。
まるで死を暗示させるかのようだと、阿求は思った。
黒の木々を掻き分け、足音だけを響かせなお進む。
そして前方に初めて黒以外の色を見つけ、ふと足を止めた。
―――・・・血、だ。
木や地面に飛び散るようにこびりついた血はまだ赤く、
その血が流れてからまだあまり時間が経っていないことを示す。
そしてその更に奥に、自分が探している人物がいるということも。
「・・・○○、」
おびただしい程の赤の中心、闇に紛れるように佇む彼に声をかける。
手には赤く濡れそぼった斧。
辺りにはばらばらになった妖怪の死体。
どちらも、彼には似合わないものだと、無意識に考える。
と、その時、○○はゆっくりとした動作でこちらを振り返った。
「・・・阿求か」
彼はこの場には到底似合わない、明るい笑顔を向けてくる。
それには流石の阿求も小さく息をのみ、目を見張った。
「阿求、どうかしたのか?いつもは家で待っててくれるじゃないか」
「いえ・・・あまりに遅いので迎えに来ました。今日も妖怪退治、ご苦労様です」
帰りましょうか、と手を差し出し、○○に問いかける。
しかし○○はその手を取る事無く、小さくかぶりをふって悲しそうに笑った。
「○○・・・?」
「・・・悪いな。もう少しだけ、ここにいたい」
それは黙とうのためだろうか。
○○が殺してしまった妖怪に対しての。
罪滅ぼしにもならないのはわかっている。
殺してしまった内臓を直視したところで、罪が消えるわけではない。
ただ、自分はこれを仕事に選び、里の人間に感謝され、
そして阿求がそばにいてくれるだけだ。
阿求はそれに何も言わず、どこかに視線を彷徨わせていた。
二人の間に自然と沈黙が訪れる。
いつもは心地良い沈黙も、今は酷く気を乱される気がして、
○○は無意識のうちに眉根を寄せていた。
そう、この時はまだ分からなかったのだ。
自分の胸に巣食う、この言いようのない不安の正体を。
「○○」
「・・・っ、何だ?」
阿求の姿を見つめながらも、意識は思考の奥深くまで潜っていた○○は、
彼女の呼びかけにはっと意識を取り戻すと、平然と返事を返した。
「・・・こんな所にも、花は咲くんですね」
その言葉に不思議そうに阿求の見る先を覗き込む。
するとそこには、名も知らぬような小さな白い花があった。
「私は、この花のように生きてみたかった」
独り言のような阿求の言葉。
しかし○○は、それを黙って聞いていた。
慈しむような優しい手つきで、白い花に触れる。
ふわりと揺れた花は、何故か阿求自身のような気がした。
「誰のためでもなくただ花を咲かせて、誰に知られる事もなく、
でも最期まで自分を誇って散るんです。
・・・そして、今にも枯れてしまいそうな瞬間にも、こうして美しいと思ってもらえる」
ここには何もないかもしれないけれど。
ただ、静かに美しく咲き誇れるでしょう?
首をかしげてみせた阿求の表情は、何かを諦めたように潔いものだった。
だから、なのかもしれない。
彼女の言葉が、こんな場所で死ねたらいいのにと、そう聞こえたのは。
「素敵だと思いませんか?」
「・・・そう、だな。でも」
そんな事を、自分の前で言わないでほしい。
口にさえ出さなかったものの、○○の困ったような笑みに、阿求もふっと、笑った。
気付いているのだろうか、彼は。
自分がひどく泣きそうな顔をしているという事に。
そんなことを頭の片隅で思いつつ、阿求はぐっと拳を握り締めた。
「わかってますよ?・・・わかってます。けれど、○○、」
わかるでしょう?と笑う阿求を○○は、どうにもできず抱き寄せる。
情けない事に、自分の体が、言葉が震えている。
この先は言わせてはならないと、本能が告げているから。
「・・・私は、もう」
「阿求、それ以上言うな」
「もう、これ以上」
「阿求・・・っ」
「生きては、んっ・・・」
「阿求・・・!」
○○が言葉を紡がせないように、阿求の唇を塞ぐ。
息苦しいほどの口付けに、阿求は視界がぼやけ、意識が浮く気がして瞳を閉じた。
・・・これで私が死んでしまったら、彼はどんな顔をするのだろう。
そう考えたら、さっきまで何ともなかったのに、無性に泣きたくなった。
「・・・○○、聞いてください」
「聞きたくない」
「我儘言わないでください」
「どっちが、だよ」
ああ、泣きそうだ。
私も、○○も。
「ええ、すみません」
本当にごめんなさい、○○。
最後の、最期まで弱い私で。
でも、愛しいから貴方の手で、迎えたい。
「・・・我儘、聞いてくれますか・・・?」
その言葉に、○○はすっと目を閉じて、今にも泣き出しそうな空を仰いだ。
月はいつの間にか雲に隠れてしまっている。
涙が、頬を伝った。
「―――・・・○○」
ああ、これはきっと、喪失感だ。
俺はこうして、この世界で全てを失くすだろう。
今は鮮やかな色も、ゆったりと流れる刻も、大切な君でさえも。
「私を、殺して?」
それでも俺は、それに抗う術を知らないから。
(せめて最期くらいは貴方に手折られたいと、そう思っ た の)
「たとえお前がどんな姿になっていようとも、俺は必ず、見つけ出してやる」
「―――・・・ええ、また来世で逢いましょう、私の愛しき人」
そして俺は、動かなくなった君を抱いて、帰路につく。
10スレ目>>652
───────────────────────────────────────────────────────────
風の噂によると、紅白の巫女は恋人と質素にニャンニャン。
白黒魔砲使いは白黒魔砲使いで恋人の家に押しかけてケーキを味わいつつニャンニャン。
夜雀もニャンニャン、人形遣いもニャンニャン、閻魔もニャンニャン、妖狐もニャンニャン、兎もニャンニャンと、それはもうピンクな空気らしい。
ニャンニャン鳴くのは猫だけで良いが、その猫も好きな人と読んで字の如くニャンニャンしているのだからたまらない。
正に世は乱世。幻想郷が桃源郷になってしまうのも時間の問題である。
で、そんなピンクな行事が行われている中。自分は何をしているのかと言うと……。
「エフッ!エフッ!ゴフッ!ガハァッ!あー畜生。チーン!」
風邪を拗らせて寝込んでました。
何ですかこのイジメ。何が悲しくてこんな苦しい思いをしなきゃならないのか。
五分ほど考えて止めた。悲しくなってくる。私の名前はザ・ソロー、人の悲しみを知れ……。
まぁそんな訳で、寝たり起きたりを繰り返しながらボーっとしていた。
ドンドンドン
そうしていると、扉を叩く音がする。ちなみに呼び鈴なんて便利なものは付いていない。
ドンドンドン
「誰だよこんな時間に……ったく」
そんな事を呟きながら玄関へと向かう。
ドンドンドン
ガチャリ
「ういー、どちら様ですか、と」
「メリークリスマース!」
「だれてめぇ」
扉を開けるとそこにはおじさん?が居た。
いや、正確に表現するとだ
黄緑っぽいボディ、黄色っぽいアーム、茶色っぽいレッグ、紫っぽいヘッド。
そしてパーティ等に使う鼻眼鏡、三角帽子、片手に一升瓶、片手にコップ。
ああ駄目だ、正確に表現したら余計何なのか分からん。
「む、酷いですね。私の顔を忘れるなんて」
「……とりあえず鼻眼鏡を取ってください、話はそれからだ」
「あ」
急いで鼻眼鏡を取る目の前の人物。どうやら付けていた事をすっかり忘れていたらしい。
鼻眼鏡を取ると、おっさんではなく少女の顔が現れた。
「あぁ、誰かと思ったらあきゅさんですか」
「阿求です。何で『う』だけ省略されてるんですか」
「いやまぁ、何となくノリ……ウゲッホ!ゲホ! 失礼。それでどうかしたんですか」
「せっかく求聞史記が書き終わって打ち上げをやっていたのですが。一人ほど未参加者が居たようなので様子見です」
どうやら自分の様子を見に来てくれたらしい。
「いや、少々風邪を拗らせまして」
「あぁ、それで……。熱はどれくらいあるんですか?」
「さっき測った時は37.6度ってとこです」
「それでは安静にしていた方が良いですね」
「そう言う事です。エホッ!エホッ! それじゃ、うつすと申し訳ないので」
ガチャン
「……」
「……」
「……あの、何で一緒に入って来るのでしょうか?」
「風邪で苦しんでいる人が居るのに私だけ楽しむのも申し訳ありませんから、特別に看病しますよ」
「いやいや大丈夫ですよ、自力で治しますから」
「いやいや遠慮しなくても、美少女が看護してあげると言っているのですよ?」
「いやいやいや」
「いやいやいや」
………
……
…
そんなやり取りが続く事5分。体調不良でスタミナの切れた自分が折れる形で決着と相成った。
「そうですね、それではお粥を……」
「昼に多目に作ったので大丈夫です」
「では水枕……」
「さっき起きたついでに買えたじゃないですか」
「氷嚢……」
「水枕と併用したら駄目だったと思ったんですが」
「それなら私は何をやれば良いんですか!!」
「知るかー!!」
とまぁ、基本的にはこんな感じだったが。
結局、雑談なんかをしているうちに眠くなってきたので、眠る事にした。
夜中、ふと目が覚めた。
しかし、目を開けることができない。開けれない事も無さそうだが、とても辛い。
寝ているにも関わらず、頭がズキズキと痛む。
呼吸は自分が聞いていても分かるほどに荒くなっている。ゆっくりとした呼吸をする事ができない。
毛布等をしっかりとかけているはずなのに、恐ろしいほどに寒い。
どうやら風邪が悪化したらしい。
この状態をどう表現すれば良いのだろうか?
故郷の方言を借りるとするならば『怖い』と表現するのが一番的確だろう。
「○○さん、○○さん、どうしました?大丈夫ですか?」
阿求さんの声が聞こえてくる。
どうやら自分が寝た後も、帰らず居てくれたらしい。
しかし、その問い掛けに答える事が出来ない。
声を出す力すら風邪に奪い取らている。
不意に、首筋と額に冷たい感触がする。
「大分熱が上がってますね……。頭、上げられますか?」
軽く首を横に振ると、自分の頭が宙に浮き、水枕を引き抜かれる。
変わりに普段使う枕を入れられ、そのままゆっくりと頭が降りていく。
暫くすると「頭上げますよ」と声がかかり、先程と同じ要領で枕と水枕が取り替えられた。
そしてまた、首筋に冷たい感触。それと同時に、やっと目が開く。
目の前には、心配そうな顔をした阿求さんの顔があった。
目と鼻の先と言うほどの近さでは無いものの、それなりに近い。
自分の額に冷たい感触。阿求さんの手が自分の額に置かれたのだと把握する。
それを見て、自分は何を思ったのだろうか。動かすのも辛いはずの腕を動かして、阿求さんの頭の後ろに添える。
そのまま、力の入らない腕で阿求さんの頭をこちらに引き寄せる。
そしてそのまま、キスをした。
再び意識が朦朧とし、視界がボヤけてくる。どうやら頭と体、両方が休憩を求めているようだ。
阿求さんの顔が自分から離れていく。その表情は、嬉しそうなようでもあり、呆れているようでもあり、困っているようでもあった。
そのまま、自分の意識は無くなっていった。
6スレ目>>590
──────────────────────────────────────────────────────────────
『見なくたって、私はずっと覚えてますから』
恥ずかしそうに、小さく笑った阿求さん。
精一杯背伸びをして、穏やかに目を閉じて。
――僕が呆然としているその間に、目の前で綺麗なおかっぱの髪が揺れた。
6スレ目>>754
──────────────────────────────────────────────────────────────
迷った。道に、迷った。
何の変哲もない、ただ進むべき道を見失っただけのこと。ちょっとだけ難しく言ったが、簡単に言えば道に迷った。
オーライ、しかし慌ててはいけない。そこらへんの岩にでも腰掛けて、待っていれば、軽い足音。
「もう……○○。いい加減に帰り道くらい覚えて下さい」
な? お迎えが来るのさ。
それも、とびっきりのかわいこちゃん。
腰に手を当てて怒って見せるが、どうしても怖くは無い。それどころか、怒りで粗雑になる仕草でさえ、上品に見える。
「わりぃわりぃ、つい景色に見とれちまってな」
「その言い訳は38回目です」
「この道は迷いやすいんだ」
「それは72回目ですね」
「あ~…………、すまん」
「全く……」
大仰にため息をついて、彼女は俺に背を向ける。そして、小さな歩幅で歩き出した。
彼女は稗田阿求。一度見たものは忘れないという特殊な技能を持っている。俺が前いた世界にも、そんな人がいた。それと同じようなものか。
2年前だったか、3年前だったか。友達とハイキングに来ていた俺は、道に迷い、気がつくとここ――幻想郷にいた。妖に鬼、亡霊に魔法使い。果ては精霊や吸血鬼と、何でもござれのここは、俺が前いた世界とは隔絶されてしまっている、らしい。もう前いた世界には帰れないといわれた日には、正直泣きそうになった。そんな俺を励ましてくれて、支えてくれたのが阿求だ。
この世界、幻想郷の歴史を書き留めていると言う彼女は、俺を自分の屋敷に連れ込んで、「何か面白いお話でもしてくれませんか?」なんて言った。初めて、幻想郷に来て笑った瞬間だった。
「○○っ。早く来て下さい。帰りますよ」
「ほいほいっと」
肩を可愛らしく怒らせて歩く彼女に追いついて、並んで歩いた。もうこれで何度目だろうか。俺と彼女がこうやって一緒の帰り道を行くのは。
さて、帰ったらどんな話をしてやろうか?
◇◆◇
「それでだ、俺はこういってやったんだ。『先生、ヒーローは遅れて登場するもんです』ってな」
「その……『先生』っていうのは、○○の世界での、慧音のようなものなのですね?」
「ああ、そうだ。しかも、それぞれ教えてくれることが違うときてる。めんどくさいったらありゃしない」
「それは……仕方のない事です。私みたいなものでもないと、全部覚えるなんて不可能です」
薄ぼんやりとした灯りの中で、阿求が手を振る。燭台一つの部屋の中で、阿求は布団の中。俺はその枕元に座っていた。いつの頃からか、阿求が寝る前に、俺が外の世界であったことを話すようになっていた。初めは本当の事を話していたのだけど、いずれネタは尽きる。そこで、俺は少しだけ嘘をつくことにした。良心が痛むが、阿求のためなら仕方ない。ちょっとだけ、俺が我慢すればいいだけの事だ。
ふうむ、と阿求が息をつく。
「やはり○○の世界は興味深いですね……いつか行ってみたい」
「その内行けるさ、俺が来れたんだから、出てもいけるはずだろ」
「…………そうですね」
こういう話題になると、いつもいつも阿求は様子が違って見える。それは諦観のような、全てを見透かしたような笑みだった。人生経験というものが違っていると、やっぱり先見性も違ってくるのだろうか?
阿求が布団の中にもぐりこんだ。もう寝る、という合図だ。俺は腰を上げて、「おやすみ」と声をかけて部屋を出る。外はまん丸な月が浮かぶ、宵闇だった。虫の音が、風の音が、趣深い。そういったものは総じて――はかない。
「った! 何不吉なこと考えてんだ、俺は」
ぶるぶる頭を振った。きっと思い違いさ。俺みたいなバカの考えることなんて、大したことじゃない。馬鹿の考え休むに似たりってね。さあ、もう寝よう。明日は、部屋の掃除をしなきゃ。
◇◆◇
はたきを箪笥にかける。その上を雑巾で拭いて…と。
「だから、違いますって! 部屋の掃除は上から下へ、これが基本です」
「ああ~? いいんじゃないのか? 最終的にきれいになればいいわけだしさ、そんな細かいこと」
「どこが細かいのですか。ああもう、貸して御覧なさい。手本を見せてあげます」
そう言って、俺の手からはたきを取り上げた阿求は小鳥のように部屋の中を飛び回る。それを何となく目で追ってるうちに、ついぽろりと本音がこぼれてしまった。が、忙しく走り回る彼女には聞こえなかったようで、安心した。今の言葉が聞こえようものなら、どうなっていたことか。想像するだけで恐ろしい。
「○○っ。少しは手伝いなさ……げほっ!」
「お、おい。大丈夫か、阿求」
「だい……じょうぶ…です。えほっ!」
「全然大丈夫じゃないだろ……ほら、後は俺がやるから、休んでろ」
「申し訳ありません……。でも、きちんとするんですよ。上から下へ、基本に忠実に、いいですね?」
「わかったわかった、わかったから。早く休んでいてくれ」
半ば追い出すように障子を閉める。陰だけになった阿求はまだ、咳き込んでいる。最近、体調があんまり良くないらしい。今みたいに咳き込むだけのこともあれば、何日も部屋から出てこないこともある。本人はどうということは無い、ただの風邪だと言っているが、それが尚更嘘っぽくて、俺は心配だ。何事も無ければいいが……。
だけど、世の中そんなにうまく出来ているわけはなくて。俺が掃除を早々に切り上げて、部屋を出ると外は荒れていた。強い風が吹き付けるのに、それはうだるように熱い。どことなく、気持ち悪い。
「阿求?」
返事は無い。声の届かない所にいるのか?
「お~い、阿求?」
返事はまたも、無い。さっきよりも大きな声を出した。よもや、聞こえていないということはあるまい。どうして返事をしないんだ。少しづつ、ほんの少しづつ、嫌な想像がつのる。
「阿求! 返事をしろ、阿求!」
最早なりふりなど構ってはいられない。乱暴に障子を開いては、足音を鳴らして屋敷の中を歩き回る。早く早く、返事をしてくれ。お茶目に脅かしてくれるのでもいい。彼女がそんな事をしたことは無いけど、今だったらしてもいい。してくれれば、いい。
「阿求! あきゅ……………………阿求!」
見つけた、彼女を見つけた。今まで、夜俺と彼女が夜遅くまで話しをしていた、彼女の寝所。そこに彼女は、うつぶせに、倒れていた。慌てて、その体を抱き上げて、顔を覗き込む。だらしなく半開きになった唇に以前のような張りは無かった。目は開けている。開けているが、その視線はどこを向いているのやら、少なくとも俺を見てはいない。頬を張って、大声を張り上げても、何の反応も示さない。ただ、ただただ、その矮躯を揺らすだけであった。
その時だった。第三者の声が、座敷に這入りこんだ。
「あや~、やっぱり死んじゃったか」
「……あんた、誰だ? やっぱりってなんだよ!? あんた何か知ってるんだな? 知ってるんだろ!? 教えてくれよ、彼女に……阿求に何があったんだ!?」
「何があったって……死んだのさ。ぽっくり逝ったの。……ああ、自己紹介がまだだったね。あたいは、小野塚小町。死神さね。よろしく」
赤い髪の死神は、親しげに右手を差し出してくる。握手でもしようってのか? 生憎、そんな余裕は無い。阿求に何があったのか、そればっかりが気になる。詰め寄るように、俺は言葉も荒く死神にまくし立てた。死神は、ウンザリするように額に手を当ててから、ため息混じりに口を開いた。
「はぁ……めんどくさいなぁ。いいかい、一回しか言わないからよく聞きなよ。彼女は、稗田の女はね、長生きできないようになってるのさ。阿求は一度見たものは忘れなかったろ? その能力があるなら、尚更さ。精々、十年かそこら生きられればいいほうじゃないのかね。あんた、阿求と出会ってから何年一緒にいるんだ?」
「二三年だと思う……。詳しく覚えてないけど……。それより、なんで阿求は死ななきゃならなかったんだよ!?」
「言ったろ、『そういう風にできてる』からさ。彼女の家系は特別でね、とある縁起を書く為に生きてるって言ってもいいくらいさ。ま、彼女はいい人生歩めたんじゃないの? 最後にあんたに会えたわけだしさ」
そういう風にできている。だから、彼女は死んだ。ただ、それだけの簡単で、あまりにも明快な理由。これだけはつらつと言われると、何も反論ができなくなる。
俯いて黙りこくった俺を見て、死神はまたため息をつく。俺の頭をぽんぽんと叩いてから、「泣くんじゃないさ」と言った。
「泣くんじゃないさ。運が良ければ、転生してまた会えるからさ。ま、運が良ければの話だけどね。他に何かあるかい? あたい、こう見えても忙しいんだ。ノルマがたまっててね」
「……………………」
「はぁ、あんたまで死にそうな顔してんな。まあいいさ。それも運命さね。……よっ…と。じゃ、縁があったらまた会おうや。ま、あんたが死んだら絶対会うわけだけどね」
ふわり。そう言って死神は阿求の亡骸を担いで何処かへ飛び去ってしまった。俺は、その場から一歩も動けないで、夜が更けるまでずっとそこに立ち尽くしていた。俺自身、動かない自分を不思議に思ったほどだ。
いい加減にしろよ。自分に言い聞かせても、どうにもならなかった。ふらふらと、幽鬼の様に足を向けたのは、阿求の部屋。後ろ手に障子を閉めて、その場にへたり込む。燭台に火も灯さない。独りごちるように俺は口を開いた。今の今まで自覚しなかった、いや、自覚はしていた。だけど気恥ずかしくていえなかった言葉を、吐き出すように、言った。
「なあ、阿求。ひとつ話をしてやる。お前が憧れた世界から来た、一人の男の話さ。その男は幻想郷に来て、絶望した。男が知ってるものは何も無い。どこを向いても、知らないものばっかりで、怖いものばっかりで、毎日膝を抱えてがたがた震えるばっかりだった。そこへお前が来てくれたんだったな、阿求。俺は狂喜したさ。俺のことを分かってくれる人がいたってな。お前は俺の話を楽しそうに聞いてくれたっけか。あれ、実はほとんど作り話だったんだぜ? 笑っちゃうだろ。それで、その男はな、今、お前を失って初めて気づいたのさ。俺は――お前が好きだ……ってな」
一筋、涙がこぼれた。それだけ、一筋だけ流れた。それ以上は、流れない。俺が、流れさせない。死神は、転生すればまた会えるといった。なら、俺は待つだけだ。いつか、阿求にまた会える日を。その時ばっかりは、絶対に言おう。
「大好き」
この言葉を送ろう。忘れられない少女に、この言葉を。
◇◆◇
文々。新聞より転載。
『九代目阿礼乙女 稗田阿求の手記より一枚の紙が発見される。
それには、彼女が同居していたと思われる男性、○○氏への言葉がつづられていた。内容を明かすことはしないが、阿求氏は○○に対し何らかの好意的な感情を抱いていたと思われる。
○○氏は、阿求氏が亡くなる数年前から彼女と同居を始め、そこで何らかの感情が芽生えていったと思われる。手記に寄れば、彼は博霊大結界の外から来た人間らしい。一緒に道を歩いている姿が、幾度となく見られていた。
なお、○○氏は阿求氏が亡くなった数年後に、死亡が確認されている。発見場所は阿求氏の邸宅。阿求氏の転生を待っていたと見られる。阿礼乙女の転生には百年近くかかると、知らなかったのであろうか?
文責:射命丸 文』
(了)
7スレ目>>289
──────────────────────────────────────────────────────────────
「今日も結構冷えるなあ」
夜半、布団に入って一人言ちる。
もう7月半ばだというのに梅雨も明けず、熱帯夜も少ないことになっている。
薄手の寝巻きと毛布、タオルケット一枚ずつでは、正直少々肌寒い気温である。
「まあいいや。寝よう」
毛布を体に巻きつけ、枕に頭を乗せる。
目を閉じて二息した辺りで障子戸の外からずるずると、
何かを引きずるような音がするのに気づいた。
何の音かと訝しんでいると、ゆっくりと障子を引き開け、毛布を大事そうに抱えた阿求が顔を出す。
声を掛けようかとも思ったが、面倒なので右目だけ明けて様子を見ておく。
すると阿求はこちらを観察するようにじっと見つめ、やおら決心したようにまた動き出す。
障子を閉め、引きずる毛布でつんのめりそうになりながら近寄ってきた。
足元まで寄ってきたら、持っていた毛布を大きく広げ、俺の上に掛ける。
毛布持ってきてくれたのか、と思っていると阿求はそのまま出て行かず、
俺の背後に回り、布団の中に入り込んできた。
頭をぴったりと首裏に付け、左腕を脇から腹に回してくる。
こそばゆいのを堪えてそのままでいると、更に体を寄せて密着してくる。
そのまま幾らかの時間が経ってから、寝返りを打つふりをして阿求の方に向き直った。
両目を明けて阿求の顔を見ると、随分安心したような表情で目を閉じている。
とりあえず枕の端に申し訳程度に乗せている程度だった頭を、深い位置に乗せかえてやり、
頭を2,3度撫でたところで阿求も目を開けた。
「起きて……いたんです、か」
「いや、こっちこそ起こしたか?」
「いえ、私は先刻からずっと……」
どうにも両方起きていたらしい。
「起きていたんなら、目を開けてればいいのに」
まあ、人のことは言えない訳だが。
「え……それは、そのですね……」
「? どしたの?」
「あなたの……匂いをちょっと、覚えようかと……」
頭に疑問符が12個くらい浮かぶ。匂い?
「何で匂い? しかも目を閉じて」
「わ……私は見たものを覚えるのは得意なんですが、そうじゃないものは……」
「苦手なのか」
「はい……」
阿求がこちらから目をそらすように頭を伏せる。
首元に阿求の額が当たる格好になるので、髪の毛が首に当たって大分くすぐったい。
「何でそんなもの覚えようと」
頭を撫で擦りながら言う。
「皆覚えたいんです……あなたのことを……。姿も声も、匂いも」
そう言って阿求が顔を上げる。
「お嫌ですか……?」
そう言う阿求の目は幾らか潤んでいる様にも見える。
「嫌……」
そう言うと阿求は顔色を失った。が、続ける。
「嫌ではないけど……覚えるのはそれだけ?」
「え?」
阿求の顔色は戻ったが、疑問符が浮かんでいる。
「覚えるのは外見とか声とかだけでいいの?」
そう言ってだんだんと顔を近づけ、うっすらと桃色に染まった阿求の
(ここから先を読むには閲覧権限を取得してください)
うpろだ266
───────────────────────────────────────────────────────────
-幻史編纂恋史-
――それはふとした切欠、と言うモノだ。
ここ、幻想郷の人里に住む、幻想郷の「中」では普通な方の人間。名は○○。
強いて挙げるなら、そうだな、「本を読み漁るだけの能力」とでも言っておこうか。
程度でもなく、だけ。勿論、趣味なんてこんな根暗なモンしかなく、
家の畑仕事や寺子屋なんかが済むと行き付けの黴臭い本屋へ向かう訳だ。
いや、友人が居ない訳でもない。ただ、お互い色々仕事がある訳で。まあ、
外の本で目にする限りには自分の歳だとまだ勉学に勤めている時期なのだそうだが、
そこまで深く何かすべき事がある訳でもなく、余った時間を全て趣味に投げ売ってしまう。
最近は、本屋中の本を全て読み漁ってしまい、本を買いもしない俺は
行き付けの本屋から目の敵にされつつある訳だが……。
外の世界に行ってみたい、そんな風に考える事もまま有る。
だが、いかんせん情報量が少なすぎる。何より、外より流れ着いた、それも
ほんの僅かな本如きで手に入る情報など高が知れている。
故に、今日も今日とてこんなボロ臭い本屋に入り浸っている訳だで……。
もはや特等席となった、良く陽の当たる壁際に腰掛けて。
「……○○さん、でしたっけ?」
「は……はぇ?」
唐突に掛けられた声に、俺はまともに反応出来ずに腑抜けた声を漏らしてしまう。
目線を上げると、何処か見覚えのある少女が逆光を背に立っていた。
「……阿求さん、だっけ?」
「はい。お久しぶりです」
稗田阿求。九代目の御阿礼の娘とやらだそうで、時たま寺子屋に資料なんかを持って来て
くれたりする。病弱な家系らしいんだが、幻想郷中を飛び回って色々調べ物してたりするとかで、
案外アクティブな娘なのかもしれないと思ってる。年格好は俺より小さいくらいなのにな。
まあ詳しくは知らないが、本を多く読む関係上、寺子屋で顔を合わせた時なんかに
良く話すんだ。最近はそんなに顔も合わせなかったけど……。
兎角、何故だか分厚い本の山をたくさん抱えて、目だけは興味津々に、俺の読んでいた本、
「妖怪と人間の関係」を覗き込んでいた(どうやら初版らしく、ボロボロだ)。
「……それ、著者分かります?」
「著者ですか? えーと……あれ、稗田?」
目の前で微笑を浮かべる彼女と同姓の人物の名がそこにはあった。
どうやら、前代の稗田家の者がまとめた物らしい。記されている内容をかいつまんで言うとすれば、
殺伐幻想郷ライフ、貴方はこの惨劇から逃れる事が出来るか、みたいな事が書いてある。
……良く分からんのだが、今は八雲さんとこの藍さん辺りに笑顔で挨拶出来る時代です。
「六代目の御阿礼の娘が書いたんですよ」とエヘンプイな阿求。お前さんが書いた訳じゃ無かろうに、
なんて無粋なツッコミを入れようか迷ったが、とりあえず「ふーん」と返しておく。
「……あんまり好反応じゃないですね?」
「あ、すみませっ。いや、別に、えーと……」
上手い反応が思いつかなかったのであたふたしていると、阿求はため息一つの後、抱えていた本の山を
ズドンと俺の目の前に叩き落し、その内の一冊を俺に差し出した。
あんまりな出来事に目を白黒させていると、阿求はニッコリと笑って言うのだった。
「幻想郷縁起! さぁ、私の、いえ、私達の偉業を少しでも多く記憶するのです」
「は……え?」
「……じゃなくて。えーと、あの、幻想郷についてまとめた本です。折角ですから
ここで会ったご縁と言う事で、一冊差し上げます。その様子では、この辺の本にも退屈して来た
トコロのようですし」
え、と呻くと、店主の咳払いが聴こえた。申し訳ないのだが、持ち合わせはあっても大抵の本は
手に取って一時間もあれば読み干してしまうので、買う事が滅多に無いのだ。
「でしょう? ですから、この本をどうぞ。少なくとも、貴方の時間潰しには成ってくれるはずですよ」
「え……と。良いんですか? あの、御代とか」
ポケットをまさぐるも、寺子屋帰りの身では何か入っている訳も無く(置き勉ってヤツか?)、
鞄さえも持ってない自分に持ち合わせがあるはずも無い。両のポケットがまるっきり
空なのを見て、阿求は申し訳無さそうに苦笑した。
「構いませんよ。御代なんかより、見て貰い、記憶して貰う事にこそ価値があるんです。
ここに置いて貰うつもりはありますが、御代は気持ち程度で良いと断ってありますからね」
「そうなんですか……」
ページをめくると、なんとまあ可愛らしいイラスト付きで読みやすさを感じる。おまけに
聞いたことはあれど見た事も無い色々が載っているようで、これは読み耽らざるを得ない……。
と、また一つページをめくろうとした瞬間響く不快そうな咳払い。
「……ちゃんと家で読んで下さいね?」
「あ、えっと、そうですね。あの、何だかわざわざありがとうございましたっ」
阿求に礼を言い、俺は陽射しに目を細めながら立ち上がる。
小脇に幻想郷縁起を抱え、店主に儀礼的に一礼してから店を走り出る。
と思ったら、ワンテンポ遅れて阿求も一緒になって出て来た。抱えていた幻想郷縁起は
手元にもはや無く、小袖を軽快に揺らしてすぐ傍に駆けて来た。
「まあまあ。そう急く事も無いでしょうに」
「いや、別に急いではないですけど……まだ昼下がりですしね」
つい先程昼飯は食べ終え、眠くなる頃合。本に読み耽っていればそんな事も無いのだが、
今日は流れでいつの間にか本屋を出てしまっていた。
「甘味屋にでも行きましょう。ね、どうせ退屈なら」
「え、でも俺持ち合わせ無いですよ?」
「大丈夫」
袖の裏から現われたのは、やたらと重厚感溢れる大きながま口の財布。
「御阿礼の娘を侮るなかれ、です」
そう言って笑う彼女は、何故だか以前よりずっと楽しそうだった。
「おいひいでふゅ」
甘味屋名物の杏仁豆腐を頬張りながら、阿求はうっとりとそう言った。
「口の中はちゃんと空にしてから喋りなよ……」
「……んむっ、えぇ。だって美味しいものですから」
いつの間にか打ち解けていたと言うか何と言うか、俺は既に敬語ではなく普通に友人と
会話するような空気で彼女と話していた。それでも阿求の敬語は癖みたいなものらしく、
俺側が軽くなろうとも、その丁寧な言葉遣いは揺るがなかった。
「んー、こう言う所に来るのも久しぶりかもしれません」
「そうなの? あっ、ちょっ待てそれ俺のさくらんぼ!!」
何気無い動作で即座に掠め取り、皿のさくらんぼはいつの間にか阿求の口中に収まっていた。
「欲ひーのなりゃ取って御覧なしゃいなー、ほへほへー」
「ぬぬぬ……」
阿求の舌先で踊る、淡い紅色の小さな果実。好きな物を最後まで取っておく俺としては、
非常に心苦しい痛手だ。これで彼女と恋仲でもあったなら、無理矢理にでも奪い去ったんだろうが……。
待て待て、何を考えているんだ俺は。
「……んみゅ。御馳走様です!」
「あぁぁぁ、俺の分が……」
そうこうしてる間に、哀れ俺のさくらんぼは阿求に奪われてしまった。卑猥な意味に聞こえるのは気のせい。
ま、奢って貰ってるんだからこれくらい……やっぱり惜しいな、くそぅ。
「……良く来たりしないの?」
「えぇ。自慢じゃないですが、私御阿礼の娘の中でも歴代一番体が強いらしいのですよ。なので、
人里にこもるより散歩してる事の方が多いんです。だから、こう言う機会も少なくて」
またもやエヘンプイ。この動作だけ見れば、裏に隠れた歴史家的な一面なんて見えないんだろうな、
なんて思う。少なくとも、俺の目に映る彼女は、純粋に今を楽しむ少女の姿をしている。
「そっか。じゃあ、暇な時は何してるんだい?」
「そうですね。編纂も大体一段落しましたし……まあ、貴方と同じと言った所でしょうか」
言うと、阿求はテーブルの上に置いてあった幻想郷縁起を手に取る。
「あとは、散歩とかかな。少なくとも、貴方よりは結構外に出てるつもりです」
「失礼な。何だよ、どうせ引きこもりだよ」
「ふふ、本だけでは分からない事だってたくさんあるものですよ。ですから」
阿求は幻想郷縁起を開くと、幻想郷の様々な場所が記されているであろうページを開いた。
「こんな風に、見やすさを追求して絵も入れてみた訳です」
「ふーむ」
それらの絵は、むしろ絵と言うより随分写実的な構図で描かれていて、その割にやたらと
活き活きしていて、何と言うか、分からん!! 要は上手いんだよ、絵が。
「だから、ね。幻想郷にはこんなに美しい自然がある。それに、妖怪と私達の、
人間との関係も良い方向に変わって来ている今がある。だから、知って貰いたいんです。
少しでも多くの人に、幻想郷の素晴らしさを。人妖問わず、ね」
そう言って笑う阿求の笑顔は、何処か儚げに見えた。
何故だろう、なんて首を傾げる間も無く、彼女の笑顔からそんな薄らぼやけた影は消えていた。
……幻想郷か。中に居るのに、何も知ろうとした事が無かった。
外は危ないから。その一言で片付けて、大人達の言いつけを守って、未だにこの本に記されている
ような美しい場所の数々を覗き見た事さえ無い。
「ま、そんな事より。イタダキですっ」
「あ、ちょっ俺の蜜柑うわああぁぁぁぁぁ」
何の脈絡も無く、俺の思考と言う静寂を打ち破って阿求の不意打ちが襲う!!
さくらんぼ<蜜柑の俺に特攻ダメージ!! 話に熱中していた隙を突き、阿求は俺の蜜柑を奪い取った!!
気付けば俺自身何を食ったのか思い出せないほどに虫食い状態の杏仁豆腐が残されていた!!
……あーんにんどーふ。
「わたひがおごってりゅんだから……んくっ、ご馳走様! 良いでしょう?」
「おぅあ、あぁ。そうだけどもね……ひでぇ」
とりあえず残りを虚しくかっ込み、蜜で流し込む。男として、過去は振り返らないのさ……。
むしろそんな事を思う脳内が拘ってるって? あぁ、その通りかも分からんね。
勘定も済み、店を出て昼下がりの人里を二人歩く俺と阿求。
昼も終わりが近いが、まだ仕事に仕事で往来を駆けずり回る人も多いようだ。
仕事……らしい仕事なんて、ここには畑仕事くらいしか無いような。いや、でも
俺の認識してるモノが少ないだけで、実際は違うのかもしれないな。
魚屋の兄ちゃんに「随分不釣合いなカップルだなぁ!」なんて囃し立てられて、
俺と阿求は二人して黙りこくってしまった。
……俺? そうだな、正直あんまり仕事はしてない。本を読んでるせいか、
随分と頭の出来た子供だと思われているらしい。別に、生活や人生に活かしている
訳でもないのに、将来に期待されているという訳だ。
どうせ自宅警備員に……え? 今なんか良く分からん単語がパッと脳内に出て来た。
「あ、あの」
「あ、うん?」
疲れてるのかな、なんて目尻をマッサージしていると、阿求がおずおずと声を掛けて来た。
「どうした?」
「えと、その。忘れないで下さいね」
ビシィ、と効果音が付きそうな動作で、目線少し下から俺を指差す阿求。あーと、いや別に
不快ではないんだが、周りの目はちょっとばかし気にして下さい。
「私が奢ってあげたんだから、今度は貴方の番です」
「あはは、そうだな。御馳走様、また御馳走になってやる」
「んなッ。卑怯です! 次は貴方の番ですよ! ちゃんと奢って貰います、また会うんですからね!」
そんなやり取りをしている内に、いつの間にか俺の家と阿求の家との岐路に辿り着いた。
気付けばもう日も暮れ始めていて、随分と大きな鴉の影が夕陽からこちらまで伸びていた。アレ、
妖怪なんじゃなかろうか。
「あ、そうです」
「ん?」
阿求は、もはや四次元ポケットと化した袖の下から何やら煤けた紙を取り出した。あ、
四次元ポケットとか言うのは、向こうの世界に居るらしい青い狸型機械人形の持ち物だとか。
そんな奇々怪々な物があるなんて、向こうは面白そうで困る。
「真新しい本が欲しいのでしたら、こちらへ行って見ては如何ですか?」
「……香霖、堂?」
何だか長い事倉庫にでも放っておいた紙切れのように古ぼけたそれには、香霖堂と言う、恐らく
雑貨屋? いや、道具屋だろうか。兎に角、初見の店の名と地図らしき物が記されていた。
「えぇ。外界の本もありますし、面白おかしな物もたくさんありますから」
「ほうほう。ありがとう、行ってみるよ」
「それと……」
先程見せた、霞みそうな笑顔と共に、彼女は言葉を続けた。
「また、逢えますか?」
「勿論、会いたい時に会えるさ。今度は奢ってあげるよ」
口元に笑みを浮かべたまま、彼女はやたらと速い動作で振り返り、一時俯いたように見えた。
――が、見間違いだったのかもしれない。振り返った彼女の顔にあの憂いのある陰りは消え、
本当に楽しそうな顔でまた笑ってくれた。
「ありがとう、ございます」
「こちらこそ。んじゃ、また会おうな」
「……えぇ。それじゃ、また――」
手を振り、歳相応の少女の姿で駆けて行く阿求の姿を、夕陽の中俺はただ見つめていた。
……今度は、蜜柑取られないようにしなくちゃ、な。
蜩が鳴いている。距離が近いせいか、あの夕暮れ時に響く
儚げな美しさは、その音色からは感じられなかった。
ただ、単純な音量だけは大きくとも、漂う弱々しさはどんなに
距離が近くとも蜩そのものな気がした。
――その内に事切れた蜩は、最期にジリとも鳴かずに庭へ転がり落ちた。
その様子はまるで、私自身のように見えた。
少しばかり気分が悪くなって、私は優しげな夕陽から逃れるように障子を閉める。
最期に寄り添う伴侶も居らず、孤独に果てた蜩。
子孫を残す、と言う生物の、種としての存在理由さえ果たせなかったこの者は、
終わりのその時に一体何を思っていたのだろう。
私は、こんな風には成りたくない――
机の上には、未だ編纂を待つ未解決、未整理の資料が並んでいる。
だけど、手を付ける気にはなれなかった。良く分からない不安が押し寄せて来て、
この部屋の暗さのように頭の中が真っ暗だ。
……何故、あんな事をしたのだろう?
どうせ、一緒には成れないのに。
成れたとしても、彼よりずっとずっと先に死ぬ事に成るだろうに。
何より、私は彼にそんな辛い想いをさせたくない。
……別に、○○さんは私の事を好きだ、なんて思っては居ないでしょうけど。
けど、私は彼と居たいと想ったんだ。いつの間にか、話している内にだろうか、
寺子屋で会った時には、そんな事思ってなかったのに。
妖怪ならば良い。私が転生して帰って来れば、また知人として、友人として
迎え入れてくれる。だけど、人間の場合そうも行かない。
私は人とは違う。彼や、あるいは他の人間達と同じ時を過ごす事は、
叶わぬ幻想なのだろう。
――独白を書いている内に、普通の人間で在りたい、なんて思ってしまったのだろうか。
ふふ、閻魔様に叱られてしまいますね。私は、そう在るように生まれついた存在じゃないか。
私のような優秀な書記が消えてしまえば、閻魔様も惑乱する事だろう。
こんな事、考えるだけ、行動するだけ無駄なのかもしれないな――
再び、障子を開け放つ。
先程よりほんの少し落ちた陽は、優しさと言うよりは無機質で生命を感じない、
感情の無い光に見えた。
屍と成った蜩は、変わらずに庭先に転がっていた。
……彼の、傍に居たい。
例え、この蝉のように成ってしまう私でも。
――私に、そんな資格はあるのかしら?
「はろう☆」
「ひやあああぁぁぁ!!?」
花屋の娘と遊んだ時、カキ氷の余った氷を背中に注がれた事がある。
そんな夏のある一日を鮮明に思い出してしまうくらい唐突に、背後から
気味の悪いハイトーンボイスが響いた。
「ななッ、なんっ、なんでスか!!」
「あらあら、声が極端に上ずってるわよ。可愛いわねぇ」
驚いた勢いで飛び出した庭の砂利を両手で味わいながら振り返ってみれば、
妖怪の賢者こと八雲紫が、相も変わらず不気味な笑みを浮かべて佇んでいた。
……一応の編纂についての打ち合わせは済んだのに、何の用かしら?
「っう、げふん……えーと、何か御用ですか? 幻想郷縁起の方でしたら、
指摘箇所は直しましたし、現在進行形で編纂も行ってますよ?」
「えぇ、ちょっとね」
起き上がり、居住まいを正しながら紫様を部屋へと招き入れる。
夕陽はついに山向こうへ隠れ、逢魔ヶ刻の空は紫様の金髪を妖しく染めていた。
お茶でもお出ししましょうか、なんて言い出そうと立ち上がりかけた瞬間、
紫様の白魚のような手がそれを制された。
「恋に生きるのは良いことですわ。求聞持の力を持てど、所詮貴方は人間なのだから」
「……えと、気付かれていたのですか?」
従者を呼ぼうとするその手が止まる。
胸中は、いつの間にか行動に現われていたのだろうか。自分では、
いつもと同じように散歩していただけのつもりだったのに、目が人里に、いや、
○○さんに向いていたのだろうか……。
「えぇ。貴方、自分でも気付かない内に里に居る頻度が増えてますわ。意中の子が
居る事くらい嫌でも分かります」
「……私が人間とて、想い人を現世に残せるほど私は強くありません」
――そう、一人に成る恐ろしさは、私が一番知っているから。
「ならば――」
フッ、と目の前から紫様が掻き消え、真後ろから惑わすようなあの声が聴こえる。
「――ならば。成ってみる? 妖怪にでも亡霊にでも、輪廻の輪から外れた存在にでも。
もう恐れる事は無い。妖怪や蓬莱人のような、死から蹴り出された存在がいくらでも居ますわ。
孤独を感じる事なぞ、須臾の間さえ無い」
「――お断り、します」
「どうして? もう幻想郷縁起なんて要らない時代なのに?」
蜘蛛のように絡みつく指先が、私の首元を這い回る。
胃に込み上げるような気持ち悪さがせり上がって来て、いつもは明瞭過ぎて悩ましい
ほどの頭脳が音を立てて凍りついて行く。
「……嫌だと言ったら、嫌です」
ツ、と唇の辺りまで来た白い指先が止まる。まるであの骸と化した蜩のように、
生命の息吹が感じられぬ冷たさがあった。
「……貴方の優秀な思考回路は何処へ行ったのかしら。何故嫌なの? 貴方の
論法に、根拠が欠如しているのはらしくないわ」
「それ、は……」
息を詰まらせたように、言葉が出て来ない。
私の存在意義。幻想郷縁起を纏め上げ、人間と妖怪の橋渡しをする存在に成る事。
今は、確かに妖怪を危険視する時代ではない。独白にも書いたが、私の存在は
もはや要らない物となりつつあるのかもしれない。
……でも、それならば。今居る私自身が私自身たる理由は……?
幻想郷でさえ幻想になった存在は、一体何処へ行き着くのだろう……?
「まあ、『時間』はありますの」
重苦しいその嫌悪感は、速やかに去った。
「……」
「尤も、『考える時間』があるかは分かりませんけどね」
皮肉めいた、そして嘲笑めいた笑みを浮かべて、紫様は暗い空間の切れ目へと
沈むように消えていった。
――時間は、ある。それこそ、私が死んでも永遠に。
うpろだ387・400
───────────────────────────────────────────────────────────
「すごい音だな」
「台風ですから」
「固定してるのに、雨戸もやたら揺れてる」
「台風ですから」
「向こうが騒がしいけど、雨漏りでもしたのかね」
「台風ですから」
先刻から同じ答えしか返ってこない。
「阿求、何でそんな奥のほうにいるの?」
「台風ですから」
「……」
暗がりの奥に阿求はいて、顔は良く見えない。
しかしこれは……。
「あきゅんたいふうこわい?」
「台風dいえ、怖くはありませんよ」
何度も経験しましたし、と声を小さくしながら続けるもそれにまったく説得力は無い。
これは明らかに怖がっている。
「怖いなら怖いって言っていいのよ」
「はい怖いです」
心地良いまでの即答痛み入る。そこまでか。
「別に強い台風って言っても、家が壊れるほどじゃないでしょ」
せいぜい屋根瓦が吹き飛ぶ程度、と付け加えると阿求から笑みがこぼれた。
「そ……そうですね。ここまで怖がることはありませんよね」
「そうそう、伊勢湾やマエミーに比べれば何のことも無い」
比べるものが間違ってる? まあ多少大きいものと比べた方がいいだろう。
「それでは落ち着いたところで、少し書き物などしてきますね」
そう言いながら立ち上がり、書斎へ行こうとする阿求。
外の廊下を使った方が早いだろうに、内の部屋伝いに行くのはやはりまだ怖いからか。
「それじゃ俺は夜に備えて横になってこよう」
夜に何をする気なんですか、と突っ込まれたが何のことは無い、ただの昼寝である。
各々やることをしに動こうとした時に、不意にそれは来た。
ガオンという轟音とともに屋敷が揺れ、遅れて風の吹き込む音が聞こえ始める。
「お。どっかの屋根瓦でもぶつかったか?」
見に行こうとした瞬間、腰をつかまれる。
「いやー。やー」
見れば阿求が泣きながらしがみついている。
「遠くでぶつかっただけで、ここにゃ被害は出んよ」
そう言いながら頭を軽く撫でてやると、幾らか落ち着いたようで泣きはしなくなった。
「じゃ見に行ってみようか」
「うにゃー」
抱きつく力をさらに強める阿求。からかいすぎたろうか。
「っていっても一応俺も少ない男手だし、見に行かんわけにも行くるまいよ」
言うとしがみつく手が少し緩まる。
「じゃあ、書斎に送ってから見に行くから」
もう少し力が弱まる。
「じゃほれ、行くよ」
言うが動かない。膝立ちのまま、じっとこちらの腿に顔を埋めている
「どうしたの。たっちは?」
「子ども扱いしないでください」
顔を上げ、やっとといった風情で阿求が声を出す。
「ん。で、どしたの」
「今ので腰が抜けました……」
「あ、あらら」
さて、どうしたものか。
手の塞がっているだろうから、女中さんらを呼ぶわけには行かない。
なら、ここで休ませておくのが上等だろうか。
「休む? 畳の上でいい? 布団引く?」
といってもこの部屋に布団はないので、持って来る必要があるが。
「いえ、とりあえず書斎に運んでください」
「でも、休んでいた方が良くないか?」
「書斎に行きたいんですっ」
強く言い切られてしまった。
書斎に何かあるのか……そういえばあそこは奥のほうにあったっけ。
「さて立てないんじゃどうするかねえ」
肩を貸すわけにも行かないし、背負っていこうか。
さてそれでは背負い紐を調達してこなければいけない。
「抱っこ」
「そうさね。背負ってえなに?」
「抱っこしてください」
抱っこ。こっちの腰が死ねる。よって却下したい。
だが、両腕広げて待っているのを見捨てるわけにも行かない。
……覚悟を決めるより他あるまいか。
阿求を横座りにさせ、左腋より腕を入れて背側に通し、右腋をつかむようにする。
同時に膝の下にも他方の腕を差し込み持ち上げ、俗に言うお姫様抱っこの状態にする。
「重い。落としそう」
「女の子に重いなんて言っちゃいけません」
そう言って阿求は肩に顎を押し付けてくる。
肩のツボが押されて地味に痛い。
「痛いでしょ。そんなことやってると落とすよ」
「きゃーおとさないでー」
そう言って阿求は腕に力を込め、顔を首筋に寄せてきた。
阿求の吐息が首にかかリ、大分くすぐったい。
「じゃ行くかね」
ふらふらと歩き始める。
普段なら1分、40歩かからない程度の場所に、
途中何度か落としそうになりながら、じっくり5分以上かけて進んでいく。
「はい、着いたよ」
言いながら、座布団の上に降ろす。
「ありがとうございました」
言うと阿求は座りなおし、背筋を伸ばして筆記机に向かう。
「それじゃ見てくるか」
「気をつけてくださいね」
外回りの廊下をのそのそ歩き、破損箇所を探す。
が、特に見つからない。
二週目に突入するがやはり見つからない。
「戸袋にでも当たったのか……?」
まあいい。目に見える被害がないなら、今はそれで上等だ。
「ただいま」
「おかえりなさい。どうでした?」
「何も壊れてないね。添え木なりにでも当たったんじゃなかろうか」
阿求の傍に胡坐をかき、言う。
「見た感じ被害がないようなんで、安心して寝れるわ」
足を伸ばし、敷いていた座布団を除け横になる。
「寝るのは構わないんですが……」
服の上のボタンをはずし、ベルトを少し緩め寝やすくする。
「何でここで寝ようとしているんですか?」
「阿求がいるから」
言いながら阿求の座っている座布団を机の影から、阿求ごと引き摺り出す。
「えっ……それはどういう」
「ん、いい高さ」
問いかけは無視して、膝の上に頭を乗せ幾らか揺り動かす。
「じゃ、おやすみ」
「膝で寝ないでください。重いでしょ」
「じゃあ、膝枕はやめよう」
座りながら言い、座布団を頭を置く方向に放り投げ、阿求を引き倒しながらまた寝転がる。
「何するんですか」
「……添い寝?」
「される方ですか?」
阿求が言っている間にこちらは座布団を二つに折り、頭をのせる。
引き倒した阿求を抱き寄せ、頭の下に左手を差し入れて座布団の上に乗せさせて、
また右手を後頭に当てる。
「まあ、いいじゃないの。台風なんだし」
と、阿求の頭を撫でてやりながら言う。
そのまま阿求の頭頂に顎を乗せる形に、あるいは頭を胸に抱きかかえるように体の位置を変える。
幾らか抜け出そうと阿求はもがいていたが、やがて観念したか、離そうと突っ張っていた左腕をこちらの脇腹にのせると、
「台風ですし、まあいいかもしれませんね」
と言って体を引き付け、やがて双方静かに寝息を立てていった。
<<その後>>
時間経てども台風未だ過ぎず、風雨未だ強し。
さすがに何時間も雨戸が揺れ続けていれば不安になってくるし、
何よりうるさくて眠れやしない。
「寝れん」
そもそも昼間に2時間寝たのが悪かった。
「というか何でこんなに風が強いままなんだ」
台風なんて6時間程度で過ぎるものじゃないのか。
もうそのくらいは経ったはずだ。
「まあ、寝て起きれば晴れてるはずだな」
言いながら毛布をかぶり、寝ようとする。
「やはり寝れん」
人間は寝溜出来ない生き物なので、あまり寝すぎることも出来ない。
本でも読んでいようかと思ったが、そういえば燈油が足りないという話なので、
おいそれとそれも出来ない。
風が幾らか止んでいれば外に出て散歩でもしていればいいのだろうが、
こう風が強くてはそれも出来ない。
(あきゅんの寝顔見物にでも行こうかしらん)
うむ、そうしよう。見つかったらその時だ。
早速足音を消すための厚手の靴下を探そうとした時、外の障子の闇が濃くなった。
かたり、と小さな音を立て障子が開く。現れたのは阿求だった。
「やはり起きてましたか」
近寄ってきた阿求が小声で言う。
「どうしたの? そっちも眠れない?」
こちらも小声で返すと、阿求は小さく頷いた。
本でも読んでいればいいのに、と言うと阿求は燈油が切れたと答えてきた。
「ですから、何か向こうにいた時の話でもしてもらおうかな、と」
さてやこれもなにかのネタにでもするつもりなのか、阿求が言ってくる。
しかし、狭く深くの交友関係だった自分には人に話すような話はさしてない。
とはいえ昔話なんぞやろうものならこっぴどく叱られそうだ。
いっそグリム童話あたり話してしまおうかとも思ったが、そも俺が覚えていない。
あたりは真っ暗。秋口とはいえ、台風の最中で未だ蒸し暑い。
「では覚えているのを幾らか。信じようと、信じまいと―」
翌日、毛布に包まり眠る阿求と、敷布団の下にいる俺がいた。
うpろだ404
───────────────────────────────────────────────────────────
この家の主が息を引き取ろうとしていた。
本当に短い間の命を、ただただ書く事のみに捧げ死んでいく。
それを何代も何代も続けているのだという。
「お世話になりました」
「いえ、このくらいなんでもありません」
「それでもです。お礼を言わせてください」
弱弱しく言う。
あぁ、やはり死ぬのだと再確認する。
もしかしたらちょっと風邪を引いただけなのかも、と望んでいたけれど。
ならば、言わなければいけないことが……
「私は……」
「言わないで下さい」
「…………」
「命短い私に、その言葉は重過ぎます」
「…………」
「泣かないで下さいよ。死にそうで泣きたいのは私なんですから」
「はい」
それでもあふれる涙をとめることは出来なかった。
それから無言でどれほどの時間いたのだろう。
ようやく涙が枯れたときには、沈みかけていた太陽はすでになく月が南の空にかかっていた。
「そろそろ……逝きますね」
「はい」
「これから息災ですごしてください」
死んでしまう。
最愛の人が。
勇気を振り絞る。
「必ずまた会います。そのときは先程の言葉を必ず聞いていただきます」
「急になんですか?
私は数百年単位で転生を繰り返しています。それに私はそのとき男か女かわかりませんよ」
「存じています。でも、必ず会います」
そう、これは強い意思。
「あなたが生まれ変わるとき私は必ずそこにいます。
あなたが女性なら男として、男性なら女として」
「閻魔様が許すとも思えませんけど」
「いいえ、誓って生まれ変わります」
「それは楽しみです」
そういって瞳を閉じ、二度と開かなかった。
その後最愛の人に遅れること数十年、十分に長生きをして死ぬことになる。
「お初お目にかかります。私は○○と申します。
幻想郷の外の出身ではありますが、この度稗田家の使用人頭としてお世話させていただくこととなりました」
「はい、よろしくお願いいたします」
そういって目の前の少女はクスリと笑った。
何か変なこといったかな?
「それにしても、本当に生まれ変わった上にきちんと男性なんですね。○○は」
「はい?」
「いいえ、なんでもありません。
ところで何か言いたいことはありませんか?」
「? いえ、特にはございませんが」
不思議そうな顔をしている俺を見てまたクスクス笑う。
なんだ?
「ちなみに私にはあります。お久しぶりです○○」
「?」
「あのときの言葉を今度こそ聞きたい。必ず言ってくださいね」
「は、はぁ、何のことか良くわかりませんが」
「はい、でもきっと思い出してください」
「? と、とにかくこれからよろしくお願いいたします、阿求さま」
と、これが俺と阿求の出会い。
ちなみに俺がこの時の会話の意味を知るのは、もうしばらく後のことだった。
うpろだ457
───────────────────────────────────────────────────────────
夜の蚊帳が下りた薄暗い林の中を一人進む。
終わらない迷路のように続く林。
聳え立つ暗い木々は寂しく朽ち果て、多いというのにどこか空虚な印象を与える。
そんな冷たい場所の明かりはただ一つ、頭上の満月のみ。
ただ、月が仄かに照らし出そうとも、この場所の陰鬱な雰囲気は変わらない。
まるで死を暗示させるかのようだと、阿求は思った。
黒の木々を掻き分け、足音だけを響かせなお進む。
そして前方に初めて黒以外の色を見つけ、ふと足を止めた。
―――・・・血、だ。
木や地面に飛び散るようにこびりついた血はまだ赤く、
その血が流れてからまだあまり時間が経っていないことを示す。
そしてその更に奥に、自分が探している人物がいるということも。
「・・・○○、」
おびただしい程の赤の中心、闇に紛れるように佇む彼に声をかける。
手には赤く濡れそぼった斧。
辺りにはばらばらになった妖怪の死体。
どちらも、彼には似合わないものだと、無意識に考える。
と、その時、○○はゆっくりとした動作でこちらを振り返った。
「・・・阿求か」
彼はこの場には到底似合わない、明るい笑顔を向けてくる。
それには流石の阿求も小さく息をのみ、目を見張った。
「阿求、どうかしたのか?いつもは家で待っててくれるじゃないか」
「いえ・・・あまりに遅いので迎えに来ました。今日も妖怪退治、ご苦労様です」
帰りましょうか、と手を差し出し、○○に問いかける。
しかし○○はその手を取る事無く、小さくかぶりをふって悲しそうに笑った。
「○○・・・?」
「・・・悪いな。もう少しだけ、ここにいたい」
それは黙とうのためだろうか。
○○が殺してしまった妖怪に対しての。
罪滅ぼしにもならないのはわかっている。
殺してしまった内臓を直視したところで、罪が消えるわけではない。
ただ、自分はこれを仕事に選び、里の人間に感謝され、
そして阿求がそばにいてくれるだけだ。
阿求はそれに何も言わず、どこかに視線を彷徨わせていた。
二人の間に自然と沈黙が訪れる。
いつもは心地良い沈黙も、今は酷く気を乱される気がして、
○○は無意識のうちに眉根を寄せていた。
そう、この時はまだ分からなかったのだ。
自分の胸に巣食う、この言いようのない不安の正体を。
「○○」
「・・・っ、何だ?」
阿求の姿を見つめながらも、意識は思考の奥深くまで潜っていた○○は、
彼女の呼びかけにはっと意識を取り戻すと、平然と返事を返した。
「・・・こんな所にも、花は咲くんですね」
その言葉に不思議そうに阿求の見る先を覗き込む。
するとそこには、名も知らぬような小さな白い花があった。
「私は、この花のように生きてみたかった」
独り言のような阿求の言葉。
しかし○○は、それを黙って聞いていた。
慈しむような優しい手つきで、白い花に触れる。
ふわりと揺れた花は、何故か阿求自身のような気がした。
「誰のためでもなくただ花を咲かせて、誰に知られる事もなく、
でも最期まで自分を誇って散るんです。
・・・そして、今にも枯れてしまいそうな瞬間にも、こうして美しいと思ってもらえる」
ここには何もないかもしれないけれど。
ただ、静かに美しく咲き誇れるでしょう?
首をかしげてみせた阿求の表情は、何かを諦めたように潔いものだった。
だから、なのかもしれない。
彼女の言葉が、こんな場所で死ねたらいいのにと、そう聞こえたのは。
「素敵だと思いませんか?」
「・・・そう、だな。でも」
そんな事を、自分の前で言わないでほしい。
口にさえ出さなかったものの、○○の困ったような笑みに、阿求もふっと、笑った。
気付いているのだろうか、彼は。
自分がひどく泣きそうな顔をしているという事に。
そんなことを頭の片隅で思いつつ、阿求はぐっと拳を握り締めた。
「わかってますよ?・・・わかってます。けれど、○○、」
わかるでしょう?と笑う阿求を○○は、どうにもできず抱き寄せる。
情けない事に、自分の体が、言葉が震えている。
この先は言わせてはならないと、本能が告げているから。
「・・・私は、もう」
「阿求、それ以上言うな」
「もう、これ以上」
「阿求・・・っ」
「生きては、んっ・・・」
「阿求・・・!」
○○が言葉を紡がせないように、阿求の唇を塞ぐ。
息苦しいほどの口付けに、阿求は視界がぼやけ、意識が浮く気がして瞳を閉じた。
・・・これで私が死んでしまったら、彼はどんな顔をするのだろう。
そう考えたら、さっきまで何ともなかったのに、無性に泣きたくなった。
「・・・○○、聞いてください」
「聞きたくない」
「我儘言わないでください」
「どっちが、だよ」
ああ、泣きそうだ。
私も、○○も。
「ええ、すみません」
本当にごめんなさい、○○。
最後の、最期まで弱い私で。
でも、愛しいから貴方の手で、迎えたい。
「・・・我儘、聞いてくれますか・・・?」
その言葉に、○○はすっと目を閉じて、今にも泣き出しそうな空を仰いだ。
月はいつの間にか雲に隠れてしまっている。
涙が、頬を伝った。
「―――・・・○○」
ああ、これはきっと、喪失感だ。
俺はこうして、この世界で全てを失くすだろう。
今は鮮やかな色も、ゆったりと流れる刻も、大切な君でさえも。
「私を、殺して?」
それでも俺は、それに抗う術を知らないから。
(せめて最期くらいは貴方に手折られたいと、そう思っ た の)
「たとえお前がどんな姿になっていようとも、俺は必ず、見つけ出してやる」
「―――・・・ええ、また来世で逢いましょう、私の愛しき人」
そして俺は、動かなくなった君を抱いて、帰路につく。
10スレ目>>652
───────────────────────────────────────────────────────────