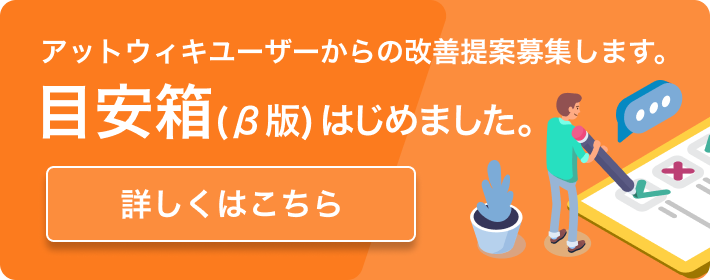プロポスレ@Wiki
紫5
最終更新:
orz1414
-
view
「ふわあ…」
(もそもそ…)
「う、もう3月…藍ったら、起こしに来てくれてもいいじゃない。」
今年も春がやってきたようだ。さて、そろそろ起きようかしら。
(のそのそ…)
いつもだったら、このままもう1年寝ていたいとか思っちゃうのだけど今年はちょっと違う。
今の私には、日々のゴロ寝と同じくらい楽しみなことがあるのだ。
そう、あれはもう半年も前の事だったかしら…
(少女回想中…)←まとめ、「紫2」の真ん中より少し下辺りの「~小劇~」より。
↑突っ込みたい部分あるかもしれないが黙って読んでくれると嬉しい。
彼は、なんとも変わった男だった。
どうやってこの迷い家までやってきたのか?
もしかしたらどこかに閉じ忘れたスキマがあったのかしら?
とにかく、ある日突然彼はやってきた。
そしてその日初めて会い、言葉など大して交わしてもいないのに
大真面目に、これ以上ない熱を込めて、私の事を好きだという。
あまりにも唐突で予想もできないその告白は
例えるならファイナルスパークをタメ無しで零距離照射されたかのようで
私の心は食らいボムを打つこともできずにこんがりと焼かれてしまったようだった。
あぁ、なんて不覚。この八雲紫、幾千幾万の弾をこの身にカスらせようとも
被弾を許す事なんて今まで生きてきた中でも数える程しかないというのに。
それをまさか、ぱっと見、何の「○○する程度の能力」もなさそうな人間に許すとは…
本当なら私が被弾を許すなんて悔しい事この上ないハズなのに
まんざらでもない気持ちになるのは身でなく心に被弾を許したせいかしら?
そう思うとやっぱりちょっと悔しいわ。
私は嬉しさ半分、悔しさ半分、それととっさの照れ隠しから
つい彼に意地悪を言ってしまった。それもとびきり絶望的な一言を。
「そうねえ…あなたがボムも復帰無敵もなしに私の弾幕をかいくぐって
私をさらってくれたら、貴方の物になっちゃおうかなあ♪」
「ΣΣ(゚д゚lll)」
ああ、バカな私。何言ってるんだろ。
人間にそんな事できるわけないじゃない。
彼は博麗でもない、魔法使いでもない、蓬莱人でもない。
そして私は⑨でも夜雀でも蛍でも毛玉でもない。
私が言ったこの一言が、普通の人間である彼にしてみればどれほどの難題か。
多分月のお姫様が出した五つの難題にも勝る難題だと思う。
でも彼は…
「紫様、なんですか、それ?」
「ああ、これ?撃墜マーク。」
「8個…愛されてますね…」
それから毎日、痛い目にあっても懲りることなくやってくる。
しかも毎日少しずつ、私の弾をよけ続ける時間が伸びているのだ。
コレはもしかしたらと期待してしまう。先は長いけど…
「難しくしすぎたかなあ…(´・ω・`)」
「ホントは攻略されたいんですね。」
「よくわかってるのね。」
「そりゃまあ、紫様あいつが来る時間帯は起きてますからね。」
なまじ彼が頑張るのもあって、今更言い出せないじゃない?
「あれはただのイジワルで言ってみたのよ」なんて…
それに彼が頑張るなら、ソレはソレで夢見たくなるのよ。
少女なら誰しも、 (←相変わらずスルー推奨)
『私をその両腕で抱きしめてくれる殿方には、
私を守ってくれるくらい強い男であって欲しいなあ』…って願うのは当然でしょ?
「ねえ藍、ちょっとあいつを手伝ってあげてくれる?」
「へいへい…でも紫様、あやつが気に入ったのでしたら、
紫様があいつの心なり人妖なりの境界いじっちゃえば…」
「それはダメよ。」
「なぜです?」
「それじゃあ私と彼の間には『主従』の関係が出来ちゃうじゃない。
彼が自分の力だけで私を攻略してこそ、
私と彼は恋する男と少女の関係を築けるのよ。キャッ(*ノノ)」
「はあ、さいですか。(汗)」
私は藍に彼の特訓をするように命じた。
藍は私のパターンを熟知しているし、一部は近い形で再現できるものもある。
もしうまくいけば、私が冬眠から覚めたころには、
見違える進歩を遂げているかもしれない。
(回想終了…)
と、言うわけで、私は期待に胸を弾ませならがら起きたのだった。
こんな気持ちで眠りから覚めるなんて、久しく記憶にないことだ。
もし彼が…本当に私を攻略できたら、なんて言おうかしら?
『よく頑張ったわね』
…う~ん、ありきたりすぎるからダメ。
『おめでとう、ご褒美は私よ♪』
これこれ、こういうの。でも、手加減したとか思われたら嫌だわ。
『こら、どれだけ待ったと思ってるのよ。』
うん、コレは私の素直な本音。
『ちゃんと責任とってよね。』
コレもいいわね。「何の責任」かあれこれ悩んでもらおうっと。
私が寝てたおよそ3ヶ月。
その間藍がみっちり鍛えててくれたのだ。
愛と欲を燃料に動く人間は、さぞかし見違える進歩を遂げているだろう。
あぁ、待ち遠しい、待ち遠しい。
幾年月をも生きた私だ。待ち遠しいなら寝てその時がくるのを待てばいい。
そう考えるのが常だったけど、今は彼の両腕に抱きしめてもらう
その日が来るのが待ち遠しくて仕方がない。
冬眠から覚めた今、1日だって待つのが辛い。
「むふふ…(じゅるり)」
そして今の私は、それを想像して笑みが漏れてしまっている。
こんな顔、絶対藍にも橙にも見せられない。
私はにやける表情を抑えて、平常心を取り戻してから寝室のふすまを開ける。
このふすまは、冬眠時に潜っている空間と通常の空間の境目でもある。
この部屋を出ればもうそこは、いつもの迷い家(我が家)…
(カラッ…)
「やあ、おはよう。それとも、あけましておめでとう、かな?」
「なっ…!?」
ふすまを開けてすぐの所に彼が立っているではないか。
(じゅうぅぅ…)
一瞬で顔が真っ赤になってしまうのが自分でも判る。
頭は茹ったようで思考がままならず、心臓は跳ねるように激しく脈うっている。
もしかしてずっと私が起きてくるのを待ち伏せしていたの?
いや、それよりももしかしてさっきの「むふふ」とか聞かれてた!?
「な、な…」
何でここに?それすらマトモに口に出来やしない。
私はスキマを使って霊夢の前や、幽々子の前に突然不意打ちのように登場する事はあるけど、
その逆、自分が不意打ちをされた事はない。
ひどい、これはひどい。そういえば初めて会ったときの告白もそうだった。
今はじめて判った。彼の能力はきっと「不意を突く程度の能力」に違いない。
「どうした?今日こそ起きるかなと、紫が起きるのを待っていたのに
だんまりで出迎えとはつれないな…」
「そ、そんなんじゃないわよ、ただ…」
「ただ…何だ、熱でもあるのか?顔真っ赤だぞ?」
「だ、大丈夫。大丈夫だからっ!」
今しがた妄想にやける表情を抑えて取り戻した平常心は、もう粉みじんに吹き飛んでしまった。
それどころか、真っ白になった頭は平衡感覚すら失わせ…
(よろろ…ばふっ)
赤面を見られまいと後ろを振り向こうとするも、
足がもつれて私は彼の胸につんのめる様に倒れてしまう。
「きゃっ…」
「全然大丈夫じゃないだろ。あんな空間で一人で寝てるからだ。
まってろよ、藍に布団の準備をしてもらおう。」
彼は私をひょいと「お姫様抱っこ」に抱え上げる。
どうやら、風邪で高い熱が出ていると誤解しているようだ。
だったら、このまま誤解していてもらおうかしら。
「(このまま風邪引いたふりしてたら、看病までしてくれちゃったりするかしら…)」
だって、あこがれのお姫様抱っこよ?
こんな王道的シチュエーションに巡り会えたら、以降のベタな展開も一通り味わいたいじゃない?
「(私が寝てる傍でずっと看病してくれたり…)」
「ところで紫。」
「(ゴハンのおかゆを『あ~んして』って、食べさせてくれたり…)」
「紫?」
「そ、そして汗で濡れた服を着替えさせようとして…そのまま勢いでっ!あぁ、ダメよそこまでは!」
「紫…(汗)」
「はっ!?な、なにかしら…?(ドキドキ…)」
しまった。ちょっとこの後の展開を妄想してぼんやりしたようだ。
えーと、私口に出してしゃべってなんかいないわよね?
「今の状態は…俺がノーボムで君を捕まえたって事にならないかな?」
「あ゛…」
や、やられたわ…GOOD ENDING No.2、
No.1条件は90日以内の正攻法攻略…って所かしら。
「そ、そうね…おめでとう、ご褒美に責任取ってよねっ!」
「何言ってんだ…?(汗)」
そのころ茶の間では…
「紫様起きたみたいですね。」
「うむ、そして○○は上手くやったみたいだな。めでたしめでたしだ。」
(ズズズ…)
藍と橙が、いまだにしまっていないコタツに入り、お茶をすすっている。
(橙の湯のみからは湯気が出てないからきっとすごくぬるいのだろう。)
ちなみにお茶菓子はガチガチに硬くなった正月のお餅の残りとにぼし。
「でも藍様怒られませんか?」
「何でだ?」
「紫様を起こしに行かなかったことと、○○の不意打ちを見逃したことと…」
「ああ、それは大丈夫だろう。紫様は○○に攻略されたいって、ハッキリ言ってたし
それに私は『○○を手伝え』って言った命令に従っただけだからな。ああ、でも橙…」
「はい?」
「紫様の不意を突けって、私が言ったのは内緒な。
○○は、自分の力だけで紫様を攻略した…わかるな?」
「…はい♪」
どうやら今回の彼の不意打ち…考えたのは藍のようだ。
もしかしたら藍の方が毎日一緒に居た分、彼の不意を突く能力に早く気づいていたのかもしれない。
さすが私の式、あなたが居て本当に良かったわ…ありがとう、藍。
(↑神速突撃で自爆させた件はなかったことに。)
こうして私の想いはみんなのおかげで叶ったのだった。
藍や橙とは違う意味で、私を大事に想ってくれる人が傍にいるというのは
なんともむずがゆくて、そしてなんとも心地よいものだ。
とりあえず彼には残る一生、私に幸せという名のゴハンを食べさせて貰おう。
それが彼の責任。年中寝ても起きても、私が幸せに飢えることがないように…
もし浮気なんかしたら、本当に食べてやるんだから…
6スレ目 >>837
───────────────────────────────────────────────────────────
家でまったりしていると、
いきなりスキマがひらいて、
紫が背中にしなだれかかってきて、
なにしてんだ。っと聞いたら
「○○分の補給。一日できれちゃうから。」っといわれた。
そのまま縁側で昼寝していたら藍が紫を迎えに来てた。
そんな日がしばらく続き…その年の秋のことである。
紫「貴方が居てくれたら、私はそれだけで(幸せで)お腹いっぱいなの♪」
(ぎゅっ…)
俺「(*´∀`)」
紫「だから…一緒に冬眠しましょ♪」
アッー…
7スレ目 >>109-110
───────────────────────────────────────────────────────────
「恋し 愛する事も、若さの秘訣だと思いませんか? 紫様」
7スレ目>>446
449 :名前が無い程度の能力:2007/05/07(月) 22:34:32 ID:cKRr5DW.0
>>446のセリフから幻視したのでちと書いてみる
紫「あらそれなら私はずっと若いままね」
○「へえ、何でそう思うんですか?」
紫「だって私は貴方に恋をしているんですもの」
○「奇遇ですね俺も紫様に恋をしてるんですよ
こんな形になっちゃいましたけど好きですよ紫様」
紫「それなら紫って呼んで……」
○「ええ、愛してますよ紫」
紫「……ん…ふぅ」
藍「…しばらく目を離したと思ったら何ですか?この状況」
幽「新しいカップルの誕生ね~♪」
橙「いいなー紫様ー!」
藍「ちぇ!ちぇちぇちぇちぇちぇ橙!?」
───────────────────────────────────────────────────────────
紫「ZZZzzz…」
○「…紫、寝た?」
紫「…ZZZzzz…」
○「(寝たかな…)」
(もそ…)
俺は紫を起こさないように、そ~っと布団から出ようとするが…
(ぎゅっ!)
強く捕まれて阻止される。
紫「(じー…)」
○「う、寝てなかったの?」
紫は恨めしいジト目…にも見える寝ぼけまなこで俺を睨んで…
紫「…抱きマクラが布団を出ちゃダメ…」
…と、有無を言わさぬ一言。
○「はい…」
毎夜こんな調子。あぁ、自制心フル稼働で、今夜も寝不足…
7スレ目>>565
───────────────────────────────────────────────────────────
「たとえ君にとって俺の一生が刹那の一時でも、共に歩んでいくことを許してくれるかい?」
7スレ目>>685
───────────────────────────────────────────────────────────
恋に溺れた、たった1つ。それだけ。
「紫様…ゆかりさまぁ…」
虚ろな眼で上を見ながら彼はただ呟いている。
最近の話だ、幻想郷の外から青年が1人やってきた。何かしらの原因でこっちに迷い込んでしまい、彼は元の世界への帰還を望んだ。
だが、ある日を境に彼は元の世界へ帰ることを望まなくなった。かわりに彼は言った。
「俺、紫さんとお話がしたい。」
博例神社境内の宴会の日、いつもは家に引きこもっていた彼も宴会のあまりの喧しさに外に出てきた。その時、彼は紫を見て恋に落ちる。
そこから彼は苦しみ悩む。
元から篭りがち性格が拍車をかけ、延々と悩んだ。
お話がしたい、俺を見て欲しい。
たとえ妖怪であろうと構わない、愛されたい。
殺されてもいい、愛されたい。
変態的な愛はみるみる膨張し、自分の内の殻を突き破ったとき通常の精神は飛散した。
彼は裸足で神社を飛び出した。紫さんに愛されたい、その一心でそこらを駆けずり回った。
途中身体が動かなくなって気を失っているところを霊夢に保護、すぐに霊夢は破綻した精神の治療を鈴仙に頼んだが結果は失敗。
「精神が一部が欠落しては波長の合わせようがない。」
それでも何とかならないかと話し合ってるうちにも、彼は両手足を縛られた身体で床を這いながら外へ行こうとする。
「芋虫みたいね。」
紫の声がした。
スキマから現れる紫、そして歓喜に満ち溢れた顔で地を這い彼は紫の所へ向かう。
「○○、ですわね?」
「はい!はい!そうです!!」
「こんなに縄で縛られて…」
紫は彼を束縛する縄を解いた。
「私がもう一度縛り直してあげますわ。」
紫は更にきつく、がんじがらめと言った風に縄で彼を縛り直す。彼は涎を垂らして悦んだ。
「私に愛されたいそうで…
私の奴隷になる?」
「喜んで!」
「じゃあ、私の足を舐めなさい。」
「はっ…!」
彼は紫の奴隷になり、スキマの中に放り込まれた。
「○○。」
「はぁああ…!ゆかりさまぁ…!」
彼は呼ばれて犬のように紫に駆け寄った。
「ほら、まずは足よ。」
「はい!あし、あしぃ…」
片足を彼に舐めさせ、余ったもう片方の足で彼を踏む。
「本当に変態な犬ね。そんなに嬉しいの?ねえ、嬉しい?」
「はい、うれしいです…!」
「ふふ、今日はそんな変態にご褒美よ。
数週間穿きっぱなしの私の靴下よ、口を開けなさい!」
「ふあ…あ、が!?」
紫は彼の口の中に黒い靴下を突っ込む。
「嬉しいでしょう?変態の貴方は靴下が大好きだものね?」
「…!…!」
言葉が出せず、頭を動かす犬。
彼の願いは叶った。
愛される。たとえそれがどんな形であれ、彼は愛されていると思っている。
彼は幸せだった。
うpろだ244
───────────────────────────────────────────────────────────
幻想郷に来て1週間が経過しようとしていた。
俺が居候をしているこの場所はマヨヒガと言い、何でも現実世界からの迷子たちがやって来る場所らしい。
「まぁ、俺もある意味では迷い子だよな」
最近俺のいた世界では『神隠し』が流行っていた。
その事についてぼんやりと思いを巡らせていた所、その『神隠し』の主犯と思しき人物・八雲紫が我が家に現れたのだ。
そして彼女との会話の中で幻想郷に興味を抱いた俺は、進んで彼女の『神隠し』に遭った。
これが事のあらましだ。
好んで現実から逃れた辺りが、俺が別の意味で“迷い子”たる証明だろう。
「しかし・・・ なかなかどうして良い所だな、此処は」
普通の人間にとって、幻想郷の日常や常識の中には受け入れがたいものもある。
「まぁ、初めて人の生頭蓋骨を見た時は驚いたけど・・・」
人間であるから、と言う理由でお遣いに出されて、その道中に頭蓋骨が一個転がっていた事があった。
流石にアレは驚いた。
同時に“自分は幻想郷にいる”と言う実感を持たせてくれた。
「みんな、俺の事を心配してくれてるかな?」
何も残さないで消えると本気で『神隠し』扱いされるので、一応テーブルの上に「ちょっと旅に出てきます」と書置きして休学届けを置いておいた。
「ま、俺如きが消えても悲しむ奴なんていないか」
元より自分が変わった人間である事は理解しているつもりだ。
もしかすると、心配するどころか内心喜ばれているかもしれない。
「・・・でもそれは少し寂しいな」
可能性は否定できない。
「あら、私は悲しいわよ?」
後ろからの声。
この声の主こそが、俺を幻想郷へと誘った存在。
「貴女が消えてしまったらね」
八雲紫。
このマヨヒガに住まう大妖怪にして、幻想郷最強と名高い存在だ。
「はは、それは食料が消えるからでしょうかね?」
「もう、食べないと言ってるじゃない」
この1週間で何度も繰り返された応対。
もはやこれがジョークの域に達している辺り、俺も此処での生活に慣れてきていると言える。
「だって食べてしまったら・・・」
しかし今回の彼女の反応は一味違った。
相変わらず、底の見えない微笑を浮かべたままこちらにやって来る。
ふいに、目の前が真っ暗になった。
「この感触も、匂いも、温もりも感じられなくなってしまうでしょう?」
言葉と一緒に流れてくる甘い香り。
魅惑的な罠の匂い。
つまり俺は彼女に抱きつかれたのだ。
「うわぁ!!」
女性に抱きつかれる、などと言う黄金経験の無い俺は、咄嗟に彼女の事を振り解いてしまった。
「あらあら、随分と初心なのね」
特に気にする様な事もなく、見慣れた胡散臭い笑みを浮かべる紫さん。
「じょ、冗談にしてもタチが悪いですよ・・・」
心臓が早鐘を打っている。
ただでさえ暑かったのに、今度は別の意味で暑くなってしまった。
「・・・・・・・・・・・・・・・冗談じゃないのに」
彼女はポソリ、と何かを呟いた様だけどよく聴き取れなかった。
「はぁ・・・」
溜め息を一つ、視線を外に戻す。
夏の夕日は空を赤く染め上げて、もう一日が終わる事を告げている。
鴉が数羽、定番の鳴き声を上げながら何処かへ飛んでいく。
どこからだか分からないが、蝉の声も聞こえてくる。
「すっかり夏ね」
「ええ」
気配が移動して、俺の横に腰を降ろした。
案外近い場所に気配を感じて俺はドギマギとしてしまう。
「知ってる? 今日ここの近くの村でお祭りがあるのよ」
「そうなんですか?」
何と幻想郷にも夏祭りは存在するらしい。
いや、収穫祭とかがあるのだからあってもおかしくはないのかも知れないが。
「ええ、だから今夜一緒に行かない?」
「え?」
突然のお誘い。
そんな言葉が来るとは思っていなかった俺は、思わず素っ頓狂な声を出していた。
「だ・か・ら、今夜お祭りに一緒に行きましょう?」
こちらを覗き込むようにして紫さんが繰り返す。
一介の居候である俺に今後の予定なぞ入っていない。
よって断る理由など無いので快諾する事にする。
「良いですね、ご一緒しましょうか」
「ふふ、そう来なくっちゃね!」
朗らかに笑う彼女の姿にはいつもの妖艶な雰囲気は無く、どこにでもいそうな少女のそれと同じように見えた。
何となく、釣られて俺も笑ってしまった。
「そうと決まれば浴衣を選ばなくちゃいけないわね・・・ ふふふ、楽しみにしていなさい♪」
そこはかとなくスキップでも始めそうな軽やかな足取りで、彼女は自室へと向かっていった。
「・・・夏祭りか」
呟きは、茜色に染まった空へと吸い込まれて溶けた。
久しぶりに人間を見た気がする。
いや、純然たる人間を見たのが久しぶりなのであって、人の形をしたものは毎日見ているのだが。
マヨヒガから最寄りの村の近くに俺は立っていた。
ちなみに自力でここまで来た訳ではない。
「九尾の狐も怯える訳だ」
どう行けばいいのか、と問う俺に対して「簡単な方法があるわ」と彼女は答えた。
その声を最後に聞いて、俺は急激な浮遊感を味わった。
要は「スキマ」に落とされた訳である。
いきなりの事に驚く間も無く、一瞬だけ視界がブラックアウトしたと思ったらここに立っていたのだ。
こうして俺は感じた事の無い猛烈な危機感と恐怖感を味わった。
「止めよう、思い出すのは・・・」
頭を振って、恐怖体験プレイバックを止める。
村の方を見やるともう祭りは始まっているのか、賑やかな人々の声と提燈の生み出す穏やかな明かりが目に入る。
「しかし祭りに行くなんて子供の時以来だ・・・」
元よりインドア派である俺は、中学に上がる頃にはお祭りなど殆ど観に行かなくなった。
単純に暑いのが嫌だった、と言うのが理由の大半を占めるのだけど。
「お待たせ」
村の近くで待機し始めてから大体15分くらい経った頃、聞き慣れた声がした。
「いや、それほどm」
振り返った先で声を失った。
「ふふ、どうかしら?」
濃紺の布地には黄色い百合(これは虎百合だろうか)が咲き乱れており、帯の色は燃えるような緋色。
いつもは降ろしている髪は結わえ上げられており、赤いヒールは黒漆の下駄になっている。
総じて、
「物凄く・・・・・・綺麗です」
「ありがとう」
浮かべた笑顔も、いつもにも増して美しく見えた。
「さ、参りましょう?」
闇にも映える白い手が差し出される。
「あ・・・はい」
おずおずと手を取る。
村の方へと向かう最中会話は殆ど無かった。
何か話そうとは思ったのだが、緊張してしまって声が出なかったのだ。
程なくして、村の中へと俺たちは足を踏み入れた。
「・・・何だ、あんまり現実世界と変わらないんだな」
祭りの会場に入って第一声はこれだった。
幻想郷のお祭りと言うからには、どこか現実離れした光景が見られるのかと思っていたのだが、思いの外現実のお祭りと変わった所は無かった。
ただ夜店で時折見たことの無いものがある辺りは、やはり幻想郷らしさを感じるが。
「へぇ・・・ 貴方の世界のお祭りもこんな感じなの?」
扇子(今回は和風だ)を軽く扇ぎながら紫さんが言った。
「ガキの頃に行ったのが最後なんで、今もそうかは分かりませんがね」
「ふぅん・・・」
俺の言葉に短く答えて、彼女は目を細めた。
視線の先には大勢の人間。
「宴会とはまた違った趣があるものね」
そう言えば、彼女は博霊神社で行われる宴会にもよく出席している妖怪だったはずだ。
しかし今の言葉から察するに、人間のお祭りはあまり行った事が無いらしい。
「あまりお祭りには参加しないんですか?」
「あら、私が何者だったかお忘れになって?」
「あ・・・・・・」
そうだ、彼女はこの幻想郷の中でも屈指の強さを誇る妖怪だ。
ならばそんな存在に対して人間はどんな感情を抱くか。
すなわち、恐怖。
「私の事を見ると大抵の人間は怯えるわ。 ・・・丁度初めて会った時の貴方の様にね」
人は理解の及ばないものを怖れる。
それが自身と相容れない存在であればなおの事。
「もっとも今は“認識の境界”を少々弄くっているから問題はないのだけれどもね」
ここまで来てようやく俺は思い至った。
彼女にとって本当は“人間のお祭り”など“孤独”を感じるだけのものに過ぎないのかもしれないと。
「何で・・・」
「ん?」
「どうして、お祭り行こうなんて言ったんですか」
境界を使って無理矢理入り込まなければならないなんて悲しすぎるじゃないか。
どんな上手に紛れ込む事が出来ても、そこに本当の彼女はいないのだから。
「一層、博霊の宴会の方が良かったんじゃないですか?」
そんな俺の言葉に彼女は目を丸くした後、
「そんな事ないわよ」
穏やかに笑った。
「でも境界を操作しないと貴女は・・・」
「その程度の事は気にしないわよ。 それよりもね・・・」
そこで一旦言葉を区切り、
「私は貴方と共通の体験をしたかったのよ」
頬を染めてそんな事を仰った。
「え? あ、いえ・・・その、光栄です・・・・・・」
ある意味これは・・・
いや、そうでなくても相当胸に来る言葉だ。
顔が火照ってくるのがよく分かる。
そこまでして俺なんかと同じ体験をしたいなんて・・・
「共通の体験をするだけならば、博霊神社の宴会でも構わないのだけど・・・」
確かにその通りだ。
体験の共有自体は、二人で同じ事をすれば良いのだから。
「吸血鬼のお嬢様とかに獲られちゃ嫌ですもの」
「あ、そう言えば・・・」
博霊神社の宴会は人と妖怪が入り乱れた混沌空間であると聞く。
ならば弾みで何が起きるか分からない。
「でも、貴女が睨みを利かせていれば問題無いのでは?」
「食べられる、と言う言葉には二つの意味がありますわ」
それはないと思う。
俺の言う事なんて紫さんでもなければただの狂人の戯言に過ぎないし。
そもそもが、そういう事も彼女ならば防げるのではないだろうか?
もしかしてこれは・・・
「・・・独占欲?」
ポソリと呟いてみる。
「ふふ・・・ どうかしら?」
対して彼女はただ恥ずかしそうにはにかむだけ。
「い、行きましょうか!」
「クス・・・ ええ、参りましょう」
彼女の手を取って歩き出す。
ただひたすら恥ずかしくて振り向けなかったが、後ろにいる彼女は何となく笑っているように思えた。
色彩豊かな時間が過ぎ去って、俺と紫さんは土手に座っていた。
「楽しかったわね♪」
「そ、それは良かったです」
人間としての“お祭りの楽しみ方”を伝えられたのなら幸いだ。
しかし様々なハプニングがあったので俺は激しく疲労している。
男としては嬉しいハプニングもあった様な気がするが、何があったかはご想像にお任せして省略する事にしよう。
「さてと・・・ そろそろ始まるかな?」
夜空を見上げて呟く。
「ああ、そう言えばそろそろ刻限じゃないかしら」
紫さんも分かっているから同じ様に空を見上げる。
ちなみに今ここにいるのは俺たちだけではない。
他の村人たちなども大勢この土手に腰掛けている。
何故ならば、
ヒューン ドン
「始まりましたね」
ヒューン ドン ヒューン ドン ドドン
夏祭りの恒例、花火大会があるからだ。
「綺麗ね」
さしもの紫さんでもこれには感嘆を禁じえないようだ。
花火、それは東洋が生んだ芸術。
中空に描かれる鮮やかな炎の軌跡は、ある時は小さな輝きとなり散り、またある時は炸裂した後にさらに小さな閃光を放って消える。
それはまさしく“一瞬の芸術”
万物には必ず崩壊の瞬間がある。
その逃れられない運命の中で精一杯輝くことの美しさを、この芸術は雄弁に語っていると思う。
「やっぱり花火は夏の風物詩ですね」
「そうね」
お互いに空を見上げたまま話し合う。
ヒューン ドン ドドン ヒューン ドン
花火の音があるのと、互いにその美しさに目を奪われている為に必然的に会話が少なくなる。
ふいに、自分の肩に重みが掛かった。
「・・・・・・!」
何事かと思って首を回すと、そこあったのは紫さんの顔。
反射的に声を上げそうになったが、周囲に人が大勢いる事を思い出して何とか踏み止まった。
艶やかな髪の毛からは、ほのかに甘い香りが漂ってくる。
「ねぇ・・・」
言葉と共に、彼女の手が俺の手に絡められた。
「な、何ですか?」
チキンな俺の声は情けなく上擦った。
しかし気にする事無く彼女は続ける。
「花火は美しいわよね」
「ええ・・・」
「それはなぜかしら?」
「一瞬で消え去ってしまうから・・・?」
先程自分が感じていた事をありのままに話す。
「そう、花火は一瞬で消え去ってしまう・・・ だからこそ人はそこに美しさを見出す」
空を見上げたまま、どこか遠くを見るような目で彼女は言った。
「そしてその美学はこの世の殆どの物に当てはまるわ」
「そうでしょうね・・・」
生命も物質も、時間も空間も、森羅万象はいずれ全て虚無へと回帰する時が来る。
“始まり”があれば“終わり”もまたあるのだから。
「それは・・・ とても残酷な事だと思わない?」
間近で見る彼女の瞳の中に、果てしない寂寥の念が見えたような気がした。
彼女は妖怪。
それもおよそ神霊の域に及ぶほどの大妖怪だ。
永い時間を過ごす彼女にとって、この世の全てはある意味一瞬の事なのかもしれない。
おそらく彼女が抱いた如何なる感情もまた同様に。
「・・・そうですね」
確かに、変わり行く事は悲しいかもしれない。
「如何に深い想いも所詮は不確かでしかなく、光年の永さから考えれば全ては泡沫なのかもしれません」
しかし・・・
「それでも良いのでは無いでしょうか」
「・・・なぜかしら?」
「もしも総てが輪廻の輪の中で廻っているのであれば、今俺がこうして紫さんと話しているという事もまた“必然”たるを得るからですよ」
これから先の未来がどうであれ、現在と同じ状況がやがて来るのであれば現在感じている感情もまた同じようにして抱くのではないだろうか。
「簡単に言うと、今の状況は来世でもあるかもしれないって事です」
久しぶりに自分の狂人ぶりを発揮してしまった。
微妙に後悔の念に苛まれる。
「クス・・・ 貴方はつくづく面白い事を言うわね」
しかし紫さんは俺の言わんとする事を理解してくれたのか小さく笑っていた。
「貴方みたいな人を見るのは本当に久しぶりだわ」
「はは、自称・変人ですからね」
かつて友人にこの持論を話したら「意味が分からん」と言われたものだ。
「でも意外ね。 貴方運命論者だったの?」
「いえ、こういう事考えるのが好きなだけですよ」
俺は思想家ではない。
第一、自分の考えに同調する事を無理強いする様な真似は嫌いだ。
「あれ、花火終わったかな?」
ふと、花火が炸裂する音が聴こえなくなったので周囲を見渡すと、先程まで大勢いた観客達はいつの間にかいなくなっていた。
「そうみたいね」
どうやら知らない内にかなり時間が経過していたらしい。
気が付けば、土手には俺たちしか残っていなかった。
「・・・二人っきりね」
「・・・そうですね」
異性と二人っきりという状況にも関わらず、不思議と心は平静を保っていた。
「もう少しだけ・・・ こうしていても良いかしら?」
彼女の問いに笑顔で答えて空を見上げる。
見上げた星空はどこまでも儚く、そして眩しく煌めいていた。
肩に感じる重みに微かな幸せを感じながら、流れ行く時に身を任せる。
虫たちの夜想曲が二人を優しく包んでいた。
そんな或る夏の夜の出来事。
うpろだ293
───────────────────────────────────────────────────────────
「・・・またか」
手に取った新聞紙の一面にはこんな事が書かれていた。
『またもや神隠し!』
ここ最近まるで疫病の流行の様にして始まった、この一連の『神隠し』事件。
『神隠し』と銘打つ位であるから、この連続的な事件の首謀者、目的、消えた者の行方は一向に分かっていない。
「ったく、誰がこんな事をやってるんだか・・・」
朝食のトーストをかじりながら、ぼんやりと呟く。
人を攫うと言うのは某国のお得意技とも言えるものだが、何せ今回は全く首謀者が見えていないのだ。
普通の誘拐事件ならばほんの数名でも目撃者はいるものだが、今回の事件では目撃者は一切見つかっていない。
要は『迷宮入り』なのだ。
「警察も早く犯人の尻尾でも掴めりゃ良いのにな・・・」
民衆を守る為に存在する組織は今回の事件においては何の功績も作れていない。
いよいよ、警察に対する国民の不信感も募ってきている。
ただ・・・
「相手が本当に“化け物”ってんなら話は別か」
最も、そんな事は有り得るはずはない。
何せその“化け物”の大半は人間の空想が生んだ産物なのだから。
生憎俺はその手のオカルトはあまり信じてはいない。
「さて、そろそろ行こうかね・・・」
朝食を腹に収め、学校に向かう支度をする。
天気は快晴。
世間を震撼させる事件が続いているとは思えない様な天候だった。
色んな意味で憂鬱な一日を終えた俺は、帰宅早々パソコンのディスプレイの前に腰を降ろした。
電源を入れてお気に入りのサイトへ直行する。
「そう言えば最近の事件って、コイツなら出来るんじゃないか?」
ディスプレイに写る女性、その名は八雲紫。
ヤリコミ度が高い事で有名な某シューティングゲームのキャラクターの一人だ。
“境界を操る程度の能力”を持つ彼女は、ゲーム中でも屈指の強さを誇る存在。
同時に“仮に”存在するのなら今回の事件の首謀者とも考えられる人物とも言える。
「いや、でもまさかな・・・」
相手は架空の存在だ。
幾らなんでもそれはないだろう。
「もしそうだとしても、今は冬じゃないし」
彼女は“人喰い”であると(設定上)言われている妖怪だ。
しかしそれは冬眠の前が主だとされている。
今、季節は夏。
ならば彼女がこんな連続事件になるほど“人を摂取”する事もないだろう。
そもそも相当頭が良いらしいので、事件として残すとは思えない。
「八雲紫・・・ま、空想の存在でしかないよな」
「あら、お呼びになったかしら?」
瞬間、全身の体毛と言う体毛が逆立ったのを知覚した。
同時に背後に現れた人の、いや“人以外のモノ”の気配。
「う、う・・・そ、だ・・・・・・ろ?」
首を向けた先にいたのは、PC画面に写っている八雲紫その人。
声帯が引き攣って、自分でも情けない程に上擦った声が出た。
「あら、酷い男性(ヒト)。 貴方がいないと仰ったから、私は自身の存在を証明しようと思って此処に来ましたのよ?」
手に持った扇子を口に当てて、目を細める。
ディスプレイと言うフィルターを通して見るのならその笑顔はさぞ美しく見えただろう。
しかし今目の前にある笑顔に対して感じるのは、ただの“恐怖”だけだった。
「あんたが八雲紫・・・なのか?」
何とか口に出してみるが、明らかに声は上擦ったままだ。
「ええ、私が八雲紫ですわ」
どこか嘲るような彼女の声色は、絶対的な勝者のそれに似ている様な気がした。
「お、俺を喰う気なのか?」
身体がガタガタと震え、同時に声も揺れてくる。
頭の片隅にいる冷静な自分が「まるで天敵に狙われた小動物だな」と笑っていた。
「まだおやつの時間には早いんですの」
ふぅ、と軽く息を吐いて彼女は言った。
どうやらいきなり喰われる事は無いようだ。
「なら何故こんな所に?」
「そうね・・・」
あまり問いばかり繰り返すと相手の機嫌を損ねかねない事は承知だが、これはある意味では俺の生死が係っているので訊いてみる。
「特に理由などは無いわね。 ただの気紛れ、と言った所かしら」
「気紛れで死ぬのか、俺は」などと心の中で呟いて心底俺は絶望した。
力のある者の前では何も出来ない。
これは弱者の真理だろう。
「何も無いなら帰ってくれません・・・か?」
微妙に狐狗狸さんにでも頼むように言ってみたが、
「少し話し相手になってくれません事?」
どうやら俺の退路は無くなってしまったようだった。
そんなこんなで話し始めて一時間程経過した。
彼女は相変わらず胡散臭い笑みを浮かべたままこちらを見ている。
一方の俺は緊張と恐怖で胃に穴が開きそうな気分だ。
一応二人分のコーヒーを淹れてみたが、その減り具合が明らかに違う。
「あら、コーヒーが冷めてしまいますわよ?」
「あ、ええ、まぁ猫舌なものですから・・・」
猫舌なのは嘘ではないのだけれど、本当はここまで冷ます必要は無い。
本当は単純に手を出すのも怖いからこうなっているだけだ。
「随分と怖がられたものね」
俺の心を悟ったのか、少し落胆したような様子で彼女は言った。
「それは・・・貴女は人を食べるらしいですから」
ライオンに懐く野ウサギがいないのと同じ事。
「食べないわよ」
「く、口では何とでも言えますよ・・・」
心外だと言わんばかりの様子で弁明してくるが、正直その笑顔で言われても説得力は皆無に等しいと思う。
すると彼女は、
「どうしたら信じてくれるかしら?」
と、のたまった。
「いや、そう言われても・・・」
“喰われない確証”など、どうすれば証明できると言うだろうか。
「貴方の考え方って結構独特だから面白いのよ」
「はぁ」
「でも貴方が私との会話を楽しんでいないって言うのは不平等でしょ?」
「そうですか?」
意外な事に、彼女は人間の事をそこまで見下げてはいないらしい。
「そう。 だからね、出来たらもう少し信用して貰いたいなと思うのよ」
「・・・・・・分かりました、善処してみます」
いきなりは難しいが、相手がそう願うのなら従ったほうが得だろう。
俺の命は所詮、彼女の掌の中にあるのだから。
「ありがとう」
一瞬だけ、彼女の笑みから胡散臭さが消えた。
その一瞬だけの本当の微笑みは、溜息が出るほどに魅力的だった。
(綺麗だな・・・)
元々、その姿は何も言わなければそこらのモデルなどよりよっぽどハイレベルなのだ。
自然な笑顔が似合わないはずが無い。
そしてその自然な笑顔に惹きつけられない男もそうはいないだろう。
「どうしたのかしら?」
ご多聞に漏れず俺も見惚れていたらしく、彼女の声で我に帰ることになった。
「い、いや、綺麗だなって・・・」
「え?」
まだぼんやりとしていたのか、ついつい本音が飛び出してしまった。
「あ! いや、あの、その・・・」
誤魔化そうと躍起になるが、言葉が見つからずただ慌てふためくだけになってしまった。
「そう・・・ありがとう」
何故だか彼女の方も少し頬を染めて答えてくる。
むしろ軽く流してくれれば良かったのだが、そんな反応をされるとかえって恥ずかしさが込み上げてきてしょうがない。
「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」
時計の針の音がやけに大きく聞こえてくる。
何となく気まずくなった俺は話題を振ることにした。
「あ、あの質問があるんですけど良いですか?」
「何かしら?」
彼女もこっちに合わせてくれたのか、素直に応じてくれる。
「最近の神隠しって、もしかして貴女が?」
「いえ、私じゃないわよ?」
「え?」
じゃあ、一体誰が“あの事件”を起こしたのだろうか。
彼女ぐらいしか、あちら側の世界で神隠しなど行う人物はいないはずなのに。
「最近どうも大結界の調子がおかしいみたいなのよ。 多分その影響でしょうね」
「大結界の調子がおかしい?」
「何でなのかはよく分からないけどね」
博霊結界と言えば、(設定では)こちら側の世界とあちら側の世界とを隔てる結界の事だ。
それが不安定になっているとなれば、あちら側に迷い込む人間が出てきてもがおかしくは無い。
「もっとも直に博霊の巫女が何とかするでしょうね。 それが彼女の役割なのだし」
「なら安心ですね」
それならば近い内に謎の『神隠し』事件には終止符が打たれる事になるのだろう。
無論、こちら側には何も分からないまま。
「信用してくれるかしら?」
「一応」
事件との関連性が無い以上、今の彼女が食物を求めてこちら側に来た可能性はある程度否定できる。
「そう、良かった。 ならば私も訊きたい事があるのだけど・・・」
「どうぞ。 俺が答えられることなら答えますよ」
「まず、この世界の・・・・・・・・・」
それからの会話は不思議なくらいにスムーズに進んでいった。
多分、彼女がむやみやたらに自分の同族を殺している訳ではないと分かったからだろう。
問答の中で彼女が時折見せる自然な笑顔は、やはりどうしようもないくらいに美しいものだなとか思ったりしながら時間は過ぎていった。
光陰矢の如し。
楽しい時間ほどその経過は早く感じるものだ。
結局ガチガチだった最初の一時間とは比べ物にならないほど俺は彼女との会話にのめり込んでいて、気が付けば時計の針は9時を指していた。
「あ、もう9時か」
「あら、もうそんな時間?」
彼女も時が経つのを忘れていたのか、俺の言葉を聞いて初めてその事に気が付いたようだった。
「あの・・・平気なんですか?」
「何がかしら?」
「あまり此処にいると、貴女の式達が心配するでしょうし・・・」
「そうねぇ」
本来なら彼女がこちら側に長居する事などあまりないはずだ。
目の前の女性が架空の存在でないのなら、その配下である二人の少女も実存するだろう。
「そろそろ戻った方が良いのでは?」
「ええ」
しかし彼女は一向に動こうとしなかった。
不思議に思って声を掛けてみる。
「あの?」
僅かな沈黙があって、彼女は口を開いた。
「・・・・・・ねぇ」
「はい、何でしょう?」
「・・・・・・・・・・・・」
「?」
「・・・・・・貴方、幻想郷に興味はあるかしら?」
「ええ、割とありますけど」
「なら来ない?」
「・・・・・・・・・え?」
いきなりのお誘いに思考回路がフリーズした。
そもそも俺みたいな一般人を幻想郷に連れて行ってどうするのか。
やっぱり喰うのだろうか。
いや、それはない事を祈りたい。
「・・・・・・嫌ならいいのだけど」
寂しそうな表情でそんな事を言う。
「嫌じゃないですけど、いきなりだったから・・・」
内心「行きたい」と言う想いはあるのだが、やはり行くのにはそれなりの準備が必要だろう。
黙って消えたら、俺も『神隠し』事件の被害者に加わる事になる。
でも彼女の誘いが魅力的なのも確かだ。
ならば・・・
「・・・少し待ってて下さい。 用意しますから」
「え?」
一度しか買えない『運命の切符』を逃すなんて出来ない。
「ちょっと、貴方本気なの?」
「ええ、本気です」
大き目のスポーツバックを取り出してきて、その中に衣服やら必需品やらをドカドカと詰め込む。
数分後にはスポーツバックは限界まで膨張していた。
「・・・・・・・・・」
はち切れんばかりのバックを、彼女は目を丸くして見ている。
そんな彼女に俺は言った。
「さ、支度が出来ましたよ」
必要なものは全てバックの中にある。
これで外出の準備は万端だ。
「どこへでも連れ去って下さい、八雲紫様」
少しだけ、おどけたように言ってみる。
「・・・・・・・・・」
彼女は一瞬ポカンとした表情をしてから、
「そうね、ならば“神隠し”と言うものを見せてあげるわ」
妖しげな微笑を浮かべ、そう言ったのだった。
斯くして、少年は幻想郷へ旅立った。
うpろだ359
───────────────────────────────────────────────────────────
「ん・・・」
光が差し込んで、沈んでいた意識が浮上する。
瞼を開ければそこには見慣れた天井。
横を見やれば赤く輝く夕日。
「・・・ん~」
布団の上で伸びをして、同時に深呼吸をする。
寝ぼけた脳に酸素が行渡って、ゆっくりと思考が鮮明になっていく。
それから服を着替える。
何となく自分が着ていた寝巻きを見やる。
「明らかに趣味が変わったわね」
ピンク色のランジェリーは夕日を浴びて少し透けていた。
そう言えば、少し前まではこんなに華やかなインナーは着けていなかったはずだ。
「やっぱり彼の影響かしらね」
小さく呟いて、頭の中に彼を思い描く。
網膜の向こうに映った彼は少し恥ずかしそうに私に微笑みかけていた。
それだけの事。
そんな些細な事で私は胸の奥が甘く、切なく疼く様な気がした。
「っと・・・ 何を考えているのかしら、私」
頭を振って、気を静める。
軽く息を吐いてから、襖を開けて縁側へ出て居間へと向かう。
少しすると、居間が見えてきた。
「あ、紫様起きられたのですか。 今食事をお持ちしますので、少々お待ち下さい」
「紫様、おはようございます!!」
居間へと足を踏み入れた私に、橙と藍が交互に声を掛けてくれる。
そして、
「おはよう、紫さん」
今一番気になっている彼が声を掛けてくれる。
その微笑みに自然と私の頬が緩むのが分かった。
「おはよう」
だから私も自分なりの最高の笑顔で彼等に答える。
ああ、そう言えばここ最近上辺だけの笑顔よりも心から笑顔を浮かべている回数が増えてきている様な気がする。
腰を降ろして、藍の作る朝食(正確には夕食)を待つ。
と言ってもすぐに食事が運ばれてくる訳ではないので必然的に時間が空く。
だからその暇な時間は彼等と会話で消費する。
「あら、今日も派手にやったみたいね」
彼の頬に掠り傷があるのを見つけたので言ってみる。
「ははは、やっぱり分かりますか」
苦笑しながら彼が答えた。
「○○ってば、全然回避出来てないんだもん。 あたしも一応手加減してるんだよ?」
「そんな事言っても俺は所詮人間だからな」
よく二人は弾幕ごっこ(と言っても橙が一方的に攻めるだけ)をしている。
彼はあんまり乗り気ではないようだが、無邪気な橙を無碍に出来ないのか結局今の様に毎日ボロボロになっている。
「えー、もっと頑張ってよ~ そうじゃないと面白くないよ」
「無理言わないでくれよ・・・」
そんな二人の様子が何となくおかしくて笑ってしまう。
「ゆ、紫さんも笑ってないで何とか言って下さいよ」
顔を引き攣らせながら、彼がそんな事を言ってきた。
「そうねぇ・・・」
少し意地悪してみようかしら。
「○○も殿方ならば、女性の要望に応えてあげるべきではなくて?」
いつもの様に口元へ扇子を当てて笑ってみる。
「ほ~ら、紫様もそうだって言ってるよ?」
「ご、ご無体な・・・」
私の言葉に勢いを得た橙が喜色満面で○○に笑いかける。
対して彼はいよいよ顔色が悪くなってきた。
これは少し厳しかったかもしれない。
このままでは少々彼が可愛そうなので救い舟を出して上げる事にする。
「でも、そうねぇ・・・ 橙としてはやっぱり歯応えがあった方が良いわよね?」
「うんっ!」
「ならば、私が少し彼の事を鍛えてあげるわ。 そうしたら今度弾幕ごっこをする時はもっと楽しくなるかもよ?」
「・・・・・・そうだね! その方が面白くなりそう!!」
「ふふ、もしかしたら○○が橙の事を追い抜いてしまうかもよ?」
「わわわ・・・それは大変だ! よ~し、あたしも少し外で鍛えてきますね!!」
言い残して橙はまるで風の様に外へと飛び出していった。
後にはホッと溜息をつく彼と私が残される。
「助かりました・・・」
「ありがとう」と深々と頭を下げてくる。
そんな彼の様子は満更でもない。
「あら、果たして助かったのかしら?」
「え・・・」
私の言葉に再び彼が凍りつく。
「今のは一時しのぎにしかなっていないのよ?」
「・・・やっぱりそうですよね」
内心分かっていたのだろう、彼は苦笑した。
「安心なさい、私が手取り足取り教えてあげるから」
「本気ですか?」
「ええ、本気よ」
実際彼にはもう少し、せめて人間としては強くなってもらいたい。
「・・・・・・・・・」
彼は暫く考えるような素振りを見せた後、
「じゃあ、その・・・ よろしくお願いします」
真剣な表情でそう言い切った。
その澄んだ表情に一瞬だけドキッとする。
だけどその本心を悟られるのは何だが躊躇われて、
「・・・その願い確かに聞き入れましたわ」
なんておどけた様な言葉を返してしまった。
でも、内心彼に期待していると言うのは本当の事。
強くなって欲しいのは、彼に守ってもらいたいから。
それはきっと如何なる女性の心の内にある一種の夢。
私、八雲紫は今、確かに彼に恋している。
さて、そもそも彼。
○○とはどういった人物なのか。
端的に言ってしまえば、彼は外の世界の住人であって同時に無力な一般人だ。
別に何か特殊な力を持っている訳でも、秀でた才がある訳でもない。
しかし彼は他の人間と明らかに異なっている点があった。
彼は人の身でありながら、時折何かを悟った様な表情を見せる事があるのだ。
“心の境界”を弄れば彼が何を考えているのかは分かるが、それはとても失礼な気がするので出来ない。
何よりも、私はそんな手段で彼の心を知りたくない。
「ふぅ・・・」
食事を終え、縁側で小さく溜息をつく。
ここ最近本心からの笑顔が増えた反面、溜息を吐く回数も増えた。
思えば何とも典型的な“恋煩い”の症状ではないか。
“恋”と言うものは知識としては知っているが、実際に本気で経験した事なんて無い。
律しようとすればする程、想いは加速して処理が追いつかなくなってしまいそうになる。
「はぁ・・・」
幾度目かの溜息。
もう数える事も意味が無いように感じる。
「どうしたんですか?」
ふいに横から彼の声が聞こえた。
振り返れば、珍しいものを見たような彼の顔。
「いえ、何でも無いわ」
平静を装ってみるが、どこまで演技できている事か。
「隣、良いですか?」
「どうぞ」
律儀に一声掛けてから彼は縁側に腰掛けた。
そうして私と同じ様に外へ視線を向ける。
「此処での暮らしはどうかしら?」
何気なしに訊いてみる。
彼は少し眉を寄せてから、
「なかなか気に入ってますよ」
と嘘偽りの無い笑顔を浮かべた。
その笑顔がまた眩しくて、心臓が跳ねる。
「・・・それは良かったわ」
今の笑顔は少々不自然になってしまったかもしれない。
「それから今更ですけど、本当にありがとうございます」
「え?」
突然の改まった礼に少し驚く。
「だって、俺ここに着てから何も出来ていませんから」
「何を言っているの、私は興味があったから貴方の事を連れて来たのよ? それに貴方は何もしていない訳ではないわ」
「そうでしょうか?」
不思議そうな顔でそんな言葉を返してくる。
全く暢気なものだ、と思う。
私を“こんな状態”にさせておいて・・・
「貴方がここに着てから藍や橙の様子が変わってきているのよ? 橙は遊び相手が出来て嬉しいと言っていたし、あの藍も良い話し相手が出来たって喜んでいたわ」
同じ女であるからよく分かる。
藍も橙も、おそらくは彼に対して好意を抱いている。
多分このまま順当に行けば、その感情が別の感情に推移するのも時間の問題だろう。
正直私は気が気でない。
それなのに彼は、
「そうなんですか? 橙の事については分かりますけど、藍さんがそう思っていたなんて知らなかったな」
心底驚いた様な表情でそんな事を言う。
幾らなんでも鈍すぎはしないだろうか。
一度、乙女心と言うものについてみっちりと教え込んだ方が良いかもしれない。
「・・・・・・・・・全く、困った男性(ヒト)ね」
「?」
幸い、呟きは聞こえなかったらしく彼は首を傾げているだけだった。
「兎に角、貴方が着てからマヨヒガの空気が変わったのよ。 貴方は何もしていない訳ではないわ」
「そんなに大層な事をした気は無いんですけどね・・・」
苦笑しながら彼が答える。
「むしろ俺は戯言ばっかり言っている気がしますよ」
「そうかしら、私は面白いと思うけど?」
これは私ばかりではない。
橙はどうだか分からないが、少なくとも藍は私と同意見のようだった。
「そう言ってくれるのは貴女だけですよ」
そんな事を言って、少しだけ寂しげな笑みを浮かべる。
「現実世界って結構シビアなんですよ。 ただ単純に自分の感性を形にしてみても、大衆がそれを受け付けられなければ批判されるんです」
そう語る彼の表情は真剣そのものだ。
「でも万人に通じるものなんて無いと思うんです。 ですから本当の意味では人は他人の価値を否定する事は出来ないと思うんです」
「人は人を否定出来ない、と言う事かしら?」
「ええ、もっともどこまで正しいかは分かりませんよ。 何せ俺も人間ですからね」
肩を竦めてみせる。
「でも貴女を始めとして、幻想郷の住人は純粋に評価対象の良し悪しを見てくれる。 その辺りは本当に好ましいですよ」
「もっとも理屈で動く人はどうだか分かりませんが」と、彼は笑った。
「・・・・・・だから、感謝しているんですよ?」
ふいに彼が立ち上がった。
直後に感じる人の温もり。
「特に貴女には・・・ね」
耳元で彼が囁いた。
「な・・・・・・」
状況を理解した途端、抑えていたはずの“感情”が暴れ始める。
身体が経験した事が無いほどに熱くなって、狂ったかのように心臓が踊り始める。
同時に甘い疼きが脳髄を侵して蕩かしていく。
“もっと近くに感じたい”
その想いが理性の壁を越えようとする瞬間、それを見計らったかのように彼は身を引いた。
「はは・・・ 少し悪戯が過ぎますね」
酷い。
これでは生殺しではないか。
「そ、そんなに怒らないで下さいよ」
どうやら本心が表情に出ていたらしい。
さっきまで悪戯っぽい笑みを浮かべていた彼は、急に怯えたような目で私の事を見ていた。
「怒ってなどいないわよ」
内心少し不満な訳だが、別段怒っている訳ではない。
「そ、そうですか? 良かった」
私の言葉に彼はホッと息を吐いた。
「ん、そろそろ時間かな・・・ それじゃお使いに行ってきますね、紫さん」
おそらく藍が頼んだであろう。
彼は一礼すると、少しだけ小走りで縁側を歩んでいった。
その姿をぼんやりと見送ってから、私はまた溜息を吐く。
「・・・本当に、どうしてしまったのかしらね」
耳元をそっと撫でる。
まだ、彼の囁きが残っているような感じがした。
もう駄目だ、これ以上は・・・
「・・・もう、我慢出来ない」
想いとは不安定なもの。
確実なものが無ければ忽ち風化して壊れてしまう。
だから私はもう待つ事を止めることにした。
「覚悟なさい○○」
今はいない彼に向けて宣戦布告をする。
さあ、これからが正念場だ。
やるからには全力で当らなければ。
せめて悔いが残らないように。
「あー・・・」
唸りながら寝返りを打つ。
寝入ってからおよそ一時間、急激に意識が覚醒してしまった。
さっきから何度も寝返りを打っているが、眠気に見放されたのかまるで眠れそうに無い。
「仕方ないな」
寝られない時は何をやっても眠れないものだ。
自分を納得させて俺は床から起き上がり、縁側へと向かう事にした。
幸い夜ともなると、日中に比べて気温が下がるので幾らから過ごしやすくなる。
俺は適当な場所に腰掛けて少し思考を巡らせる事にした。
「・・・・・・やっぱり夕方のアレはやり過ぎたかな」
アレ、とは紫さんの耳元で囁いた事だ。
普段彼女はよく俺をからかう事があるので、今回は逆に彼女の事をからかって見ようと思ってやったのだ。
「つか、明らかに怒ってたよな・・・」
多分あれがジト目と言うものなのだろう。
しかも微妙に不機嫌オーラが漂っていた。
でも心なし瞳が潤んでいたような・・・
「・・・ないな」
きっとそれは茹だった俺の脳が見せた幻想に違いない。
何せ相手は数え切れない程の歳月を生きた大妖怪。
俺如き青二才相手にそんな感情を抱くなんて考えられない。
「むしろ逆鱗に触れたんじゃ・・・」
だとしたら拙い。
相手は妖怪、自分は人間。
二つの種族の間にある差はどうあっても埋められるものではない。
逆鱗に触れたのならば、制裁は覚悟するべきだろう。
最悪、殺されるかもしれない。
「・・・・・・・・・」
ああ、何を今更怯えているのだろう。
そもそも此処に来た時点で覚悟はしていたはずじゃないか。
「八雲紫は冬には冬眠する。 その際には人間を蓄える・・・」
蓄える、つまりは“喰う”のだ。
元より妖怪は人間を食べるものであるから、その行為自体は自然な事だろう。
しかし被捕食者としてはそれを“自然な事”で済ます事は出来ない。
「・・・まぁ、元より冬までの命だとは思っていたけど」
言っていて薄ら寒くなる。
だが、どんなに逃げようとも逃げられるわけも無い。
何せ相手があまりにも悪すぎるのだ。
「ふぅ・・・」
もっともただで死ぬ気は無い。
せめて死ぬのであれば最期に盛大に何かをやって見せよう。
「そう」
何せ俺は・・・
「俺は彼女を愛しているんだからな」
そう、あろう事か俺は彼女に対して“愛情”を感じているのだから。
もっともその想いが成就する事など考えていない。
意味が無いからだ。
「愛も憎しみも、生きていて初めて告げられる」
死に逝く未来ならば、想いを告げても意味は無い。
告げられた相手はただ辛く感じるだけだ。
「生きられぬのなら証を刻めばいい」
それは言葉か、それは歴史か、それは・・・傷痕か。
「俺は彼女の心に残れればそれで良いんだから・・・」
ああ、何て酷い考えだ。
どうしようもない。
でもどうしようもなくしてしまったのは彼女だ。
彼女が俺の戯言を「面白い」と言ってしまったから。
俺を肯定してしまったから。
「歪んでるな、俺・・・・・・」
何故だろう、それが自分の心情のはずなのに目頭が熱くなってくる。
「死にたくないな・・・ 死んだら俺は彼女の傍にはいられない」
霊になる、と言う手だってある。
でも俺にはきっと其処に至るまでの精神力は無い。
だから死んだらそれで終わり。
「・・・俺には八雲紫(かのじょ)に愛される未来なんて無いのか」
そもそも相手はこっちをただの肉としてしか見ていないかもしれない。
久しく、俺は頬を熱いものが伝っていく感覚を味わった。
「・・・・・・未来はまだ決まってはいないわ」
声の方を見やると、そこには紫さんが立っていた。
彼女は本来夜に起きている事の方が多かった事をすっかり失念していた。
「運命論者ではない、貴方はそう言ったでしょう?」
それはかつて俺の言った事の確認。
「・・・いつから其処に?」
「さあ? いつからでしょう?」
問いに対して、彼女は見慣れた胡散臭い微笑みで答えた。
身体中の筋肉と言う筋肉が引き攣り、目の前が白くなっていく気がする。
「・・・答えが知りたいかしら?」
何に対しての答えなのだろうか。
俺にはそれを知る術は無い。
「答えが欲しいのなら来なさい」
彼女はそう言って縁側を歩いていく。
俺は何も言わずにそれに従った。
如何なる答えであろうと、ただ受け入れようと心に誓って。
彼女の部屋に入った事は何度かある。
しかし夜ともなると同じ部屋でもどこか違って見えてくる。
特に今の場合は状況が状況だけに。
「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」
重苦しい沈黙が続いている。
まるで空気が鉛にでもなってしまったかのように、呼吸をするのも苦しく感じる。
俺と彼女は部屋に入ってから互いに立ったままだ。
彼女はなぜか座る気配を見せないので、俺もそれに倣っているのだ。
「ねぇ・・・」
「はい」
彼女はこちらに背を向けたまま小さく言った。
「貴方、自分は私に愛されないと言ったわね」
「ええ」
「なぜかしら?」
やはり彼女は振り向かないままで問う。
「・・・・・・言うまでも無いのでは?」
不思議と冷静だった。
一種の極限状態であるにも関わらず、なぜか俺は自分でも驚くほどに冷静だった。
「私は貴方の口から聞きたいの」
一瞬だけ、彼女がこちらを見た。
黄金色に輝くその瞳が射抜くように俺を捉えていた。
「人間と妖怪は相容れないからです」
その視線を威嚇ととって、俺は総てをその一言に込めた。
どんな理由も、最終的にはこの一言に集約出来ると思ったから。
でも果たしてそれは俺の本心なのだろうか?
「だから私に愛されないと言うの?」
小さく頷いて、肯定する。
すると彼女は振り返って言った。
「・・・ならば逆に問うわ。 貴方は私を愛してくれないの?」
「それは・・・」
酷な質問だ。
本音で言えば俺は彼女を愛している。
しかしそれを告げた所で何になると言うのか。
「私は貴方を愛しているのよ?」
「それは食料としてでしょう?」
いつものジョーク。
でも今この言葉には冗談を込めたつもりはない。
それが真理であると疑わなかったからだ。
「いいえ」
けれど彼女はゆっくりと首を横に振った。
「私は貴方を愛しているわ」
そして微笑んだ。
その黄金色の双眸から、透明な涙を零しながら。
「好きで好きでしょうがないのよ? もうそれこそ狂ってしまいそうな位に」
「っ・・・」
「貴方を想うだけで、こうして涙が溢れてくるのよ?」
なぜそんな綺麗な笑顔を浮かべられるのだろう。
俺は何も答えられずに顔を俯かせた。
と、ふいに感じた事のある甘い香りが鼻腔をくすぐった。
「なっ!」
気が付けば、俺は彼女に抱きつかれていた。
同時に片手に感じる質感。
「そのナイフは妖怪を殺す事が出来る概念付加を受けたもの。 無論、私でも殺せるわ」
利き手に収まった小さなナイフ。
目の前には彼女。
「もしも貴方にとって私が恐怖の対象でしかないのならそれで私を刺せば良いわ。 だから・・・」
「・・・・・・・・・」
「ねぇ、教えて頂戴。 貴方は私をどう想っているの?」
耳元で彼女が囁く。
俺は・・・
「卑怯ですよ・・・・・・」
軽い音がして、ナイフが床に落ちた。
「そんな事、出来る訳ないじゃないですか・・・」
そうして俺はそっと紫さんの事を抱きしめた。
「俺だって狂う位貴女の事を愛しているんですよ?」
涙で視界が滲む。
頭では分かっていても、心では割り切れない。
それが感情と言うものだから。
「たとえ貴女にとっては食料でしかなくても、路傍の石と同じような存在であっても」
「・・・・・・」
「俺は貴女を愛している」
目を逸らさずに、彼女の瞳をしっかりと見つめて言い放った。
そして自分で言って初めて分かった。
これこそが自分の偽り無い本心なのだと。
数瞬の後、彼女はふわりと柔らかな笑みを浮かべた。
「・・・その言葉を、私がどれほど待っていたと思う?」
聖母のように、全てを包み込むような眼差し。
「ちゃんと言えるじゃない」
熱く潤んだ瞳が揺れている。
ふいに、視界一杯に彼女の顔が広がって。
「愛しているわ、○○」
唇に柔らかな感触。
「――――――」
思考が明滅を繰り返す。
喜び、驚き、幸せが三原色のように混ざり合って多彩な感情を生む。
やがて感情はただ一つに収束して、俺はその想いを心の底から受け入れた。
収束した結果に生まれた感情の名は“愛”。
「・・・はぁ」
「・・・ふぅ」
永遠とも一瞬ともつかない時間の後に、重なった唇は離れた。
意図せずして熱っぽい吐息が零れた。
「もう離さないわよ」
頬を紅潮させながら、上目遣いに宣言してくる。
その姿に愛おしさが加速していく。
「望むところです」
こちらももう歯止めは効かない。
彼女に誘導されて、建前と本音の境界を踏み外してしまった以上後戻りなんて出来ない。
俺は再び彼女に口付けた。
彼女もまたそれに答えてくれる。
今度は互いの舌を絡ませて、より熱く深く繋がり合う。
水音が部屋に響き渡る頃には、どちらからとも無く床に転がっていた。
そして俺たちは―――――――――――
斯くして、二つの想いは繋がった。
うpろだ360
───────────────────────────────────────────────────────────
遠野物語をご存知だろうか。
遠野物語の奇談の中には「マヨヒガ」と言うものがある。
そこは基本的に無人で、多くの家畜がおり、座敷には豪華な食器があるだけの屋敷であると言われている。
登場人物は基本的にマヨヒガに辿り着いても、そのまま一休みしてから帰る事が多い。
だが幻想郷のマヨヒガは、辿り着いてしまえば二度と帰る事は叶わない。
それはその屋敷の主人の食料となってしまうからだ。
屋敷の主人は人ではなく遥かな昔より存在する大妖怪であり、冬になるとまるで熊か何かのように冬眠する習性がある。
だが長期間の休眠状態にはそれ相応のエネルギーが必要になる。
そこで、その妖怪は冬眠の前に人を喰らうのである。
ゆえに幻想郷のマヨヒガは、迷い込んだが最後二度と元の世界には帰れなくなるのだ。
「・・・・・・ここでの生活にも随分慣れたもんだ」
そう、俺もここに来てかなりの時間が経過している。
本当ならばいつ例の妖怪に喰われるか怯えていてもおかしくはないのだが、俺にはそのような恐怖心は全く無い。
なぜならば・・・
「・・・俺は“彼女”を愛しているからな」
あろう事か俺はその妖怪を心から愛しているからだ。
無論“彼女”の従者である子達をも含めて。
「あーあ、愛は人を狂わせるってのは本当だったんだな」
そう、俺もまた意味は違えども帰れなくなってしまったのだ。
それはただ“愛”ゆえに。
もっともその事が悲しいとは思わないし、「狂っている」と言われても構わない。
俺にとっては今あるこの日常が何よりも大事な事なのだから。
マヨヒガでの生活は現実世界にいた頃よりも案外楽だ。
俺はただの人間でしかないので人里へお使いに行ったり、屋敷の掃除や家事手伝いをするぐらいしか仕事が無い。
よって、よほどの事が無い限りは予定が空いている。
今日もやはり特にする事が無いので、縁側でお茶を飲みながらぼんやりとしていた。
「○○~!!」
けたたましい音を立てながら橙がやって来た。
「どうしたんだい、橙?」
手に持った湯飲みを脇によけて訊く。
「弾幕ごっこしよう!!」
「え゛・・・」
にこにこと太陽の様な笑顔を浮かべて橙が言ってくるが、逆に俺はその言葉に凍りついた。
「ねぇねぇ、やろうよ~~」
「い、いや、え~っと・・・・・・」
彼女はじゃれ合いのつもりで言っているのだろうが、人間である俺にとってはじゃれ合いのレベルでは済まない。
そもそも俺は空を飛ぶ事も弾幕を放つ事も出来ないのだから、はっきり言って一種のリンチである。
「ねぇ~、遊ぼうよ○○~~」
唐突に彼女は俺の膝の上でゴロゴロと転がり始めた。
元が化け猫であり、人化していても頭頂部に猫の耳があるのでこの仕草は非常にマッチしている。
「・・・・・・」
「うにゃ~~♪」
試しに頭を撫でてやると猫そのものの声で橙が鳴いた。
どうやら喜んでいるらしい。
「・・・・・・」
「うにゃ~ん♪」
「・・・・・・ふふ」
「うな~・・・ゴロゴロ」
猫にするよう撫でていると、それに応じて橙も反応する。
どうやらすでに弾幕ごっこの事についてはどうでもよくなったらしい。
「・・・可愛いなぁ、橙は」
無邪気にじゃれてくる彼女に、思わず俺はこぼしていた。
その言葉を聴いて橙は一瞬だけ驚いたような顔をしたが、すぐに再び膝の上で転がり始めた。
「それそれ」
「うにゃにゃ~ん♪」
心なしさっきよりも嬉しそうにじゃれてくる橙を微笑ましく思いながら、俺は昼ご飯まで彼女の事を撫でていた。
ちなみに、昼を知らせにきてくれた藍さんにブッ飛ばされたのはまた別のお話だ。
「それじゃ、今日もお願いします」
「ああ、それでは始めようか」
昼食(蕎麦だったのだが油揚げが無かった)を終えてから、藍さんと向かい合って座る。
卓袱台の上には様々なジャンルの本が並べられている。
「さて、今日はどうする?」
「そうですね・・・ 今日はこれなんてどうでしょうか?」
「ほう、なるほど。 最近めっきりやらなくなったからな丁度良い機会かも知れないな」
「藍さんこれ好きですよね」
「ああ、ここだけの話だが私は特にこれが好きでな。 内心、いつ来るか楽しみにしていたんだよ」
「そうですか、ならこれにしましょう」
ちなみに橙はいない。
彼女は今外に遊びに行っている。
仮にいたとしても、きっとこの手のものはまだ早いと思うから外へ行って貰うと思うが。
「しかしこの“シュレーディンガーの波動関数”はいつ見ても面白い」
・・・今もしかして卑猥な想像をした方いました?
だとしたら残念ながらそれは無いよ。
何せ卓袱台の上の本も、ただの参考書の山だから。
「俺には何が面白いのかさっぱり分かりませんよ」
彼女は数字、早い話が数学関係に強いので面白みを感じるのだろうが、俺はそっち方面の人間では無いので理解できない。
「ふふ、その面白さを教えてやる為に私がいるのだぞ?」
「そうでしたね」
ただ単純にマヨヒガでのんびりしていると、徐々に知識が無くなってしまうのではないかと思った俺は、危機感からこうして藍さんなどを頼りにして勉強を続けているのだ。
「さて、まずは粒子が時刻・・・」
「ふむ・・・・・・」
かくして二人だけの勉強会は始まった。
この勉強会は基本的に藍さんが教師役を勤め、俺が生徒役というスタンスになっている。
それから毎日やっている訳ではなく、藍さんが仕事を終えてしまっている時ぐらいしかやっていない。
無論、彼女は本来かなり多忙の身であるので正直気が引けてしまうので、それを言ったら、
「ははは、心配してくれるのか。 優しいな○○は。 だが安心しろ、私なら平気だ」
とか言って笑われた。
でも実際あんまり安心していない。
何せ以前彼女の部屋の前を通ったら、何かすすり泣く様な声が聴こえてきたのだから。
(・・・実に心配だ)
何か彼女その内鬱にでもなるんではないだろうか。
確か数日前にも“彼女”に無理難題を押し付けられていたし。
そう思うと、目の前で嬉々として数式の説明をしている女性の事を不安に思ってきてしまう。
「あの、藍さん」
「何だ、○○? 解らない所でもあったのか?」
「い、いやそうでは無いんですが」
言ってみたものの、何と言って切り出せば良いのか悩む。
「どうしたんだ?」
黙りこくった俺を訝しがる様に藍さんが問うてきた。
こうなれば言ってしまうしかない。
「あ、あのですね藍さん!」
「な、ななな何だ!?」
勢い余って乗り出してしまった。
流石に彼女もたじろいだらしく、心なし身体を後の方へと倒している。
「ど、どうしたんだ○○。 そんなに意気込んで・・・」
何故だか頬を染めて、俯き加減で藍さん。
いつものキリッとした様子が一転、年頃の娘のような様子に変わってしまう。
非常にぐっと来るものがあるが、そこは何とか抑えて俺は言葉を口にした。
「・・・藍さん、ストレス溜まっていませんか?」
俺の言葉を最後に、無音の空間が生まれる。
藍さんは俺の言葉を受けてポカンとした表情でこちらを見つめていた。
あれ、もしかして俺はおかしな事でも言ったのだろうか。
「・・・何だそんな事か。 全く驚かせてくれるな」
硬直が解けて、彼女は苦笑した。
「全く○○は心配性だな。 前にも言ったが私は大丈夫だよ」
「嘘ですね」
幾分声のトーンを落として言う。
そもそもストレス性の疾病と言うものは本人がストレスを溜め込む事で生じる事が多いのだ。
表面上繕ってはいるが、このままではいつか破綻してしまうのは目に見えている。
俺にとってそれが何よりの気掛かりだった。
「この前だって自分の部屋ですすり泣いていたでしょう」
「っ!?」
俺の言った事が核心に触れたのか、藍さんは目を剥いた。
「お、お前何故それを知っている!?」
「偶然ですよ。 夜、トイレに行った帰りにね」
「な、なななな・・・・・・!!!」
唐突に彼女の顔がボンッと音を立てそうな勢いで赤くなった。
「どうしたんですか、藍さん?」
“日頃のストレスで泣く”ってそんなに恥ずかしいだろうか。
それとも彼女にとって「泣いた」と言う事実が恥ずかしい事だったのだろうか。
「お、おおお・・・」
「お?」
壊れた機械のように繰り返す藍さんに、ついつい合わせてしまう。
が、ふいに彼女は顔を上げたかと思うと、
「お前と言う奴はぁーーーーーーーーーー!!!!!!!!!」
「え? う、うわあああぁぁぁぁぁあああーーーーーー!!!!??」
物凄い勢いで飛び掛ってきた。
(少女撲殺中…)
「すまないっ!!」
「いや、良いんですよ・・・」
10分後、ようやく開放された俺の顔はもはや原型を留めていなかった。
痣、切り傷、腫れ、その他様々。
幸い歯とかは無くなっていないのだが、それにしたってやはり痛いものは痛い。
「本当にすまない!! 私とした事がついつい我を見失ってしまった!」
「ははは、良いですよ。 誰にでもある事でしょう?」
「し、しかし!」
律儀に謝り続ける彼女に思わず苦笑してしまう。
「・・・顔を上げてくださいよ。 そもそもは俺が妙な事を言ったのが発端なんですから」
ちなみに「何故取り乱したんですか?」と問うても、彼女は真っ赤になるだけで答えくれなかった。
「だ、だが私はお前の好意を無碍にしてしまったんだ! 私は、私の事が許せない・・・」
それは自責の念。
やれやれ、真面目な上に心優しいとはなかなか彼女も損な気質だ。
だから俺は提案する。
「ならば、俺に何かやらせて下さい」
「は?」
「ですから、藍さんが喜ぶような事を俺にやらせて下さい」
藍さんは一瞬フリーズした後、意味を理解したのか、
「な、何を言っているんだお前は! 何でお前が私の為に何かをするんだ!! 私はお前を害してしまったんだぞ!?」
と怒鳴り声を上げた。
でもこちらも負けずと返す。
「そもそも俺は好意で日頃疲れている貴女の為に何かしてあげたいと思っていたんですよ。 ならばそれを大人しく受けてもらうのが一番良い罰になると思いますが?」
「う、むむむ・・・」
「ね?」
しばらく唸り声を上げていたがやがて彼女も納得したらしく、
「なら・・・ その、頼む」
少しだけ恥ずかしそうにそう言った。
夕飯を終えた後、俺は縁側に腰掛けて夜風に当っていた。
「やっぱり藍さんは相当疲れていたみたいだな」
結局彼女が俺に所望したのはマッサージだった。
日頃から肉体労働(精神労働も)の絶えない彼女の肩は、女性の物とは思えない程に凝っていた。
「まさか母に教え込まれたものが役立つ時が来るとは思わなかった」
俺は幼少期から親は何かとマッサージなどを教え込まれた。
いらない知識だと思っていたのだが、この様な形で実践する日が来るとは思わなかった。
内心、少し親に感謝している。
「少しは楽になったのなら良いけど・・・」
所詮は素人のマッサージだ。
専門家のそれに比べたら、どれほど効能があるか分からない。
それでも藍さんは始終心地良さそうにしていてくれた。
「・・・全く良く出来た人だ」
本当ならばそんなに心地良いものでも無かっただろうに。
仕舞いには「またやってくれるか?」なんて訊いてくる始末だ。
まるで立場が逆だな、とか思った。
まぁ、とりあえず「いつでもどうぞ」と答えておいたのだけど。
「やれやれ・・・ 俺って役立たずだな」
小さく溜息を吐く。
実際、人間である俺に出来る事は少ない。
“彼女”は「そんな事は無い」と言ってくれるが、そもそも俺がやっている(らしい)事は実感出来るものでは無い事が多い。
「認知出来ないものは存在しないに等しいからなぁ」
例えば身体的な変化(背が伸びる等)だって、他人に指摘されて初めて気が付くだろう。
要はそれと同じ事。
“役立っている”と言う実感がなければ、その人間は自分が何かの役に立っているとは思えないのだ。
「・・・頑張ろう」
仮にも俺は“彼女”に見初められた男だ。
いつまでも“頼りない人間”ではいられない。
夜空の星の下で、俺は小さく呟いた。
「何を頑張るのかしら?」
横からふいに人の気配が現れ、声がした。
「・・・色々ですね」
視線を向けずに言う。
軽い音がした後、気配の主は俺の隣に腰掛けた。
「もう、あんまり根を詰めちゃ駄目よ?」
俺の最愛の“彼女”、八雲 紫はそう言って微笑んだ。
「いえいえ、貴方の“恋人”である以上はもっと頼れる男にならないといけませんからね」
「あら、頼もしい」
むん、と大して無い力こぶを作って言うと、彼女はクスクスと可笑しそうに笑った。
「でも、私は今の貴方でも十分だと思うわよ?」
「そんな事は無いでしょう」
「そうかしら?」
ふいに彼女の笑顔の種類が変わった。
「貴方・・・ 今日も橙や藍と仲良くしていたわよね?」
よく見る胡散臭い笑顔だ。
しかし迫力がいつもより5割増しぐらいになっている気がする。
というか、何で昼間の事を知っているんだ?
「え、いや、それはですね・・・」
言い訳が全く思いつかない。
そもそも今更反論しても、むしろ「はい、そうです」と言っているのと同じだ。
「・・・・・・・・・・・・」
俺が反論しないのを見て、紫さんの笑顔が徐々に不機嫌そうな顔になっていく。
と、彼女は急に腕を伸ばし、
「い、いひゃいでふよ、ゆはひひゃん!!」
俺の頬をグイグイと引っ張り始めた。
当然俺は抗議の声を上げたが、彼女は許す訳もない。
「当然の罰ですわ」
とだけ言って、俺の頬を引っ張り続ける。
内心そのむくれた表情が可愛い、とか思っていたりするのだが、そんな事を言う余裕は俺には無い。
結局それから大体5分くらいの間、俺は彼女の好きなようにされてからようやく解放された。
「い、痛い・・・」
「当然よ、痛くしたんですもの」
ヒリヒリとした頬をさすりながら言うのへ、紫さんがピシャリと言う。
「うう・・・すいません」
言い訳なんて出来るはずもないので、俺は誠意を込めて謝罪する事にした。
「・・・・・・つーん」
ツイッと顔を背けられる。
これは、可愛らしいと思う反面非常にショッキングだ。
ちなみにこう言ったやり取りは、彼女の“恋人”となった日から結構な頻度起こっている。
どうも彼女は俺が橙や藍さんと仲良くしているのが気に入らないらしい。
「むむ・・・困ったな」
しかしここまでへそを曲げられたのは初めてだ。
普段はただ必死に真摯な態度で謝罪すれば許してくれるのだが、どうやら今回はそれでは済みそうにない。
「本当にすいませんでしたっ!!!」
もうこうなればなりふり構っていられないので、縁側に頭を擦り付ける勢いで土下座してみる。
「・・・・・・・・・」
チラリと上目遣いで様子を窺うと、横目でではあるが彼女が目を丸くしているのが見えた。
しかしまだ彼女の唇から「許す」と言う言葉は出てこない。
さて、どうしたものか。
(・・・そうだ)
妙案と言えるかは分からないが、この策ならば現状を打開する事が出来るかも知れない。
ただこの方法は後の事を考えると、ある意味では諸刃の剣であると言える。
早い話が引かれたら終わりだからだ。
だがこのまま土下座を繰り返すだけは埒が明かないだろう。
ならばリスクを負う事になってもやる価値はあるのではないだろうか。
(イチかバチか・・・ やってみようか)
ゆっくりと、出来るだけ音を消して紫さんの背後に回り込む。
・・・今だ。
「紫さん・・・」
「な!!」
そっと少し押すようにして彼女の身体を背後から抱きしめて、
「紫さん、許してくれませんか?」
わざと耳元で囁くように許しを請う。
「ちょ、ちょっと・・・!」
拘束から逃れようと身をよじるが、俺は上から覆いかぶさる様に抱きついているのでそう易々とは抜け出せない。
風呂上りだったのだろうか、シャンプーの甘い香りが俺の鼻腔をくすぐった。
その香りに酔いしれて、俺は一層彼女を抱く力を強くした。
「ん・・・もう、○○ったら・・・・・・」
そのまましばらくそうしていると、徐々に彼女の抵抗も弱くなって行った。
「・・・許してくれませんか、俺の大切な紫さん」
頬を擦り合わせる様にして再び許しを請う。
「卑怯ね、○○は・・・ そんな風に言われたら許すしか無いじゃないの」
でも一つ条件があるわ、と彼女は続けた。
「紫って呼んで」
「え?」
「だから、私の事を紫って呼んで頂戴」
期待するような眼差しでリクエストしてくる。
そう言えば、よくよく考えると“恋人”になってからも彼女の事を呼び捨てた記憶は無かった。
多分、それは彼女に対する一種の敬意の様なものだったのだと思う。
でも彼女にしてみれば“恋人”にそんな感情を持って接されるのはあまり嬉しいものではなかったのだろう。
ならば、俺は彼女の願いに答える。
「紫・・・これで良いかな?」
「ええ、それで良いわ」
純粋に嬉しそうな彼女の笑顔を見て、俺もついつい釣られて微笑んでしまう。
「ね、もっと私を呼んで」
クルリと身体の向きを180°回転させ、向き合うような体勢になってねだって来た。
勿論、答えない理由なんて無い。
「紫・・・」
「○○・・・」
名前を呼び合って見つめ合う。
まさに王道的な恋人同士の空間が発生した様な気がする。
それが何となくこそばゆく感じた俺は、ちょっとした悪戯を試みる事にした。
「・・・愛してるよ、紫」
と、イケメンボイス(某領主風)で囁いてみる。
「・・・・・・・・・」
瞬間、紫の表情が硬直した。
そして徐々に瞳が妖しく揺れ始める。
・・・あ、しまった!
「ああ、もう我慢ならないわ!! さぁ○○、二人で楽園に逝きましょう?」
「ちょ、おまっ!!! 字がおかしいですって!」
「うふふ・・・大丈夫よ、優しくしてあげるから♪」
「や、止めてーーーー!!!!」
「逃がさないわよ♪」
(少年少女奮闘中…)
十数分後、俺達は互いに縁側に仰向けに倒れていた。
「はぁ・・・はぁ・・・はぁ・・・お、俺を殺す気ですか」
何の準備運動も無しに1000m走でもやらされた様に俺は全身から汗をかいていた。
「・・・もう、つれないんだから」
対して彼女は俺と同じ様に縁側に転がっているが、殆ど息が上がっていない。
「藍も橙もとっくに眠っているのだから、ナニをしたって良いじゃない」
「か、勘弁して下さいよ・・・」
今また字がおかしかった様な気がする。
でもツッコミを入れるとそれを逆手に取られそうなので止めておく。
「○○」
ふいに彼女の顔がアップになった。
おそらくはスキマを使って、俺の上に転移したんだろう。
腹の上に感じる彼女の重みが心地良い。
「愛しているわ」
言葉と同時に、そっと唇を奪われた。
微かに触れる程度のフレンチキス。
それはまるで麻薬か何かのように脳髄を甘く蕩かしていく。
「紫・・・」
「○○・・・ん」
どちらからとも無く再び口付け。
今度は先程よりも長く、深く。
互いの想いを確かめ合うかのように。
「っはぁ・・・・・・ねぇ、○○」
「ん?」
永遠の様な刹那の後、俺の上に跨ったまま頬を染めて彼女が言った。
「・・・そろそろ良いかしら?」
「・・・ん、分かった」
夜は更けていく。
恋人たちは今宵もきっと幸せな夢を見るだろう。
どうか、どうか二人の穏やかな幸せが末長く続きますように。
うpろだ361
───────────────────────────────────────────────────────────
吾輩は罪袋である
名前は知らない
年齢も、血液型も、自分の顔も知らない。
「ゆかゆか~ゆかりん~~ゆかりんゆかゆか~♪」
今日も今日とて、吾輩はゆかりんをつけ狙う。
「ゆかりん~♪……ゆか?」
クンクン……
おおぅっ! 吾輩のゆかりんレーダーに反応がっ!
匂う……匂う匂う匂うぞッ!
胸一杯に吸い込まれる浄土宗……否、少女臭。
方向は12時方向、距離は約3km。
――――ん?
匂いの位置が変わった……スキマで飛んだか?
今度は3時方向で距離2km。
そのまま、吾輩の方向へまっすぐ近づいてくる。
「―――― スキマで移動しながら近づいても、気付かれてしまうみたいねぇ」
「かっわいいよ、かっわいいよ ゆ~かり~んり~~ん~~♪」
袋で目の前は見えないが、バットを構えた姿も美しい。
「今日こそ、殺してあげるわ……」
殺意を込めてバットを両手で握るゆかりん。
うぉぅ、これやばくね?
「今日と言う今日は永遠に私に付きまとえなくしてあげる!!」
一度、ゆかりんの式に「お前は、何故紫様をつけ狙うんだ?」聴かれたことがある
理由は無い
是非も無い
愛でもなく、憎しみでもなく、嫌悪でもなく――――
ただ、在るがままに此処に在り、在るがままにゆかりんを追い
在るがままにゆかりんから逃げ惑い、在るがままにゆかりんに折檻される。
そこに愛だの恋だの陳腐な感情などいらんのです!
偉い人にはそれがわからんのです!
「待ちなさ―――――い!!」
ゆかりんが走って追いかけてくる。
楽しい……楽しい楽しい楽しい~♪
追って追われて、折檻されて――――
「きゃっ!!」
可愛らしい声が響く……ちょっと待ちたまへ、今の可愛らしい悲鳴はゆかりんかッ?
「いたた……」
急ブレーキをかけて背後を振り返ると、ゆかりんが鼻を押さえていた。
どうやら、木の根っこに足を取られてすっ転んだらしい。
GJ!! 初めて見るゆかりんのドジっ子属性もGJだッ!!
いあ、それよりもスカートが肌蹴られていて白い下着とガーターベルトが――――
「――――きゃあっ!!」
吾輩の視線に気づいたゆかりんは、慌てて、スカートを抑える。
「~~~~ッ!」
怒りと恥じらいにより、一瞬で頬を赤く染めて
近くに転がっていたバットをスキマで手繰り寄せて
「飛んでいきなさ――――いっ!!!」
カッキ――――――ン!!!
「お~ぱ~○~つ、見えてるよ~!!」
おおぅ、これ大気圏脱出できるんじゃね?
生身で大気圏脱出ってすごくね?
って、いつの間にか大気圏脱出したよ俺SUGEEEEEEEEEEE!!
あれ? ……なんか太陽が近づいてきてる
そうかー、このまま太陽に突入して燃え尽きるのかー
熱いなあ、地球が遠くなっていくな……萌えていくなぁ……
「 か わ い い よ ~ ゆ か り ん ! ! か わ い ~ い よ ~~~♪」
でも吾輩は死ぬことは無い。
いろいろ手を尽くして、明日には幻想郷に戻れるだろう。
あぁいる びぃぃー ばぁぁーーーーっく!!
……吾輩は罪袋である。
名前はいらない。
・
・
・
―――― 一方、博麗神社の境内では霊夢と藍と橙がお茶を啜りながら
「以前、あの罪袋に『お前は、何故紫様をつけ狙うんだ?』って聞いたら……
『お前は、何故 自分が此処にいるか 考えたことはあるか?』……って返されてな」
「何それ、どういうこと? 」
「あの罪袋にとっては、紫様に付きまとうのは愛じゃなくて……
自分が存在すること=紫様を追いかけ追い回され折檻される……と言うことだろうな」
「難儀ねぇ……紫もあの変態も」
「紫様おっしゃってましたねぇ……『あの罪袋が相手だと自分のペースが狂わされる。あんな不条理な生物は見たことない』……って」
「そうだなぁ……紫様のスキマで異次元にすっ飛ばしても、次の日には必ず戻って来るしな……」
「どういう生き物なのよ……」
「最近では紫様、逃げるの諦めて自分からあの罪袋を叩きのめしに向かわれてるんです……」
「でも、心底気持ち悪がられている反面、妙にノリノリでバット持って出かけられるんだよな……」
「…………」
end
ちなみに、罪袋=○○ ねー
うpろだ383
───────────────────────────────────────────────────────────
「ちょっと待てー!?俺が一体何をしたー!?」
「問答無用!!」
チュドーン!!
「ウボァ~~!」
先ほどから馬鹿騒ぎをしているのは私の主、八雲 紫様とその恋人○○である
恋人なのに上のようにバイオレンスな関係なのはひとえに我が主紫様の所為である
妖怪の賢者とまで言われていてもこと恋愛関係には非常に初心だ
以前○○が不意打ちで紫様にキスをした時真っ赤になってテンパった紫様に
「高速の永久弾幕結界」で白玉庵まで吹き飛ばされたことは記憶に新しい
その後吹き飛んだ○○をみて赤い表情から青い表情になったときは不謹慎だが面白いと思ってしまった
ちなみに今回の騒ぎになった原因は……
~回想開始~
「ゆっかりー、おはよー!」
「ZZzz」
「紫ー、起きろー」 ゆさゆさ
「Zzz」
「ゆーかーりー!グッド、モーニーング!!」
「Zz、ん~もう少し寝かせてよ藍~…………………!!??」
ガバッ!
「○、○?」
「おそよう紫」
「…………もしかして見た?」
「もしかして寝顔のことか?それなら見たぞ、可愛い寝顔だった」
「ghs8bfD#gje!!??/////」
「ん?どした?顔、真っ赤だぞ」
「……の馬鹿」
「は?」
「○○の馬鹿ー!!!」
そして冒頭へ
~回想終了~
とまあ単純に紫様が○○に寝顔を見られたのが恥ずかしいから怒ったことだ
まったく紫様もいつまでたっても初心だな、他の者の恋をからかうのは好きなのに
自分の事になると奥手になる、そして恥ずかしがって○○に当たる
○○も災難だな
うむ、まだ続いてるな
「待ちなさい、○○!!」
「だが断る!!今待ったら死ぬ!」
「なら!」
紫奥儀「弾幕結界」
でた紫様の切り札「弾幕結界」逃げ道を防ぐように展開される弾幕には
○○ごときでは成す術もなく落とされてしまう
救急箱の準備と橙に頼んで薬師を呼んできてもらうか
「甘いぞ紫!!今までの俺と思うな!!」
「何をする気?」
反則「防弾結界」
○○がスペルカードを発動すると周囲に結界が貼られ弾幕がすべて消え去った
まさに反則だ
「な、なによこれ!?」
「これぞ俺の切り札の一つ「防弾結界」、発動すれば結果内の弾幕は全て消え去る!」
「それは反則よ○○」
「うるせー!日々弾幕に追われぼっこぼこに被弾する俺の気持ちも考えろ
紫に始まり魔理沙にチルノ、雑魚妖精や毛玉にも撃たれボコボコにされ……
あれ?目からしょっぱい水が……なんだろうすごく悲しいや、うぅ!!」
漫画みたいな大粒の涙を流す○○、よっぽど悔しかったか……
というか毛玉にやられるって……
見れば紫様も物凄く気の毒そうな目で○○を見ている
「ま、○○だって頑張れば強くなれるわよ
現にこんなにすごいスペルカードを作ったじゃない
もっと頑張れば毛玉なんかすぐに倒せるわよ」
「でも俺接近戦が主体で弾幕なんて撃てないし
第一空、飛べない」
「で、でもスペルカードならそんなハンデなんて覆せるわよ
あるでしょ、攻撃用のスペルカード」
「あるにはあるけど効果がちょっと……」
「男は度胸、なんでも試してみるべきよ
変なところがあったら私も協力するから直せば良いじゃない」
「うーん、紫がそこまで言うならちょっとやってみるか
じゃあとりあえず結界貼ってくれ」
「分かったわ、壊すぐらいの気合でやりなさいよ
まあ無理だろうけど」
境符「四重結界」
「んじゃ、いくぞ!!」
そう言うと○○は拳を振りかぶりスペルカードを発動させた
鬼拳「一方通行」
ゴゥッ!!
○○の拳から撃ち出された拳大ほどの大きさしかないレーザーみたいなものは
真っ直ぐと紫様の方へ飛んでいった
速さは大したものだが紫様は事前に結界を貼っているから大丈夫だろう
ギリリッ パリィン!!
「!?紫、避けろ!!」
「くっ!!」
それは四重結界に当たると暫らく拮抗した後四重結界を破っりそのまま紫様に直撃しそうになった
しかし○○が結界が破られる前に避けるように警告した為
掠っただけで紫様は無事回避できた
一方通行は四重結界に当たったにも拘らずそのまま真っ直ぐ飛んでいった
別に真っ直ぐ飛ぶのは問題ないんだがただ私の位置に問題があった
図にするとこうなる
○○ 紫様 ――→ 私
↑
一方通行
紫様の後ろで観戦してた私は四重結界が破られたことに驚いて
紫様がとっさに避けた一方通行を避けきれずそのまま直撃を受けてしまった
その衝撃で気絶直前の意識が捕らえたものは
「紫!大丈夫か?」
「ええ、○○が早めに教えてくれたから掠っただけよ
それにしても結構な威力ね」
「スマン、俺の所為で紫に傷を……」
「文字通りかすり傷だから大丈夫よ」
「でも、紫の陶磁器の様な肌に傷をつけてしまった」
「も、もうほめても何もでないわよ////」
「紫、本当にすまない」
「だからもう謝らないでっていってるでしょ」
「俺の気がすまないんだよ」
「なら……だ、だだだだだだ抱きしめてくれない?////」
「それぐらいならいくらだってしてやるよ
なんならキスもどう?」
「だだだだ抱きしめるだけで十分よ!!」
「そっか、残念」
顔を真っ赤にしながら○○に抱きしめてもらう紫様と
紫様を抱きしめさりげなく紫様の髪の匂いを嗅ぐ○○の姿だった
……………………覚えてろ○○
そして目を覚ました私が見たものは真っ赤な顔をしながら私の枕元に座っている橙と
あの後何があったのか知らないがやけにイチャネチョしている二人の姿だった
その様子を見てもう大丈夫なんだなと思いもう一度意識を手放した
うpろだ405
───────────────────────────────────────────────────────────
「…………………・・・○○…………○○……」
「ううぅん、何ですか紫様……。まだ眠いですよ…」
「そりゃあれだけハッスルすればね。うふふ、元気だったわね」
「もう精も根も尽き果てましたよ。あいたたた……腰どころか背中まで痛い…」
「うふふ。はい、お水。のど渇いてるでしょ?」
「ありがと……んっ…ちゅるっ……ぷはっ」
「まだ飲みたい?」
「どうして口移しで飲む必要があるんですか……」
7スレ目>>745
>>745の続きを勝手に考えて書いてみた
反省はしているが後悔はしていない、若干紫の性格が違うかも
「紫様、お食事ここに置いておきますね」
襖の向こうから→「ええ、ありがとう藍、ほら○○ご飯よー」
同上 →「ちょ!?待て!紫一人で食べれるかr」
「藍様ー、ご飯持っていたんですよね?紫様と○○さんどうでしたー?」
「あ、ああ二人ともちゃんとご飯を食べてるよ」
「そっかー、でもなんで箸一つしか使わないんだろ?」
「き、きっと紫様が○○に『あーん』をしてあげているんだろう」
(○○の様子だと絶対口移しで食べさせられたんだろうな……)
「仲いいですね紫様と○○さん」
「恋人同士だからな」
(それにしたって四日間部屋に篭りっきりっていうのは……その、なんだ橙の教育に悪いよな、声も時々聞こえてくるし)
「でも今度は四人一緒に食べたいです」
「ああ、楽しみだなその時はご馳走を作るから橙も手伝ってくれるか?」
「はい!」
「などと言ってますけど、そろそろ出るか?橙も寂しがってるし……ってなんで泣くんだよ!?」
「グスッ…ヒック、だって……○○は私のこと嫌い?」
「嫌いじゃないって!愛してるから、な?泣くなよ」
「ええ、分かったわ、だからもう少しだけ……ね?」
「ああ、分かった、来いよ紫お前の全部、俺が受け止めてやるよ」
(……惚れた弱みだな、すまん橙、四人一緒にご飯食べるのはもう少し後になりそうだ)
7スレ目>>791
───────────────────────────────────────────────────────────
藍の日記より。 ~乙女(?)の葡萄踏み~
@月*日。
紫様が台所に立っている。
最近御執心の○○に手料理を振舞おうと張り切っておられるようで、
そんな紫様からは少女臭がぷんぷんする。 それにしてもあれは…
紫「~♪」
藍「紫様、何をされるおつもりで?」
紫「今年はブドウの出来がよかったから、
きっと美味しいワインができるって聞いたのよ。」
藍「それで…そのブドウを人里から失敬してきたと?」
紫「それだけじゃないわ。私の手作りワインを造って、
ああしてこうして、○○をとろけさせてやるのよ♪」
藍「人里のお酒なんて、できあがったやつを失敬してくればいいじゃないですか。」
紫「いえいえ藍。男は女の手作り料理や贈り物に弱点属性持ってるものよ。
人間の女性は手料理ひとつで男の愛と恋の境界を操ってしまうのだから。」
そういうと紫様はたるの中にブドウをほいほいと詰め込んでいく。
ああ、まてよ?たしかブドウからワインを作る方法って…
ttp://allabout.co.jp/gourmet/wine/closeup/CU20051006A/
紫「さあ、できたわ♪ 藍、ちょっと味見してみない?」
藍「あ、頂きます。」
(ぐび…カシャーン!)
藍「ぐおぉ…」
私は…それを一口飲んだだけで倒れてしまった。
鼻を突く刺激臭、なんてレベルのものではない。視界が…歪む…
紫「あら、藍?あなたそんなにお酒に弱かったかしら?」
藍「い、いえ…その、紫様…ひとつお聞きしてもよろしいですか?」
紫「なぁに?」
藍「その…靴下は…」
紫「ああ、本当は脱ぐのよね。
種や枝が当たると痛いから履いたまま踏んじゃったけど…」
藍「ウボァ」
(バタッ!)
後日、人里でワインを調達して中身をすり替えておこう。
私は紫様の従者なればこそ、主が哀しむ結末を避ける義務があるのだから…
7スレ目>>796
───────────────────────────────────────────────────────────
「ごはん…私のごはん…(ジュルリ)」→みんな
「貴女の為ならこの身体。喜んで貴女の血肉となりましょう」
7スレ目832-833
───────────────────────────────────────────────────────────
(もそもそ…)
「う、もう3月…藍ったら、起こしに来てくれてもいいじゃない。」
今年も春がやってきたようだ。さて、そろそろ起きようかしら。
(のそのそ…)
いつもだったら、このままもう1年寝ていたいとか思っちゃうのだけど今年はちょっと違う。
今の私には、日々のゴロ寝と同じくらい楽しみなことがあるのだ。
そう、あれはもう半年も前の事だったかしら…
(少女回想中…)←まとめ、「紫2」の真ん中より少し下辺りの「~小劇~」より。
↑突っ込みたい部分あるかもしれないが黙って読んでくれると嬉しい。
彼は、なんとも変わった男だった。
どうやってこの迷い家までやってきたのか?
もしかしたらどこかに閉じ忘れたスキマがあったのかしら?
とにかく、ある日突然彼はやってきた。
そしてその日初めて会い、言葉など大して交わしてもいないのに
大真面目に、これ以上ない熱を込めて、私の事を好きだという。
あまりにも唐突で予想もできないその告白は
例えるならファイナルスパークをタメ無しで零距離照射されたかのようで
私の心は食らいボムを打つこともできずにこんがりと焼かれてしまったようだった。
あぁ、なんて不覚。この八雲紫、幾千幾万の弾をこの身にカスらせようとも
被弾を許す事なんて今まで生きてきた中でも数える程しかないというのに。
それをまさか、ぱっと見、何の「○○する程度の能力」もなさそうな人間に許すとは…
本当なら私が被弾を許すなんて悔しい事この上ないハズなのに
まんざらでもない気持ちになるのは身でなく心に被弾を許したせいかしら?
そう思うとやっぱりちょっと悔しいわ。
私は嬉しさ半分、悔しさ半分、それととっさの照れ隠しから
つい彼に意地悪を言ってしまった。それもとびきり絶望的な一言を。
「そうねえ…あなたがボムも復帰無敵もなしに私の弾幕をかいくぐって
私をさらってくれたら、貴方の物になっちゃおうかなあ♪」
「ΣΣ(゚д゚lll)」
ああ、バカな私。何言ってるんだろ。
人間にそんな事できるわけないじゃない。
彼は博麗でもない、魔法使いでもない、蓬莱人でもない。
そして私は⑨でも夜雀でも蛍でも毛玉でもない。
私が言ったこの一言が、普通の人間である彼にしてみればどれほどの難題か。
多分月のお姫様が出した五つの難題にも勝る難題だと思う。
でも彼は…
「紫様、なんですか、それ?」
「ああ、これ?撃墜マーク。」
「8個…愛されてますね…」
それから毎日、痛い目にあっても懲りることなくやってくる。
しかも毎日少しずつ、私の弾をよけ続ける時間が伸びているのだ。
コレはもしかしたらと期待してしまう。先は長いけど…
「難しくしすぎたかなあ…(´・ω・`)」
「ホントは攻略されたいんですね。」
「よくわかってるのね。」
「そりゃまあ、紫様あいつが来る時間帯は起きてますからね。」
なまじ彼が頑張るのもあって、今更言い出せないじゃない?
「あれはただのイジワルで言ってみたのよ」なんて…
それに彼が頑張るなら、ソレはソレで夢見たくなるのよ。
少女なら誰しも、 (←相変わらずスルー推奨)
『私をその両腕で抱きしめてくれる殿方には、
私を守ってくれるくらい強い男であって欲しいなあ』…って願うのは当然でしょ?
「ねえ藍、ちょっとあいつを手伝ってあげてくれる?」
「へいへい…でも紫様、あやつが気に入ったのでしたら、
紫様があいつの心なり人妖なりの境界いじっちゃえば…」
「それはダメよ。」
「なぜです?」
「それじゃあ私と彼の間には『主従』の関係が出来ちゃうじゃない。
彼が自分の力だけで私を攻略してこそ、
私と彼は恋する男と少女の関係を築けるのよ。キャッ(*ノノ)」
「はあ、さいですか。(汗)」
私は藍に彼の特訓をするように命じた。
藍は私のパターンを熟知しているし、一部は近い形で再現できるものもある。
もしうまくいけば、私が冬眠から覚めたころには、
見違える進歩を遂げているかもしれない。
(回想終了…)
と、言うわけで、私は期待に胸を弾ませならがら起きたのだった。
こんな気持ちで眠りから覚めるなんて、久しく記憶にないことだ。
もし彼が…本当に私を攻略できたら、なんて言おうかしら?
『よく頑張ったわね』
…う~ん、ありきたりすぎるからダメ。
『おめでとう、ご褒美は私よ♪』
これこれ、こういうの。でも、手加減したとか思われたら嫌だわ。
『こら、どれだけ待ったと思ってるのよ。』
うん、コレは私の素直な本音。
『ちゃんと責任とってよね。』
コレもいいわね。「何の責任」かあれこれ悩んでもらおうっと。
私が寝てたおよそ3ヶ月。
その間藍がみっちり鍛えててくれたのだ。
愛と欲を燃料に動く人間は、さぞかし見違える進歩を遂げているだろう。
あぁ、待ち遠しい、待ち遠しい。
幾年月をも生きた私だ。待ち遠しいなら寝てその時がくるのを待てばいい。
そう考えるのが常だったけど、今は彼の両腕に抱きしめてもらう
その日が来るのが待ち遠しくて仕方がない。
冬眠から覚めた今、1日だって待つのが辛い。
「むふふ…(じゅるり)」
そして今の私は、それを想像して笑みが漏れてしまっている。
こんな顔、絶対藍にも橙にも見せられない。
私はにやける表情を抑えて、平常心を取り戻してから寝室のふすまを開ける。
このふすまは、冬眠時に潜っている空間と通常の空間の境目でもある。
この部屋を出ればもうそこは、いつもの迷い家(我が家)…
(カラッ…)
「やあ、おはよう。それとも、あけましておめでとう、かな?」
「なっ…!?」
ふすまを開けてすぐの所に彼が立っているではないか。
(じゅうぅぅ…)
一瞬で顔が真っ赤になってしまうのが自分でも判る。
頭は茹ったようで思考がままならず、心臓は跳ねるように激しく脈うっている。
もしかしてずっと私が起きてくるのを待ち伏せしていたの?
いや、それよりももしかしてさっきの「むふふ」とか聞かれてた!?
「な、な…」
何でここに?それすらマトモに口に出来やしない。
私はスキマを使って霊夢の前や、幽々子の前に突然不意打ちのように登場する事はあるけど、
その逆、自分が不意打ちをされた事はない。
ひどい、これはひどい。そういえば初めて会ったときの告白もそうだった。
今はじめて判った。彼の能力はきっと「不意を突く程度の能力」に違いない。
「どうした?今日こそ起きるかなと、紫が起きるのを待っていたのに
だんまりで出迎えとはつれないな…」
「そ、そんなんじゃないわよ、ただ…」
「ただ…何だ、熱でもあるのか?顔真っ赤だぞ?」
「だ、大丈夫。大丈夫だからっ!」
今しがた妄想にやける表情を抑えて取り戻した平常心は、もう粉みじんに吹き飛んでしまった。
それどころか、真っ白になった頭は平衡感覚すら失わせ…
(よろろ…ばふっ)
赤面を見られまいと後ろを振り向こうとするも、
足がもつれて私は彼の胸につんのめる様に倒れてしまう。
「きゃっ…」
「全然大丈夫じゃないだろ。あんな空間で一人で寝てるからだ。
まってろよ、藍に布団の準備をしてもらおう。」
彼は私をひょいと「お姫様抱っこ」に抱え上げる。
どうやら、風邪で高い熱が出ていると誤解しているようだ。
だったら、このまま誤解していてもらおうかしら。
「(このまま風邪引いたふりしてたら、看病までしてくれちゃったりするかしら…)」
だって、あこがれのお姫様抱っこよ?
こんな王道的シチュエーションに巡り会えたら、以降のベタな展開も一通り味わいたいじゃない?
「(私が寝てる傍でずっと看病してくれたり…)」
「ところで紫。」
「(ゴハンのおかゆを『あ~んして』って、食べさせてくれたり…)」
「紫?」
「そ、そして汗で濡れた服を着替えさせようとして…そのまま勢いでっ!あぁ、ダメよそこまでは!」
「紫…(汗)」
「はっ!?な、なにかしら…?(ドキドキ…)」
しまった。ちょっとこの後の展開を妄想してぼんやりしたようだ。
えーと、私口に出してしゃべってなんかいないわよね?
「今の状態は…俺がノーボムで君を捕まえたって事にならないかな?」
「あ゛…」
や、やられたわ…GOOD ENDING No.2、
No.1条件は90日以内の正攻法攻略…って所かしら。
「そ、そうね…おめでとう、ご褒美に責任取ってよねっ!」
「何言ってんだ…?(汗)」
そのころ茶の間では…
「紫様起きたみたいですね。」
「うむ、そして○○は上手くやったみたいだな。めでたしめでたしだ。」
(ズズズ…)
藍と橙が、いまだにしまっていないコタツに入り、お茶をすすっている。
(橙の湯のみからは湯気が出てないからきっとすごくぬるいのだろう。)
ちなみにお茶菓子はガチガチに硬くなった正月のお餅の残りとにぼし。
「でも藍様怒られませんか?」
「何でだ?」
「紫様を起こしに行かなかったことと、○○の不意打ちを見逃したことと…」
「ああ、それは大丈夫だろう。紫様は○○に攻略されたいって、ハッキリ言ってたし
それに私は『○○を手伝え』って言った命令に従っただけだからな。ああ、でも橙…」
「はい?」
「紫様の不意を突けって、私が言ったのは内緒な。
○○は、自分の力だけで紫様を攻略した…わかるな?」
「…はい♪」
どうやら今回の彼の不意打ち…考えたのは藍のようだ。
もしかしたら藍の方が毎日一緒に居た分、彼の不意を突く能力に早く気づいていたのかもしれない。
さすが私の式、あなたが居て本当に良かったわ…ありがとう、藍。
(↑神速突撃で自爆させた件はなかったことに。)
こうして私の想いはみんなのおかげで叶ったのだった。
藍や橙とは違う意味で、私を大事に想ってくれる人が傍にいるというのは
なんともむずがゆくて、そしてなんとも心地よいものだ。
とりあえず彼には残る一生、私に幸せという名のゴハンを食べさせて貰おう。
それが彼の責任。年中寝ても起きても、私が幸せに飢えることがないように…
もし浮気なんかしたら、本当に食べてやるんだから…
6スレ目 >>837
───────────────────────────────────────────────────────────
家でまったりしていると、
いきなりスキマがひらいて、
紫が背中にしなだれかかってきて、
なにしてんだ。っと聞いたら
「○○分の補給。一日できれちゃうから。」っといわれた。
そのまま縁側で昼寝していたら藍が紫を迎えに来てた。
そんな日がしばらく続き…その年の秋のことである。
紫「貴方が居てくれたら、私はそれだけで(幸せで)お腹いっぱいなの♪」
(ぎゅっ…)
俺「(*´∀`)」
紫「だから…一緒に冬眠しましょ♪」
アッー…
7スレ目 >>109-110
───────────────────────────────────────────────────────────
「恋し 愛する事も、若さの秘訣だと思いませんか? 紫様」
7スレ目>>446
449 :名前が無い程度の能力:2007/05/07(月) 22:34:32 ID:cKRr5DW.0
>>446のセリフから幻視したのでちと書いてみる
紫「あらそれなら私はずっと若いままね」
○「へえ、何でそう思うんですか?」
紫「だって私は貴方に恋をしているんですもの」
○「奇遇ですね俺も紫様に恋をしてるんですよ
こんな形になっちゃいましたけど好きですよ紫様」
紫「それなら紫って呼んで……」
○「ええ、愛してますよ紫」
紫「……ん…ふぅ」
藍「…しばらく目を離したと思ったら何ですか?この状況」
幽「新しいカップルの誕生ね~♪」
橙「いいなー紫様ー!」
藍「ちぇ!ちぇちぇちぇちぇちぇ橙!?」
───────────────────────────────────────────────────────────
紫「ZZZzzz…」
○「…紫、寝た?」
紫「…ZZZzzz…」
○「(寝たかな…)」
(もそ…)
俺は紫を起こさないように、そ~っと布団から出ようとするが…
(ぎゅっ!)
強く捕まれて阻止される。
紫「(じー…)」
○「う、寝てなかったの?」
紫は恨めしいジト目…にも見える寝ぼけまなこで俺を睨んで…
紫「…抱きマクラが布団を出ちゃダメ…」
…と、有無を言わさぬ一言。
○「はい…」
毎夜こんな調子。あぁ、自制心フル稼働で、今夜も寝不足…
7スレ目>>565
───────────────────────────────────────────────────────────
「たとえ君にとって俺の一生が刹那の一時でも、共に歩んでいくことを許してくれるかい?」
7スレ目>>685
───────────────────────────────────────────────────────────
恋に溺れた、たった1つ。それだけ。
「紫様…ゆかりさまぁ…」
虚ろな眼で上を見ながら彼はただ呟いている。
最近の話だ、幻想郷の外から青年が1人やってきた。何かしらの原因でこっちに迷い込んでしまい、彼は元の世界への帰還を望んだ。
だが、ある日を境に彼は元の世界へ帰ることを望まなくなった。かわりに彼は言った。
「俺、紫さんとお話がしたい。」
博例神社境内の宴会の日、いつもは家に引きこもっていた彼も宴会のあまりの喧しさに外に出てきた。その時、彼は紫を見て恋に落ちる。
そこから彼は苦しみ悩む。
元から篭りがち性格が拍車をかけ、延々と悩んだ。
お話がしたい、俺を見て欲しい。
たとえ妖怪であろうと構わない、愛されたい。
殺されてもいい、愛されたい。
変態的な愛はみるみる膨張し、自分の内の殻を突き破ったとき通常の精神は飛散した。
彼は裸足で神社を飛び出した。紫さんに愛されたい、その一心でそこらを駆けずり回った。
途中身体が動かなくなって気を失っているところを霊夢に保護、すぐに霊夢は破綻した精神の治療を鈴仙に頼んだが結果は失敗。
「精神が一部が欠落しては波長の合わせようがない。」
それでも何とかならないかと話し合ってるうちにも、彼は両手足を縛られた身体で床を這いながら外へ行こうとする。
「芋虫みたいね。」
紫の声がした。
スキマから現れる紫、そして歓喜に満ち溢れた顔で地を這い彼は紫の所へ向かう。
「○○、ですわね?」
「はい!はい!そうです!!」
「こんなに縄で縛られて…」
紫は彼を束縛する縄を解いた。
「私がもう一度縛り直してあげますわ。」
紫は更にきつく、がんじがらめと言った風に縄で彼を縛り直す。彼は涎を垂らして悦んだ。
「私に愛されたいそうで…
私の奴隷になる?」
「喜んで!」
「じゃあ、私の足を舐めなさい。」
「はっ…!」
彼は紫の奴隷になり、スキマの中に放り込まれた。
「○○。」
「はぁああ…!ゆかりさまぁ…!」
彼は呼ばれて犬のように紫に駆け寄った。
「ほら、まずは足よ。」
「はい!あし、あしぃ…」
片足を彼に舐めさせ、余ったもう片方の足で彼を踏む。
「本当に変態な犬ね。そんなに嬉しいの?ねえ、嬉しい?」
「はい、うれしいです…!」
「ふふ、今日はそんな変態にご褒美よ。
数週間穿きっぱなしの私の靴下よ、口を開けなさい!」
「ふあ…あ、が!?」
紫は彼の口の中に黒い靴下を突っ込む。
「嬉しいでしょう?変態の貴方は靴下が大好きだものね?」
「…!…!」
言葉が出せず、頭を動かす犬。
彼の願いは叶った。
愛される。たとえそれがどんな形であれ、彼は愛されていると思っている。
彼は幸せだった。
うpろだ244
───────────────────────────────────────────────────────────
幻想郷に来て1週間が経過しようとしていた。
俺が居候をしているこの場所はマヨヒガと言い、何でも現実世界からの迷子たちがやって来る場所らしい。
「まぁ、俺もある意味では迷い子だよな」
最近俺のいた世界では『神隠し』が流行っていた。
その事についてぼんやりと思いを巡らせていた所、その『神隠し』の主犯と思しき人物・八雲紫が我が家に現れたのだ。
そして彼女との会話の中で幻想郷に興味を抱いた俺は、進んで彼女の『神隠し』に遭った。
これが事のあらましだ。
好んで現実から逃れた辺りが、俺が別の意味で“迷い子”たる証明だろう。
「しかし・・・ なかなかどうして良い所だな、此処は」
普通の人間にとって、幻想郷の日常や常識の中には受け入れがたいものもある。
「まぁ、初めて人の生頭蓋骨を見た時は驚いたけど・・・」
人間であるから、と言う理由でお遣いに出されて、その道中に頭蓋骨が一個転がっていた事があった。
流石にアレは驚いた。
同時に“自分は幻想郷にいる”と言う実感を持たせてくれた。
「みんな、俺の事を心配してくれてるかな?」
何も残さないで消えると本気で『神隠し』扱いされるので、一応テーブルの上に「ちょっと旅に出てきます」と書置きして休学届けを置いておいた。
「ま、俺如きが消えても悲しむ奴なんていないか」
元より自分が変わった人間である事は理解しているつもりだ。
もしかすると、心配するどころか内心喜ばれているかもしれない。
「・・・でもそれは少し寂しいな」
可能性は否定できない。
「あら、私は悲しいわよ?」
後ろからの声。
この声の主こそが、俺を幻想郷へと誘った存在。
「貴女が消えてしまったらね」
八雲紫。
このマヨヒガに住まう大妖怪にして、幻想郷最強と名高い存在だ。
「はは、それは食料が消えるからでしょうかね?」
「もう、食べないと言ってるじゃない」
この1週間で何度も繰り返された応対。
もはやこれがジョークの域に達している辺り、俺も此処での生活に慣れてきていると言える。
「だって食べてしまったら・・・」
しかし今回の彼女の反応は一味違った。
相変わらず、底の見えない微笑を浮かべたままこちらにやって来る。
ふいに、目の前が真っ暗になった。
「この感触も、匂いも、温もりも感じられなくなってしまうでしょう?」
言葉と一緒に流れてくる甘い香り。
魅惑的な罠の匂い。
つまり俺は彼女に抱きつかれたのだ。
「うわぁ!!」
女性に抱きつかれる、などと言う黄金経験の無い俺は、咄嗟に彼女の事を振り解いてしまった。
「あらあら、随分と初心なのね」
特に気にする様な事もなく、見慣れた胡散臭い笑みを浮かべる紫さん。
「じょ、冗談にしてもタチが悪いですよ・・・」
心臓が早鐘を打っている。
ただでさえ暑かったのに、今度は別の意味で暑くなってしまった。
「・・・・・・・・・・・・・・・冗談じゃないのに」
彼女はポソリ、と何かを呟いた様だけどよく聴き取れなかった。
「はぁ・・・」
溜め息を一つ、視線を外に戻す。
夏の夕日は空を赤く染め上げて、もう一日が終わる事を告げている。
鴉が数羽、定番の鳴き声を上げながら何処かへ飛んでいく。
どこからだか分からないが、蝉の声も聞こえてくる。
「すっかり夏ね」
「ええ」
気配が移動して、俺の横に腰を降ろした。
案外近い場所に気配を感じて俺はドギマギとしてしまう。
「知ってる? 今日ここの近くの村でお祭りがあるのよ」
「そうなんですか?」
何と幻想郷にも夏祭りは存在するらしい。
いや、収穫祭とかがあるのだからあってもおかしくはないのかも知れないが。
「ええ、だから今夜一緒に行かない?」
「え?」
突然のお誘い。
そんな言葉が来るとは思っていなかった俺は、思わず素っ頓狂な声を出していた。
「だ・か・ら、今夜お祭りに一緒に行きましょう?」
こちらを覗き込むようにして紫さんが繰り返す。
一介の居候である俺に今後の予定なぞ入っていない。
よって断る理由など無いので快諾する事にする。
「良いですね、ご一緒しましょうか」
「ふふ、そう来なくっちゃね!」
朗らかに笑う彼女の姿にはいつもの妖艶な雰囲気は無く、どこにでもいそうな少女のそれと同じように見えた。
何となく、釣られて俺も笑ってしまった。
「そうと決まれば浴衣を選ばなくちゃいけないわね・・・ ふふふ、楽しみにしていなさい♪」
そこはかとなくスキップでも始めそうな軽やかな足取りで、彼女は自室へと向かっていった。
「・・・夏祭りか」
呟きは、茜色に染まった空へと吸い込まれて溶けた。
久しぶりに人間を見た気がする。
いや、純然たる人間を見たのが久しぶりなのであって、人の形をしたものは毎日見ているのだが。
マヨヒガから最寄りの村の近くに俺は立っていた。
ちなみに自力でここまで来た訳ではない。
「九尾の狐も怯える訳だ」
どう行けばいいのか、と問う俺に対して「簡単な方法があるわ」と彼女は答えた。
その声を最後に聞いて、俺は急激な浮遊感を味わった。
要は「スキマ」に落とされた訳である。
いきなりの事に驚く間も無く、一瞬だけ視界がブラックアウトしたと思ったらここに立っていたのだ。
こうして俺は感じた事の無い猛烈な危機感と恐怖感を味わった。
「止めよう、思い出すのは・・・」
頭を振って、恐怖体験プレイバックを止める。
村の方を見やるともう祭りは始まっているのか、賑やかな人々の声と提燈の生み出す穏やかな明かりが目に入る。
「しかし祭りに行くなんて子供の時以来だ・・・」
元よりインドア派である俺は、中学に上がる頃にはお祭りなど殆ど観に行かなくなった。
単純に暑いのが嫌だった、と言うのが理由の大半を占めるのだけど。
「お待たせ」
村の近くで待機し始めてから大体15分くらい経った頃、聞き慣れた声がした。
「いや、それほどm」
振り返った先で声を失った。
「ふふ、どうかしら?」
濃紺の布地には黄色い百合(これは虎百合だろうか)が咲き乱れており、帯の色は燃えるような緋色。
いつもは降ろしている髪は結わえ上げられており、赤いヒールは黒漆の下駄になっている。
総じて、
「物凄く・・・・・・綺麗です」
「ありがとう」
浮かべた笑顔も、いつもにも増して美しく見えた。
「さ、参りましょう?」
闇にも映える白い手が差し出される。
「あ・・・はい」
おずおずと手を取る。
村の方へと向かう最中会話は殆ど無かった。
何か話そうとは思ったのだが、緊張してしまって声が出なかったのだ。
程なくして、村の中へと俺たちは足を踏み入れた。
「・・・何だ、あんまり現実世界と変わらないんだな」
祭りの会場に入って第一声はこれだった。
幻想郷のお祭りと言うからには、どこか現実離れした光景が見られるのかと思っていたのだが、思いの外現実のお祭りと変わった所は無かった。
ただ夜店で時折見たことの無いものがある辺りは、やはり幻想郷らしさを感じるが。
「へぇ・・・ 貴方の世界のお祭りもこんな感じなの?」
扇子(今回は和風だ)を軽く扇ぎながら紫さんが言った。
「ガキの頃に行ったのが最後なんで、今もそうかは分かりませんがね」
「ふぅん・・・」
俺の言葉に短く答えて、彼女は目を細めた。
視線の先には大勢の人間。
「宴会とはまた違った趣があるものね」
そう言えば、彼女は博霊神社で行われる宴会にもよく出席している妖怪だったはずだ。
しかし今の言葉から察するに、人間のお祭りはあまり行った事が無いらしい。
「あまりお祭りには参加しないんですか?」
「あら、私が何者だったかお忘れになって?」
「あ・・・・・・」
そうだ、彼女はこの幻想郷の中でも屈指の強さを誇る妖怪だ。
ならばそんな存在に対して人間はどんな感情を抱くか。
すなわち、恐怖。
「私の事を見ると大抵の人間は怯えるわ。 ・・・丁度初めて会った時の貴方の様にね」
人は理解の及ばないものを怖れる。
それが自身と相容れない存在であればなおの事。
「もっとも今は“認識の境界”を少々弄くっているから問題はないのだけれどもね」
ここまで来てようやく俺は思い至った。
彼女にとって本当は“人間のお祭り”など“孤独”を感じるだけのものに過ぎないのかもしれないと。
「何で・・・」
「ん?」
「どうして、お祭り行こうなんて言ったんですか」
境界を使って無理矢理入り込まなければならないなんて悲しすぎるじゃないか。
どんな上手に紛れ込む事が出来ても、そこに本当の彼女はいないのだから。
「一層、博霊の宴会の方が良かったんじゃないですか?」
そんな俺の言葉に彼女は目を丸くした後、
「そんな事ないわよ」
穏やかに笑った。
「でも境界を操作しないと貴女は・・・」
「その程度の事は気にしないわよ。 それよりもね・・・」
そこで一旦言葉を区切り、
「私は貴方と共通の体験をしたかったのよ」
頬を染めてそんな事を仰った。
「え? あ、いえ・・・その、光栄です・・・・・・」
ある意味これは・・・
いや、そうでなくても相当胸に来る言葉だ。
顔が火照ってくるのがよく分かる。
そこまでして俺なんかと同じ体験をしたいなんて・・・
「共通の体験をするだけならば、博霊神社の宴会でも構わないのだけど・・・」
確かにその通りだ。
体験の共有自体は、二人で同じ事をすれば良いのだから。
「吸血鬼のお嬢様とかに獲られちゃ嫌ですもの」
「あ、そう言えば・・・」
博霊神社の宴会は人と妖怪が入り乱れた混沌空間であると聞く。
ならば弾みで何が起きるか分からない。
「でも、貴女が睨みを利かせていれば問題無いのでは?」
「食べられる、と言う言葉には二つの意味がありますわ」
それはないと思う。
俺の言う事なんて紫さんでもなければただの狂人の戯言に過ぎないし。
そもそもが、そういう事も彼女ならば防げるのではないだろうか?
もしかしてこれは・・・
「・・・独占欲?」
ポソリと呟いてみる。
「ふふ・・・ どうかしら?」
対して彼女はただ恥ずかしそうにはにかむだけ。
「い、行きましょうか!」
「クス・・・ ええ、参りましょう」
彼女の手を取って歩き出す。
ただひたすら恥ずかしくて振り向けなかったが、後ろにいる彼女は何となく笑っているように思えた。
色彩豊かな時間が過ぎ去って、俺と紫さんは土手に座っていた。
「楽しかったわね♪」
「そ、それは良かったです」
人間としての“お祭りの楽しみ方”を伝えられたのなら幸いだ。
しかし様々なハプニングがあったので俺は激しく疲労している。
男としては嬉しいハプニングもあった様な気がするが、何があったかはご想像にお任せして省略する事にしよう。
「さてと・・・ そろそろ始まるかな?」
夜空を見上げて呟く。
「ああ、そう言えばそろそろ刻限じゃないかしら」
紫さんも分かっているから同じ様に空を見上げる。
ちなみに今ここにいるのは俺たちだけではない。
他の村人たちなども大勢この土手に腰掛けている。
何故ならば、
ヒューン ドン
「始まりましたね」
ヒューン ドン ヒューン ドン ドドン
夏祭りの恒例、花火大会があるからだ。
「綺麗ね」
さしもの紫さんでもこれには感嘆を禁じえないようだ。
花火、それは東洋が生んだ芸術。
中空に描かれる鮮やかな炎の軌跡は、ある時は小さな輝きとなり散り、またある時は炸裂した後にさらに小さな閃光を放って消える。
それはまさしく“一瞬の芸術”
万物には必ず崩壊の瞬間がある。
その逃れられない運命の中で精一杯輝くことの美しさを、この芸術は雄弁に語っていると思う。
「やっぱり花火は夏の風物詩ですね」
「そうね」
お互いに空を見上げたまま話し合う。
ヒューン ドン ドドン ヒューン ドン
花火の音があるのと、互いにその美しさに目を奪われている為に必然的に会話が少なくなる。
ふいに、自分の肩に重みが掛かった。
「・・・・・・!」
何事かと思って首を回すと、そこあったのは紫さんの顔。
反射的に声を上げそうになったが、周囲に人が大勢いる事を思い出して何とか踏み止まった。
艶やかな髪の毛からは、ほのかに甘い香りが漂ってくる。
「ねぇ・・・」
言葉と共に、彼女の手が俺の手に絡められた。
「な、何ですか?」
チキンな俺の声は情けなく上擦った。
しかし気にする事無く彼女は続ける。
「花火は美しいわよね」
「ええ・・・」
「それはなぜかしら?」
「一瞬で消え去ってしまうから・・・?」
先程自分が感じていた事をありのままに話す。
「そう、花火は一瞬で消え去ってしまう・・・ だからこそ人はそこに美しさを見出す」
空を見上げたまま、どこか遠くを見るような目で彼女は言った。
「そしてその美学はこの世の殆どの物に当てはまるわ」
「そうでしょうね・・・」
生命も物質も、時間も空間も、森羅万象はいずれ全て虚無へと回帰する時が来る。
“始まり”があれば“終わり”もまたあるのだから。
「それは・・・ とても残酷な事だと思わない?」
間近で見る彼女の瞳の中に、果てしない寂寥の念が見えたような気がした。
彼女は妖怪。
それもおよそ神霊の域に及ぶほどの大妖怪だ。
永い時間を過ごす彼女にとって、この世の全てはある意味一瞬の事なのかもしれない。
おそらく彼女が抱いた如何なる感情もまた同様に。
「・・・そうですね」
確かに、変わり行く事は悲しいかもしれない。
「如何に深い想いも所詮は不確かでしかなく、光年の永さから考えれば全ては泡沫なのかもしれません」
しかし・・・
「それでも良いのでは無いでしょうか」
「・・・なぜかしら?」
「もしも総てが輪廻の輪の中で廻っているのであれば、今俺がこうして紫さんと話しているという事もまた“必然”たるを得るからですよ」
これから先の未来がどうであれ、現在と同じ状況がやがて来るのであれば現在感じている感情もまた同じようにして抱くのではないだろうか。
「簡単に言うと、今の状況は来世でもあるかもしれないって事です」
久しぶりに自分の狂人ぶりを発揮してしまった。
微妙に後悔の念に苛まれる。
「クス・・・ 貴方はつくづく面白い事を言うわね」
しかし紫さんは俺の言わんとする事を理解してくれたのか小さく笑っていた。
「貴方みたいな人を見るのは本当に久しぶりだわ」
「はは、自称・変人ですからね」
かつて友人にこの持論を話したら「意味が分からん」と言われたものだ。
「でも意外ね。 貴方運命論者だったの?」
「いえ、こういう事考えるのが好きなだけですよ」
俺は思想家ではない。
第一、自分の考えに同調する事を無理強いする様な真似は嫌いだ。
「あれ、花火終わったかな?」
ふと、花火が炸裂する音が聴こえなくなったので周囲を見渡すと、先程まで大勢いた観客達はいつの間にかいなくなっていた。
「そうみたいね」
どうやら知らない内にかなり時間が経過していたらしい。
気が付けば、土手には俺たちしか残っていなかった。
「・・・二人っきりね」
「・・・そうですね」
異性と二人っきりという状況にも関わらず、不思議と心は平静を保っていた。
「もう少しだけ・・・ こうしていても良いかしら?」
彼女の問いに笑顔で答えて空を見上げる。
見上げた星空はどこまでも儚く、そして眩しく煌めいていた。
肩に感じる重みに微かな幸せを感じながら、流れ行く時に身を任せる。
虫たちの夜想曲が二人を優しく包んでいた。
そんな或る夏の夜の出来事。
うpろだ293
───────────────────────────────────────────────────────────
「・・・またか」
手に取った新聞紙の一面にはこんな事が書かれていた。
『またもや神隠し!』
ここ最近まるで疫病の流行の様にして始まった、この一連の『神隠し』事件。
『神隠し』と銘打つ位であるから、この連続的な事件の首謀者、目的、消えた者の行方は一向に分かっていない。
「ったく、誰がこんな事をやってるんだか・・・」
朝食のトーストをかじりながら、ぼんやりと呟く。
人を攫うと言うのは某国のお得意技とも言えるものだが、何せ今回は全く首謀者が見えていないのだ。
普通の誘拐事件ならばほんの数名でも目撃者はいるものだが、今回の事件では目撃者は一切見つかっていない。
要は『迷宮入り』なのだ。
「警察も早く犯人の尻尾でも掴めりゃ良いのにな・・・」
民衆を守る為に存在する組織は今回の事件においては何の功績も作れていない。
いよいよ、警察に対する国民の不信感も募ってきている。
ただ・・・
「相手が本当に“化け物”ってんなら話は別か」
最も、そんな事は有り得るはずはない。
何せその“化け物”の大半は人間の空想が生んだ産物なのだから。
生憎俺はその手のオカルトはあまり信じてはいない。
「さて、そろそろ行こうかね・・・」
朝食を腹に収め、学校に向かう支度をする。
天気は快晴。
世間を震撼させる事件が続いているとは思えない様な天候だった。
色んな意味で憂鬱な一日を終えた俺は、帰宅早々パソコンのディスプレイの前に腰を降ろした。
電源を入れてお気に入りのサイトへ直行する。
「そう言えば最近の事件って、コイツなら出来るんじゃないか?」
ディスプレイに写る女性、その名は八雲紫。
ヤリコミ度が高い事で有名な某シューティングゲームのキャラクターの一人だ。
“境界を操る程度の能力”を持つ彼女は、ゲーム中でも屈指の強さを誇る存在。
同時に“仮に”存在するのなら今回の事件の首謀者とも考えられる人物とも言える。
「いや、でもまさかな・・・」
相手は架空の存在だ。
幾らなんでもそれはないだろう。
「もしそうだとしても、今は冬じゃないし」
彼女は“人喰い”であると(設定上)言われている妖怪だ。
しかしそれは冬眠の前が主だとされている。
今、季節は夏。
ならば彼女がこんな連続事件になるほど“人を摂取”する事もないだろう。
そもそも相当頭が良いらしいので、事件として残すとは思えない。
「八雲紫・・・ま、空想の存在でしかないよな」
「あら、お呼びになったかしら?」
瞬間、全身の体毛と言う体毛が逆立ったのを知覚した。
同時に背後に現れた人の、いや“人以外のモノ”の気配。
「う、う・・・そ、だ・・・・・・ろ?」
首を向けた先にいたのは、PC画面に写っている八雲紫その人。
声帯が引き攣って、自分でも情けない程に上擦った声が出た。
「あら、酷い男性(ヒト)。 貴方がいないと仰ったから、私は自身の存在を証明しようと思って此処に来ましたのよ?」
手に持った扇子を口に当てて、目を細める。
ディスプレイと言うフィルターを通して見るのならその笑顔はさぞ美しく見えただろう。
しかし今目の前にある笑顔に対して感じるのは、ただの“恐怖”だけだった。
「あんたが八雲紫・・・なのか?」
何とか口に出してみるが、明らかに声は上擦ったままだ。
「ええ、私が八雲紫ですわ」
どこか嘲るような彼女の声色は、絶対的な勝者のそれに似ている様な気がした。
「お、俺を喰う気なのか?」
身体がガタガタと震え、同時に声も揺れてくる。
頭の片隅にいる冷静な自分が「まるで天敵に狙われた小動物だな」と笑っていた。
「まだおやつの時間には早いんですの」
ふぅ、と軽く息を吐いて彼女は言った。
どうやらいきなり喰われる事は無いようだ。
「なら何故こんな所に?」
「そうね・・・」
あまり問いばかり繰り返すと相手の機嫌を損ねかねない事は承知だが、これはある意味では俺の生死が係っているので訊いてみる。
「特に理由などは無いわね。 ただの気紛れ、と言った所かしら」
「気紛れで死ぬのか、俺は」などと心の中で呟いて心底俺は絶望した。
力のある者の前では何も出来ない。
これは弱者の真理だろう。
「何も無いなら帰ってくれません・・・か?」
微妙に狐狗狸さんにでも頼むように言ってみたが、
「少し話し相手になってくれません事?」
どうやら俺の退路は無くなってしまったようだった。
そんなこんなで話し始めて一時間程経過した。
彼女は相変わらず胡散臭い笑みを浮かべたままこちらを見ている。
一方の俺は緊張と恐怖で胃に穴が開きそうな気分だ。
一応二人分のコーヒーを淹れてみたが、その減り具合が明らかに違う。
「あら、コーヒーが冷めてしまいますわよ?」
「あ、ええ、まぁ猫舌なものですから・・・」
猫舌なのは嘘ではないのだけれど、本当はここまで冷ます必要は無い。
本当は単純に手を出すのも怖いからこうなっているだけだ。
「随分と怖がられたものね」
俺の心を悟ったのか、少し落胆したような様子で彼女は言った。
「それは・・・貴女は人を食べるらしいですから」
ライオンに懐く野ウサギがいないのと同じ事。
「食べないわよ」
「く、口では何とでも言えますよ・・・」
心外だと言わんばかりの様子で弁明してくるが、正直その笑顔で言われても説得力は皆無に等しいと思う。
すると彼女は、
「どうしたら信じてくれるかしら?」
と、のたまった。
「いや、そう言われても・・・」
“喰われない確証”など、どうすれば証明できると言うだろうか。
「貴方の考え方って結構独特だから面白いのよ」
「はぁ」
「でも貴方が私との会話を楽しんでいないって言うのは不平等でしょ?」
「そうですか?」
意外な事に、彼女は人間の事をそこまで見下げてはいないらしい。
「そう。 だからね、出来たらもう少し信用して貰いたいなと思うのよ」
「・・・・・・分かりました、善処してみます」
いきなりは難しいが、相手がそう願うのなら従ったほうが得だろう。
俺の命は所詮、彼女の掌の中にあるのだから。
「ありがとう」
一瞬だけ、彼女の笑みから胡散臭さが消えた。
その一瞬だけの本当の微笑みは、溜息が出るほどに魅力的だった。
(綺麗だな・・・)
元々、その姿は何も言わなければそこらのモデルなどよりよっぽどハイレベルなのだ。
自然な笑顔が似合わないはずが無い。
そしてその自然な笑顔に惹きつけられない男もそうはいないだろう。
「どうしたのかしら?」
ご多聞に漏れず俺も見惚れていたらしく、彼女の声で我に帰ることになった。
「い、いや、綺麗だなって・・・」
「え?」
まだぼんやりとしていたのか、ついつい本音が飛び出してしまった。
「あ! いや、あの、その・・・」
誤魔化そうと躍起になるが、言葉が見つからずただ慌てふためくだけになってしまった。
「そう・・・ありがとう」
何故だか彼女の方も少し頬を染めて答えてくる。
むしろ軽く流してくれれば良かったのだが、そんな反応をされるとかえって恥ずかしさが込み上げてきてしょうがない。
「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」
時計の針の音がやけに大きく聞こえてくる。
何となく気まずくなった俺は話題を振ることにした。
「あ、あの質問があるんですけど良いですか?」
「何かしら?」
彼女もこっちに合わせてくれたのか、素直に応じてくれる。
「最近の神隠しって、もしかして貴女が?」
「いえ、私じゃないわよ?」
「え?」
じゃあ、一体誰が“あの事件”を起こしたのだろうか。
彼女ぐらいしか、あちら側の世界で神隠しなど行う人物はいないはずなのに。
「最近どうも大結界の調子がおかしいみたいなのよ。 多分その影響でしょうね」
「大結界の調子がおかしい?」
「何でなのかはよく分からないけどね」
博霊結界と言えば、(設定では)こちら側の世界とあちら側の世界とを隔てる結界の事だ。
それが不安定になっているとなれば、あちら側に迷い込む人間が出てきてもがおかしくは無い。
「もっとも直に博霊の巫女が何とかするでしょうね。 それが彼女の役割なのだし」
「なら安心ですね」
それならば近い内に謎の『神隠し』事件には終止符が打たれる事になるのだろう。
無論、こちら側には何も分からないまま。
「信用してくれるかしら?」
「一応」
事件との関連性が無い以上、今の彼女が食物を求めてこちら側に来た可能性はある程度否定できる。
「そう、良かった。 ならば私も訊きたい事があるのだけど・・・」
「どうぞ。 俺が答えられることなら答えますよ」
「まず、この世界の・・・・・・・・・」
それからの会話は不思議なくらいにスムーズに進んでいった。
多分、彼女がむやみやたらに自分の同族を殺している訳ではないと分かったからだろう。
問答の中で彼女が時折見せる自然な笑顔は、やはりどうしようもないくらいに美しいものだなとか思ったりしながら時間は過ぎていった。
光陰矢の如し。
楽しい時間ほどその経過は早く感じるものだ。
結局ガチガチだった最初の一時間とは比べ物にならないほど俺は彼女との会話にのめり込んでいて、気が付けば時計の針は9時を指していた。
「あ、もう9時か」
「あら、もうそんな時間?」
彼女も時が経つのを忘れていたのか、俺の言葉を聞いて初めてその事に気が付いたようだった。
「あの・・・平気なんですか?」
「何がかしら?」
「あまり此処にいると、貴女の式達が心配するでしょうし・・・」
「そうねぇ」
本来なら彼女がこちら側に長居する事などあまりないはずだ。
目の前の女性が架空の存在でないのなら、その配下である二人の少女も実存するだろう。
「そろそろ戻った方が良いのでは?」
「ええ」
しかし彼女は一向に動こうとしなかった。
不思議に思って声を掛けてみる。
「あの?」
僅かな沈黙があって、彼女は口を開いた。
「・・・・・・ねぇ」
「はい、何でしょう?」
「・・・・・・・・・・・・」
「?」
「・・・・・・貴方、幻想郷に興味はあるかしら?」
「ええ、割とありますけど」
「なら来ない?」
「・・・・・・・・・え?」
いきなりのお誘いに思考回路がフリーズした。
そもそも俺みたいな一般人を幻想郷に連れて行ってどうするのか。
やっぱり喰うのだろうか。
いや、それはない事を祈りたい。
「・・・・・・嫌ならいいのだけど」
寂しそうな表情でそんな事を言う。
「嫌じゃないですけど、いきなりだったから・・・」
内心「行きたい」と言う想いはあるのだが、やはり行くのにはそれなりの準備が必要だろう。
黙って消えたら、俺も『神隠し』事件の被害者に加わる事になる。
でも彼女の誘いが魅力的なのも確かだ。
ならば・・・
「・・・少し待ってて下さい。 用意しますから」
「え?」
一度しか買えない『運命の切符』を逃すなんて出来ない。
「ちょっと、貴方本気なの?」
「ええ、本気です」
大き目のスポーツバックを取り出してきて、その中に衣服やら必需品やらをドカドカと詰め込む。
数分後にはスポーツバックは限界まで膨張していた。
「・・・・・・・・・」
はち切れんばかりのバックを、彼女は目を丸くして見ている。
そんな彼女に俺は言った。
「さ、支度が出来ましたよ」
必要なものは全てバックの中にある。
これで外出の準備は万端だ。
「どこへでも連れ去って下さい、八雲紫様」
少しだけ、おどけたように言ってみる。
「・・・・・・・・・」
彼女は一瞬ポカンとした表情をしてから、
「そうね、ならば“神隠し”と言うものを見せてあげるわ」
妖しげな微笑を浮かべ、そう言ったのだった。
斯くして、少年は幻想郷へ旅立った。
うpろだ359
───────────────────────────────────────────────────────────
「ん・・・」
光が差し込んで、沈んでいた意識が浮上する。
瞼を開ければそこには見慣れた天井。
横を見やれば赤く輝く夕日。
「・・・ん~」
布団の上で伸びをして、同時に深呼吸をする。
寝ぼけた脳に酸素が行渡って、ゆっくりと思考が鮮明になっていく。
それから服を着替える。
何となく自分が着ていた寝巻きを見やる。
「明らかに趣味が変わったわね」
ピンク色のランジェリーは夕日を浴びて少し透けていた。
そう言えば、少し前まではこんなに華やかなインナーは着けていなかったはずだ。
「やっぱり彼の影響かしらね」
小さく呟いて、頭の中に彼を思い描く。
網膜の向こうに映った彼は少し恥ずかしそうに私に微笑みかけていた。
それだけの事。
そんな些細な事で私は胸の奥が甘く、切なく疼く様な気がした。
「っと・・・ 何を考えているのかしら、私」
頭を振って、気を静める。
軽く息を吐いてから、襖を開けて縁側へ出て居間へと向かう。
少しすると、居間が見えてきた。
「あ、紫様起きられたのですか。 今食事をお持ちしますので、少々お待ち下さい」
「紫様、おはようございます!!」
居間へと足を踏み入れた私に、橙と藍が交互に声を掛けてくれる。
そして、
「おはよう、紫さん」
今一番気になっている彼が声を掛けてくれる。
その微笑みに自然と私の頬が緩むのが分かった。
「おはよう」
だから私も自分なりの最高の笑顔で彼等に答える。
ああ、そう言えばここ最近上辺だけの笑顔よりも心から笑顔を浮かべている回数が増えてきている様な気がする。
腰を降ろして、藍の作る朝食(正確には夕食)を待つ。
と言ってもすぐに食事が運ばれてくる訳ではないので必然的に時間が空く。
だからその暇な時間は彼等と会話で消費する。
「あら、今日も派手にやったみたいね」
彼の頬に掠り傷があるのを見つけたので言ってみる。
「ははは、やっぱり分かりますか」
苦笑しながら彼が答えた。
「○○ってば、全然回避出来てないんだもん。 あたしも一応手加減してるんだよ?」
「そんな事言っても俺は所詮人間だからな」
よく二人は弾幕ごっこ(と言っても橙が一方的に攻めるだけ)をしている。
彼はあんまり乗り気ではないようだが、無邪気な橙を無碍に出来ないのか結局今の様に毎日ボロボロになっている。
「えー、もっと頑張ってよ~ そうじゃないと面白くないよ」
「無理言わないでくれよ・・・」
そんな二人の様子が何となくおかしくて笑ってしまう。
「ゆ、紫さんも笑ってないで何とか言って下さいよ」
顔を引き攣らせながら、彼がそんな事を言ってきた。
「そうねぇ・・・」
少し意地悪してみようかしら。
「○○も殿方ならば、女性の要望に応えてあげるべきではなくて?」
いつもの様に口元へ扇子を当てて笑ってみる。
「ほ~ら、紫様もそうだって言ってるよ?」
「ご、ご無体な・・・」
私の言葉に勢いを得た橙が喜色満面で○○に笑いかける。
対して彼はいよいよ顔色が悪くなってきた。
これは少し厳しかったかもしれない。
このままでは少々彼が可愛そうなので救い舟を出して上げる事にする。
「でも、そうねぇ・・・ 橙としてはやっぱり歯応えがあった方が良いわよね?」
「うんっ!」
「ならば、私が少し彼の事を鍛えてあげるわ。 そうしたら今度弾幕ごっこをする時はもっと楽しくなるかもよ?」
「・・・・・・そうだね! その方が面白くなりそう!!」
「ふふ、もしかしたら○○が橙の事を追い抜いてしまうかもよ?」
「わわわ・・・それは大変だ! よ~し、あたしも少し外で鍛えてきますね!!」
言い残して橙はまるで風の様に外へと飛び出していった。
後にはホッと溜息をつく彼と私が残される。
「助かりました・・・」
「ありがとう」と深々と頭を下げてくる。
そんな彼の様子は満更でもない。
「あら、果たして助かったのかしら?」
「え・・・」
私の言葉に再び彼が凍りつく。
「今のは一時しのぎにしかなっていないのよ?」
「・・・やっぱりそうですよね」
内心分かっていたのだろう、彼は苦笑した。
「安心なさい、私が手取り足取り教えてあげるから」
「本気ですか?」
「ええ、本気よ」
実際彼にはもう少し、せめて人間としては強くなってもらいたい。
「・・・・・・・・・」
彼は暫く考えるような素振りを見せた後、
「じゃあ、その・・・ よろしくお願いします」
真剣な表情でそう言い切った。
その澄んだ表情に一瞬だけドキッとする。
だけどその本心を悟られるのは何だが躊躇われて、
「・・・その願い確かに聞き入れましたわ」
なんておどけた様な言葉を返してしまった。
でも、内心彼に期待していると言うのは本当の事。
強くなって欲しいのは、彼に守ってもらいたいから。
それはきっと如何なる女性の心の内にある一種の夢。
私、八雲紫は今、確かに彼に恋している。
さて、そもそも彼。
○○とはどういった人物なのか。
端的に言ってしまえば、彼は外の世界の住人であって同時に無力な一般人だ。
別に何か特殊な力を持っている訳でも、秀でた才がある訳でもない。
しかし彼は他の人間と明らかに異なっている点があった。
彼は人の身でありながら、時折何かを悟った様な表情を見せる事があるのだ。
“心の境界”を弄れば彼が何を考えているのかは分かるが、それはとても失礼な気がするので出来ない。
何よりも、私はそんな手段で彼の心を知りたくない。
「ふぅ・・・」
食事を終え、縁側で小さく溜息をつく。
ここ最近本心からの笑顔が増えた反面、溜息を吐く回数も増えた。
思えば何とも典型的な“恋煩い”の症状ではないか。
“恋”と言うものは知識としては知っているが、実際に本気で経験した事なんて無い。
律しようとすればする程、想いは加速して処理が追いつかなくなってしまいそうになる。
「はぁ・・・」
幾度目かの溜息。
もう数える事も意味が無いように感じる。
「どうしたんですか?」
ふいに横から彼の声が聞こえた。
振り返れば、珍しいものを見たような彼の顔。
「いえ、何でも無いわ」
平静を装ってみるが、どこまで演技できている事か。
「隣、良いですか?」
「どうぞ」
律儀に一声掛けてから彼は縁側に腰掛けた。
そうして私と同じ様に外へ視線を向ける。
「此処での暮らしはどうかしら?」
何気なしに訊いてみる。
彼は少し眉を寄せてから、
「なかなか気に入ってますよ」
と嘘偽りの無い笑顔を浮かべた。
その笑顔がまた眩しくて、心臓が跳ねる。
「・・・それは良かったわ」
今の笑顔は少々不自然になってしまったかもしれない。
「それから今更ですけど、本当にありがとうございます」
「え?」
突然の改まった礼に少し驚く。
「だって、俺ここに着てから何も出来ていませんから」
「何を言っているの、私は興味があったから貴方の事を連れて来たのよ? それに貴方は何もしていない訳ではないわ」
「そうでしょうか?」
不思議そうな顔でそんな言葉を返してくる。
全く暢気なものだ、と思う。
私を“こんな状態”にさせておいて・・・
「貴方がここに着てから藍や橙の様子が変わってきているのよ? 橙は遊び相手が出来て嬉しいと言っていたし、あの藍も良い話し相手が出来たって喜んでいたわ」
同じ女であるからよく分かる。
藍も橙も、おそらくは彼に対して好意を抱いている。
多分このまま順当に行けば、その感情が別の感情に推移するのも時間の問題だろう。
正直私は気が気でない。
それなのに彼は、
「そうなんですか? 橙の事については分かりますけど、藍さんがそう思っていたなんて知らなかったな」
心底驚いた様な表情でそんな事を言う。
幾らなんでも鈍すぎはしないだろうか。
一度、乙女心と言うものについてみっちりと教え込んだ方が良いかもしれない。
「・・・・・・・・・全く、困った男性(ヒト)ね」
「?」
幸い、呟きは聞こえなかったらしく彼は首を傾げているだけだった。
「兎に角、貴方が着てからマヨヒガの空気が変わったのよ。 貴方は何もしていない訳ではないわ」
「そんなに大層な事をした気は無いんですけどね・・・」
苦笑しながら彼が答える。
「むしろ俺は戯言ばっかり言っている気がしますよ」
「そうかしら、私は面白いと思うけど?」
これは私ばかりではない。
橙はどうだか分からないが、少なくとも藍は私と同意見のようだった。
「そう言ってくれるのは貴女だけですよ」
そんな事を言って、少しだけ寂しげな笑みを浮かべる。
「現実世界って結構シビアなんですよ。 ただ単純に自分の感性を形にしてみても、大衆がそれを受け付けられなければ批判されるんです」
そう語る彼の表情は真剣そのものだ。
「でも万人に通じるものなんて無いと思うんです。 ですから本当の意味では人は他人の価値を否定する事は出来ないと思うんです」
「人は人を否定出来ない、と言う事かしら?」
「ええ、もっともどこまで正しいかは分かりませんよ。 何せ俺も人間ですからね」
肩を竦めてみせる。
「でも貴女を始めとして、幻想郷の住人は純粋に評価対象の良し悪しを見てくれる。 その辺りは本当に好ましいですよ」
「もっとも理屈で動く人はどうだか分かりませんが」と、彼は笑った。
「・・・・・・だから、感謝しているんですよ?」
ふいに彼が立ち上がった。
直後に感じる人の温もり。
「特に貴女には・・・ね」
耳元で彼が囁いた。
「な・・・・・・」
状況を理解した途端、抑えていたはずの“感情”が暴れ始める。
身体が経験した事が無いほどに熱くなって、狂ったかのように心臓が踊り始める。
同時に甘い疼きが脳髄を侵して蕩かしていく。
“もっと近くに感じたい”
その想いが理性の壁を越えようとする瞬間、それを見計らったかのように彼は身を引いた。
「はは・・・ 少し悪戯が過ぎますね」
酷い。
これでは生殺しではないか。
「そ、そんなに怒らないで下さいよ」
どうやら本心が表情に出ていたらしい。
さっきまで悪戯っぽい笑みを浮かべていた彼は、急に怯えたような目で私の事を見ていた。
「怒ってなどいないわよ」
内心少し不満な訳だが、別段怒っている訳ではない。
「そ、そうですか? 良かった」
私の言葉に彼はホッと息を吐いた。
「ん、そろそろ時間かな・・・ それじゃお使いに行ってきますね、紫さん」
おそらく藍が頼んだであろう。
彼は一礼すると、少しだけ小走りで縁側を歩んでいった。
その姿をぼんやりと見送ってから、私はまた溜息を吐く。
「・・・本当に、どうしてしまったのかしらね」
耳元をそっと撫でる。
まだ、彼の囁きが残っているような感じがした。
もう駄目だ、これ以上は・・・
「・・・もう、我慢出来ない」
想いとは不安定なもの。
確実なものが無ければ忽ち風化して壊れてしまう。
だから私はもう待つ事を止めることにした。
「覚悟なさい○○」
今はいない彼に向けて宣戦布告をする。
さあ、これからが正念場だ。
やるからには全力で当らなければ。
せめて悔いが残らないように。
「あー・・・」
唸りながら寝返りを打つ。
寝入ってからおよそ一時間、急激に意識が覚醒してしまった。
さっきから何度も寝返りを打っているが、眠気に見放されたのかまるで眠れそうに無い。
「仕方ないな」
寝られない時は何をやっても眠れないものだ。
自分を納得させて俺は床から起き上がり、縁側へと向かう事にした。
幸い夜ともなると、日中に比べて気温が下がるので幾らから過ごしやすくなる。
俺は適当な場所に腰掛けて少し思考を巡らせる事にした。
「・・・・・・やっぱり夕方のアレはやり過ぎたかな」
アレ、とは紫さんの耳元で囁いた事だ。
普段彼女はよく俺をからかう事があるので、今回は逆に彼女の事をからかって見ようと思ってやったのだ。
「つか、明らかに怒ってたよな・・・」
多分あれがジト目と言うものなのだろう。
しかも微妙に不機嫌オーラが漂っていた。
でも心なし瞳が潤んでいたような・・・
「・・・ないな」
きっとそれは茹だった俺の脳が見せた幻想に違いない。
何せ相手は数え切れない程の歳月を生きた大妖怪。
俺如き青二才相手にそんな感情を抱くなんて考えられない。
「むしろ逆鱗に触れたんじゃ・・・」
だとしたら拙い。
相手は妖怪、自分は人間。
二つの種族の間にある差はどうあっても埋められるものではない。
逆鱗に触れたのならば、制裁は覚悟するべきだろう。
最悪、殺されるかもしれない。
「・・・・・・・・・」
ああ、何を今更怯えているのだろう。
そもそも此処に来た時点で覚悟はしていたはずじゃないか。
「八雲紫は冬には冬眠する。 その際には人間を蓄える・・・」
蓄える、つまりは“喰う”のだ。
元より妖怪は人間を食べるものであるから、その行為自体は自然な事だろう。
しかし被捕食者としてはそれを“自然な事”で済ます事は出来ない。
「・・・まぁ、元より冬までの命だとは思っていたけど」
言っていて薄ら寒くなる。
だが、どんなに逃げようとも逃げられるわけも無い。
何せ相手があまりにも悪すぎるのだ。
「ふぅ・・・」
もっともただで死ぬ気は無い。
せめて死ぬのであれば最期に盛大に何かをやって見せよう。
「そう」
何せ俺は・・・
「俺は彼女を愛しているんだからな」
そう、あろう事か俺は彼女に対して“愛情”を感じているのだから。
もっともその想いが成就する事など考えていない。
意味が無いからだ。
「愛も憎しみも、生きていて初めて告げられる」
死に逝く未来ならば、想いを告げても意味は無い。
告げられた相手はただ辛く感じるだけだ。
「生きられぬのなら証を刻めばいい」
それは言葉か、それは歴史か、それは・・・傷痕か。
「俺は彼女の心に残れればそれで良いんだから・・・」
ああ、何て酷い考えだ。
どうしようもない。
でもどうしようもなくしてしまったのは彼女だ。
彼女が俺の戯言を「面白い」と言ってしまったから。
俺を肯定してしまったから。
「歪んでるな、俺・・・・・・」
何故だろう、それが自分の心情のはずなのに目頭が熱くなってくる。
「死にたくないな・・・ 死んだら俺は彼女の傍にはいられない」
霊になる、と言う手だってある。
でも俺にはきっと其処に至るまでの精神力は無い。
だから死んだらそれで終わり。
「・・・俺には八雲紫(かのじょ)に愛される未来なんて無いのか」
そもそも相手はこっちをただの肉としてしか見ていないかもしれない。
久しく、俺は頬を熱いものが伝っていく感覚を味わった。
「・・・・・・未来はまだ決まってはいないわ」
声の方を見やると、そこには紫さんが立っていた。
彼女は本来夜に起きている事の方が多かった事をすっかり失念していた。
「運命論者ではない、貴方はそう言ったでしょう?」
それはかつて俺の言った事の確認。
「・・・いつから其処に?」
「さあ? いつからでしょう?」
問いに対して、彼女は見慣れた胡散臭い微笑みで答えた。
身体中の筋肉と言う筋肉が引き攣り、目の前が白くなっていく気がする。
「・・・答えが知りたいかしら?」
何に対しての答えなのだろうか。
俺にはそれを知る術は無い。
「答えが欲しいのなら来なさい」
彼女はそう言って縁側を歩いていく。
俺は何も言わずにそれに従った。
如何なる答えであろうと、ただ受け入れようと心に誓って。
彼女の部屋に入った事は何度かある。
しかし夜ともなると同じ部屋でもどこか違って見えてくる。
特に今の場合は状況が状況だけに。
「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」
重苦しい沈黙が続いている。
まるで空気が鉛にでもなってしまったかのように、呼吸をするのも苦しく感じる。
俺と彼女は部屋に入ってから互いに立ったままだ。
彼女はなぜか座る気配を見せないので、俺もそれに倣っているのだ。
「ねぇ・・・」
「はい」
彼女はこちらに背を向けたまま小さく言った。
「貴方、自分は私に愛されないと言ったわね」
「ええ」
「なぜかしら?」
やはり彼女は振り向かないままで問う。
「・・・・・・言うまでも無いのでは?」
不思議と冷静だった。
一種の極限状態であるにも関わらず、なぜか俺は自分でも驚くほどに冷静だった。
「私は貴方の口から聞きたいの」
一瞬だけ、彼女がこちらを見た。
黄金色に輝くその瞳が射抜くように俺を捉えていた。
「人間と妖怪は相容れないからです」
その視線を威嚇ととって、俺は総てをその一言に込めた。
どんな理由も、最終的にはこの一言に集約出来ると思ったから。
でも果たしてそれは俺の本心なのだろうか?
「だから私に愛されないと言うの?」
小さく頷いて、肯定する。
すると彼女は振り返って言った。
「・・・ならば逆に問うわ。 貴方は私を愛してくれないの?」
「それは・・・」
酷な質問だ。
本音で言えば俺は彼女を愛している。
しかしそれを告げた所で何になると言うのか。
「私は貴方を愛しているのよ?」
「それは食料としてでしょう?」
いつものジョーク。
でも今この言葉には冗談を込めたつもりはない。
それが真理であると疑わなかったからだ。
「いいえ」
けれど彼女はゆっくりと首を横に振った。
「私は貴方を愛しているわ」
そして微笑んだ。
その黄金色の双眸から、透明な涙を零しながら。
「好きで好きでしょうがないのよ? もうそれこそ狂ってしまいそうな位に」
「っ・・・」
「貴方を想うだけで、こうして涙が溢れてくるのよ?」
なぜそんな綺麗な笑顔を浮かべられるのだろう。
俺は何も答えられずに顔を俯かせた。
と、ふいに感じた事のある甘い香りが鼻腔をくすぐった。
「なっ!」
気が付けば、俺は彼女に抱きつかれていた。
同時に片手に感じる質感。
「そのナイフは妖怪を殺す事が出来る概念付加を受けたもの。 無論、私でも殺せるわ」
利き手に収まった小さなナイフ。
目の前には彼女。
「もしも貴方にとって私が恐怖の対象でしかないのならそれで私を刺せば良いわ。 だから・・・」
「・・・・・・・・・」
「ねぇ、教えて頂戴。 貴方は私をどう想っているの?」
耳元で彼女が囁く。
俺は・・・
「卑怯ですよ・・・・・・」
軽い音がして、ナイフが床に落ちた。
「そんな事、出来る訳ないじゃないですか・・・」
そうして俺はそっと紫さんの事を抱きしめた。
「俺だって狂う位貴女の事を愛しているんですよ?」
涙で視界が滲む。
頭では分かっていても、心では割り切れない。
それが感情と言うものだから。
「たとえ貴女にとっては食料でしかなくても、路傍の石と同じような存在であっても」
「・・・・・・」
「俺は貴女を愛している」
目を逸らさずに、彼女の瞳をしっかりと見つめて言い放った。
そして自分で言って初めて分かった。
これこそが自分の偽り無い本心なのだと。
数瞬の後、彼女はふわりと柔らかな笑みを浮かべた。
「・・・その言葉を、私がどれほど待っていたと思う?」
聖母のように、全てを包み込むような眼差し。
「ちゃんと言えるじゃない」
熱く潤んだ瞳が揺れている。
ふいに、視界一杯に彼女の顔が広がって。
「愛しているわ、○○」
唇に柔らかな感触。
「――――――」
思考が明滅を繰り返す。
喜び、驚き、幸せが三原色のように混ざり合って多彩な感情を生む。
やがて感情はただ一つに収束して、俺はその想いを心の底から受け入れた。
収束した結果に生まれた感情の名は“愛”。
「・・・はぁ」
「・・・ふぅ」
永遠とも一瞬ともつかない時間の後に、重なった唇は離れた。
意図せずして熱っぽい吐息が零れた。
「もう離さないわよ」
頬を紅潮させながら、上目遣いに宣言してくる。
その姿に愛おしさが加速していく。
「望むところです」
こちらももう歯止めは効かない。
彼女に誘導されて、建前と本音の境界を踏み外してしまった以上後戻りなんて出来ない。
俺は再び彼女に口付けた。
彼女もまたそれに答えてくれる。
今度は互いの舌を絡ませて、より熱く深く繋がり合う。
水音が部屋に響き渡る頃には、どちらからとも無く床に転がっていた。
そして俺たちは―――――――――――
斯くして、二つの想いは繋がった。
うpろだ360
───────────────────────────────────────────────────────────
遠野物語をご存知だろうか。
遠野物語の奇談の中には「マヨヒガ」と言うものがある。
そこは基本的に無人で、多くの家畜がおり、座敷には豪華な食器があるだけの屋敷であると言われている。
登場人物は基本的にマヨヒガに辿り着いても、そのまま一休みしてから帰る事が多い。
だが幻想郷のマヨヒガは、辿り着いてしまえば二度と帰る事は叶わない。
それはその屋敷の主人の食料となってしまうからだ。
屋敷の主人は人ではなく遥かな昔より存在する大妖怪であり、冬になるとまるで熊か何かのように冬眠する習性がある。
だが長期間の休眠状態にはそれ相応のエネルギーが必要になる。
そこで、その妖怪は冬眠の前に人を喰らうのである。
ゆえに幻想郷のマヨヒガは、迷い込んだが最後二度と元の世界には帰れなくなるのだ。
「・・・・・・ここでの生活にも随分慣れたもんだ」
そう、俺もここに来てかなりの時間が経過している。
本当ならばいつ例の妖怪に喰われるか怯えていてもおかしくはないのだが、俺にはそのような恐怖心は全く無い。
なぜならば・・・
「・・・俺は“彼女”を愛しているからな」
あろう事か俺はその妖怪を心から愛しているからだ。
無論“彼女”の従者である子達をも含めて。
「あーあ、愛は人を狂わせるってのは本当だったんだな」
そう、俺もまた意味は違えども帰れなくなってしまったのだ。
それはただ“愛”ゆえに。
もっともその事が悲しいとは思わないし、「狂っている」と言われても構わない。
俺にとっては今あるこの日常が何よりも大事な事なのだから。
マヨヒガでの生活は現実世界にいた頃よりも案外楽だ。
俺はただの人間でしかないので人里へお使いに行ったり、屋敷の掃除や家事手伝いをするぐらいしか仕事が無い。
よって、よほどの事が無い限りは予定が空いている。
今日もやはり特にする事が無いので、縁側でお茶を飲みながらぼんやりとしていた。
「○○~!!」
けたたましい音を立てながら橙がやって来た。
「どうしたんだい、橙?」
手に持った湯飲みを脇によけて訊く。
「弾幕ごっこしよう!!」
「え゛・・・」
にこにこと太陽の様な笑顔を浮かべて橙が言ってくるが、逆に俺はその言葉に凍りついた。
「ねぇねぇ、やろうよ~~」
「い、いや、え~っと・・・・・・」
彼女はじゃれ合いのつもりで言っているのだろうが、人間である俺にとってはじゃれ合いのレベルでは済まない。
そもそも俺は空を飛ぶ事も弾幕を放つ事も出来ないのだから、はっきり言って一種のリンチである。
「ねぇ~、遊ぼうよ○○~~」
唐突に彼女は俺の膝の上でゴロゴロと転がり始めた。
元が化け猫であり、人化していても頭頂部に猫の耳があるのでこの仕草は非常にマッチしている。
「・・・・・・」
「うにゃ~~♪」
試しに頭を撫でてやると猫そのものの声で橙が鳴いた。
どうやら喜んでいるらしい。
「・・・・・・」
「うにゃ~ん♪」
「・・・・・・ふふ」
「うな~・・・ゴロゴロ」
猫にするよう撫でていると、それに応じて橙も反応する。
どうやらすでに弾幕ごっこの事についてはどうでもよくなったらしい。
「・・・可愛いなぁ、橙は」
無邪気にじゃれてくる彼女に、思わず俺はこぼしていた。
その言葉を聴いて橙は一瞬だけ驚いたような顔をしたが、すぐに再び膝の上で転がり始めた。
「それそれ」
「うにゃにゃ~ん♪」
心なしさっきよりも嬉しそうにじゃれてくる橙を微笑ましく思いながら、俺は昼ご飯まで彼女の事を撫でていた。
ちなみに、昼を知らせにきてくれた藍さんにブッ飛ばされたのはまた別のお話だ。
「それじゃ、今日もお願いします」
「ああ、それでは始めようか」
昼食(蕎麦だったのだが油揚げが無かった)を終えてから、藍さんと向かい合って座る。
卓袱台の上には様々なジャンルの本が並べられている。
「さて、今日はどうする?」
「そうですね・・・ 今日はこれなんてどうでしょうか?」
「ほう、なるほど。 最近めっきりやらなくなったからな丁度良い機会かも知れないな」
「藍さんこれ好きですよね」
「ああ、ここだけの話だが私は特にこれが好きでな。 内心、いつ来るか楽しみにしていたんだよ」
「そうですか、ならこれにしましょう」
ちなみに橙はいない。
彼女は今外に遊びに行っている。
仮にいたとしても、きっとこの手のものはまだ早いと思うから外へ行って貰うと思うが。
「しかしこの“シュレーディンガーの波動関数”はいつ見ても面白い」
・・・今もしかして卑猥な想像をした方いました?
だとしたら残念ながらそれは無いよ。
何せ卓袱台の上の本も、ただの参考書の山だから。
「俺には何が面白いのかさっぱり分かりませんよ」
彼女は数字、早い話が数学関係に強いので面白みを感じるのだろうが、俺はそっち方面の人間では無いので理解できない。
「ふふ、その面白さを教えてやる為に私がいるのだぞ?」
「そうでしたね」
ただ単純にマヨヒガでのんびりしていると、徐々に知識が無くなってしまうのではないかと思った俺は、危機感からこうして藍さんなどを頼りにして勉強を続けているのだ。
「さて、まずは粒子が時刻・・・」
「ふむ・・・・・・」
かくして二人だけの勉強会は始まった。
この勉強会は基本的に藍さんが教師役を勤め、俺が生徒役というスタンスになっている。
それから毎日やっている訳ではなく、藍さんが仕事を終えてしまっている時ぐらいしかやっていない。
無論、彼女は本来かなり多忙の身であるので正直気が引けてしまうので、それを言ったら、
「ははは、心配してくれるのか。 優しいな○○は。 だが安心しろ、私なら平気だ」
とか言って笑われた。
でも実際あんまり安心していない。
何せ以前彼女の部屋の前を通ったら、何かすすり泣く様な声が聴こえてきたのだから。
(・・・実に心配だ)
何か彼女その内鬱にでもなるんではないだろうか。
確か数日前にも“彼女”に無理難題を押し付けられていたし。
そう思うと、目の前で嬉々として数式の説明をしている女性の事を不安に思ってきてしまう。
「あの、藍さん」
「何だ、○○? 解らない所でもあったのか?」
「い、いやそうでは無いんですが」
言ってみたものの、何と言って切り出せば良いのか悩む。
「どうしたんだ?」
黙りこくった俺を訝しがる様に藍さんが問うてきた。
こうなれば言ってしまうしかない。
「あ、あのですね藍さん!」
「な、ななな何だ!?」
勢い余って乗り出してしまった。
流石に彼女もたじろいだらしく、心なし身体を後の方へと倒している。
「ど、どうしたんだ○○。 そんなに意気込んで・・・」
何故だか頬を染めて、俯き加減で藍さん。
いつものキリッとした様子が一転、年頃の娘のような様子に変わってしまう。
非常にぐっと来るものがあるが、そこは何とか抑えて俺は言葉を口にした。
「・・・藍さん、ストレス溜まっていませんか?」
俺の言葉を最後に、無音の空間が生まれる。
藍さんは俺の言葉を受けてポカンとした表情でこちらを見つめていた。
あれ、もしかして俺はおかしな事でも言ったのだろうか。
「・・・何だそんな事か。 全く驚かせてくれるな」
硬直が解けて、彼女は苦笑した。
「全く○○は心配性だな。 前にも言ったが私は大丈夫だよ」
「嘘ですね」
幾分声のトーンを落として言う。
そもそもストレス性の疾病と言うものは本人がストレスを溜め込む事で生じる事が多いのだ。
表面上繕ってはいるが、このままではいつか破綻してしまうのは目に見えている。
俺にとってそれが何よりの気掛かりだった。
「この前だって自分の部屋ですすり泣いていたでしょう」
「っ!?」
俺の言った事が核心に触れたのか、藍さんは目を剥いた。
「お、お前何故それを知っている!?」
「偶然ですよ。 夜、トイレに行った帰りにね」
「な、なななな・・・・・・!!!」
唐突に彼女の顔がボンッと音を立てそうな勢いで赤くなった。
「どうしたんですか、藍さん?」
“日頃のストレスで泣く”ってそんなに恥ずかしいだろうか。
それとも彼女にとって「泣いた」と言う事実が恥ずかしい事だったのだろうか。
「お、おおお・・・」
「お?」
壊れた機械のように繰り返す藍さんに、ついつい合わせてしまう。
が、ふいに彼女は顔を上げたかと思うと、
「お前と言う奴はぁーーーーーーーーーー!!!!!!!!!」
「え? う、うわあああぁぁぁぁぁあああーーーーーー!!!!??」
物凄い勢いで飛び掛ってきた。
(少女撲殺中…)
「すまないっ!!」
「いや、良いんですよ・・・」
10分後、ようやく開放された俺の顔はもはや原型を留めていなかった。
痣、切り傷、腫れ、その他様々。
幸い歯とかは無くなっていないのだが、それにしたってやはり痛いものは痛い。
「本当にすまない!! 私とした事がついつい我を見失ってしまった!」
「ははは、良いですよ。 誰にでもある事でしょう?」
「し、しかし!」
律儀に謝り続ける彼女に思わず苦笑してしまう。
「・・・顔を上げてくださいよ。 そもそもは俺が妙な事を言ったのが発端なんですから」
ちなみに「何故取り乱したんですか?」と問うても、彼女は真っ赤になるだけで答えくれなかった。
「だ、だが私はお前の好意を無碍にしてしまったんだ! 私は、私の事が許せない・・・」
それは自責の念。
やれやれ、真面目な上に心優しいとはなかなか彼女も損な気質だ。
だから俺は提案する。
「ならば、俺に何かやらせて下さい」
「は?」
「ですから、藍さんが喜ぶような事を俺にやらせて下さい」
藍さんは一瞬フリーズした後、意味を理解したのか、
「な、何を言っているんだお前は! 何でお前が私の為に何かをするんだ!! 私はお前を害してしまったんだぞ!?」
と怒鳴り声を上げた。
でもこちらも負けずと返す。
「そもそも俺は好意で日頃疲れている貴女の為に何かしてあげたいと思っていたんですよ。 ならばそれを大人しく受けてもらうのが一番良い罰になると思いますが?」
「う、むむむ・・・」
「ね?」
しばらく唸り声を上げていたがやがて彼女も納得したらしく、
「なら・・・ その、頼む」
少しだけ恥ずかしそうにそう言った。
夕飯を終えた後、俺は縁側に腰掛けて夜風に当っていた。
「やっぱり藍さんは相当疲れていたみたいだな」
結局彼女が俺に所望したのはマッサージだった。
日頃から肉体労働(精神労働も)の絶えない彼女の肩は、女性の物とは思えない程に凝っていた。
「まさか母に教え込まれたものが役立つ時が来るとは思わなかった」
俺は幼少期から親は何かとマッサージなどを教え込まれた。
いらない知識だと思っていたのだが、この様な形で実践する日が来るとは思わなかった。
内心、少し親に感謝している。
「少しは楽になったのなら良いけど・・・」
所詮は素人のマッサージだ。
専門家のそれに比べたら、どれほど効能があるか分からない。
それでも藍さんは始終心地良さそうにしていてくれた。
「・・・全く良く出来た人だ」
本当ならばそんなに心地良いものでも無かっただろうに。
仕舞いには「またやってくれるか?」なんて訊いてくる始末だ。
まるで立場が逆だな、とか思った。
まぁ、とりあえず「いつでもどうぞ」と答えておいたのだけど。
「やれやれ・・・ 俺って役立たずだな」
小さく溜息を吐く。
実際、人間である俺に出来る事は少ない。
“彼女”は「そんな事は無い」と言ってくれるが、そもそも俺がやっている(らしい)事は実感出来るものでは無い事が多い。
「認知出来ないものは存在しないに等しいからなぁ」
例えば身体的な変化(背が伸びる等)だって、他人に指摘されて初めて気が付くだろう。
要はそれと同じ事。
“役立っている”と言う実感がなければ、その人間は自分が何かの役に立っているとは思えないのだ。
「・・・頑張ろう」
仮にも俺は“彼女”に見初められた男だ。
いつまでも“頼りない人間”ではいられない。
夜空の星の下で、俺は小さく呟いた。
「何を頑張るのかしら?」
横からふいに人の気配が現れ、声がした。
「・・・色々ですね」
視線を向けずに言う。
軽い音がした後、気配の主は俺の隣に腰掛けた。
「もう、あんまり根を詰めちゃ駄目よ?」
俺の最愛の“彼女”、八雲 紫はそう言って微笑んだ。
「いえいえ、貴方の“恋人”である以上はもっと頼れる男にならないといけませんからね」
「あら、頼もしい」
むん、と大して無い力こぶを作って言うと、彼女はクスクスと可笑しそうに笑った。
「でも、私は今の貴方でも十分だと思うわよ?」
「そんな事は無いでしょう」
「そうかしら?」
ふいに彼女の笑顔の種類が変わった。
「貴方・・・ 今日も橙や藍と仲良くしていたわよね?」
よく見る胡散臭い笑顔だ。
しかし迫力がいつもより5割増しぐらいになっている気がする。
というか、何で昼間の事を知っているんだ?
「え、いや、それはですね・・・」
言い訳が全く思いつかない。
そもそも今更反論しても、むしろ「はい、そうです」と言っているのと同じだ。
「・・・・・・・・・・・・」
俺が反論しないのを見て、紫さんの笑顔が徐々に不機嫌そうな顔になっていく。
と、彼女は急に腕を伸ばし、
「い、いひゃいでふよ、ゆはひひゃん!!」
俺の頬をグイグイと引っ張り始めた。
当然俺は抗議の声を上げたが、彼女は許す訳もない。
「当然の罰ですわ」
とだけ言って、俺の頬を引っ張り続ける。
内心そのむくれた表情が可愛い、とか思っていたりするのだが、そんな事を言う余裕は俺には無い。
結局それから大体5分くらいの間、俺は彼女の好きなようにされてからようやく解放された。
「い、痛い・・・」
「当然よ、痛くしたんですもの」
ヒリヒリとした頬をさすりながら言うのへ、紫さんがピシャリと言う。
「うう・・・すいません」
言い訳なんて出来るはずもないので、俺は誠意を込めて謝罪する事にした。
「・・・・・・つーん」
ツイッと顔を背けられる。
これは、可愛らしいと思う反面非常にショッキングだ。
ちなみにこう言ったやり取りは、彼女の“恋人”となった日から結構な頻度起こっている。
どうも彼女は俺が橙や藍さんと仲良くしているのが気に入らないらしい。
「むむ・・・困ったな」
しかしここまでへそを曲げられたのは初めてだ。
普段はただ必死に真摯な態度で謝罪すれば許してくれるのだが、どうやら今回はそれでは済みそうにない。
「本当にすいませんでしたっ!!!」
もうこうなればなりふり構っていられないので、縁側に頭を擦り付ける勢いで土下座してみる。
「・・・・・・・・・」
チラリと上目遣いで様子を窺うと、横目でではあるが彼女が目を丸くしているのが見えた。
しかしまだ彼女の唇から「許す」と言う言葉は出てこない。
さて、どうしたものか。
(・・・そうだ)
妙案と言えるかは分からないが、この策ならば現状を打開する事が出来るかも知れない。
ただこの方法は後の事を考えると、ある意味では諸刃の剣であると言える。
早い話が引かれたら終わりだからだ。
だがこのまま土下座を繰り返すだけは埒が明かないだろう。
ならばリスクを負う事になってもやる価値はあるのではないだろうか。
(イチかバチか・・・ やってみようか)
ゆっくりと、出来るだけ音を消して紫さんの背後に回り込む。
・・・今だ。
「紫さん・・・」
「な!!」
そっと少し押すようにして彼女の身体を背後から抱きしめて、
「紫さん、許してくれませんか?」
わざと耳元で囁くように許しを請う。
「ちょ、ちょっと・・・!」
拘束から逃れようと身をよじるが、俺は上から覆いかぶさる様に抱きついているのでそう易々とは抜け出せない。
風呂上りだったのだろうか、シャンプーの甘い香りが俺の鼻腔をくすぐった。
その香りに酔いしれて、俺は一層彼女を抱く力を強くした。
「ん・・・もう、○○ったら・・・・・・」
そのまましばらくそうしていると、徐々に彼女の抵抗も弱くなって行った。
「・・・許してくれませんか、俺の大切な紫さん」
頬を擦り合わせる様にして再び許しを請う。
「卑怯ね、○○は・・・ そんな風に言われたら許すしか無いじゃないの」
でも一つ条件があるわ、と彼女は続けた。
「紫って呼んで」
「え?」
「だから、私の事を紫って呼んで頂戴」
期待するような眼差しでリクエストしてくる。
そう言えば、よくよく考えると“恋人”になってからも彼女の事を呼び捨てた記憶は無かった。
多分、それは彼女に対する一種の敬意の様なものだったのだと思う。
でも彼女にしてみれば“恋人”にそんな感情を持って接されるのはあまり嬉しいものではなかったのだろう。
ならば、俺は彼女の願いに答える。
「紫・・・これで良いかな?」
「ええ、それで良いわ」
純粋に嬉しそうな彼女の笑顔を見て、俺もついつい釣られて微笑んでしまう。
「ね、もっと私を呼んで」
クルリと身体の向きを180°回転させ、向き合うような体勢になってねだって来た。
勿論、答えない理由なんて無い。
「紫・・・」
「○○・・・」
名前を呼び合って見つめ合う。
まさに王道的な恋人同士の空間が発生した様な気がする。
それが何となくこそばゆく感じた俺は、ちょっとした悪戯を試みる事にした。
「・・・愛してるよ、紫」
と、イケメンボイス(某領主風)で囁いてみる。
「・・・・・・・・・」
瞬間、紫の表情が硬直した。
そして徐々に瞳が妖しく揺れ始める。
・・・あ、しまった!
「ああ、もう我慢ならないわ!! さぁ○○、二人で楽園に逝きましょう?」
「ちょ、おまっ!!! 字がおかしいですって!」
「うふふ・・・大丈夫よ、優しくしてあげるから♪」
「や、止めてーーーー!!!!」
「逃がさないわよ♪」
(少年少女奮闘中…)
十数分後、俺達は互いに縁側に仰向けに倒れていた。
「はぁ・・・はぁ・・・はぁ・・・お、俺を殺す気ですか」
何の準備運動も無しに1000m走でもやらされた様に俺は全身から汗をかいていた。
「・・・もう、つれないんだから」
対して彼女は俺と同じ様に縁側に転がっているが、殆ど息が上がっていない。
「藍も橙もとっくに眠っているのだから、ナニをしたって良いじゃない」
「か、勘弁して下さいよ・・・」
今また字がおかしかった様な気がする。
でもツッコミを入れるとそれを逆手に取られそうなので止めておく。
「○○」
ふいに彼女の顔がアップになった。
おそらくはスキマを使って、俺の上に転移したんだろう。
腹の上に感じる彼女の重みが心地良い。
「愛しているわ」
言葉と同時に、そっと唇を奪われた。
微かに触れる程度のフレンチキス。
それはまるで麻薬か何かのように脳髄を甘く蕩かしていく。
「紫・・・」
「○○・・・ん」
どちらからとも無く再び口付け。
今度は先程よりも長く、深く。
互いの想いを確かめ合うかのように。
「っはぁ・・・・・・ねぇ、○○」
「ん?」
永遠の様な刹那の後、俺の上に跨ったまま頬を染めて彼女が言った。
「・・・そろそろ良いかしら?」
「・・・ん、分かった」
夜は更けていく。
恋人たちは今宵もきっと幸せな夢を見るだろう。
どうか、どうか二人の穏やかな幸せが末長く続きますように。
うpろだ361
───────────────────────────────────────────────────────────
吾輩は罪袋である
名前は知らない
年齢も、血液型も、自分の顔も知らない。
「ゆかゆか~ゆかりん~~ゆかりんゆかゆか~♪」
今日も今日とて、吾輩はゆかりんをつけ狙う。
「ゆかりん~♪……ゆか?」
クンクン……
おおぅっ! 吾輩のゆかりんレーダーに反応がっ!
匂う……匂う匂う匂うぞッ!
胸一杯に吸い込まれる浄土宗……否、少女臭。
方向は12時方向、距離は約3km。
――――ん?
匂いの位置が変わった……スキマで飛んだか?
今度は3時方向で距離2km。
そのまま、吾輩の方向へまっすぐ近づいてくる。
「―――― スキマで移動しながら近づいても、気付かれてしまうみたいねぇ」
「かっわいいよ、かっわいいよ ゆ~かり~んり~~ん~~♪」
袋で目の前は見えないが、バットを構えた姿も美しい。
「今日こそ、殺してあげるわ……」
殺意を込めてバットを両手で握るゆかりん。
うぉぅ、これやばくね?
「今日と言う今日は永遠に私に付きまとえなくしてあげる!!」
一度、ゆかりんの式に「お前は、何故紫様をつけ狙うんだ?」聴かれたことがある
理由は無い
是非も無い
愛でもなく、憎しみでもなく、嫌悪でもなく――――
ただ、在るがままに此処に在り、在るがままにゆかりんを追い
在るがままにゆかりんから逃げ惑い、在るがままにゆかりんに折檻される。
そこに愛だの恋だの陳腐な感情などいらんのです!
偉い人にはそれがわからんのです!
「待ちなさ―――――い!!」
ゆかりんが走って追いかけてくる。
楽しい……楽しい楽しい楽しい~♪
追って追われて、折檻されて――――
「きゃっ!!」
可愛らしい声が響く……ちょっと待ちたまへ、今の可愛らしい悲鳴はゆかりんかッ?
「いたた……」
急ブレーキをかけて背後を振り返ると、ゆかりんが鼻を押さえていた。
どうやら、木の根っこに足を取られてすっ転んだらしい。
GJ!! 初めて見るゆかりんのドジっ子属性もGJだッ!!
いあ、それよりもスカートが肌蹴られていて白い下着とガーターベルトが――――
「――――きゃあっ!!」
吾輩の視線に気づいたゆかりんは、慌てて、スカートを抑える。
「~~~~ッ!」
怒りと恥じらいにより、一瞬で頬を赤く染めて
近くに転がっていたバットをスキマで手繰り寄せて
「飛んでいきなさ――――いっ!!!」
カッキ――――――ン!!!
「お~ぱ~○~つ、見えてるよ~!!」
おおぅ、これ大気圏脱出できるんじゃね?
生身で大気圏脱出ってすごくね?
って、いつの間にか大気圏脱出したよ俺SUGEEEEEEEEEEE!!
あれ? ……なんか太陽が近づいてきてる
そうかー、このまま太陽に突入して燃え尽きるのかー
熱いなあ、地球が遠くなっていくな……萌えていくなぁ……
「 か わ い い よ ~ ゆ か り ん ! ! か わ い ~ い よ ~~~♪」
でも吾輩は死ぬことは無い。
いろいろ手を尽くして、明日には幻想郷に戻れるだろう。
あぁいる びぃぃー ばぁぁーーーーっく!!
……吾輩は罪袋である。
名前はいらない。
・
・
・
―――― 一方、博麗神社の境内では霊夢と藍と橙がお茶を啜りながら
「以前、あの罪袋に『お前は、何故紫様をつけ狙うんだ?』って聞いたら……
『お前は、何故 自分が此処にいるか 考えたことはあるか?』……って返されてな」
「何それ、どういうこと? 」
「あの罪袋にとっては、紫様に付きまとうのは愛じゃなくて……
自分が存在すること=紫様を追いかけ追い回され折檻される……と言うことだろうな」
「難儀ねぇ……紫もあの変態も」
「紫様おっしゃってましたねぇ……『あの罪袋が相手だと自分のペースが狂わされる。あんな不条理な生物は見たことない』……って」
「そうだなぁ……紫様のスキマで異次元にすっ飛ばしても、次の日には必ず戻って来るしな……」
「どういう生き物なのよ……」
「最近では紫様、逃げるの諦めて自分からあの罪袋を叩きのめしに向かわれてるんです……」
「でも、心底気持ち悪がられている反面、妙にノリノリでバット持って出かけられるんだよな……」
「…………」
end
ちなみに、罪袋=○○ ねー
うpろだ383
───────────────────────────────────────────────────────────
「ちょっと待てー!?俺が一体何をしたー!?」
「問答無用!!」
チュドーン!!
「ウボァ~~!」
先ほどから馬鹿騒ぎをしているのは私の主、八雲 紫様とその恋人○○である
恋人なのに上のようにバイオレンスな関係なのはひとえに我が主紫様の所為である
妖怪の賢者とまで言われていてもこと恋愛関係には非常に初心だ
以前○○が不意打ちで紫様にキスをした時真っ赤になってテンパった紫様に
「高速の永久弾幕結界」で白玉庵まで吹き飛ばされたことは記憶に新しい
その後吹き飛んだ○○をみて赤い表情から青い表情になったときは不謹慎だが面白いと思ってしまった
ちなみに今回の騒ぎになった原因は……
~回想開始~
「ゆっかりー、おはよー!」
「ZZzz」
「紫ー、起きろー」 ゆさゆさ
「Zzz」
「ゆーかーりー!グッド、モーニーング!!」
「Zz、ん~もう少し寝かせてよ藍~…………………!!??」
ガバッ!
「○、○?」
「おそよう紫」
「…………もしかして見た?」
「もしかして寝顔のことか?それなら見たぞ、可愛い寝顔だった」
「ghs8bfD#gje!!??/////」
「ん?どした?顔、真っ赤だぞ」
「……の馬鹿」
「は?」
「○○の馬鹿ー!!!」
そして冒頭へ
~回想終了~
とまあ単純に紫様が○○に寝顔を見られたのが恥ずかしいから怒ったことだ
まったく紫様もいつまでたっても初心だな、他の者の恋をからかうのは好きなのに
自分の事になると奥手になる、そして恥ずかしがって○○に当たる
○○も災難だな
うむ、まだ続いてるな
「待ちなさい、○○!!」
「だが断る!!今待ったら死ぬ!」
「なら!」
紫奥儀「弾幕結界」
でた紫様の切り札「弾幕結界」逃げ道を防ぐように展開される弾幕には
○○ごときでは成す術もなく落とされてしまう
救急箱の準備と橙に頼んで薬師を呼んできてもらうか
「甘いぞ紫!!今までの俺と思うな!!」
「何をする気?」
反則「防弾結界」
○○がスペルカードを発動すると周囲に結界が貼られ弾幕がすべて消え去った
まさに反則だ
「な、なによこれ!?」
「これぞ俺の切り札の一つ「防弾結界」、発動すれば結果内の弾幕は全て消え去る!」
「それは反則よ○○」
「うるせー!日々弾幕に追われぼっこぼこに被弾する俺の気持ちも考えろ
紫に始まり魔理沙にチルノ、雑魚妖精や毛玉にも撃たれボコボコにされ……
あれ?目からしょっぱい水が……なんだろうすごく悲しいや、うぅ!!」
漫画みたいな大粒の涙を流す○○、よっぽど悔しかったか……
というか毛玉にやられるって……
見れば紫様も物凄く気の毒そうな目で○○を見ている
「ま、○○だって頑張れば強くなれるわよ
現にこんなにすごいスペルカードを作ったじゃない
もっと頑張れば毛玉なんかすぐに倒せるわよ」
「でも俺接近戦が主体で弾幕なんて撃てないし
第一空、飛べない」
「で、でもスペルカードならそんなハンデなんて覆せるわよ
あるでしょ、攻撃用のスペルカード」
「あるにはあるけど効果がちょっと……」
「男は度胸、なんでも試してみるべきよ
変なところがあったら私も協力するから直せば良いじゃない」
「うーん、紫がそこまで言うならちょっとやってみるか
じゃあとりあえず結界貼ってくれ」
「分かったわ、壊すぐらいの気合でやりなさいよ
まあ無理だろうけど」
境符「四重結界」
「んじゃ、いくぞ!!」
そう言うと○○は拳を振りかぶりスペルカードを発動させた
鬼拳「一方通行」
ゴゥッ!!
○○の拳から撃ち出された拳大ほどの大きさしかないレーザーみたいなものは
真っ直ぐと紫様の方へ飛んでいった
速さは大したものだが紫様は事前に結界を貼っているから大丈夫だろう
ギリリッ パリィン!!
「!?紫、避けろ!!」
「くっ!!」
それは四重結界に当たると暫らく拮抗した後四重結界を破っりそのまま紫様に直撃しそうになった
しかし○○が結界が破られる前に避けるように警告した為
掠っただけで紫様は無事回避できた
一方通行は四重結界に当たったにも拘らずそのまま真っ直ぐ飛んでいった
別に真っ直ぐ飛ぶのは問題ないんだがただ私の位置に問題があった
図にするとこうなる
○○ 紫様 ――→ 私
↑
一方通行
紫様の後ろで観戦してた私は四重結界が破られたことに驚いて
紫様がとっさに避けた一方通行を避けきれずそのまま直撃を受けてしまった
その衝撃で気絶直前の意識が捕らえたものは
「紫!大丈夫か?」
「ええ、○○が早めに教えてくれたから掠っただけよ
それにしても結構な威力ね」
「スマン、俺の所為で紫に傷を……」
「文字通りかすり傷だから大丈夫よ」
「でも、紫の陶磁器の様な肌に傷をつけてしまった」
「も、もうほめても何もでないわよ////」
「紫、本当にすまない」
「だからもう謝らないでっていってるでしょ」
「俺の気がすまないんだよ」
「なら……だ、だだだだだだ抱きしめてくれない?////」
「それぐらいならいくらだってしてやるよ
なんならキスもどう?」
「だだだだ抱きしめるだけで十分よ!!」
「そっか、残念」
顔を真っ赤にしながら○○に抱きしめてもらう紫様と
紫様を抱きしめさりげなく紫様の髪の匂いを嗅ぐ○○の姿だった
……………………覚えてろ○○
そして目を覚ました私が見たものは真っ赤な顔をしながら私の枕元に座っている橙と
あの後何があったのか知らないがやけにイチャネチョしている二人の姿だった
その様子を見てもう大丈夫なんだなと思いもう一度意識を手放した
うpろだ405
───────────────────────────────────────────────────────────
「…………………・・・○○…………○○……」
「ううぅん、何ですか紫様……。まだ眠いですよ…」
「そりゃあれだけハッスルすればね。うふふ、元気だったわね」
「もう精も根も尽き果てましたよ。あいたたた……腰どころか背中まで痛い…」
「うふふ。はい、お水。のど渇いてるでしょ?」
「ありがと……んっ…ちゅるっ……ぷはっ」
「まだ飲みたい?」
「どうして口移しで飲む必要があるんですか……」
7スレ目>>745
>>745の続きを勝手に考えて書いてみた
反省はしているが後悔はしていない、若干紫の性格が違うかも
「紫様、お食事ここに置いておきますね」
襖の向こうから→「ええ、ありがとう藍、ほら○○ご飯よー」
同上 →「ちょ!?待て!紫一人で食べれるかr」
「藍様ー、ご飯持っていたんですよね?紫様と○○さんどうでしたー?」
「あ、ああ二人ともちゃんとご飯を食べてるよ」
「そっかー、でもなんで箸一つしか使わないんだろ?」
「き、きっと紫様が○○に『あーん』をしてあげているんだろう」
(○○の様子だと絶対口移しで食べさせられたんだろうな……)
「仲いいですね紫様と○○さん」
「恋人同士だからな」
(それにしたって四日間部屋に篭りっきりっていうのは……その、なんだ橙の教育に悪いよな、声も時々聞こえてくるし)
「でも今度は四人一緒に食べたいです」
「ああ、楽しみだなその時はご馳走を作るから橙も手伝ってくれるか?」
「はい!」
「などと言ってますけど、そろそろ出るか?橙も寂しがってるし……ってなんで泣くんだよ!?」
「グスッ…ヒック、だって……○○は私のこと嫌い?」
「嫌いじゃないって!愛してるから、な?泣くなよ」
「ええ、分かったわ、だからもう少しだけ……ね?」
「ああ、分かった、来いよ紫お前の全部、俺が受け止めてやるよ」
(……惚れた弱みだな、すまん橙、四人一緒にご飯食べるのはもう少し後になりそうだ)
7スレ目>>791
───────────────────────────────────────────────────────────
藍の日記より。 ~乙女(?)の葡萄踏み~
@月*日。
紫様が台所に立っている。
最近御執心の○○に手料理を振舞おうと張り切っておられるようで、
そんな紫様からは少女臭がぷんぷんする。 それにしてもあれは…
紫「~♪」
藍「紫様、何をされるおつもりで?」
紫「今年はブドウの出来がよかったから、
きっと美味しいワインができるって聞いたのよ。」
藍「それで…そのブドウを人里から失敬してきたと?」
紫「それだけじゃないわ。私の手作りワインを造って、
ああしてこうして、○○をとろけさせてやるのよ♪」
藍「人里のお酒なんて、できあがったやつを失敬してくればいいじゃないですか。」
紫「いえいえ藍。男は女の手作り料理や贈り物に弱点属性持ってるものよ。
人間の女性は手料理ひとつで男の愛と恋の境界を操ってしまうのだから。」
そういうと紫様はたるの中にブドウをほいほいと詰め込んでいく。
ああ、まてよ?たしかブドウからワインを作る方法って…
ttp://allabout.co.jp/gourmet/wine/closeup/CU20051006A/
紫「さあ、できたわ♪ 藍、ちょっと味見してみない?」
藍「あ、頂きます。」
(ぐび…カシャーン!)
藍「ぐおぉ…」
私は…それを一口飲んだだけで倒れてしまった。
鼻を突く刺激臭、なんてレベルのものではない。視界が…歪む…
紫「あら、藍?あなたそんなにお酒に弱かったかしら?」
藍「い、いえ…その、紫様…ひとつお聞きしてもよろしいですか?」
紫「なぁに?」
藍「その…靴下は…」
紫「ああ、本当は脱ぐのよね。
種や枝が当たると痛いから履いたまま踏んじゃったけど…」
藍「ウボァ」
(バタッ!)
後日、人里でワインを調達して中身をすり替えておこう。
私は紫様の従者なればこそ、主が哀しむ結末を避ける義務があるのだから…
7スレ目>>796
───────────────────────────────────────────────────────────
「ごはん…私のごはん…(ジュルリ)」→みんな
「貴女の為ならこの身体。喜んで貴女の血肉となりましょう」
7スレ目832-833
───────────────────────────────────────────────────────────