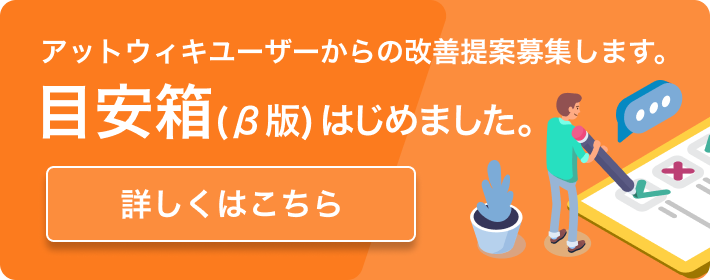プロポスレ@Wiki
アリス6
最終更新:
orz1414
-
view
■アリス6
最後の最期まで
貴方のコトを
ズルリ、ズルリ
やけに重く感じる自分の身体を引きずりながら夜の森を進む。
そして自分の家へ。やっとのことで辿り着き、壁沿いに這うようにして歩む。
まるで死に場所を求めているかのように。そう考えて小さく嘲った。そうだ、まさにその通りじゃないか。
「・・・まだ、伝えれてないっていうのに・・・・・・」
ポツリとつぶやいた言葉も、ただ空しく闇に消えていくだけ。
いつもはそれを聞き届けてくれる人形も、もう全部壊れてしまった。
もう、助からない。
わかってる、そんなことくらい。
だって、切り裂かれた所からは止めどなく血が溢れているのに、もう、痛みすら感じないのだから。
やがて歩く力も尽き果て、地面に崩れ落ちる。
こんな私にも、自分に最期の時が来た事くらいわかるつもりだ。
所詮魔法使いという種族は人間より寿命が長いだけ。攻撃を受ければ普通に死んでしまう。
それでも、まだ生きたいと思っている自分がいるのだけれど。
「だって、何も、何も言えてないのよ・・・っ」
傷口を押さえていた手は、真っ赤で。
でもそれ以上に、私の両手は、自分のものじゃない血で真っ赤で。
ああ、これは罰なのだ。
ただ、貴方の側にいるためだけに、血に、罪に染まった私への罰。
ただ少し、貴方の手伝いがしたかっただけ。
だから、妖怪退治なんてものを積極的にやり始めたというのに―――
「ふふっ・・・本当にバカね、私」
言葉にして伝えることが怖くて。
貴方に拒絶されるのが恐くて。
そして何より、この関係が壊れてしまうのではと思ったら、何もできなかった。
何もできないけれど、役に立ちたかったから、せめて仕事の手伝いをしようとした。
慣れない妖怪退治。
本当はしたくなかった妖怪殺し。
それで貴方の役に立てるのならと、必死に言い聞かせて頑張ってきた。
「ごめんなさい、弱虫で」
それでもせめてと、側にいる事だけを願って。
まあ、妖怪退治の相方なんて、お世辞でも良い関係なんて言えないかもしれないけれど。
「でも・・・私、貴方の側に居られて、本当に良かった」
そんな関係が心地よくて、幸せだった。
ずっと側に居れるのならって、柄にもなくそう思ってた。
人間と関わりを持つ事なんて好きじゃなかった筈なのに。
彼にとって私はただの相方で、それ以上でもそれ以下でもなかった筈なのに。
『おかしな奴だな、アリスは』
○○の、声が聞こえた気がする。『アリス』と、私を呼ぶ声。
貴方なら、地獄の底までも来てくれるだろうか。
こんな私を、見つけてくれるだろうか。
「○○は・・・・気付いてくれるかしら」
誰に看取られる事もなく、ひっそりと死んでいく私に。
託すように真っ赤な血で、古くなった家の壁に小さく文字を綴っていく。
書いたところから崩れるように滲んでいくそれは、きっと、貴方が来る頃には全部滲んで何も見えないのだろうけど。
それでもいいと、そう思った。
否、これで充分だった。
「・・・○○、私は、貴方を愛してたのよ」
だから、せめて眠りにつく前だけは。
「―――・・・愛してた」
この想いを空に還す事を赦してください。
”I love you... Good night.”
それじゃあ、おやすみなさい
私は先に眠るわ
きっと、この滲んだ文字に託した想いでさえも
貴方には届かないのだろうから
10スレ目>>678
───────────────────────────────────────────────────────────
ここは魔理沙邸前。
今、俺の目の前にはあいつがいる。
「こんなところで会うなんて奇遇だな、アリス」
「ええ、私もまさかこんなところで会うなんて思わなかったわ」
セリフだけから考えるなら俺達は単なる友人どうしにしか見えない。
だが、実際は違う。
「たまには違うところに行ったらどう? まあ、友人の少ないあなたじゃ無理だと思うけど」
「その言葉、そっくりお前に返してやるよ。友達の少ないアリスさん」
人によっては俺達のことをこう言うだろう。
あいつらの間には常に火花が散っているぞ、と。
そう、俺達は魔理沙をめぐる恋のライバルなのだ。
「二人とも、そんなところで何やってんだ?」
「「ま、魔理沙!?」」
「お、おう。で、何の用だ?」
「「え、えっと」」
ええい、何のためにここに来たと思ってるんだ、俺!
早く言わないと……。
「「クッキーを焼いてきたんだ(きたのよ)」」
勇気を出して言ったはいいが、横からも同じ内容の言葉が聞こえてきた。
「そ、そうか。二人が同時にそんなもの持ってくるなんて珍しいな。
まあ、茶ぐらいは用意するからあがっていけよ」
そう言うと魔理沙は家の中へと入っていった。
「ちょっと、男のあんたが何でクッキーなんか焼いてくるのよ!」
「時代遅れだな。今じゃあ、男だって料理スキルぐらい持ってるもんだぞ」
この女、どうやら俺と同じ考えでここに来たらしい。
昨日の魔理沙が言った、クッキーか何か甘いものでも食べたいなあ、って言葉に反応してだ。
「おおい、早く入って来いよ」
「くっ、覚えてなさいよ」
そして俺達は魔理沙邸に入っていった。
何回目になるかもわからない、魔理沙争奪戦の始まりである。
「いやぁ、やっぱアリスのクッキーはなかなかうまいぜ」
「あたりまえでしょ。どっかの誰かさんみたいに思いつきで作ってるわけじゃないんだから」
「どっかの誰かさんってのは誰のことなのかな?」
「さて、誰のことでしょうねぇ」
「「……ふふふふふっ」」
「じゃあ、今度は○○の方をもらうぜ」
「ああ、ぜひ食ってみてくれ」
魔理沙は俺の作ったクッキーを手に取り、口の中へ運んだ。
俺とアリスの二人は固唾を飲んでそれを見守る。
「うん、○○のもかなりうまいな」
「そんな! 素人のはずなのに……」
アリスは慌ててクッキーをつかみ、それを口の中へ放り込んだ。
「う、うそ。負けた……」
「ふっ、幻想郷に来るまでの俺の趣味はお菓子づくりだったんだよ。だから、クッキーぐらい焼けて当然だ」
「へー、そうなのか。何か意外だぜ」
そこで俺は隣に座っているアリスに勝ち誇った目を向けてやった。
彼女はその視線にすぐ気がついたようだ。
「……っ!」
「痛っ!」
いきなり背中に痛みが走った。
どうやら、アリスが思いっきりつねっているらしい。
しかも魔理沙に見つからないように。
だが、黙ってやられている俺じゃない。
「うっ!」
そう、俺もあいつの背中を力一杯つねってやった。
相当痛いらしく、少し涙目でこっちをにらんできた。
その後、こっちの背中の痛みがさらに激しくなった。
「くっ! 往生際の悪い……」
負けじと俺もさらに力を加える。
そしてさらにアリスも……。
それが何度か続いてから、魔理沙が口を開いた。
「二人ともどうした? なんか顔が少し赤いぜ」
「「な、なんでもないっ!」」
「そうか、ならいいぜ。ん? 茶が切れたな。また入れてくるぜ」
彼女はポットを持って台所へ引っこんでいった。
「ねぇ、少しいいかしら」
アリスが小声で話しかけてくる。
「私としてはそろそろこの不毛な戦いをやめにしたいんだけど」
「まったくもって同感だな」
「ええ、だからもう決着をつけようと思うの」
「どうやってだ? まさか川原で殴り合いでもするのか?」
「弾幕ごっこならしてもいいけど」
「遠慮しとくわ」
そう、俺は弾幕ごっこができない。というより、弾幕すら出せないんだ。
だから、こんなことで勝負されても困る。
理由は違うがそれはアリスの方も同じだった。
「……まったく、私は正々堂々と勝ちたいの。だから、こういう方法をとるわ」
そこで彼女はある提案を話してくれた。
要約するとこうだ。
まず、今日の帰り際に二人が同時に魔理沙に告白する。
そしてその返事をもらえた方が勝ち。負けた方はいさぎよく身を引く。
ここで俺がこの提案を飲まなければ、アリスは臆病だとあざ笑うだろう。
それも癪に思ったので、それに乗ることにした。
「ふうん。それでいいよ、俺は」
「ずいぶんな自信ね。ぶっつけ本番で出来るのかしら?」
挑発した目でこちらを見つめる。
「俺を誰だと思ってる? いつも感じている感情をそのまま伝えるだけじゃないか」
「まあいいわ。どうせ勝つのは私だから」
「それはこっちのセリフだ」
しばらくお互いに火花を散らしていると、ようやく魔理沙が戻ってきた。
「おまたせ……っと、どうやらお邪魔だったみたいだな」
見つめ合う俺達を見て、微妙に勘違いしたことを言いやがった。
「「だれがこんな奴と!」」
それに対して俺達もかなりベタな返し方をした。
さっきはああ言ったものの、実際に告白の内容を考えるとなるとどう言えばいいのかわからない。
しかも、その本人が目の前にいるのだ。
気恥ずかしいやら何やらで悶々と考えていると、いつのまにやらもう帰る時間になっていた。
「じゃあ、魔理沙。私達はそろそろ帰るわ」
「わかった。気をつけて帰れよ」
「でも、その前に私達からあなたに伝えたいことがあるの」
「ん、何だ?」
ついにこのときが来てしまった。
正直、心臓がバクバクしてて今にも破裂しそうだ。
「えっとね、その……私は魔理沙が……」
「俺は魔理沙のことが……その……」
「私がどうしたんだ?」
「だ、だ……だいす……」
「だい……、だ、だ……」
「だ? すまん、後ろが聞こえなかったんだぜ」
頭の中は真っ白だ。さっきまで考えてた言葉も全然出てこない。
でも、言わなきゃ。俺は魔理沙が大好きなんだって。
とにかく、言わなきゃ……。
「「だ……、弾幕ごっこしろ!(しなさい!)」」
「は? まあ、別にかまわないけど。○○は弾幕が使えないんじゃないのか?」
「う、うるせぇ! 男は度胸だろうが!」
「そうよ! 早くしなさいよ!」
「わ、わかったよ。じゃあ、外で待ってるぜ」
魔理沙はほうきとミニ八卦炉を手に取り、家の外へと出て行った。
ああ……、俺はなんてことをしてしまったんだろう。
いくら恥ずかしいからってあんなことを言ってしまうなんて。
横を見ると、顔を真っ赤にして震えているアリスがいた。
今の俺も第三者から見ればあんな風なんだろうな。
そんな詮無いことを考えながら、俺とアリスの二人はとぼとぼと外へ歩いて行った。
目が覚めると、草木の焼けるにおいが鼻をついた。
予想通りの結果だが、俺は今地面に横たわってる。
そして隣には同じようなアリスの姿がある。
その原因は魔理沙だけでなく俺にもあるが。
俺は開始早々アリスの人形をつかまえ、彼女の後頭部めがけて全力で投げつけた。
そしてその結果アリスはそれに気を取られ、弾幕の海に沈んだ。
まあ俺に勝ち目はないから、俺にとっての最悪の事態さえ避けれればそれでいい。
「やってくれるじゃない、○○」
「お前一人を勝たせるとでも思ったか」
「「ふふふふふ……、はぁ……」」
「で、魔理沙は?」
「もう帰ったみたい。私達が気絶してる間にね」
「……薄情だな」
「まったくね」
再び、二人はため息をついた。
「じゃあ、俺も帰るとするか。もう動けるぐらいには回復したから」
「私はまだ無理ね。あなたほど手加減されてなかったし、直撃だったから」
「無様だな、アリス」
「誰のせいだと思ってんのよ」
半ばあきれるような目でこっちをにらんできた。
「ふぅ、わかったよ。夜になると危ないからな。俺が送っていってやる」
俺は彼女を抱きあげ、背中に背負った。
「ちょっ、何するのよ! 放しなさい!」
「うおっ! 暴れるな、落ちるぞ」
「変なとこ触んないでよ! この変態!」
「せっかく送ってやってんのにその言い草は何だよ!」
「うるさい! 元はと言えばあなたのせいでしょうが!」
しばらくそんなやりとりを続けていると、お互いに言いたいことを言いきってしまったのか、話すことがなくなってしまった。
しかし、アリスって思ってたより軽いな。やっぱ女の子なんだな。
これでもう少し静かならかわいいのに……って何変なこと考えてるんだ!
俺は魔理沙一筋だろうが! その俺が何でアリスのことなんか考えなきゃいけないんだ。
だが、一度そう思ってしまうとどうもそのことが頭から離れなくなってしまう。
肩にかかる彼女の髪。ほのかに漂ってくる女の子の香り。
そして、背中に当たるむ(ry
はっ、いかんいかん! また変な考えをしてしまうところだった。
と、そこでようやくアリスの家にたどり着いた。
「えっと、玄関まででいいわ。もう歩けるから」
「そ、そうか……」
まずい。さっきあんなことを考えてたせいか彼女の顔を正面から見られない。
「一応お礼は言っておくわ。……その、ありがと」
「あ、ああ。別にいいさ。ま……また今度な。」
「……はっ。う、うん」
別れの挨拶をした俺は足早に帰った。
今のこの真っ赤にそまっているだろう顔をアリスに見せないために。
もしこのとき彼女の顔を見ていたら、俺はあることに気が付いていただろう。
そう、俺の顔と同じぐらいに彼女の顔も真っ赤になっていたことに。
そして彼女もまた、俺の顔を直視できていなかったということに。
10スレ目>>638
───────────────────────────────────────────────────────────
雨が、降ってきた。
夜の冷たい雨が降り、人通りのない暗く冷たい森の中。
点々と赤い道しるべを残しながら、それでもとアリスは家の壁を伝うように扉へと進んでいた。
しくじったわね・・・なんて考える頭もぼうっとしてきてハッキリしない。
本当は妖怪退治を終えたのだから真っ先に彼の所へ行って報告したいところだが、体が思うように動いてくれない。
如何せん、血を流し過ぎた。
切り裂かれた腹は熱く、血は止まるという事を知りそうにない。
雨のせいもあってか体温がみるみる奪われていくのが分かった。
カクンと膝が落ち、壁にもたれかかるように座り込むと、水溜りが赤く染まる。
「ん・・・・そろそろ、かし、ら」
顔の前に左手をかざしながら、自嘲と共に呟く。
傷口を押さえていたその手は既に血塗れで、今の自分は返り血と自分の血で全身真っ赤だ。
息は今までにないほど熱く乱れている。
酸素を求めようと呼吸を繰り返すが、喉元からこぼれてゆき失敗に終わっていく。
最悪の状況。
人形を持たない人形使い。
動く事もままならない重い身体。
指の隙間からこぼれてゆく、血。
「―――・・・・・・」
最悪の状況、なのに。
考えているのは自分の命の心配じゃなくて、もっと。
こうなる状況を作ってしまった、罪作りな男のこと。
私が望んで追いかけてきた、(私のことをどうとも思っていない、)あのひとのこと。
私が死んでも、(私があなたのことをどれだけ考えていたかも知らないで、)泣かないだろうあのひとのこと。
もとよりこんな関係だった。
そこに悔むべき箇所も、取り戻すべき失態もない。
何もできないからせめてと、この道を選んだのは私自身なのだから。
心残りがあるとすればただひとつ。
それは自分の力不足に他ならない。
勝手に追いかけて、ひとりで滑稽に踊って、そして最期は誰にも目を向けられず。
そして目的もただひとつだった。
私は彼に、○○に認められたいと思って、最初からそれだけで、
「・・・・・・ッ」
ふと、近づいてくる気配に口端を上げた。
「・・・見つかっちゃった」
仕留め損ねた残党が来たらしい。
少しくらい静かにしてほしいものだ、という願いとは裏腹に、バタバタと足音が大きく聞こえるようになる。
妖怪が近づいてくる。
光が殆ど差し込んでこないために、それらの表情はよく見えないが、きっと笑っているのだろうと予想する。
きっと、弱った私を見て、そして殺せるというコトが嬉しいのだろう。
「Good-bye, ・・・let's meet in hell.」
・・・最後に、さようなら地獄で会いましょうなんて恨み事を残して。
もう、どうにもならない事は分かっているけれど。
どうする事もできないのだから。
だから、すっと瞳を閉じた。
しかし、来るはずの衝撃はいつまでたってもアリスを襲う事はない。
不審に思ったアリスがゆっくりと瞳を開けると、そこにはさっきまで戦っていた妖怪たちの亡骸。
そして暗闇の中から、聞きなれた声が私の耳に届いた。
「―――・・・何を、やってるんだ」
その声の主に、アリスは思わず目を見開く。
「・・・意外。どうして、こんなところに」
そう言うと、彼は少し眉間にしわを寄せた。
何故かと思ったが、あえて口には出さなかった。
「そんなに意外か?」
「だって、○○が来るなんて、思わなかったもの」
ふふっと弱々しく途切れながらも笑うアリスに、○○がゆっくりと近づく。
そして、眉間にしわを寄せたまま、傷口にそっと手を添えた。
「・・・里の奴らがもう少しで来てくれる。そしたら治療できるからな」
「大丈夫よ、急所は外れてるし」
まあ少し、出血が多いけど・・・とアリスが笑う。
その顔に血の気はなく、『何が大丈夫なのか』と聞きたくなるほどで、
○○はその笑みを見るたびに胸を締め付けられるような感覚に、ぐっと手を握りしめた。
「・・・・・・どう、して・・・・・・」
「・・・○○?」
「どうして、お前は笑っていられるんだよ・・・!?」
『どうしたの?』とアリスは急に俯いてしまった○○の顔を覗き込もうとした。
しかし、それはアリスの首元に頭を埋めるようにして寄りかかってきた○○のせいで出来なかった。
「俺はお前を見つけた時、心臓が止まるんじゃないかと思うほどだったのに、今だって、」
ポツリ、ポツリと言葉を漏らす○○にアリスはじっと耳を傾ける。
「お前を失ってしまうんじゃないかと、」
「居なくなってしまうんじゃないかと、」
「なのに、お前は・・・笑って・・・ッ」
微かに肩を震わす○○の背になんとか手を回しながら、アリスは微笑んだ。
いつの間にか雨は止んでいて、同じように濡れていたはずの○○は温かく感じた。
「・・・ごめん、なさいね?心配かけて」
「・・・ゴメンじゃ、ねえよ」
顔を上げた○○と目が合う。
瞬間、アリスの表情は驚きへと変わった。
「○○・・・泣いてるの?」
「何で泣かなくちゃ、ならないんだよ」
「だって、涙・・・」
そう言って、アリスが○○の頬をゆっくりとした動作で拭う。
○○の頬には幾重にも水の流れた跡があった。
「・・・これは、雨だ」
○○がアリスの手を掴んで止めさせようとする。
けれど、アリスは止めようとはしなかった。
「・・・もう、雨は止んでるのに?」
「・・・っ」
「ありがとう、○○」
「!?」
・・・私の為に泣いてくれて。
私を想って泣いてくれて。
「・・・私、まだ夢じゃないかと思ってるのよ、だって、うれしいもの、」
でなければこれは死後の世界の幻覚か。
それほどに、○○がここに居てくれる事は得難い奇跡だったのだ。
「・・・○○、が、きてくれたって、こと」
会いたいと思った。
死ぬ前に、心の底から愛した人に会わせてほしいと、ただ願った。
無意識のうちに、祈っていた。
・・・それだけじゃない。
○○のあんな顔を見て、心配されて、その優しい言葉に、
なぜだかむねにわきあがるあたたかいもの。
・・・ああ、いとしいのだ、と。
私は本当に、このひとのことが―――
「大好き、よ・・・・」
そう微笑んだアリスが、ゆっくりと瞳を閉じた。
「・・・アリス・・・?」
ぱたりと話す事も、動く事もなくなったアリスに、○○は狼狽する。
まさか、という気持ちが沸き起こり、アリスの肩を強く揺すりながら必死で名前を呼んだ。
「アリス・・・ッ!!アリスーッ!!」
「五月蝿い」
「ふごっ!?」
刹那、○○の腹にドスッと突きが入る。
何事かと○○がアリスを見ると、不機嫌極まりない様子でこちらを睨みつけていた。
「少しぐらい寝かせなさいよ」
驚きを隠せない○○は、あんぐりと口を開けていて。
「な・・・!?死んだん、じゃ・・・・」
「勝手に殺さないで頂戴」
「生憎、まだ死んでなんてあげないから」
貴方に泣かれてまで、死ねるわけ無いでしょう?
だって心残りで
安心してあの世なんかいけないわ
貴方の泣き顔なんて
見てしまったら もう
(・・・勿体無くって何処にも逝けやしない)
10スレ目>>694
───────────────────────────────────────────────────────────
私は今日紅魔館に来ている、もちろん本を借りる為だ
いやいや、魔理沙と違って私は借りたものは返すわよ?
「んー・・・あれ?」
「どうしたのアリス?」
そんなこんなで図書館で物色していると、見慣れない奴を見かけたのだ
「アップルティーです、パチュリー様・・・・・・」
机に紅茶とシフォンケーキ、そして彼は私を見つめた
「ええと・・・」
「彼女はアリス、私の友人よ」
「そうでしたか・・・此処で執事をさせてもらっている○○というものです」
「へぇ・・・改めて、私はアリス、アリス・マーガトロイドよ」
「よろしくお願いします・・・それでは仕事に戻ります」
お盆だけ持って彼は退室した
「ねぇ、彼って人間?」
「いえ、吸血鬼の出来損ないよ」
「へえ・・・」
そのときは特に気にも留めなかった
ちょっといい男ぐらいに思ってたんだけど
レミリアが気に入った男なんだから、何かあるんだろう、それぐらいの認識
そんな考えもすぐに何処かへと、私は読書に意識を戻すのだった
「はぁ、すっかり遅くなっちゃった」
本を読んでいるといつの間にか夜
パチュリーと一緒に本を読んでいると時間間隔がなくなっちゃうわね
「おや?アリスさんお帰りですか?」
「あら○○さん、私はもう帰るところよ」
「玄関まで遅らせてもらいます」
「ありがと」
相変わらず長い廊下、図書館から玄関まで十分近く掛かるのではないか、そういう長さだ
「そういえば○○さんはどうして紅魔館に?」
「どうして・・・そうですね、簡単に説明すると吸血鬼になって行き場がない私を、レミリア様が保護してくれたんです」
「へえ・・・え?貴方ってレミリアから派生した吸血鬼じゃないの!?」
「いえ、半端な方法で吸血鬼になったもので・・・半人前以下です」
たぶん、私が彼に興味を持ったのはこの瞬間ではないだろうか?
幻想郷に存在する唯一の吸血鬼、スカーレット
しかし此処に、スカーレット姉妹以外の吸血鬼が居る、それだけで彼の存在は重いものとなる
「アリスさん?もう玄関ですよ」
「え?あ、ああ・・・」
ちょっと色々考えてしまった、ボーっとするにも程がある
「あ、ありがとう!それじゃあおやすみなさい」
彼女は危ない足取りで闇に溶けていった
「大丈夫かな・・・」
「何が大丈夫なのかしら?」
「うひゃぁ!?さ、咲夜さん」
いつの間にか背後にいるのは慣れたけどいちいち耳にふーってしないでください
「うふふ、可愛いのね・・・このあと」
「あ、アリスさんを送り届けてきますねっ!」
脱兎の如く、逃げましたよ
以前あんな感じで誘われてホイホイついて行っちまって・・・
まぁ忘れよう、世の中にはそういうことのほうが多い、はずだ
「う~ん」
吸血鬼になるには吸血鬼にかんでもらうか、それ以外の方法で
「アリスーマエヲミテー」
「へ?きゃっ!?」
考え事をしていたせいで思いっきり太い枝におでこをぶつけてしまった
「いたた・・・」
驚いてついでにこけてしまった、お尻が痛い
「アリスさん!大丈夫ですか!」
「○、○○さん!?どうして」
「いや、うわのそらだったので、いちおう・・・心配で・・・」
差し伸べられた大きな手、一瞬躊躇って、掴んだ
彼の手が暖かかったからだろうか?なぜか私は恥ずかしくなった
こけた事もおでこをうった事も、なぜか無性に恥ずかしくなった
「あ、ああありがとう!それじゃあ」
彼女は俺の前からまさに脱兎の如く逃げ出した
でもすぐに何かにぶつかってうめく声が聞こえた・・・もうなんだかな
~後日~
「お邪魔するわ」
「あらアリス、またきたの」
「今日はちょっとね・・・」
「?」
館内をうろうろ、うろうろ
「何処にいるのよ・・・」
うろうろ、きょろきょろ
ただでさえ広い、そして部屋数も多いから探すのは大変だ
「吸血鬼なんだから日光が当たらないところにいるはずよね」
となると必ず館の中にいると思うんだけど
「う~ん・・・」
とりあえず上海と手分けして探す事にした
「はぁ・・・これで今日の仕事は終り・・・明日の分まで・・・いや止めとこう、明日出来ることは~って言うし」
「ミツケター、○○ミツケター」
「ん?人形・・・・・・・確か、何処かで見たような・・・」
「アリスー○○ミツケター」
「ああ、アリスさんの右斜め上にいた人形ちゃんじゃ無いか」
「グッドモーニング○○ー」
「え?ああ、グッドモーニング」
ずいぶんと愛嬌のある人形だ、可愛らしい事この上ない
「○○さん?」
「アリスさん、おはようございます」
「あ、おはようございます・・・ちょっとお時間いいですか?」
「?」
その後俺は吸血鬼になった経緯と方法を根掘り葉掘り聞かれた
根掘るって解るけどよ、葉を掘ったら裏に(ry
「じゃあまだ吸血鬼の能力を手にしたわけではないのね?」
「一応今は腐敗が終わって人間と同じぐらいにはなりました、でも身体能力などはまだ・・・治癒は少々」
「へぇ・・・じゃあ今は欠点だらけって事ね」
「はい・・・これから欠点を補うほどの能力がつけばいいのですが」
今のところ吸血鬼の欠点だけを持っている感じだ
個人的には怪力とか霧になるとかは便利そうなんだけども
「ふぅん・・・まぁつまりホントに出来損ないだったのね」
痛いところをつかれた、まったく持って反論できないのが悔しい
「まぁ最初から完璧な吸血鬼なんていませんよHAHAHA」
「ふふ、そういう事にしておくわ」
彼の手
暖かい手
大きな手
あのときの暖かい手の感触
なぜかドキリとしてしまった、なぜ?
「・・・アリスさん?」
「え?あ・・・」
いけない、私ったら彼の事ばっかり
「そ、そろそろ帰るわね」
「あ、はい、お送りします」
長い廊下、廊下の半分には日が当たらないように設計されている
当然彼は影を歩く
そうか、今は昼だから、玄関まで・・・か
そうよね、灰になっちゃうもんね
「ねぇ○○さん」
「はい、なんでしょう」
「いま・・・その・・・付き合ってる女性はいたりする?」
「い、いえ・・・いませんが」
「も、もしかして男s「男もいません!」
そうかそうか、この紅魔館で紅一点?でありながらフリーなんだ、そうなんだ
「じゃあ・・・私と付き合ってみない?」
「え?・・・」
「・・・」
「じゃ、じゃあ今度までに返事を頂戴ね!」
「ちょ、ちょっと待ってくださ・・・あ」
「ふふ」
彼女は既に日の光の下にいる
危うく灰になるところだった、つまりまんまと逃げられたわけだ
「またね~」
ひらひらと、陽気に手を振るアリスさん、結局声をかける間もなく、視界から消えてしまった
「・・・人生初の告白(される側)が・・・これか」
影の中で少し明るい気分になった
しかし彼女の言う次が気になるのも事実であった
「い、言っちゃった・・・」
心臓がバクバクと、大きな音を立てて鼓動を刻む
震えるぞハート!燃え尽きるほどの・・・尽きちゃ駄目だ
「はは、言えたんだ」
ほとんど勢いで、それでも言えた
意気地なしの自分が、言う事が出来た
ああ、日の光ってこんなにも・・・眩しかったのか
何となく、とても、機嫌がいい
そうだ、今日ぐらいは茶菓子を買って行って上げようかしら?
不思議と不安はない、拒絶が怖いとか、そういう気持ちは浮かばない
「何でかしら?・・・いい研究内容だわ」
(何故私は、こんなにも強気なのか?)
それはきっと恋の魔法
何処かの白黒のお株を奪わんばかりの・・・恋の予感
「次はいつ、紅魔館に行こうかしら?」
「彼女はいつ、紅魔館に来るのか?」
10スレ目>>731
───────────────────────────────────────────────────────────
思えばあれはただの私の気まぐれだったのに。
なんでこんなに、胸が苦しいのだろう?
私の家に突然現れ
[貴女の事を高名な人形師と聞いた。 弟子にしてくれないか?]
という紙キレをいきなり突きつけてきた男。
幾度か断っても紙切れを取り下げることはなく、とうとう私が根負けしてしまった。
何故紙切れなの? という問いにだけ、彼はその紙切れの裏に
[私は喋れないんだ]
とだけ書き、悲しそうに微笑んだ。
それが、全ての始まり。
口がきけなくても、夢はあった。
――意のままに操れる人形を作り、子供達を楽しませたい
喋ることができないのを筆頭に、音楽も試したがてんでダメだった。
昔から裁縫等の細かい作業は割と得意だったので、人形なら、と思い立ったのだ。
腕のいい人形師はいないかと方々を聞いて(見せて)まわり、ようやくそれらしき人物の話を聞けることが出来た。
まるで魔法のように人形を操る人物……アリス・マーガトロイド。
里から少し離れた魔法の森とよばれる奥深い森に居を構えているという。
居ても立ってもいられず、馬を借りて森へと駆けた。
……途中で雨が降ってきたのは予想外だったが。
"必需品"は雨に濡れないように油紙を被せてある。問題はないだろう。
教えられた道とも言えぬ道を走ること半刻ばかり、それらしき家を見つけた。
幸いなことに明かりも着いている。
少々不躾だとは思っていたが、この機を逃すわけにもいかない。
前準備としていくつかの事を紙に書き留め、呼び鈴を鳴らす。
「どちらさま?」
戸を開けて現れたのは私より年下と思えるくらいの少女だった。
相当面食らったが、すぐに冷静を取り戻す。この子はアリスとやらの弟子かも知れない。
[失礼だが、貴女はアリス・マーガトロイドで間違いないかな?]
とりあえず最初の紙切れを差し出す。
喋れない私はこうしてコミュニケーションをとる他ないのだ。
「え、ええ……そうだけど、それが何か?」
少々驚いた顔で私の顔を見る。それにしてもやはりこの少女がアリスだったのか。
構わずに次の紙を差し出す。
[貴女の事を高名な人形師と聞いた。 弟子にしてくれないか?]
その紙切れを見るなり、彼女は若干の溜息をつく。
「貴方には悪いけれど、弟子を取るつもりはないのよ。面倒だしね」
……予想していたとは言え、さすがにこうもハッキリいわれるとは。
それでもあきらめるわけにはいかない。
差し出した紙も、下げない。
「だから嫌だって、言ってるじゃない。それに、人形師になって何をするつもりなの?」
しまったな、それの答えは用意していない。
ちょっと待っていろ、とジェスチャーで示し、紙に筆を走らせる。
[子供達を、喜ばせたい]
急いでいたせいで随分汚い字面になってしまったが、読めない程でもない。
その紙切れを示した後、今度は先ほどの紙切れを半分破り
[弟子に、してくれないか?]
再度、突き出した。
元々手が器用だったせいもあってか、彼はめきめきと上達していった。
最初は針の穴に糸を通すことすら苦心していたのに。
ちょっとしたコツや素材の選び方等も教えると彼は熱心に聞いて、そして吸収してくれた。
弟子を取るのは今までにその技術を悪用しようとするものがいたから断っていたのだけれど。
彼はどこまでも純粋だった。
私が魔法使いだと知った時も
[すごいな、空とか飛べるんだろ?]
と書いた紙をくれた。
普通の人間ならもう少し驚いたり怖がったりするものなのに、ね。
その時からかな、少しずつ彼が気になり始めた。
もう私にとってはルーチンワークでしかないような作業……彼もとっくにマスターしているはずの事ですら
彼は真剣そのものの表情で取り組む。
[弟子なんだから、これくらい]
そう言いながら、身の回りの世話も全てやってくれた。
割と小奇麗にはしていた家ではあったけれど、前にも増して綺麗になっていった。
仕事の合間を見つけては掃除をしたり、簡単な日用品を作ったり、修繕したり。
そのくらい私がやるわ、と言っても
[いいから、いいから]
と決して譲りはしなかった。
あれから、どれほどの月日が過ぎただろうか。
時々家を空ける彼女に代わり、人形師としての腕を磨く片手間家事をする。
日々をいくつも積み重ねたのち、私はようやく彼女のお墨付きが出る程度の腕前にはなった。
曰く、「もう一人で動いても問題はないんじゃないかしら」という程には。
さすがに魔力なんてもんは持ち合わせていないので、人形を喋らせたりなんて芸は出来なかったけれど。
彼女と過ごす日々は楽しかった。
弟子なんだから何でも言いつけてくれと言ったのにあくまで対等に接してきたのにはさすがに驚いた。
結局こっちから色々やってしまっているのだが。
私を弟子にしたのも何とも変な理由だった。理由を尋ねた時も
「その体格で、子供達を楽しませたいなんていうものだから……面白くって」
そうしてひとしきり笑った彼女はとても眩しかった。
さて、今アリスは家を空けている。近くに住んでいるらしい知り合いの魔法使いに薬剤を貰いに行ったようだ。
恐らく、あと数時間は戻ってこないだろう。長くて半日か。
……チャンスがあるなら、今か。
「ふぅ……ただいま。魔理沙ったら散々私の事からかって……
○○? 外にいるのかしら」
魔理沙から目的のモノを貰い、揚々と帰って来た。
普段のように長引きはしなかったが、色々とからかわれた。
彼に愚痴りながらまたいつものように人形でも作ろうと思った。
家の中にはいる気配がしなかった。
外で野良仕事でもしているのかと思い、ぐるっと回ってみてもいなかった。
入れ違いかと思って家へ戻っても、彼はいなかった。
変わりに見つけたのは、彼がいつも座っていた作業机の上に乗せられたメモだった。
[ええっと、我が師ことアリス・マーガトロイドへ。
今まで長らくお世話になりました。
貴女の言う、一人で動いても問題ない、がどの程度のものなのか少々試してみたく
誠に勝手ながら暫くのお別れです。
道中が無事でありますよう
頭の片隅ででも祈ってくれればこれ幸い。
追伸:旅に出るにあたり、いくつかの食料を拝借致しました。申し訳ない。
北の畑を上空から眺めて下さい。最後のメッセージです。
それでは、お元気で。 ○○]
「ちょっと、何よこれ……」
勝手に出て行っていいなんて言った覚えはない。
彼の腕は確かに上等だけど、まだまだ教え足りない。ツメも甘い。
安楽椅子の手摺の調子が悪いから直してもらわなきゃいけないのに。
まだ畑の取り入れも終わってない。私一人じゃ重いから彼には居てもらわないといけないのに。
まだ、まだ……
気づけば、涙が頬を流れていた。
それと同時に自分の気持ちに気づいてしまった。
追いつけばまだどこかを歩いているかもしれない。
慌てて空へと飛び上がる。彼のメモを握り締めたまま。
そこでふと下に目線を落とす。
北の、畑。
いくつかの作物を刈り取った後に残された文字が、見て取れた。
[愛してる]
そして「る」の場所にはまだ刈り取りをしている○○の姿が。
いつもなら後数時間は帰ってこない。そうタカをくくっていたのだろう。
「あの、馬鹿……!」
(こんなもんかなぁ……ちゃんと字になってるよな。多分)
満足気に腕を組み、頷く。
(さて、そろそろ行く、か)
彼女ともう会えないかも知れないのはとても寂しい、が
いつか戻ってくるつもりではある。
立派になった自分を見てもらうために。
荷物を肩に背負ったあたりで後ろに気配を感じた。
「アンタね……
そういうことは、もっと早く言いなさいよ、この、馬鹿ッ!」
蹴られた。
受身も何も取るまでもなく、畑の剥き出しの土の上に倒れる。
あれ、なんでこんな所にいるんだ……まだ魔理沙の家にいるはずなのに。
うわ、しかも私のメモ持ってるし。
何か泣いてるし。何かあったのか……?
それらを尋ねようとメモ帳とペンを手にしたところで
上からアリスが飛び乗ってきた。
「言いたいことだけ言って逃げるなんて卑怯よ!
私の気持ちも知らないで!
大体、興行くらいなら麓の里で十分できるじゃない!
私は貴方が好きなの!
私は、アナタと……○○と、もっと一緒にいたいの!」
それだけ一気に言うと、アリスは私の服に顔を埋めた。
どうやら泣きじゃくっているらしい。
本来ならば言葉でもかけたいが、喋ることができない私にはどうしようもない。
優しく抱きしめることで、彼女が落ち着くまで待った。
そのまま起き上がる。アリスは丁度私の足の間に座って私にもたれている。
改めてペンと紙を握り、先の返事を書く。
[このまま一緒にいたら、私が気持ちを抑えられそうもなかったから]
だから出て行こうと、思った。
[貴女は私のことなんてさして気にもしていないと思っていたんだが]
これはさすがに小突かれた。「女心が分かってないわ」との説教つきで。
[すまない]
頭を下げる。
「謝らなくてもいいわ……こうして追いつくまでもなかったけれど、また会えたのだし」
そうして涙目で笑顔を浮かべる彼女はいつにもまして綺麗に見えた。
[それで、今後のことなのだが]
彼女も私を好きだと言ってくれた。
それならば、家を出なくても問題にはならないということだろう
「どうしたの?」
この一言を書いてもいいものか、逡巡した後に。
悩んでも仕方ない、と一気に書き綴る。
[君さえよければ、また一緒に暮らしたい]
そのメモを破り、彼女の手に持たせる。
[ダメかな?]
渡したメモにそう書き足す。
「そうね……返事は……」
言うなりペンをひったくられる。
そして書かれた文字は
[いいわよ、未来の旦那様]
驚きに目を見張る私を見て彼女は微笑み、
そのまま唇を合わせた。
「さ、帰りましょ、私達の家に」
>>うpろだ540
───────────────────────────────────────────────────────────
「それにしてもあのときの霊夢の落ちこんだ顔は忘れられそうにないぜ」
「……魔理沙、その60ガバスっていうものを賽銭箱に入れたのはあなたなんでしょ?」
「そのとおりだぜ。いやぁ、パチュリーにも見せたかったぜ。なぁ、アリス?」
「私に話をふらないでよ」
「……本当にあなたは毎度毎度お騒がせなんだから」
日の光の入らないヴワル図書館。
今、この図書館に居るのは四人の少女達と一人の青年、つまり俺である。
今日も今日とて魔理沙の強奪劇に有無を言わさず駆り出された俺はいつものように紅茶をご馳走になっている。
まあ、ここへ連れて来られるのはいつも無理やりだがそれでも悪いことばかりとは思えない。
まず第一にここへ来ればいろいろな本、それも外の世界ではお目にかかれないようなものが読める。
次に咲夜さんの淹れてくれたおいしい紅茶が飲める。
そして何より、アリスと必ず会うことができる。
正直に言おう。俺はアリスに惚れている。
いわゆるベタ惚れというやつだ。
なぜ俺が彼女に惚れたのかは彼女との出会いから説明しなければならんので今は割愛させていただく。
まぁそれはおいといて、俺と彼女との仲は客観的に見てもそれほど悪いものではないと思う。
だがそれ以上は進展していない。
というのは、俺に後一歩踏み出す勇気が足りないんだ。
そう、俺は今の関係が崩れるのを恐れている。
もしアリスに拒絶されてしまったら。もしそれまでのように友人としても付き合えなくなってしまったら。
そんなことばかり考えてしまう。
ああ、せめて何かチャンスがあればなぁ……。
「ん、それじゃあそろそろ魔導書を取りに行くか」
「ちゃんと返しなさいよ」
「大丈夫。後できっと返すぜ」
「全く……、少しはアリスや○○を見習いなさい」
「そうね。少しは返す努力をしたらどう?」
「はいはいっと。じゃあ先に行ってるぜ。また後でなパチュリー! ○○!」
「待ちなさい! 魔理沙!」
「小悪魔、魔理沙が必要以上に借りていかないように見張ってなさい」
「はい、パチュリー様」
そんなかしましい会話とともに魔理沙、アリス、小悪魔の三人の姿は見えなくなった。
と、ふいにパチュリーが口を開いた。
「○○、ちょっといいかしら」
「うん? どうした?」
「あなたってアリスが好きなのよね?」
「なっ……! くぁwせdrftgyふじこ!」
彼女から放たれた言葉は俺の予期しなかったものだった。
ていうか何故にあなたが俺の秘めたる思いを知っているんで!?
「あなたのアリスへの態度を見ればすぐにわかるわ。あれでわからないのはよっぽど鈍感なやつだけよ」
「う……、その……」
「それで本題に入るわけだけど、どうして彼女にその思いを伝えないの?」
「えっと……、それは……」
「今の関係が壊れるかもしれないから?」
ガタッ!!
核心を突く言葉に思わず立ち上がってしまった。
「そう、なるほどね。だったら一つ言わせてもらうけど、あなたが思ってるほどアリスは弱くはないわ。
もし彼女があなたの申し出を断ったとしても、あなたが態度を変えなければ今のままの関係、友人としての関係はきっと続くわ」
「けど……」
「少なくともアリスとの付き合いは私の方が長いわ。だからまあ、私を信じて突撃してきなさい」
そう言い、彼女はカップに口をつける。
「……本当に信じてもいいんですか?」
「ええ、保障するわ」
「わかりました。俺は「ストップ、その前にこれをあげるわ」
そこにあったのは一冊の本だった。
「えっと……、初心者のための恋愛バイブル?」
「それを読んで少しは勉強しなさい」
「……」
いくら何でもこれはないだろう……。
「不満そうね。せっかく私があなたのためと思って用意したのに」
彼女の方を見るとこれ以上ないくらいに微笑んでいた。ただし目は全く笑っていなかったが。
「い、いえ……そんなことありません!」
「そう、なら頑張りなさい」
その後、家に帰ってから俺はその本を読みふけった。
「何よ……、これ……」
顔が熱い。きっと私の顔は真赤になっているだろう。
今、私が見ているのは一冊の雑誌。しかも外の世界のものである。
そこにはデートではどうすればいいとか、彼氏へのプレゼントは何がいいか、などが書かれていた。
そしてさらには口では言えないような過激なことも……。
私がこんなものを持っている理由……、それは魔理沙と別れて魔導書を探している途中に小悪魔から渡されたからだ。
その時の彼女は満面の笑顔でこう言った。
『これで○○さんとの仲もきっと進展しますよ♪』
はぁ……、どうして私が○○のことが好きだとわかったのだろうか。
このことは魔理沙にも言ったことないのに……。
「うう……」
いけないいけない。さっきのことを思い出したらまた顔が……。
でも、小悪魔が応援してくれているのは事実よね。
よし! この本の知識を借りて○○ともっと仲良くなろう。
そしてあわよくば恋人に……。
「よーし! やるわよ!」
あれから俺はパチュリーにもらった本を読み、五つの必勝法を編み出した。
まず一つ目は、デートで仲を進展させるべし、だ。
ということでさっそく誘ってみることにした。
とはいえさすがに二人でデートに行こうと言っても断られるのがオチである。
だから彼女には薬草を採りに行くから手伝ってくれと言ってある。
まあ、一応採りに行くから嘘は言ってない。
よっしゃ! 彼女とのデート、絶対に成功させるぞ!
それからしばらくしてアリスがやってきた。
そして俺の必勝法、二つ目と三つ目が炸裂する!
まずはいつもと違う服を着てくること。これにより今日は特別な日だと印象づけるのだ。
「おはよう○○。あら、今日はいつもと少し感じが違うわね。そういうのも結構似合ってるわ」
よっしゃ! 大成功!
わざわざ香霖堂まで行って買ってきた甲斐があったぜ。
そしてすかさずもうひとつを発動!
「ありがとう。いやぁ、今日のアリスもかわいいね。そのカチューシャもよく似合ってるよ」
「お世辞なんか言っても何にも出ないわよ」
「お世辞なんかじゃないさ。俺がそう思ったから言ったわけだから」
「そ、そう……。あ、ありがとう……」
さりげなく女性の容姿を褒めるべし。
こっちもなかなかの成果だな。
「そ、それじゃ行きましょ」
「おう」
こうして俺とアリスの薬草探し、もといデートが始まった。
ああ、かわいいなんて言われちゃった……。
もう嬉しすぎて死んじゃいそう。
それにいつもと違う服の○○もカッコいい……。
ああ、今日は本当にいい日だなぁ。
て、呆けてる場合じゃないわ。今日のような日のためにいろいろと仕込んできたんだから。
しかしまさか○○の方から二人きりでデート……、じゃなくて薬草採りに誘ってくれるなんて。
アリス! 今日というチャンスを最大限に生かすのよ!
「ふぅ、結構腰にくるな」
と、薬草を採っていた○○が立ち上がりながら言う。
さっそくチャンスね!
「ここは私にまかせて。上海!」
「シャンハーイ」
上海の持つ剣は次々と薬草を刈っていく。
「アリスの人形はいつ見てもすごいなぁ。うちにも欲しいぐらいだよ」
「そう? じゃあ今度作ってあげようか? 最も自律型みたいなのは無理だけど」
「え、でも何か悪いなぁ」
「いいのいいの。好きでやってることだから」
「そう? じゃあお願いできるかな」
よし! これで○○とまた会う口実ができた。
いつもは魔理沙のつきそいぐらいでしか会えないからなぁ。
もっと会えれば、あんなことやこんなことを……。
「じゃあ、今度はあっちをお願い」
「え? う、うん。わかったわ」
あ、危なかった。つい思考がトリップしてしまった。
ちゃんと気をつけないと……。
「ふぅ、これだけ集めれば十分でしょ」
「いやぁ、助かるよ」
薬草はなんだかんだでお金になるからな。
そう言えば魔理沙にも何度か手伝ってもらったっけ。
と、もう昼過ぎだな。
よし四つ目を発動させるときだな。
「えっと、アリス?」「その、○○?」
と、アリスが言った言葉とかぶってしまった。
「じゃ、じゃあアリスから先に言って……」
「○○の方こそ先に……」
「「……」」
「ねぇ、同時に言わない?」
「そうね、そうしましょ」
「「せーの」」
「そろそろお弁当を食べないか? 俺が二人分用意してきたからさ」
「そろそろお弁当でも食べましょ。私が二人分用意してきたから」
「「……」」
おい、内容もかぶっちゃたよ。
これじゃ四つ目の必勝法、男は黙って料理で勝負、の効果が発揮できないじゃないか!
でも、アリスの手料理も食べたいし……。
「「ぐぎゅるー」」
と、何やら変な音が二つ聞こえた。
「……とにかくお昼御飯にしましょ」
「そ、そうだな……」
うう、アリスにあんな音を聞かせてしまうなんて……。
「うん、この卵焼きおいしいね」
「ありがとう。○○のつくったハンバーグもとってもおいしいわ」
「いやぁ、頑張って作ったからね」
結局、二人で分け合って食べることにした。
俺の料理も褒めてもらったし、アリスの手料理も食べられたし本当に最高だ。
まあ四人分あるわけだからかなりの量が余ってしまうが……。
「ん、もうお腹いっぱい。ごちそうさま」
「おそまつさまでした。私ももういいわ」
「余ったのはどうする?」
「んー、二人で分け合えばいいんじゃない?」
「そうだな」
それから二人の間に少し会話がなくなった。
よし、これなら最後の必勝法を……。
いい雰囲気になったところで愛の言葉をささやくっていうのを……。
あ、愛の言葉……?
しまった!? 必勝法を考えるのに夢中で告白の内容まで考えてなかった……。
え、えっと……。ど、どどどどうしよう……!?。
何か、何か言わなくちゃ! せっかくのチャンスなんだから……。
こんなにいいチャンスもう二度とないかもしれないんだぞ!
せっかくパチュリーも手伝ってくれたんだぞ!
こうなったら男○○。一世一代の大勝負に出る!
「あー、アリス? ちょっと話があるんだが……」「○○? ちょっといいかしら……」
「「……」」
ま、またかぶってしまった……。
け、けど言わなきゃ! 何か言わなきゃ!
テンパッてて何言えばいいかわからないけどとにかく言わなきゃ!
「アリス!」「○○!」
またかぶった。けど今の俺にはそこまで気にする余裕はない!
「俺はアリスのことが好きなんだ!」「私は○○のことが好きなの!」
「「……え?」」
しばらく二人の間に何とも言えない空気が流れる。
「え、えっとつまりその俺達は……」
「そ、そうね。要するに……」
「「最初から両想いだった?」」
何なんだろう今のこの気持ちは?
告白が成功したのに、こう何か複雑というか。
あそこまでテンパった意味はなかったなぁっというか。
まあ、嬉しいに決まってはいるんだが。
と、そんなことを考えていると彼女が話しかけてきた。
「ね、ねぇ。う、嘘じゃない……よね」
「あ、当たり前だろう! 俺はアリスが好きなんだ」
その言葉に俺は精一杯肯定の意を示す。
「う、うん! 私も!」
アリスは本当にうれしそうに笑いながら答えてくれた。
それにつられて俺も微笑んだ。
うん。とりあえず今はこの喜びをかみしめていよう。
そして、俺に踏ん切りをつけてくれたパチュリーにも感謝を。
「うまくいきましたね、パチュリー様」
「そうね」
暗闇の中、パチュリーと呼ばれた少女は答えた。
そこには遠見の魔法で映し出されたアリスと○○の姿があった。
「それにしても、慌てる二人を見るのは楽しかったなぁ。さらにこのネタを新聞へ提供すれば礼金もたんまり……。じゅるり……」
「本当にうまくいって良かったわ。そう、誰もが納得する形で……」
「これで不安要素の芽はつぶせましたね」
「ええ。これからはゆっくりと私の愛を告げていくだけ……。そう、魔理沙は私だけのモノよ……。ふふふ……」
広大な図書館に魔女の妖艶な声が響き渡る。
11スレ目>>18
───────────────────────────────────────────────────────────
「んー」
外に出て軽く身体を伸ばす。
すっかり弱くなった秋口の日差しが、やさしく私をお出迎え。
今日はハロウィン。
外来のイベントなのだが、寺子屋では子供たちに仮想させて、ご丁寧にも一軒一軒回るらしい。
愛しい彼は、寺子屋の先生の真似事をやっているので、
私ことアリスも、彼が引率して来るのに合わせて、こうやってお菓子作りをしているのだ。
美味しいお菓子を食べさせて、子供たちに「人形遣いのおばさん」などと言われないようにしなければ。
「だーれだ?」
不意に、視界が暗くなる。
こめかみには、筋肉質のごつごつとした手の感触。
この大きな手は――。
「○○?」
「正解。もう少し声色を変えるべきだったかな」
両目にかかる手をゆっくり外して振り返ると、そこには、微笑を浮かべた彼の姿があった。
「どうしたの? こんな時間に。子供たちが来るのは夕方じゃなかった?」
「ああ。でも一応、道の確認をね。いざ、という時に焦らないようにしないと。
それに――」
「それに?」
「なんとなく、アリスと会えるような気がしたから」
顔を朱色に染めながら、気障を言う彼。
そんな言葉を聞かされたら、私まで照れてしまう。
「も、もう! バカ! それに私は怒っているんだからっ!」
プイッ
頬を膨らませて抗議する。ついでに横も向いてやった。
あんまり、照れた顔は見せたくない。
だけど、彼は、
「どうしたんだー、ア・リ・ス」
頬をぷにぷにとつついてくる。
「本当は怒ってないこと、わかっているよ」とでも言わんばかりに。
そんな彼の手を振り払って、一言。
「Trick or Treatって言わなかったでしょう? いきなり悪戯なんて、ルール違反よ」
「それはすまなかった。では、改めて。
Trick or Treat」
「え?」
しまった。
まさか、こう返されるとは。
今の私の顔はきっと、ぽかん、としているに違いない。
それもそのはず。
パウンドケーキはさっきオーブンに入れたところだし、もう作ってあるクッキーはテーブルの布巾の中。
これからもう一踏ん張り、と思っていたガレットデロワは、まだ生地を寝かせたまま。
つまり、お菓子なんて持ってない。
「あ、あの――」
「ふふふ、持ってないようだね。じゃ、遠慮なく悪戯しようかな。
さあ、目を瞑って」
ぎゅっと目を瞑る。悪戯好きな彼のことだ。何をしてくるか、予想がつかない。
カシャッ カシャッ
落ち葉を踏んで、彼が近づいてくる音がする。
きっと、もう唇が触れられるくらい。
彼の吐息が、カールした前髪をそっと、靡かせた。
「――っ!」
手が、首筋にかかる。
も、もしかしてキス!? もしかしてキスなの!?
彼の両手が、うなじを撫でて――。
「ひゃん!」
肩を、揉みだした。
「アリスのことだから、きっとケーキとか力の要る洋菓子作ってたんだろう?
やっぱり、相当凝ってるよ。無理しないで欲しいな」
「あ、あふう、そ、その……」
「はい、これで終わり」
最後に軽く肩を叩くと、揉むのをやめる彼。
うう、なんだかさっきから見透かされている。
ちょっとでも、逆襲したいな。
そう思っているところに、天啓が閃いた。……これならば、きっと。
「―― ― ――」
「おいおい、道の下見に来た俺が、お菓子なんて持っている訳ないだろう。
はいはい、悪戯を受けますよ、お姫様」
茶目っ気たっぷりの彼の言葉。
ならば、遠慮なく。
「じゃあ、目を瞑ってくれる?」
「ん。こうか?」
私より頭一つは大きい彼が、目を瞑ったことを確認する。
うん、大丈夫。
ゴクリ
一つ、唾を飲み込む。
そして。
彼の首に両手を回すと、一気に唇を奪った。
「んんっ! ア、アリスっ!」
「じゃ、じゃあ、夕方には待ってるからっ!」
そのまま、玄関のドアを開けてバタバタと家の中に入ってしまう。
頬が火照り、心臓が早鐘を打っていた。
恥ずかしい。
自分は、あんなに大胆だっただろうか。
窓枠に肘をついて、紅潮した頬を冷ましながら彼を見ていると。
彼は、呆然と唇に手を触れ、その後、こちらを振り返りながら村の方へと去っていった。
彼は、気がついていただろうか。私がその言葉を放った時点で、このことは確定事項だったと。
それは、魔法の言葉。
「Trick and Treat(いたずら、そして甘い口づけ)」
11スレ目>>73
───────────────────────────────────────────────────────────
最後の最期まで
貴方のコトを
ズルリ、ズルリ
やけに重く感じる自分の身体を引きずりながら夜の森を進む。
そして自分の家へ。やっとのことで辿り着き、壁沿いに這うようにして歩む。
まるで死に場所を求めているかのように。そう考えて小さく嘲った。そうだ、まさにその通りじゃないか。
「・・・まだ、伝えれてないっていうのに・・・・・・」
ポツリとつぶやいた言葉も、ただ空しく闇に消えていくだけ。
いつもはそれを聞き届けてくれる人形も、もう全部壊れてしまった。
もう、助からない。
わかってる、そんなことくらい。
だって、切り裂かれた所からは止めどなく血が溢れているのに、もう、痛みすら感じないのだから。
やがて歩く力も尽き果て、地面に崩れ落ちる。
こんな私にも、自分に最期の時が来た事くらいわかるつもりだ。
所詮魔法使いという種族は人間より寿命が長いだけ。攻撃を受ければ普通に死んでしまう。
それでも、まだ生きたいと思っている自分がいるのだけれど。
「だって、何も、何も言えてないのよ・・・っ」
傷口を押さえていた手は、真っ赤で。
でもそれ以上に、私の両手は、自分のものじゃない血で真っ赤で。
ああ、これは罰なのだ。
ただ、貴方の側にいるためだけに、血に、罪に染まった私への罰。
ただ少し、貴方の手伝いがしたかっただけ。
だから、妖怪退治なんてものを積極的にやり始めたというのに―――
「ふふっ・・・本当にバカね、私」
言葉にして伝えることが怖くて。
貴方に拒絶されるのが恐くて。
そして何より、この関係が壊れてしまうのではと思ったら、何もできなかった。
何もできないけれど、役に立ちたかったから、せめて仕事の手伝いをしようとした。
慣れない妖怪退治。
本当はしたくなかった妖怪殺し。
それで貴方の役に立てるのならと、必死に言い聞かせて頑張ってきた。
「ごめんなさい、弱虫で」
それでもせめてと、側にいる事だけを願って。
まあ、妖怪退治の相方なんて、お世辞でも良い関係なんて言えないかもしれないけれど。
「でも・・・私、貴方の側に居られて、本当に良かった」
そんな関係が心地よくて、幸せだった。
ずっと側に居れるのならって、柄にもなくそう思ってた。
人間と関わりを持つ事なんて好きじゃなかった筈なのに。
彼にとって私はただの相方で、それ以上でもそれ以下でもなかった筈なのに。
『おかしな奴だな、アリスは』
○○の、声が聞こえた気がする。『アリス』と、私を呼ぶ声。
貴方なら、地獄の底までも来てくれるだろうか。
こんな私を、見つけてくれるだろうか。
「○○は・・・・気付いてくれるかしら」
誰に看取られる事もなく、ひっそりと死んでいく私に。
託すように真っ赤な血で、古くなった家の壁に小さく文字を綴っていく。
書いたところから崩れるように滲んでいくそれは、きっと、貴方が来る頃には全部滲んで何も見えないのだろうけど。
それでもいいと、そう思った。
否、これで充分だった。
「・・・○○、私は、貴方を愛してたのよ」
だから、せめて眠りにつく前だけは。
「―――・・・愛してた」
この想いを空に還す事を赦してください。
”I love you... Good night.”
それじゃあ、おやすみなさい
私は先に眠るわ
きっと、この滲んだ文字に託した想いでさえも
貴方には届かないのだろうから
10スレ目>>678
───────────────────────────────────────────────────────────
ここは魔理沙邸前。
今、俺の目の前にはあいつがいる。
「こんなところで会うなんて奇遇だな、アリス」
「ええ、私もまさかこんなところで会うなんて思わなかったわ」
セリフだけから考えるなら俺達は単なる友人どうしにしか見えない。
だが、実際は違う。
「たまには違うところに行ったらどう? まあ、友人の少ないあなたじゃ無理だと思うけど」
「その言葉、そっくりお前に返してやるよ。友達の少ないアリスさん」
人によっては俺達のことをこう言うだろう。
あいつらの間には常に火花が散っているぞ、と。
そう、俺達は魔理沙をめぐる恋のライバルなのだ。
「二人とも、そんなところで何やってんだ?」
「「ま、魔理沙!?」」
「お、おう。で、何の用だ?」
「「え、えっと」」
ええい、何のためにここに来たと思ってるんだ、俺!
早く言わないと……。
「「クッキーを焼いてきたんだ(きたのよ)」」
勇気を出して言ったはいいが、横からも同じ内容の言葉が聞こえてきた。
「そ、そうか。二人が同時にそんなもの持ってくるなんて珍しいな。
まあ、茶ぐらいは用意するからあがっていけよ」
そう言うと魔理沙は家の中へと入っていった。
「ちょっと、男のあんたが何でクッキーなんか焼いてくるのよ!」
「時代遅れだな。今じゃあ、男だって料理スキルぐらい持ってるもんだぞ」
この女、どうやら俺と同じ考えでここに来たらしい。
昨日の魔理沙が言った、クッキーか何か甘いものでも食べたいなあ、って言葉に反応してだ。
「おおい、早く入って来いよ」
「くっ、覚えてなさいよ」
そして俺達は魔理沙邸に入っていった。
何回目になるかもわからない、魔理沙争奪戦の始まりである。
「いやぁ、やっぱアリスのクッキーはなかなかうまいぜ」
「あたりまえでしょ。どっかの誰かさんみたいに思いつきで作ってるわけじゃないんだから」
「どっかの誰かさんってのは誰のことなのかな?」
「さて、誰のことでしょうねぇ」
「「……ふふふふふっ」」
「じゃあ、今度は○○の方をもらうぜ」
「ああ、ぜひ食ってみてくれ」
魔理沙は俺の作ったクッキーを手に取り、口の中へ運んだ。
俺とアリスの二人は固唾を飲んでそれを見守る。
「うん、○○のもかなりうまいな」
「そんな! 素人のはずなのに……」
アリスは慌ててクッキーをつかみ、それを口の中へ放り込んだ。
「う、うそ。負けた……」
「ふっ、幻想郷に来るまでの俺の趣味はお菓子づくりだったんだよ。だから、クッキーぐらい焼けて当然だ」
「へー、そうなのか。何か意外だぜ」
そこで俺は隣に座っているアリスに勝ち誇った目を向けてやった。
彼女はその視線にすぐ気がついたようだ。
「……っ!」
「痛っ!」
いきなり背中に痛みが走った。
どうやら、アリスが思いっきりつねっているらしい。
しかも魔理沙に見つからないように。
だが、黙ってやられている俺じゃない。
「うっ!」
そう、俺もあいつの背中を力一杯つねってやった。
相当痛いらしく、少し涙目でこっちをにらんできた。
その後、こっちの背中の痛みがさらに激しくなった。
「くっ! 往生際の悪い……」
負けじと俺もさらに力を加える。
そしてさらにアリスも……。
それが何度か続いてから、魔理沙が口を開いた。
「二人ともどうした? なんか顔が少し赤いぜ」
「「な、なんでもないっ!」」
「そうか、ならいいぜ。ん? 茶が切れたな。また入れてくるぜ」
彼女はポットを持って台所へ引っこんでいった。
「ねぇ、少しいいかしら」
アリスが小声で話しかけてくる。
「私としてはそろそろこの不毛な戦いをやめにしたいんだけど」
「まったくもって同感だな」
「ええ、だからもう決着をつけようと思うの」
「どうやってだ? まさか川原で殴り合いでもするのか?」
「弾幕ごっこならしてもいいけど」
「遠慮しとくわ」
そう、俺は弾幕ごっこができない。というより、弾幕すら出せないんだ。
だから、こんなことで勝負されても困る。
理由は違うがそれはアリスの方も同じだった。
「……まったく、私は正々堂々と勝ちたいの。だから、こういう方法をとるわ」
そこで彼女はある提案を話してくれた。
要約するとこうだ。
まず、今日の帰り際に二人が同時に魔理沙に告白する。
そしてその返事をもらえた方が勝ち。負けた方はいさぎよく身を引く。
ここで俺がこの提案を飲まなければ、アリスは臆病だとあざ笑うだろう。
それも癪に思ったので、それに乗ることにした。
「ふうん。それでいいよ、俺は」
「ずいぶんな自信ね。ぶっつけ本番で出来るのかしら?」
挑発した目でこちらを見つめる。
「俺を誰だと思ってる? いつも感じている感情をそのまま伝えるだけじゃないか」
「まあいいわ。どうせ勝つのは私だから」
「それはこっちのセリフだ」
しばらくお互いに火花を散らしていると、ようやく魔理沙が戻ってきた。
「おまたせ……っと、どうやらお邪魔だったみたいだな」
見つめ合う俺達を見て、微妙に勘違いしたことを言いやがった。
「「だれがこんな奴と!」」
それに対して俺達もかなりベタな返し方をした。
さっきはああ言ったものの、実際に告白の内容を考えるとなるとどう言えばいいのかわからない。
しかも、その本人が目の前にいるのだ。
気恥ずかしいやら何やらで悶々と考えていると、いつのまにやらもう帰る時間になっていた。
「じゃあ、魔理沙。私達はそろそろ帰るわ」
「わかった。気をつけて帰れよ」
「でも、その前に私達からあなたに伝えたいことがあるの」
「ん、何だ?」
ついにこのときが来てしまった。
正直、心臓がバクバクしてて今にも破裂しそうだ。
「えっとね、その……私は魔理沙が……」
「俺は魔理沙のことが……その……」
「私がどうしたんだ?」
「だ、だ……だいす……」
「だい……、だ、だ……」
「だ? すまん、後ろが聞こえなかったんだぜ」
頭の中は真っ白だ。さっきまで考えてた言葉も全然出てこない。
でも、言わなきゃ。俺は魔理沙が大好きなんだって。
とにかく、言わなきゃ……。
「「だ……、弾幕ごっこしろ!(しなさい!)」」
「は? まあ、別にかまわないけど。○○は弾幕が使えないんじゃないのか?」
「う、うるせぇ! 男は度胸だろうが!」
「そうよ! 早くしなさいよ!」
「わ、わかったよ。じゃあ、外で待ってるぜ」
魔理沙はほうきとミニ八卦炉を手に取り、家の外へと出て行った。
ああ……、俺はなんてことをしてしまったんだろう。
いくら恥ずかしいからってあんなことを言ってしまうなんて。
横を見ると、顔を真っ赤にして震えているアリスがいた。
今の俺も第三者から見ればあんな風なんだろうな。
そんな詮無いことを考えながら、俺とアリスの二人はとぼとぼと外へ歩いて行った。
目が覚めると、草木の焼けるにおいが鼻をついた。
予想通りの結果だが、俺は今地面に横たわってる。
そして隣には同じようなアリスの姿がある。
その原因は魔理沙だけでなく俺にもあるが。
俺は開始早々アリスの人形をつかまえ、彼女の後頭部めがけて全力で投げつけた。
そしてその結果アリスはそれに気を取られ、弾幕の海に沈んだ。
まあ俺に勝ち目はないから、俺にとっての最悪の事態さえ避けれればそれでいい。
「やってくれるじゃない、○○」
「お前一人を勝たせるとでも思ったか」
「「ふふふふふ……、はぁ……」」
「で、魔理沙は?」
「もう帰ったみたい。私達が気絶してる間にね」
「……薄情だな」
「まったくね」
再び、二人はため息をついた。
「じゃあ、俺も帰るとするか。もう動けるぐらいには回復したから」
「私はまだ無理ね。あなたほど手加減されてなかったし、直撃だったから」
「無様だな、アリス」
「誰のせいだと思ってんのよ」
半ばあきれるような目でこっちをにらんできた。
「ふぅ、わかったよ。夜になると危ないからな。俺が送っていってやる」
俺は彼女を抱きあげ、背中に背負った。
「ちょっ、何するのよ! 放しなさい!」
「うおっ! 暴れるな、落ちるぞ」
「変なとこ触んないでよ! この変態!」
「せっかく送ってやってんのにその言い草は何だよ!」
「うるさい! 元はと言えばあなたのせいでしょうが!」
しばらくそんなやりとりを続けていると、お互いに言いたいことを言いきってしまったのか、話すことがなくなってしまった。
しかし、アリスって思ってたより軽いな。やっぱ女の子なんだな。
これでもう少し静かならかわいいのに……って何変なこと考えてるんだ!
俺は魔理沙一筋だろうが! その俺が何でアリスのことなんか考えなきゃいけないんだ。
だが、一度そう思ってしまうとどうもそのことが頭から離れなくなってしまう。
肩にかかる彼女の髪。ほのかに漂ってくる女の子の香り。
そして、背中に当たるむ(ry
はっ、いかんいかん! また変な考えをしてしまうところだった。
と、そこでようやくアリスの家にたどり着いた。
「えっと、玄関まででいいわ。もう歩けるから」
「そ、そうか……」
まずい。さっきあんなことを考えてたせいか彼女の顔を正面から見られない。
「一応お礼は言っておくわ。……その、ありがと」
「あ、ああ。別にいいさ。ま……また今度な。」
「……はっ。う、うん」
別れの挨拶をした俺は足早に帰った。
今のこの真っ赤にそまっているだろう顔をアリスに見せないために。
もしこのとき彼女の顔を見ていたら、俺はあることに気が付いていただろう。
そう、俺の顔と同じぐらいに彼女の顔も真っ赤になっていたことに。
そして彼女もまた、俺の顔を直視できていなかったということに。
10スレ目>>638
───────────────────────────────────────────────────────────
雨が、降ってきた。
夜の冷たい雨が降り、人通りのない暗く冷たい森の中。
点々と赤い道しるべを残しながら、それでもとアリスは家の壁を伝うように扉へと進んでいた。
しくじったわね・・・なんて考える頭もぼうっとしてきてハッキリしない。
本当は妖怪退治を終えたのだから真っ先に彼の所へ行って報告したいところだが、体が思うように動いてくれない。
如何せん、血を流し過ぎた。
切り裂かれた腹は熱く、血は止まるという事を知りそうにない。
雨のせいもあってか体温がみるみる奪われていくのが分かった。
カクンと膝が落ち、壁にもたれかかるように座り込むと、水溜りが赤く染まる。
「ん・・・・そろそろ、かし、ら」
顔の前に左手をかざしながら、自嘲と共に呟く。
傷口を押さえていたその手は既に血塗れで、今の自分は返り血と自分の血で全身真っ赤だ。
息は今までにないほど熱く乱れている。
酸素を求めようと呼吸を繰り返すが、喉元からこぼれてゆき失敗に終わっていく。
最悪の状況。
人形を持たない人形使い。
動く事もままならない重い身体。
指の隙間からこぼれてゆく、血。
「―――・・・・・・」
最悪の状況、なのに。
考えているのは自分の命の心配じゃなくて、もっと。
こうなる状況を作ってしまった、罪作りな男のこと。
私が望んで追いかけてきた、(私のことをどうとも思っていない、)あのひとのこと。
私が死んでも、(私があなたのことをどれだけ考えていたかも知らないで、)泣かないだろうあのひとのこと。
もとよりこんな関係だった。
そこに悔むべき箇所も、取り戻すべき失態もない。
何もできないからせめてと、この道を選んだのは私自身なのだから。
心残りがあるとすればただひとつ。
それは自分の力不足に他ならない。
勝手に追いかけて、ひとりで滑稽に踊って、そして最期は誰にも目を向けられず。
そして目的もただひとつだった。
私は彼に、○○に認められたいと思って、最初からそれだけで、
「・・・・・・ッ」
ふと、近づいてくる気配に口端を上げた。
「・・・見つかっちゃった」
仕留め損ねた残党が来たらしい。
少しくらい静かにしてほしいものだ、という願いとは裏腹に、バタバタと足音が大きく聞こえるようになる。
妖怪が近づいてくる。
光が殆ど差し込んでこないために、それらの表情はよく見えないが、きっと笑っているのだろうと予想する。
きっと、弱った私を見て、そして殺せるというコトが嬉しいのだろう。
「Good-bye, ・・・let's meet in hell.」
・・・最後に、さようなら地獄で会いましょうなんて恨み事を残して。
もう、どうにもならない事は分かっているけれど。
どうする事もできないのだから。
だから、すっと瞳を閉じた。
しかし、来るはずの衝撃はいつまでたってもアリスを襲う事はない。
不審に思ったアリスがゆっくりと瞳を開けると、そこにはさっきまで戦っていた妖怪たちの亡骸。
そして暗闇の中から、聞きなれた声が私の耳に届いた。
「―――・・・何を、やってるんだ」
その声の主に、アリスは思わず目を見開く。
「・・・意外。どうして、こんなところに」
そう言うと、彼は少し眉間にしわを寄せた。
何故かと思ったが、あえて口には出さなかった。
「そんなに意外か?」
「だって、○○が来るなんて、思わなかったもの」
ふふっと弱々しく途切れながらも笑うアリスに、○○がゆっくりと近づく。
そして、眉間にしわを寄せたまま、傷口にそっと手を添えた。
「・・・里の奴らがもう少しで来てくれる。そしたら治療できるからな」
「大丈夫よ、急所は外れてるし」
まあ少し、出血が多いけど・・・とアリスが笑う。
その顔に血の気はなく、『何が大丈夫なのか』と聞きたくなるほどで、
○○はその笑みを見るたびに胸を締め付けられるような感覚に、ぐっと手を握りしめた。
「・・・・・・どう、して・・・・・・」
「・・・○○?」
「どうして、お前は笑っていられるんだよ・・・!?」
『どうしたの?』とアリスは急に俯いてしまった○○の顔を覗き込もうとした。
しかし、それはアリスの首元に頭を埋めるようにして寄りかかってきた○○のせいで出来なかった。
「俺はお前を見つけた時、心臓が止まるんじゃないかと思うほどだったのに、今だって、」
ポツリ、ポツリと言葉を漏らす○○にアリスはじっと耳を傾ける。
「お前を失ってしまうんじゃないかと、」
「居なくなってしまうんじゃないかと、」
「なのに、お前は・・・笑って・・・ッ」
微かに肩を震わす○○の背になんとか手を回しながら、アリスは微笑んだ。
いつの間にか雨は止んでいて、同じように濡れていたはずの○○は温かく感じた。
「・・・ごめん、なさいね?心配かけて」
「・・・ゴメンじゃ、ねえよ」
顔を上げた○○と目が合う。
瞬間、アリスの表情は驚きへと変わった。
「○○・・・泣いてるの?」
「何で泣かなくちゃ、ならないんだよ」
「だって、涙・・・」
そう言って、アリスが○○の頬をゆっくりとした動作で拭う。
○○の頬には幾重にも水の流れた跡があった。
「・・・これは、雨だ」
○○がアリスの手を掴んで止めさせようとする。
けれど、アリスは止めようとはしなかった。
「・・・もう、雨は止んでるのに?」
「・・・っ」
「ありがとう、○○」
「!?」
・・・私の為に泣いてくれて。
私を想って泣いてくれて。
「・・・私、まだ夢じゃないかと思ってるのよ、だって、うれしいもの、」
でなければこれは死後の世界の幻覚か。
それほどに、○○がここに居てくれる事は得難い奇跡だったのだ。
「・・・○○、が、きてくれたって、こと」
会いたいと思った。
死ぬ前に、心の底から愛した人に会わせてほしいと、ただ願った。
無意識のうちに、祈っていた。
・・・それだけじゃない。
○○のあんな顔を見て、心配されて、その優しい言葉に、
なぜだかむねにわきあがるあたたかいもの。
・・・ああ、いとしいのだ、と。
私は本当に、このひとのことが―――
「大好き、よ・・・・」
そう微笑んだアリスが、ゆっくりと瞳を閉じた。
「・・・アリス・・・?」
ぱたりと話す事も、動く事もなくなったアリスに、○○は狼狽する。
まさか、という気持ちが沸き起こり、アリスの肩を強く揺すりながら必死で名前を呼んだ。
「アリス・・・ッ!!アリスーッ!!」
「五月蝿い」
「ふごっ!?」
刹那、○○の腹にドスッと突きが入る。
何事かと○○がアリスを見ると、不機嫌極まりない様子でこちらを睨みつけていた。
「少しぐらい寝かせなさいよ」
驚きを隠せない○○は、あんぐりと口を開けていて。
「な・・・!?死んだん、じゃ・・・・」
「勝手に殺さないで頂戴」
「生憎、まだ死んでなんてあげないから」
貴方に泣かれてまで、死ねるわけ無いでしょう?
だって心残りで
安心してあの世なんかいけないわ
貴方の泣き顔なんて
見てしまったら もう
(・・・勿体無くって何処にも逝けやしない)
10スレ目>>694
───────────────────────────────────────────────────────────
私は今日紅魔館に来ている、もちろん本を借りる為だ
いやいや、魔理沙と違って私は借りたものは返すわよ?
「んー・・・あれ?」
「どうしたのアリス?」
そんなこんなで図書館で物色していると、見慣れない奴を見かけたのだ
「アップルティーです、パチュリー様・・・・・・」
机に紅茶とシフォンケーキ、そして彼は私を見つめた
「ええと・・・」
「彼女はアリス、私の友人よ」
「そうでしたか・・・此処で執事をさせてもらっている○○というものです」
「へぇ・・・改めて、私はアリス、アリス・マーガトロイドよ」
「よろしくお願いします・・・それでは仕事に戻ります」
お盆だけ持って彼は退室した
「ねぇ、彼って人間?」
「いえ、吸血鬼の出来損ないよ」
「へえ・・・」
そのときは特に気にも留めなかった
ちょっといい男ぐらいに思ってたんだけど
レミリアが気に入った男なんだから、何かあるんだろう、それぐらいの認識
そんな考えもすぐに何処かへと、私は読書に意識を戻すのだった
「はぁ、すっかり遅くなっちゃった」
本を読んでいるといつの間にか夜
パチュリーと一緒に本を読んでいると時間間隔がなくなっちゃうわね
「おや?アリスさんお帰りですか?」
「あら○○さん、私はもう帰るところよ」
「玄関まで遅らせてもらいます」
「ありがと」
相変わらず長い廊下、図書館から玄関まで十分近く掛かるのではないか、そういう長さだ
「そういえば○○さんはどうして紅魔館に?」
「どうして・・・そうですね、簡単に説明すると吸血鬼になって行き場がない私を、レミリア様が保護してくれたんです」
「へえ・・・え?貴方ってレミリアから派生した吸血鬼じゃないの!?」
「いえ、半端な方法で吸血鬼になったもので・・・半人前以下です」
たぶん、私が彼に興味を持ったのはこの瞬間ではないだろうか?
幻想郷に存在する唯一の吸血鬼、スカーレット
しかし此処に、スカーレット姉妹以外の吸血鬼が居る、それだけで彼の存在は重いものとなる
「アリスさん?もう玄関ですよ」
「え?あ、ああ・・・」
ちょっと色々考えてしまった、ボーっとするにも程がある
「あ、ありがとう!それじゃあおやすみなさい」
彼女は危ない足取りで闇に溶けていった
「大丈夫かな・・・」
「何が大丈夫なのかしら?」
「うひゃぁ!?さ、咲夜さん」
いつの間にか背後にいるのは慣れたけどいちいち耳にふーってしないでください
「うふふ、可愛いのね・・・このあと」
「あ、アリスさんを送り届けてきますねっ!」
脱兎の如く、逃げましたよ
以前あんな感じで誘われてホイホイついて行っちまって・・・
まぁ忘れよう、世の中にはそういうことのほうが多い、はずだ
「う~ん」
吸血鬼になるには吸血鬼にかんでもらうか、それ以外の方法で
「アリスーマエヲミテー」
「へ?きゃっ!?」
考え事をしていたせいで思いっきり太い枝におでこをぶつけてしまった
「いたた・・・」
驚いてついでにこけてしまった、お尻が痛い
「アリスさん!大丈夫ですか!」
「○、○○さん!?どうして」
「いや、うわのそらだったので、いちおう・・・心配で・・・」
差し伸べられた大きな手、一瞬躊躇って、掴んだ
彼の手が暖かかったからだろうか?なぜか私は恥ずかしくなった
こけた事もおでこをうった事も、なぜか無性に恥ずかしくなった
「あ、ああありがとう!それじゃあ」
彼女は俺の前からまさに脱兎の如く逃げ出した
でもすぐに何かにぶつかってうめく声が聞こえた・・・もうなんだかな
~後日~
「お邪魔するわ」
「あらアリス、またきたの」
「今日はちょっとね・・・」
「?」
館内をうろうろ、うろうろ
「何処にいるのよ・・・」
うろうろ、きょろきょろ
ただでさえ広い、そして部屋数も多いから探すのは大変だ
「吸血鬼なんだから日光が当たらないところにいるはずよね」
となると必ず館の中にいると思うんだけど
「う~ん・・・」
とりあえず上海と手分けして探す事にした
「はぁ・・・これで今日の仕事は終り・・・明日の分まで・・・いや止めとこう、明日出来ることは~って言うし」
「ミツケター、○○ミツケター」
「ん?人形・・・・・・・確か、何処かで見たような・・・」
「アリスー○○ミツケター」
「ああ、アリスさんの右斜め上にいた人形ちゃんじゃ無いか」
「グッドモーニング○○ー」
「え?ああ、グッドモーニング」
ずいぶんと愛嬌のある人形だ、可愛らしい事この上ない
「○○さん?」
「アリスさん、おはようございます」
「あ、おはようございます・・・ちょっとお時間いいですか?」
「?」
その後俺は吸血鬼になった経緯と方法を根掘り葉掘り聞かれた
根掘るって解るけどよ、葉を掘ったら裏に(ry
「じゃあまだ吸血鬼の能力を手にしたわけではないのね?」
「一応今は腐敗が終わって人間と同じぐらいにはなりました、でも身体能力などはまだ・・・治癒は少々」
「へぇ・・・じゃあ今は欠点だらけって事ね」
「はい・・・これから欠点を補うほどの能力がつけばいいのですが」
今のところ吸血鬼の欠点だけを持っている感じだ
個人的には怪力とか霧になるとかは便利そうなんだけども
「ふぅん・・・まぁつまりホントに出来損ないだったのね」
痛いところをつかれた、まったく持って反論できないのが悔しい
「まぁ最初から完璧な吸血鬼なんていませんよHAHAHA」
「ふふ、そういう事にしておくわ」
彼の手
暖かい手
大きな手
あのときの暖かい手の感触
なぜかドキリとしてしまった、なぜ?
「・・・アリスさん?」
「え?あ・・・」
いけない、私ったら彼の事ばっかり
「そ、そろそろ帰るわね」
「あ、はい、お送りします」
長い廊下、廊下の半分には日が当たらないように設計されている
当然彼は影を歩く
そうか、今は昼だから、玄関まで・・・か
そうよね、灰になっちゃうもんね
「ねぇ○○さん」
「はい、なんでしょう」
「いま・・・その・・・付き合ってる女性はいたりする?」
「い、いえ・・・いませんが」
「も、もしかして男s「男もいません!」
そうかそうか、この紅魔館で紅一点?でありながらフリーなんだ、そうなんだ
「じゃあ・・・私と付き合ってみない?」
「え?・・・」
「・・・」
「じゃ、じゃあ今度までに返事を頂戴ね!」
「ちょ、ちょっと待ってくださ・・・あ」
「ふふ」
彼女は既に日の光の下にいる
危うく灰になるところだった、つまりまんまと逃げられたわけだ
「またね~」
ひらひらと、陽気に手を振るアリスさん、結局声をかける間もなく、視界から消えてしまった
「・・・人生初の告白(される側)が・・・これか」
影の中で少し明るい気分になった
しかし彼女の言う次が気になるのも事実であった
「い、言っちゃった・・・」
心臓がバクバクと、大きな音を立てて鼓動を刻む
震えるぞハート!燃え尽きるほどの・・・尽きちゃ駄目だ
「はは、言えたんだ」
ほとんど勢いで、それでも言えた
意気地なしの自分が、言う事が出来た
ああ、日の光ってこんなにも・・・眩しかったのか
何となく、とても、機嫌がいい
そうだ、今日ぐらいは茶菓子を買って行って上げようかしら?
不思議と不安はない、拒絶が怖いとか、そういう気持ちは浮かばない
「何でかしら?・・・いい研究内容だわ」
(何故私は、こんなにも強気なのか?)
それはきっと恋の魔法
何処かの白黒のお株を奪わんばかりの・・・恋の予感
「次はいつ、紅魔館に行こうかしら?」
「彼女はいつ、紅魔館に来るのか?」
10スレ目>>731
───────────────────────────────────────────────────────────
思えばあれはただの私の気まぐれだったのに。
なんでこんなに、胸が苦しいのだろう?
私の家に突然現れ
[貴女の事を高名な人形師と聞いた。 弟子にしてくれないか?]
という紙キレをいきなり突きつけてきた男。
幾度か断っても紙切れを取り下げることはなく、とうとう私が根負けしてしまった。
何故紙切れなの? という問いにだけ、彼はその紙切れの裏に
[私は喋れないんだ]
とだけ書き、悲しそうに微笑んだ。
それが、全ての始まり。
口がきけなくても、夢はあった。
――意のままに操れる人形を作り、子供達を楽しませたい
喋ることができないのを筆頭に、音楽も試したがてんでダメだった。
昔から裁縫等の細かい作業は割と得意だったので、人形なら、と思い立ったのだ。
腕のいい人形師はいないかと方々を聞いて(見せて)まわり、ようやくそれらしき人物の話を聞けることが出来た。
まるで魔法のように人形を操る人物……アリス・マーガトロイド。
里から少し離れた魔法の森とよばれる奥深い森に居を構えているという。
居ても立ってもいられず、馬を借りて森へと駆けた。
……途中で雨が降ってきたのは予想外だったが。
"必需品"は雨に濡れないように油紙を被せてある。問題はないだろう。
教えられた道とも言えぬ道を走ること半刻ばかり、それらしき家を見つけた。
幸いなことに明かりも着いている。
少々不躾だとは思っていたが、この機を逃すわけにもいかない。
前準備としていくつかの事を紙に書き留め、呼び鈴を鳴らす。
「どちらさま?」
戸を開けて現れたのは私より年下と思えるくらいの少女だった。
相当面食らったが、すぐに冷静を取り戻す。この子はアリスとやらの弟子かも知れない。
[失礼だが、貴女はアリス・マーガトロイドで間違いないかな?]
とりあえず最初の紙切れを差し出す。
喋れない私はこうしてコミュニケーションをとる他ないのだ。
「え、ええ……そうだけど、それが何か?」
少々驚いた顔で私の顔を見る。それにしてもやはりこの少女がアリスだったのか。
構わずに次の紙を差し出す。
[貴女の事を高名な人形師と聞いた。 弟子にしてくれないか?]
その紙切れを見るなり、彼女は若干の溜息をつく。
「貴方には悪いけれど、弟子を取るつもりはないのよ。面倒だしね」
……予想していたとは言え、さすがにこうもハッキリいわれるとは。
それでもあきらめるわけにはいかない。
差し出した紙も、下げない。
「だから嫌だって、言ってるじゃない。それに、人形師になって何をするつもりなの?」
しまったな、それの答えは用意していない。
ちょっと待っていろ、とジェスチャーで示し、紙に筆を走らせる。
[子供達を、喜ばせたい]
急いでいたせいで随分汚い字面になってしまったが、読めない程でもない。
その紙切れを示した後、今度は先ほどの紙切れを半分破り
[弟子に、してくれないか?]
再度、突き出した。
元々手が器用だったせいもあってか、彼はめきめきと上達していった。
最初は針の穴に糸を通すことすら苦心していたのに。
ちょっとしたコツや素材の選び方等も教えると彼は熱心に聞いて、そして吸収してくれた。
弟子を取るのは今までにその技術を悪用しようとするものがいたから断っていたのだけれど。
彼はどこまでも純粋だった。
私が魔法使いだと知った時も
[すごいな、空とか飛べるんだろ?]
と書いた紙をくれた。
普通の人間ならもう少し驚いたり怖がったりするものなのに、ね。
その時からかな、少しずつ彼が気になり始めた。
もう私にとってはルーチンワークでしかないような作業……彼もとっくにマスターしているはずの事ですら
彼は真剣そのものの表情で取り組む。
[弟子なんだから、これくらい]
そう言いながら、身の回りの世話も全てやってくれた。
割と小奇麗にはしていた家ではあったけれど、前にも増して綺麗になっていった。
仕事の合間を見つけては掃除をしたり、簡単な日用品を作ったり、修繕したり。
そのくらい私がやるわ、と言っても
[いいから、いいから]
と決して譲りはしなかった。
あれから、どれほどの月日が過ぎただろうか。
時々家を空ける彼女に代わり、人形師としての腕を磨く片手間家事をする。
日々をいくつも積み重ねたのち、私はようやく彼女のお墨付きが出る程度の腕前にはなった。
曰く、「もう一人で動いても問題はないんじゃないかしら」という程には。
さすがに魔力なんてもんは持ち合わせていないので、人形を喋らせたりなんて芸は出来なかったけれど。
彼女と過ごす日々は楽しかった。
弟子なんだから何でも言いつけてくれと言ったのにあくまで対等に接してきたのにはさすがに驚いた。
結局こっちから色々やってしまっているのだが。
私を弟子にしたのも何とも変な理由だった。理由を尋ねた時も
「その体格で、子供達を楽しませたいなんていうものだから……面白くって」
そうしてひとしきり笑った彼女はとても眩しかった。
さて、今アリスは家を空けている。近くに住んでいるらしい知り合いの魔法使いに薬剤を貰いに行ったようだ。
恐らく、あと数時間は戻ってこないだろう。長くて半日か。
……チャンスがあるなら、今か。
「ふぅ……ただいま。魔理沙ったら散々私の事からかって……
○○? 外にいるのかしら」
魔理沙から目的のモノを貰い、揚々と帰って来た。
普段のように長引きはしなかったが、色々とからかわれた。
彼に愚痴りながらまたいつものように人形でも作ろうと思った。
家の中にはいる気配がしなかった。
外で野良仕事でもしているのかと思い、ぐるっと回ってみてもいなかった。
入れ違いかと思って家へ戻っても、彼はいなかった。
変わりに見つけたのは、彼がいつも座っていた作業机の上に乗せられたメモだった。
[ええっと、我が師ことアリス・マーガトロイドへ。
今まで長らくお世話になりました。
貴女の言う、一人で動いても問題ない、がどの程度のものなのか少々試してみたく
誠に勝手ながら暫くのお別れです。
道中が無事でありますよう
頭の片隅ででも祈ってくれればこれ幸い。
追伸:旅に出るにあたり、いくつかの食料を拝借致しました。申し訳ない。
北の畑を上空から眺めて下さい。最後のメッセージです。
それでは、お元気で。 ○○]
「ちょっと、何よこれ……」
勝手に出て行っていいなんて言った覚えはない。
彼の腕は確かに上等だけど、まだまだ教え足りない。ツメも甘い。
安楽椅子の手摺の調子が悪いから直してもらわなきゃいけないのに。
まだ畑の取り入れも終わってない。私一人じゃ重いから彼には居てもらわないといけないのに。
まだ、まだ……
気づけば、涙が頬を流れていた。
それと同時に自分の気持ちに気づいてしまった。
追いつけばまだどこかを歩いているかもしれない。
慌てて空へと飛び上がる。彼のメモを握り締めたまま。
そこでふと下に目線を落とす。
北の、畑。
いくつかの作物を刈り取った後に残された文字が、見て取れた。
[愛してる]
そして「る」の場所にはまだ刈り取りをしている○○の姿が。
いつもなら後数時間は帰ってこない。そうタカをくくっていたのだろう。
「あの、馬鹿……!」
(こんなもんかなぁ……ちゃんと字になってるよな。多分)
満足気に腕を組み、頷く。
(さて、そろそろ行く、か)
彼女ともう会えないかも知れないのはとても寂しい、が
いつか戻ってくるつもりではある。
立派になった自分を見てもらうために。
荷物を肩に背負ったあたりで後ろに気配を感じた。
「アンタね……
そういうことは、もっと早く言いなさいよ、この、馬鹿ッ!」
蹴られた。
受身も何も取るまでもなく、畑の剥き出しの土の上に倒れる。
あれ、なんでこんな所にいるんだ……まだ魔理沙の家にいるはずなのに。
うわ、しかも私のメモ持ってるし。
何か泣いてるし。何かあったのか……?
それらを尋ねようとメモ帳とペンを手にしたところで
上からアリスが飛び乗ってきた。
「言いたいことだけ言って逃げるなんて卑怯よ!
私の気持ちも知らないで!
大体、興行くらいなら麓の里で十分できるじゃない!
私は貴方が好きなの!
私は、アナタと……○○と、もっと一緒にいたいの!」
それだけ一気に言うと、アリスは私の服に顔を埋めた。
どうやら泣きじゃくっているらしい。
本来ならば言葉でもかけたいが、喋ることができない私にはどうしようもない。
優しく抱きしめることで、彼女が落ち着くまで待った。
そのまま起き上がる。アリスは丁度私の足の間に座って私にもたれている。
改めてペンと紙を握り、先の返事を書く。
[このまま一緒にいたら、私が気持ちを抑えられそうもなかったから]
だから出て行こうと、思った。
[貴女は私のことなんてさして気にもしていないと思っていたんだが]
これはさすがに小突かれた。「女心が分かってないわ」との説教つきで。
[すまない]
頭を下げる。
「謝らなくてもいいわ……こうして追いつくまでもなかったけれど、また会えたのだし」
そうして涙目で笑顔を浮かべる彼女はいつにもまして綺麗に見えた。
[それで、今後のことなのだが]
彼女も私を好きだと言ってくれた。
それならば、家を出なくても問題にはならないということだろう
「どうしたの?」
この一言を書いてもいいものか、逡巡した後に。
悩んでも仕方ない、と一気に書き綴る。
[君さえよければ、また一緒に暮らしたい]
そのメモを破り、彼女の手に持たせる。
[ダメかな?]
渡したメモにそう書き足す。
「そうね……返事は……」
言うなりペンをひったくられる。
そして書かれた文字は
[いいわよ、未来の旦那様]
驚きに目を見張る私を見て彼女は微笑み、
そのまま唇を合わせた。
「さ、帰りましょ、私達の家に」
>>うpろだ540
───────────────────────────────────────────────────────────
「それにしてもあのときの霊夢の落ちこんだ顔は忘れられそうにないぜ」
「……魔理沙、その60ガバスっていうものを賽銭箱に入れたのはあなたなんでしょ?」
「そのとおりだぜ。いやぁ、パチュリーにも見せたかったぜ。なぁ、アリス?」
「私に話をふらないでよ」
「……本当にあなたは毎度毎度お騒がせなんだから」
日の光の入らないヴワル図書館。
今、この図書館に居るのは四人の少女達と一人の青年、つまり俺である。
今日も今日とて魔理沙の強奪劇に有無を言わさず駆り出された俺はいつものように紅茶をご馳走になっている。
まあ、ここへ連れて来られるのはいつも無理やりだがそれでも悪いことばかりとは思えない。
まず第一にここへ来ればいろいろな本、それも外の世界ではお目にかかれないようなものが読める。
次に咲夜さんの淹れてくれたおいしい紅茶が飲める。
そして何より、アリスと必ず会うことができる。
正直に言おう。俺はアリスに惚れている。
いわゆるベタ惚れというやつだ。
なぜ俺が彼女に惚れたのかは彼女との出会いから説明しなければならんので今は割愛させていただく。
まぁそれはおいといて、俺と彼女との仲は客観的に見てもそれほど悪いものではないと思う。
だがそれ以上は進展していない。
というのは、俺に後一歩踏み出す勇気が足りないんだ。
そう、俺は今の関係が崩れるのを恐れている。
もしアリスに拒絶されてしまったら。もしそれまでのように友人としても付き合えなくなってしまったら。
そんなことばかり考えてしまう。
ああ、せめて何かチャンスがあればなぁ……。
「ん、それじゃあそろそろ魔導書を取りに行くか」
「ちゃんと返しなさいよ」
「大丈夫。後できっと返すぜ」
「全く……、少しはアリスや○○を見習いなさい」
「そうね。少しは返す努力をしたらどう?」
「はいはいっと。じゃあ先に行ってるぜ。また後でなパチュリー! ○○!」
「待ちなさい! 魔理沙!」
「小悪魔、魔理沙が必要以上に借りていかないように見張ってなさい」
「はい、パチュリー様」
そんなかしましい会話とともに魔理沙、アリス、小悪魔の三人の姿は見えなくなった。
と、ふいにパチュリーが口を開いた。
「○○、ちょっといいかしら」
「うん? どうした?」
「あなたってアリスが好きなのよね?」
「なっ……! くぁwせdrftgyふじこ!」
彼女から放たれた言葉は俺の予期しなかったものだった。
ていうか何故にあなたが俺の秘めたる思いを知っているんで!?
「あなたのアリスへの態度を見ればすぐにわかるわ。あれでわからないのはよっぽど鈍感なやつだけよ」
「う……、その……」
「それで本題に入るわけだけど、どうして彼女にその思いを伝えないの?」
「えっと……、それは……」
「今の関係が壊れるかもしれないから?」
ガタッ!!
核心を突く言葉に思わず立ち上がってしまった。
「そう、なるほどね。だったら一つ言わせてもらうけど、あなたが思ってるほどアリスは弱くはないわ。
もし彼女があなたの申し出を断ったとしても、あなたが態度を変えなければ今のままの関係、友人としての関係はきっと続くわ」
「けど……」
「少なくともアリスとの付き合いは私の方が長いわ。だからまあ、私を信じて突撃してきなさい」
そう言い、彼女はカップに口をつける。
「……本当に信じてもいいんですか?」
「ええ、保障するわ」
「わかりました。俺は「ストップ、その前にこれをあげるわ」
そこにあったのは一冊の本だった。
「えっと……、初心者のための恋愛バイブル?」
「それを読んで少しは勉強しなさい」
「……」
いくら何でもこれはないだろう……。
「不満そうね。せっかく私があなたのためと思って用意したのに」
彼女の方を見るとこれ以上ないくらいに微笑んでいた。ただし目は全く笑っていなかったが。
「い、いえ……そんなことありません!」
「そう、なら頑張りなさい」
その後、家に帰ってから俺はその本を読みふけった。
「何よ……、これ……」
顔が熱い。きっと私の顔は真赤になっているだろう。
今、私が見ているのは一冊の雑誌。しかも外の世界のものである。
そこにはデートではどうすればいいとか、彼氏へのプレゼントは何がいいか、などが書かれていた。
そしてさらには口では言えないような過激なことも……。
私がこんなものを持っている理由……、それは魔理沙と別れて魔導書を探している途中に小悪魔から渡されたからだ。
その時の彼女は満面の笑顔でこう言った。
『これで○○さんとの仲もきっと進展しますよ♪』
はぁ……、どうして私が○○のことが好きだとわかったのだろうか。
このことは魔理沙にも言ったことないのに……。
「うう……」
いけないいけない。さっきのことを思い出したらまた顔が……。
でも、小悪魔が応援してくれているのは事実よね。
よし! この本の知識を借りて○○ともっと仲良くなろう。
そしてあわよくば恋人に……。
「よーし! やるわよ!」
あれから俺はパチュリーにもらった本を読み、五つの必勝法を編み出した。
まず一つ目は、デートで仲を進展させるべし、だ。
ということでさっそく誘ってみることにした。
とはいえさすがに二人でデートに行こうと言っても断られるのがオチである。
だから彼女には薬草を採りに行くから手伝ってくれと言ってある。
まあ、一応採りに行くから嘘は言ってない。
よっしゃ! 彼女とのデート、絶対に成功させるぞ!
それからしばらくしてアリスがやってきた。
そして俺の必勝法、二つ目と三つ目が炸裂する!
まずはいつもと違う服を着てくること。これにより今日は特別な日だと印象づけるのだ。
「おはよう○○。あら、今日はいつもと少し感じが違うわね。そういうのも結構似合ってるわ」
よっしゃ! 大成功!
わざわざ香霖堂まで行って買ってきた甲斐があったぜ。
そしてすかさずもうひとつを発動!
「ありがとう。いやぁ、今日のアリスもかわいいね。そのカチューシャもよく似合ってるよ」
「お世辞なんか言っても何にも出ないわよ」
「お世辞なんかじゃないさ。俺がそう思ったから言ったわけだから」
「そ、そう……。あ、ありがとう……」
さりげなく女性の容姿を褒めるべし。
こっちもなかなかの成果だな。
「そ、それじゃ行きましょ」
「おう」
こうして俺とアリスの薬草探し、もといデートが始まった。
ああ、かわいいなんて言われちゃった……。
もう嬉しすぎて死んじゃいそう。
それにいつもと違う服の○○もカッコいい……。
ああ、今日は本当にいい日だなぁ。
て、呆けてる場合じゃないわ。今日のような日のためにいろいろと仕込んできたんだから。
しかしまさか○○の方から二人きりでデート……、じゃなくて薬草採りに誘ってくれるなんて。
アリス! 今日というチャンスを最大限に生かすのよ!
「ふぅ、結構腰にくるな」
と、薬草を採っていた○○が立ち上がりながら言う。
さっそくチャンスね!
「ここは私にまかせて。上海!」
「シャンハーイ」
上海の持つ剣は次々と薬草を刈っていく。
「アリスの人形はいつ見てもすごいなぁ。うちにも欲しいぐらいだよ」
「そう? じゃあ今度作ってあげようか? 最も自律型みたいなのは無理だけど」
「え、でも何か悪いなぁ」
「いいのいいの。好きでやってることだから」
「そう? じゃあお願いできるかな」
よし! これで○○とまた会う口実ができた。
いつもは魔理沙のつきそいぐらいでしか会えないからなぁ。
もっと会えれば、あんなことやこんなことを……。
「じゃあ、今度はあっちをお願い」
「え? う、うん。わかったわ」
あ、危なかった。つい思考がトリップしてしまった。
ちゃんと気をつけないと……。
「ふぅ、これだけ集めれば十分でしょ」
「いやぁ、助かるよ」
薬草はなんだかんだでお金になるからな。
そう言えば魔理沙にも何度か手伝ってもらったっけ。
と、もう昼過ぎだな。
よし四つ目を発動させるときだな。
「えっと、アリス?」「その、○○?」
と、アリスが言った言葉とかぶってしまった。
「じゃ、じゃあアリスから先に言って……」
「○○の方こそ先に……」
「「……」」
「ねぇ、同時に言わない?」
「そうね、そうしましょ」
「「せーの」」
「そろそろお弁当を食べないか? 俺が二人分用意してきたからさ」
「そろそろお弁当でも食べましょ。私が二人分用意してきたから」
「「……」」
おい、内容もかぶっちゃたよ。
これじゃ四つ目の必勝法、男は黙って料理で勝負、の効果が発揮できないじゃないか!
でも、アリスの手料理も食べたいし……。
「「ぐぎゅるー」」
と、何やら変な音が二つ聞こえた。
「……とにかくお昼御飯にしましょ」
「そ、そうだな……」
うう、アリスにあんな音を聞かせてしまうなんて……。
「うん、この卵焼きおいしいね」
「ありがとう。○○のつくったハンバーグもとってもおいしいわ」
「いやぁ、頑張って作ったからね」
結局、二人で分け合って食べることにした。
俺の料理も褒めてもらったし、アリスの手料理も食べられたし本当に最高だ。
まあ四人分あるわけだからかなりの量が余ってしまうが……。
「ん、もうお腹いっぱい。ごちそうさま」
「おそまつさまでした。私ももういいわ」
「余ったのはどうする?」
「んー、二人で分け合えばいいんじゃない?」
「そうだな」
それから二人の間に少し会話がなくなった。
よし、これなら最後の必勝法を……。
いい雰囲気になったところで愛の言葉をささやくっていうのを……。
あ、愛の言葉……?
しまった!? 必勝法を考えるのに夢中で告白の内容まで考えてなかった……。
え、えっと……。ど、どどどどうしよう……!?。
何か、何か言わなくちゃ! せっかくのチャンスなんだから……。
こんなにいいチャンスもう二度とないかもしれないんだぞ!
せっかくパチュリーも手伝ってくれたんだぞ!
こうなったら男○○。一世一代の大勝負に出る!
「あー、アリス? ちょっと話があるんだが……」「○○? ちょっといいかしら……」
「「……」」
ま、またかぶってしまった……。
け、けど言わなきゃ! 何か言わなきゃ!
テンパッてて何言えばいいかわからないけどとにかく言わなきゃ!
「アリス!」「○○!」
またかぶった。けど今の俺にはそこまで気にする余裕はない!
「俺はアリスのことが好きなんだ!」「私は○○のことが好きなの!」
「「……え?」」
しばらく二人の間に何とも言えない空気が流れる。
「え、えっとつまりその俺達は……」
「そ、そうね。要するに……」
「「最初から両想いだった?」」
何なんだろう今のこの気持ちは?
告白が成功したのに、こう何か複雑というか。
あそこまでテンパった意味はなかったなぁっというか。
まあ、嬉しいに決まってはいるんだが。
と、そんなことを考えていると彼女が話しかけてきた。
「ね、ねぇ。う、嘘じゃない……よね」
「あ、当たり前だろう! 俺はアリスが好きなんだ」
その言葉に俺は精一杯肯定の意を示す。
「う、うん! 私も!」
アリスは本当にうれしそうに笑いながら答えてくれた。
それにつられて俺も微笑んだ。
うん。とりあえず今はこの喜びをかみしめていよう。
そして、俺に踏ん切りをつけてくれたパチュリーにも感謝を。
「うまくいきましたね、パチュリー様」
「そうね」
暗闇の中、パチュリーと呼ばれた少女は答えた。
そこには遠見の魔法で映し出されたアリスと○○の姿があった。
「それにしても、慌てる二人を見るのは楽しかったなぁ。さらにこのネタを新聞へ提供すれば礼金もたんまり……。じゅるり……」
「本当にうまくいって良かったわ。そう、誰もが納得する形で……」
「これで不安要素の芽はつぶせましたね」
「ええ。これからはゆっくりと私の愛を告げていくだけ……。そう、魔理沙は私だけのモノよ……。ふふふ……」
広大な図書館に魔女の妖艶な声が響き渡る。
11スレ目>>18
───────────────────────────────────────────────────────────
「んー」
外に出て軽く身体を伸ばす。
すっかり弱くなった秋口の日差しが、やさしく私をお出迎え。
今日はハロウィン。
外来のイベントなのだが、寺子屋では子供たちに仮想させて、ご丁寧にも一軒一軒回るらしい。
愛しい彼は、寺子屋の先生の真似事をやっているので、
私ことアリスも、彼が引率して来るのに合わせて、こうやってお菓子作りをしているのだ。
美味しいお菓子を食べさせて、子供たちに「人形遣いのおばさん」などと言われないようにしなければ。
「だーれだ?」
不意に、視界が暗くなる。
こめかみには、筋肉質のごつごつとした手の感触。
この大きな手は――。
「○○?」
「正解。もう少し声色を変えるべきだったかな」
両目にかかる手をゆっくり外して振り返ると、そこには、微笑を浮かべた彼の姿があった。
「どうしたの? こんな時間に。子供たちが来るのは夕方じゃなかった?」
「ああ。でも一応、道の確認をね。いざ、という時に焦らないようにしないと。
それに――」
「それに?」
「なんとなく、アリスと会えるような気がしたから」
顔を朱色に染めながら、気障を言う彼。
そんな言葉を聞かされたら、私まで照れてしまう。
「も、もう! バカ! それに私は怒っているんだからっ!」
プイッ
頬を膨らませて抗議する。ついでに横も向いてやった。
あんまり、照れた顔は見せたくない。
だけど、彼は、
「どうしたんだー、ア・リ・ス」
頬をぷにぷにとつついてくる。
「本当は怒ってないこと、わかっているよ」とでも言わんばかりに。
そんな彼の手を振り払って、一言。
「Trick or Treatって言わなかったでしょう? いきなり悪戯なんて、ルール違反よ」
「それはすまなかった。では、改めて。
Trick or Treat」
「え?」
しまった。
まさか、こう返されるとは。
今の私の顔はきっと、ぽかん、としているに違いない。
それもそのはず。
パウンドケーキはさっきオーブンに入れたところだし、もう作ってあるクッキーはテーブルの布巾の中。
これからもう一踏ん張り、と思っていたガレットデロワは、まだ生地を寝かせたまま。
つまり、お菓子なんて持ってない。
「あ、あの――」
「ふふふ、持ってないようだね。じゃ、遠慮なく悪戯しようかな。
さあ、目を瞑って」
ぎゅっと目を瞑る。悪戯好きな彼のことだ。何をしてくるか、予想がつかない。
カシャッ カシャッ
落ち葉を踏んで、彼が近づいてくる音がする。
きっと、もう唇が触れられるくらい。
彼の吐息が、カールした前髪をそっと、靡かせた。
「――っ!」
手が、首筋にかかる。
も、もしかしてキス!? もしかしてキスなの!?
彼の両手が、うなじを撫でて――。
「ひゃん!」
肩を、揉みだした。
「アリスのことだから、きっとケーキとか力の要る洋菓子作ってたんだろう?
やっぱり、相当凝ってるよ。無理しないで欲しいな」
「あ、あふう、そ、その……」
「はい、これで終わり」
最後に軽く肩を叩くと、揉むのをやめる彼。
うう、なんだかさっきから見透かされている。
ちょっとでも、逆襲したいな。
そう思っているところに、天啓が閃いた。……これならば、きっと。
「―― ― ――」
「おいおい、道の下見に来た俺が、お菓子なんて持っている訳ないだろう。
はいはい、悪戯を受けますよ、お姫様」
茶目っ気たっぷりの彼の言葉。
ならば、遠慮なく。
「じゃあ、目を瞑ってくれる?」
「ん。こうか?」
私より頭一つは大きい彼が、目を瞑ったことを確認する。
うん、大丈夫。
ゴクリ
一つ、唾を飲み込む。
そして。
彼の首に両手を回すと、一気に唇を奪った。
「んんっ! ア、アリスっ!」
「じゃ、じゃあ、夕方には待ってるからっ!」
そのまま、玄関のドアを開けてバタバタと家の中に入ってしまう。
頬が火照り、心臓が早鐘を打っていた。
恥ずかしい。
自分は、あんなに大胆だっただろうか。
窓枠に肘をついて、紅潮した頬を冷ましながら彼を見ていると。
彼は、呆然と唇に手を触れ、その後、こちらを振り返りながら村の方へと去っていった。
彼は、気がついていただろうか。私がその言葉を放った時点で、このことは確定事項だったと。
それは、魔法の言葉。
「Trick and Treat(いたずら、そして甘い口づけ)」
11スレ目>>73
───────────────────────────────────────────────────────────