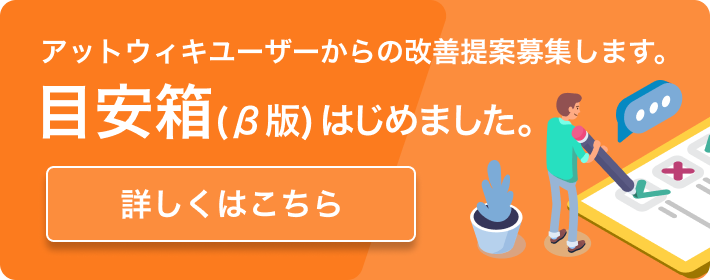日は天頂をわずかに過ぎた頃。
時折吹く柔らかな風。
細雪の如く舞う桜が雅な境内。
春先の日差しが心地よい。
ここ博麗神社の縁側では、真昼間から酒宴が催されていた。
「……というわけなの。酷いと思わない?」
「ハイハイハイ、そうね」
博麗の巫女はやる気のない相槌を打ち、紫様から視線を逸らすと、やれやれと嘆息した。
うんまあ、朝にいきなり訪ねてから今までずっと付き合わされてきたのだから、彼女がそうなるのも無理はないだろう。
私としても主に代わってすまないと言うしかない。
「あ~……まあ、あんたらがどこで酒盛りをしようが、私が迷惑を被らない限り何も言うつもりはないんだけどさ」
「あら心外ね。せっかく美味しいお酒を持ってきてあげたのに」
「酒だけ置いてとっとと帰れ」
「それこそ心外だわ。
私はここに花見にかこつけて愚痴を言いに来てるんだから、そんなことするわけないじゃない」
ここに来た目的を恥ずかしげもなく言い切る紫様。
本音を隠しもしないところを見るに、相当酔いが回っておられるようだ。
紫様は時折素面ででもこういう身も蓋もないことをおっしゃることがあるが、今回は深酒の結果だろう。――おそらく。
博麗の巫女は頭痛がするのか、しきりに眉間を指で揉んでいた。
私が彼女と同じ立場だとしたら、同じようになっていただろうことが予想できるから、素直に同情する。
紫様の突拍子もない行動は今に始まった訳ではない。
私たちがここにいる発端は、マヨヒガの縁側で自棄酒をかっ食らっておられた紫様の思いつきだった。
突然――
「花見にいくわ」
と宣言された。
身構える暇もあればこそ。
あっさりスキマに吸い込まれた私たち。
次の瞬間、目の前に広がっていたのは、見慣れてはいけないのに何故か見慣れてしまった場所――博麗神社だった。
博麗の巫女に事情を説明される紫様。
勿論○○と喧嘩してしまい、その愚痴を言いに来たなどとは言わない。
ただ、花見に来たとだけおっしゃられていた。酒の入った徳利をユラユラと揺らしながら。
博麗の巫女は紫様の発言に裏がありそうな気配を察していた様子だったが、表立っては何も言わなかった。
というか、むしろ――
「おっけー」
酒の魔力に自ら誤魔化される始末。
これにはツッコミを入れるべきか、それとも彼女の性質を知った上で、手玉に取った紫様を讃えるべきか私も悩んだ。
そうして始まる酒宴。
橙は開始早々に酒精の強いものをカパカパ鯨飲し、早々に酔いつぶれてしまっていた。
ある意味これは自棄酒をかっ食らう紫様への正しい対処方法かもしれない。
少なくとも紫様の口から延々の溢れてくる不毛な愚痴を聞かずに済むのだから。
一方の博麗の巫女は始まってしばらくして、しまったという顔をしていた。
紫様が何しに酒を持って来たのか理解したようだ。
だがすでにその後悔は手遅れだった。いや、手遅れだから後悔というのだけれども。
大量の酒を周囲に侍らせ、紫様がすぐ隣に陣取った状態ではとてもではないが逃げられそうになかった。
こうして博麗の巫女は今の今まで、ぐだぐだとくだを巻く紫様の相手をしていた。
そして私は何をしているかといえば、紫様の相手を博麗の巫女に任せて、横で二人の様子を傍観していた。
紫様の愚痴を直接聞かされずに飲める酒の何と美味いことか。
しばらくは彼女に紫様の相手をしてもらうことにした。
「――でね、○○ったらこう言うのよ……って、ちょっと、聞いてる? 霊夢」
「ハイハイ聞いてるわよ。
床の上の○○は意外としつこいとか、毎晩じゃあ身体が持たないっていいたいんでしょ。
実は紫って恵まれてるんじゃないかって、引っ叩いてやりたいと思わないでもないけど、ちゃんと聞いてるわ」
○○に対する不満を口にする紫様にてきとーに相槌を打ちつつ、周囲にある酒をかっ食らう博麗の巫女。
と――
紫様が酒精に負け、ついにウトウトとし始めた。
「ん~。聞いてるんだったらいいんだけど…………え~っと、何だったかしら」
「ちょっと休憩したら? いい加減、かなりの量飲んでるわよ」
「そうぉ? ……まあ、霊夢がそう言うんだったら、言う通りにしようかしら。
じゃあ、ちょっと横にならせてもらうわ」
博麗の巫女がここぞとばかりに寝てしまえと勧める。
いつまでも自棄酒につき合わされちゃあ精神衛生上良くないし、彼女のそうした行動は分からないでもない。
ぼんやりとした様子で勧めを受け入れる紫様。ぽてっと博麗の巫女の太腿を枕にして横になる。
十秒も経たない内に紫様は寝息を立て始めた。かなり酔いが回っていたようだ。
やれやれ、ようやっと静かになったな。
「あんたも色々大変よね」
紫様を膝枕したまま、ぐいっと酒を呷る博麗の巫女。
何気に彼女もかなりの量を飲んでいる気がする。
実は博麗の巫女もこの席は自棄酒だったりするんだろうか。どうでもいいことだけれども。
「私が飲む量なんて、他の奴らに比べたら高が知れてるでしょ。
というか紫の惚気話に付き合ってあげてるんだから、正当な報酬よ」
確かに聞かなくてもいい他人の惚気話を聞かされるのは、あまり気分のよいものではないな。
……というか霊夢、これが惚気話だとよく分かったな。
紫様は○○の気の利かなさとか、身勝手さの不満しか口にしていなかったんだが。
「あのねぇ……。これが惚気話でなくて何だってのよ。少なくとも私は色んな意味でお腹いっぱいよ」
はっは。こんなもので二人の仲に中てられていたら、到底最近の紫様の相手はできないぞ。
少なくとも○○が居る時のマヨヒガでは、二人がイチャつくのは日常茶飯事なんだからな。
「そいつはご愁傷様。
けど、○○が紫の言ってるような、自分の利益だけしか考えていない奴だったら、ここまで紫が不貞腐れるわけがないわよね」
確かに……。
本当に○○のことが気に入らないのだったなら、別れて何でもない間柄になればいいのだしな。
「そういうこと。
気に入らないとか言っときながら、実は『こんな問題だらけの男なんて皆いらないでしょ』って牽制してるんだから……」
面倒くさいったらありゃしないわ、と鼻を鳴らしてから酒をくいっと呷った。
手酌で酒を注ぐ。
なみなみと注がれた盃に口を持って行き、溢れそうになった酒を啜る。
「今回紫が不貞腐れてるのだって、要は○○がウチで結婚式を挙げるんだって勝手に決めたのが原因だろうし。
ウチに来たのはそのことへのあてつけでしょ」
博麗の巫女は紫様の頬をムニムニと摘んだ。
――って。
待て。霊夢。
今、何と? 私の聞き違いでなければ、結婚式がどうのと聞こえたんだが。
「あら? ひょっとして知らされてなかった?」
知らされるも何も。そんな話、初耳だ。
私は素直に彼女の問いに肯定の意を返した。
博麗の巫女は私の作った揚げ出汁豆腐を箸で小さく切り分けると、口へ運んだ。
意外と美味かったのか、口元を綻ばせた。
そして酒をちびりと啜る。
「少し前に○○が来てね、縁ある博麗神社で結婚式を挙げたいと言ってきたのよ。
私としては断る理由なんて色々な準備が面倒臭いってこと以外にはないから、引き受けたんだけどね」
かなりの実入りが臨めそうだからというのもありそうだな。
「否定はしないわ」
うわ。あっさりと認めた。
一体どのくらいの金額を提示したのか問い詰めてみたい気もしたが、後で○○本人に訊ねればいいことに気づいて、ここは流すことにした。
いやしかし……うん、そうか。○○もついに決めたんだな。
二人の仲をずっと見守ってきた身としては、ようやっとというか、ついにという思いだ。
○○も口では結婚しようと言い続けてきたが、それを行動に移す様子がなく、私はそのことにやきもきしていたのだ。
奴が行動に移したのなら、私だってそれを支援するのにやぶさかではない。
寧ろ全力で二人の結婚を支援するつもりだ。
紫様が結婚を躊躇っているのは、いつか必ず来るであろう○○との別離を突きつけられることであって、共にあることではないのだし。
いや、この際だから紫様のことは置いておこう。
○○が決めたというのなら、私が反対する理由など全くない。
むしろ『二人の恋路を邪魔する奴は馬に蹴られて……』というやつである。
そんな感じで私が○○への応援について考えていた時だ。
ふと、博麗の巫女が悪戯っぽい視線を投げかけてきていることに気づいた。
「まあ、あんたとしたら狙ってた男が当初の予定通りに紫のものになっちゃったんだから、ご愁傷様ね」
博麗の巫女の言葉を聞いて、私は不愉快な感情を隠すことなく彼女を横目で睨んだ。
確かに私は○○が好きだ。
二人が結婚してしまうと、この想いは決して成就することはなくなるのだ。……成就してどうするという話もあるが。
だが、ここに至ればそんなことなど、私にすればどうでもいいことだった。
酒で唇を軽く湿らせてから盃をそっと脇に置いた。
私は胸の中の想いに決着をつけるため、そして彼女の発言の誤りを指摘するために口を開いた。
ふん。余計なお世話だ。
言っておくが、紫様と○○が結婚したからといって、私と○○の関係が変わることはないぞ。
それに、もし仮に今までの関係が御破算になったのだとしても、また新しい絆を作ればいいのだしな。それは私にとっては願ってもないことだ。
まあ、おそらく私たちの関係は変わらないだろうけどね。
今までの私たちの関係を表すとしたら、それは親友であり、紫様を敬愛する同志だ。
さらにここに家族という絆が加わるんだ。むしろ二人の婚儀は大歓迎さ。
「……まあ、あんたがそう言い切るんなら、それでいいんだけど」
それでいいんだ。私と○○の仲はそれ以上の何物でもないさ。
博麗の巫女はつまらないことを聞いたとばかりにフンと鼻を鳴らした。
そして彼女がすっと差し出した徳利に、私は盃を持っていった。
私は盃の中の酒をぐいと飲み干した。
先程と変わらぬ酒のはずなのに、何故かそれは渋くて酸っぱくて。ちっとも酔えそうになかった。
それからしばらく、私たちは他愛ない話をしつつ、盃を交し合っていた。
博麗神社の例大祭のこと。
賽銭の入りは○○のものを差っ引けば、相変わらずなのが不満なこと。
今年の籾巻きは例年よりも早く終わったことなど、様々なことを時間も忘れて話していた。
そう。私は○○を護衛するというここに来る前の使命を忘れて、自棄酒を飲んでいたのだ。
これが後にどういうしっぺ返しを食らうことになるかとも考えずに……。
ふと会話が途切れた。
博麗の巫女が空を見上げているのに釣られて私も同じように空を見上げると、そこには春にしては珍しい雲一つない空。
――そこに黒いシミが一つ。
……何だ?
目を凝らしてみる。
次第にシミだったそれの輪郭がはっきりしてきた。
黒い服に白いエプロン、あと三角帽。
その特徴的な格好。そして猛烈な速度で高空を滑空する箒には見覚えがあった。
「……魔理沙ね」
そのようだな。
ひょっとして私たちが酒盛りしているというのを聞きつけてやってきたんだろうか。
「萃香じゃあるまいし。
いや、魔理沙ならありうるか。あいつのそういうことに関する勘は意外と鋭いし」
などと二人して魔理沙について悪口を垂れている内に、件の噂の主が到着する。
桜の花弁が箒から発生する魔力の突風に煽られて上空に巻き上げられた。
境内に敷き詰められた玉砂利が、尋常ではない速度のまま突入してきた魔理沙に吹き飛ばされる。
なんともはや。
あ~。この光景に到着という言葉を使うのは、到着という言葉に失礼だな。
言い直そう。
噂の主、霧雨魔理沙が博麗神社に着弾した。
「ちょっと魔理沙。いきなり何してるのよ」
「悪ぃ、急いでたんだ」
物凄い剣幕で睨みつける巫女に、魔理沙は悪びれた様子もなく片手を挙げて謝罪の意を示した。
魔理沙はそこで我々八雲家の面々が博麗神社にいることに気づいたらしい。何故かハッと息を飲んだ。
その鳶色の瞳を爛々と輝かせて、突然こっちに向かって走ってきた。
「おいッ! お前ら何してんだ!?」
その剣幕に一体何事かと目を白黒させる。
「一体何をそんなに騒いでるのよ。この世の中、そう急ぐことなんてありはしないわよ」
「馬鹿ッ。こっちは危篤で急いでるんだ! ああ、もう! 何でこう、今日に限ってこんなにタイミングが悪いんだよ!」
一向に落ち着かない様子の彼女に、私たちは顔を見合わせた。
何やら切羽詰っている様子であるのだが、その理由がさっぱり見えてこなかった。
危篤がどうのと言っていることから、知り合いが災難に遭ったのだろうというのは理解できるのだが……。
魔理沙は私たちに構わずに巫女の膝枕で寝息を立てている紫様に詰め寄ると、肩を揺さぶった。
「おい、紫、起きろ! ○○が緊急事態だ! 起きろ!」
「……何事よ、もう。人が折角いい気分で寝転がってたのに」
「○○の命の危険が危ないんだ。急げ!」
すっと紫様の朱をさしたようだった頬が平静のものに戻る。
おそらく『酔いと素面』の境界でも弄られたのだろう。
紫様の表情が不愉快そうに歪められる。
「あのね、魔理沙。私そういう冗談は好きじゃないの」
「誰がこんな笑えない冗談言うか。ああ、もう。いいから永遠亭に急げ!」
「……分かったわ。永遠亭に行けばいいのね。
言っておくけど、何もなったら――酷いわよ」
永遠亭に運び込まれるということは、それなりの傷を負ったということなのだろうと私たちは理解した。
なるほどそれは一大事だ。
今日のような護衛をしなかった日に限って怪我をするとは、なんと間の悪いことだろう。
私たちは○○の被った運に頭を抱えた。
それでも、永遠亭に運ばれたということは、まず助かったと見ていいだろう。○○の悪運は意外とあるのだ。
私たちは魔理沙に○○の状況を訊ねることもせず(そんな暇もなかったが)、永遠亭に運ばれたことに安心していた。
それは今思えば、永遠亭の薬師に対する過大な期待というものだった。
だが、この時の私たちはそんなことに気づきもせず、単純に安堵していた。
紫様はゆったりとした仕草で博麗の巫女の太腿から離れると、縁側と境内の間にスキマを作って、そこを潜った。
私たちもその後に続く。
本来なら魔理沙が来た時点で気づいておくべきだったのだ。
彼女の慌てよう、そしてそのエプロンに赤い染みが付着していたことが、一体どういうことを示しているのか、その時の私たちは全く思い至っていなかった。
そうしてやってきた永遠亭。
相も変わらず青々した竹林が鬱陶しい所だ。
「呼んできたぜ!」
魔理沙が盛大な音を立てて引き戸を開けた。
が、それなのに中の住人には誰にも責められる様子はなかった。それどころかやってきた兎たちは、安堵の表情をしている者が多い。
それほどまでに○○の容態は悪いのだろうか?
何故だか、えもいわれぬ不安が湧いてきた。
「どうぞこちらに……」
兎に導かれて通された部屋の中は、見たこともない器具や薬瓶が並べられていた。
アドレナリンの臭いが少しだけ鼻についた。
部屋の中には、やや疲労した面持ちの薬師とその弟子、あと弟子の恋人がいた。
「ああ、呼んできてくれたのね。ありがとう。――ああ、貴方たちは患者の具合を診てきてちょうだい」
魔理沙に礼を言った後、弟子二人にそう伝えて部屋から下がらせる。
弟子二人はあれこれ相談してから、幾つかの薬瓶をから薬剤を持ち出していった。
「……さて、貴女たちにはこっちに来てもらおうかしら」
私たち――というよりも紫様を見据えて八意医師は、何かの感情をこらえた目をしたまま言った。
ついてきなさい、と奥の部屋に誘導する。
ぞろぞろとそれについていく私たち。
通された部屋は殺風景で、どこか冷たい印象がした。
薄暗くひんやりとした部屋にただ一床のみあるベッドが、そう思わせているのかもしれない。
何故か血の臭いがした。
「…………え……?」
誰の声だったのだろう。
それを見た瞬間、誰かが呆然とした声を漏らした。
ベッドの上に横になっている人影がいる。
誰かと思うまでもなく分かる。○○だ。
見た目は静かに眠っているようだ。
傷などもなく、治療は無事済んだのだろう。
相変わらず見事な腕だ。
そう、ホッと胸を撫で下ろした時だ。
「残念ながら、もう息はないわ」
理解できない言葉が頭上を掠めていった。
――は……?
「○○の肉体はこの通り完全に元通りにはできたわ。だけど二度と心臓が動くことはなかったの」
「は、はは。おいおい、笑えない冗談はやめといた方がいいぜ」
「……こんな悪質な冗談は言わないわ」
魔理沙が無理矢理に笑おうとして、八意医師がそれを否定する。
博麗の巫女は静かに黙祷していた。
私は何も考えられないまま、○○の傍に歩み寄った。
彼の頬に手を当てた。
この間キスをしようとした時と同じように、その頬は少しかさついていたが適度に柔らかかった。
調子に乗って、そっと青白くなってしまった唇を――初めて触ることに成功した。
だが、そんなことをしているのに、まったく心臓はバクバクとしないし、顔だって熱くなってこなかった。
きっとこれは○○の体温がこんなにも冷たいから、それが私に伝染したに違いない。
そう思い……。
そう思って……。
零れ落ちそうになる涙をぐっと飲んだ。
まだ○○の死因やどうしてここに運ばれたのかなど、何も分かっていないのだ。泣き喚くにはまだ早い。
今は、まだ、早い。
そう自身に言い聞かせて、感情を抑え込んだ。
そうして――
ふと、そういえば紫様はどうしたんだろうかと思った。
さっきから無反応で、一体どうしたんだろうか?
そう思って主に目をやると――
「…………ふぅっ」
ああっ。紫様っ!?
額に手の甲をやったまま紫様は卒倒された。
────────
○○との別れは本当に唐突だった。
去来するのは、日常交わしていた○○との益体もない会話の数々。
紫様がいて、私がいて、橙がいて、そして○○がいて。
この日常がずっと続いていくものだとばかり思っていた。
そう。この日常こそが奇跡の産物だったのだということにも気づかずに。
紫様が冷たくなった○○の傍らに立ちつくしている。
正気を取り戻された紫様が次になさったことは、○○に直接会うということだった。
永遠亭の薬師は特に引き止めるような素振りは見せなかった。
その理由を彼女は身近な者との別れを最も印象付けるのは、直接会って確かめることだと言っていた。
また倒れられては困るので、私も主の後について行くことにした。
紫様は彼の顔を抱きかかえるようにして身を寄せると、乱れた前髪をいとおしむようにして指先でそっと整えられた。
○○の頬にご自身の頬を重ね合わせる。
だが、どんなに撫でようが擦ろうが、○○の目は開くことなどなかった。
紫様は金の双眸に涙を湛えたまま、ボソボソと愛する人の耳元で何事か囁かれた。
紫様の感情が式を通して私に流れ込んでくる。
哀しい。哀しい。哀しい。
胸が痛い。胸が痛い。胸が痛い。
私は思わず目をとじた。正直、見ていられなかった。
私は紫様についてきた目的も忘れて、思わず外へと出ていた。
引き戸にそっと背中を預けると、天井を見上げた。
言葉もない。言葉が出ない。
身を切り刻まれるような切なさに身をさらされながらも、私はぐっと唇を噛んで涙を飲み込んだ。
私は紫様の式だ。主に断りもなく主の替わりに涙を見せるわけにはいかない。
そう自身に言い聞かせ、私は紫様が出てくるのを待つのだった。
まあ、それからのことは大して面白いものでもない。
親しい知人との別れが済めば、あとは残った遺体の処分だ。
○○は外から来た人間だから、身寄りもない――つまり家系の墓に入らずに無縁仏として扱われたそうな。
執り行われた葬式は空虚であったが、しめやかなものだったという。
私が何故伝聞調で言っているかというと、実際には立ち会っていないからだった。
本来なら紫様が喪主として執り行った方がよいのだろうが、現実的なしがらみから、それは出来ぬ相談だった。
強力な妖怪である私たちは人に畏れられる存在だ。
そんな立場の私たちが人里に堂々と侵入し、厳粛な式を乱すことは流石にやってはならないことだと理解していた。
力ある存在に付き纏う責任とか役割というやつだ。
前述したしがらみと言い換えてもいいかもしれない。
――というのが表立っての葬式への不参加の理由だ。
ちなみに表立ってということは裏があるということで。
博麗の巫女やら幽々子様など幻想郷の力ある立場の者たちには、それとなく知れ渡っていることだが――
実は、永遠亭から帰宅して以後、紫様が部屋に引き篭もったまま出てこなくなったのだ。
現在、紫様の部屋は入口と出口の境界を弄くっておられるせいで、中に入れなかったりする。
紫様の引き篭もりを知っている方たちは、それほどまでに○○との別れはショックだったのかと同情を向けてくれている。
有難いことだ。
私自身、彼女たちの向けてくれる同情によって、心に受けている負担は幾分かは和らいでいる。
話を戻そう。
紫様の寝室の前に食事を置いておくと、いつの間にやら食べ終えた食器が台所に積まれているので、きちんと食事は召し上がってはいらっしゃるようだ。
気がついたら干乾びている主を発見というような心配はなさそうなので、その点だけは安心していた。
ああ、そういえば○○の死因を説明していなかったな。
薬師が言っていたことを纏めるとこうだ。
一、直接の死因は心臓の損傷による失血死。
二、傷の具合から見て、おそらく○○を襲ったのは妖怪だと思われる。
どうして真昼間から妖怪が○○を襲い、重症を負わせただけで済ませたのかとか。
普通、妖が人を襲ったのなら、その肉を食べるだろうとか。
博麗の巫女の作った厄除け符は効果がなかったのかとか。
疑問は幾つかあったが、ここではひとまず置いておくことにした。
そんなことよりも重要なことがあった。
それは永遠亭のチート薬師の手によってですら蘇生に失敗したという事実だ。
私が何が起こったのかと疑問を呈してみると、薬師はおそらくだけれどと前置きをして答えた。
「蘇生しなかったのは、魂魄が幽体から剥がれ落ちたからでしょうね。
回復状況を鑑みるに、少なくともウチに来た時にはまだ肉体には魂魄はあったはずなんだけど……。
どうして剥がれたのかは不明ね」
薬師はそうトンデモないことを口にした。
魂魄が剥がれ落ちる。
死者となった者は、肉体から魂を天に魄を地に遣ることで次なる世界に輪廻することになる。
まあ、輪廻する前に魂は三途の川を渡って閻魔――幻想郷においては映姫様――の裁きを受けるわけではあるが。
ちなみに紫様が『生と死の境界』を弄くって死者を生き返らせたりできるのは、映姫様に裁かれる前までである。
いや、輪廻の途についてからでもできないわけではないだろうけれど、それは判決を反故にされることを望まない映姫様の意思に反するわけで。
となると無理に押し通ろうとすれば、お二人が激突することは避けられないわけだ。
この世とあの世の境界を操作し、幻想郷のこの世にあの世を現出せしめ、○○を蘇らせようとなさる紫様。
対する映姫様は曖昧になった彼岸と此岸の境界を白黒はっきりさせることで、元に戻そうとする。
そうはさせじと白と黒の境界を曖昧にして、映姫様の能力一時的に封じる紫様。
だが、映姫様もその程度で引っ込むようならそもそも閻魔などやっていない。曖昧と曖昧でないものの白黒をつけ、全てを正道に正していく。
紫様は正しいものと正しくないものの境界を操り、映姫様は全ての境界に白黒をつけて歪みを正す……!
お二方の能力がせめぎ合い凌ぎ合い、ぶつかりあった余波が幻想郷に襲いかかる。
そうして気がつくと――
そこには全てが生きながら全てが死んでいるという、混沌とした地獄がそこに現出しているのであった……。
…………。
ひぃっ。今、とっても嫌な未来が見えた!
却下だ却下。
紫様も老獪なお方なのだから、その辺はきっと理解し、分別されておられるだろう。うん、そうに違いない。
閑話休題。
そうして紫様が部屋に引っ込まれてから二週間が経った。
未だ紫様は出てこない。
そろそろ何とかして、紫様を引っ張り出す方法を考えなければならないだろうかと、そんな心配が私の胸に頭をもたげ始めていた。
気がつくと、幻想郷の景色は桜の花弁が散る季節から、若葉萌ゆる季節に変わろうとしていた。
私は縁側に腰掛けて、いつもの仕事である幻想郷に張り巡らされた結界の様子を確認していた。
今のところ特に結界に綻びはなく、整えなければならない歪みもなかった。
橙も外へ遊びに行っているし、外から何かが迷い込んでくるような兆しもない。
まさに長閑で平和な日だ。
どこにも○○がいないということを除けば……。
ふう、と私は気の抜けた溜息を吐いた。
どうにも胸にぽっかりと空いた思いがやるせない。
このまま日がな何もない日々が続いて、いつの間にか○○のことも思い出として受け入れていくことになるんだろうか。
記憶はいつか風化し、セピア色をした思い出になっていく。
そう、それは仕方がないことだ。
私たち長命な者はそうして生きてきた。そしてこれからもそういう生き方をしていくのだろう。
だが今は、それが何だか自身の想いに裏切られたような、そんな気分なのだった。
ふと――
夕闇の帳が下りる時刻、近くに何者かの気配を感じた。
我に返り、意識をそちらへ向けた。
私は目を見開いた。
そこには紫様が立っていらっしゃったからだ。
少し、頬がやつれていらっしゃるようにも見えたが、その美貌は些かも減じてはおられなかった。
紫様は小さく首を傾げ、愛らしい仕草でおっしゃった。
「藍――」
はい、紫様。ようやっとお出になられたんですね。
安堵で私はやれやれと肩を落とした。
良くも悪くも、これで一歩前に踏み出したのだと思ったのだ。
だが、現実はそんなに甘いものではなかった。
紫様は私の声掛けを無視して続けた。
「藍。○○は来たかしら?」
…………ッ!
私は息を呑んだ。
主の言葉を耳にした瞬間、私の背に冷たいものが流れ落ちた。
そんな馬鹿なという思いと、さもありなんという相反する思いが去来した。
紫様の○○への想いは、その心を壊してしまうほどに強かったのか。
否、この程度の精神的打撃など、大妖怪、八雲紫にとればどうということはないはずだ。
胸中の一瞬のせめぎ合い。
私は一度深呼吸して内心の動揺を抑え、姿勢を正して主の問いに答えた。
紫様、○○は死んでしまったので、もう……二度とマヨヒガに来ることはありません。
「……そう。遅いわね。ずっと待っているのに、何をしてるのかしら」
紫様は私の言葉を聞き流した。
扇子を頬に当て、童女のように可愛らしく小首を傾げる様が逆に哀れを誘う。
「一体どこで道草食ってるのかしら?
まだ来てないとなると……そうね、行ってみようから」
どこか焦点の合わない遠くを見つめているような、精神の平衡を失ったかに見える眼差し。
泣きたくなった。
だが、現状は泣いていてはどうにもならないどころか、むしろ危機的状況だ。
紫様が本当に心を病んでしまわれているのであれば、早めになんとかしなければならない。
より精神を主に置く妖怪にとって、精神の崩壊は存在自体の危機である。
もしそのまま病状が進行して紫様の身に何かご不幸があれば、幻想郷の人妖のバランスが崩れてしまいかねないからだ。
私の心配をよそに、紫様はいつもの調子で扇子をすっと振って空間にスキマを広げられた。
出掛けられるのですか?
「ええ。ちょっと博麗神社とか人里に、ね」
にこやかに行き先を告げられる紫様。
って、は? え? ちょっと!?
人里に行かれるんですか? それは色々拙いんでは……。
「確かめたいことがあるのよ」
確かめたいこと、ですか?
博麗神社や人里で調べたいことがあるなんて、一体なんだろうか。
私にはさっぱり思いつかなかった。
「まあ、私が直接人里に入るのが拙いと思うのなら、藍に調べてきてもらってもいいんだけど」
いいですけど。一体何を調べればいいんです?
「○○が挨拶に現れたかどうかを、彼と親しくしていた人に訊いてもらえるかしら。
ああ、勿論、今すぐ行けと言っているわけじゃないわ。
そうね、三、四日後時にでも分かればいいわ」
また妙なことを言い出したな。
そんなことを訊ねても、普通返ってくるのは「来ていない」だろうに。
まあ、それで紫様の気が晴れるのならば、いくらでもするが。
紫様はじゃあお願いね。私は霊夢のところに行くからと言い残すと、そのままスキマに入っていかれたのだった。
さて、理由はよく分からないが、とにかく指令を受けたからには行動しよう。
まあ夕飯のおかずを買いに行きがてら、調べることにするか。
それから三日後――
ようやっと結果が出た。
意外と○○の人里での交友範囲は広くて、里を端から端まで歩くことになったしまった。
里の人たちの私を見る目は、大きく分けて二パターンあった。
私と○○の関係を知らない者には、その関係を説明した。
要は○○の恋人の紫様の式だということだな。
それに対して、里の人の反応は私たち妖怪のせいで○○が死んでしまったと嘆き、怒る者。
愛する者が突如奪われ、さぞやつらい思いをしていることだろうと、同情の目を向けてくれる者だ。
比率にすれば6:4といったところだろうか。
どちらの反応にせよ、疲れることには変わりはなかったが。
で、だ。
結果は案の定「そんなものは来ていない」だった。
ようやっと調べきったところで夕食の席でそう紫様に報告すると、さして落胆した様子もなく――いや、むしろ当然といった様子で頷かれた。
だったら一体紫様は何を考えて、私に調査をさせたんだろうか。
さて、夕飯を食べ終え、湯浴みも終えて、縁側でゆったりしていた時だ。
「藍、出かけるわ。ついてきなさい」
否も応もなくスキマに吸い込まれた。
相変わらずの傍若無人。
そこに感動もしないし憧れもしないが、これでこそ紫様だと思うのは何か間違っているだろうか。
で、次に目の前に広がっていたのは、無数の四角く細長い石の列の並んだ場所――墓場だった。
周囲では私たちの妖気に中てられた霊魂がざわめき始めていた。
「何をボーっとしてるの。こっちよ」
紫様に急かされ、慌ててその後を追った。
足元に絡み付いてきた霊魂を振り払い、奥へと進む。
四半刻程テクテクと歩いただろうか。
私たちが辿り着いたのは、まだ真新しい卒塔婆の立った状態の土饅頭の墓だった。
紫様……これ、ひょっとして。
「ええ。○○のお墓よ」
私は思わず紫様のお顔を窺ってしまった。
紫様は私目を見つめ返し、軽く頷いた。
そうか、人の居ない時にお墓参りをされることにしたんだな、と私は納得した。
「――ということで藍、今からこのお墓を暴くから、見張り、お願いね」
…………は?
自身の耳を疑うような台詞が主の口から何の脈絡もなく漏れた。
ちょっ。待っ。紫様!?
紫様は私の制止の声を無視して右手を水平に構えられた。
ドドドッと低い呻り声を上げて弾幕が周囲に発生する。
「右よし、左よし。薙ぎ払え~ッ」
語尾に音符が付いていそうなエラく軽いノリで、盛られていた土を弾幕で吹き飛ばす紫様。
吹き上がった土砂に巻き込まれた卒塔婆が、半ばでへし折れて吹っ飛んでいった。
あー、あー、あー。
そうして出土する(この表現でいいのか?)棺桶の蓋。
「さあ、藍。人が来ないうちにとっととやっちゃうわよ」
いや、ちょっと、紫様? 一体何を……!?
私のうろたえる様子が可笑しかったのか、紫様は小さく微笑まれる。
紫様は残っていた土を掌で払うと、棺桶の端に無理矢理手を突っ込まれた。
湿った音を立ててめり込む紫様の指先。
ふと、そこでちょっとした疑問が脳裏をよぎった。
紫様に浮かんだ疑問を投げかけてみることにした。
「何かしら?」
どうしてわざわざこんな目立つ墓荒らしをなさってるんです?
棺桶の中の○○に会いたいのならば、スキマを開ければよいことでは?
紫様は丁寧に棺桶の蓋をひっぺがしながら答えた。
「念のためよ。○○ったら、肉体だけになっても私の能力を否定するんだもの」
何でも永遠亭で二人きりになったときに『生と死の境界』を弄くってみたらしい。
しかし、○○の肉体はそれを受け付けなかった。何回か試してみたものの、結局全て何も起こらないまま終わったのだそうな。
ああ、あの時のことか、と私は思い出していた。
私の胸がチクリと疼いた。
○○に抱きついて、なかなか出てこなかったのは色々試されていたからなのだな、と一人納得する。
そうして完全に蓋が棺桶から取り払われた。
中を覗き込む紫様。
その時、丁度月明りが棺桶の中に注ぎ込まれた。
私は息を飲んだ。
と同時に自身の目を疑った。
そこには腐乱を開始した○○の崩れかけた肉体があるはずだった。
あるはずなのだ。
それなのに――
そこには副葬品として入れられていた枯れた草花があるだけで、○○の姿はどこにもなかった。
いくら目を擦っても、頬を抓ってみてもその事実は変わらずそこにあった。
○○の死体がない。
棺桶に入れ忘れたのだろうか。
いや、そんな間抜けなことが起こるわけはあるまい。
だとすると、○○が生ける屍か何かになって棺桶から逃げ出した?
どうやって? 土は棺桶の上に被せられたままだった。
誰かが掘り起こして○○の肉体を奪った?
それこそどうやって?
というより、態々掘り返して奪ってから、もう一度何事もなかったかのように空の棺桶に蓋をして土を被せる、そのメリットは?
私が混乱しているのをよそに、紫様は棺桶の中に身を入れ、何やらごそごそとなさっていた。
何かを見つけたのか、紫様はそれを懐に収められた。
ちらと見えたものは親指の先ほどの大きさの小さな白い物体だった。
「さ。藍、次行くわよ」
そう――まるで○○と逢引していたときのような軽やかさで、紫様は身をひるがえされたのだった。
─────────
そうして紫様に連れられ、私が次に訪れたところはというと――
「……では、判決を申し渡します。
主文――被告は無賃乗車、斜め横断、食い逃げと無法の限りを尽くした。その罪はとても重い。
よって被告は地獄行きです。
しばらく法の何たるかというものを、その魂に刻み込むとよいでしょう。
それとですね……」
あー。もうここがどこかお分かりだろう。
私たちは幻想郷のあの世にある裁判所に来ていた。
現在、映姫様の行なっている審判が終わるのを、森羅殿で待っているという状況である。
相変わらず傍論の長い判決だなぁ。
朗々と判決文を読み上げる映姫様のお声を遠くに聞きつつ、私は出された茶をすすっていた。
一方の紫様はこの間一言も言葉を発することなく、茶に口をつけることもなく静かに瞑目しておられた。
といっても眠っているというわけでも、或いは瞑想しているわけでもなく、ただ目を瞑っておられるだけのようだ。
丁度いいので、ここで私は紫様に幽冥界を訪れた理由について訊ねてみることにした。
「あら、森羅殿に態々訪れる理由なんて、そう沢山あることじゃないでしょう。
だとしたら、藍にだってその理由は思いつくんじゃなくって?」
私が思いつくことといったら、それこそ○○を賭けての幽冥界との大立ち回りくらいしかないんですが。
ここへは○○の魂を取り戻しに、参られたのでしょう?
今までの紫様と○○の経緯を考えると、出てくる答えは自ずと決まってくる。
○○が死んだというのであれば、その転生先を探し出して逢いに行くに違いない。
そして転生先を最も手っ取り早く知ることができる場所が、幻想郷とこの世とあの世を結ぶここ幽冥界というわけだ。
問題があるとすると、紫様の目的とあの世の規則が真っ向から対立するということか。
紫様が輪廻の理を捻じ曲げて○○をこの世に蘇らせようとするならば、彼岸を支配する幽冥界は確実にそれを止めようと動く。
そうなれば待っているのは、八雲家と幽冥界の戦争だ。
というようなことを説明すると、紫様はしかつめらしく頷かれた。
「そう。藍がそう考えているのだったら、それが正しいのかもしれないわね」
ほ、本気ですか?
私のげぇっといわんばかりの表情を見て、紫様は苦笑なさった。
「この程度の言葉遊びで慌てないの。
私が何を考えてここに来たのかは、それこそ四季様がお見えになれば分かることなんだから、貴女は私の傍で泰然と侍っていなさい」
紫様は私にそう忠告なさり、大分温くなった茶に口をつけてすまし顔だ。
いやいやいや。
『泰然としていろ』って言われても、紫様が不安を煽ってるんじゃないか。
――と思わないでもないが、恐らくツッコんでも無駄に違いない。
紫様の面の皮は、そんなありきたりな文句程度では傷ひとつ付かないのである。
会話をしていて分かったことがある。
紫様は今回の訪問の目的に関する具体的な明言を避けようとしていらっしゃる、ということだ。
何か思うところがあるのか、それとも言いたくない気分なのか(おそらく前者だとは思うんだけれども、時折後者の可能性もあるから困る)。
とりあえずこれ以上は追及しても、のらりくらりとかわされることになるだろうというのは理解した。
話そうと思っていない口を無理矢理に開かせるのは至難の業だ。
そう理解した私は大人しく引き下がったのだった。
小半刻後、ようやく裁判に区切りをつけた映姫様がお見えになった。
紫様と私は席から立ち上がり、彼女をお迎えする。
映姫様は片手を軽く挙げて謝辞を示された。
「お待たせしました」
「いいえ。こちらこそ突然お邪魔、失礼しておりますわ」
まずは互いに当たり障りのない挨拶から始める。
どんな相手にもまずは挨拶から、というのは万国共通の理念だろう。
ふと、映姫様の視線に牽制するような、探るようなものを感じた。
まあこれは紫様のような強大な妖怪が何の前触れもなく幽冥界を訪れたのだから、不審に思われるのも仕方のないことだろうが。
私だって今回の紫様の突拍子もない行動の裏が読めず、不安を抱いているのだから。
表面上は穏やかな会話が続く。
「貴女も壮健のようで、まずは重畳と申しておきましょう」
「ありがとうございます。映姫様も相変わらずのご様子で安心いたしましたわ」
互いに相手の健勝を寿ぐ。
まあ、紫様の言葉には裏の意味が含まれていそうだけれど。
分かり易い言葉で表現すると『あんた話長過ぎ』だろうか。
映姫様もその辺りの意訳はきちんと受け取られたようで、頬が微かに引き攣っていたのを私は見逃さなかった。
「そういう貴女は色々変わったようですね。
最近の貴女に関する噂は、森羅殿にも聞こえてきていますよ。なかなか面白いことになっているようで……。
なんでも人間を伴侶とするのだとか」
「あら、それはお耳汚しですわね」
映姫様の揶揄を紫様はいつもの胡散臭い笑みで受け流した。
私は映姫様の揶揄に苦いものがこみ上げてくるのを感じた。
主と○○の仲が映姫様の耳にまで届いていたことは、本来ならば喜ばしいことであるはずなのだ。
あの世に噂が達するということは、それほどまでに二人の絆が深まっていたということの証左なのだから。
であるにも関わらず、全く喜びが湧いてこない。
何故だ。
簡単だ。
もはやこの世に○○がいないからだ。
もはや紫様との絆を育まれることがないからだ。
お二人の会話を聞きつつ、私は知らず知らずに服の裾を強く握り締めていた。
目尻に力を籠めて涙がこぼれないように努めた。
○○、何故死んだ。
何故死んでしまったんだ。
お前のせいで、紫様はこんなところにまで来てしまったんだぞ。
ああ、自分でも理不尽なことを考えているということは分かっている。
○○はただの人間だ。
人は安易に死ぬものだ。
橋から足を滑らせて川に落ちても。
風邪をこじらせても。
妖怪に襲われても。
たった百年ほど生きただけでも、人は簡単に死んでしまうのだ。
そのぐらいのことは、人里の子供たちでも知っている。
だが――
だが、○○よ。
お前の不在はあまりにも大きな傷跡を、私たちに刻み込んでいるぞ。
「さて、八雲の妖怪。この度は一体どのような用件があってここに踏み入ったのですか?」
いつまでも雑談をしているわけにもいかない映姫様が本題に入った。単刀直入に訊ねられる。
紫様は口元を扇子で隠し、いつもの胡散臭い流し目で映姫様を見やった。
「実は――」
紫様を中心として、陰鬱な妖気がじわりと辺りに漂い始める。
「とある人間の転生先をお訊きしたくて、まかりこしましたの」
「そうですか……」
ところが口元に慈悲溢れる笑みさえ浮かべなさって、映姫様はそれを平然と受け止めていた。
映姫様は紫様のおっしゃった理由を聞いて納得し、うんうんというように頭を肯かせている。
そしてまっすぐ紫様の方を見て、返答された。
「古今東西、死者に逢いたいと思うのは、生ける者の業でしかありませんよ。
記紀を紐解くまでもなく、口にした者がそれを実行して、碌な目に遭ったためしはないんですから」
訥々と紫様を諭される映姫様。
脅しが効かないと判断するや、紫様はすぐに妖気を霧散させた。
一方の私はというと――
ようやく紫様がここに来た理由を聞くことができたというのに、安堵感は微塵もなかった。
むしろ幽冥界を相手取った戦争ということが現実味を帯びてきたことで、慄然としていたわけであるが。
無論、表面上は努めて無表情を装っているので、顔色に出したりしない。
もしも紫様が死者の禁を犯すとなると、その未来はなかなか骨の折れることになりそうだ。
よほど慎重に事を運び、上手く立ち回って引き時を見定めなければなるまい。
少しでも筋道を見誤ろうものならば、危険な妖怪として地の底に封印されてしまうことだろう。
『○○は生き返りました。けれども紫様は封印されました』
――では目も当てられまい。
それだけは紫様としても本位ではないはずだ。
ということは、今は先走っていらぬ言質を映姫様に取られないよう、口をつぐんでいるのが一番無難か。
私は主の横顔をまんじりと眺めていた。
果たして、私が危惧していることを、この方は本当に為さろうとしているのだろうか、と。
そんなこと、顔に書いてあるはずがないのは分かっている。
けれども、紫様の進まれる道はその視線の向こうにあると信じているから。
私がお仕えする主は、この方をおいて他にいないから。
全力を以ってお支えする為に、私は自身の主の一挙手一投足を見つめていた。
などと私が心の中で現状を捏ね繰り回している間にも、お二人の会話は続いていた。
「無論、存じておりますわ。
冥界門を潜るということがどういうことかも、それを実行した時の危険性も。
それでも――
映姫様にお縋りするしか、この胸の中にわだかまる澱んだ闇が晴れないんですの」
ご自身の胸を押さえ、潤んだ瞳で心情を吐露する紫様。
映姫様は珍しいものを見たと言わんばかりにまじまじと主のことを眺めていた。
いや、実際紫様がこんな表情をなさることを知っている者など、幻想郷でも数えるほどしかいない。
であるので、映姫様が驚かれるのも無理はないことなのだった。
映姫様は小さく一つ嘆息なさった。
「分かりました。
無理に留め置いて、貴女が無理にでも冥界門を押し通るというような事態は、私としても避けたいですしね」
「ご配慮、痛み入りますわ。
まあそこで、『押し通る!』『来いやぁぁッ!』という展開も、ちょっと燃えるものがありますけれど」
元ネタを知らなかった映姫様は、怪訝な顔をなさっていた。
元ネタの分かった私は、思わず指先で眉間を揉んでいた。
そうして考えることといえば『やっぱり紫様って○○に毒されてるなぁ』ということだった。
「ですが、これだけは約束してください。
その者の転生先はお教えしますが、決して冥界門を潜ることのないように」
とりあえず映姫様は後半の言を聞かなかったことにしたらしい。正しい反応です。
「承知いたしましたわ。
八雲紫、決して無断で冥界門を越えたりいたしませんわ」
「宜しい」
映姫様も私と同様の危惧を抱いていらっしゃったようだ。
そこはぬかりなく、事前に約定を交わすことで、未然にお防ぎになったようだけれど。
しかし、これで問題がなくなったかといえば、そんなわけはない。
何故ならば、○○の転生先を紫様が知ったならば、必ず冥界の門を越えて迎えに行くことが目に見えているからだ。
それも無断ではなく、押し通ることを先方に断った上で、堂々と。
「それで。どなたの転生先を知りたいというのですか?」
「それでは……○○の転生先をお聞かせいただけますか」
言った。
ついに言ってしまった。
これで二度と引き返せない所に、私たちは足を踏み入れた。
これで○○に逢える。
私の脳裏にそんな思いがよぎった。
覚悟と安堵。
私がその感情に身を委ねようとしたその時――
「……は? ○○ですか?」
きょとんとして鸚鵡返しに訊ねられる映姫様。
何故か怪訝な表情をなさっていた。
「あのですね。ここへは死者以外は来ることはないんですが」
――はい?
そう、よく分からないことを仰った。
えっと……。
映姫様の様子から判断するに、○○はまだ彼岸には来ていない……?
いや、そうであるならば、こんな仰り方はするまい。
その場合は『まだ死神が三途の川を渡している最中だ』とか『まだ裁判中です』といった感じに仰ることだろう。
だとすると何? ○○は生きている?
それこそ否だ。
永遠亭の薬師の診断は、○○は魂魄が剥が落ちて死んだと言っていたではないか。
それにこの手にはまだ、あの○○の身体に触れた時の冷たさを覚えている。
あの時の心が凍りつくような寒さを覚えている。
だとすると、映姫様は何をそんなもったいぶった様子でいらっしゃるのだろうか。
「知っての通り、人は死ぬと鬼籍――すなわち閻魔帳へその功罪と共に名が記されます。
現在のところ○○は他の人と同様に地獄街道一直線の人生を歩まれていますが、その寿命が尽きるのはまだ先で……す……? こ、これは!?」
映姫様は懐から閻魔帳を取り出されると、パラパラと頁をめくって該当箇所を探されていた。
ところが、○○の部分を見つけて目を通している内に、ハッと目を大きく見開かれた。
「どうかなさいまして?」
「いえ……確かにここへは死者しか訪れることはない……。
……しかし、これは……いや、そうするとあれしか考えられない……」
紫様が何かあったのかと訊ねられた。
けれども映姫様はすぐに我に返るようなこともなく、何やらブツブツと意味を成さないことを呻いておられた。
映姫様ともあろう方が他人の言葉が耳に入らないなど、かなり珍しい光景だ。
紫様は映姫様の様子を静かに窺っていた。
映姫様の取り乱し様をまるで当然のことであるかのような様子で見ていた。
…………?
あれ?
ひょっとして紫様は何か知っていらっしゃるのだろうか。
「○○はまだここには来ていない――そう受け取ってよろしいかしら?」
紫様は映姫様の耳元に囁かれた。
ようやくそこでハッと我に返られた映姫様は、閻魔帳をパタリと閉じる。
すぐさま平静に取り繕われた。
「お見苦しいところを見せてしまいましたね。
私としたことが、些か予想外の事態に戸惑ってしまったようです」
「こういうことは滅多にあることではないですし、そうなるのも仕方ないかと」
「そうポコポコあられても困ります」
「確かに」
そうして二人して苦笑なさる。
うん、どうやら紫様が何か重大なことに気づかれていることは確かなようだ。
二人共同じ結論に至られているということは理解したが、私にはそれが何なのかさっぱり分からなかった。
ちょっと悔しい。
紫様はここで席を立たれる。どうやら暇を告げられるようだ。
私も主に追従する。
「さて、ここに○○が伺っていると思ったんですけれど、どうやら違ったようですわね」
紫様の非常にわざとらしい台詞に、映姫様は苦笑されていた。
そうして部屋を辞する直前――
「ああ、○○に会ったら伝えていただけますか」
ふと、映姫様はそんなことを仰った。
この方は一体何を言っているんだろうかと、私は思わず胡乱な顔をしてしまった。
○○は死んでいて、もはやここでしか死後の情報を得られないと思ってやってきたのに、まだ来ていない(死んでいない?)と言う。
不信感が湧いていたところに、この無体な依頼。
これで呆れなかったらいつ呆れるというのか。
この時私は大変混乱していたのがよく分かる。
紫様は映姫様の様子に呆れるでもなく、憤慨するでもなく、ただ一言頷かれた。
「承りますわ」
「では、こうこう伝えてください。
『百年後の彼方、必ずやお迎えに上がりますので、お覚悟召されよ』と」
主は幻想郷の閻魔の言葉に頷かれ、必ずや伝えますわと艶やかに受け入れられ――
「ですが、お生憎様。
貴女方のご挨拶は全て叩き潰して差し上げますわ」
獰猛な笑みと共にそんな宣言をなさった。
そして映姫様は主の返答に破願されたのだった。
踵を返す紫様。私もそれに続く。
紫様は森羅殿を振り返ることなく、此岸を目指して歩かれる。
それはもう、いそいそと。
本人にすれば、礼を失しないよう心掛けているつもりなのだろうが、後ろをついて行っている私にははっきりと豹変した態度が見て取れた。
今にもスキップしそうなウキウキとした足下。
私も釣られて楽しくなってしまう。そんな後姿。
既視感――否、私はこの背中を知っている。
○○のところに逢引に行く時と同じなんだと思い至る。
ああ、この後姿を見るのも久し振りだなぁと、嬉しくなって一人主の背中に向けて頷いていた。
ん? 待て待て。
紫様は何をそんなに喜んでおられるんだ?
疑問を感じた私は道すがら、紫様に訊ねてみた。
一体何があったのですか、何をそんなに嬉しそうにしているんですかと。
すると紫様はポツリと一言。
「――尸解よ」
その一言が結論であり、また始まりであった。
──────────
人という階位を超越し、天地と寿命を等しくするには、いくつかの方法がある。
一つ目は捨食の法や捨虫の法などの外法をもって魔法使いとなる。
二つ目は太陽を避け、闇に潜み、夜に蠢く有象無象たる妖怪へと堕ちる。
三つ目は蓬莱の薬を使用する。
そして四つ目、幾多の修行の果てに仙人と至るという方法だ。
異論はあるかもしれないが、ひとまずこのまま進めさせてもらう。
今回注目すべき話題は、四つ目の仙人になるという方法だ。
仙人になるには天に昇ったり山で修行したりと幾つか方法が存在するが、その内のひとつに尸解というものがある。
有体にいうと尸解とは死後、人としての肉体を捨て、仙人としての体へと変化させることをいう。
火に身を投げてみたり、毒を飲んでみたりと、兎に角人としての肉体を一度捨て去るのが一般的な尸解の方法だ。
文字通りしかばねを解いてしまうがゆえに、尸解という。
この尸解を行なった果てに至るのが尸解仙といって、仙人の位の中では最も低い階位のものといわれている。
まあ、中には長い仙道修行の過程のひとつともいわれることもあるが。
とまれ、私たちにとっては縁遠い話のはずなのだけれども……。
――『尸解』ですか?
突拍子もない言葉が紫様の口から漏れ出た。
それを私は深く考えることもなしに、思わず主に鸚鵡返しに訊ねてしまった。
頷かれる紫様。
「そう。天仙、地仙、尸解仙の尸解よ」
○○ってごく普通の人じゃなかったんですか?
私の記憶では奴は仙道の修行に励む道士でもなかったし、仙人骨があったなんてついぞ聞いたことがないんですが。
仙道は欲を否定しないとはいえ、奴の生活態度を鑑みるに、仙人の暮らしからは程遠いものだと思われる。
酒は飲むし、よく食べるし、なにより紫様との色欲に溺れているのだ。
あれで仙人に至れるんだったら、世の中にいる人間は死後はすべからく仙人になれるだろう。
うん、それはないな。
私の結論を聞いて、紫様もそうねとそれを肯定された。
苦笑を抑えようとしていないところを見ると、紫様自身もその辺は理解しているのだろう。
「でもね、藍。状況から考えると、そうとしか考えられないのよ」
紫様は理由を指折り挙げられる。
「まず一つ目。○○は皆に死んだと認識している。
永遠亭の薬師の診断もその補強になっているわね」
私は複雑な思いに囚われた。
あの時去来した背筋を凍らせるような虚無感のことを思い出す。
あの肌の冷たさが誤認だというのだろうか?
永遠亭の薬師の診断が、偽りだったとおっしゃりたいのだろうか?
思わず紫様を見つめる視線に、非難の感情が篭ってしまった。
「そうは言わないわ。彼の肉体から魂魄が剥がれ落ちたのは確かでしょうし。
私もあの時は、かなりショックだったわ」
紫様、前後不覚になってましたしね。
「あれは不覚だったわ。
――話を戻すわ。
私も彼の肉体に魂がないのを確認したわ。だから、診断は間違ってないわよ」
紫様は私から視線を切り、透徹した目で空を見上げた。
東の空が大分明るくなってきていた。もうすぐ夜が明ける。
その時――
「……そういう意味では人という生物としての○○の生は、確かにあそこで終わっているわね」
ポツリとつぶやいた紫様の横顔が、とても印象的だった。
見た目には特に表情は変わっていなかった。
けれども悔しさを堪えているような、哀しんでいるような、そんな風に私には見えた。
「理由二つ目。棺桶に入れられたはずなのに、○○の死体がない。
これはきちんと彼が棺桶に入れられてから埋められたのを見たって、葬式に参列した霊夢に確認済みよ。
そしてこれこそが、彼が尸解したという確たる証。
魂魄が剥がれ落ちたというのも、そう考えれば納得いくわ」
尸解というのは確かに、肉体と魂魄の繋がりを絶つ術ではありますが……。
そうなると疑問が湧いてくる。
尸解とは要は凡体骨肉を捨て、仙人としての肉体を得ることを目的とした術だ。
肉体を脱し、魂魄のみになることまでは比較的容易だ。
普通に死んでしまえば、肉体と魂魄の分離は可能だからだ。
まあそれだけでは輪廻の輪から抜け出せない――つまり仙人にはなれないのだけれども。
問題はその後、肉体を捨て去ってからの話だ。
魂魄と肉体を切り離すと、それのみで自意識を保つのはかなり難しくなる。
放っておくと容易く魄は地へ、魂は彼岸へと分かれて行ってしまうからだ。
故に魂魄が分離しないようにしつつ自我を保っていられるようにするには、高度な修行が必要となってくるのだ。
奴の生活態度を思い出す限り、そんな修行をしている節は見当たらなかった。
それ故に、紫様の言葉が私には釈然としなかった。
「そして理由三つ目。○○は四季様のところへ行っていない」
それを確かめに映姫様のところをお訪ねしたんですよね。
幽冥界との戦争を覚悟していたけれど、そうはならなかったのは僥倖だった。
「予想通り、○○は彼岸に逝っていなかったわ。
四季様のあの様子からすると、おそらく閻魔帳にある寿命欄も書き替えられていたんでしょうね」
閻魔帳の書き替えなんて、できるんですか?
あれは一種、契約書の宝貝みたいなものだから、そうそう書き替えたりはできないはずなんですが。
「あら、須菩提祖師のお弟子さんは書き替えたじゃない」
あんな化物と○○を一緒にしないでください。
確かに○○は多少変なところはありますけど、そんなことできるはずないじゃないですか。
「……まあ、今は閻魔帳が書き替えられたかどうかは問題じゃないわ。
四季様も○○が尸解仙化したと判断したというのが今は重要なことよ」
そういえば映姫様はそんなことをおっしゃっていたなと、私は思い出した。
……あの時。百年後がどうのこうのとおっしゃっていたのは、そういうことか。
仙人はだいたい百年ごとに、地獄から刺客がやってくるというのは有名な話である。
現状は納得できないが、主の言わんとすることは理解できた。
それからしばしの間、無言の行軍(といっても空を飛んでいる)が続く。
日の出が拝めそうな小高い丘を発見し、私たちはそこへ降り立った。
ここで○○を復活させるということだろうか。
それにしてもどこかで見たことがある景色だと思ったら、ここはマヨヒガと○○の家の中間地点辺りだ。
○○が妖怪に襲われたといわれている場所に近い。
そういえばどんな妖怪に彼は襲われたというんだろうか?
博麗の巫女や黒白の魔法使いが退治したという噂も聞かないし、どうなっているか後で調べるか。
そんな風にとりとめもなく思考を巡らせていると、
「一つ言っておくことがあるわ、藍」
なんでしょうか?
「貴女、○○が只人だっていってるけれど、彼は一般人じゃないわ」
そうでしょうか?
私が知る限り、○○は何かを信仰していたわけでもなく、仙道の修行もしてもいません。
弾幕も撃てなければ、空を飛んだりもできません。
だとすれば、一般人といっても差し支えないと思うんですが。
奴の運動神経、というか身体のキレは、どう贔屓目に見ても幻想郷の一般人レベルだ。
ひょっとするとそれより低いかもしれない。
妖怪退治を生業としている者たちとの比較だと、話にもならない。
「それは一面を見ているだけにすぎないわ。いいこと――」
紫様は子供に言い聞かせるような優しげな声音でおっしゃった。
「――普通の人は八雲家に繋がっているはずのスキマを潜って、成層圏から落ちたりなんかしないわ」
身も蓋もない台詞ですね。
いやまあ、確かにそういう意味ではそうなんですけど。
ちなみにその時の最終着地点は霧の湖で、盛大に水柱が立つような飛び込み方だったという。
こう、胸からびたーんと。
全治1週間だった。
何か色々と間違っているような気もするが、まあ○○だし。
…………。
……ちょっと待て。
○○は変人だから、変なことが起こって……。
ああ、そういうことか。
ここで私は紫様の言わんとすることに気づいた。
確かに○○って只人じゃあないですよね。
人間の限界を超越した、というか逸脱したようなところがありますし。
ゴキ並みのしぶとさというか、生き汚さが特に。
「……何だか酷い言われようね」
紫様の胡散臭い笑みを浮かべた頬に、一筋汗が流れ落ちた。
「どうやら貴女にも解ったかしら?
確かに○○の身体能力は普通の人並みにしかないわ。
だけど藍の言うように生命力もそうだけど、彼の精神の強靭さだって妖怪並みに並外れているわ」
妖怪並って……。それはそれで酷い物言いのような気がします、紫様。
いやまあ、確かに奴の日々の仕事振りを私も知っているから、妖怪扱いは分からないでもないですが。
思い出されるのは、週刊で3冊、月刊で1冊の漫画を助手なしで週末までに描き上げる大馬力。
それでいて週末には必ず紫様との逢瀬を楽しむのだ。
一体奴の一日は何時間あるんだろうと思わないでもない。
そしてこの大馬力を支えているのが、変態的な体力と精神力なのだろう。
「彼の精神が鍛えられている原因は分かるかしら?」
ええ、その程度なら。
おそらく彼は私や紫様のような強力な妖怪と共にあることで、自然と鍛え上げられたのでしょう。
聖人の傍に仕える従者が、永く共にある内に聖者に近づくように。
よくできましたと言わんばかりに、紫様は満面の笑みで頷かれた。
「その通り。○○は私たちと一緒にいることで、尋常ではないほどの鍛錬になったようね。
幸か不幸かは分からないけれど」
ふと、この日常生活を要因とした精神鍛錬というところに引っかかるものがあった。
このタイプでいけばもう一つ、○○の精神を自然と鍛えているものがあることに思い至った。
けれども、それを口にするのは、ちょっと憚られるものがあった。
だってアレだしなぁ。
私自身、それを具体的に想像するのは、ちょっとだけ悔しいというか羨ましいというか――
兎に角あまり楽しい気分にはならないのは確かだった。
「あら、藍ったら、何不満そうな顔をしてるのかしら?」
で、当然そんなことを考えていたら、紫様に見咎められるわけで。
私としては報告にかこつけて……、もとい、問われたのならば、式として答える義務が生じるわけである。
あー、そのですね……。
後、○○と紫様の閨でも意外と鍛えられてるかもしれないと思っただけです。
不満なんてないです。ええ。
「ああ……うん。そ、そうね。
確かに藍の言うのもあるかもしれないわね」
思わぬ私の揶揄に、紫様はぎょっとなさる。
頬を真っ赤に染めて視線はキョロキョロ、口調はしどろもどろになる。
とはいえ、そんな風になっても私の言葉を理解し、発言内容を肯定なさっているところは、実に紫様である。
こういったちょっとしたことで紫様が可愛らしくなることを知っているのは、おそらく私と○○のみだろう。
何だか最近私は、それがとても嬉しく感じるのだった。
私の視線を感じたのか、紫様は照れくさそうに視線を逸らされた。
妙な空気が二人の間に流れる。
やがて、こほんと咳払いをしてその空気を振り払うと、紫様は話を戻された。
「現在の○○が尸解しても魂のみでも生きている、という理由は理解できて?」
はい。ですが、そうなるとまた疑問が出てきます。
魂魄のみで生きていられるのならば、何故○○は一向に姿を見せないのですか?
自身の現状が理解できているのなら、甦るために助けを求めにやってきてもいいではないですか。
すると紫様はこいつ何を言っているのかしらんといった様子で、まじまじと私の顔を覗き込んできた。
紫様がなじるような視線で見つめてくる。
あれ? 何か拙いことを言ったかな?
「そんなの決まってるじゃない。
今彼の身に起こっているのは、様々な条件が重なった上での偶発的に起こった尸解。
決して正当な手続きを踏んだ末の尸解というわけじゃないのよ。
だったら仙人の身体を再構築する方法どころか、自身に起こっている状況すら理解していないはずよ」
……言われてみればそうですね。すいません。
我ながらあまりにも間抜けな疑問だったことに気づいて、私は小さくなった。
どうやら私はそんな単純なことにも気づかないほど混乱していたようだ。
「今、○○は幻想郷のどこかにいる――というかどこにでもいるという状態よ。私にはそれが感じ取れるわ」
私にはそんなものは全然感じ取れません。
おそらく『境界を操る程度の能力』を持つ紫様だからこそ、感じ取れることなのだろうが。
紫様がおっしゃるには、○○は今、幻想郷の隅々にまで風よりも薄く解け消えている状態なのだという。
○○の死体が墓場から消えてしまったのは、墓泥棒が出たはわけではなく、死肉喰らいが出たわけでもない。
彼の屍は解け消えた魂魄に引きずられたか、より人外に近い存在になってしまったが故に、塵となって消えたのだろう。
尸解した時によく聞く話だ。
そして現在、紫様はその薄くなっている○○を、どうにかして復活させようとなさっているのだ。
具体的に証拠を提示されたわけではないが、今まで主につき従ってきた状況を省みるに、そうとしか考えられなかった。
紫様が懐から白っぽい小さな物を取り出すと私を呼び寄せ、それを私に預かるように命じられた。
これは……?
どこかで見たことのある物だった。
「○○の骨よ。棺桶の底に転がっていたの」
ああ、なるほど。
○○の棺桶から拾い上げていたあれですね。
二人で墓荒らしをしていた時に、紫様が○○の亡骸が入っていた棺桶から何やら拾っていたのを思い出した。
あれがこの○○の骨だったのだろう。
尸解したにも関わらず、骨を残すような不手際があったというのは、ちょっと珍しいことだ。
まあ、今回は修行も準備もせずに敢行した尸解だからこそ起こった、珍しい事例なのだろうけれど。
主のなさろうとしていることが、私にも分かる。
紫様はそれを使って○○を再生しようということなのだろう。
「流石に何の媒体もなしに彼を復元することは難しいから、これを核にして魂魄の定着を図るわ。
あの人は私の能力を受け付けにくいから、このくらいの補助は欲しかったの」
まあ、そうでしょうね。
元々自分の身体の一部だから、定着はし易いだろう。
また、これは幻想郷中に霧散している○○の魂魄を呼び寄せる誘蛾灯の役目も果たすはずだ。
二重の意味でもこの○○の骨は、彼の復活に必須の物に違いあるまい。
と――
ここまで考えたところで、私は紫様の行動に不可解なものを感じた。
それは何故私をここまで連れ回したのか、ということだった。
実際のところ、彼が生きている証拠を確認するだけなら、紫様お一人でも可能なのだ。
そして○○を復活させるのだって同様だ。
私がそれを補助したとしても、今回に限ればほとんど役には立たないだろう。
まあ、うどんに振り掛ける薬味程度には効果はあるかもしれないが。
「あら。貴女にも、彼の現状を知らせた方がいいと思って連れてきたんだけど、必要なかったかしら?」
私の愚痴めいた発言に、紫様はからかうようにおっしゃった。口元には胡散臭い笑みを浮かんでいた。
そう問われたら、私としては有難いことですと返すしかなかった。
本来ならば結果のみ私に伝えればよいはずなのだ。
それを私の○○に対する想いを紫様は理解なさっているが故に、ここまで厚意を示してくださったのだろう。
これが有難いといわなくて、何といえばよいというのか。
まあ紫様のことだから、今おっしゃったこと以外にも二重三重の意味を持たせているのだろうけれど。
「それじゃあ、日の出と共に始めるわ」
スッと目を細めて精神を集中される紫様。
普段ならしないような真剣な表情。
能力が効きづらいというのは、そこまで大変なものなのだろう。
ひょっとして奴のこの妙に限定された能力って、紫様と一緒に居すぎたせいで発現したものだったりするんだろうか?
ずっと共にあって、いつの間にか境界を操られることに耐性がついた、とか。
もしこの予想が正しいとたら、それは何という不運なのだろう。
互いの心が近づきすぎたが故に、それ以外のところで拒絶反応が出てしまう……。
………………。
……いや、『それはそれで燃える!』とか言い出しかねないな、奴は。
○○の反応を考えてみて、そんな風な回答を導き出した私は、思わず小さく笑ってしまった。
あまりに突拍子もない答えだった。
そして、とても○○らしい台詞だった。
私の集中が途切れていることに気づいた紫様が、咎めるようにギロリと横目で睨んできた。
すいませんすいません。真面目にやります。
慌てて私も意識を集中し、○○の骨を握りこんで祈ったのだった。
○○。帰って来い。
私たちはずっと待っているんだぞ。紫様も心配している。
帰ってきてくれたら、腕によりをかけたご飯をご馳走しよう。
それから、皆で花見に行こう。
花はもう散ってしまったけれど、たぶん一緒にいるだけで楽しいだろうから。
それから――
二人で祈る。
祈る。祈りを籠める。
そうして気がついた。
日の出から輝きがこぼれ落ちている。
私にも分かる。
○○がそこここにいるのが――
そうしてついに――
───────────────────────────────────────────────────────────
時折吹く柔らかな風。
細雪の如く舞う桜が雅な境内。
春先の日差しが心地よい。
ここ博麗神社の縁側では、真昼間から酒宴が催されていた。
「……というわけなの。酷いと思わない?」
「ハイハイハイ、そうね」
博麗の巫女はやる気のない相槌を打ち、紫様から視線を逸らすと、やれやれと嘆息した。
うんまあ、朝にいきなり訪ねてから今までずっと付き合わされてきたのだから、彼女がそうなるのも無理はないだろう。
私としても主に代わってすまないと言うしかない。
「あ~……まあ、あんたらがどこで酒盛りをしようが、私が迷惑を被らない限り何も言うつもりはないんだけどさ」
「あら心外ね。せっかく美味しいお酒を持ってきてあげたのに」
「酒だけ置いてとっとと帰れ」
「それこそ心外だわ。
私はここに花見にかこつけて愚痴を言いに来てるんだから、そんなことするわけないじゃない」
ここに来た目的を恥ずかしげもなく言い切る紫様。
本音を隠しもしないところを見るに、相当酔いが回っておられるようだ。
紫様は時折素面ででもこういう身も蓋もないことをおっしゃることがあるが、今回は深酒の結果だろう。――おそらく。
博麗の巫女は頭痛がするのか、しきりに眉間を指で揉んでいた。
私が彼女と同じ立場だとしたら、同じようになっていただろうことが予想できるから、素直に同情する。
紫様の突拍子もない行動は今に始まった訳ではない。
私たちがここにいる発端は、マヨヒガの縁側で自棄酒をかっ食らっておられた紫様の思いつきだった。
突然――
「花見にいくわ」
と宣言された。
身構える暇もあればこそ。
あっさりスキマに吸い込まれた私たち。
次の瞬間、目の前に広がっていたのは、見慣れてはいけないのに何故か見慣れてしまった場所――博麗神社だった。
博麗の巫女に事情を説明される紫様。
勿論○○と喧嘩してしまい、その愚痴を言いに来たなどとは言わない。
ただ、花見に来たとだけおっしゃられていた。酒の入った徳利をユラユラと揺らしながら。
博麗の巫女は紫様の発言に裏がありそうな気配を察していた様子だったが、表立っては何も言わなかった。
というか、むしろ――
「おっけー」
酒の魔力に自ら誤魔化される始末。
これにはツッコミを入れるべきか、それとも彼女の性質を知った上で、手玉に取った紫様を讃えるべきか私も悩んだ。
そうして始まる酒宴。
橙は開始早々に酒精の強いものをカパカパ鯨飲し、早々に酔いつぶれてしまっていた。
ある意味これは自棄酒をかっ食らう紫様への正しい対処方法かもしれない。
少なくとも紫様の口から延々の溢れてくる不毛な愚痴を聞かずに済むのだから。
一方の博麗の巫女は始まってしばらくして、しまったという顔をしていた。
紫様が何しに酒を持って来たのか理解したようだ。
だがすでにその後悔は手遅れだった。いや、手遅れだから後悔というのだけれども。
大量の酒を周囲に侍らせ、紫様がすぐ隣に陣取った状態ではとてもではないが逃げられそうになかった。
こうして博麗の巫女は今の今まで、ぐだぐだとくだを巻く紫様の相手をしていた。
そして私は何をしているかといえば、紫様の相手を博麗の巫女に任せて、横で二人の様子を傍観していた。
紫様の愚痴を直接聞かされずに飲める酒の何と美味いことか。
しばらくは彼女に紫様の相手をしてもらうことにした。
「――でね、○○ったらこう言うのよ……って、ちょっと、聞いてる? 霊夢」
「ハイハイ聞いてるわよ。
床の上の○○は意外としつこいとか、毎晩じゃあ身体が持たないっていいたいんでしょ。
実は紫って恵まれてるんじゃないかって、引っ叩いてやりたいと思わないでもないけど、ちゃんと聞いてるわ」
○○に対する不満を口にする紫様にてきとーに相槌を打ちつつ、周囲にある酒をかっ食らう博麗の巫女。
と――
紫様が酒精に負け、ついにウトウトとし始めた。
「ん~。聞いてるんだったらいいんだけど…………え~っと、何だったかしら」
「ちょっと休憩したら? いい加減、かなりの量飲んでるわよ」
「そうぉ? ……まあ、霊夢がそう言うんだったら、言う通りにしようかしら。
じゃあ、ちょっと横にならせてもらうわ」
博麗の巫女がここぞとばかりに寝てしまえと勧める。
いつまでも自棄酒につき合わされちゃあ精神衛生上良くないし、彼女のそうした行動は分からないでもない。
ぼんやりとした様子で勧めを受け入れる紫様。ぽてっと博麗の巫女の太腿を枕にして横になる。
十秒も経たない内に紫様は寝息を立て始めた。かなり酔いが回っていたようだ。
やれやれ、ようやっと静かになったな。
「あんたも色々大変よね」
紫様を膝枕したまま、ぐいっと酒を呷る博麗の巫女。
何気に彼女もかなりの量を飲んでいる気がする。
実は博麗の巫女もこの席は自棄酒だったりするんだろうか。どうでもいいことだけれども。
「私が飲む量なんて、他の奴らに比べたら高が知れてるでしょ。
というか紫の惚気話に付き合ってあげてるんだから、正当な報酬よ」
確かに聞かなくてもいい他人の惚気話を聞かされるのは、あまり気分のよいものではないな。
……というか霊夢、これが惚気話だとよく分かったな。
紫様は○○の気の利かなさとか、身勝手さの不満しか口にしていなかったんだが。
「あのねぇ……。これが惚気話でなくて何だってのよ。少なくとも私は色んな意味でお腹いっぱいよ」
はっは。こんなもので二人の仲に中てられていたら、到底最近の紫様の相手はできないぞ。
少なくとも○○が居る時のマヨヒガでは、二人がイチャつくのは日常茶飯事なんだからな。
「そいつはご愁傷様。
けど、○○が紫の言ってるような、自分の利益だけしか考えていない奴だったら、ここまで紫が不貞腐れるわけがないわよね」
確かに……。
本当に○○のことが気に入らないのだったなら、別れて何でもない間柄になればいいのだしな。
「そういうこと。
気に入らないとか言っときながら、実は『こんな問題だらけの男なんて皆いらないでしょ』って牽制してるんだから……」
面倒くさいったらありゃしないわ、と鼻を鳴らしてから酒をくいっと呷った。
手酌で酒を注ぐ。
なみなみと注がれた盃に口を持って行き、溢れそうになった酒を啜る。
「今回紫が不貞腐れてるのだって、要は○○がウチで結婚式を挙げるんだって勝手に決めたのが原因だろうし。
ウチに来たのはそのことへのあてつけでしょ」
博麗の巫女は紫様の頬をムニムニと摘んだ。
――って。
待て。霊夢。
今、何と? 私の聞き違いでなければ、結婚式がどうのと聞こえたんだが。
「あら? ひょっとして知らされてなかった?」
知らされるも何も。そんな話、初耳だ。
私は素直に彼女の問いに肯定の意を返した。
博麗の巫女は私の作った揚げ出汁豆腐を箸で小さく切り分けると、口へ運んだ。
意外と美味かったのか、口元を綻ばせた。
そして酒をちびりと啜る。
「少し前に○○が来てね、縁ある博麗神社で結婚式を挙げたいと言ってきたのよ。
私としては断る理由なんて色々な準備が面倒臭いってこと以外にはないから、引き受けたんだけどね」
かなりの実入りが臨めそうだからというのもありそうだな。
「否定はしないわ」
うわ。あっさりと認めた。
一体どのくらいの金額を提示したのか問い詰めてみたい気もしたが、後で○○本人に訊ねればいいことに気づいて、ここは流すことにした。
いやしかし……うん、そうか。○○もついに決めたんだな。
二人の仲をずっと見守ってきた身としては、ようやっとというか、ついにという思いだ。
○○も口では結婚しようと言い続けてきたが、それを行動に移す様子がなく、私はそのことにやきもきしていたのだ。
奴が行動に移したのなら、私だってそれを支援するのにやぶさかではない。
寧ろ全力で二人の結婚を支援するつもりだ。
紫様が結婚を躊躇っているのは、いつか必ず来るであろう○○との別離を突きつけられることであって、共にあることではないのだし。
いや、この際だから紫様のことは置いておこう。
○○が決めたというのなら、私が反対する理由など全くない。
むしろ『二人の恋路を邪魔する奴は馬に蹴られて……』というやつである。
そんな感じで私が○○への応援について考えていた時だ。
ふと、博麗の巫女が悪戯っぽい視線を投げかけてきていることに気づいた。
「まあ、あんたとしたら狙ってた男が当初の予定通りに紫のものになっちゃったんだから、ご愁傷様ね」
博麗の巫女の言葉を聞いて、私は不愉快な感情を隠すことなく彼女を横目で睨んだ。
確かに私は○○が好きだ。
二人が結婚してしまうと、この想いは決して成就することはなくなるのだ。……成就してどうするという話もあるが。
だが、ここに至ればそんなことなど、私にすればどうでもいいことだった。
酒で唇を軽く湿らせてから盃をそっと脇に置いた。
私は胸の中の想いに決着をつけるため、そして彼女の発言の誤りを指摘するために口を開いた。
ふん。余計なお世話だ。
言っておくが、紫様と○○が結婚したからといって、私と○○の関係が変わることはないぞ。
それに、もし仮に今までの関係が御破算になったのだとしても、また新しい絆を作ればいいのだしな。それは私にとっては願ってもないことだ。
まあ、おそらく私たちの関係は変わらないだろうけどね。
今までの私たちの関係を表すとしたら、それは親友であり、紫様を敬愛する同志だ。
さらにここに家族という絆が加わるんだ。むしろ二人の婚儀は大歓迎さ。
「……まあ、あんたがそう言い切るんなら、それでいいんだけど」
それでいいんだ。私と○○の仲はそれ以上の何物でもないさ。
博麗の巫女はつまらないことを聞いたとばかりにフンと鼻を鳴らした。
そして彼女がすっと差し出した徳利に、私は盃を持っていった。
私は盃の中の酒をぐいと飲み干した。
先程と変わらぬ酒のはずなのに、何故かそれは渋くて酸っぱくて。ちっとも酔えそうになかった。
それからしばらく、私たちは他愛ない話をしつつ、盃を交し合っていた。
博麗神社の例大祭のこと。
賽銭の入りは○○のものを差っ引けば、相変わらずなのが不満なこと。
今年の籾巻きは例年よりも早く終わったことなど、様々なことを時間も忘れて話していた。
そう。私は○○を護衛するというここに来る前の使命を忘れて、自棄酒を飲んでいたのだ。
これが後にどういうしっぺ返しを食らうことになるかとも考えずに……。
ふと会話が途切れた。
博麗の巫女が空を見上げているのに釣られて私も同じように空を見上げると、そこには春にしては珍しい雲一つない空。
――そこに黒いシミが一つ。
……何だ?
目を凝らしてみる。
次第にシミだったそれの輪郭がはっきりしてきた。
黒い服に白いエプロン、あと三角帽。
その特徴的な格好。そして猛烈な速度で高空を滑空する箒には見覚えがあった。
「……魔理沙ね」
そのようだな。
ひょっとして私たちが酒盛りしているというのを聞きつけてやってきたんだろうか。
「萃香じゃあるまいし。
いや、魔理沙ならありうるか。あいつのそういうことに関する勘は意外と鋭いし」
などと二人して魔理沙について悪口を垂れている内に、件の噂の主が到着する。
桜の花弁が箒から発生する魔力の突風に煽られて上空に巻き上げられた。
境内に敷き詰められた玉砂利が、尋常ではない速度のまま突入してきた魔理沙に吹き飛ばされる。
なんともはや。
あ~。この光景に到着という言葉を使うのは、到着という言葉に失礼だな。
言い直そう。
噂の主、霧雨魔理沙が博麗神社に着弾した。
「ちょっと魔理沙。いきなり何してるのよ」
「悪ぃ、急いでたんだ」
物凄い剣幕で睨みつける巫女に、魔理沙は悪びれた様子もなく片手を挙げて謝罪の意を示した。
魔理沙はそこで我々八雲家の面々が博麗神社にいることに気づいたらしい。何故かハッと息を飲んだ。
その鳶色の瞳を爛々と輝かせて、突然こっちに向かって走ってきた。
「おいッ! お前ら何してんだ!?」
その剣幕に一体何事かと目を白黒させる。
「一体何をそんなに騒いでるのよ。この世の中、そう急ぐことなんてありはしないわよ」
「馬鹿ッ。こっちは危篤で急いでるんだ! ああ、もう! 何でこう、今日に限ってこんなにタイミングが悪いんだよ!」
一向に落ち着かない様子の彼女に、私たちは顔を見合わせた。
何やら切羽詰っている様子であるのだが、その理由がさっぱり見えてこなかった。
危篤がどうのと言っていることから、知り合いが災難に遭ったのだろうというのは理解できるのだが……。
魔理沙は私たちに構わずに巫女の膝枕で寝息を立てている紫様に詰め寄ると、肩を揺さぶった。
「おい、紫、起きろ! ○○が緊急事態だ! 起きろ!」
「……何事よ、もう。人が折角いい気分で寝転がってたのに」
「○○の命の危険が危ないんだ。急げ!」
すっと紫様の朱をさしたようだった頬が平静のものに戻る。
おそらく『酔いと素面』の境界でも弄られたのだろう。
紫様の表情が不愉快そうに歪められる。
「あのね、魔理沙。私そういう冗談は好きじゃないの」
「誰がこんな笑えない冗談言うか。ああ、もう。いいから永遠亭に急げ!」
「……分かったわ。永遠亭に行けばいいのね。
言っておくけど、何もなったら――酷いわよ」
永遠亭に運び込まれるということは、それなりの傷を負ったということなのだろうと私たちは理解した。
なるほどそれは一大事だ。
今日のような護衛をしなかった日に限って怪我をするとは、なんと間の悪いことだろう。
私たちは○○の被った運に頭を抱えた。
それでも、永遠亭に運ばれたということは、まず助かったと見ていいだろう。○○の悪運は意外とあるのだ。
私たちは魔理沙に○○の状況を訊ねることもせず(そんな暇もなかったが)、永遠亭に運ばれたことに安心していた。
それは今思えば、永遠亭の薬師に対する過大な期待というものだった。
だが、この時の私たちはそんなことに気づきもせず、単純に安堵していた。
紫様はゆったりとした仕草で博麗の巫女の太腿から離れると、縁側と境内の間にスキマを作って、そこを潜った。
私たちもその後に続く。
本来なら魔理沙が来た時点で気づいておくべきだったのだ。
彼女の慌てよう、そしてそのエプロンに赤い染みが付着していたことが、一体どういうことを示しているのか、その時の私たちは全く思い至っていなかった。
そうしてやってきた永遠亭。
相も変わらず青々した竹林が鬱陶しい所だ。
「呼んできたぜ!」
魔理沙が盛大な音を立てて引き戸を開けた。
が、それなのに中の住人には誰にも責められる様子はなかった。それどころかやってきた兎たちは、安堵の表情をしている者が多い。
それほどまでに○○の容態は悪いのだろうか?
何故だか、えもいわれぬ不安が湧いてきた。
「どうぞこちらに……」
兎に導かれて通された部屋の中は、見たこともない器具や薬瓶が並べられていた。
アドレナリンの臭いが少しだけ鼻についた。
部屋の中には、やや疲労した面持ちの薬師とその弟子、あと弟子の恋人がいた。
「ああ、呼んできてくれたのね。ありがとう。――ああ、貴方たちは患者の具合を診てきてちょうだい」
魔理沙に礼を言った後、弟子二人にそう伝えて部屋から下がらせる。
弟子二人はあれこれ相談してから、幾つかの薬瓶をから薬剤を持ち出していった。
「……さて、貴女たちにはこっちに来てもらおうかしら」
私たち――というよりも紫様を見据えて八意医師は、何かの感情をこらえた目をしたまま言った。
ついてきなさい、と奥の部屋に誘導する。
ぞろぞろとそれについていく私たち。
通された部屋は殺風景で、どこか冷たい印象がした。
薄暗くひんやりとした部屋にただ一床のみあるベッドが、そう思わせているのかもしれない。
何故か血の臭いがした。
「…………え……?」
誰の声だったのだろう。
それを見た瞬間、誰かが呆然とした声を漏らした。
ベッドの上に横になっている人影がいる。
誰かと思うまでもなく分かる。○○だ。
見た目は静かに眠っているようだ。
傷などもなく、治療は無事済んだのだろう。
相変わらず見事な腕だ。
そう、ホッと胸を撫で下ろした時だ。
「残念ながら、もう息はないわ」
理解できない言葉が頭上を掠めていった。
――は……?
「○○の肉体はこの通り完全に元通りにはできたわ。だけど二度と心臓が動くことはなかったの」
「は、はは。おいおい、笑えない冗談はやめといた方がいいぜ」
「……こんな悪質な冗談は言わないわ」
魔理沙が無理矢理に笑おうとして、八意医師がそれを否定する。
博麗の巫女は静かに黙祷していた。
私は何も考えられないまま、○○の傍に歩み寄った。
彼の頬に手を当てた。
この間キスをしようとした時と同じように、その頬は少しかさついていたが適度に柔らかかった。
調子に乗って、そっと青白くなってしまった唇を――初めて触ることに成功した。
だが、そんなことをしているのに、まったく心臓はバクバクとしないし、顔だって熱くなってこなかった。
きっとこれは○○の体温がこんなにも冷たいから、それが私に伝染したに違いない。
そう思い……。
そう思って……。
零れ落ちそうになる涙をぐっと飲んだ。
まだ○○の死因やどうしてここに運ばれたのかなど、何も分かっていないのだ。泣き喚くにはまだ早い。
今は、まだ、早い。
そう自身に言い聞かせて、感情を抑え込んだ。
そうして――
ふと、そういえば紫様はどうしたんだろうかと思った。
さっきから無反応で、一体どうしたんだろうか?
そう思って主に目をやると――
「…………ふぅっ」
ああっ。紫様っ!?
額に手の甲をやったまま紫様は卒倒された。
────────
○○との別れは本当に唐突だった。
去来するのは、日常交わしていた○○との益体もない会話の数々。
紫様がいて、私がいて、橙がいて、そして○○がいて。
この日常がずっと続いていくものだとばかり思っていた。
そう。この日常こそが奇跡の産物だったのだということにも気づかずに。
紫様が冷たくなった○○の傍らに立ちつくしている。
正気を取り戻された紫様が次になさったことは、○○に直接会うということだった。
永遠亭の薬師は特に引き止めるような素振りは見せなかった。
その理由を彼女は身近な者との別れを最も印象付けるのは、直接会って確かめることだと言っていた。
また倒れられては困るので、私も主の後について行くことにした。
紫様は彼の顔を抱きかかえるようにして身を寄せると、乱れた前髪をいとおしむようにして指先でそっと整えられた。
○○の頬にご自身の頬を重ね合わせる。
だが、どんなに撫でようが擦ろうが、○○の目は開くことなどなかった。
紫様は金の双眸に涙を湛えたまま、ボソボソと愛する人の耳元で何事か囁かれた。
紫様の感情が式を通して私に流れ込んでくる。
哀しい。哀しい。哀しい。
胸が痛い。胸が痛い。胸が痛い。
私は思わず目をとじた。正直、見ていられなかった。
私は紫様についてきた目的も忘れて、思わず外へと出ていた。
引き戸にそっと背中を預けると、天井を見上げた。
言葉もない。言葉が出ない。
身を切り刻まれるような切なさに身をさらされながらも、私はぐっと唇を噛んで涙を飲み込んだ。
私は紫様の式だ。主に断りもなく主の替わりに涙を見せるわけにはいかない。
そう自身に言い聞かせ、私は紫様が出てくるのを待つのだった。
まあ、それからのことは大して面白いものでもない。
親しい知人との別れが済めば、あとは残った遺体の処分だ。
○○は外から来た人間だから、身寄りもない――つまり家系の墓に入らずに無縁仏として扱われたそうな。
執り行われた葬式は空虚であったが、しめやかなものだったという。
私が何故伝聞調で言っているかというと、実際には立ち会っていないからだった。
本来なら紫様が喪主として執り行った方がよいのだろうが、現実的なしがらみから、それは出来ぬ相談だった。
強力な妖怪である私たちは人に畏れられる存在だ。
そんな立場の私たちが人里に堂々と侵入し、厳粛な式を乱すことは流石にやってはならないことだと理解していた。
力ある存在に付き纏う責任とか役割というやつだ。
前述したしがらみと言い換えてもいいかもしれない。
――というのが表立っての葬式への不参加の理由だ。
ちなみに表立ってということは裏があるということで。
博麗の巫女やら幽々子様など幻想郷の力ある立場の者たちには、それとなく知れ渡っていることだが――
実は、永遠亭から帰宅して以後、紫様が部屋に引き篭もったまま出てこなくなったのだ。
現在、紫様の部屋は入口と出口の境界を弄くっておられるせいで、中に入れなかったりする。
紫様の引き篭もりを知っている方たちは、それほどまでに○○との別れはショックだったのかと同情を向けてくれている。
有難いことだ。
私自身、彼女たちの向けてくれる同情によって、心に受けている負担は幾分かは和らいでいる。
話を戻そう。
紫様の寝室の前に食事を置いておくと、いつの間にやら食べ終えた食器が台所に積まれているので、きちんと食事は召し上がってはいらっしゃるようだ。
気がついたら干乾びている主を発見というような心配はなさそうなので、その点だけは安心していた。
ああ、そういえば○○の死因を説明していなかったな。
薬師が言っていたことを纏めるとこうだ。
一、直接の死因は心臓の損傷による失血死。
二、傷の具合から見て、おそらく○○を襲ったのは妖怪だと思われる。
どうして真昼間から妖怪が○○を襲い、重症を負わせただけで済ませたのかとか。
普通、妖が人を襲ったのなら、その肉を食べるだろうとか。
博麗の巫女の作った厄除け符は効果がなかったのかとか。
疑問は幾つかあったが、ここではひとまず置いておくことにした。
そんなことよりも重要なことがあった。
それは永遠亭のチート薬師の手によってですら蘇生に失敗したという事実だ。
私が何が起こったのかと疑問を呈してみると、薬師はおそらくだけれどと前置きをして答えた。
「蘇生しなかったのは、魂魄が幽体から剥がれ落ちたからでしょうね。
回復状況を鑑みるに、少なくともウチに来た時にはまだ肉体には魂魄はあったはずなんだけど……。
どうして剥がれたのかは不明ね」
薬師はそうトンデモないことを口にした。
魂魄が剥がれ落ちる。
死者となった者は、肉体から魂を天に魄を地に遣ることで次なる世界に輪廻することになる。
まあ、輪廻する前に魂は三途の川を渡って閻魔――幻想郷においては映姫様――の裁きを受けるわけではあるが。
ちなみに紫様が『生と死の境界』を弄くって死者を生き返らせたりできるのは、映姫様に裁かれる前までである。
いや、輪廻の途についてからでもできないわけではないだろうけれど、それは判決を反故にされることを望まない映姫様の意思に反するわけで。
となると無理に押し通ろうとすれば、お二人が激突することは避けられないわけだ。
この世とあの世の境界を操作し、幻想郷のこの世にあの世を現出せしめ、○○を蘇らせようとなさる紫様。
対する映姫様は曖昧になった彼岸と此岸の境界を白黒はっきりさせることで、元に戻そうとする。
そうはさせじと白と黒の境界を曖昧にして、映姫様の能力一時的に封じる紫様。
だが、映姫様もその程度で引っ込むようならそもそも閻魔などやっていない。曖昧と曖昧でないものの白黒をつけ、全てを正道に正していく。
紫様は正しいものと正しくないものの境界を操り、映姫様は全ての境界に白黒をつけて歪みを正す……!
お二方の能力がせめぎ合い凌ぎ合い、ぶつかりあった余波が幻想郷に襲いかかる。
そうして気がつくと――
そこには全てが生きながら全てが死んでいるという、混沌とした地獄がそこに現出しているのであった……。
…………。
ひぃっ。今、とっても嫌な未来が見えた!
却下だ却下。
紫様も老獪なお方なのだから、その辺はきっと理解し、分別されておられるだろう。うん、そうに違いない。
閑話休題。
そうして紫様が部屋に引っ込まれてから二週間が経った。
未だ紫様は出てこない。
そろそろ何とかして、紫様を引っ張り出す方法を考えなければならないだろうかと、そんな心配が私の胸に頭をもたげ始めていた。
気がつくと、幻想郷の景色は桜の花弁が散る季節から、若葉萌ゆる季節に変わろうとしていた。
私は縁側に腰掛けて、いつもの仕事である幻想郷に張り巡らされた結界の様子を確認していた。
今のところ特に結界に綻びはなく、整えなければならない歪みもなかった。
橙も外へ遊びに行っているし、外から何かが迷い込んでくるような兆しもない。
まさに長閑で平和な日だ。
どこにも○○がいないということを除けば……。
ふう、と私は気の抜けた溜息を吐いた。
どうにも胸にぽっかりと空いた思いがやるせない。
このまま日がな何もない日々が続いて、いつの間にか○○のことも思い出として受け入れていくことになるんだろうか。
記憶はいつか風化し、セピア色をした思い出になっていく。
そう、それは仕方がないことだ。
私たち長命な者はそうして生きてきた。そしてこれからもそういう生き方をしていくのだろう。
だが今は、それが何だか自身の想いに裏切られたような、そんな気分なのだった。
ふと――
夕闇の帳が下りる時刻、近くに何者かの気配を感じた。
我に返り、意識をそちらへ向けた。
私は目を見開いた。
そこには紫様が立っていらっしゃったからだ。
少し、頬がやつれていらっしゃるようにも見えたが、その美貌は些かも減じてはおられなかった。
紫様は小さく首を傾げ、愛らしい仕草でおっしゃった。
「藍――」
はい、紫様。ようやっとお出になられたんですね。
安堵で私はやれやれと肩を落とした。
良くも悪くも、これで一歩前に踏み出したのだと思ったのだ。
だが、現実はそんなに甘いものではなかった。
紫様は私の声掛けを無視して続けた。
「藍。○○は来たかしら?」
…………ッ!
私は息を呑んだ。
主の言葉を耳にした瞬間、私の背に冷たいものが流れ落ちた。
そんな馬鹿なという思いと、さもありなんという相反する思いが去来した。
紫様の○○への想いは、その心を壊してしまうほどに強かったのか。
否、この程度の精神的打撃など、大妖怪、八雲紫にとればどうということはないはずだ。
胸中の一瞬のせめぎ合い。
私は一度深呼吸して内心の動揺を抑え、姿勢を正して主の問いに答えた。
紫様、○○は死んでしまったので、もう……二度とマヨヒガに来ることはありません。
「……そう。遅いわね。ずっと待っているのに、何をしてるのかしら」
紫様は私の言葉を聞き流した。
扇子を頬に当て、童女のように可愛らしく小首を傾げる様が逆に哀れを誘う。
「一体どこで道草食ってるのかしら?
まだ来てないとなると……そうね、行ってみようから」
どこか焦点の合わない遠くを見つめているような、精神の平衡を失ったかに見える眼差し。
泣きたくなった。
だが、現状は泣いていてはどうにもならないどころか、むしろ危機的状況だ。
紫様が本当に心を病んでしまわれているのであれば、早めになんとかしなければならない。
より精神を主に置く妖怪にとって、精神の崩壊は存在自体の危機である。
もしそのまま病状が進行して紫様の身に何かご不幸があれば、幻想郷の人妖のバランスが崩れてしまいかねないからだ。
私の心配をよそに、紫様はいつもの調子で扇子をすっと振って空間にスキマを広げられた。
出掛けられるのですか?
「ええ。ちょっと博麗神社とか人里に、ね」
にこやかに行き先を告げられる紫様。
って、は? え? ちょっと!?
人里に行かれるんですか? それは色々拙いんでは……。
「確かめたいことがあるのよ」
確かめたいこと、ですか?
博麗神社や人里で調べたいことがあるなんて、一体なんだろうか。
私にはさっぱり思いつかなかった。
「まあ、私が直接人里に入るのが拙いと思うのなら、藍に調べてきてもらってもいいんだけど」
いいですけど。一体何を調べればいいんです?
「○○が挨拶に現れたかどうかを、彼と親しくしていた人に訊いてもらえるかしら。
ああ、勿論、今すぐ行けと言っているわけじゃないわ。
そうね、三、四日後時にでも分かればいいわ」
また妙なことを言い出したな。
そんなことを訊ねても、普通返ってくるのは「来ていない」だろうに。
まあ、それで紫様の気が晴れるのならば、いくらでもするが。
紫様はじゃあお願いね。私は霊夢のところに行くからと言い残すと、そのままスキマに入っていかれたのだった。
さて、理由はよく分からないが、とにかく指令を受けたからには行動しよう。
まあ夕飯のおかずを買いに行きがてら、調べることにするか。
それから三日後――
ようやっと結果が出た。
意外と○○の人里での交友範囲は広くて、里を端から端まで歩くことになったしまった。
里の人たちの私を見る目は、大きく分けて二パターンあった。
私と○○の関係を知らない者には、その関係を説明した。
要は○○の恋人の紫様の式だということだな。
それに対して、里の人の反応は私たち妖怪のせいで○○が死んでしまったと嘆き、怒る者。
愛する者が突如奪われ、さぞやつらい思いをしていることだろうと、同情の目を向けてくれる者だ。
比率にすれば6:4といったところだろうか。
どちらの反応にせよ、疲れることには変わりはなかったが。
で、だ。
結果は案の定「そんなものは来ていない」だった。
ようやっと調べきったところで夕食の席でそう紫様に報告すると、さして落胆した様子もなく――いや、むしろ当然といった様子で頷かれた。
だったら一体紫様は何を考えて、私に調査をさせたんだろうか。
さて、夕飯を食べ終え、湯浴みも終えて、縁側でゆったりしていた時だ。
「藍、出かけるわ。ついてきなさい」
否も応もなくスキマに吸い込まれた。
相変わらずの傍若無人。
そこに感動もしないし憧れもしないが、これでこそ紫様だと思うのは何か間違っているだろうか。
で、次に目の前に広がっていたのは、無数の四角く細長い石の列の並んだ場所――墓場だった。
周囲では私たちの妖気に中てられた霊魂がざわめき始めていた。
「何をボーっとしてるの。こっちよ」
紫様に急かされ、慌ててその後を追った。
足元に絡み付いてきた霊魂を振り払い、奥へと進む。
四半刻程テクテクと歩いただろうか。
私たちが辿り着いたのは、まだ真新しい卒塔婆の立った状態の土饅頭の墓だった。
紫様……これ、ひょっとして。
「ええ。○○のお墓よ」
私は思わず紫様のお顔を窺ってしまった。
紫様は私目を見つめ返し、軽く頷いた。
そうか、人の居ない時にお墓参りをされることにしたんだな、と私は納得した。
「――ということで藍、今からこのお墓を暴くから、見張り、お願いね」
…………は?
自身の耳を疑うような台詞が主の口から何の脈絡もなく漏れた。
ちょっ。待っ。紫様!?
紫様は私の制止の声を無視して右手を水平に構えられた。
ドドドッと低い呻り声を上げて弾幕が周囲に発生する。
「右よし、左よし。薙ぎ払え~ッ」
語尾に音符が付いていそうなエラく軽いノリで、盛られていた土を弾幕で吹き飛ばす紫様。
吹き上がった土砂に巻き込まれた卒塔婆が、半ばでへし折れて吹っ飛んでいった。
あー、あー、あー。
そうして出土する(この表現でいいのか?)棺桶の蓋。
「さあ、藍。人が来ないうちにとっととやっちゃうわよ」
いや、ちょっと、紫様? 一体何を……!?
私のうろたえる様子が可笑しかったのか、紫様は小さく微笑まれる。
紫様は残っていた土を掌で払うと、棺桶の端に無理矢理手を突っ込まれた。
湿った音を立ててめり込む紫様の指先。
ふと、そこでちょっとした疑問が脳裏をよぎった。
紫様に浮かんだ疑問を投げかけてみることにした。
「何かしら?」
どうしてわざわざこんな目立つ墓荒らしをなさってるんです?
棺桶の中の○○に会いたいのならば、スキマを開ければよいことでは?
紫様は丁寧に棺桶の蓋をひっぺがしながら答えた。
「念のためよ。○○ったら、肉体だけになっても私の能力を否定するんだもの」
何でも永遠亭で二人きりになったときに『生と死の境界』を弄くってみたらしい。
しかし、○○の肉体はそれを受け付けなかった。何回か試してみたものの、結局全て何も起こらないまま終わったのだそうな。
ああ、あの時のことか、と私は思い出していた。
私の胸がチクリと疼いた。
○○に抱きついて、なかなか出てこなかったのは色々試されていたからなのだな、と一人納得する。
そうして完全に蓋が棺桶から取り払われた。
中を覗き込む紫様。
その時、丁度月明りが棺桶の中に注ぎ込まれた。
私は息を飲んだ。
と同時に自身の目を疑った。
そこには腐乱を開始した○○の崩れかけた肉体があるはずだった。
あるはずなのだ。
それなのに――
そこには副葬品として入れられていた枯れた草花があるだけで、○○の姿はどこにもなかった。
いくら目を擦っても、頬を抓ってみてもその事実は変わらずそこにあった。
○○の死体がない。
棺桶に入れ忘れたのだろうか。
いや、そんな間抜けなことが起こるわけはあるまい。
だとすると、○○が生ける屍か何かになって棺桶から逃げ出した?
どうやって? 土は棺桶の上に被せられたままだった。
誰かが掘り起こして○○の肉体を奪った?
それこそどうやって?
というより、態々掘り返して奪ってから、もう一度何事もなかったかのように空の棺桶に蓋をして土を被せる、そのメリットは?
私が混乱しているのをよそに、紫様は棺桶の中に身を入れ、何やらごそごそとなさっていた。
何かを見つけたのか、紫様はそれを懐に収められた。
ちらと見えたものは親指の先ほどの大きさの小さな白い物体だった。
「さ。藍、次行くわよ」
そう――まるで○○と逢引していたときのような軽やかさで、紫様は身をひるがえされたのだった。
─────────
そうして紫様に連れられ、私が次に訪れたところはというと――
「……では、判決を申し渡します。
主文――被告は無賃乗車、斜め横断、食い逃げと無法の限りを尽くした。その罪はとても重い。
よって被告は地獄行きです。
しばらく法の何たるかというものを、その魂に刻み込むとよいでしょう。
それとですね……」
あー。もうここがどこかお分かりだろう。
私たちは幻想郷のあの世にある裁判所に来ていた。
現在、映姫様の行なっている審判が終わるのを、森羅殿で待っているという状況である。
相変わらず傍論の長い判決だなぁ。
朗々と判決文を読み上げる映姫様のお声を遠くに聞きつつ、私は出された茶をすすっていた。
一方の紫様はこの間一言も言葉を発することなく、茶に口をつけることもなく静かに瞑目しておられた。
といっても眠っているというわけでも、或いは瞑想しているわけでもなく、ただ目を瞑っておられるだけのようだ。
丁度いいので、ここで私は紫様に幽冥界を訪れた理由について訊ねてみることにした。
「あら、森羅殿に態々訪れる理由なんて、そう沢山あることじゃないでしょう。
だとしたら、藍にだってその理由は思いつくんじゃなくって?」
私が思いつくことといったら、それこそ○○を賭けての幽冥界との大立ち回りくらいしかないんですが。
ここへは○○の魂を取り戻しに、参られたのでしょう?
今までの紫様と○○の経緯を考えると、出てくる答えは自ずと決まってくる。
○○が死んだというのであれば、その転生先を探し出して逢いに行くに違いない。
そして転生先を最も手っ取り早く知ることができる場所が、幻想郷とこの世とあの世を結ぶここ幽冥界というわけだ。
問題があるとすると、紫様の目的とあの世の規則が真っ向から対立するということか。
紫様が輪廻の理を捻じ曲げて○○をこの世に蘇らせようとするならば、彼岸を支配する幽冥界は確実にそれを止めようと動く。
そうなれば待っているのは、八雲家と幽冥界の戦争だ。
というようなことを説明すると、紫様はしかつめらしく頷かれた。
「そう。藍がそう考えているのだったら、それが正しいのかもしれないわね」
ほ、本気ですか?
私のげぇっといわんばかりの表情を見て、紫様は苦笑なさった。
「この程度の言葉遊びで慌てないの。
私が何を考えてここに来たのかは、それこそ四季様がお見えになれば分かることなんだから、貴女は私の傍で泰然と侍っていなさい」
紫様は私にそう忠告なさり、大分温くなった茶に口をつけてすまし顔だ。
いやいやいや。
『泰然としていろ』って言われても、紫様が不安を煽ってるんじゃないか。
――と思わないでもないが、恐らくツッコんでも無駄に違いない。
紫様の面の皮は、そんなありきたりな文句程度では傷ひとつ付かないのである。
会話をしていて分かったことがある。
紫様は今回の訪問の目的に関する具体的な明言を避けようとしていらっしゃる、ということだ。
何か思うところがあるのか、それとも言いたくない気分なのか(おそらく前者だとは思うんだけれども、時折後者の可能性もあるから困る)。
とりあえずこれ以上は追及しても、のらりくらりとかわされることになるだろうというのは理解した。
話そうと思っていない口を無理矢理に開かせるのは至難の業だ。
そう理解した私は大人しく引き下がったのだった。
小半刻後、ようやく裁判に区切りをつけた映姫様がお見えになった。
紫様と私は席から立ち上がり、彼女をお迎えする。
映姫様は片手を軽く挙げて謝辞を示された。
「お待たせしました」
「いいえ。こちらこそ突然お邪魔、失礼しておりますわ」
まずは互いに当たり障りのない挨拶から始める。
どんな相手にもまずは挨拶から、というのは万国共通の理念だろう。
ふと、映姫様の視線に牽制するような、探るようなものを感じた。
まあこれは紫様のような強大な妖怪が何の前触れもなく幽冥界を訪れたのだから、不審に思われるのも仕方のないことだろうが。
私だって今回の紫様の突拍子もない行動の裏が読めず、不安を抱いているのだから。
表面上は穏やかな会話が続く。
「貴女も壮健のようで、まずは重畳と申しておきましょう」
「ありがとうございます。映姫様も相変わらずのご様子で安心いたしましたわ」
互いに相手の健勝を寿ぐ。
まあ、紫様の言葉には裏の意味が含まれていそうだけれど。
分かり易い言葉で表現すると『あんた話長過ぎ』だろうか。
映姫様もその辺りの意訳はきちんと受け取られたようで、頬が微かに引き攣っていたのを私は見逃さなかった。
「そういう貴女は色々変わったようですね。
最近の貴女に関する噂は、森羅殿にも聞こえてきていますよ。なかなか面白いことになっているようで……。
なんでも人間を伴侶とするのだとか」
「あら、それはお耳汚しですわね」
映姫様の揶揄を紫様はいつもの胡散臭い笑みで受け流した。
私は映姫様の揶揄に苦いものがこみ上げてくるのを感じた。
主と○○の仲が映姫様の耳にまで届いていたことは、本来ならば喜ばしいことであるはずなのだ。
あの世に噂が達するということは、それほどまでに二人の絆が深まっていたということの証左なのだから。
であるにも関わらず、全く喜びが湧いてこない。
何故だ。
簡単だ。
もはやこの世に○○がいないからだ。
もはや紫様との絆を育まれることがないからだ。
お二人の会話を聞きつつ、私は知らず知らずに服の裾を強く握り締めていた。
目尻に力を籠めて涙がこぼれないように努めた。
○○、何故死んだ。
何故死んでしまったんだ。
お前のせいで、紫様はこんなところにまで来てしまったんだぞ。
ああ、自分でも理不尽なことを考えているということは分かっている。
○○はただの人間だ。
人は安易に死ぬものだ。
橋から足を滑らせて川に落ちても。
風邪をこじらせても。
妖怪に襲われても。
たった百年ほど生きただけでも、人は簡単に死んでしまうのだ。
そのぐらいのことは、人里の子供たちでも知っている。
だが――
だが、○○よ。
お前の不在はあまりにも大きな傷跡を、私たちに刻み込んでいるぞ。
「さて、八雲の妖怪。この度は一体どのような用件があってここに踏み入ったのですか?」
いつまでも雑談をしているわけにもいかない映姫様が本題に入った。単刀直入に訊ねられる。
紫様は口元を扇子で隠し、いつもの胡散臭い流し目で映姫様を見やった。
「実は――」
紫様を中心として、陰鬱な妖気がじわりと辺りに漂い始める。
「とある人間の転生先をお訊きしたくて、まかりこしましたの」
「そうですか……」
ところが口元に慈悲溢れる笑みさえ浮かべなさって、映姫様はそれを平然と受け止めていた。
映姫様は紫様のおっしゃった理由を聞いて納得し、うんうんというように頭を肯かせている。
そしてまっすぐ紫様の方を見て、返答された。
「古今東西、死者に逢いたいと思うのは、生ける者の業でしかありませんよ。
記紀を紐解くまでもなく、口にした者がそれを実行して、碌な目に遭ったためしはないんですから」
訥々と紫様を諭される映姫様。
脅しが効かないと判断するや、紫様はすぐに妖気を霧散させた。
一方の私はというと――
ようやく紫様がここに来た理由を聞くことができたというのに、安堵感は微塵もなかった。
むしろ幽冥界を相手取った戦争ということが現実味を帯びてきたことで、慄然としていたわけであるが。
無論、表面上は努めて無表情を装っているので、顔色に出したりしない。
もしも紫様が死者の禁を犯すとなると、その未来はなかなか骨の折れることになりそうだ。
よほど慎重に事を運び、上手く立ち回って引き時を見定めなければなるまい。
少しでも筋道を見誤ろうものならば、危険な妖怪として地の底に封印されてしまうことだろう。
『○○は生き返りました。けれども紫様は封印されました』
――では目も当てられまい。
それだけは紫様としても本位ではないはずだ。
ということは、今は先走っていらぬ言質を映姫様に取られないよう、口をつぐんでいるのが一番無難か。
私は主の横顔をまんじりと眺めていた。
果たして、私が危惧していることを、この方は本当に為さろうとしているのだろうか、と。
そんなこと、顔に書いてあるはずがないのは分かっている。
けれども、紫様の進まれる道はその視線の向こうにあると信じているから。
私がお仕えする主は、この方をおいて他にいないから。
全力を以ってお支えする為に、私は自身の主の一挙手一投足を見つめていた。
などと私が心の中で現状を捏ね繰り回している間にも、お二人の会話は続いていた。
「無論、存じておりますわ。
冥界門を潜るということがどういうことかも、それを実行した時の危険性も。
それでも――
映姫様にお縋りするしか、この胸の中にわだかまる澱んだ闇が晴れないんですの」
ご自身の胸を押さえ、潤んだ瞳で心情を吐露する紫様。
映姫様は珍しいものを見たと言わんばかりにまじまじと主のことを眺めていた。
いや、実際紫様がこんな表情をなさることを知っている者など、幻想郷でも数えるほどしかいない。
であるので、映姫様が驚かれるのも無理はないことなのだった。
映姫様は小さく一つ嘆息なさった。
「分かりました。
無理に留め置いて、貴女が無理にでも冥界門を押し通るというような事態は、私としても避けたいですしね」
「ご配慮、痛み入りますわ。
まあそこで、『押し通る!』『来いやぁぁッ!』という展開も、ちょっと燃えるものがありますけれど」
元ネタを知らなかった映姫様は、怪訝な顔をなさっていた。
元ネタの分かった私は、思わず指先で眉間を揉んでいた。
そうして考えることといえば『やっぱり紫様って○○に毒されてるなぁ』ということだった。
「ですが、これだけは約束してください。
その者の転生先はお教えしますが、決して冥界門を潜ることのないように」
とりあえず映姫様は後半の言を聞かなかったことにしたらしい。正しい反応です。
「承知いたしましたわ。
八雲紫、決して無断で冥界門を越えたりいたしませんわ」
「宜しい」
映姫様も私と同様の危惧を抱いていらっしゃったようだ。
そこはぬかりなく、事前に約定を交わすことで、未然にお防ぎになったようだけれど。
しかし、これで問題がなくなったかといえば、そんなわけはない。
何故ならば、○○の転生先を紫様が知ったならば、必ず冥界の門を越えて迎えに行くことが目に見えているからだ。
それも無断ではなく、押し通ることを先方に断った上で、堂々と。
「それで。どなたの転生先を知りたいというのですか?」
「それでは……○○の転生先をお聞かせいただけますか」
言った。
ついに言ってしまった。
これで二度と引き返せない所に、私たちは足を踏み入れた。
これで○○に逢える。
私の脳裏にそんな思いがよぎった。
覚悟と安堵。
私がその感情に身を委ねようとしたその時――
「……は? ○○ですか?」
きょとんとして鸚鵡返しに訊ねられる映姫様。
何故か怪訝な表情をなさっていた。
「あのですね。ここへは死者以外は来ることはないんですが」
――はい?
そう、よく分からないことを仰った。
えっと……。
映姫様の様子から判断するに、○○はまだ彼岸には来ていない……?
いや、そうであるならば、こんな仰り方はするまい。
その場合は『まだ死神が三途の川を渡している最中だ』とか『まだ裁判中です』といった感じに仰ることだろう。
だとすると何? ○○は生きている?
それこそ否だ。
永遠亭の薬師の診断は、○○は魂魄が剥が落ちて死んだと言っていたではないか。
それにこの手にはまだ、あの○○の身体に触れた時の冷たさを覚えている。
あの時の心が凍りつくような寒さを覚えている。
だとすると、映姫様は何をそんなもったいぶった様子でいらっしゃるのだろうか。
「知っての通り、人は死ぬと鬼籍――すなわち閻魔帳へその功罪と共に名が記されます。
現在のところ○○は他の人と同様に地獄街道一直線の人生を歩まれていますが、その寿命が尽きるのはまだ先で……す……? こ、これは!?」
映姫様は懐から閻魔帳を取り出されると、パラパラと頁をめくって該当箇所を探されていた。
ところが、○○の部分を見つけて目を通している内に、ハッと目を大きく見開かれた。
「どうかなさいまして?」
「いえ……確かにここへは死者しか訪れることはない……。
……しかし、これは……いや、そうするとあれしか考えられない……」
紫様が何かあったのかと訊ねられた。
けれども映姫様はすぐに我に返るようなこともなく、何やらブツブツと意味を成さないことを呻いておられた。
映姫様ともあろう方が他人の言葉が耳に入らないなど、かなり珍しい光景だ。
紫様は映姫様の様子を静かに窺っていた。
映姫様の取り乱し様をまるで当然のことであるかのような様子で見ていた。
…………?
あれ?
ひょっとして紫様は何か知っていらっしゃるのだろうか。
「○○はまだここには来ていない――そう受け取ってよろしいかしら?」
紫様は映姫様の耳元に囁かれた。
ようやくそこでハッと我に返られた映姫様は、閻魔帳をパタリと閉じる。
すぐさま平静に取り繕われた。
「お見苦しいところを見せてしまいましたね。
私としたことが、些か予想外の事態に戸惑ってしまったようです」
「こういうことは滅多にあることではないですし、そうなるのも仕方ないかと」
「そうポコポコあられても困ります」
「確かに」
そうして二人して苦笑なさる。
うん、どうやら紫様が何か重大なことに気づかれていることは確かなようだ。
二人共同じ結論に至られているということは理解したが、私にはそれが何なのかさっぱり分からなかった。
ちょっと悔しい。
紫様はここで席を立たれる。どうやら暇を告げられるようだ。
私も主に追従する。
「さて、ここに○○が伺っていると思ったんですけれど、どうやら違ったようですわね」
紫様の非常にわざとらしい台詞に、映姫様は苦笑されていた。
そうして部屋を辞する直前――
「ああ、○○に会ったら伝えていただけますか」
ふと、映姫様はそんなことを仰った。
この方は一体何を言っているんだろうかと、私は思わず胡乱な顔をしてしまった。
○○は死んでいて、もはやここでしか死後の情報を得られないと思ってやってきたのに、まだ来ていない(死んでいない?)と言う。
不信感が湧いていたところに、この無体な依頼。
これで呆れなかったらいつ呆れるというのか。
この時私は大変混乱していたのがよく分かる。
紫様は映姫様の様子に呆れるでもなく、憤慨するでもなく、ただ一言頷かれた。
「承りますわ」
「では、こうこう伝えてください。
『百年後の彼方、必ずやお迎えに上がりますので、お覚悟召されよ』と」
主は幻想郷の閻魔の言葉に頷かれ、必ずや伝えますわと艶やかに受け入れられ――
「ですが、お生憎様。
貴女方のご挨拶は全て叩き潰して差し上げますわ」
獰猛な笑みと共にそんな宣言をなさった。
そして映姫様は主の返答に破願されたのだった。
踵を返す紫様。私もそれに続く。
紫様は森羅殿を振り返ることなく、此岸を目指して歩かれる。
それはもう、いそいそと。
本人にすれば、礼を失しないよう心掛けているつもりなのだろうが、後ろをついて行っている私にははっきりと豹変した態度が見て取れた。
今にもスキップしそうなウキウキとした足下。
私も釣られて楽しくなってしまう。そんな後姿。
既視感――否、私はこの背中を知っている。
○○のところに逢引に行く時と同じなんだと思い至る。
ああ、この後姿を見るのも久し振りだなぁと、嬉しくなって一人主の背中に向けて頷いていた。
ん? 待て待て。
紫様は何をそんなに喜んでおられるんだ?
疑問を感じた私は道すがら、紫様に訊ねてみた。
一体何があったのですか、何をそんなに嬉しそうにしているんですかと。
すると紫様はポツリと一言。
「――尸解よ」
その一言が結論であり、また始まりであった。
──────────
人という階位を超越し、天地と寿命を等しくするには、いくつかの方法がある。
一つ目は捨食の法や捨虫の法などの外法をもって魔法使いとなる。
二つ目は太陽を避け、闇に潜み、夜に蠢く有象無象たる妖怪へと堕ちる。
三つ目は蓬莱の薬を使用する。
そして四つ目、幾多の修行の果てに仙人と至るという方法だ。
異論はあるかもしれないが、ひとまずこのまま進めさせてもらう。
今回注目すべき話題は、四つ目の仙人になるという方法だ。
仙人になるには天に昇ったり山で修行したりと幾つか方法が存在するが、その内のひとつに尸解というものがある。
有体にいうと尸解とは死後、人としての肉体を捨て、仙人としての体へと変化させることをいう。
火に身を投げてみたり、毒を飲んでみたりと、兎に角人としての肉体を一度捨て去るのが一般的な尸解の方法だ。
文字通りしかばねを解いてしまうがゆえに、尸解という。
この尸解を行なった果てに至るのが尸解仙といって、仙人の位の中では最も低い階位のものといわれている。
まあ、中には長い仙道修行の過程のひとつともいわれることもあるが。
とまれ、私たちにとっては縁遠い話のはずなのだけれども……。
――『尸解』ですか?
突拍子もない言葉が紫様の口から漏れ出た。
それを私は深く考えることもなしに、思わず主に鸚鵡返しに訊ねてしまった。
頷かれる紫様。
「そう。天仙、地仙、尸解仙の尸解よ」
○○ってごく普通の人じゃなかったんですか?
私の記憶では奴は仙道の修行に励む道士でもなかったし、仙人骨があったなんてついぞ聞いたことがないんですが。
仙道は欲を否定しないとはいえ、奴の生活態度を鑑みるに、仙人の暮らしからは程遠いものだと思われる。
酒は飲むし、よく食べるし、なにより紫様との色欲に溺れているのだ。
あれで仙人に至れるんだったら、世の中にいる人間は死後はすべからく仙人になれるだろう。
うん、それはないな。
私の結論を聞いて、紫様もそうねとそれを肯定された。
苦笑を抑えようとしていないところを見ると、紫様自身もその辺は理解しているのだろう。
「でもね、藍。状況から考えると、そうとしか考えられないのよ」
紫様は理由を指折り挙げられる。
「まず一つ目。○○は皆に死んだと認識している。
永遠亭の薬師の診断もその補強になっているわね」
私は複雑な思いに囚われた。
あの時去来した背筋を凍らせるような虚無感のことを思い出す。
あの肌の冷たさが誤認だというのだろうか?
永遠亭の薬師の診断が、偽りだったとおっしゃりたいのだろうか?
思わず紫様を見つめる視線に、非難の感情が篭ってしまった。
「そうは言わないわ。彼の肉体から魂魄が剥がれ落ちたのは確かでしょうし。
私もあの時は、かなりショックだったわ」
紫様、前後不覚になってましたしね。
「あれは不覚だったわ。
――話を戻すわ。
私も彼の肉体に魂がないのを確認したわ。だから、診断は間違ってないわよ」
紫様は私から視線を切り、透徹した目で空を見上げた。
東の空が大分明るくなってきていた。もうすぐ夜が明ける。
その時――
「……そういう意味では人という生物としての○○の生は、確かにあそこで終わっているわね」
ポツリとつぶやいた紫様の横顔が、とても印象的だった。
見た目には特に表情は変わっていなかった。
けれども悔しさを堪えているような、哀しんでいるような、そんな風に私には見えた。
「理由二つ目。棺桶に入れられたはずなのに、○○の死体がない。
これはきちんと彼が棺桶に入れられてから埋められたのを見たって、葬式に参列した霊夢に確認済みよ。
そしてこれこそが、彼が尸解したという確たる証。
魂魄が剥がれ落ちたというのも、そう考えれば納得いくわ」
尸解というのは確かに、肉体と魂魄の繋がりを絶つ術ではありますが……。
そうなると疑問が湧いてくる。
尸解とは要は凡体骨肉を捨て、仙人としての肉体を得ることを目的とした術だ。
肉体を脱し、魂魄のみになることまでは比較的容易だ。
普通に死んでしまえば、肉体と魂魄の分離は可能だからだ。
まあそれだけでは輪廻の輪から抜け出せない――つまり仙人にはなれないのだけれども。
問題はその後、肉体を捨て去ってからの話だ。
魂魄と肉体を切り離すと、それのみで自意識を保つのはかなり難しくなる。
放っておくと容易く魄は地へ、魂は彼岸へと分かれて行ってしまうからだ。
故に魂魄が分離しないようにしつつ自我を保っていられるようにするには、高度な修行が必要となってくるのだ。
奴の生活態度を思い出す限り、そんな修行をしている節は見当たらなかった。
それ故に、紫様の言葉が私には釈然としなかった。
「そして理由三つ目。○○は四季様のところへ行っていない」
それを確かめに映姫様のところをお訪ねしたんですよね。
幽冥界との戦争を覚悟していたけれど、そうはならなかったのは僥倖だった。
「予想通り、○○は彼岸に逝っていなかったわ。
四季様のあの様子からすると、おそらく閻魔帳にある寿命欄も書き替えられていたんでしょうね」
閻魔帳の書き替えなんて、できるんですか?
あれは一種、契約書の宝貝みたいなものだから、そうそう書き替えたりはできないはずなんですが。
「あら、須菩提祖師のお弟子さんは書き替えたじゃない」
あんな化物と○○を一緒にしないでください。
確かに○○は多少変なところはありますけど、そんなことできるはずないじゃないですか。
「……まあ、今は閻魔帳が書き替えられたかどうかは問題じゃないわ。
四季様も○○が尸解仙化したと判断したというのが今は重要なことよ」
そういえば映姫様はそんなことをおっしゃっていたなと、私は思い出した。
……あの時。百年後がどうのこうのとおっしゃっていたのは、そういうことか。
仙人はだいたい百年ごとに、地獄から刺客がやってくるというのは有名な話である。
現状は納得できないが、主の言わんとすることは理解できた。
それからしばしの間、無言の行軍(といっても空を飛んでいる)が続く。
日の出が拝めそうな小高い丘を発見し、私たちはそこへ降り立った。
ここで○○を復活させるということだろうか。
それにしてもどこかで見たことがある景色だと思ったら、ここはマヨヒガと○○の家の中間地点辺りだ。
○○が妖怪に襲われたといわれている場所に近い。
そういえばどんな妖怪に彼は襲われたというんだろうか?
博麗の巫女や黒白の魔法使いが退治したという噂も聞かないし、どうなっているか後で調べるか。
そんな風にとりとめもなく思考を巡らせていると、
「一つ言っておくことがあるわ、藍」
なんでしょうか?
「貴女、○○が只人だっていってるけれど、彼は一般人じゃないわ」
そうでしょうか?
私が知る限り、○○は何かを信仰していたわけでもなく、仙道の修行もしてもいません。
弾幕も撃てなければ、空を飛んだりもできません。
だとすれば、一般人といっても差し支えないと思うんですが。
奴の運動神経、というか身体のキレは、どう贔屓目に見ても幻想郷の一般人レベルだ。
ひょっとするとそれより低いかもしれない。
妖怪退治を生業としている者たちとの比較だと、話にもならない。
「それは一面を見ているだけにすぎないわ。いいこと――」
紫様は子供に言い聞かせるような優しげな声音でおっしゃった。
「――普通の人は八雲家に繋がっているはずのスキマを潜って、成層圏から落ちたりなんかしないわ」
身も蓋もない台詞ですね。
いやまあ、確かにそういう意味ではそうなんですけど。
ちなみにその時の最終着地点は霧の湖で、盛大に水柱が立つような飛び込み方だったという。
こう、胸からびたーんと。
全治1週間だった。
何か色々と間違っているような気もするが、まあ○○だし。
…………。
……ちょっと待て。
○○は変人だから、変なことが起こって……。
ああ、そういうことか。
ここで私は紫様の言わんとすることに気づいた。
確かに○○って只人じゃあないですよね。
人間の限界を超越した、というか逸脱したようなところがありますし。
ゴキ並みのしぶとさというか、生き汚さが特に。
「……何だか酷い言われようね」
紫様の胡散臭い笑みを浮かべた頬に、一筋汗が流れ落ちた。
「どうやら貴女にも解ったかしら?
確かに○○の身体能力は普通の人並みにしかないわ。
だけど藍の言うように生命力もそうだけど、彼の精神の強靭さだって妖怪並みに並外れているわ」
妖怪並って……。それはそれで酷い物言いのような気がします、紫様。
いやまあ、確かに奴の日々の仕事振りを私も知っているから、妖怪扱いは分からないでもないですが。
思い出されるのは、週刊で3冊、月刊で1冊の漫画を助手なしで週末までに描き上げる大馬力。
それでいて週末には必ず紫様との逢瀬を楽しむのだ。
一体奴の一日は何時間あるんだろうと思わないでもない。
そしてこの大馬力を支えているのが、変態的な体力と精神力なのだろう。
「彼の精神が鍛えられている原因は分かるかしら?」
ええ、その程度なら。
おそらく彼は私や紫様のような強力な妖怪と共にあることで、自然と鍛え上げられたのでしょう。
聖人の傍に仕える従者が、永く共にある内に聖者に近づくように。
よくできましたと言わんばかりに、紫様は満面の笑みで頷かれた。
「その通り。○○は私たちと一緒にいることで、尋常ではないほどの鍛錬になったようね。
幸か不幸かは分からないけれど」
ふと、この日常生活を要因とした精神鍛錬というところに引っかかるものがあった。
このタイプでいけばもう一つ、○○の精神を自然と鍛えているものがあることに思い至った。
けれども、それを口にするのは、ちょっと憚られるものがあった。
だってアレだしなぁ。
私自身、それを具体的に想像するのは、ちょっとだけ悔しいというか羨ましいというか――
兎に角あまり楽しい気分にはならないのは確かだった。
「あら、藍ったら、何不満そうな顔をしてるのかしら?」
で、当然そんなことを考えていたら、紫様に見咎められるわけで。
私としては報告にかこつけて……、もとい、問われたのならば、式として答える義務が生じるわけである。
あー、そのですね……。
後、○○と紫様の閨でも意外と鍛えられてるかもしれないと思っただけです。
不満なんてないです。ええ。
「ああ……うん。そ、そうね。
確かに藍の言うのもあるかもしれないわね」
思わぬ私の揶揄に、紫様はぎょっとなさる。
頬を真っ赤に染めて視線はキョロキョロ、口調はしどろもどろになる。
とはいえ、そんな風になっても私の言葉を理解し、発言内容を肯定なさっているところは、実に紫様である。
こういったちょっとしたことで紫様が可愛らしくなることを知っているのは、おそらく私と○○のみだろう。
何だか最近私は、それがとても嬉しく感じるのだった。
私の視線を感じたのか、紫様は照れくさそうに視線を逸らされた。
妙な空気が二人の間に流れる。
やがて、こほんと咳払いをしてその空気を振り払うと、紫様は話を戻された。
「現在の○○が尸解しても魂のみでも生きている、という理由は理解できて?」
はい。ですが、そうなるとまた疑問が出てきます。
魂魄のみで生きていられるのならば、何故○○は一向に姿を見せないのですか?
自身の現状が理解できているのなら、甦るために助けを求めにやってきてもいいではないですか。
すると紫様はこいつ何を言っているのかしらんといった様子で、まじまじと私の顔を覗き込んできた。
紫様がなじるような視線で見つめてくる。
あれ? 何か拙いことを言ったかな?
「そんなの決まってるじゃない。
今彼の身に起こっているのは、様々な条件が重なった上での偶発的に起こった尸解。
決して正当な手続きを踏んだ末の尸解というわけじゃないのよ。
だったら仙人の身体を再構築する方法どころか、自身に起こっている状況すら理解していないはずよ」
……言われてみればそうですね。すいません。
我ながらあまりにも間抜けな疑問だったことに気づいて、私は小さくなった。
どうやら私はそんな単純なことにも気づかないほど混乱していたようだ。
「今、○○は幻想郷のどこかにいる――というかどこにでもいるという状態よ。私にはそれが感じ取れるわ」
私にはそんなものは全然感じ取れません。
おそらく『境界を操る程度の能力』を持つ紫様だからこそ、感じ取れることなのだろうが。
紫様がおっしゃるには、○○は今、幻想郷の隅々にまで風よりも薄く解け消えている状態なのだという。
○○の死体が墓場から消えてしまったのは、墓泥棒が出たはわけではなく、死肉喰らいが出たわけでもない。
彼の屍は解け消えた魂魄に引きずられたか、より人外に近い存在になってしまったが故に、塵となって消えたのだろう。
尸解した時によく聞く話だ。
そして現在、紫様はその薄くなっている○○を、どうにかして復活させようとなさっているのだ。
具体的に証拠を提示されたわけではないが、今まで主につき従ってきた状況を省みるに、そうとしか考えられなかった。
紫様が懐から白っぽい小さな物を取り出すと私を呼び寄せ、それを私に預かるように命じられた。
これは……?
どこかで見たことのある物だった。
「○○の骨よ。棺桶の底に転がっていたの」
ああ、なるほど。
○○の棺桶から拾い上げていたあれですね。
二人で墓荒らしをしていた時に、紫様が○○の亡骸が入っていた棺桶から何やら拾っていたのを思い出した。
あれがこの○○の骨だったのだろう。
尸解したにも関わらず、骨を残すような不手際があったというのは、ちょっと珍しいことだ。
まあ、今回は修行も準備もせずに敢行した尸解だからこそ起こった、珍しい事例なのだろうけれど。
主のなさろうとしていることが、私にも分かる。
紫様はそれを使って○○を再生しようということなのだろう。
「流石に何の媒体もなしに彼を復元することは難しいから、これを核にして魂魄の定着を図るわ。
あの人は私の能力を受け付けにくいから、このくらいの補助は欲しかったの」
まあ、そうでしょうね。
元々自分の身体の一部だから、定着はし易いだろう。
また、これは幻想郷中に霧散している○○の魂魄を呼び寄せる誘蛾灯の役目も果たすはずだ。
二重の意味でもこの○○の骨は、彼の復活に必須の物に違いあるまい。
と――
ここまで考えたところで、私は紫様の行動に不可解なものを感じた。
それは何故私をここまで連れ回したのか、ということだった。
実際のところ、彼が生きている証拠を確認するだけなら、紫様お一人でも可能なのだ。
そして○○を復活させるのだって同様だ。
私がそれを補助したとしても、今回に限ればほとんど役には立たないだろう。
まあ、うどんに振り掛ける薬味程度には効果はあるかもしれないが。
「あら。貴女にも、彼の現状を知らせた方がいいと思って連れてきたんだけど、必要なかったかしら?」
私の愚痴めいた発言に、紫様はからかうようにおっしゃった。口元には胡散臭い笑みを浮かんでいた。
そう問われたら、私としては有難いことですと返すしかなかった。
本来ならば結果のみ私に伝えればよいはずなのだ。
それを私の○○に対する想いを紫様は理解なさっているが故に、ここまで厚意を示してくださったのだろう。
これが有難いといわなくて、何といえばよいというのか。
まあ紫様のことだから、今おっしゃったこと以外にも二重三重の意味を持たせているのだろうけれど。
「それじゃあ、日の出と共に始めるわ」
スッと目を細めて精神を集中される紫様。
普段ならしないような真剣な表情。
能力が効きづらいというのは、そこまで大変なものなのだろう。
ひょっとして奴のこの妙に限定された能力って、紫様と一緒に居すぎたせいで発現したものだったりするんだろうか?
ずっと共にあって、いつの間にか境界を操られることに耐性がついた、とか。
もしこの予想が正しいとたら、それは何という不運なのだろう。
互いの心が近づきすぎたが故に、それ以外のところで拒絶反応が出てしまう……。
………………。
……いや、『それはそれで燃える!』とか言い出しかねないな、奴は。
○○の反応を考えてみて、そんな風な回答を導き出した私は、思わず小さく笑ってしまった。
あまりに突拍子もない答えだった。
そして、とても○○らしい台詞だった。
私の集中が途切れていることに気づいた紫様が、咎めるようにギロリと横目で睨んできた。
すいませんすいません。真面目にやります。
慌てて私も意識を集中し、○○の骨を握りこんで祈ったのだった。
○○。帰って来い。
私たちはずっと待っているんだぞ。紫様も心配している。
帰ってきてくれたら、腕によりをかけたご飯をご馳走しよう。
それから、皆で花見に行こう。
花はもう散ってしまったけれど、たぶん一緒にいるだけで楽しいだろうから。
それから――
二人で祈る。
祈る。祈りを籠める。
そうして気がついた。
日の出から輝きがこぼれ落ちている。
私にも分かる。
○○がそこここにいるのが――
そうしてついに――
───────────────────────────────────────────────────────────