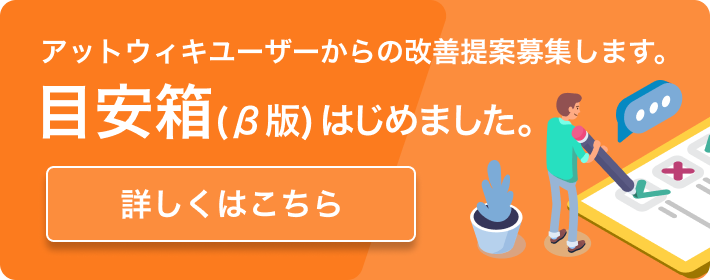「紫様、一つお聞きしたいことがあるのですが」
割烹着を着て、頭には手ぬぐいを姉さん被りにした藍が、はたきをかけながら尋ねる。
煎餅をかじりながら、ふさふさと揺れる藍の尻尾をぼんやり眺めていた紫は、問いに気付いて意識を戻した。
「なあに?めずらしいわね、貴女がそんなこと言うなんて」
滅多にない展開に興味を抱いたらしく、身を乗り出す紫。
「その……後ろからと前からと、どちらの方が愛があるものでしょうか」
藍の質問に紫は一瞬目を丸くしたが、すぐににやりと意味深な笑みを浮かべる。
「あらまあ、藍もずいぶんと大胆になったものね。
昼間からそんな、紅魔館の魔女が目を吊り上げそうなことをさらっと言うなんて。やっぱり恋人ができると違うわねぇ」
人の悪い笑顔でそんなことを言われた藍は、顔を真っ赤に染めてしまった。
「な……あ、いえ紫様、私はそんな意味で言ったわけでは」
「あら、私がどんな意味に取ったと思ってるのかしら?」
頭から湯気が出るのではと思える様子で焦る藍を見て、紫はおかしそうに笑う。
「冗談はこのぐらいにしておきましょう。
それで?どうしてそんなことを?」
「もう……いえ、○○のことなんですが」
○○は、幻想郷に迷い込んできたところを紫が拾ってきた外の人間だ。
本当ならすぐに送り返すはずだったのだが、ちょうど冬眠前で眠かった紫が面倒くさがり、
「起きたらちゃんと片付けるから、しばらく面倒見といて」
と、式神二人に押し付けてしまったのだ。
春が来て紫が起きてみると、○○はすっかりマヨヒガに馴染んでしまっていた。
外の世界に帰すから、と切り出した紫に、まず橙が「ちゃんと面倒見るから○○を帰さないで」とぐずり、
藍は藍で「橙もあのように懐いていますし、このまま置いてしまっては」などと言いながら、
その実自分もひどく寂しそうな顔を見せた。
当の○○も別れ難い様子であることから結局紫が折れ、
○○は家事手伝い兼橙の遊び相手兼紫の暇つぶしとしてマヨヒガで暮らすことになった。
意外と家事が得意だった○○はそれまで藍が一人でやっていた仕事を手伝うことが多く、
結果として藍と一緒に過ごす時間が多くなっていった。
二人の関係が特別なものになっていったのも、起こるべくして起こったことと言えるかもしれない。
人目をはばからずイチャつくわけではないが、それでも紫は幸せそうな○○を、初々しく彼に寄り添う藍を、よく目にするようになった。
……いや、実際のところは退屈しのぎに自らスキマを開けて二人の様子を眺めているのだが。
「その……○○が、私のことをよく抱きしめてくれるのですが」
「けっこうなことじゃない」
「最近はいつも、背中からなのです」
「……それで?」
「私の尻尾を気に入っている、そうで」
ふわり、と金色の尻尾が揺れる。
ふさふさした彼女の尻尾の感触が心地よいことは、長い付き合いである紫にもよくわかっている。
「いいじゃないの。その尻尾は、貴女にとっても自慢でしょう?」
「ですが、その……」
「もう、何なの?」
幾分いらだちを含んだ声で、紫は問いかける。
ためらいがちに話す藍の言葉からは、依然話が見えない。
「私は、ちゃんと愛されているのでしょうか?」
「……?」
「後ろから抱きしめる方が、前から抱きしめるより愛情のこもった行為なのでしょうか。
そうでなかったら、○○はもう私ではなくて、私の尻尾に惹かれているだけなのでは、と……
もし、尻尾がなかったとしても、○○は私を抱きしめてくれるでしょうか?」
紫は呆れたようにため息をついた。
恋とは、あの冷静な藍をここまで不安定にするものなのか。
取るに足らないようなことをこんなにも深刻に捉え、悩み、不安そうにしている藍の姿は、紫にとっても目新しいものだった。
「直接聞けばいいんじゃないの?もしくは尻尾をしまっておくとか。
それぐらい藍ならたやすいでしょうに」
「そ、それでもし、『尻尾が好きなだけ』と言われたら?抱きしめてくれなくなったら?
紫様、私は、私は……」
「ああもう、落ち着きなさい!」
かなり重症らしい。なんらかの対処が必要だろう。
この状況を半ば面白がりつつも、紫は考え込んでしまった。
スキマから新たな煎餅の袋を取り出す。
「ねー、○○」
「ん?なんだい橙」
庭の掃き掃除をしながら、○○は返事をする。
橙は縁側に腰掛けて足をぶらぶらさせながら、○○の仕事ぶりを眺めていた。
「○○は、藍さまのこと好き?」
「好きだよ」
即答する。あまりやりすぎると教育上よろしくないので、なるべく橙の前ではべたべたしないように心がけているが、
お互いを好きあっていること自体は別に隠すことではない。
「藍さまの尻尾は好き?」
今まさに藍がそのことで悩んでいるとも知らず、橙は特に深い考えもなく問いかける。
頭の中で少しその感触を思い出してから、感慨深げに○○は答えた。
「……好きだな」
「ふかふかで気持ち良いよね」
意見が一致したことが嬉しいのか、楽しそうに笑う橙。
穏やかな一時を過ごしていた二人のところに、廊下の向こうから紫がやってきた。
「あら、楽しそうね」
「あ、紫さん」
「どうしたんですか、紫さま?」
「橙、ちょっといいかしら」
「はーい」
呼ばれて、橙は立ち上がる。
紫は○○に話が聞こえないように、橙を廊下の曲がり角まで連れていった。
「橙には黙っていたけど……今日は百年に一度の『尻尾の日』なのよ」
「え、そうだったんですか!?私全然知りませんでした……」
もちろん嘘だ。藍なら頭を抱えて呆れ返るところだろうが、橙は紫の言葉を疑わなかった。
「そうよ。だから遠慮なく藍の尻尾をもふもふしなさい。私の分までお願いね」
「はっ、はい紫さま!わかりました!」
別に普段から遠慮などしていない橙だったが、主の主である紫の言葉に元気よく返事をする。
そのまま勢いよく駆け出そうとするところに、紫はもう一言声をかける。
「そうそう、○○には内緒よ。普段からいっぱいもふもふしてるから」
「はーい、わかりましたー!」
話の内容を聞き取れないまま掃除を続けていた○○は、走っていく橙をぼんやりと眺めていた。
「らーんさまっ」
台所に立っていた藍の尻尾に、橙が抱きつく。
まだ幾分うわの空だった藍だが、それでも振り向くと、優しい笑顔を見せた。
「ん、どうした橙?」
「えへへー」
尻尾に頬ずりする橙。藍は、やれやれといった表情で橙の頭を撫でると、また仕事に戻る。
(やはり○○も、私の尻尾が好きなだけなのだろうか……)
相変わらず悶々とする藍をよそに、橙はさらに深く尻尾に顔を埋める。
結局その日の夜まで、橙は暇さえあれば藍の尻尾にくっついていた。
夜。
床に就いた藍は、眠れずにいた。尻尾に潜り込むようにして寝ている橙が原因ではない。
就寝前に紫がそっと話したことが、藍を悩ませているのだ。
「何考えてるんだ紫様は……」
(貴女の尻尾に対する○○の欲求は、橙によって満たされない状態にしてあるわ)
「いや、そもそもそんな欲求があるのか―いや、やっぱりあるのだろうか……」
(橙はこのまま、貴女の尻尾の中で眠ってしまうでしょうね。もし、○○がやって来て)
(いたいけな橙を追い出すような暴挙に出てまで尻尾を堪能しようとするなら)
(○○は単なる尻尾狂と見なすことができるわ。その場合、○○は明日の私の晩御飯ということで)
「……むちゃくちゃだ」
理屈も何もあったものではない。だが紫の場合、一概に冗談とも言えない。
例え冗談だったとしても、いざその状況が訪れたら気まぐれで実行に移しかねないのが恐ろしい。
「もし、紫様の言うとおりになったら……」
○○には二度と会えなくなってしまうだろう。
藍は寒気を覚えて、寝巻きの襟を掻き合わせた。
(頼む、○○、来るんじゃない―)
藍の耳がぴくりと動いた。
気付かれないようにそっと見ると、願いもむなしく、ふすまを開けて部屋に入ってきたのは○○だった。
「ああ、やっぱり―」
藍が眠っていると思ったのか、○○は畳の上を足音を立てないように近づいてくる。
目覚めていると気付かれないように息を潜めていた藍は、ふいに冷たい空気を感じた。
○○が布団をめくり上げたのだ。
(やめろ○○、これでは紫様の)
「本当にもう、しょうがないな……よっ、と」
(ああ……)
尻尾の中から発掘した橙を抱きかかえ、立ち上がる○○。
そのまま部屋を出て行く。おそらく、橙を布団まで運びに行くのだろう。
そこらに転がしていかないだけましだが、このまま紫の仮定通り○○が尻尾に触れようとした場合、彼は紫のご飯にされてしまう。
(まずい、まずいぞ……だが、このまま戻ってこなければ……)
程なくして、廊下を戻ってくる足音が聞こえる。間違い様もない、○○の足音だ。
部屋に足を踏み入れ、ゆっくりと布団の方へ歩を進めてくる。
(あああああ、○○、来てはだめだ、来ては……)
布団の側にかがみこむ○○。
藍は背中を冷や汗が伝うのを感じた。
(このままではお前は、紫様に)
何も知らない○○は、藍の寝顔を覗き込もうとしている。
追い詰められた藍は、混乱のきわみにあった。
そして。
「○○っ!」
「うわっ!?」
藍は勢いよく飛び起きた。
驚く○○を真正面から抱きしめ、そのまま布団に倒れこむ。
「ら、藍!?いきなり何を」
「静かに!」
腕にぎゅっと力が込もる。
「ちょっと、苦し……」
「すまない。だが今は朝まで、このまま……」
確かにこの状態を保てば、紫の言ったとおりにはならない。
藍は○○が動かないよう、胸に抱きかかえるように彼の頭を押さえ込んだ。
雀の鳴く声がする。どうやら夜も明けたらしい。
「……何とかやりすごしたか」
時折うつらうつらしながらも、藍は○○を離さずにいることができた。
ひとまず、これで安心だろう。
「朝だぞ○○、もう起きても大丈夫だ」
「うーん……」
半ば気を失うようにして眠りについていた○○は、藍に促されて目を覚ました。
「あー……もう朝か。いったい何が……」
「すまなかったな。事情は……そうだな、後で話すよ」
「うん……とりあえず、朝ごはんの支度をしないと。着替えてくるよ」
「そうだな。では私も着替えて、すぐ行くから」
○○の背中を見送ると、藍は枕元にたたんであったいつもの法衣に着替え始めた。
上から割烹着を着ると、台所へ向かう。
「……と、いうわけだ」
味噌汁に入れる大根を刻みながら、藍は経緯をかいつまんで話した。
昨日までなら○○自身に話すことなど思いも寄らなかっただろうが、色々あって吹っ切れたようだ。
「一歩間違えば危うく食べられるところだったわけだ」
七輪の前にしゃがんで魚を焼いていた○○が、他人事のようにつぶやく。
藍はその反応に、少し眉根を寄せた。
「もう少し焦ったらどうだ。元はと言えばお前が……その、私の尻尾ばかり」
「そうかな。そんなに執着してるように見えた?」
「見えた。昨夜だって、橙を運んでから戻ってきた時は、てっきり紫様の言う通りお前が私の尻尾を独占しようとしているのかと」
「あれは、橙が自分の布団にいないようだったんで探してみたら案の定藍のところにいたから。
そのままだと藍が寝苦しいんじゃないかと思って」
「そ、そうか。だがそれでも、最近その……後ろから私を抱きしめることが多い気がする」
「それで、ちゃんと愛されてるのか不安になったんだ?」
「う……」
頬を染めて口ごもる藍を見て、○○は微笑む。
ほんの少しのからかいと、たくさんの愛しさを含んだ笑顔だ。
「確かに尻尾は好きだけれど
―藍のことが好きだからこそだよ」
「うう……」
「いや、藍が後ろからよりも前からの方が好きだって言うならそうするけど」
「ううう……」
真っ赤になった藍は、消え入りそうな声で答える。
「わ、私は、○○のことを愛しているから……ちゃんと愛情を込めてくれるならどちらでも、嬉しい……」
「………………そうストレートに言われると」
聞いていて今更のように照れが出てきたのか、今度は○○が黙る番だった。
「でも……」
包丁を置き、側に寄ってきた藍は身を屈めると、○○を包むように抱いた。
「私から、というのも悪くはないかな……」
お互いの体温が伝わってくるのを感じながら、二人だけの世界に浸る。
「朝ごはんまだー?」
「……はっ」
居間から紫の呼ぶ声が聞こえて、二人は我に返った。橙もそろそろ起きてきただろう。
「……っと。急ごうか、藍」
「そうだな。紫様も橙もお腹を空かせているだろうし」
「ええ、もうぺこぺこよ」
居間にいたはずの紫がいつの間にか台所に来ていた。いつもながら、気配を感じさせない。
「あ、紫さん」
「ゆ、紫様!?」
紫は優しい目で二人を見つめている。
「解決したみたいね、藍」
「……はい」
「抱きしめられて迷うなら自分から抱きしめて、わからない気持ちを確かめるのも大事よ?」
「紫様……ありがとうございます」
全て考えた上で自分を後押ししてくれていたのだ。
そう思うと、藍の心は紫に対する感謝の気持ちでいっぱいだった。
「それにしても残念ね。今日はたんぱく質豊富な晩ごはんになると思ったのに」
「ちょっと紫様!?それは嘘も方便というやつだったのでは」
「さあ、どうかしらねー」
「駄目ですよ、もう解決したんですからね!紫様と言えど私の○○に手は出させませ」
「あの、二人とも朝ごはん……」
「藍さま、おなかすいたー」
本日も、概ね何事もなし。
すっかり馴染みつつある○○を交えて、マヨヒガの日常は流れていく。
うpろだ1283
───────────────────────────────────────────────────────────
雲一つない空に突如として花火が打ち上がった。
昨日まで何もなかった広場には、マイクやスピーカー、観客席等が用意され、大にぎわいを見せている。
……何故こんなことになったのだろう。
○○は溜め息を吐き、会場の入り口の看板を眺める。
願わくば、先程読んだそれが自分の見間違いであるようにと。
……残念ながら、看板に書かれた文字は、先程と同じだった。
『第一回、従者オブ従者選手権決勝』
ことの起こりは三日前の宴会でのこと。
スキマな事情により、紆余曲折の後にマヨヒガで住み込みで働くことになった○○。
雇用期間は死ぬまで。つまり永久就職。
三食及び雇い主からの愛情保証という特典付き。
職業名を『専業主夫』という。
久しぶりにという雇い主、八雲藍の誘いで、博霊神社の宴会に出向いた○○は、酒の飲み方を忘れていたらしい。
注がれるままに飲みに飲んでしまった結果、藍の膝の上に頭を載せ、唸るはめになってしまっていた。
「すまないな、○○。私が調子に乗って飲ませ過ぎたばかりに」
「……いや、俺もはめをはずしすぎた」
「藍さま、お水持ってきました」
藍の式神である橙がコップを片手に、とてとてと二人によって来る。
「ああ、ありがとう」
自らの腕にもたれ掛かる○○の口に水を運ぶ藍。
その甲斐甲斐しさは正に妻のそれ。
……いや、母のそれだろうか。
「……それにしても」
橙は○○をじっと見ながら言う。
「……なんで藍さまは○○なんかと」
「おや、橙は○○が私の夫では不服なのか?」
「当たり前です! ○○ってば段幕は撃てないし、力は弱いし、今だってこんなに情けない格好で……」
あれこれ不満をまくしたてる橙だが、その実○○を気に入ってることを藍は知っている。
単に○○が藍を独占していることが面白くないだけなのだ。
「いや、申し訳ない」
「申し訳ないじゃないよ○○! もっとしっかりしてよね!」
「「まったくね(です)」」
そんな○○と橙の微笑ましいやりとりに、口を挟む者がいた。
紅い悪魔の従者十六夜咲夜と、亡霊嬢の従者魂魄妖夢だ。
「私達に何か用事かな?」
不粋な闖入者に顔をしかめながら、藍が尋ねる。
「貴女の従者は随分となってないのね」
ピクリと、藍の形の良い眉が上がる。
「自らの限界も弁えず、主人を省みないで酒を飲み」
「あまつさえ、主人に迷惑をかけるなど、言語道断。同じ立場の者として恥ずかしい限りです」
ぶわりと、美しい九つの尻尾が大きく膨れた。
……明らかに怒っている。
「要するに、このダメ従者に一言言ってやりたくてね」
「お前ら……!」
ぶっとばしてやろうかしらと、懐のスペルカードに手を伸ばし……
「主夫を、……なめんなーーーーーっ!」
唐突に○○が立ち上がった。
「あら起きたの、ダメ従者」
「従者じゃない! 主夫だ!」
「ならダメ主夫ですね」
「言ってくれる。こちとら家事のプロフェッショナルだ! 家事の技量ならあんたらよりも上だ!」
この発言に今度は従者二人がこめかみをひくつかせる。
「西行寺の庭番をつかまえて、自分の方が上と? 言いますね」
「紅魔館のメイド長よりも家事ができる? ……面白い冗談ね」
一触即発。
三者三様のプライドを火花に変えてぶつけ合う、自分こそ最高と信じて疑わない三人。
いつのまに三つ巴になったのやら……
「……こうなれば」
いいながらスペルカードを取り出す妖夢。
「あら、分かりやすくていいわね」
同じように咲夜もスペルカードを手にとった。
「……」
一方いまだ丸腰のままの○○。
ただの人間である彼にはスペルカードなど使えるわけもなく……
「どうしたんです? まさか素手で闘うつもりですか?」
「へえ…… 甘く見られたものね。やって見せてもらおうかしら」
矛先を一辺に向けられた○○、早くもピンチである。
それでも主人、……いや、嫁である藍が見ているのだ。
情けない真似はできない。
「ちょっと待て、悪魔の狗に半霊。わたしの目の前で○○を痛め付けようなんて、良い度胸じゃないか」
そこに助け船を出す藍。橙を引き連れ、すでに臨戦体制である。
「……式の猫といい、ずいぶんと部下を甘やかすのね」
「訂正しなさい。○○はわたしの夫であって、部下じゃない。
それに、彼が傷付くところは見たくない」
「主が従者を守るだなんて、おかしな話ではないですか?」
「○○を従者と呼ぶな」
「同じよ。立場としては」
「……少し痛い目に逢いたいのかしら、悪魔の狗」
くっと目を細めた藍に内心動揺しつつも簡単には引き下がれない二人。
「ら、藍、もういいから……」
「いいや、良くない。わたしはともかく、○○と橙を馬鹿にする奴は誰であろうと許さない」
止めなくてはと、○○は藍に駆け寄るが、効果無し。
しばしの睨み合いの後。
「その辺にしなさい、妖夢」
「幽々子様!?」
「咲夜、あなたもやりすぎよ」
「お嬢様……」
膠着状態を破ったのは、紅魔館と白玉楼、それぞれの主であるレミリアと幽々子。
「ごめんなさいね、紫の式。この子もまだ半人前なのに生意気に」
「……申し訳ありませんでした」
「私からも謝るわ。まさか咲夜の失態をフォローする事になるなんてね」
「……お恥ずかしい限りです」
主にたしなめられうつむく従者二人
「だけど、このまま終わりにするにはもったいないわね、この展開」
「奇遇ね、わたしもそう思ってたところよ。
……というわけで」
レミリアと幽々子が笑いかける先には、心得たとばかりににやつく紫と文。
……そして話は冒頭に戻る。
「さあ始まりました。第一回従者オブ従者選手権決勝戦。司会はわたくし、射命丸文です。どうぞよろしくお願いします」
「解説の八雲紫です。よろしく」
あの時の一コマからわずか三日でこれである。
……最早突っ込むのもばからしい。
「あや~、それにしても、ずいぶんとお客さんが集まりましたね」
「貴女の記事の仕業ではなくて? 新聞記者さん」
「そうであれば喜ばしい限りですが、どちらかといえばあなたの仕業だと思いますが。
ああ、催しの宣伝の際には文々。新聞を是非ご贔屓に」
フィフティーフィフティーでこの二人の仕業だ。間違いない。
本当にわずか三日でよく集まったものだ。
普段宴会で見る連中はいいとして、里の人間まで混じっているのはどういうことだろう。
人知れず頭を抱える○○。
「さて、関係ない話はそのくらいにして、そろそろ始めましょうか」
「そうですね。ではこれより第一回従者オブ従者選手権決勝戦を開催いたします」
文の開会宣言とともに、満員の観客席が沸く。
幻想郷には暇人が多いらしい。
「……すまないな、○○。紫様が迷惑をかけた」
すまなそうに謝る藍。
「なに、俺が君のことをどれだけ想っているか、アピールするいいチャンスだよ」
多少の去勢はあるが、藍を想うこの気持ちは、誰にも負けない自負がある。
他のことはともかく、あの二人に想いで負けるわけにはいかない。
「……ばっ、馬鹿!」
頬を染め、照れ隠しに目を逸らす藍。
なんというナイスリアクション。これだから、八雲の専業主夫はやめられない。
「それではまず、ルール説明をしたいと思います。これから幾つかの質問に答えていただき、それを審査員が10点満点で評価します。総合得点の高い者が優勝となります」
「平時からの心構えがカギというところかしらね」
「単純な力だけが優秀な従者の条件ではありません」
「ええ、マヨイガの主夫が、それを証明してるわ。ただの人間があんな中決勝まであがってくるなんて、正直驚いたもの」
しかしこの進行役、ノリノリである。
早くも板についているあたり、流石というかなんというか……
というより、今更だが予選なんか何時やった?
「続きまして審査員の紹介をさせて頂きます。
まずは一人目、幻想郷の歴史を語り続ける求聞持の賢人、稗田阿求さんです」
花の髪飾りをつけた小柄な少女がぺこりと頭を下げる。
……だからどんだけ暇なんだよ、幻想郷。
「縁起に載るだけの妖怪たちの主従関係。非常に興味深いです」
……仕事の一環ですか?
それともただの職業病ですか?
「阿求さん、ずばり今回の注目点は?」
「もちろん、○○さんです。あの八雲藍の夫がただの人間であることには、わたしも驚きましたから」
「主であるわたしも驚いたわ」
「今日は○○さんのことを調べあげて、縁起に追加掲載するつもりです」
これはいよいよ情けない真似は出来ない……
「○○、そんなに硬くなるな。結果が振るわなくとも、お前の想いをしっかり伝えてもらえれば、わたしは満足だから」
「藍……」
「それでは、今日はどうぞよろしくお願い致します」
「はい。……わくわく」
目の前の鴉天狗のお株を奪わんばかりに、わくわくしている阿求。
……職業病だな、ありゃ。
「続きまして、永遠亭の月の兎、鈴仙・優曇華院・イナバさんです」
「よろしくお願いします」
「同じ立場の目線といったところかしら」
「惜しくも予選で小野塚小町さんに敗れてしまいましたが、今回、誰が優勝すると思われますか?」
「誰が優勝してもおかしくはないとおもうわ。まぐれでここまで勝ち上がってきたわけではなさそうだし」
「成る程。目が離せない戦いとなりそうですね」
「そうね」
「それでは、審査員よろしくお願いします」
……あれ? ひょっとして、「決勝」に突っ込んでるの俺だけ?
「さて、最後の審査員は、……って何でこの方? 水橋パルスィさん」
「……平気でわたしをぞんざいに扱える貴女が妬ましいわ」
「ストレートな審査なら、彼女が一番でしょう。だから呼んだのよ」
「……妬ましい、妬ましいわ。こんな争いを起こすほどに慕われてる主も、慕う相手のいる従者も」
「成程、分かりやすいですね」
確かに分かりやすいかもしれないが ……非常に怖い。
「さて、審査員も出揃いましたところで、いよいよ選手入場といきましょう」
待ってましたとばかりに観客が歓声をあげる。
どいつもこいつも本当にノリがいいな。
それともこれが普通なのか?
……どこぞの巫女の、頭のネジを外しただけある。
「まずは、紅魔館のメイド長、十六夜咲夜!」
名前を呼ばれると同時に、お得意の時間操作能力で音もなく現れる咲夜。
「予選から他を寄せ付けない圧倒的な強さで決勝進出。瀟洒な従者ここにあり!
主への絶対の忠誠とその能力で今回の優勝候補です!」
「紅魔の名に敗北の文字などありません。従者のなんたるかを皆さんにお教え致しましょう」
穏やかな表情で頭を下げる。
うん、瀟洒だ。
「続いて白玉楼の庭師、魂魄妖夢!」
目にも止まらぬ早さで、台上にあがる妖夢、一陣の風と共に参上だ。
「小柄な体つきならではのフットワークは抜群。主のために日々成長中! まだまだ未知数のその力に期待です!」
「剣を持つものとして、従者の名において、負けるわけにはいきません。全力でお相手させていただきます」
真っ直ぐに咲夜を睨み付け、宣戦布告をする妖夢。
対する咲夜は余裕ともとれる笑みで受け流す。
「あらあら、早くもボルテージが上がってきたわね」
「最初からクライマックスてやつでしょうか?
……さて、そして最後に八雲の専業主夫、○○!」
「それじゃ、行って来る」
「ああ、行ってこい。……ふふ、いつもと逆だな。頑張れ」
「ああ」
ゆっくりと台上へと向かう○○。
その姿は二人とはまた違った風格を、……醸し出せてはいない。
「持ち前のガッツと、主人八雲藍への強い想いで、ここまで勝ち進んだ、ある意味で幻想郷最強の人間。
今日、ついにその全貌が明らかになります!」
会場の視線が自分に集まるにつれて、開き直りに近い度胸が湧いてくる。
「俺は従者でなく主夫だ。この二人に戦闘では勝てない。
だけど、藍を愛する気持ちは、従者の主を想うそれに劣らない。
愛する人のために、力の限りに戦い抜くつもりだ」
先ほどまで頭を抱えていた姿はどこへやら。
なんだかんだでノリやすい○○も、立派に幻想郷の住人なんだろう。
「なんというか、甘いですね」
「文字通り、甘く見ると痛い目に遭うわよ」
「すいーつってやつですか?」
「甘い砂糖と、スパイスと、その他素敵な、なにもかもってね。まさかこのわたしが二人の前で膝を付くなんて思わなかったわ」
「八雲紫が、ですか!?」
「ええ、普段はすましてるけど、二人きりな時には近付かない方が良いわ。
一歩近付きゃ、砂糖にまみれ
二歩近付きゃ、味覚を忘れ
三歩近付きゃ、貴様も桃色の空間に溺れるがいい……」
「あ、あの、紫さん、その位で勘弁して下さい」
恥ずかしい紫の解説を止めにはいる○○。
「あら、これからだったのに、残念。
ともかく、これで役者は揃ったわね」
「はい。それでは改めまして、これより第一回従者にオブ従者選手権決勝を始めたいと思います」
割れんばかりの大歓声が、会場に響き渡った。
新ろだ115
───────────────────────────────────────────────────────────
目の前で花弁のように広がる九房の柔毛。金色の光沢を持つその一房を手にとり、俺は丁寧にピンブラシを掛けていく。
毛を傷つけないように、生きている毛を抜いてしまわないように、ゆっくりゆっくりと時間を掛けて作業をする。そうして被毛のもつれを解き、ホコリを除去して、次の作業に移る。
ピンブラシでのブラッシングが終わったら、豚の毛を用いた柔らかいブラシを使って抜け落ちた毛を絡め取っていく。
一房だけでも結構なボリュームがあるためにそこそこの時間がかかるものを、あと九回も繰り返さなければならないのだ。
だが、それもまた楽しいものである。
俺がじっくりと時間を掛けて房の一つ一つに取りかかっていると、この房の持ち主から声がかかった。
「いつもすまないな。自分ではよく見えないし、手も届かないからあまり手入れが出来なくて……」
「いや、気にしないでくださいよ。藍さま」
俺が手入れをしているのは八雲藍、つまり九尾の狐と呼ばれる最強の妖獣の尻尾なのである。
最強の妖獣とはいえ、無礼を働かなければ穏和で折り目正しいお姉さんだ。恐れることはない。
何より、俺はこの美しい九尾と彼女の人柄に魅せられていた。
「俺も藍さまの尻尾を手入れするの、好きですし」
「そう言ってくれるとありがたい。この九尾は私の自慢なんだが……」
九尾の狐なんだから、そりゃ尻尾は自慢だろう。それ以前に、ツヤ、手触り、ボリュームのどれをとっても最高の尻尾だ。自慢になるのももっともだと言えよう。
「手入れをしようと思っても自分では出来ないし、軽々しく他人に触らせたくもない。かといって、紫様にやらせるわけにもいかないし、橙は少し頼りない。君がいてくれて本当に助かっているよ」
「俺なんかに藍さまの大事な尻尾を預けてもらえて、逆に光栄ってなもんです」
「そ、そう。そうなんだ。君だから、この尻尾を預ける気になるというわけで……」
ん? ちょっとモジモジしないでください、藍さま。ブラシが掛けにくいですから。
無意識にやっているのか、そんな俺の思いとは逆に、藍さまは尻尾をワサワサと揺すっている。
まさか尻尾を鷲掴みにするわけにもいかないので、優しく尻尾の先だけを掴んでブラッシングを続けた。
「それに、九本もあるから手間も時間もかかるだろう? それを手入れして欲しいなんてワガママを聞いてくれて、感謝している」
感謝するのはこっちですよ。藍さまの尻尾を手入れさせてもらえるんですから。
名残惜しいと感じつつも、俺は最後の尻尾にブラシをかけ終えた。終了の合図に藍さまの肩を軽く叩く。
こっちを振り向いた藍さまに向かい、俺は言った。
「構いませんって。それに藍さまはもっとワガママ言わないと、ストレスでパンクしちゃいますよ? 俺でよければ聞きますから」
すると藍さまは一瞬驚いて、次に嬉しそうな、最後に照れ臭そうな顔をした。
「……参ったな。ワガママを言えなんて言われたのは初めてだ、嬉しいよ。だが、これ以上君に私のワガママを押し付けるのも心苦しい。
そこで」
コホンと一つ咳払いを入れる藍さま。どことなく顔が赤いのは気のせいだろうか?
「私も君のワガママを聞いてあげようと思う。それならお互い様だろ?」
「いやいや、それには及びませんって。藍さまの胃袋に穴を開けるわけにはいかないですから」
さっきは咳払い。今度は溜息をつく藍さま。
「……まったく、鈍いな君は。私は君と、ワガママを言い合えるような関係になりたいと、そう言っているんだ」
一方的ではなく、互いにワガママを言い合える関係。主従でも家族でもなく、友人ともわずかに違ったその関係。
ああ、そうか。気づいていなかったんじゃなくて俺が真っ先に切り捨てた、諦めていたその関係。それを指しているのか。
「じゃあ、言います。……これからも、俺だけに藍さまの尻尾の手入れをさせてください。他の誰にも渡したくありません」
「やれやれ、それじゃ今までとほとんど同じじゃないか。でも約束させてもらうよ、君以外には決して触れさせないと。
……それで、私からも新しいワガママを二つほど言わせて欲しい」
俺はコクリと頷いてみせる。柔らかく微笑んで、藍さまは言った。
「私に敬語を使うのはやめてくれ。それから私のことはこう呼んでくれ……藍、と」
「分かったよ、藍」
戸外からパラパラと音がする。窓の外を見れば、雲もないのに雨が降っていた。
藍の体を抱きしめつつ、俺は天の神の粋な計らいに感謝した。
新ろだ188
───────────────────────────────────────────────────────────
斜陽の差し込む土間に二つの椅子を並べ、俺と藍はそこに腰掛けていた。
二人で仲良く横並びに座るのではなく、俺が藍の背後にくっつくような形で座っている。
藍の背中の最下部、腰骨の辺りから垂れ下がる金毛の九尾を自分の膝に乗せ、その一房をそっと掴む。
そして、俺は自分の得物を取り出した。
「藍、始めるよ」
「ああ、よろしく頼む」
ピンブラシ、獣毛ブラシ、金属製の櫛。その三つを使い、丁寧に被毛のもつれを解き、ホコリを除去し、廃毛を絡め取って、仕上げに毛を整える。
それを九回にわたって繰り返すのは手間も時間もかかる作業だったが、まったく苦にはならなかった。
これは義務でも仕事でもなく、俺に与えられた特権なのだから。
丹精して藍の九尾を手入れしていくと、わずかな違和感を覚えた。
少しばかり尻尾の手触りがパサついた感じがするし、日本刀の刃文を思わせる光沢もくすんでいる。
この九尾は藍の自慢なだけに、常に美しく保っておきたい。俺はいつも以上に時間を掛けて手入れをしていった。
「藍、終わったよ」
最後の尻尾を櫛で整え、俺は藍に声を掛けた。藍からの返事はなく、振り返りもしない。
「……藍?」
不思議に思って前に回ると、藍はコックリコックリと船を漕いでいた。どうも居眠りをしているらしい。
無防備な寝顔は可愛らしいが、椅子の上で船を漕いでいるというのは大変に危ない。
起こしてやろうかとも考えたが、この寝顔をもう少し見ていたい。俺は藍を横になれる場所に運んでやろうと手を伸ばす。
しかし俺の手が触れるその寸前、藍の肩がピクリと動いた。残念に思いつつ、俺は手を引っ込めた。
「……おっと、いつの間にか眠ってしまったのか」
目を覚ました藍はゆっくりと頭をもたげ、俺の顔を見て自嘲気味に微笑んだ。
「だらしない顔を見せてしまったな、忘れてくれるか」
「あんなに可愛い寝顔、忘れられないよ」
「……っ! と、年上をからかうんじゃない、まったく……」
口ではそう言っているが、藍もまんざらではなさそうだった。照れ気味の表情と尻尾の動きがそれを物語っている。
と言うか、あんまり尻尾を振るとホコリが付いてしまうんだが……ただでさえ静電気の溜まりそうな尻尾なんだから。
まあ、それは後で何とかするとして、俺には気になっていることがあった。
「それにしても、藍が居眠りするなんて珍しいな」
「……ん、ああ。あんまり気持ちがよかったからつい、眠くなってしまったよ」
嬉しいことを言ってくれるじゃないか。でも、それだけじゃないだろう。俺は指摘する。
「藍、疲れてるんじゃないのか?」
「……バレていたのか」
「尻尾を見れば判るさ。毛づやも手触りも、いつもより少し落ちてたからね。疲労やストレスが溜まってる証拠だ」
「ふふ、君は私の専門家だな」
藍はわずかに嬉しそうな表情をしたが、その顔にははっきりと疲れが見て取れる。
やつれていると言うほどではないが、どことなく精彩を欠いていた。
「そろそろ紫様が長期睡眠に入る時期だから、いろいろとまとめて仰せつかっていてね……。
この仕事が済めば、しばらくは私も暇が持てるんだが」
ふう、と大きく息を吐く藍。やはりずいぶんと疲れが溜まっているようだ。
どうにか藍の力になってやりたいが、九尾の狐でも一苦労の仕事を前に、ただの一般人である俺にどれだけのことが出来るのか。
俺にも妖怪並みの能力があれば……と考えたその時、俺の脳裏に稲光のごとく妙案が閃いた。
「藍。俺を藍の式にしてくれないか?」
「!? ……どういう風の吹き回しだ? 私の式になりたいだなんて……」
藍は驚いて目を丸くしている。まあ、それはそうだろう。普通、妖怪の式になりたいと言う人間はいないからな。
俺は答えた。
「藍の式になれば、条件次第じゃ藍と同じ能力を発揮できるらしいじゃないか。
そうすれば藍の力になれるだろ? そうでなくても、ただの人間よりはマシだと思うよ」
ぐっ、と藍は声を詰まらせる。感激でもしてくれたのか、嬉しそうに笑いながらも目の端には光るものが見えた。
光る雫を指先で拭い、藍はかぶりを振った。
「君の気持ちは嬉しい。……本当に、だ。でも、君と私はそんな『使う』『使われる』の関係じゃないだろ?
私たちは、その、こ、こい……」
「……恋人。対等な、互いにワガママを言い合える関係、か」
顔を真っ赤に染めて、藍は水飲み鳥の玩具みたいに首を上下に振った。杞憂だと分かっているが、頭がスッ飛んでいかないかと心配になる。
藍の言うとおりかもしれない、と俺は考えた。
俺は俺の意思で藍の支えになりたい。命令に従う式神というのは、やはり違う気がする。
「そうだな、俺も藍と対等でありたい。やっぱり、俺は俺に出来るやり方で藍を支えるよ」
「はは、そんなに気を張らなくてもいい。今までの君で充分さ」
「藍の式神になるのも悪くないと思ったんだけどな」
俺がそう言うと藍はちょっと考えて、何だか恥ずかしそうにしながら口を開いた。
「じゃあ……少しだけ、真似事でもしてみるか?」
「真似事? ああ、何でも命令してくれ」
よく分からないが、藍は何か俺にして欲しいことがあるのだろう。もちろん、俺はその話に乗ることにした。
俺が了承すると、藍はうつむき加減で何かを呟いた。
「……を……てくれないか」
「ああ、そんなこと」
「そ、そんなことって言うな! 今の一言を言うのに私がどれだけ恥ずかしい思いをしたと……」
「まあまあ」
喚いている藍をなだめつつ、俺は座敷のへりにどっかりと座り込んだ。大きく足を開き、太股をポンポンと叩く。
藍は唇を尖らせつつもこっちに寄ってきて、俺に背中を向けて膝の内側にドスンと座り込んだ。
俺は藍の帽子を脱がせ、頭の上に手を置いた。
そして。
なでなで。
「……あ」
なでなで。
「……」
「どうだ?」
なでなで。
「何というか、幸せな感じがする……」
「頭を撫でて欲しいなんて、藍は可愛いなあ」
「……橙にはよくしてやるが、自分がしてもらうのは初めてだ。すごく、安心するな……」
恍惚としながら、藍は俺の胸に背中を預けてくる。
喜んでもらえたようで何よりだ。けど、他にも藍が望むことがあるならしてやりたい。
耳の裏側の付け根を重点的に撫でながら、俺は聞いてみた。
「他には?」
「……その。ぎゅっ、ってしてくれ……」
「了解」
藍の両脇から腕を前に回して、ぎゅー。
しばらくしても藍は何も言わない。さらに、ぎゅー。
やっぱり藍は無言のまま。もっともっと、ぎゅー。
いつまで抱いていればいいのだろうか。まあ、いつまででも構わないけど。
いつも頑張っている藍にたまのご褒美だ……というか、俺にとってもご褒美だが。
などと考えていると、ようやく藍は口を開いた。
「……はあ。幸せなものだな、誰かに支えてもらうというのは。
九尾となってから、紫様の式となってから、こんな風にしてもらうのは初めてだ。
力を得て、誰かに甘えることなど忘れてしまったような気がする」
「藍は可愛くて器用で可愛くて強くて可愛くて賢いからね。どうしても頼られる側になるんだろうな。
でも、藍はもう少し他人を頼ったり甘えたりしてもいいんじゃないかな?」
俺の胸に頭を当てて、藍は俺の顔を見上げてきた。普段とは違った視線に心臓が一拍、強く弾んだ。
「それならもうやっているさ。この通り、な」
大した人間でもない俺を支えにしてくれるのはすごく嬉しい。でも、そうじゃないんだよ、藍。
俺は小さく首を横に振った。
「違うよ。もっと身近な人たちを信じてみたらどうかな、ってことさ。
紫さまもきっと、藍が甘えたら優しくしてくれる。橙だってきっと、藍が頼れば期待に応えてくれる。
二人と会ったことはないけど、俺は藍を信じてる。藍の好きな人たちは藍を裏切らないって信じてる」
何をえらそうに言ってるんだか、と自分でも思う。
だけど、どんな理由にせよ、俺はいつか藍の前から姿を消す。その時、藍には他に頼れる人がいることを知っておいて欲しい。
例え俺には分からなくても、俺がいなくても藍は笑って暮らしていると信じていたい。
俺を見上げたまま、藍は目を細めて笑った。気負いのない、いい表情だ。俺の守りたい、藍の笑顔。
顔の向きを前へと戻し、藍は言った。
「……そうだな。君の信じてくれる、私の中の二人を信じてみよう。
甘えてみたら、紫様は私のワガママを聞いてくれるかな?」
「きっと。藍の御主人様なら、藍を大事にしてくれるはずさ」
「なら、一つお願いでもしてみようか」
藍のお願いとは何だろう。お暇をください、とかじゃないよな。何かが欲しいのか、何かをして欲しいのか。
紫さまにお願いするくらいだから、きっと俺には出来ないことなんだろう。
顔も知らない紫さま、どうか藍のお願いを聞いて上げてください。
俺が心の中で祈っていると、そのまま藍は言葉を続けた。
「マヨヒガに一人、新しい家族を増やしたいのですが……と」
「へっ?」
思いがけない発言に、思わず素っ頓狂な声をあげてしまう。
まさか、どこかから動物を拾ってきて飼いたいという意味じゃないだろう。と言うことは、ひょっとして……?
藍を見れば、広々とした袖で恥ずかしそうに顔を覆っていた。
「き、君も心の準備をしておいてくれっ!」
藍は帽子をかぶりながら勢いよく立ち上がると、呆然とする俺の鼻を抓んで家を飛び出していった。
マヨヒガに新しい家族? 俺に心の準備? それって、やっぱり……。
「……一緒に暮らそう、ってことか?」
独りごちて、やっと認識する。
勝手に頬が緩むのが分かるが、自分の意思では止められない。きっと、今の俺は妖怪ですら目を逸らすほど薄気味悪いだろう。
まったく締まりのなくなった顔で柏手を打ち、俺はさっきと同じように祈った。
「紫さまっ! どうか藍のお願いを聞いて上げてくださいっ!」
ふと首筋に感じる、冷たい空気の流れ。戸も窓もしっかり閉まっているはずなのに……スキマ風?
俺が不思議に思っていると。
「だったらまず、その薄気味悪い顔をどうにかなさいな。正視に堪えないわよ」
「!?」
耳元に届くあでやかな女性の声。頭の中に響いたとかではない。確実に俺の鼓膜を震わせていた。
しかし、声の主らしき姿はどこにも見当たらない。
「……幻聴、か? それとも、妖精の悪戯……?」
さっきの声が親切に答えてくれるということはなかった。
ただ、なんとなく、藍と一緒に暮らせるのはもう少し後になりそうな予感がひしひしとしていた。
新ろだ195
───────────────────────────────────────────────────────────
年の瀬も押し詰まり、今年も残すところあと一週間となった。つまり、今夜は聖誕祭前夜である。
今日はそのお祝いも兼ねて……というより、それを口実にして俺はマヨヒガの面々と顔合わせをすることになっていた。
恋人である八雲藍と、その主の紫さまに、藍の式である橙。どんな人たちなんだろうか、期待と緊張で胸は高鳴りっぱなしだ。
プレゼントも用意したし、後は藍が迎えに来てくれるのを待つだけだった。
「ん……?」
何げなく天井を見上げると、奇妙な物体が浮いていた。陽光を思わせる山吹色をした、毛の塊が九本。
どこかで見たことがあるような……というか、藍の尻尾にそっくりなんだが。
目の前の異様な光景に首をひねっていると、唐突に空間が裂けた。
何を言っているのか分からないと思うが、そうとしか表現できない。カーテンを左右に開くように、空間の一部が開いたのだ。
開いた空間からコロリと飛び出てくる尻尾……と、その持ち主。
藍だ!
思わず飛び出した俺の手の中に、藍が転がり落ちてくる。急に腕にかかった重みによろけてしまうが、俺は何とか転ばないように踏ん張った。
「ふう、危なかった……」
「あ、ありがとう。おかげで助かったよ」
俺は藍をそっと床に下ろし、疑問をぶつけた。
「いったい何がどうなってるんだ? いきなり目玉だらけの空間が開いたと思ったら、藍が転がり落ちてきて……」
「それは後で説明するが、先に言っておかなければならないことがあるんだ」
衝撃的な登場の仕方をした藍は、真剣そのものの面持ちで、さらに衝撃的な発言をした。
「クリスマスは中止になった」
!?
あまりにも突飛な発言に俺は固まってしまった。
「……何ですと?」
「すまない、言い間違いだ。正確には『クリスマスパーティーは中止になった』だ」
何だ、言い間違いか。てっきり原油高の影響でサンタの都合が悪くて中止になったのかと……。
「え、中止!? マヨヒガでやる予定だったのが?」
「ああ。楽しみにしていてくれた君には申し訳ないんだが……」
「何で? 紫さまの都合が悪いとか……」
俺が尋ねると、藍は何とも決まりが悪そうな表情をした。
「ええと、その……。今日、君の紹介を兼ねて祝宴を催したい旨を紫様に伝えたところ……
『クリスマスって言ったら二人きりで過ごすでしょ常識的に考えて……』
と、ものすごく微妙な顔で言われてしまった。
それで、今日明日は帰ってこなくていいからと、スキマに放り込まれてしまって……」
「スキマ?」
妙な文脈の単語があったので、尋ねてみる。
すると、藍は端的に紫さまが操る空間の裂け目だと説明してくれた。とんでもない能力だ。
しかし、ピンポイントで俺の家に放り込んできたってことは……。
「もしかして、俺たちのこと知ってるんじゃ?」
「どうもそうらしい。どこかで覗いて……監視……見守ってくれていたんだろう」
何というプライバシー侵害。
これも藍の気苦労の一つなのだろうか。藍は目を瞑り、全身が萎みそうなほど大きな溜息をつく。
気を取り直して、藍は言った。
「ともかく、今日明日と私は帰るところがなくなってしまったわけだが……」
片目を開け、チラリと俺を見る。素知らぬ顔をする藍だが、鼻の頭が少し赤かった。
「だったらウチにいればいいさ。大して広くはないけど、客用の布団くらいはおいてあるし」
「そ、そうか。じゃあ、世話になるよ」
「ああ、遠慮なくどうぞ」
当初の予定とは違ったけど、まさか藍と二人だけのクリスマスとは。嬉しい、嬉しすぎるぞ。
「しかし、サンタは煙突から入ってくるものだとばかり思ってたけど、まさかスキマからプレゼントを投げ込んでくれるとは」
「あの方なりに気を遣って下さったのだろうか……?」
「藍が頑張ってくれてるから、ご褒美をくれたんだよ」
「……そうかもしれないな」
一応頷いてはいるけど、顔が全然納得してないぞ、藍。『遊ばれている気が……』とか言ってるし。
何でそんなに信用ならない妖怪(ひと)に仕えているのか、俺は不思議でしょうがなかった。
何はともあれ、これからのことを考えよう。
「二人で過ごせるのはいいけど、予定が変わっちゃったな。準備をやり直さないと」
「マヨヒガで過ごすものとして準備を整えてきたからな。とりあえず、買い出しに出ようか」
「そうだな」
そういうことで、俺たちは街に買い出しに出ることにした。
二人並んで街を歩きながら、藍は幾度となく俺の方に視線を送ってきた。ふと気づく、所在なげな藍の左手。
周りを見れば、俺たちと同じような仲睦まじい男女が何組も見える。その中で俺だけが……。
なんて馬鹿野郎なんだ、俺は。
藍の喜ぶことだけを考えてきたつもりなのに、こんな簡単なことに気が付かないなんて。
自分の間抜けさを呪いつつ、俺は藍の左腕に自分の右腕を絡め、指を併せるようにして手を握った。
「ごめん。ずいぶん冷たくなっちゃったな」
「鈍感は罪だぞ? まあ、自分で気づいたから今回は許してあげよう」
「もっと経験を積まないとな」
「ふふ、なら私が協力してあげようか」
藍が機嫌を直してくれてよかった。俺ももっと男を磨かないとな。こんなざまじゃ紫さまに申し訳が立たない。
気合いを入れ直して、俺は藍と一緒に街を巡った。
七面鳥を焼こうか、たまにはワインもいいんじゃないか、ケーキはどうしよう、稲荷寿司は他と浮いてるんじゃないか、などと話しながら二人で買い物を進めていく。
もちろん、その間もずっと手は繋いだままだ。
そうしているうちに、空からちらほらと舞い降りる冬の妖精。雪だ。
ひとひらの雪を藍が手に取ると、それは幻想であったかのように儚く消える。
しばし雪を眺めて藍は言った。
「雪か……。今夜は寒い夜になりそうだな」
「いや、暖かい夜になると思うよ」
俺の言葉に藍は小首をかしげた。俺も学んでるんだよ、藍。
「今夜は二人だから。さっきみたいに、藍に冷たい思いはさせない」
「……そうだな。身を寄せ合わないといられないくらい、寒くなるといいな……」
そう言って、俺たちは肩を寄せ合った。
風景に交じる雪の量が次第に増えてくる。今夜はとても冷えるだろうが、寒ささえも俺たちにはクリスマスプレゼントだ。
雪よ、降り積もれ。
その分、俺たちの想いも積もってゆくから。
新ろだ217
───────────────────────────────────────────────────────────
俺と藍が並んで街を歩いていると、人だかりがあった。その人だかりの最前列には羽織袴と白無垢の男女。
結婚式か。藍の花嫁姿は、それはそれは画になるんだろうなと、思わず空想する。
「花嫁衣装か……。いつかは私も着てみたいものだな」
花嫁をじっと見つめて、藍は呟いた。
俺が着せてあげるよと言おうとすると、藍は言葉を続けた。
「きっと、花嫁衣装を着る私の隣に立つのは君ではないんだろうな」
「えっ……」
「君よりも力があって、知恵も回って、地位も財も兼ね備えた男がいいな。ひょっとすると、相手も九尾の狐かもしれない。
そして、誰もが私たちの結婚を祝福してくれるんだ」
そう言って、藍は軽く笑った。
当然の発想だった。俺みたいなただの人間よりも、その方が藍を幸せにしてくれるだろう。
分かってはいるが、目の奥から熱いものが込み上げてくる。
それが目からこぼれる前に、藍はさらに言葉を紡ぐ。
「けれど、そこに君が唐突に現れて、私に手を差し出すんだ。
私は力も地位も財もない、私に優しくしてくれるだけのただの人間を選んで、式場を飛び出していく。
そしてどこまでも、二人だけの場所を目指して駆けていくんだ」
ふわりと微笑んで、藍は言った。
「どうだ、素敵だろう?」
やはり、目から熱いものが溢れそうになる。けど、その理由は先ほどとは正反対だった。
ぐっと堪えて、言葉を搾り出す。
「ああ、最高に素敵だ。藍に手を差し出したとき、藍に選んでもらえるように頑張るよ」
「ふふ、期待しているからな」
そっと伸ばされた藍の手を、俺はしっかりと握りしめた。
* * *
「……ところで」
「ん?」
「もしも紫様が私たちの結婚に反対したとして、その時君は私を攫って逃げてくれるか?」
即座に俺は首を横に振った。そして、答える。
「ダメだよ。紫さまは藍の家族だろ? だったら、祝福してもらわなきゃ本当の結婚とは言えないと俺は思うよ。
紫さまから藍を攫ってはあげられないけど、その代わり、絶対に紫様に認めてもらってみせる。
……これで、どうかな?」
俺の出した答えに、藍は春の日差しのように柔らかな笑みで返してくれた。
新ろだ312
───────────────────────────────────────────────────────────
割烹着を着て、頭には手ぬぐいを姉さん被りにした藍が、はたきをかけながら尋ねる。
煎餅をかじりながら、ふさふさと揺れる藍の尻尾をぼんやり眺めていた紫は、問いに気付いて意識を戻した。
「なあに?めずらしいわね、貴女がそんなこと言うなんて」
滅多にない展開に興味を抱いたらしく、身を乗り出す紫。
「その……後ろからと前からと、どちらの方が愛があるものでしょうか」
藍の質問に紫は一瞬目を丸くしたが、すぐににやりと意味深な笑みを浮かべる。
「あらまあ、藍もずいぶんと大胆になったものね。
昼間からそんな、紅魔館の魔女が目を吊り上げそうなことをさらっと言うなんて。やっぱり恋人ができると違うわねぇ」
人の悪い笑顔でそんなことを言われた藍は、顔を真っ赤に染めてしまった。
「な……あ、いえ紫様、私はそんな意味で言ったわけでは」
「あら、私がどんな意味に取ったと思ってるのかしら?」
頭から湯気が出るのではと思える様子で焦る藍を見て、紫はおかしそうに笑う。
「冗談はこのぐらいにしておきましょう。
それで?どうしてそんなことを?」
「もう……いえ、○○のことなんですが」
○○は、幻想郷に迷い込んできたところを紫が拾ってきた外の人間だ。
本当ならすぐに送り返すはずだったのだが、ちょうど冬眠前で眠かった紫が面倒くさがり、
「起きたらちゃんと片付けるから、しばらく面倒見といて」
と、式神二人に押し付けてしまったのだ。
春が来て紫が起きてみると、○○はすっかりマヨヒガに馴染んでしまっていた。
外の世界に帰すから、と切り出した紫に、まず橙が「ちゃんと面倒見るから○○を帰さないで」とぐずり、
藍は藍で「橙もあのように懐いていますし、このまま置いてしまっては」などと言いながら、
その実自分もひどく寂しそうな顔を見せた。
当の○○も別れ難い様子であることから結局紫が折れ、
○○は家事手伝い兼橙の遊び相手兼紫の暇つぶしとしてマヨヒガで暮らすことになった。
意外と家事が得意だった○○はそれまで藍が一人でやっていた仕事を手伝うことが多く、
結果として藍と一緒に過ごす時間が多くなっていった。
二人の関係が特別なものになっていったのも、起こるべくして起こったことと言えるかもしれない。
人目をはばからずイチャつくわけではないが、それでも紫は幸せそうな○○を、初々しく彼に寄り添う藍を、よく目にするようになった。
……いや、実際のところは退屈しのぎに自らスキマを開けて二人の様子を眺めているのだが。
「その……○○が、私のことをよく抱きしめてくれるのですが」
「けっこうなことじゃない」
「最近はいつも、背中からなのです」
「……それで?」
「私の尻尾を気に入っている、そうで」
ふわり、と金色の尻尾が揺れる。
ふさふさした彼女の尻尾の感触が心地よいことは、長い付き合いである紫にもよくわかっている。
「いいじゃないの。その尻尾は、貴女にとっても自慢でしょう?」
「ですが、その……」
「もう、何なの?」
幾分いらだちを含んだ声で、紫は問いかける。
ためらいがちに話す藍の言葉からは、依然話が見えない。
「私は、ちゃんと愛されているのでしょうか?」
「……?」
「後ろから抱きしめる方が、前から抱きしめるより愛情のこもった行為なのでしょうか。
そうでなかったら、○○はもう私ではなくて、私の尻尾に惹かれているだけなのでは、と……
もし、尻尾がなかったとしても、○○は私を抱きしめてくれるでしょうか?」
紫は呆れたようにため息をついた。
恋とは、あの冷静な藍をここまで不安定にするものなのか。
取るに足らないようなことをこんなにも深刻に捉え、悩み、不安そうにしている藍の姿は、紫にとっても目新しいものだった。
「直接聞けばいいんじゃないの?もしくは尻尾をしまっておくとか。
それぐらい藍ならたやすいでしょうに」
「そ、それでもし、『尻尾が好きなだけ』と言われたら?抱きしめてくれなくなったら?
紫様、私は、私は……」
「ああもう、落ち着きなさい!」
かなり重症らしい。なんらかの対処が必要だろう。
この状況を半ば面白がりつつも、紫は考え込んでしまった。
スキマから新たな煎餅の袋を取り出す。
「ねー、○○」
「ん?なんだい橙」
庭の掃き掃除をしながら、○○は返事をする。
橙は縁側に腰掛けて足をぶらぶらさせながら、○○の仕事ぶりを眺めていた。
「○○は、藍さまのこと好き?」
「好きだよ」
即答する。あまりやりすぎると教育上よろしくないので、なるべく橙の前ではべたべたしないように心がけているが、
お互いを好きあっていること自体は別に隠すことではない。
「藍さまの尻尾は好き?」
今まさに藍がそのことで悩んでいるとも知らず、橙は特に深い考えもなく問いかける。
頭の中で少しその感触を思い出してから、感慨深げに○○は答えた。
「……好きだな」
「ふかふかで気持ち良いよね」
意見が一致したことが嬉しいのか、楽しそうに笑う橙。
穏やかな一時を過ごしていた二人のところに、廊下の向こうから紫がやってきた。
「あら、楽しそうね」
「あ、紫さん」
「どうしたんですか、紫さま?」
「橙、ちょっといいかしら」
「はーい」
呼ばれて、橙は立ち上がる。
紫は○○に話が聞こえないように、橙を廊下の曲がり角まで連れていった。
「橙には黙っていたけど……今日は百年に一度の『尻尾の日』なのよ」
「え、そうだったんですか!?私全然知りませんでした……」
もちろん嘘だ。藍なら頭を抱えて呆れ返るところだろうが、橙は紫の言葉を疑わなかった。
「そうよ。だから遠慮なく藍の尻尾をもふもふしなさい。私の分までお願いね」
「はっ、はい紫さま!わかりました!」
別に普段から遠慮などしていない橙だったが、主の主である紫の言葉に元気よく返事をする。
そのまま勢いよく駆け出そうとするところに、紫はもう一言声をかける。
「そうそう、○○には内緒よ。普段からいっぱいもふもふしてるから」
「はーい、わかりましたー!」
話の内容を聞き取れないまま掃除を続けていた○○は、走っていく橙をぼんやりと眺めていた。
「らーんさまっ」
台所に立っていた藍の尻尾に、橙が抱きつく。
まだ幾分うわの空だった藍だが、それでも振り向くと、優しい笑顔を見せた。
「ん、どうした橙?」
「えへへー」
尻尾に頬ずりする橙。藍は、やれやれといった表情で橙の頭を撫でると、また仕事に戻る。
(やはり○○も、私の尻尾が好きなだけなのだろうか……)
相変わらず悶々とする藍をよそに、橙はさらに深く尻尾に顔を埋める。
結局その日の夜まで、橙は暇さえあれば藍の尻尾にくっついていた。
夜。
床に就いた藍は、眠れずにいた。尻尾に潜り込むようにして寝ている橙が原因ではない。
就寝前に紫がそっと話したことが、藍を悩ませているのだ。
「何考えてるんだ紫様は……」
(貴女の尻尾に対する○○の欲求は、橙によって満たされない状態にしてあるわ)
「いや、そもそもそんな欲求があるのか―いや、やっぱりあるのだろうか……」
(橙はこのまま、貴女の尻尾の中で眠ってしまうでしょうね。もし、○○がやって来て)
(いたいけな橙を追い出すような暴挙に出てまで尻尾を堪能しようとするなら)
(○○は単なる尻尾狂と見なすことができるわ。その場合、○○は明日の私の晩御飯ということで)
「……むちゃくちゃだ」
理屈も何もあったものではない。だが紫の場合、一概に冗談とも言えない。
例え冗談だったとしても、いざその状況が訪れたら気まぐれで実行に移しかねないのが恐ろしい。
「もし、紫様の言うとおりになったら……」
○○には二度と会えなくなってしまうだろう。
藍は寒気を覚えて、寝巻きの襟を掻き合わせた。
(頼む、○○、来るんじゃない―)
藍の耳がぴくりと動いた。
気付かれないようにそっと見ると、願いもむなしく、ふすまを開けて部屋に入ってきたのは○○だった。
「ああ、やっぱり―」
藍が眠っていると思ったのか、○○は畳の上を足音を立てないように近づいてくる。
目覚めていると気付かれないように息を潜めていた藍は、ふいに冷たい空気を感じた。
○○が布団をめくり上げたのだ。
(やめろ○○、これでは紫様の)
「本当にもう、しょうがないな……よっ、と」
(ああ……)
尻尾の中から発掘した橙を抱きかかえ、立ち上がる○○。
そのまま部屋を出て行く。おそらく、橙を布団まで運びに行くのだろう。
そこらに転がしていかないだけましだが、このまま紫の仮定通り○○が尻尾に触れようとした場合、彼は紫のご飯にされてしまう。
(まずい、まずいぞ……だが、このまま戻ってこなければ……)
程なくして、廊下を戻ってくる足音が聞こえる。間違い様もない、○○の足音だ。
部屋に足を踏み入れ、ゆっくりと布団の方へ歩を進めてくる。
(あああああ、○○、来てはだめだ、来ては……)
布団の側にかがみこむ○○。
藍は背中を冷や汗が伝うのを感じた。
(このままではお前は、紫様に)
何も知らない○○は、藍の寝顔を覗き込もうとしている。
追い詰められた藍は、混乱のきわみにあった。
そして。
「○○っ!」
「うわっ!?」
藍は勢いよく飛び起きた。
驚く○○を真正面から抱きしめ、そのまま布団に倒れこむ。
「ら、藍!?いきなり何を」
「静かに!」
腕にぎゅっと力が込もる。
「ちょっと、苦し……」
「すまない。だが今は朝まで、このまま……」
確かにこの状態を保てば、紫の言ったとおりにはならない。
藍は○○が動かないよう、胸に抱きかかえるように彼の頭を押さえ込んだ。
雀の鳴く声がする。どうやら夜も明けたらしい。
「……何とかやりすごしたか」
時折うつらうつらしながらも、藍は○○を離さずにいることができた。
ひとまず、これで安心だろう。
「朝だぞ○○、もう起きても大丈夫だ」
「うーん……」
半ば気を失うようにして眠りについていた○○は、藍に促されて目を覚ました。
「あー……もう朝か。いったい何が……」
「すまなかったな。事情は……そうだな、後で話すよ」
「うん……とりあえず、朝ごはんの支度をしないと。着替えてくるよ」
「そうだな。では私も着替えて、すぐ行くから」
○○の背中を見送ると、藍は枕元にたたんであったいつもの法衣に着替え始めた。
上から割烹着を着ると、台所へ向かう。
「……と、いうわけだ」
味噌汁に入れる大根を刻みながら、藍は経緯をかいつまんで話した。
昨日までなら○○自身に話すことなど思いも寄らなかっただろうが、色々あって吹っ切れたようだ。
「一歩間違えば危うく食べられるところだったわけだ」
七輪の前にしゃがんで魚を焼いていた○○が、他人事のようにつぶやく。
藍はその反応に、少し眉根を寄せた。
「もう少し焦ったらどうだ。元はと言えばお前が……その、私の尻尾ばかり」
「そうかな。そんなに執着してるように見えた?」
「見えた。昨夜だって、橙を運んでから戻ってきた時は、てっきり紫様の言う通りお前が私の尻尾を独占しようとしているのかと」
「あれは、橙が自分の布団にいないようだったんで探してみたら案の定藍のところにいたから。
そのままだと藍が寝苦しいんじゃないかと思って」
「そ、そうか。だがそれでも、最近その……後ろから私を抱きしめることが多い気がする」
「それで、ちゃんと愛されてるのか不安になったんだ?」
「う……」
頬を染めて口ごもる藍を見て、○○は微笑む。
ほんの少しのからかいと、たくさんの愛しさを含んだ笑顔だ。
「確かに尻尾は好きだけれど
―藍のことが好きだからこそだよ」
「うう……」
「いや、藍が後ろからよりも前からの方が好きだって言うならそうするけど」
「ううう……」
真っ赤になった藍は、消え入りそうな声で答える。
「わ、私は、○○のことを愛しているから……ちゃんと愛情を込めてくれるならどちらでも、嬉しい……」
「………………そうストレートに言われると」
聞いていて今更のように照れが出てきたのか、今度は○○が黙る番だった。
「でも……」
包丁を置き、側に寄ってきた藍は身を屈めると、○○を包むように抱いた。
「私から、というのも悪くはないかな……」
お互いの体温が伝わってくるのを感じながら、二人だけの世界に浸る。
「朝ごはんまだー?」
「……はっ」
居間から紫の呼ぶ声が聞こえて、二人は我に返った。橙もそろそろ起きてきただろう。
「……っと。急ごうか、藍」
「そうだな。紫様も橙もお腹を空かせているだろうし」
「ええ、もうぺこぺこよ」
居間にいたはずの紫がいつの間にか台所に来ていた。いつもながら、気配を感じさせない。
「あ、紫さん」
「ゆ、紫様!?」
紫は優しい目で二人を見つめている。
「解決したみたいね、藍」
「……はい」
「抱きしめられて迷うなら自分から抱きしめて、わからない気持ちを確かめるのも大事よ?」
「紫様……ありがとうございます」
全て考えた上で自分を後押ししてくれていたのだ。
そう思うと、藍の心は紫に対する感謝の気持ちでいっぱいだった。
「それにしても残念ね。今日はたんぱく質豊富な晩ごはんになると思ったのに」
「ちょっと紫様!?それは嘘も方便というやつだったのでは」
「さあ、どうかしらねー」
「駄目ですよ、もう解決したんですからね!紫様と言えど私の○○に手は出させませ」
「あの、二人とも朝ごはん……」
「藍さま、おなかすいたー」
本日も、概ね何事もなし。
すっかり馴染みつつある○○を交えて、マヨヒガの日常は流れていく。
うpろだ1283
───────────────────────────────────────────────────────────
雲一つない空に突如として花火が打ち上がった。
昨日まで何もなかった広場には、マイクやスピーカー、観客席等が用意され、大にぎわいを見せている。
……何故こんなことになったのだろう。
○○は溜め息を吐き、会場の入り口の看板を眺める。
願わくば、先程読んだそれが自分の見間違いであるようにと。
……残念ながら、看板に書かれた文字は、先程と同じだった。
『第一回、従者オブ従者選手権決勝』
ことの起こりは三日前の宴会でのこと。
スキマな事情により、紆余曲折の後にマヨヒガで住み込みで働くことになった○○。
雇用期間は死ぬまで。つまり永久就職。
三食及び雇い主からの愛情保証という特典付き。
職業名を『専業主夫』という。
久しぶりにという雇い主、八雲藍の誘いで、博霊神社の宴会に出向いた○○は、酒の飲み方を忘れていたらしい。
注がれるままに飲みに飲んでしまった結果、藍の膝の上に頭を載せ、唸るはめになってしまっていた。
「すまないな、○○。私が調子に乗って飲ませ過ぎたばかりに」
「……いや、俺もはめをはずしすぎた」
「藍さま、お水持ってきました」
藍の式神である橙がコップを片手に、とてとてと二人によって来る。
「ああ、ありがとう」
自らの腕にもたれ掛かる○○の口に水を運ぶ藍。
その甲斐甲斐しさは正に妻のそれ。
……いや、母のそれだろうか。
「……それにしても」
橙は○○をじっと見ながら言う。
「……なんで藍さまは○○なんかと」
「おや、橙は○○が私の夫では不服なのか?」
「当たり前です! ○○ってば段幕は撃てないし、力は弱いし、今だってこんなに情けない格好で……」
あれこれ不満をまくしたてる橙だが、その実○○を気に入ってることを藍は知っている。
単に○○が藍を独占していることが面白くないだけなのだ。
「いや、申し訳ない」
「申し訳ないじゃないよ○○! もっとしっかりしてよね!」
「「まったくね(です)」」
そんな○○と橙の微笑ましいやりとりに、口を挟む者がいた。
紅い悪魔の従者十六夜咲夜と、亡霊嬢の従者魂魄妖夢だ。
「私達に何か用事かな?」
不粋な闖入者に顔をしかめながら、藍が尋ねる。
「貴女の従者は随分となってないのね」
ピクリと、藍の形の良い眉が上がる。
「自らの限界も弁えず、主人を省みないで酒を飲み」
「あまつさえ、主人に迷惑をかけるなど、言語道断。同じ立場の者として恥ずかしい限りです」
ぶわりと、美しい九つの尻尾が大きく膨れた。
……明らかに怒っている。
「要するに、このダメ従者に一言言ってやりたくてね」
「お前ら……!」
ぶっとばしてやろうかしらと、懐のスペルカードに手を伸ばし……
「主夫を、……なめんなーーーーーっ!」
唐突に○○が立ち上がった。
「あら起きたの、ダメ従者」
「従者じゃない! 主夫だ!」
「ならダメ主夫ですね」
「言ってくれる。こちとら家事のプロフェッショナルだ! 家事の技量ならあんたらよりも上だ!」
この発言に今度は従者二人がこめかみをひくつかせる。
「西行寺の庭番をつかまえて、自分の方が上と? 言いますね」
「紅魔館のメイド長よりも家事ができる? ……面白い冗談ね」
一触即発。
三者三様のプライドを火花に変えてぶつけ合う、自分こそ最高と信じて疑わない三人。
いつのまに三つ巴になったのやら……
「……こうなれば」
いいながらスペルカードを取り出す妖夢。
「あら、分かりやすくていいわね」
同じように咲夜もスペルカードを手にとった。
「……」
一方いまだ丸腰のままの○○。
ただの人間である彼にはスペルカードなど使えるわけもなく……
「どうしたんです? まさか素手で闘うつもりですか?」
「へえ…… 甘く見られたものね。やって見せてもらおうかしら」
矛先を一辺に向けられた○○、早くもピンチである。
それでも主人、……いや、嫁である藍が見ているのだ。
情けない真似はできない。
「ちょっと待て、悪魔の狗に半霊。わたしの目の前で○○を痛め付けようなんて、良い度胸じゃないか」
そこに助け船を出す藍。橙を引き連れ、すでに臨戦体制である。
「……式の猫といい、ずいぶんと部下を甘やかすのね」
「訂正しなさい。○○はわたしの夫であって、部下じゃない。
それに、彼が傷付くところは見たくない」
「主が従者を守るだなんて、おかしな話ではないですか?」
「○○を従者と呼ぶな」
「同じよ。立場としては」
「……少し痛い目に逢いたいのかしら、悪魔の狗」
くっと目を細めた藍に内心動揺しつつも簡単には引き下がれない二人。
「ら、藍、もういいから……」
「いいや、良くない。わたしはともかく、○○と橙を馬鹿にする奴は誰であろうと許さない」
止めなくてはと、○○は藍に駆け寄るが、効果無し。
しばしの睨み合いの後。
「その辺にしなさい、妖夢」
「幽々子様!?」
「咲夜、あなたもやりすぎよ」
「お嬢様……」
膠着状態を破ったのは、紅魔館と白玉楼、それぞれの主であるレミリアと幽々子。
「ごめんなさいね、紫の式。この子もまだ半人前なのに生意気に」
「……申し訳ありませんでした」
「私からも謝るわ。まさか咲夜の失態をフォローする事になるなんてね」
「……お恥ずかしい限りです」
主にたしなめられうつむく従者二人
「だけど、このまま終わりにするにはもったいないわね、この展開」
「奇遇ね、わたしもそう思ってたところよ。
……というわけで」
レミリアと幽々子が笑いかける先には、心得たとばかりににやつく紫と文。
……そして話は冒頭に戻る。
「さあ始まりました。第一回従者オブ従者選手権決勝戦。司会はわたくし、射命丸文です。どうぞよろしくお願いします」
「解説の八雲紫です。よろしく」
あの時の一コマからわずか三日でこれである。
……最早突っ込むのもばからしい。
「あや~、それにしても、ずいぶんとお客さんが集まりましたね」
「貴女の記事の仕業ではなくて? 新聞記者さん」
「そうであれば喜ばしい限りですが、どちらかといえばあなたの仕業だと思いますが。
ああ、催しの宣伝の際には文々。新聞を是非ご贔屓に」
フィフティーフィフティーでこの二人の仕業だ。間違いない。
本当にわずか三日でよく集まったものだ。
普段宴会で見る連中はいいとして、里の人間まで混じっているのはどういうことだろう。
人知れず頭を抱える○○。
「さて、関係ない話はそのくらいにして、そろそろ始めましょうか」
「そうですね。ではこれより第一回従者オブ従者選手権決勝戦を開催いたします」
文の開会宣言とともに、満員の観客席が沸く。
幻想郷には暇人が多いらしい。
「……すまないな、○○。紫様が迷惑をかけた」
すまなそうに謝る藍。
「なに、俺が君のことをどれだけ想っているか、アピールするいいチャンスだよ」
多少の去勢はあるが、藍を想うこの気持ちは、誰にも負けない自負がある。
他のことはともかく、あの二人に想いで負けるわけにはいかない。
「……ばっ、馬鹿!」
頬を染め、照れ隠しに目を逸らす藍。
なんというナイスリアクション。これだから、八雲の専業主夫はやめられない。
「それではまず、ルール説明をしたいと思います。これから幾つかの質問に答えていただき、それを審査員が10点満点で評価します。総合得点の高い者が優勝となります」
「平時からの心構えがカギというところかしらね」
「単純な力だけが優秀な従者の条件ではありません」
「ええ、マヨイガの主夫が、それを証明してるわ。ただの人間があんな中決勝まであがってくるなんて、正直驚いたもの」
しかしこの進行役、ノリノリである。
早くも板についているあたり、流石というかなんというか……
というより、今更だが予選なんか何時やった?
「続きまして審査員の紹介をさせて頂きます。
まずは一人目、幻想郷の歴史を語り続ける求聞持の賢人、稗田阿求さんです」
花の髪飾りをつけた小柄な少女がぺこりと頭を下げる。
……だからどんだけ暇なんだよ、幻想郷。
「縁起に載るだけの妖怪たちの主従関係。非常に興味深いです」
……仕事の一環ですか?
それともただの職業病ですか?
「阿求さん、ずばり今回の注目点は?」
「もちろん、○○さんです。あの八雲藍の夫がただの人間であることには、わたしも驚きましたから」
「主であるわたしも驚いたわ」
「今日は○○さんのことを調べあげて、縁起に追加掲載するつもりです」
これはいよいよ情けない真似は出来ない……
「○○、そんなに硬くなるな。結果が振るわなくとも、お前の想いをしっかり伝えてもらえれば、わたしは満足だから」
「藍……」
「それでは、今日はどうぞよろしくお願い致します」
「はい。……わくわく」
目の前の鴉天狗のお株を奪わんばかりに、わくわくしている阿求。
……職業病だな、ありゃ。
「続きまして、永遠亭の月の兎、鈴仙・優曇華院・イナバさんです」
「よろしくお願いします」
「同じ立場の目線といったところかしら」
「惜しくも予選で小野塚小町さんに敗れてしまいましたが、今回、誰が優勝すると思われますか?」
「誰が優勝してもおかしくはないとおもうわ。まぐれでここまで勝ち上がってきたわけではなさそうだし」
「成る程。目が離せない戦いとなりそうですね」
「そうね」
「それでは、審査員よろしくお願いします」
……あれ? ひょっとして、「決勝」に突っ込んでるの俺だけ?
「さて、最後の審査員は、……って何でこの方? 水橋パルスィさん」
「……平気でわたしをぞんざいに扱える貴女が妬ましいわ」
「ストレートな審査なら、彼女が一番でしょう。だから呼んだのよ」
「……妬ましい、妬ましいわ。こんな争いを起こすほどに慕われてる主も、慕う相手のいる従者も」
「成程、分かりやすいですね」
確かに分かりやすいかもしれないが ……非常に怖い。
「さて、審査員も出揃いましたところで、いよいよ選手入場といきましょう」
待ってましたとばかりに観客が歓声をあげる。
どいつもこいつも本当にノリがいいな。
それともこれが普通なのか?
……どこぞの巫女の、頭のネジを外しただけある。
「まずは、紅魔館のメイド長、十六夜咲夜!」
名前を呼ばれると同時に、お得意の時間操作能力で音もなく現れる咲夜。
「予選から他を寄せ付けない圧倒的な強さで決勝進出。瀟洒な従者ここにあり!
主への絶対の忠誠とその能力で今回の優勝候補です!」
「紅魔の名に敗北の文字などありません。従者のなんたるかを皆さんにお教え致しましょう」
穏やかな表情で頭を下げる。
うん、瀟洒だ。
「続いて白玉楼の庭師、魂魄妖夢!」
目にも止まらぬ早さで、台上にあがる妖夢、一陣の風と共に参上だ。
「小柄な体つきならではのフットワークは抜群。主のために日々成長中! まだまだ未知数のその力に期待です!」
「剣を持つものとして、従者の名において、負けるわけにはいきません。全力でお相手させていただきます」
真っ直ぐに咲夜を睨み付け、宣戦布告をする妖夢。
対する咲夜は余裕ともとれる笑みで受け流す。
「あらあら、早くもボルテージが上がってきたわね」
「最初からクライマックスてやつでしょうか?
……さて、そして最後に八雲の専業主夫、○○!」
「それじゃ、行って来る」
「ああ、行ってこい。……ふふ、いつもと逆だな。頑張れ」
「ああ」
ゆっくりと台上へと向かう○○。
その姿は二人とはまた違った風格を、……醸し出せてはいない。
「持ち前のガッツと、主人八雲藍への強い想いで、ここまで勝ち進んだ、ある意味で幻想郷最強の人間。
今日、ついにその全貌が明らかになります!」
会場の視線が自分に集まるにつれて、開き直りに近い度胸が湧いてくる。
「俺は従者でなく主夫だ。この二人に戦闘では勝てない。
だけど、藍を愛する気持ちは、従者の主を想うそれに劣らない。
愛する人のために、力の限りに戦い抜くつもりだ」
先ほどまで頭を抱えていた姿はどこへやら。
なんだかんだでノリやすい○○も、立派に幻想郷の住人なんだろう。
「なんというか、甘いですね」
「文字通り、甘く見ると痛い目に遭うわよ」
「すいーつってやつですか?」
「甘い砂糖と、スパイスと、その他素敵な、なにもかもってね。まさかこのわたしが二人の前で膝を付くなんて思わなかったわ」
「八雲紫が、ですか!?」
「ええ、普段はすましてるけど、二人きりな時には近付かない方が良いわ。
一歩近付きゃ、砂糖にまみれ
二歩近付きゃ、味覚を忘れ
三歩近付きゃ、貴様も桃色の空間に溺れるがいい……」
「あ、あの、紫さん、その位で勘弁して下さい」
恥ずかしい紫の解説を止めにはいる○○。
「あら、これからだったのに、残念。
ともかく、これで役者は揃ったわね」
「はい。それでは改めまして、これより第一回従者にオブ従者選手権決勝を始めたいと思います」
割れんばかりの大歓声が、会場に響き渡った。
新ろだ115
───────────────────────────────────────────────────────────
目の前で花弁のように広がる九房の柔毛。金色の光沢を持つその一房を手にとり、俺は丁寧にピンブラシを掛けていく。
毛を傷つけないように、生きている毛を抜いてしまわないように、ゆっくりゆっくりと時間を掛けて作業をする。そうして被毛のもつれを解き、ホコリを除去して、次の作業に移る。
ピンブラシでのブラッシングが終わったら、豚の毛を用いた柔らかいブラシを使って抜け落ちた毛を絡め取っていく。
一房だけでも結構なボリュームがあるためにそこそこの時間がかかるものを、あと九回も繰り返さなければならないのだ。
だが、それもまた楽しいものである。
俺がじっくりと時間を掛けて房の一つ一つに取りかかっていると、この房の持ち主から声がかかった。
「いつもすまないな。自分ではよく見えないし、手も届かないからあまり手入れが出来なくて……」
「いや、気にしないでくださいよ。藍さま」
俺が手入れをしているのは八雲藍、つまり九尾の狐と呼ばれる最強の妖獣の尻尾なのである。
最強の妖獣とはいえ、無礼を働かなければ穏和で折り目正しいお姉さんだ。恐れることはない。
何より、俺はこの美しい九尾と彼女の人柄に魅せられていた。
「俺も藍さまの尻尾を手入れするの、好きですし」
「そう言ってくれるとありがたい。この九尾は私の自慢なんだが……」
九尾の狐なんだから、そりゃ尻尾は自慢だろう。それ以前に、ツヤ、手触り、ボリュームのどれをとっても最高の尻尾だ。自慢になるのももっともだと言えよう。
「手入れをしようと思っても自分では出来ないし、軽々しく他人に触らせたくもない。かといって、紫様にやらせるわけにもいかないし、橙は少し頼りない。君がいてくれて本当に助かっているよ」
「俺なんかに藍さまの大事な尻尾を預けてもらえて、逆に光栄ってなもんです」
「そ、そう。そうなんだ。君だから、この尻尾を預ける気になるというわけで……」
ん? ちょっとモジモジしないでください、藍さま。ブラシが掛けにくいですから。
無意識にやっているのか、そんな俺の思いとは逆に、藍さまは尻尾をワサワサと揺すっている。
まさか尻尾を鷲掴みにするわけにもいかないので、優しく尻尾の先だけを掴んでブラッシングを続けた。
「それに、九本もあるから手間も時間もかかるだろう? それを手入れして欲しいなんてワガママを聞いてくれて、感謝している」
感謝するのはこっちですよ。藍さまの尻尾を手入れさせてもらえるんですから。
名残惜しいと感じつつも、俺は最後の尻尾にブラシをかけ終えた。終了の合図に藍さまの肩を軽く叩く。
こっちを振り向いた藍さまに向かい、俺は言った。
「構いませんって。それに藍さまはもっとワガママ言わないと、ストレスでパンクしちゃいますよ? 俺でよければ聞きますから」
すると藍さまは一瞬驚いて、次に嬉しそうな、最後に照れ臭そうな顔をした。
「……参ったな。ワガママを言えなんて言われたのは初めてだ、嬉しいよ。だが、これ以上君に私のワガママを押し付けるのも心苦しい。
そこで」
コホンと一つ咳払いを入れる藍さま。どことなく顔が赤いのは気のせいだろうか?
「私も君のワガママを聞いてあげようと思う。それならお互い様だろ?」
「いやいや、それには及びませんって。藍さまの胃袋に穴を開けるわけにはいかないですから」
さっきは咳払い。今度は溜息をつく藍さま。
「……まったく、鈍いな君は。私は君と、ワガママを言い合えるような関係になりたいと、そう言っているんだ」
一方的ではなく、互いにワガママを言い合える関係。主従でも家族でもなく、友人ともわずかに違ったその関係。
ああ、そうか。気づいていなかったんじゃなくて俺が真っ先に切り捨てた、諦めていたその関係。それを指しているのか。
「じゃあ、言います。……これからも、俺だけに藍さまの尻尾の手入れをさせてください。他の誰にも渡したくありません」
「やれやれ、それじゃ今までとほとんど同じじゃないか。でも約束させてもらうよ、君以外には決して触れさせないと。
……それで、私からも新しいワガママを二つほど言わせて欲しい」
俺はコクリと頷いてみせる。柔らかく微笑んで、藍さまは言った。
「私に敬語を使うのはやめてくれ。それから私のことはこう呼んでくれ……藍、と」
「分かったよ、藍」
戸外からパラパラと音がする。窓の外を見れば、雲もないのに雨が降っていた。
藍の体を抱きしめつつ、俺は天の神の粋な計らいに感謝した。
新ろだ188
───────────────────────────────────────────────────────────
斜陽の差し込む土間に二つの椅子を並べ、俺と藍はそこに腰掛けていた。
二人で仲良く横並びに座るのではなく、俺が藍の背後にくっつくような形で座っている。
藍の背中の最下部、腰骨の辺りから垂れ下がる金毛の九尾を自分の膝に乗せ、その一房をそっと掴む。
そして、俺は自分の得物を取り出した。
「藍、始めるよ」
「ああ、よろしく頼む」
ピンブラシ、獣毛ブラシ、金属製の櫛。その三つを使い、丁寧に被毛のもつれを解き、ホコリを除去し、廃毛を絡め取って、仕上げに毛を整える。
それを九回にわたって繰り返すのは手間も時間もかかる作業だったが、まったく苦にはならなかった。
これは義務でも仕事でもなく、俺に与えられた特権なのだから。
丹精して藍の九尾を手入れしていくと、わずかな違和感を覚えた。
少しばかり尻尾の手触りがパサついた感じがするし、日本刀の刃文を思わせる光沢もくすんでいる。
この九尾は藍の自慢なだけに、常に美しく保っておきたい。俺はいつも以上に時間を掛けて手入れをしていった。
「藍、終わったよ」
最後の尻尾を櫛で整え、俺は藍に声を掛けた。藍からの返事はなく、振り返りもしない。
「……藍?」
不思議に思って前に回ると、藍はコックリコックリと船を漕いでいた。どうも居眠りをしているらしい。
無防備な寝顔は可愛らしいが、椅子の上で船を漕いでいるというのは大変に危ない。
起こしてやろうかとも考えたが、この寝顔をもう少し見ていたい。俺は藍を横になれる場所に運んでやろうと手を伸ばす。
しかし俺の手が触れるその寸前、藍の肩がピクリと動いた。残念に思いつつ、俺は手を引っ込めた。
「……おっと、いつの間にか眠ってしまったのか」
目を覚ました藍はゆっくりと頭をもたげ、俺の顔を見て自嘲気味に微笑んだ。
「だらしない顔を見せてしまったな、忘れてくれるか」
「あんなに可愛い寝顔、忘れられないよ」
「……っ! と、年上をからかうんじゃない、まったく……」
口ではそう言っているが、藍もまんざらではなさそうだった。照れ気味の表情と尻尾の動きがそれを物語っている。
と言うか、あんまり尻尾を振るとホコリが付いてしまうんだが……ただでさえ静電気の溜まりそうな尻尾なんだから。
まあ、それは後で何とかするとして、俺には気になっていることがあった。
「それにしても、藍が居眠りするなんて珍しいな」
「……ん、ああ。あんまり気持ちがよかったからつい、眠くなってしまったよ」
嬉しいことを言ってくれるじゃないか。でも、それだけじゃないだろう。俺は指摘する。
「藍、疲れてるんじゃないのか?」
「……バレていたのか」
「尻尾を見れば判るさ。毛づやも手触りも、いつもより少し落ちてたからね。疲労やストレスが溜まってる証拠だ」
「ふふ、君は私の専門家だな」
藍はわずかに嬉しそうな表情をしたが、その顔にははっきりと疲れが見て取れる。
やつれていると言うほどではないが、どことなく精彩を欠いていた。
「そろそろ紫様が長期睡眠に入る時期だから、いろいろとまとめて仰せつかっていてね……。
この仕事が済めば、しばらくは私も暇が持てるんだが」
ふう、と大きく息を吐く藍。やはりずいぶんと疲れが溜まっているようだ。
どうにか藍の力になってやりたいが、九尾の狐でも一苦労の仕事を前に、ただの一般人である俺にどれだけのことが出来るのか。
俺にも妖怪並みの能力があれば……と考えたその時、俺の脳裏に稲光のごとく妙案が閃いた。
「藍。俺を藍の式にしてくれないか?」
「!? ……どういう風の吹き回しだ? 私の式になりたいだなんて……」
藍は驚いて目を丸くしている。まあ、それはそうだろう。普通、妖怪の式になりたいと言う人間はいないからな。
俺は答えた。
「藍の式になれば、条件次第じゃ藍と同じ能力を発揮できるらしいじゃないか。
そうすれば藍の力になれるだろ? そうでなくても、ただの人間よりはマシだと思うよ」
ぐっ、と藍は声を詰まらせる。感激でもしてくれたのか、嬉しそうに笑いながらも目の端には光るものが見えた。
光る雫を指先で拭い、藍はかぶりを振った。
「君の気持ちは嬉しい。……本当に、だ。でも、君と私はそんな『使う』『使われる』の関係じゃないだろ?
私たちは、その、こ、こい……」
「……恋人。対等な、互いにワガママを言い合える関係、か」
顔を真っ赤に染めて、藍は水飲み鳥の玩具みたいに首を上下に振った。杞憂だと分かっているが、頭がスッ飛んでいかないかと心配になる。
藍の言うとおりかもしれない、と俺は考えた。
俺は俺の意思で藍の支えになりたい。命令に従う式神というのは、やはり違う気がする。
「そうだな、俺も藍と対等でありたい。やっぱり、俺は俺に出来るやり方で藍を支えるよ」
「はは、そんなに気を張らなくてもいい。今までの君で充分さ」
「藍の式神になるのも悪くないと思ったんだけどな」
俺がそう言うと藍はちょっと考えて、何だか恥ずかしそうにしながら口を開いた。
「じゃあ……少しだけ、真似事でもしてみるか?」
「真似事? ああ、何でも命令してくれ」
よく分からないが、藍は何か俺にして欲しいことがあるのだろう。もちろん、俺はその話に乗ることにした。
俺が了承すると、藍はうつむき加減で何かを呟いた。
「……を……てくれないか」
「ああ、そんなこと」
「そ、そんなことって言うな! 今の一言を言うのに私がどれだけ恥ずかしい思いをしたと……」
「まあまあ」
喚いている藍をなだめつつ、俺は座敷のへりにどっかりと座り込んだ。大きく足を開き、太股をポンポンと叩く。
藍は唇を尖らせつつもこっちに寄ってきて、俺に背中を向けて膝の内側にドスンと座り込んだ。
俺は藍の帽子を脱がせ、頭の上に手を置いた。
そして。
なでなで。
「……あ」
なでなで。
「……」
「どうだ?」
なでなで。
「何というか、幸せな感じがする……」
「頭を撫でて欲しいなんて、藍は可愛いなあ」
「……橙にはよくしてやるが、自分がしてもらうのは初めてだ。すごく、安心するな……」
恍惚としながら、藍は俺の胸に背中を預けてくる。
喜んでもらえたようで何よりだ。けど、他にも藍が望むことがあるならしてやりたい。
耳の裏側の付け根を重点的に撫でながら、俺は聞いてみた。
「他には?」
「……その。ぎゅっ、ってしてくれ……」
「了解」
藍の両脇から腕を前に回して、ぎゅー。
しばらくしても藍は何も言わない。さらに、ぎゅー。
やっぱり藍は無言のまま。もっともっと、ぎゅー。
いつまで抱いていればいいのだろうか。まあ、いつまででも構わないけど。
いつも頑張っている藍にたまのご褒美だ……というか、俺にとってもご褒美だが。
などと考えていると、ようやく藍は口を開いた。
「……はあ。幸せなものだな、誰かに支えてもらうというのは。
九尾となってから、紫様の式となってから、こんな風にしてもらうのは初めてだ。
力を得て、誰かに甘えることなど忘れてしまったような気がする」
「藍は可愛くて器用で可愛くて強くて可愛くて賢いからね。どうしても頼られる側になるんだろうな。
でも、藍はもう少し他人を頼ったり甘えたりしてもいいんじゃないかな?」
俺の胸に頭を当てて、藍は俺の顔を見上げてきた。普段とは違った視線に心臓が一拍、強く弾んだ。
「それならもうやっているさ。この通り、な」
大した人間でもない俺を支えにしてくれるのはすごく嬉しい。でも、そうじゃないんだよ、藍。
俺は小さく首を横に振った。
「違うよ。もっと身近な人たちを信じてみたらどうかな、ってことさ。
紫さまもきっと、藍が甘えたら優しくしてくれる。橙だってきっと、藍が頼れば期待に応えてくれる。
二人と会ったことはないけど、俺は藍を信じてる。藍の好きな人たちは藍を裏切らないって信じてる」
何をえらそうに言ってるんだか、と自分でも思う。
だけど、どんな理由にせよ、俺はいつか藍の前から姿を消す。その時、藍には他に頼れる人がいることを知っておいて欲しい。
例え俺には分からなくても、俺がいなくても藍は笑って暮らしていると信じていたい。
俺を見上げたまま、藍は目を細めて笑った。気負いのない、いい表情だ。俺の守りたい、藍の笑顔。
顔の向きを前へと戻し、藍は言った。
「……そうだな。君の信じてくれる、私の中の二人を信じてみよう。
甘えてみたら、紫様は私のワガママを聞いてくれるかな?」
「きっと。藍の御主人様なら、藍を大事にしてくれるはずさ」
「なら、一つお願いでもしてみようか」
藍のお願いとは何だろう。お暇をください、とかじゃないよな。何かが欲しいのか、何かをして欲しいのか。
紫さまにお願いするくらいだから、きっと俺には出来ないことなんだろう。
顔も知らない紫さま、どうか藍のお願いを聞いて上げてください。
俺が心の中で祈っていると、そのまま藍は言葉を続けた。
「マヨヒガに一人、新しい家族を増やしたいのですが……と」
「へっ?」
思いがけない発言に、思わず素っ頓狂な声をあげてしまう。
まさか、どこかから動物を拾ってきて飼いたいという意味じゃないだろう。と言うことは、ひょっとして……?
藍を見れば、広々とした袖で恥ずかしそうに顔を覆っていた。
「き、君も心の準備をしておいてくれっ!」
藍は帽子をかぶりながら勢いよく立ち上がると、呆然とする俺の鼻を抓んで家を飛び出していった。
マヨヒガに新しい家族? 俺に心の準備? それって、やっぱり……。
「……一緒に暮らそう、ってことか?」
独りごちて、やっと認識する。
勝手に頬が緩むのが分かるが、自分の意思では止められない。きっと、今の俺は妖怪ですら目を逸らすほど薄気味悪いだろう。
まったく締まりのなくなった顔で柏手を打ち、俺はさっきと同じように祈った。
「紫さまっ! どうか藍のお願いを聞いて上げてくださいっ!」
ふと首筋に感じる、冷たい空気の流れ。戸も窓もしっかり閉まっているはずなのに……スキマ風?
俺が不思議に思っていると。
「だったらまず、その薄気味悪い顔をどうにかなさいな。正視に堪えないわよ」
「!?」
耳元に届くあでやかな女性の声。頭の中に響いたとかではない。確実に俺の鼓膜を震わせていた。
しかし、声の主らしき姿はどこにも見当たらない。
「……幻聴、か? それとも、妖精の悪戯……?」
さっきの声が親切に答えてくれるということはなかった。
ただ、なんとなく、藍と一緒に暮らせるのはもう少し後になりそうな予感がひしひしとしていた。
新ろだ195
───────────────────────────────────────────────────────────
年の瀬も押し詰まり、今年も残すところあと一週間となった。つまり、今夜は聖誕祭前夜である。
今日はそのお祝いも兼ねて……というより、それを口実にして俺はマヨヒガの面々と顔合わせをすることになっていた。
恋人である八雲藍と、その主の紫さまに、藍の式である橙。どんな人たちなんだろうか、期待と緊張で胸は高鳴りっぱなしだ。
プレゼントも用意したし、後は藍が迎えに来てくれるのを待つだけだった。
「ん……?」
何げなく天井を見上げると、奇妙な物体が浮いていた。陽光を思わせる山吹色をした、毛の塊が九本。
どこかで見たことがあるような……というか、藍の尻尾にそっくりなんだが。
目の前の異様な光景に首をひねっていると、唐突に空間が裂けた。
何を言っているのか分からないと思うが、そうとしか表現できない。カーテンを左右に開くように、空間の一部が開いたのだ。
開いた空間からコロリと飛び出てくる尻尾……と、その持ち主。
藍だ!
思わず飛び出した俺の手の中に、藍が転がり落ちてくる。急に腕にかかった重みによろけてしまうが、俺は何とか転ばないように踏ん張った。
「ふう、危なかった……」
「あ、ありがとう。おかげで助かったよ」
俺は藍をそっと床に下ろし、疑問をぶつけた。
「いったい何がどうなってるんだ? いきなり目玉だらけの空間が開いたと思ったら、藍が転がり落ちてきて……」
「それは後で説明するが、先に言っておかなければならないことがあるんだ」
衝撃的な登場の仕方をした藍は、真剣そのものの面持ちで、さらに衝撃的な発言をした。
「クリスマスは中止になった」
!?
あまりにも突飛な発言に俺は固まってしまった。
「……何ですと?」
「すまない、言い間違いだ。正確には『クリスマスパーティーは中止になった』だ」
何だ、言い間違いか。てっきり原油高の影響でサンタの都合が悪くて中止になったのかと……。
「え、中止!? マヨヒガでやる予定だったのが?」
「ああ。楽しみにしていてくれた君には申し訳ないんだが……」
「何で? 紫さまの都合が悪いとか……」
俺が尋ねると、藍は何とも決まりが悪そうな表情をした。
「ええと、その……。今日、君の紹介を兼ねて祝宴を催したい旨を紫様に伝えたところ……
『クリスマスって言ったら二人きりで過ごすでしょ常識的に考えて……』
と、ものすごく微妙な顔で言われてしまった。
それで、今日明日は帰ってこなくていいからと、スキマに放り込まれてしまって……」
「スキマ?」
妙な文脈の単語があったので、尋ねてみる。
すると、藍は端的に紫さまが操る空間の裂け目だと説明してくれた。とんでもない能力だ。
しかし、ピンポイントで俺の家に放り込んできたってことは……。
「もしかして、俺たちのこと知ってるんじゃ?」
「どうもそうらしい。どこかで覗いて……監視……見守ってくれていたんだろう」
何というプライバシー侵害。
これも藍の気苦労の一つなのだろうか。藍は目を瞑り、全身が萎みそうなほど大きな溜息をつく。
気を取り直して、藍は言った。
「ともかく、今日明日と私は帰るところがなくなってしまったわけだが……」
片目を開け、チラリと俺を見る。素知らぬ顔をする藍だが、鼻の頭が少し赤かった。
「だったらウチにいればいいさ。大して広くはないけど、客用の布団くらいはおいてあるし」
「そ、そうか。じゃあ、世話になるよ」
「ああ、遠慮なくどうぞ」
当初の予定とは違ったけど、まさか藍と二人だけのクリスマスとは。嬉しい、嬉しすぎるぞ。
「しかし、サンタは煙突から入ってくるものだとばかり思ってたけど、まさかスキマからプレゼントを投げ込んでくれるとは」
「あの方なりに気を遣って下さったのだろうか……?」
「藍が頑張ってくれてるから、ご褒美をくれたんだよ」
「……そうかもしれないな」
一応頷いてはいるけど、顔が全然納得してないぞ、藍。『遊ばれている気が……』とか言ってるし。
何でそんなに信用ならない妖怪(ひと)に仕えているのか、俺は不思議でしょうがなかった。
何はともあれ、これからのことを考えよう。
「二人で過ごせるのはいいけど、予定が変わっちゃったな。準備をやり直さないと」
「マヨヒガで過ごすものとして準備を整えてきたからな。とりあえず、買い出しに出ようか」
「そうだな」
そういうことで、俺たちは街に買い出しに出ることにした。
二人並んで街を歩きながら、藍は幾度となく俺の方に視線を送ってきた。ふと気づく、所在なげな藍の左手。
周りを見れば、俺たちと同じような仲睦まじい男女が何組も見える。その中で俺だけが……。
なんて馬鹿野郎なんだ、俺は。
藍の喜ぶことだけを考えてきたつもりなのに、こんな簡単なことに気が付かないなんて。
自分の間抜けさを呪いつつ、俺は藍の左腕に自分の右腕を絡め、指を併せるようにして手を握った。
「ごめん。ずいぶん冷たくなっちゃったな」
「鈍感は罪だぞ? まあ、自分で気づいたから今回は許してあげよう」
「もっと経験を積まないとな」
「ふふ、なら私が協力してあげようか」
藍が機嫌を直してくれてよかった。俺ももっと男を磨かないとな。こんなざまじゃ紫さまに申し訳が立たない。
気合いを入れ直して、俺は藍と一緒に街を巡った。
七面鳥を焼こうか、たまにはワインもいいんじゃないか、ケーキはどうしよう、稲荷寿司は他と浮いてるんじゃないか、などと話しながら二人で買い物を進めていく。
もちろん、その間もずっと手は繋いだままだ。
そうしているうちに、空からちらほらと舞い降りる冬の妖精。雪だ。
ひとひらの雪を藍が手に取ると、それは幻想であったかのように儚く消える。
しばし雪を眺めて藍は言った。
「雪か……。今夜は寒い夜になりそうだな」
「いや、暖かい夜になると思うよ」
俺の言葉に藍は小首をかしげた。俺も学んでるんだよ、藍。
「今夜は二人だから。さっきみたいに、藍に冷たい思いはさせない」
「……そうだな。身を寄せ合わないといられないくらい、寒くなるといいな……」
そう言って、俺たちは肩を寄せ合った。
風景に交じる雪の量が次第に増えてくる。今夜はとても冷えるだろうが、寒ささえも俺たちにはクリスマスプレゼントだ。
雪よ、降り積もれ。
その分、俺たちの想いも積もってゆくから。
新ろだ217
───────────────────────────────────────────────────────────
俺と藍が並んで街を歩いていると、人だかりがあった。その人だかりの最前列には羽織袴と白無垢の男女。
結婚式か。藍の花嫁姿は、それはそれは画になるんだろうなと、思わず空想する。
「花嫁衣装か……。いつかは私も着てみたいものだな」
花嫁をじっと見つめて、藍は呟いた。
俺が着せてあげるよと言おうとすると、藍は言葉を続けた。
「きっと、花嫁衣装を着る私の隣に立つのは君ではないんだろうな」
「えっ……」
「君よりも力があって、知恵も回って、地位も財も兼ね備えた男がいいな。ひょっとすると、相手も九尾の狐かもしれない。
そして、誰もが私たちの結婚を祝福してくれるんだ」
そう言って、藍は軽く笑った。
当然の発想だった。俺みたいなただの人間よりも、その方が藍を幸せにしてくれるだろう。
分かってはいるが、目の奥から熱いものが込み上げてくる。
それが目からこぼれる前に、藍はさらに言葉を紡ぐ。
「けれど、そこに君が唐突に現れて、私に手を差し出すんだ。
私は力も地位も財もない、私に優しくしてくれるだけのただの人間を選んで、式場を飛び出していく。
そしてどこまでも、二人だけの場所を目指して駆けていくんだ」
ふわりと微笑んで、藍は言った。
「どうだ、素敵だろう?」
やはり、目から熱いものが溢れそうになる。けど、その理由は先ほどとは正反対だった。
ぐっと堪えて、言葉を搾り出す。
「ああ、最高に素敵だ。藍に手を差し出したとき、藍に選んでもらえるように頑張るよ」
「ふふ、期待しているからな」
そっと伸ばされた藍の手を、俺はしっかりと握りしめた。
* * *
「……ところで」
「ん?」
「もしも紫様が私たちの結婚に反対したとして、その時君は私を攫って逃げてくれるか?」
即座に俺は首を横に振った。そして、答える。
「ダメだよ。紫さまは藍の家族だろ? だったら、祝福してもらわなきゃ本当の結婚とは言えないと俺は思うよ。
紫さまから藍を攫ってはあげられないけど、その代わり、絶対に紫様に認めてもらってみせる。
……これで、どうかな?」
俺の出した答えに、藍は春の日差しのように柔らかな笑みで返してくれた。
新ろだ312
───────────────────────────────────────────────────────────