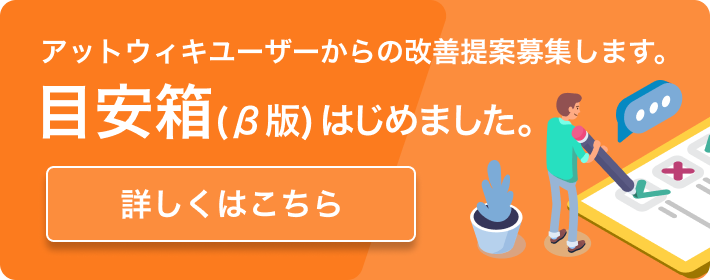「おー湯気が凄いな」
○○は博麗神社近くに湧いた温泉に入りに来ていた。
お湯と気温の差が激しいためか一面真っ白だ。
○○は体と頭を洗いゆっくりと足を湯船に沈めた。
「くあ……ちょっと熱いかな」
頭に手ぬぐいを乗せてリラックスする○○。
そこに一陣の風が吹いて月明かりに照らされた裸の勇儀の姿が現れた。
「うわぁっ!?」
「きゃっ!?」
お互い叫び声をあげて○○は顔を背け、勇儀は湯に体を沈めた。
しばらく気まずい沈黙が続いたあと、おずおずと勇儀が話しかけてきた。
「あ、あのさ……悪いんだけれど、そこにあるタオル取ってくれないか?」
「あ、ああ、これね……」
彼女の方を向かないように縁にあったタオルを取ると勇儀に差し出した。
ちゃぷちゃぷと水音がしてもうこっち向いてもいいと言われたので○○は視線を向けると勇儀は体にタオルを巻いてあった。
勇儀は○○に近づくと隣に座り肩を並べた。
そして同じく縁に置いてあった杯を手に取るとくいっと中の酒を煽った。
「……飲むか?」
「じゃあ、一口だけ」
手渡された杯を受け取りほんの一口だけ口に含む。
「……辛いな」
「そうか?」
戻された杯を手にまた勢いよく酒を飲む。
また沈黙が続くが先ほどとは違い嫌ではない。
勇儀が不意に○○の腹に手を這わす。
「ずいぶん引き締まったな」
そう言ってゆっくりと臍の辺りを何度も撫でる。
確かに○○の腹は締まっており腹筋が割れて、身体全体も筋肉質だ。
くすぐったさに○○は身をよじる。
「くすぐったいよ……」
「ふふ、わざとそうしてる。しかし良い体つきになったな」
「勇儀に鍛えられたからね」
「男らしくていいじゃないか……私も、お前に出会って変わったしな」
はにかんだ勇儀はその外見とは裏腹に可愛らしい。
「最近まではこの胸も邪魔なだけだった。重いし重心がずれるしな。でもようやく分かった。
女の胸は子供を育てるため以外にも男を包み込むためでもあるんだな」
「勇儀……」
「○○、お前のおかげだ。私はお前に会えて女として自覚できた」
勇儀は○○の前に回り肩に両手を置きじっと瞳を見つめた。
はらりと身体に巻いたタオルが落ちるが気にも留めない。
○○の視線はどうしても乙女のシンボルである胸や引き締まった脚の付け根に向かってしまう。
付け根から脚に伝う水滴はお湯や汗だけではないようだ。
「勇儀、お湯が汚れちゃうよ……」
「なら掃除すればいい。それにどうしても止めたければ力ずくでな。でも鬼の力をナメるなよ?」
ゆっくりと水面に向かい腰を落としていく勇儀。
そこにまた一陣の風が吹き――
四人の少女の姿がそこにあった。
みんな顔を赤くして手で顔を隠しているが指は全開に開かれている。
あっけにとられる二人を余所に彼女たちは騒ぎ始める。
「ちょっと萃香! ちゃんと湯気萃めておかないとダメじゃない!」
「しょうがないじゃん! 湯気なんだからいくら萃めても風が吹けば飛んじゃうよ!」
「あ、あはは……お邪魔しましたー」
「私たちはこれで失礼するからあとはゆっくりたのしんでいってね!!」
霊夢、萃香、早苗、魔理沙は一目散に脱衣所に逃げていく。再起動した勇儀はざばっと水音を立てて立ちあがる。
「おまぁえぇらあぁっ! ってあれ……?」
立ちくらみを起こしたのかふらつき倒れそうになる勇儀を○○は後ろから抱きとめた。
「あ、ああ……すまないな」
「大丈夫?」
「お、おう……ちょっと逆上せてしまったかな? まだ少しふらつく」
「そうか。なら、よっと」
「きゃっ!?」
○○は膝下に手を入れて勇儀を抱っこする。いわゆるお姫様だっこというやつだ。
「こうやって支えられるのも勇儀のおかげだな」
「……ばか」
○○が辛くないように首に腕を絡める。胸板にたわわなメロンがぴったりくっついているのでタオル前にテントが張るのはご愛敬。
そのまま○○は勇儀を抱いて脱衣所に向かった。
「はい、水」
「ありがと」
温泉の外にあるベンチで一休みする。二人肩を寄せ合い○○は牛乳、勇儀は水を飲む。
少し冷えたのか○○はくしゃみをする。
「大丈夫か?」
「ああ、まぁ多分」
「風邪なんか引かせたら悪いからな。ほらもっとこっちに来い」
勇儀は○○を抱きよせて首に巻いたマフラーを○○の首にも巻く。
二人が巻いても若干余るので元々長いマフラーのようだ。
「あったかいね……」
「あったかいな……」
ほてった身体に涼しい風が心地よい。どちらともなく指を絡める。
そうして自然に唇が重なる。
「これからお前の家に行ってもいいか?」
「酒でも飲むのか?」
「いや、さっきの続きだ……」
「ん……いいよ……」
ベンチから立ち上がり指は離さぬまま家路に向かう。
そんな二人をあの四人は瓶入りサイダーを飲みつつ遠くから見つめていた。
「「「「妬ましい、あんなにイチャつかれると乙女回路がキュンキュンして妬ましいわ」」」」
どうやらこの四人もどこか逆上せているようだ。
うpろだ1480
───────────────────────────────────────────────────────────
「女って、どういうもんかねえ」
それが最近の姐さんの悩みらしかった。姐さんは酒浸りと言っても過言ではない生活をして
いるが、酔って潰れることはまずないし、人と飲み交わしているときは尚更だ。ただ重要なの
は、そのバイオリズムがものすごく繊細にできていること、姐さんがなにか抱えていて心のバ
ランスを崩しているときは、それらの均衡がおもしろいくらい裏目に働くということだ。
今夜もちょうどそうだった。普段の余裕はどこへやら、打って変わってべろんべろんに酔っ
払った鬼は、数刻前にどうと倒れたっきり意識を取り戻す様子もない。そりゃもう見事に横ざ
まに倒れたわりに、腕はちゃんと枕になる位置にあったり、スカートは乱れてもふとももまで
だったりで、俺は一人おいしいやら歯痒いやら収拾のつかない気持ちを持て余していた。
ふと、泥のようにぴったりくっついていた瞼がぴくりと蠢いた。俺の視線に気付いたのかも
しれない。驚くべきは、星熊童子が戦いのプロであるということだ。生き物には総じて気配が
あり、鬼はそれを感じる能力に長けている。おそろしいほど。それだけのことさね、といつぞ
やの飲み会で姐さんが変わらぬ笑顔で自慢していたことを、俺は今になって思い出した。
でも、それは本当に自慢になるんだろうか。本当に、それだけのことなんだろうか。
俺は姐さんを見下ろした。酒に濡れた唇はうすく開いて、哀れな蜜蜂を誘っている。見たら
最後だ、目が離せない。姐さんが好きだ。好きで好きで好きで、この人をめちゃくちゃにした
い。傷つけたり、救ったり、愛したり、泣かせたりしたい、という欲望で、体中がいっぱいに
なる。しかもそういう感情はあっという間にふくらむ。放っておけば、破裂する。
俺は一生に一度のフルパワーでもって、隙あらば横顔に貼りつこうとする両目を引っぺがし
た。膨れた風船もガスを抜いてぺしゃんこにする。この作業はいつも、少しさびしい。
「ちゃんとした時間に眠らないから、らしくなく潰れたりするんだよ」
悔し紛れに角をつつくと、姐さんは、んん、と呻いて、胡乱げに薄目を開けた。まっさらに
なった眼差しが、前触れなく機嫌の悪くなった俺をぼんやり見上げる。意思と記憶を盃の中に
落っことして飲み干した姐さんは幼げで、無防備で、あどけない。俺は再び途方に暮れる。
いじめたくなる顔の一角鬼は、その後もわりと長い時間からっぽの頭を整理しようとがんば
り、俺は今の姐さんを見るとムラムラするのであさっての方角を向いて酒を呷っていた。やが
て、ああ…、と悩ましげなため息が聞こえ、まただいぶ経ってから思い出したように大人しい
声が、これは…私としたことが…情けないねえ…、とのんびり締め括った。酔っ払いめ。
「まだ寝るのか?」と尋ねれば、億劫そうに首を振る。かといって体を起こすでもなく、相変
わらずだるそうに寝そべって、呆れてしばらく放っておけば、今度は人差し指と中指を逆ピー
スにして人の足そっくりに動かしている。整った桜色の爪が蝶のように揺れていた。
「なにをしてんだ、子供みたいに」
「ふふん、今日は妙にかわいいねって、誉めてくれてもいいんだよ」
「…大丈夫か?まわっちゃいけない器官にまで酒が染みてるぞ」
「おおー、さっきから頭が石みたいに重いと思ったら、それでかねぇ」
ヘラヘラ笑って遊んでいる本体とは裏腹に、ミニ姐さんは縦横無尽に歩きまわった。終いに
は人の手でも登山しようとするので、俺はやむなく小さな分身を捕まえた。姐さんは懲りずに
へらっとした。魔法みたいに指同士が絡まったので、俺は慌てて握り返した。隙間なくぴった
り重ねた指は怖気が立つほどつめたい。思わず「姐さん?」恐る恐る繋いだ手を揺らすと、
「アンタには、悪いことしたねぇ。こんなかわいげのない女に、いいようにされちまって」
突然、背中に氷を流しこまれたみたいだった。それも大量に。目が白黒する。次いで、萎ま
せたはずの風船が、爆発しそうなすごい勢いで膨張するのを感じて、咄嗟に口を噤んだ。必死
に息を止めて、体の内側からそいつがジェット機ばりに飛んでいかないよう踏ん張る。
気付けば喉がからからで、搾り出した声は自分でもぎょっとするほど低かった。
「なんだよ、急に、藪から棒に」
「ふふ。いま思いついたから、いま言ったのさ」
悪いことしたねぇ、と密かにつぶやいた姐さんは気持ちよさそうに瞼を下ろしていて、その
まま穏やかに死んでしまってもいいような顔だった。繋いだ手をゆらゆらと揺らされる。子供
をあやすような、いじらしい仕草に、心臓がぎゅうっと窄まった。破裂する一瞬前みたいに。
俺は口を噤んだ。それから可哀想な姐さんの上に屈んで、黙って唇を押しつけた。掌の下で
力任せに押さえつけた肩が、驚きに強張るのがわかった。かまわない。こじ開けて、奥まで滑
りこんだ。俺は完全に頭に血が上っていて、完全に息の根を止めてやるつもりだった。少なく
とも気概だけはそのくらいあった。稲穂色のほつれ髪が、色素に見放されたようなうなじに張
りついていて、どちらのものとも知れない汗が舌先をぴりぴりと刺す。決して俺に乱暴できな
い姐さんをラフプレーで押さえこんで、くぐもる声を無理やり飲みこんで舐めたり吸ったり噛
んだりしまくった。そのたび姐さんの体は健気に跳ねた。それでもやめなかった。頭が朦朧と
するまでキスした。こんな人、真っ白になっちまえばいい。一打ちで山をも砕く拳は、今はこ
んなにも弱々しく俺の背中を引っ掻いている。これでもだめなのか?これでも……。
ありったけの恨み言らしきものをぶつけきると、あとは波が引いたようにさあっと薄青色の
かなしみが流れこんだ。熱を持った唇を離すと、姐さんはうつろな目で俺を見返した。涎まみ
れの唇で荒い息をしている。まろみのある優しい胸が、大袈裟なくらい上下していた。
「そっちこそ」姐さんは険のとれた目で微かに笑った。「藪から棒じゃないか」
「おたがいさまだろ」
俺はすかさず言い返した。なにかを言われる前に。たとえ言われても、きっとうまくは説明
できない。姐さんは一瞬勘ぐるような目つきになったが、すぐに言葉を捜すのをやめた。そん
な方法よりもっと合理的な手段が目の前に転がっていることに気付いたみたいだった。そして
それが一番正しい。いつだって。豪快な言動や性格のせいで霞みがちな、意外と線の細い体を
抱き直したのとほぼ同時に、姐さんの手が覆いかぶさる胸を這う。指先に、熱がある。
「…する?」
とろんと瞬きをして、姐さんはささやく。光る唇がまあるく開いて、そこからさっき思うが
まま貪った白い歯や気だるげな舌がちらりと覗く。それを目にした途端、まだ足りない、と頭
の裏側で誰かが毒を吹きこんだ。飽きもせず俺は、見えない引力に従って体を沈める。わざわ
ざ油断と隙を振り撒いてくれている愛しい罠に生き物みたいな舌をぬるりと忍ばせると、その
瞬間、かろうじて開いていた目が三日月より細くなった。そして姐さんは瞬く間に生き返る。
結局、どうあっても姐さんはおんななのだ。俺が姐さんをおんなにする。あけすけで、凛々
しくて、どんな男よりかっこいい姐さんを、つややかで、しぶとくて、奔放なのに策略家で、
時たま淫乱なおんなにする。それは今までも、これからもずうっとだ。ずうっと変わらない。
俺と姐さん。
姐さんが好きだ。
好きだ。
姐さんはもう、我を忘れかけている。綺麗な眉を苦しげに寄せて、夢中で俺の唇を貪る姐さ
んは早くも堪えきれないみたいで、蝶の羽ばたきのように頼りなく震えている。俺は可哀想な
姐さんがどうにも辛抱できなくなって、その綺麗な目の端っこから悔しそうに涙を零し、はや
くさわって、とささやくのを待つが、それより先に、どうせ酒の味が丸二日は落ちなさそうな
ぽってりした唇に誘われて、なにもかもめちゃくちゃにせずにはいられなくなる。
うpろだ1512
───────────────────────────────────────────────────────────
とある晴れた冬の始め、俺は一人の女性と待ち合わせしていた。
その女性とは星熊 勇儀、地下の旧都の守鬼だ。
地霊異変の後、博麗神社の宴会にちょくちょく顔を出すようになりそれが切っ掛けで仲良くなった。
ついこの間、何故か俺と勇儀で飲み比べをすることになり、すでに俺はへべれけだったし鬼にそんな勝負を挑む時点で正気じゃないことは確かだろう。
案の定あっさり負けて何かひとつ言うことを聞くことになり勇儀は一日俺と遊びたいという願いを言ったらしい。
ぼんやりとそんなことを考えていると目の前に何かが突然落ちてきた。
砂埃が治まるとその落下物の衝撃でクレーターが出来ており、その中心にはにこにこと笑う勇儀の姿があった。
……もうちょっと普通の登場はできないものか?
「やぁ○○。待たせてしまったか?」
「いやそんなに時間経ってないし気にしなくていいよ」
勇儀はいつも通りの体操着みたいな上着にロングスカート。特に着飾ったわけでもないのに格好よく見えるのは美人の特権だな。
「ん? どうした私の格好をじっと見て。どこかおかしいところでもあるのか?」
「いや、ただなんとなくだな」
「ああ、そうか。安心してくれ、ちゃんと下にはブルマを穿いているからな。
白黒の奴が言うには上下セットじゃなくちゃダメみたいだからな。それともスパッツの方が良かったか?」
ペロリとスカートを捲り上げる勇儀。い、いきなり何してるんですかこの人ーっ!!
引き締まった脚にブルマってのは健康美な感じがいいって俺何考えてんだ!
しかも捲り上げすぎてくびれた腰と若干筋肉質なお腹まで見えてしまっている。
「ああ、気にしなくていいぞ。鬼は性に明け透けだからブルマくらい見せてもなんともない」
「少しは気にしろよ! 露出狂みたいじゃねぇか!」
「ちなみにぱんつはいてない」
「聞いてねー!!」
玉兎のお株奪うようなまねするな! つーか鬼ってこんなんばっかりか!
「むう……悪かった。調子に乗り過ぎたか」
しょぼんとスカートを下ろしキュッと締まったお腹が見えなくなってしまった。
もうちょっと見ていたかったって俺は変態か。
「悪いな、久しぶりの地上なんでな。一人で盛り上がってしまった。許してくれ」
ぺこりと頭を下げる勇儀。
なんというか意外に子供っぽいところもあるんだな。
「いや、気にしてないから。それよりもどこかに行こう。このまま突っ立っているわけにもいかないし」
「そうだな。それじゃエスコートよろしくっ!」
勇儀は俺の左側に回り込むと腕を組み手を繋いできた。
というより指を絡めてしっかりと握っている。しっとりと柔らかく普段こんな手で馬鹿力を出しているとは思えないくらいだ。
しかも腕には自慢の胸を押し付けてきているので肘にぷにぷにと肉まんのような感触が伝わり、どうもそこに意識がいってしまう。
「ん? どうした? 気持ちよくないか?」
「いや、気持ちいっていうか恥ずかしい。というか確信犯か」
「気にすることはない。○○にならいきなり胸を鷲掴みにされても受け入れる準備はできている。安心してほしい」
「だから俺を勝手におっぱい星人にするなー!!」
馬鹿な(一方的に勇儀がボケる)やりとりとしながら俺達は里へと向かった。
「○○、あれはなんだ?」
「ん? 活動写真……映画のことか」
里に着きまず勇儀が興味を示したのは映画だった。今外界ではデジタルが主流になってしまったため逆にフィルム映画が幻想郷に流れてきている。
結構知られざる名作も多いので人妖問わず人気な見世物だ。
「ほぅ、面白そうだな。先に入ってるぞ」
「あっ、ちょっ!」
一足先に駆けていき、小屋の中に入っていく。
しょうがないので二人分の料金を払って上映タイトルを調べる。
「えっと今の時間だと上映しているのは……『まじかる☆めいど 咲夜ちゃん』か……」
激しく地雷の臭いがするんだが勇儀が先に入ってしまっているためどうしようもない。
ええい! ままよ! 毒を食らわば皿までっ!!
――映画視聴中――
「…………」
「…………」
映画を観終わった俺達はしばらくしゃべることもできなかった。
ポップなタイトルのくせに内容はバリバリのバトルもの。
しかも魔法少女でもリリカルな○はやカードキャプターさ○ら系ではなく魔法少女○イ系で血みどろぐちゃ満載。
この映画には早々にR-21禁タグをつけてもらいたい。子供が見たら一生モノのトラウマになるぞ。
「えーとそのなんだな、たとえて言うなら こ れ は ひ ど い」
「勇儀が勝手に突っ込んでいくからだ。これからはちゃんと内容確認してから見るようにしような」
「ああ。ところで少し小腹が減ったんだが何か食べるものはないか?」
「そうだな。近くに茶店があったからそこに行こうか」
馴染みの妖怪の爺さんがやっている茶店でお茶をすることにする。
俺に気づいた爺さんが冷やかしてきたがそれにも色ボケネタで返すので爆笑された。この頭が春状態な鬼めっ。
端の席に座りお品書きを眺める。そこにお茶とおしぼりが運ばれてくるがその店員に俺と勇儀は驚いた。
「いらっしゃい。二人揃って逢引?」
「何でもそういう方向に持っていこうとするんじゃない!」
「○○は不全だから私が誘っても一向に獣になってくれないんだ」
「お前は俺を一体どういう風に解釈しているんだよ! で、なんで萃香が給仕なんてしているんだ?」
「いやー霊夢がさ、いい加減うちに居候するんなら金払えって言ってさ、追い出されちゃって。ここで給仕として雇ってもらったんだ。どう? この恰好似合う?」
くるくると回る萃香を上から下まで一通り眺める。
矢絣模様で紫色した和服は某馬車の道のウェイトレスそっくり。俺が前外界には可愛い給仕服があるってこと話したがそれを再現させたのか。爺さん、GJ。
元が女学生をイメージしているためにちっちゃい萃香にはよく似合っている。
「似合っている。可愛いよ」
「えへーありがと。でもね、女の子連れている時に他の娘口説いちゃだめだよ」
そう釘を刺して萃香は注文を聞いて裏に引っ込んでいった。
勇儀はしばらく目を泳がせていたが俺が視線を向けたと分かるとおずおずと話を切り出してきた。
「な、なあ、○○はその、小さい方が好きなのか?」
「小さいって身長のことだよな?」
『違う、胸の話だ』などというボケが来るのではないかと身構えてしまったが、もじもじとしてこちらを窺っているところを見るとどうやら真剣な質問だったようだ。
うーん、意外だ。勇儀が実は大きいことにコンプレックスを抱いていたとは。
「別にあまり気にしたことはないな」
「そうか。いや、背が高いとな、どうしても着られるものが限られてくるんでな。実を言うとフリルとかにはちょっと興味がある」
確かに勇儀にフリルはどうかと……。やっぱりフリルが似合う霊夢や咲夜さん、アリスとかはみんな小柄だもんな。
「それでも勇儀は十分可愛いと思うけどな」
「なっ!? ばばば、馬鹿なこというなっ! わ、私が可愛いなんて……」
勇儀はみるみる顔を赤くして俯き加減になる。
おや、意外な弱点発見。鬼には何かしら弱いところがあるらしいがこれはいい。
ふふ、散々振り回された仕返しをしてやる。とりあえず次行くところは決まったな。
「お待たせしましたー。白玉ぜんざいとお汁粉になりますー」
そこに萃香が注文した和菓子を持ってきた。
とりあえず頼んだものを平らげてから実行に移すとしよう。
それからしばらくぶらぶらと里を歩いていわゆるウインドゥショッピングといわれる冷やかしをして最後にとある店に入った。
「おい○○、ここは――」
「そう、見れば分かるな。女性服の店だ」
やっぱり幻想郷でも女性は可愛らしい服が好きなのだろう。華やかな衣装がそこかしこに並べられている。
「くっ、はかったな○○!」
「別に謀ってなんてないさー。着飾った勇儀が見てみたいだけで」
「だから私は可愛くなんか」
「やってみないと分からないさ。今までの積極性はどうしたんだよ」
すいません。困っている勇儀見てちょっぴり楽しんでいる俺。
とりあえず店員を呼び、勇儀に似合う服を見つくろってもらおう。
俺の横で気まずそうにしている――あれ? 何でそんな素敵な笑顔浮かべているんだ?
そこにこの店の店員らしき人が近づいてきた。
「お客様? 服をお探しですか?」
「ああ、私の彼が可愛らしく着飾った私を見たいと言うからな」
な、なんですとーっ!? 三人称ではなく恋人に使う彼!? しかも私のっ!?
「普段はべったりなんだが出かけると妙にそっけなくて逆に私が甘えないとダメなんでな。困ったやつだ」
ぎゃー! もういつもの調子を取り戻している!
このままではマズイ! 援護しろ!!
辺りを見回しても管制室から支援攻撃が来ることはなかった。
「もう、昨日寝床であんなに可愛い可愛いと囁いてくれたのにどうして素直になってくれないんだ? それともやっぱりデカイ女は可愛くないか?」
「なっ! そんな記憶はねー! 勝手に捏造すんな! だ、だけど勇儀は普通にか、可愛いと思うぞ……」
「ふふ……そう言ってくれると嬉しいな。しかし私はあまり流行に詳しくない。○○に全部見てもらわないとな」
そう言って視線を向けた先を見て俺は凍りついた。そこは所謂女性下着売り場だ。
「待て待て待てっ!! そんな所に男が入っていっていい訳ないだろう!」
「いえ、意外に一緒に入る男性の方も居ますよ。この間鴉天狗と白狼天狗の方がお連れさんと選んでいましたから」
敵に援護してどうすんだ! 管制室ちゃんと援護しろよ!!
その間もずるずると引きずられて行く俺。どんなに力を入れても抵抗すらできやしない。
こんな時だけ怪力乱神を発動するなー!
「ふふふ……乙女の花園へようこそ。歓迎しよう。それじゃまず私のつぼみから見てみるか?」
「――! ――、―、――!!」
もう限界だった。フリルだらけの布に囲まれて俺の思考は灼熱地獄に放り込まれたかのようにドロドロになっていった……
「くーっ、楽しかった。久しぶりに酒を使わないで大暴れできた」
「ああ、そいつはよかったな」
あの後のことはよく覚えてない。とにかく勇儀はすごかった。いろいろと。キュッとしてドカーンって感じ。どこかは言えないが。
「○○、相手の弱点を突くのはいいが攻めきれないのなら手痛い反撃を受けることになるぞ。ちゃんと追い打ちまでかけられるようにならなければうかつに手は出さないことだ」
「ああ、肝に銘じるよ」
勇儀姐さんのありがたいアドバイスだった。
「さて、これでしばらく地上にこれなくても大丈夫だな」
「えっ、どうして?」
「んー、ちょっと旧都の方でごたごたがあってな。しばらく離れられそうもなくてな」
「宴会にもか?」
コクリとうなづく勇儀に何だか胸の奥が寂しく感じた。
「また、会えるよな?」
不安そうな表情を浮かべていたんだろう。勇儀はそんな俺の気持ちを吹き飛ばすかのように満面の笑みを見せた。
「心配するな。すぐに片付けてまたお前と飲み比べをしてやる」
「無茶を言うなよ。負けること確定じゃないか」
「そうしたらまた出かける約束を取り付けてやる」
「普通に誘えよ」
彼女の笑顔にいつの間にか不安はぬぐい去られていた。
そして不意に勇儀が近づき――
ちゅっ――
っと俺の額に口づけをした。
「お前にはもう私が唾をつけたからな。浮気は許さん。守ってくれたなら次にはもっと凄いことしていいぞ」
ああもう、まったくこの鬼は――
「……本当に押し倒すぞ」
「……いいよ」
夕焼けより赤くなった顔で上目使いをしている勇儀は本当に可愛らしかった。
そのまま後ろを振り返りたったと走って行って途中でこちらに手を振ってきた。
俺が振り返すと満足したのかあっという間に見えなくなってしまった。
ずいぶん振り回されたがこれはこれで得難い幸せだったのかもしれない。
新ろだ110
───────────────────────────────────────────────────────────
前回勇儀に振り回されたデート(あれはデートだったのか?)から暫く経ったある日のことだ。
旧都での問題が解決したのか勇儀が萃香を連れて俺の家に乗り込んできた。
押しかけてくるのは何を言っても止めないだろうからもう諦めたがいきなり玄関のドアを力いっぱい開けないでほしい。
魔理沙がマスパでも撃ち込んできたのかと思ってヒヤヒヤしたぜ。
別にこれといった用事はなかったので部屋にあげた。
まず間違いなく酒盛りになるんだろう。小山みたいにつまみを持っていることからすぐに察することはできた。
ちなみに言葉のあやではなく本当に山盛り状態で、ヘタしたらダンプ並みに運んできているかもしれない。
部屋の机につまみをこんもりと乗せるとふぅと勇儀は一息いれた。
「さて、エロ本でも探すか」
「それは男友達がやるイベントだろう!」
「あ、本棚の3つ目の棚に何冊か隠れているよ」
「な、なぜそれを知っている!!」
「くふふ、香霖堂に行った日はちょうど霧雨だったね」
「お前あの雨の中隠れて見てやがったのか! 油断も隙もないな!」
「むぅ、お姉さん系も多いがつるぺたも好きなようだな」
「私のおっぱい吸う? 何も出ないけど感度はいいよ?」
「だから何でお前ら鬼はそうエロい方向に持っていこうとするんだ! お前らのそういうところ嫌いだよ!」
「あ、ご、ごめん……ちょっと調子に乗り過ぎた」
「そうはっきり言われると少し傷つくな……」
二人ともしょんぼりしてしまう。なんだか俺が悪者みたいだ。
「お、俺も言いすぎたかも……別に萃香と勇儀が嫌いなわけじゃなくて、二人は大好きだよ……」
告白みたいになってしまった。なんだこの空気は。
俺の言葉に元気を取り戻した二人の鬼はさっそく酒盛りを始めようとした。
当然俺も付き合うことになる。さほど強くはないがそこそこ飲めると自負しているがやはり妖怪には敵わない。
ウォッカやウイスキーをストレートでカパカパ飲める奴は酒飲みじゃねぇよ。うわばみだ、うわばみ。
あっという間に三人の酔っ払いが出来上がりあんまり途中のことは覚えていない。
気がついたらかなりの数の酒瓶が転がって、つまみは散乱、俺と勇儀は床に転がって、萃香はちゃぶ台にうつ伏せになっていた。
コチコチと時計の秒針が時を刻む音だけが響く中俺は口を開いた。
「……で、何かあったのか?」
「んー、まぁいろいろと」
「そっか……」
何かあったことはすぐに分かった。騒ぐことが好きな鬼が二人だけでやってくること自体おかしいんだ。
「……話せる?」
「いや……」
「あんまり溜めこむなよ。誰だって逃げ出したいときはあるさ。その、なんだ。俺でよければさ、付き合うから……」
誰にだって悩みはあるものだ。それは自分で背負っていかなければならない。
けれど、その荷物を共に支えることはできるはずだ。人でも、妖怪でも。
勇儀は旧都の守護者をやっているだけあってかなり膨大なものを抱えてるはずだ。
彼女は強い。一人でも重荷を支えることはできるんだろうが、俺だって彼女の助けになりたい。
そう願うだけでもいいだろう?
「……○○はやさしいな」
また静かな時が流れる。と、萃香がむくりと起き上がり青い顔をしてヨロヨロと部屋から出て行った。
途中廊下からガンと頭をぶつけたような音がした。
「おいおい……大丈夫か?」
「……萃香には気を使わせてしまったな」
「えっ? うわっ!?」
勇儀は俺を抱えあげベットに放り投げると覆いかぶさってきた。
顔が赤いのは酔っ払っているだけじゃなさそうだ。
「……嫌なら抵抗してくれ、すぐに止めるから……」
「……嫌じゃない。むしろして欲しい」
ゆっくりと、確実に赤く染まった勇儀の顔が俺に近づいてくる。
そしてお互いの唇が重なった。
「……んぅ、ん、あん……っあ、……ふぅうん……んんぅ」
そっと勇儀の両肩に手を置いて引き寄せる。勇儀は抵抗の意を示さず俺に体重を預けてきた。
なんというか、本気で可愛い。俺にしか見せない無防備な勇儀が目の前にいる。
「ふぁ……ぅん、あぅ、んっ、はぁ……っんんぅ」
暫く見つめ合い、もう一度求め合うようにキスをする。
「んふぅ……あぁ、ん、ふぁ……あん、ちゅっ……くぅうん、ふああぁ」
少しずつ勇儀の口内に舌を滑り込ませる
最初は抵抗していたがやがて自分から舌を絡ませて俺を受け入れてくれた。
長く、甘いキスを名残惜しそうに終える。
「……酒臭い」
「あれだけ飲んだからな……。これからは少し控えようか……?」
「いや、それじゃ勇儀らしくない。俺は気にしないよ」
「そっか……。ありがとう」
言うと勇儀は再び俺に抱きついてキスを再開する。
「はぁん、んく……ちゅ、ちゅうぅ……はうぅ、んぐ……」
優しい光を宿した瞳で俺の目を見つめてくる。
「あ、その……こんなこと言うの、恥ずかしいんだが、わたし……はじめてなんだ……や、やさしくしてくれ」
「……なんか可愛いな。いつものエロさはどこにいったんだ?」
「ちゃ、茶化すな! き、緊張しているんだ……」
「ああ、そうだよな……。俺だって初めてだし、できるだけやさしくする……」
「ん、ふぁっ……あ、あんまり女らしくない体だけど……ひゃん! ○○の、好きにしてくれ……」
くるりと体を入れ替えて勇儀を下にすると今度は俺が彼女に覆いかぶさった……
――鬼娘求愛中――
目が覚めると部屋は眩しい朝日に包まれていた。
隣に勇儀がいないことに気づいて慌てて飛び起きるが同時に部屋のドアが開いて勇儀が入ってきた。
「……おはよう。よく眠っていたな」
「ああ……おはよう。勇儀は?」
「私もしばらく前まではぐっすり眠っていた。その、結構疲れるものなんだな……。弾幕ごっこより……」
昨日の情事を思いだしお互い赤面する。ふと柔らかな石鹸の匂いが鼻をくすぐる。
「勇儀、風呂入った?」
「ん? ああ、酒と汗で凄い臭いだったからな……。これでも女なんだ。少しは気にする。」
普段の大雑把でざっくばらんな勇儀と今の年頃の女の子らしい勇儀のギャップが可愛らしい。
そしてお互い、何かを言うまでもなく口づけを交わした。
「ふぅ、んん……あぅ、ん……ぅん」
とろけるような甘いキスをする。口からは酒の匂いはせず、ミントのような清潔な匂いがした。
「んっ……勇儀、歯磨いた?」
「ああ、少しは女らしくしようとな……○○に、き、嫌われたくないし……」
俺のためというのが純粋に嬉しかった。
お互い飽きるまでキスを繰り返した。
その後居間に行くとうつ伏せで倒れている萃香を見つけた。
どうやらずいぶん飲んでいたようで体を揺すって起こすとすっごい不機嫌な顔で起き上がった。
「……今までで一番悪飲みしたかも。うぶ……ぎもぢわるい」
うーむ、萃香には悪いことしたな。今度ウマい酒を奢らないと呪われそうだ。
朝ごはんの用意は萃香が用意していたらしい。だが赤飯なのは嫌味か?
『大豆じゃないから弱点じゃないもん!』と、どこかイッてしまった目で言っていたのでどこかから毒電波でも萃めてしまったんだろう……。
俺と勇儀は顔を赤く、萃香はニヤニヤと嫌な笑顔を浮かべ、複雑な心境の中朝食は進んでいった。
穏やかな、何気ない日常がとても大事なものに思えた。
それは勇儀との関係が変わったなのかと思うと少し恥ずかしくなった。
「○○、ありがとう。今度は地下にきてくれ。旧都を案内する」
「それは楽しみだ。でも無事にたどり着けるか分かんないけどな」
「う……そうか……」
「私が連れて行ってあげるよ。それ以外なら霊夢か魔理沙に頼めばいいし」
……名残惜しげに勇儀の手が俺の手から離れる。
ずっと握って離さないんだからまた萃香にからかわれた。
「また、辛くなったら会いに来る」
「ああ、いつでも待ってる」
陽光の中、太陽より眩しく笑う――
――どうかこの優しく強い鬼をずっと、ずっと俺の力が続く限り支えられますように。
新ろだ148
───────────────────────────────────────────────────────────
二月三日、節分。御存じの通り、この日には炒り豆を撒いて邪気を追い払うという行事が催される。
現に、俺の目の前では子供たちが升の中の豆を掴んでは『鬼は外、福は内』と、楽しそうに鬼に向かって投げつけていた。
鬼の方もまた、ひゃあひゃあと大げさに喚きながら、楽しそうに逃げ回っている。
鬼の役を受け持っている人、ではない。
正真正銘の、鬼だ。それも女の。
その額から突き出た立派な一本角は、面の一部や角に見立てた飾りではないのだ。
星熊勇儀。それがあの鬼の名前だった。
鬼と言っても、それほど恐ろしい感じはしない。見た目だって額の角を除けば、特に人間と変わりはない。
伝承が間違っていたのか、勇儀が鬼の中でも風変わりな存在なのか、多くの鬼を知るわけではない俺には分からない。
だが、升の中の豆をまとめてぶっかけられ、引っ繰り返されたダンゴムシみたいにもがいて見せている勇儀。
子供たちを笑わせているその姿は、少なくとも悪い鬼には思えなかった。
だからこそ、俺も勇儀と一緒に酒を酌み交わしているのだけれども。
豆まきが終わってからもしばらくの間、勇儀は子供たちを腕にぶら下げたり、肩車をしたりして遊んでやっていた。
しかし、そろそろ日も暮れてきた。子供たちは勇儀に手を振りながら家路に就き、勇儀も手を振り返して子供たちを見送る。
子供たちの姿が見えなくなったところで、勇儀は俺のところに戻ってきた。
「待たせたね。さ、帰るとしようか」
散々子供たちの相手をしていた勇儀だったが、その声はまだまだ自分は元気だと主張するかのように張りがあった。
ああ、と一言だけ返事をして、俺は勇儀と肩を並べ、燃えるような夕日を背に、白い月を正面に歩き出す。
家に帰るまでの間、勇儀の口数の少なさが俺は妙に気になっていた。
* * *
勇儀と連れ立って自宅に帰り、俺は玄関の戸を大きく開け放って家に上がる。
後ろ手に戸を閉めて下駄を脱ぎながら、勇儀は久方ぶりに口を開いた。
「いやあ、やられたやられた。
やっぱり鬼も人も子供は変わらないね。元気なもんだ」
「ご苦労さんだったな。さすがの勇儀もくたびれただろ」
「はっはっは、鬼を舐めちゃあいけない。あれしきの運動、準備運動にもなりゃしないさ」
「そうか? それにしちゃ、汗をかいてるようだが」
勇儀の額にはうっすらと汗が滲んでいた。今の時期に暑さで汗をかくわけがない。ならば、運動による発汗だろう。
でなければ……。
俺が指摘すると、勇儀はすぐさま手の甲で額の汗を拭った。
「……おっと。こいつは参ったね」
「ま、なんでもいいさ。今、飲み物を用意するから、先に炬燵に入って待っててくれ。
炭は新しいのが入ってるから、火を着けといてくれるか」
「あいよ」
そんな風に返事をしながら、勇儀は居間の炬燵へと向かっていく。
勇儀の背を見送りながら、さっきの勇儀の様子を思い出す。
俺が勇儀の額の汗を指摘したとき、勇儀は一瞬真顔になった。いつもの余裕の笑みが消えていたのだ。
勇儀の様子を気にかけつつ、戸棚から湯飲みを二つ取り出しながら、声を掛ける。
「コーヒー切らしてるんでお茶でいいか?」
訊きながら勇儀を見ると、杯を傾けるような仕草をする。そして、言った。
「どっちかと言えば『おちゃけ』の方が嬉しいねぇ」
「オッサンか、お前は」
歯を見せて笑う勇儀。あきれながら、思わず俺も笑ってしまう。
取り出しかけていた急須を戸棚に戻し、代わりに酒瓶を引っ張り出す。まだ蓋も開けていない新品だ。
ま、勇儀は背中を丸めて茶を啜るより、こっちの方が似合っているだろう。
左手の親指と人差し指で二つの湯飲みを挟んで持ち、右手には酒瓶を持つ。
それらを全て炬燵の天板に置き、俺は湯飲みに酒をなみなみと注いで、勇儀に差し出した。
「お、悪いね。催促したみたいで」
「露骨に催促しただろ」
俺の突っ込みにも動じず、勇儀は湯飲みの中の酒を一気に呷った。
そんな飲み方をしたら心配になる。……この調子で飲まれたら、ウチの酒が空になってしまうんではないか、と。
勇儀の体? 鬼がこの程度で体調を崩すものか。
空になった湯飲みを叩きつけるようにして炬燵の上に置き、息を漏らして勇儀は言った。
「ああ、一仕事終えた後の一杯ってのは最高だね! おかわり!」
ニコニコ笑いながらグイと湯飲みを突き出す勇儀。
俺は苦笑いを浮かべながら、空になった湯飲みに酒を注ぎ足す。それをまた、一気に飲み干す勇儀。
勇儀は空になった湯飲みの底をじっと見ている。
「……悪いけど、もう一杯もらえるかい?」
しょうがないヤツだ。……が、少しばかり深刻そうな顔をしていると思ったのは気のせいだろうか?
俺はもう一度、酒を注ぐ。
「かけつけ三杯かよ。湯飲みでするもんじゃないだろ」
「まあ、いいじゃないか。ふう、いい酒だねえ」
そう言って、勇儀はグイグイと酒を飲み干していく。
おかしい。普段の勇儀ならこんな乱暴な酒の飲み方はせず、もっと味わって酒を楽しむはずだ。
勢いよく呑むのは、雰囲気が大事な宴の時くらいだろう。
これではまるで、酔うためだけに酒を飲んでいるようではないか。
「……勇儀。俺に何か隠してないか?」
「はて? 何のことだい」
俺には分かる、勇儀が空惚けているのが。鬼は嘘をつかないらしいが、事実の隠蔽はするらしい。
このまま訊いても埒が明かない。俺は核心を突いた。
「辛いんだろ? 鬼払いを受けて平気なはずがないんだよな、よく考えたら。
酔いで痛みをごまかそうとしてたんだろ」
「……やれやれ。とぼけた顔して、細かいところまで見てるもんだね」
「分かるさ。今までどれだけ、お前と顔突き合わせて酒を飲んできたと思ってるんだ」
「はは、あんたに隠し事はできないか。さすがだね」
「別に、俺はそんなに聡いわけじゃない。けど、お前が苦しんでることくらい分かってやれるぞ」
「……悪いね」
やせ我慢ではなく、自然な表情で勇儀は笑った。人に心配かけて嬉しそうにしてるんじゃないっての。
俺は何も注いでない方の湯飲みを持ち、もう一度戸棚に向かう。
「ちょっと待ってな。気休めかもしれんが、薬を持ってくる」
「すまないね、世話をかける」
「気にするなよ。今まで俺が何遍酔い潰れて、お前に家まで運んでもらったことか」
「それもそうだ。じゃ、気にしない」
「そうしろ」
戸棚の中から鎮痛剤を取りだし、水を注いだ湯飲みと一緒に勇儀に差し出す。酒を飲んですぐに薬というのは良くないが、仕方ないだろう。
勇儀はまず水を口に含んでから、薬包紙の上の散剤を口に入れた。そして、口の中のものを一気に飲み込む。
苦い薬が苦手なんだろうか?
そうだとすれば微笑ましいが、そんなことよりも俺には気になっていることがあった。
俺は訊いた。
「しかし、何だってそんな目に遭ってまで、豆まきの鬼を引き受けたんだ?」
そう。勇儀は鬼の役をやらされていたわけでも、頼まれて引き受けたわけでもなかった。
元々鬼の役をするのは俺の役目だったのだが、何気なしにそれを勇儀に話したところ、なぜか自分がやりたいと言い出したのだ。
妖怪、それも鬼が町内行事に参加するなんて無理ではないかと思ったが、意外なほど簡単に話は通った。
おそらくは鬼の提案をはねのけるなんて出来ないと言った理由なのだろうが、俺は勇儀の人格を信用してくれたのだと信じたい。
勇儀は少し迷った様子だったが、やがて口を開いた。
「……やっぱり、あんたに隠し事はできないね。まあ、隠すほどのことでもなし、話してもいいか」
「そうしてくれ。俺も余計な詮索をしたくはないし、お前と差し向かいで飲む酒が不味くなるのもゴメンだ」
「そうだね。あたしも不味い酒は飲みたくないからね」
真面目な顔つきで、勇儀は頷いた。
「あたしの仲間の萃香は知ってたよな? 鬼の伊吹萃香さ」
伊吹萃香。勇儀の口からたびたび語られるその名前を、当然俺は知っていた。姿も、一度だけ見たことがある。
「ああ、あのチビっこくて二本角の可愛い娘か」
俺がそう言うと、勇儀は口を大きく歪めてニヤリと笑った。
「おや、ああいうのがお好みかい? 意外だねえ」
「いいや。俺は角は一本の方が好みだ」
「角の話かい……と、話が逸れたね」
コホンと咳払いをして、勇儀は再び話し始めた。
「少し前の事件で、その萃香が人間と仲良くやってるらしい……ってのを知って、あたしも地上(こっち)に興味を持ったってわけなんだが。
それで地上に来てみて、萃香が人間と肩を並べて楽しそうに呑んでるのを見て、思ったのさ。
そろそろ鬼と人間の在り方も変わるべきなのかも……ってね。
もう、鬼が人間に恐れられなきゃならない時代は終わったんだよ。これからは鬼も人と折り合いをつけてやっていくべきなのさ」
ようやく納得がいった。わざわざ苦手な豆まきに参加したのは敵意のないことを示して、鬼の方から人間に馴染もうとしたってわけか。
「なるほどな。そのためにまず、自分から歩み寄ろうとしたんだな」
「そうさ。何ごとも願っているだけじゃ叶わないからね」
「なら、勇儀のやり方は間違ってなかったってことだろうな。勇儀が相手してやってたチビたち、初めて本物の鬼を見たってんで大はしゃぎだったじゃないか」
「そうだね。あの子らが大人になって、その子がまた大人になって。そうやって少しずつ、鬼と人との関係が変わっていくといいんだが」
ひとしきり喋って、神妙だった勇儀の面構えが不意に綻んだ。
「ま、本音を言えば旨い酒を酌み交わせる相手を増やしたかっただけなんだけどね。
……あんたみたいな、さ」
「俺も、お前と飲む酒は極上に旨いと思うぜ」
素直な言葉が俺の口からこぼれる。勇儀と飲む酒は格別に旨い。だから、いつも飲み過ぎちまうんだ。
俺は笑った。勇儀も笑う。
珍しく硬い話をして体も硬くなったのか、勇儀は目を瞑って大きな伸びをした。
「ううん、酔ってるときに小難しい話をするもんじゃないね。酒が変なところに入っちまった。
……よっこらしょ」
年寄りじみた掛け声をあげて、勇儀は立ち上がった。そして、そのまま俺のすぐ隣に座り直す。
「……ふう。今日は子供たちに付き合って、ちょいとばかりはしゃぎすぎたみたいだ。
……少し、寝る。悪いけど、枕を借りるよ」
言いながら、勇儀は倒れるようにして寝転がり、俺の太股に頭を載せた。そのまますぐに寝息が聞こえてくる。
寝付きがいいと言うより、まるで卒倒したかのようだ。
その様子を見て、思わず口から言葉がこぼれる。
「やっぱり、体に結構な負担がかかってたんじゃないか。
……無理しやがって」
大口を開けて眠っている勇儀に手を伸ばし、山吹色の前髪をそっと梳く。意外に柔らかく、馬のたてがみのような感触がした。
まったく、いい女だよ、お前は。
「本当に、鬼と人間が上手くやっていける日が来るといいな。
……俺とお前が並んで歩いても、誰も変に思ったりしないように」
ふと気づく。俺、勇儀が目を覚ますまで、ずっとこの格好でいなきゃならないのか?
どうしたもんかと下を見れば、勇儀は小さくイビキをかいている。グッスリという言葉がよく似合う眠り方だ。
俺は上半身を傾けて、出掛ける前に脱ぎ捨てていった丹前を掴み、それを勇儀の体に掛けた。
そして、炬燵の上に載せておいた酒瓶から湯飲みに酒を注ぎ、口をつける。
「……まあ、いいか。珍しい肴もあることだし、一人でのんびりやりますか」
窓の外では、そろそろ陽の光が月の光に取って代わられようとしていた。
明かりも点けず、薄明の中の勇儀の寝顔を眺めながら、俺はチビチビと酒を飲み続けていた。
* * *
酒を飲みながら、いつの間にか俺は眠ってしまったらしい。
目を覚ますと、勇儀が俺の顔を覗き込んでいた。暗くてよく分からないが、勇儀の柔らかな笑みの向こうに天井らしきものが見える。
頭の下には、パンパンに張った水枕のような、柔らかくて弾力のある感触。ほんのりと感じる温かみ。
これは……俺が勇儀に膝枕をされてるのか?
「お、お目覚めみたいだね」
「勇儀……具合はどうなんだ? もう大丈夫なのか?」
「ああ、お陰様でね。一眠りしたらすっかり良くなっちまったよ」
歯を見せて笑い、勇儀は晴れやかな表情を見せた。その笑みに違和感はなく、どうやら本当に回復したようだった。
安堵して、俺は上半身を起こそうとした。
すると、勇儀は人差し指で俺の額の真ん中を押さえてきた。俺の頭は固定されたように、びくともしなくなる。
「無粋な真似をしなさんな。もう少し、このままにさせておくれ」
「……分かった」
「それに、さっきは長々と膝の上に居座っちまったからね。これはそのお返しさ」
「構いやしねえよ。勇儀の寝顔なんて珍しい物も見られたしな。珍しいと言うより、初めてか」
「いっつもあんたの方が先に酔い潰れちまうからねえ」
勇儀はからかうように笑った。
「酒の強さで鬼に勝てるわけ無いだろ」
「何も、酔うのは酒にだけとは限らないさ。またあたしの寝顔が見たけりゃ別の物で酔わせてみな。
……男の魅力とかでね」
そう言って俺を見つめる勇儀の眼差しはとても妖しげで、艶めかしかった。勇儀から受ける印象とはちょいと遠いが、魔性の女と言えるかもしれない。
俺は寝転がったまま、小さく肩をすくめる。
「なおさら無理な話だ。……そっちも俺の方が酔ってる」
「だったら強くなりな。酒にも、男としても、ね。鬼の寿命は長いから気長に待ってるよ」
「ま、やってみますか」
「頑張りなよ。あんまり女を待たせるもんじゃないからね」
俺は力強く頷いてみせ……たかったが、勇儀に額を押さえられているせいで頭が動かなかった。
このザマで本当に強くなれるのか? 苦笑して、俺は勇儀に言った。
「そろそろ起きたいんだが」
「もう少しいいじゃないか。たまには女らしい真似の一つもさせとくれ」
「明かりを点けたいんでね。暗くてお前の顔もまともに見えやしない。せっかく勇儀が目の前にいるのに、顔を見ないなんて勿体ないじゃないか」
「……なら、しょうがないね」
ニヤリとして、勇儀は俺の額から指を離してくれた。
ようやく立ち上がることの出来た俺はいくつかの照明に火を点け、適当にツマミになりそうな物を引っ張り出して、勇儀の向かいに座り直した。
最初に座っていたのとは逆の位置関係だ。
俺たちが差し向かいになってする事と言えば一つしかない。勇儀の体調も戻ったことだし、そろそろよかろう。
片手で酒瓶を持ち上げて、俺は訊いた。
「やるか?」
勇儀は湯飲みを手にとり、こっちに向かって突き出した。
「もちろん」
俺たちは互いの湯飲みに酒を注ぎ合う。そして、その湯飲み同士をぶつけ合った。
かちんと陶器がぶつかり合う心地よい音。鼻腔をくすぐる芳醇な香り。痺れるような熱さを伴う喉越し。
いつもと大差ない酒のはずなのに、なぜだか今日は全てが最高の物に感じられた。
* * *
酒を飲みながら、勇儀は唐突に訊いてきた。
「……なあ、鬼と人の関係を変えるなんて、本当にできると思うかい?」
少し自信なさげな勇儀の言葉。
無理もないだろう。勇儀のしようとしてることは自分だけの問題じゃないし、力尽くでどうこうできるものでもない。
だが、俺には不安は髪の毛の先ほどもなかった。
燻煙した干し肉を囓りながら、俺は答えた。
「できるだろ。ここにただの人間と鬼の四天王が、顔突き合わせて仲良く酒を飲んでるって前例があるんだからな」
わずかばかり不安に強張った表情をほぐれさせ、間抜けなことを言ったとばかりに勇儀は笑った。
「そういや、そうだったね。……それじゃ、もっと先まで進めるって前例を作っておこうか」
「ほう。そいつはいったいどういう……」
俺が尋ねる間もなく、炬燵の向こうにあった勇儀の顔が迫ってきていた。
勇儀の額の角が俺の耳の下を通り、直後に感じる唇の柔らかくて温かい感触。
なるほど、そういうことなら喜んで協力しようじゃないか。
炬燵の上に身を乗り出している勇儀の腰に両腕を回し、抱え込むようにして後ろに倒れ込むと同時に炬燵から自分の体を引き抜いた。
重ね合った唇を離し、しばし余韻に浸った後、俺は口を開いた。
「こいつはいい前例だ」
「もしも鬼と人の夫婦ができて、そいつが街中を仲睦まじく歩いてるとなりゃ、鬼も人も考えを改めるだろうね」
「そうだな」
鬼嫁は勘弁してくれと言いたかったが、そんな冗談を言ったら殴られそうなのでやめておく。
それはともかくとして、異種族の橋渡しと言えばアレが定番だろう。
俺は馬鹿みたいに真面目な顔を作って、言った。
「……勇儀。いっそのこと、子供でも作っちまうか。愛の結晶となりゃ、問答無用だぜ?」
勇儀も、馬鹿みたいに真面目な顔で答えた。
「悪くない話だね。でも……」
俺たちは二人同時に、台本でもあるみたいに同じ台詞を言った。
「子供ができたら一緒に酒が飲めなくなるじゃないか。だからしばらくは、今の話はナシで」
俺たちは二人して、馬鹿みたいに笑った。
* * *
二月三日、節分。
俺の視線の先では子供たちが升の中の豆を掴んでは『福は内、鬼も内』と、楽しそうに鬼に向かって投げつけていた。
鬼の方もまた、ひゃあひゃあと大げさに喚きながら、楽しそうに逃げ回っている。
俺は地面に落ちている豆の一粒を摘む。
それが生の豆であると知って、俺は無性に嬉しくなった。
新ろだ301
───────────────────────────────────────────────────────────
「「「「「鬼はー外♪福はー内♪」」」」」
節分
--1年の無病息災を願い
災いの元となる鬼を追い出し
福を呼び込むため豆をまく行事
幻想郷でも節分の日には豆はまかれる
ただ現代の世界と違うことは
----鬼が実在すること----
鬼にとって炒り豆は天敵
節分ほど彼女等にとって厄日は無い
「鬼が居たぞー!!」
「どこだぁ!豆投げつけろー!!」
鬼が一匹、追われているらしい
追っ手には炒り豆
鬼がいくら屈強とはいえ炒り豆の弾幕を受ければただでは済まない
死ぬことは無いものの、太刀打ちできず地に伏すことは必至
「うぉおい!?何だ何だ!?久しぶりに地上に出てきたら、いきなり炒り豆かい?
これじゃ、どっちが地獄かわからんぞ!?」
地霊殿で騒動がおきたあの日以降
旧都には時たま人間が紛れ込むようになった
騒動を解決した人間に宴会に来ないか?と誘われ
地下旧都より久しぶりに地上に出てきた鬼-星熊勇儀は不幸にも節分の日に地上に出てきてしまった
まさに飛んで火にいる夏の虫、いや飛んで豆に炒る冬の鬼か(意味不明
「さぁ!鬼め!追い詰めたぞ!!炒り豆でも喰らえぇぇぇぇぇぇ!!!」
「っく!そうはいかん!!三歩必殺!」
鬼より放たれた弾幕は地に当たり土煙を上げた
「うぉぉぉぉ!?」
「(よし今だ!炒り豆相手には逃げるが勝ち!)」
…
……
………
「っクソ!鬼めぇ!何処へいった!?」
「探せ!まだ近くにいるはずだ!」
すでに豆撒きでなく鬼退治と化しつつある節分であった
「……なんとか撒いたか。今日は節分だったのか。ついてないねぇ」
まさに厄日である
--呼んだかしら?厄なら貰う受けるわよ?
--いや及びでないです。
--あら、そう?残念ね
何か居た気がするが気のせいである
「小屋があるねぇ。あそこに夜まで隠れてようか?人が居たらマズイが…」
偶然目にしたボロ小屋。おそらく納屋か何かであろう
妖怪がうろつき、人が居なくなる夜までそこに身を隠すことは出来そうだ。
しかし人が居たら大変だ。それこそ狭い小屋では的である
「居たぞ!あそこだ!」
「っく!?また来たか!一か八かだ。三歩必殺!!」
「クソ!またか!!」
土煙があがっている内に鬼は小屋へと逃げ込んだ。
「ふぅ…危ない、危ない。」
『おや?勇儀姐じゃないか?どうしたんだ?』
「うん?その声は…○○か!?」
『そうだ。俺だ。どうした勇儀。地上に来るなんて珍しいじゃないか』
「いや、前に来た地霊殿の一件を解決した人間に宴会をやると誘われてね。
萃香にも会いたいから久しぶりに地上に来てみたら、いきなり炒り豆投げれてな」
『ハハハ、それは運が無かった。今日は節分だからな。それに宴会は明日だ』
「何!?…まったく、鬼にとっちゃ今日以上に厄介な日は無いよ。」
『炒り豆は鬼の天敵か…さて質問だが』
「うん?なんだい」
『ここに豆がある』
「!!!まさか…お前…!!」
『無論投げるに決まっている』
「お ま え も か!!」
『誰もお前に投げるとは言っていない。そこをどけ』
「は?私に投げないのか?」
『いいから少しどいてくれ』
「あ、ああ。わかった…?」
『まぁ見とけ・・・・福はー外、鬼はー内・・・・ってな」
「それは逆だろう」
『別にいいじゃないか。俺は好きでこういってるんだし』
「…………」
『外、見た限りじゃ、どうやらまだお前さんを探してるようだぜ。
明日まで、ここで休んでいけ。どうせ外にも出られないだろうしな』
「……何か変な事考えてないか?」
『いくらなんでも鬼に手を出すほどの力は持っていない。
……どうせ暇なんだ。酒でも飲むか?』
「お、いいねぇ。ちょうど酒が飲みたかったんだ」
『ちなみに銘柄は「鬼殺し」』
「・・・・・・・・・」
『冗談だ。「水道水」と自家製の酒だ。肴に豆でもどうだ?』
「鬼に豆を薦める奴がどこにいるか。」
『此処にいる。それに炒り豆じゃないから大丈夫だ。』
「そうかい。じゃぁ、飲もう」
小3時間後
『アハハハハハ、それは大変だったな。地獄でそんなことがあったとはな』
「笑い事では無いんだがな。」
『いやいや、スマンスマン』
「そういや、○○。なんでお前は『福は外、鬼は内』なんていったんだ?
他の連中と一緒に騒いだりはしないのか?」
『んん~?それかぁ。
俺はなぁ、こういうときに外で動き回るよりも部屋で静かに本でも読んでたほうが好きなんでね。
少々、俺には騒々しすぎる』
「酒飲みや宴会は好きなのにか?」
『それとこれとは別だ。ああいう席では静かよりも騒々しいほうが好きだ
酒も入って皆とドンちゃん騒ぎするから楽しいしな。』
「へぇ、そうかい。変わってるねぇ」
『鬼のあんたに言われたかぁ、ないねぇ。
ま、実際はあんたのことが好きだから匿ったに過ぎないからな』
「!?・・・なんだって!?」
『・・・・zzz』
「……寝てる」
『んん~、むにゃぁ~、勇儀ぃ~』
「・・・なんだ?」
『…好きだぁ。俺は人間だけどお前が好きだぁ~…zzz』
「!・・・・・・・」
『zzzzz』
「・・・・人間は風邪引きやすいからな。羽織でもかけておくか」
「節分で厄日だったが、
こいつと酒も飲めて、面白いことも聞けて、悪くは無かったな・・・・」
『・・・ぅぎぃ・・・・うにゅぅ~』
「鬼と人間の中も悪くないねぇ。酔ってないときにコイツに問いただしてみるとするかね」
ひとり佇み、己よりも数段弱い者の寝顔を肴に顔の紅い鬼は酒を飲んだ
「明日の宴会には面白い肴と見ものが出来たな…」
新ろだ303
───────────────────────────────────────────────────────────