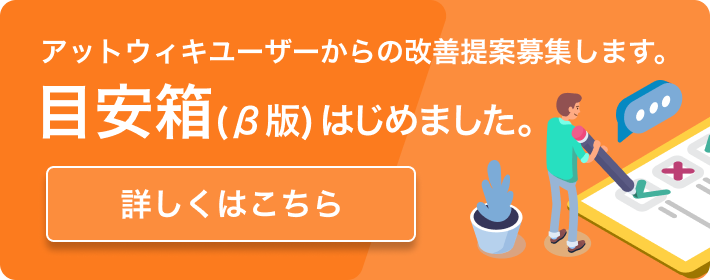紅魔館に私が住みつくようになってから、割と長い時間が経つ。
この図書館の本もそれに比例して、司書の小悪魔がいなければとても整理することができないくらいに増えた。
大多数は魔導書が占めているが、一部には外の世界から流れてきた本も存在する。
漫画、ファッション雑誌、教科書、哲学書、恋愛物の小説。
この他にも多種多様の本がもっとあるのだが、どういうわけか最後に記したやつだけは、あまり他の書物に比べて共感を得ることができなかった。
この館が女所帯であるし、男との付き合いなど無に等しかったからだろうか。
人里に下りれば男は居るだろうが、男と付き合う気はないし、第一外に出ること自体が私の性分ではない。
そんなことをしている暇があるなら、魔導書の作成に力を注ぐほうが遥かに懸命である。
そう思っていたのだ。
ところが少し前にそんな私の考えを一部否定せざるをえない事件があった。
これからその時間軸に戻ったつもりで事件を振り返ってみることにする。
「あ、そこ違いますよ。その本はもっと向こう……え、ちょ、ちょっときゃあああああ」
……またこの音か。
最近になって本の落下頻度が軒並み上昇傾向にある。
原因はそう遠くない日にこっちの世界にやってきた、○○とかいう人間。
行き場を無くして行き倒れになっているところを門番が拾ってきたようだ。
だからいつまで経ってもザル呼ばわりなのよ。
「あー…すみません」
「もうこれで十一回目ですよ…いい加減丁寧に扱うようにしてくださいね?」
「善処します」
「じゃあ早く終わらせましょう。私はもう向こうに戻りますから……」
「わかりました」
最初、私は内心この人間を館に招き入れることをなんとなく拒んでいた唯一の存在であった。
理由は特に無い。誰にだってなんとなくで事を済ませたいときがあるだろう。それと同じことだ。
しかし、私以外の館に住む皆はこの人間を招き入れることを存外嫌でもないと思っていたのだろうか。
ここに身を置いてもよいとレミィがあっけなく許可してしまったのだ。
もっとも私もこの館に住まわせてもらっている存在であるから、とやかく発言できる立場でもない。
そう思ったので私の「なんとなく」は胸の深部に永遠に隠しておこうと決めた。
「おおっ……っと、危なかった」
「むむ」
小悪魔が目を細めて○○を見やる。
どうやら今回も自分が手伝わないと駄目だという事に気づいたらしい。
ここで○○についての説明を入れておく。
種族は先ほど言ったとおり人間に属する。性別は男。
身体的特徴を述べるとするなら、背丈はその歳の平均的な男の身長に比べて少し低い。
性格ははっきり言って気が弱く、自分の意見をこれと言って主張するようなこともない。
もっと簡潔に言うなら、薄志弱行。
顔のほうはまあ、悪いといえば悪いのか、良いといえば良いのかだろうか。
はっきりとしないから、どこにでも転がっていそうな顔だということにする。
聞いたところによれば、そこそこ外の世界に関しての知識を持っているというので、仕事にさせるに当たって都合がよいということでこの図書館に配属させたが……
本を落とす、落下させる、重力に従わせるの美しき見事な三重奏を奏でてみせる。先ほどもその予兆が見られた。
そして挙句の果てにたった一度ではあるが黒白に本を渡してしまったとくる。
黒白には気をつけろとあれほど小悪魔に言わせておいたのに。
次にした音は三重奏とはほど遠いものだった。どうやらいつもの鼠の音だ。
この音で少しばかり気持ちがほっと楽になったのは私だけだろう。
音のした方向が○○が担当している区域に近いところであったから、もしかすると本を渡した真相の片鱗を垣間見ることができるかもしれない。
そんな思いから生まれ出た好奇心が、空気に身を乗せその場所へと急行することを私に命令した。
「よお○○、どうだ? この黴臭い図書館」
私が二人の死角となる本棚の影にちょうど着いたときに、黒白が飄々とそう言い放った。
黴臭くて結構。埃っぽくて結構。喘息持ちではあるが、本の傍に我が身があって、我が身の傍に本がある。
私がそう望んでいるのだから黴臭いだとかはこの際どうでもよい。
「はあ、確かにこの図書館はその……黴臭い…かな?」
○○も黒白の意見に同調する。
「そうだろ? まあそれはどうでもいいんだが」
「また本を借りに来たんですか? 駄目ですよ、今回ばかりは絶対」
「お、○○らしくないな。いつもならあんな事しなくても、押せばなんとかいけるんだが」
やはりいつものごり押しで丸めこんでいたのが明らかとなった。
だが今回はあまりそれが通じないと見て黒白も手を引く。
「小悪魔さんからも散々忠告を受けましたし、パチュリーさんからも目で物を言われて……」
「まあそう固いこと言わず……な?」
私は自らの存在を知られてしまうことを防ぐため、できる限り気配を薄く消散させて影からじっと様子を見ていた。
実の所、私が黒白と○○がこういったやり取りをしているのを見るのはこれが初めてである。
○○が黒白に本を渡したという話は小悪魔から聞いただけで、その時はレミィとのティータイムに付き合っていたから目撃は叶わなかった。
ちなみに○○は私が自分がしでかした失態には気づいていないと思っている。呑気なものだ。
だが今日はいかにもその現場に押さえられそうとあって、実に気分がいい。
何故鼠に本を渡すような真似をしたのか、今にこの目で見届けてやる。
そして、直接この場で○○を問い詰めてやるのだ。
図書館の主である私が言ってやったほうが少しは効能があるかもしれない。
一人そうやって勝手で都合のよい思考を巡らせていると、黒白が思わぬ暴挙に出た。
「なぁ……○○…いいだろ?……」
「駄目…ですってば」
猫撫で声を出しながら黒白が自分の両手を○○へとそっと伸ばす。
間もなく左腕が○○の腰に回り、右手が○○の左頬を弄ぶ。
その身を捩ったり、左腕に力を入れて体と体を密着させたり、押し付けたりしながらどんどん黒白は○○を壁の方向へと追い詰めていく。
○○も黒白の挙動に流されて徐々に自分の体を壁の方向へとどんどん追いやっていく。
あんな事、というのは色仕掛けのことだった。
なるほど口で理解させられないなら体で理解させようという魂胆のようだ。
色気はパワーだぜ! と威勢の良い声が聞こえた気がしたが、気のせいか。
「誰も見てやしないぜ……この前はどこまでいったっけな?」
「魔理沙さん……目的変わってませんか。それとそんな如何わしいことはした覚えはありません」
「私のことはさん付けしなくていい。それに目的を変えたつもりはないぜ」
この黒白、○○を先の戦法で弱らせて本をせしめたとみた。
「う~ん……」
「私のこと……嫌いなのか」
「き、嫌いというわけでは」
「だったらいいじゃないか……減るもんじゃないぜ?」
何故か私はこの雰囲気に既視感を覚えたが、どこで見たかは判然としない。
原因は黒白の痴態と○○の優柔不断、ということがわかったんだからもうそろそろ出てもいいだろう。
あと黒白という表現はちょっと飽きてきたのでこれからは素直に魔理沙とする。
「やっぱり無理ですってー」
「あー? 前はこんなにしつこくなかったのになー。仕方ない、実力行使だ」
「どっちがですか! …ってそれは」
「待ちなさい」
魔理沙が懐からミニ八卦炉を出したのを見計らい、私はそう言って二人の前へと飛び出した。
○○はとうとうやってしまったか、と、絶望をそのまま色にしたような顔色をしている。
魔理沙はやっときたか、といういつもの勝気な表情を浮かべ、○○から少し距離をとってミニ八卦炉を私に向ける。
子悪魔は二人のずっと向こう側の本棚の影で、少し前の私と同じようにそっとこちらの様子を見ている。
にやにやと気味の悪い顔をしている。少しは手伝ってほしい。
「前から忠告は聞いていたはずなのに……こういうわけだったのね」
「いやその……」
「言い訳は聞かないわ」
ぴしゃりと○○の優柔不断を一刀両断してやる。
それを切り口として私は本格的に攻撃の体制へと移る。
「私に無断で、忠告もさせたのに、よりによって魔理沙に本を渡すなんて一体どういう了見なのかしら?」
「し、知ってたんですか……」
「聞いたのよ、小悪魔からね。全部というわけではないけど」
「……申し訳ございません」
「もう遅い」
隠し通せると思っていたのか、私の攻撃に○○は狼狽した。
すぐに謝ってくれたのなら少しくらいは評価を上げておいたのに。
「まあまあ許してやれよ。○○のおかげで以前より本が多く借りれそうなんだ」
「あなたは良くても、私は良くないわ」
「私は良いし、○○だって良いぜ?」
「言わないでください……」
先ほどの情事を思い出しているのか、○○の顔がみるみるうちに赤くなっていく。
魔理沙も相変わらず超然とした態度を変えない。変える積もりもないのだろう。
「兎に角、これ以上何かしでかすなら追い出す以外に選択の余地はないわ」
「結局こうなるんだな。別に嫌いじゃあないが」
「いつものくせに」
「いつものことだぜ」
私は紅魔館に住む以前に幻想郷という世界に住んでいる。
この世界ではいざこざや争いを解決するシステムとして「いつもの」……所謂、弾幕ごっこという画期的な方法がある。
詳しく説明すると非常に長くなるのでここでは省略する。
一言で言うならパターン作りごっこだ、と紅白が言ってたと妹様が仰っていた。
しかし、魔理沙の様に相当の努力を重ねた人間でないと当然弾幕など張れないので、○○にはこの場から退散してもらう。
「○○は危ないから向こうに行ってて」
「え、あ、はい」
「む、パチュリーが他人の事を心配するなんて珍しいな」
珍しくないわよ、と素っ気無くやり返す。
もし怪我でもされたら治療が面倒なだし、死なれても後味が悪いだけだ。
「じゃあデキてるのか?」
その句が魔理沙の口から吐かれた瞬間、急に私の顔の温度が上昇し、懐にしまいこんでいた符を何の策や考えも無しに宣言してしまった。
こうしていよいよ図書館兼私の書斎は戦場と化した。
○○は町を攻撃され必死に逃げ惑う町衆の一人のように、書斎を所狭しと駆け回る。
○○が恐らく初めて弾幕を見たとき、美しさのせいなのか恐ろしさのせいなのだろうか。
その身をまったく動かそうとしないものだから、小悪魔が無理矢理○○を引きずって避難させていたのを今でも覚えている。
それを考えると一人で逃げれるだけでも幾分かマシになったというものだ。
小悪魔はさっきの場所にはもう居なかった。仕事の上乗せとして後で戦場の後始末をさせることにする。
しばらくすると私は流れ来る星弾や、時たまに放たれる極大の光線を避けるのに精一杯になっていた。
精一杯ではあったが無数の弾と光線を避ける合間に、私の頭を何かが掠めているのを自覚した。弾ではない。
戦闘が始まる前に魔理沙が言った言葉――
どうにも落ち着かない。
私の頭は避けるということの他にあの言葉の方にも神経を向けるのを不思議とやめないのだ。
それが仇になったという言い訳はしたくないのだが、いつもよりも早く当たってしまった。
図書館の床にその身が落ちていくのを感じる。
生死をかけた死闘とかそんな大それた戦いではないから、別段重傷を負ったとかそういうことはない。
魔法を使って、ゆっくりと自分の体を埃の少ない床に移動させる。
――そういえば、○○は掃除だけはできるのだった。流石に咲夜には及ばないが……
そんなことはさておいて、もう暫く休憩したい気分だった。
あれから私は意識的に○○を避けていた。
何故避けてしまうのかと、自問自答の日々が続いた。
しかしながら自問自答して答が容易に出るようなら、人も妖も苦労はしない。
理性と思考をあわせ持つ存在は必ず命の紅炎が燃え盛る合間に、幾度と無く何事かに悩みぬくことになる。
そこらに這い蹲る動物にはそんな苦労もないし、理解もできないし、する必要もない。
そんなそこらの動物のことを羨ましいと思う知的生命体はいるのだろうか? 少なくとも私が羨むことはない。
私の職業である知識人という職からしてみれば、悩むというのはなくてはならない絶対要素だからである。
普通の人間や普通の妖怪にもその要素は必要であるが、比重と質が普通の奴らと私とでは全く違う。
とはいえ、やはり悩み続けるというのは職でも辛い。
歌うことを職とする者といえど、四六時中歌いたいとは思っていないはずだ。誰だってたまには休みたい。
よって私もしばしの休息を取るべく、前々から溜め込んでおいた外の本を読み漁ることにする。
こんな時は魔道書を作成したり、まだ手をつけていない魔道書を読んだりするよりも、まずは息抜きをするに限る。
幻想郷に住む者の価値観を覆すような事が大抵の内容である外の本ときたなら、その効果は何乗にもなるのだ。
まったく、こういう時の○○だというのに……私もそうだが、○○もまた私の事を避けているように感じる。
この前は言い過ぎただろうか? いや、そこまできつく言ったつもりは無い。
仮にも図書館の司書……まあ、半分雑用扱いではあるが、それでも私の許可なしに、ましてあの魔理沙に本を渡した?
まったくもって迷惑千万の一言に尽きる。
今後また繰り返すようなら、本当に配属を別の場所へと移してもらうつもり。
誰一人聞いてくれない愚痴を心の中で呟いた後、傍にあった比較的古めの外の本に手に取って開いてみる。
暫く何となしにページをペラペラめくっていくうちにある事に気がついた。
これは……あの共感が得られないとかで他の本に比べて、ところどころ適当に飛ばしながら読んでいたあの恋愛物の小説ではないか。
胸の鼓動に不可思議な加速がかかる。
――最初から、読んでみようか。
読み終わったその時、私の中にあったあの既視感が手に取るようにわかった。
魔理沙が○○に迫ったあの時……
この小説の中盤部分に非常に酷似した場面が書かれてあったのだ。もっとも小説の場合、男と女の立場が逆であったが。
それと、魔理沙が私と戦う直前に言った言葉……これも同じページにその男と女の情事を男の友人が見てしまい、その友人が放ったある一言にもまた似ている。
デキて――
いやいやいやいや、いや。
そんなわけがない。
○○は出来損ないで、鼠にちょっと言い寄られただけで本を渡してしまう馬鹿で駄目な司書。
ただ、それだけである。
「……さん」
元々司書というものは力と知識を持っていることが基本中の基本であって、知識だけあっても力が無ければ本の整理ができない。
注意でどうにかなると思っていたが、ちょっと冷静になって考えれば○○は男のくせにまるで力というものが無かったの思い出した。
この前も咲夜に頼まれて少し重たそうな荷物を運ぶのにいっぱいいっぱいの様子だったことは、私の記憶に新しい。
だから本だってああもばさばさと落とすのだ。
不本意ではあるが門番の所に通わせて少しは体を鍛えさせる必要がある。
「ぱちゅ……さ…」
ああ、今日でもう十三回目か……といつものように嘆いてみるが、少し頻度が下がっていることに気づく。だが落としているという事実に変わりない。
しかしあれでも掃除の方は割と丁寧にやってくれるのだ。この前汚れていない床に着地できたのも、きっと○○が掃除していたおかげだろう。
それとこれとで、プラスマイナス0ということだろうか?
「パチュリーさん!」
聞き覚えのある大きな声をもってして私が我に返ると、いつの間にか本を抱えた○○が真横につっ立っていた。
どうやら自分でも気づかない内に思考の海にその身を投げ出し、盛大に溺れていたようだ。
「パチュリーさん……?」
言葉を返そうとするが、変に意識してしまって上唇と下唇が鉛のように重くなって動かない。
今思うにこれは動かなかったのではなく、動かせなかったという方が正しい。
「聞こえていますか」
「……」
まだ動かせない。
「あの」
「な、なに」
ようやく一言返せた。
「あ、いや、この本の元の置き場所なんですが……今、小悪魔さんが居なくてわからないんですよ」
「見せて」
「どうぞ」
本を手渡された拍子に私の指先と○○の指先が触れ合う。
○○にとってはそれだけだったようだが、私は意外にも大きい○○の指に驚いてしまい、うっかり本を○○と同じように重力に従わせて落としてしまった。
「っ……」
「す、すみません、大丈夫ですか?」
「……別になんともないわ」
落ちた時に付着した埃を払いのけて再び本を手に取る。
○○がこちらを心配そうに見ていて、一向に落ち着かない。
なんだか今は見ないでほしい、このままでは自分の中の何かがおかしくなってしまう。
懇願が○○に届くことはない、しかし届いたら届いたで少し恥ずかしい。
となると、おかしくなる前に○○の目から発せられるこの理解不能な圧力から逃げるより他ない。
その場をなんとか凌ごうとこの意味不明の圧力の防御も含め、本来の目的を果たすことに集中すべく顔を本のほうに向けた。
○○の目にはただ俯いている私が映っているのだろう。
こっちは映されているせいで大分迷惑をしているというのに。
タイトルが目に入ったとき運がよいと言えばいいのか、それは前々から探していた本であることに気づいた。
同時にこの場から逃げ出す方法も思いついたから早速実行に移す。
「この本は……そうね、かなり奥の方だから私が置いてくる」
「置くぐらいでしたら場所を教えてくれれば僕が……」
「いい。どうせまた落とされても困るだけだし」
「はあ」
適当に弱点を突き、○○を弱らせて隙を作る。
追い討ちとしてまだ整理できてないところを引き続きやって、と言って退散させる。
わかりました、と○○もその追い討ちに従って私を探すために通ってきたであろう道を戻っていった。
どうにかこうにか私はなんとか戦線離脱を果たした。
しかしどうして○○が私の目的物を持ってきたのだろうか。
それは偶然としておくにしても、その時の私は逃げることしか頭になかった。
普通なら礼を言うべき立場なのに……それも言えずに飛び去ってきてしまったのだ。
もしかしてレミィの仕業? だとしたら随分と粋な真似をするようになったものだ、今度とっておきのネタを吹き込んでやろう。
そうやってくだらないことを考えていないと、自分の頭が冷静さを失ってすぐに破裂してしまいそうだった。
本の背表紙を指でなぞりながら、図書館の中空を一人行く。
もう何年も触っていない本をなぞると、薄く積もっている埃が丁度真下に居た小悪魔の頭に落下した。
小悪魔がそれに気づいてどのような反応を示したのか、私には今もってわからない。
そのくらい、頭には何の事もなかった。
他の本より少し背が出っ張った本に指がぶつかった時にふと、こんなことが頭に浮かんだ。
何故さっきから私は○○の事ばかり気にしていたのだろうか?
力の無い○○を鍛えさせるには門番の所に行かせるのが都合がいいはずなのに、どうして不本意などと思ったのだろうか?
ずっと○○に呼びかけられていたのに、どうして呑気にあの海で溺れていたのだろうか?
その上私は咄嗟に○○に返答することさえできず、さらに指が触れ合っただけなのに○○と同じように――
極め付けに、○○の視線から大気圧や水圧や電圧の類とは全く異なる奇怪な圧力を感じて、逃げたくなったのだ。
それからはずっとそのことばかりを頭の中でぐるぐると回転させてみたが、解決には向かわなかった。
漸く結論が出たのは、それから三日くらい経ってからである。
私が私自身の気持ちに気づいた時、結論に至るまでの三日間が急に馬鹿馬鹿しく思えてきた。
その馬鹿馬鹿しい三日間でようやく理解を果たした事は認めよう。
しかし、こんなものを一体どうしろというのだ。
誰に聞くともできず悩み続けることしか、私にはできなかった。
───────
やはり○○にも思う節があったのだろうか。
私がその三日間に頭の中で気持ちの揺らぎを回転させている間に、○○は門番の所に通い始めて体力の強化に励んでいた。
加えて最近は要領良く魔理沙を追い返せているらしい。
どのようにして追い返しているのかは私の知るところではないが、兎に角前の様に押し負けることは無くなったようだ。
無くなったとは言ってもやはり先の事件に対して一抹の不安も有ったので、○○に本を渡したかどうか聞いてみた。
○○からは後ろめたい様子を一切認められず「信頼されるように頑張ります」と一言だけ返された。
しつこいと思いつつ後に持ってかれた本がないか確認したが、何一つそのような形跡は無かった。
○○が館にやって来てからそろそろ二ヶ月は経とうかという頃だったと思う。
やはり変わりなくその日も本に喰らいついていた私は突如として「一休みしませんかパチュリー様」と咲夜からの誘いを受けた。
少し休むのに丁度良いだろうと思いその意向を伝えた矢先、○○もどう? という声がした。私はこの意向を撤回するかどうか迷った。
僕も行っていいのですか、と○○が返したとき、更に迷いが強くなって私の気持ちを足踏みさせた。
しかし行くといった手前○○が承諾してから私が断るというのは、何だか私が○○を嫌っているように思われはしないかと考えた。
結局、図書館に居た私達は咲夜に引っ張られるような形で二階のテラスで向かうことと相成った。
三つの影が一緒にテラスに出ると既にレミィが湖の先の先をじっと眺めていた。
暫く外に出ていなかったせいで天頂からの日の光が私には少々痛かった。
「あら、○○も来たの」
心底以外そうに○○に口をきいたこの「レミィ」という者を詳しく説明していなかったので、この場を借りて簡単に説明する。
本名は『レミリア・スカーレット」と言って、その愛称を「レミィ」と言う。
この紅魔館の主でありながら、日の下を歩けない、流水を渡れない等数々の弱点を保有する吸血鬼という種族に属する。
よって今レミィが日光を遮るパラソルの下にその身を置いているということは私や咲夜、○○にとってさえ当たり前の事だった。
○○は少し緊張した面持ちで「咲夜さんにどうですかと誘われたので」と答えていた。
「そう、まあいいわ、賑やかな茶会というのも。そんで咲夜、今日はまた珍しいものが入っているのよねぇ」
「ええ、貴重なものですわ」
「何を入れてるのか知らないけど……あんまり苦いのはよしなさいよ。この前紅茶にどれだけ砂糖を入れたと思ってるの」
私が不満を訴え出てすぐに、この前の紅茶って何ですか、と○○が不意に私に聞いてきた。
何もこんなときに口をきかなくったって良いのにと大いに焦ったが、今度はレミィが前の紅茶に対する不満を訴えでて私はそれを答えずに済んだ。
「確かにアレは酷かったねぇ。一体何を入れたのよ」
「魔法の森に生えていたキノコですわ」
「ちゃんと味を確かめてからいれてよね。それと、今度からはそういうのは少しは控えめになさい、咲夜」
「そうですか、ではまた福寿草でも……」
「それだってもういいから!」
福寿草の茶というのは飲んだことが無いのでその味について明言はできないが、レミィの様子からして避けて通りたい味のようだった。
それから咲夜の言葉に今日の茶は福寿草の茶ではない意を汲み取り、安堵した。
そんなものが入れられた日には本の数がいつもよりやたら減っていた時と同じ心持でその日を過ごす羽目になるに違いないのだ。
話が別所に飛ぶのだが、レミィを媒介にして咲夜を困らせているのは、時たまに私だ。
主の命令に方々を駆け回る忠実なメイド長は犬と評しても差し支えなく、その様は真に愉快である。
ただし以前猫度を測定したところ、非常に残念な程度のものであったのでそこは改善の余地が有ると信じ今後に期待する。
冷めないうちにと、カップの中の液体を口にそっと注ぎ舌の上から鼻腔全体に香りが充満した時、思ったとおりというか、瞬時に上に表した心持になった。
私は、これは私とレミィと○○への当て付けなのかという非難の意を込めて、なるべく鋭利な視線を咲夜に送りつけた。
レミィもカップを受け皿に置いたなり、じとりとした目で咲夜を睨んでいる。
当の従者は平生通り澄ました顔で佇んでいる。
○○は美味しいです、と呑気なことを言っている。
すぐ私は○○の味覚を疑ったが、これは後から咲夜が○○の分だけ別に普通の紅茶を入れていたからであった。
どんな仕返しをしてやろうかと思い、それは次の猫度測定はずっと厳しくするということで収まった。
「ところでパチェ」
一段落落ち着いたところで不意にレミィが問いかけてきたので何と返してやった。
「何?」
「○○はどうかしら。ちゃんと司書の仕事をやってるの?」
レミィにしては自分がここに住んでもよいと許可した人間が今どんな様子だろうかと、一番○○に近い存在に何となく聞いただけだろう。
私にとってはそれは口に含んだ紅茶を弾幕の如く、それも高密度のものをテーブルを挟んで向かい側に居たレミィの顔面と胸あたりにぶちまけるくらいの不意打ちでしかなかった。
と言うか、そういうことは直接○○に聞いてほしいのだが。
「ちょっとパチェ!」
「……げほ」
お嬢様、すぐにお着替えを…、と言いながら咲夜がレミィの顔についた紅茶を丁寧に優しく拭きとる。
一人で着替えるから咲夜は紅茶を片付けて掃除でもしてなさい、とレミィも言い返す。
その言葉を聞いた咲夜はちょっと驚いて見せたが、またすぐ元の調子に戻ってしまった。
○○は私が吹いて以来咳が止まらないのを心配して、大丈夫ですかと懸命に背中を摩ってくれた。
私が喘息持ちで呼吸器が少し弱いということは○○も前から知っていたので尚更心配してくれたのだろう。
少し楽になったところで口が軽くなっていることに気づいた私は○○に感謝の意を伝えようとしたのだが、何を思ったか○○は咲夜に習って私の口を拭こうとしだした。
私の抵抗感からかそれぐらい自分でやれるという意を込めて、手で○○を制しておいた。
本当はその、してもらっても悪い気はしまいと思ったのだが、状況が状況であるからもしかしたら精神が振り切れてもおかしくはなかった。
しかし今にしてみればちょっと勿体無いことをしたと思う。
「かしこまりました。すぐに着替えてくださいよ? ほっとくと中々洗い流せないんですから」
「ああもう早くいったいった……ほら、ぼーっとしてないで○○も早く仕事に戻れ」
「僕もですか」
お邪魔虫のように咲夜と○○を追い払ったレミィを見て私は嫌な気分になった。
嫌な気分というのは主が従者の心配を余所に置いて、一方的に追い払ったことが原因として生まれたものではない。
私にはレミィの発した言葉の片々から、席を外せと咲夜や○○に伝えようとする意を感じたのだ。
何となくではあるがどうせ○○のことだろう。触れたいことであると同時に触れたくないことでもある。
こんな失態を犯してしまったことに私は後悔した。
「さてと、パチェ。覚悟はいいかしら」
従者と紅茶と○○が去ったテラスにはもう二人しか居なかった。
パラソルやテーブルや二つの椅子は在って無いような背景と化していたと言っても差し支えない。
「……何の、覚悟かしら」
「ふふ、とぼけても無駄よパチェ」
何もかもを知ったような顔でにやりと笑うレミィの顔にはカリスマと呼ばれる由縁が確かに存在した。
しかしそれはあくまで今まで会ったことのない存在に対してだけ効力が発揮されるのであり、レミィとある程度の気心が知れている者にとって何でもないこともまた確かであった。
いつも隣に居る咲夜などは尚更だろう。
「もう隠すのは無理みたいね。いいわ」
「そうそう最初からそうやって素直に話せばいいのよ」
「別に話すつもりではなかったのだけれど……」
「ぶふぅ」
「こらっ」
私の失態を真似するおどけた友人を見て、僅かながら気持ちが楽になった。
私はその時包み隠さず一切を話してしまう心持でいた。
だが本人に想いを直接伝えるわけでもないのに、あの重さがまた私の口を鈍らせるのだ。
レミィはゆっくり、落ち着いてからでよいと私の心に鎮静を施してくれた。
しかし喘息とは違う類の苦しさは、顔についた紅茶と同じようには拭いきれなかった。
なんとか平生の気持ちを取り戻せた頃には日は少し西へと傾いていた。
「――とりあえず単刀直入にまとめると『○○が好き』、と」
「……う、ん」
「パチェ」
「どうしたら、どうしたらいいのかしら」
友という存在に言った手前、もう後戻りはできなかった。
近いうちに私に決着がつくというのは薄々ながらこの日に感じていた。
レミィからは「あんたには押しが足りない」と言われた。また「積極性がない」とも言われた。
途中レミィがばんとテーブルを叩きながら叱るような調子で私に物を言っていたのも覚えている。
私は十分消極的よ、と言われっぱなしでは腹が立つから少し強がりを見せたが、その強がりはさらに自身を追い詰める羽目になった。
「それが駄目、と言ってるのがまだわからないのかしら?」と言われたとき、私はついにレミィに白旗をあげてしまった。
それは、その言葉に対抗できうるものを自分の内に持ち合わせていなかったためである。
外側は取り繕って見せても内側では自分に十分な積極性がないということを深く認知していたからである。
徐々に自分が情けなくなっていく様は、レミィには私の体が段々と縮こまっていくように見えたかもしれない。
「レミィ……私」
「言いなさいな」
私は心の薄膜を突き破ろうとする何かを外側から必死に抑えつけていたのだが、とうとう薄膜を突き破って私の口からあふれ出てしまった。
ついに私は私以外の存在にその何かをぶつけた。
この想いを自覚してから、四六時中○○のことばかり考えてしまい、読んでいる本の内容が何一つ頭に入らないこと。
○○に声をかけられた時、胸がぐっと握り潰されそうな圧迫感に襲われ、それに影響されて口が動かず返事一つ返せないこと。
最近では○○の姿を見ただけでも、体の芯から言い知れぬ熱が湧き出し、瞬く間に全身、特に顔の方に回って自らの自由を奪うということ。
レミィはその不安を遮ろうともせず、ただ黙って受け止めていた。
そのとき私は確かに目が著しく濡れていたことを記憶している。
しかしとうとう自分以外の誰かにこのことを話してしまったのは、非常に気が楽になってしまって、私にとって良い方面に向かっているらしかった。
「重傷ね」
レミィは呆れたよという調子でそっけなく言ってのけた。
「想っているだけでは、その気持ちが伝わらないのは、わかりきったことね」
「……そう」
「それに○○の想い、というものあるだろうからねぇ」
そう言ってにやにやしながらレミィは私の顔を見た。
そのにやにやが何を意味をしているのか、私にはちょっと理解できなかった。
実際○○が誰を想っているのか、はたして誰を何とも想っていないのか判然としなかった。
○○はそういう素振りは見せもしなかったし、また思わせもしない人間だったのである。
「恐らくさ、パチェは私にこの事を言ってくれた時、すごく、楽になったと思うのよ。違う?」
「違、わない」
「……○○に言えるようになれば、もっと楽になれると思うのだけれど」
それが出来ればここまで言うことはないのだ、と言い返そうと思ったができなかった。
レミィだって恐らくは本気で私のことを自分なりに気遣っているに相違なかった。
あの下品な振る舞いだってきっとその目的を達しているに相違なかった。現に私の気持ちの凝りはきっと解れたのだから。
そしてそういうことはレミィと友人になって以来、互いに大なり小なり覚えているものや忘れているものも含めて多々あったことなのだ。
その友人の気持ちを無下に扱うことは、私は絶対に避けたかった。
レミィはまたこう続けた。
「それに今のパチェは一人ではないわ、パチェが私に伝えてくれたから、私もパチェの背中を押してあげられるのよ。
加えて私達は一つ屋根の下で暮らす家族だと、踏み込んで言っても言い過ぎではないと思うの。
パチェが困っている時は私が助ける。だから私が困った時は、パチェが助けて」
目の前の友が、とても悪魔には見えなかった。そうして私ははっとさせられてしまった。
もう随分この友と付き合ってきたはずなのだが、家族という言葉を聞いたのはこの時が初めてだったからである。
私はレミィが単なる知識人として私をこの館に置いているのではなく、一人の家族として置いてるのだとその言葉で強く実感を得た。
私の心に以前とは全く正反対の性質が帯びていくのを感じた。
「ありがとう、レミィ」
私は礼を言った。言わなければどうしても私の気が済まなかった。
礼を受け取ったレミィはちょっと頬を朱に染めて照れくさそうにそっぽを向いた。
「もう、今更いいわよ、どんだけ付き合ってると思ってるの」
「でも……」
「あーはいはい湿っぽいのはこれで終わりよ、こういうのってあんまり好きじゃないのよね」
レミィはそう言って椅子から降りた。
まあ近いうちにそういう機会が回ってくるよと、よく要領が掴めない言葉を残した後、パラソルで日光を遮りながらそそくさと館の中へ戻ってしまった。
しばらくしてまた宴会が行われる旨を魔理沙が伝えにやってきた。
その後○○を前と同じように同じ理由で誘っていたようだったが、失敗に終わったらしく「やはり守備が硬くなっているな」と一言漏らして帰っていった。
身体を鍛えることは精神を鍛えることにも通ずると言うから、体力強化の成果は少なからず出ていたらしい。
しかしいつも間にかごっそり開いた本と本との間隔を見たとき、私はため息すらでなかった。
宴会という場は正しく幻想郷において人と妖とが等しくなる場に相違なかった。
酒を飲むという共通の事項を通して分け隔てることなく、散々どんちゃん騒ぎを起こすのだ。
そうして誰も後片付けはしない。無論私も。
そんなことは紅白が担うという事が常識として私達妖怪の精神に染み付いているからである。
準備に関しては咲夜が度々手伝っているようであったが、それ以外は知らなかった。
宴会場は大体博霊の神社と決まっている。
紅魔館からはレミィ、咲夜、私、そして今回は○○も付属してきた。
図書館に居てばかりで、まだ幻想郷そのものに慣れていないんじゃない? というレミィの言が連れてきた理由だった。
実際○○はここに来てから宴会というものにまるで参加しなかった。
不参加の理由は咲夜の言によると、○○は相当の下戸であるということらしかった。
ある日の夕食の料理に多少の酒が残っていたらしく、それを食べて暫くした後○○が咲夜に休みたい旨を伝えたそうだ。
その料理は酒を残すことが普通で、これは咲夜の間違いではないことを付け加えておく。
宴会が○○にとってあまり良いものでないことは、恐らく咲夜が一番わかっていたのだろう。
妖気と酒気が入り混じる混沌の空間が間もなく境内に生まれた。
天狗が酒を浴びるように飲み、それに負けじと鬼も両手に酒瓶を持って口にどばどば流し込む様を見て、よくもまあやるものだと私は感心しなかった。
その二つの酒豪のみならず、ここに集う者殆どが決まって酒豪だった。
当の○○は飲めや飲めやと酒瓶を押し付けられたり、お前この中の誰とだったら付き合う、などと幾多の妖怪に散々からかわれていた。
もっと積極的な妖怪からは大胆にも甘い言葉と共に背中から抱きつかれたりしていた。
○○は顔を真っ赤にしてどうにも動けなさそうで、また満更でも無さそうな表情も浮かべていた。
その時私は少々の妬みと羨みが心から染み出たことを告白する。
宴会をしていると時間に対する感覚が麻痺してしまうので何時の事だったかは覚えていない。
だが少し疲れた様子とふらふらの千鳥足で○○が私の元へとやってきたのは確かなこととして覚えている。
暫く歩いて私の座っている椅子から丁度九十度の位置にあった椅子に座り、そのままぐったりと用意されたテーブルに突っ伏してしまった。
「皆さん、お酒に強いですね……」
独り言のように漏れたその言葉から何となく私から何か返して欲しいという気を感じ取った。
私はその時例に漏れず酒を飲んで少々高揚した気分であった。
その時だけは○○に対してだけ発生する口の重みはまったく感じられなかったように思う。
「ええ、そうね」
「パチュリーさんももう随分飲んだのですか」
「こういう時くらい、私だって本を読まず酒を飲むわ」
「そうですか」
「貴方、相当の下戸のようね、咲夜から聞いたわ」
「情けないです。お嬢様から強く言われなければまたずっと館に居残るつもりでした」
「たまには悪くないわよ? 別にあの天狗や鬼みたいにがぶがぶ飲まなければいけないということはないの。
自分の調子で飲めれば、宴会も楽しいものになるわ。まあ簡単に妖怪からからかわれるような貴方では無理でしょうけど」
「パチュリーさん、一緒に飲みませんか」
「どうして貴方と」
私と○○がこんな軽い調子で話ができたのは想いを意識しだして以来初めてのことだった。
自分の力ではなく大方酒の力によるものだろうが、私は嬉しかった。
私は、急に私と飲みたいという意見を突き出され、それを反射的に断りかけてまた悩んだ。
悩んだ裏側に杯を共にしたいという気持ちががあったのは楽に知れることだろう。
「私と飲んだって何も面白くないわよ。向こうで飲んできたらどうなの」
「構いません。私はパチュリーさんと飲みたいです」
「勝手にしなさい」
「……」
「何ぼーっとしてるの。飲むんでしょう? 早く注いで」
「はい、パチュリーさん」
かくして境内の隅っこで私と○○は酒杯を交わすことになった。
細かなことまでは覚えていないが、色々と話し込んだ気がする。
○○が幻想郷に来る前に向こうの世界で何をしていただとか、図書館の本が多すぎるという愚痴や、
小悪魔が度々仕事をサボっているという告げ口や、自分には好きな者がいるということも聞いた。私も○○に同じ旨を言ってやった。
その時誰が好きであるかという事は互いに話さなかった。
今までよくわからなかった○○という存在が、一層近くに感じれるきっかけであったと私はこの日の宴会に感謝している。
限界が来たのか、もう私が話しかけても○○は返事を返さなくなった。
安らかな面持ちで何の夢を見ているのかもわからない想い人の顔を見つめていると、突然火照った○○の頬を触ってみたい衝動に駆られた。
いつもの宴会以上に酒をかっ喰らっていた私はやはり気がおかしくなっていたのだ。
私は自分が座っていた椅子から降りて○○の体にぶつけない程度にその椅子を押しやった。
そうしてまた椅子に座って、○○の顔を覗き込んだ。
これほど近くに顔を見るのは初めてのことで、普段の私なら即時その場を逃れるように離れただろう。
暫くじっと見つめていたが寝息以外の変化を見せる様子がなかったのでついに頬を触ってみることにした。
最初は軽く触れる程度であったが、徐々に私の中の私が抓れだとか指で押せだとかいらぬ言葉を吐いてきた。
仕方ない、とそれに従って抓ったり押したりしていると、意外にも餅肌であることが発覚した。気持ちがよい。
調子の乗り出したもう一人の私が小さく「接吻」と呟いた時、私は吃驚して椅子から盛大に転げ落ちてしまった。
その音に気づいた○○がうぇええと奇怪な声を上げてすぐに転げた私を見、慌てて私を抱き起こした。
別の私の呟きと抱き起こされた事とで頭が回転せず、○○の呼びかけがすっかり左耳から右耳へと抜け出ていた。
近くから一部始終を見ていた妖怪からはやっぱり出来上がっていたかだとか、けしからん向こうでやっとけなど滅茶苦茶なことを言われてしまった。
○○は終始戸惑った様子と苦笑いでそれに答えていた。
私は何も言えなかった。
気がつけばもう空は明るさを取り戻しかけていた。
あたり一面は宴会の遺物が散乱しており、紅白がうんざりした顔で隅の方から片づけを始めていた。
レミィがもう帰ると言い出したので○○と咲夜は片付けの手伝いを切り上げて、私とレミィの元に駆け寄った。
その時突然レミィが「じゃあがんばって」と意味不明な応援句を私に向かって言い放ち、咲夜と共に超速度で館の方へ向かってしまった。
○○は唖然としてもう点になってしまった従者とその主を目で追っていた。
ようやく私はそういう機会、ということを今に自覚した。
隣に居る人間に私達も帰りませんか、と言われたとき、友の言葉を思い出し私は強くその人間の目を覗き込んだ。
少しだけ待ってと言って、私は俯いて高ぶる気持ちを必死に押さえつけた。
朝の涼しく静かな風が私を優しく撫ぜていく。
その風はどうだ、と私の心に問いかけてから何処かへと流れていった。
その風に行く着く当ては無いだろうが、私には有る。
やるべきことは、もうとっくに決まっていた。
うpろだ1344、1383
───────────────────────────────────────────────────────────
ある日の紅魔館の一室で、俺はメイド長と一緒にいた。
「しかしまたなんでこんなものを」
「お嬢様たちのおやつに作ったのよ」
目の前には小鉢に入れられたマロングラッセが数個。
「それを何で使用人が?」
「さあ、なんででしょう。何でだと思う?」
軽いクイズを出され、目の前にあるものをまじまじと見つめる。
小鉢の中は彩り豊かで、形も凹んでいたり穴が開いていたりと様々だ。
「ああ、不出来なのはお出しできないからですか」
「そういうこと。お嬢様や妹様のおやつになれるのは綺麗なものだけよ」
言いながら咲夜さんがフォークを渡してくる。
「後は味見と毒見ね」
お嬢様に毒なんて効かないんだけど、と言って咲夜さんは笑う。
それに釣られて俺も笑う。毒を混ぜたことがあるのかと戦々恐々としながら。
「いい感じに甘い……いやだいぶ甘い」
「少しシロップが濃かったのかしら?」
口に放り込むとパリと言う音と一緒に、栗の外の糖が割れる。
外の砂糖と共に栗の甘さも口に溶け出し、紅茶がないと少しつらい。
「まあ、これくらいなら許容範囲でしょ。お嬢様方は甘いもの好きだし」
そう言いながら咲夜さんは紅茶を口に含む。
すぐに口に含むあたり、やはり相当甘いと感じたのかも知れない。
「咲夜さーん、頼まれていた本持ってきましたー」
「ありがとう。そこのテーブルにでも置いておいて」
館内のことと図書館のことで多少話し合っていると、小悪魔がやってきた。
数冊の革表紙の本をテーブルに置くとこちらにさらに近寄ってくる。
「おいしそうなの食べてますねえ」
「心配しないでも後でパチュリー様の分と一緒に持っていかせるわよ」
どうやら関心があったのは今日のおやつだったようで、自分の分もあると判ると歓声を上げている。
「お味はどうなんです?」
小悪魔が期待するような目でこちらを見る。
咲夜さんは我関せずといった体でやはりこちらを見ている。
ため息をつきながら小悪魔の口の中に栗をひとつ放り込む。
すると満面の笑みを浮かべながら小悪魔はそれを咀嚼し、口直しに俺の紅茶を少し飲むと礼を言って出ていった。
「あなたも大変ね」
こちらもため息混じりに咲夜さんが言う。
俺は何も言わずに紅茶を口に流し込んだ。
「パチュリー様、三時の紅茶とお茶受けです」
図書館に紅茶とお茶菓子を運ぶのは日々の日課だ。
妖精メイドが粗相をしては面倒だし、メイド長はお嬢様方の世話をしているのだから、当然とも言える。
「今日のお菓子はマロングラッセです」
テーブルにポットなどを並べながら言う。
普段なら最低限本から目を離しこちらに目をやるのだが、今日に限ってはぷいと向こうを向いたままだ。
それを特に気にせず砂糖壷を掴み何杯入れるかを聞くが、やはり返事は無い。
「パチュリー様、どうしました?」
返事は無い。どうにも機嫌が悪いようだ。
「なあ、今日何かあった? 白黒の来襲とか」
「いいえ、今日は誰も来客はありません」
不満の原因を探るべく、そこらを歩いていた小悪魔を捕まえて尋ねる。
「じゃあ、何か今日のおやつでパチュリー様に言った?」
そう問いかけるとすぐに返事が返ってきた。
「ええ、ひとつ食べさせてもらいましたが、甘くておいしかったですよ、って」
言動に何も不審な点は見当たらない。
「それ以外には?」
「特に何も。あとは咲夜さんの部屋に行ったらあなたが居た、ってことくらいでしょうか」
「確かに特に何も無いなあ。なら、不満の原因は別のところに……」
ここでハタと気付く。さっき小悪魔はなんて言っていた?
「もらったじゃなくて、食べさせてもらった?」
「ええ、そうです」
小悪魔が小悪魔らしい笑みを浮かべる。
「それで機嫌が悪いのか」
「パチュリー様にもおんなじことをして差し上げないと、きっと機嫌は直らないでしょうね」
「だろうね」
頭を抱えながら振り返るとパチュリーが見ていた。
「パチュリー様どうぞ」
フォークに一粒栗を突き刺し、口の前に差し出す。
しかし一瞥しただけで、またそっぽを向いてしまう
「小悪魔と同じようにしてくれないと食べないわ」
パチュリーが小さな声出つぶやく。
小悪魔の方へ向き直ると、やはり笑いながらこっちを見ていた。
フォークを置いて小悪魔に近寄ると、小悪魔は抑えてと言う風なジェスチャーをする。
「パチュリー様になんて言ったんだ?」
声を押さえ気味に、つまりは怒りを隠すように言う。
「食べさせてもらったって言っただけですよ」
小悪魔は笑いながら答える。
「じゃあ、どういう風に食べさせてもらったって言ったんだ?」
また尋ねる。小悪魔はやはり笑いながら言う。
「聞きたいですか?」
その笑みからおよそどう言ったのかがわかる。
「いや、やっぱいいや」
「指でつまんで、優しく口の中に入れてもらって、指についた砂糖は綺麗に舐めて……」
「だからいいって言ってるだろうに」
全く口移しといわなかっただけまだましとはいえ、この悪戯娘には本当に困る。
「この悪魔め」
「いいえ、小悪魔です」
小悪魔は平然とした顔で返してきた。
「ほら、早く戻らないとパチュリー様怒っていますよ」
振り返ると、こちらを凝視しているパチュリーと目が合う。
彼女は目を逸らそうともせず、ただこちらを睨め付けていた。
「パチュリー様お口開けてください」
栗を一粒つかんで、子供をあやすように言うと、パチュリーは少し見た後、口を開けた。
開けた口の中に、恐る恐るといった体で栗を入れていく。
何分少ししか口を開けないし、一粒入るとも思えないので、適当なところで噛み切らせないと息を詰まらせてしまうだろう。
ティーカップを見ると量も色も変わっているので、こちらには手をつけているらしい。
二口目で一粒全部を食べ終えると、パチュリーはカップに手を伸ばし一口二口紅茶を飲んだ。
その間に指を拭いてしまいたかったのだが、パチュリーの空いたほうの手で抑えられているのでそれが出来ない。
振り解こうと思えば、それは容易く出来るのだがそうしてしまうわけにはいかなかろう。
紅茶を飲み終えると、パチュリーは親指と人差し指を順繰りに口に含み、指についた砂糖を舐めとっていった。
こそばゆい上に噛まれるかも判らないので怖いのだが、言っても止めてはくれないだろう。これは意地のようなものだ。
考え事をしていると、袖を引っ張られ次の催促をされた。
テーブルの上においた腕を動かし二粒目を摘みあげようとする。
とここで気付いた。卓の上に肘を乗せるのは、いかにも行儀が悪い。
皿に伸ばした手を引っ込め、椅子から立ち上がる。
「こっちの方が食べさせやすい」
顔に疑問符を浮かべるパチュリーを持ち上げると、彼女の座っていた椅子に座る。
抱えていたパチュリーを膝の上に座らせると、二粒目を手にとり口元に近づけていく。
空いた左手で頭を撫でてやると、パチュリーは気持ちよさそうに目を細めた。
半分をかじると、パチュリーが小声で言ってきた。
「今日の仕事はもう終わりにしていいわ。だからパチェって呼んで」
早上がりは度々あったが、今日は特に早い。
「はいな、パチェ。紅茶のお代わりは?」
「いいえ、まだいいわ」
二粒目の残りを口中においてやり、言う。
仕事が終わった途端にフランクになるのは仕方が無い。こういう性分だ。
「それよりあなたも一つどう?」
「いや、俺はさっき味見したしいいよ」
「そう? これもおいしいわよ」
咲夜のことだから歪んだのしか出していないでしょうと、言いながら一粒手にとる。
それを口に半分咥え、差し出すように顔をこちらに向けて突き出した。
顔を真っ赤にしている様をじっと見てやろうかという悪戯心もでたが、やめておく。
せっかく直してくれた機嫌をこんなことで損ね、天国を失うわけにはいかない。
ゆっくりパチェの口に顔を近づけ、栗を攫う振りをしてパチェの舌を攫った。
ちなみに妙をした小悪魔の分は没収しようとしたが、いつの間にかすべて平らげられていた。
うpろだ1408
───────────────────────────────────────────────────────────
「ふぅ、此処の冬は寒いなぁ」
真っ暗な廊下を蝋燭の明かりを頼りに歩いた
外は雪が降っているようだ、暗いので良くわからないが
吐く息が白くなる、窓は風でがたがたと音を立てている
「ん?」
咳き込むような、声のような
少し先の部屋から明かりが漏れていた
部屋の中をのぞいてみる
誰も居ない?
いや、背中を丸めて小さくなっている、誰かが
「大丈夫ですか?」
少女は声に振り向き、辛そうな顔を見せた
「貴方は確か・・・」
「○○です、先週から此処でお世話になってます」
少女、たしかパチュリーとか言う魔女の人だったと思う
「パチュリー様、苦しそうですが」
「ただの喘息よ、寒いとね」
喘息か、なるほど
俺はパチュリー様にしばし待つように言って、厨房に向かった
「お待たせしました」
お盆に魔法瓶やら何やらのせて部屋に戻った
彼女は相変わらず苦しそうだ
「それは?」
「お茶です、あったかいの」
「ありがと・・・」
「沢山飲んでください、その方が良い、それと・・・」
俺は自分のポケットからあるものを取り出した
「・・・なにそれ?」
「喘息の吸入器ですよ、此処をこうすると―」
彼はそれから背中さすったり新しくお茶を入れてくれたりと、私を看病してくれた
「・・・ありがと、だいぶ良いわ」
「みたいですね・・・じゃあ俺はこれ片付けて見回りに戻ります」
そういって部屋を出ようとする彼
私はそれを呼び止めた
「○○・・・ありがとう、助かったわ」
「・・・苦しいときは何時でも呼んでください、少しなら力になれるかもしれません」
彼は、一応置いて行きます、と言ってさっきの薬を置いていった
「・・・○○か」
その晩、私はゆっくりと眠る事ができたらしい、気がついたらお昼過ぎだった
しかもちょうど起きたときに、彼が居たのだ
「あ、おはようございます」
「○○?おはよう・・・」
何で彼がいるのだろう、まずその疑問が頭に浮かんだ
「いえ、心配だったので何度か見に来たんですが、ぐっすり眠ってらっしゃったので安心しました」
そう答える彼、つまり眠ってないのでは?しかし疲れた様子もなく、微笑んでいた
「あ、パチュリー様、おはようございます」
廊下を歩いていると咲夜に会った
「ご機嫌ですねパチュリー様」
自分でも良くわかる、今私は機嫌がいい
「ええ、好い事があったの」
「それは良かったですね・・・それで何があったんですか?」
「秘密よ・・・それより、レミィは部屋にいる?」
「はい、いま紅茶をお持ちしたのでまだいらっしゃるかと」
咲夜に礼を言って、レミィの部屋まで足を運ぶ事にした
部屋の前に立ったとき、ちょうどドアが開き、レミィが出てきた
「あ、パチュりー、ちょうど良かったわ、今からお茶するんだけど一人じゃ寂しいから、付き合って」
「良いわ、ちょうど貴女に話があったの」
それで話は?彼女の視線がそういっていた
レミィはおそらく茶会に相応しい暇を潰せる話を求めたのだろうが
残念ながら渡しにその手の話のボキャブラリーは存在しない
「○○っているじゃない」
「ええ、いるけど・・・彼が何か?」
「彼、私に頂戴」
レミィは少しだけ考えていた
そして
「いいけど・・・頂戴って言われると急に惜しくなるわね」
「ふふ、そんなものよ、なくなるからこそ愛おしいんじゃない」
「・・・それで、なんで彼?」
当然の質問だ、昨日の晩まで彼とは話した事などなかった
そう、一目ぼれだ
いやちょっと違う、だが、弱っているときは、やさしさが沁みるのだ
「気に入ったのよ、彼が」
レミィは何か納得したようで
ニヤニヤしながら紅茶を飲んでいた
「なによ、気味悪いわね」
「いや、だって貴女が・・・一個人を、しかもただの人間を気に入るなんて、珍しい」
私だって元人間だ、そういう感情を持ったりもする
だがレミィは違う、彼女は生まれついての、化け物なのだ、しかし・・・
さて、お茶もなくなったし、図書館に戻ろうか
「それじゃあレミィ、私は図書館に行くわ」
「そう、それじゃあ○○には私から伝えておくわ」
「レミィ、貴女にもいつか・・・素敵な出会いがあるわよ」
「なに、それわけ解んないわ」
「だってここは幻想郷よ?何が起こっても不思議はないわ」
だって私でさえ、こんな少女のような恋心を持つぐらいだ
「ふぅん・・・じゃあそれを楽しみにしてるわ」
私はそれを聞いて、扉を閉じた
私は彼をもっと好きになりたい
そして彼には私を好きになってほしい
まぁあってまだ二日だ、あまりあせるといい結果は出ない、魔術と同じだ
とりあえず、図書館に行って恋愛について書かれた本でも探してみるとしよう
うpろだ1491
───────────────────────────────────────────────────────────
※注
本作品はまとめのパチュリー7、10スレ目96(1)
およびパチュリー6、10スレ目286(2)に連なる話です。
~Day Of The Scarlet Halloween~
図書館へ戻る為に廊下を歩いていると、聞き慣れない三つの声に呼び止められた。
「お菓子くれなきゃいたずらするぞーー!」
振り向いた視線の先には、両手をつきだしてお菓子を催促する3人の女の子がいる。
どうやら妖精の様だが、この屋敷では見ない顔だ。
ストレートのロング、縦ロール、セミロング……いや、これはセミショートというやつか?
幻想郷の女性の法則なのか、この子達も他の例に漏れず、揃いも揃って可愛らしい。
ただ、小さ過ぎるのが難点か。
人間で、尚且つもう少し年齢を重ねれば、良い女に成長するだろう。
他の妖怪でも成長はするのだろうか?
好みを言うなら、ロングの子。
だが、この子がどれだけ良い女になっても、パチュリーを超える事は……
「無いな」
考えた事の最後だけ、無意識に口を衝いて出た。
前述した通りの意味なのだが、そんな意を彼女達が汲み取れる筈も無く、
「え~っ、無いの?」
「今日はハロウィンとか言う日なんでしょ?」
等、先の発言に対する返答だと勘違いした非難が飛んでくる。
あながち間違っていないせいもあり、苦笑しか出てこない。
「悪いな。 俺はお菓子を持ってないけど、厨房に行けばもらえるかもしれない」
どうやって美鈴がいる門を抜けてきたのか等、幾つかの疑問はあったが、それは口にはしない。
失礼な事を思ってしまった侘びでもあったが、何より、特に興味も無かったからだ。
最大の疑問は、パチュリーに訊けば解決するだろう。
道順を教えてやると、三妖精は軽く礼を言って駆け出し、廊下の奥へと消えた。
咲夜さんに、お菓子ではなくナイフをもらう可能性は、一応侵入者だという事もあって、あえて伏せておく。
良心の呵責を感じはしたが、彼女達の無事を祈りつつ、俺も再び図書館に向かって歩き出そうと、進行方向へ向き直すと
「見ましたよ~」
怪しい笑みを浮かべた小悪魔の顔が目の前にあった。
「何をだ?」
「ふふふ。 全部です」
真剣な問いに返ってくる、はぐらかした答え。
明らかに楽しんでるな……。
嫌な予感を感じつつ、問答を続ける。
「具体的には?」
「あの子達を見ながら、何か考え事をしてましたね?」
「……」
勘というのは、どうして悪い方ばかり当たる物なんだろう。
確信に満ちた物言いに、しらを切り通すのは無理だと判断して言い訳を始める。
「ただ、成長すれば良い女になるだろうなと思っただけだ」
「思ったんですね?」
「男っていうのは、そういう事を少なからず考えちまうものなんだ。 だから……頼むから黙っててくれ!! 後生だ!!」
小悪魔は、余計に口をにんまりさせた。
「髪の長い子を特に見てましたね」
「ああ。 まあな……」
「パチュリー様も綺麗なロングヘアーですよね。 ひょっとして旦那様は、ロングの女性なら誰でも良いのでは?」
突拍子もない事を言う。
髪の長さだけで女性を好きになるような事はない。
そういった輩はいるだろうが、少なくとも俺は違う。
声色から察するに、小悪魔自身もその事は良く解っている様子だった。
「馬鹿言うなよ。 短いよりは長い方が好きなだけだ。 さっきのは本当に子供だし、お前もロングだろ」
「じゃあ、私も守備範囲に入ったり?」
「当然髪の事は抜きにして言うが、それは無い――」
続きの、『とは言い切れない』という言葉は、
「冗談ですよ。 からかったりしてすみませんでした」
小悪魔によって、事前に用意されていた答えに掻き消された。
確かに、この女性は良い女だと思う。
だが、あの妖精達の事もそうだが、そう思うだけだ。
言い訳の続きに聞こえるかもしれないが、当然、抱く感情は恋慕や愛情とはかけ離れている。
理解され難いのかも知れないが。
「行動も口も災いの元です。 解っていると思いますが、もう少し気をつけて下さい。 パチュリー様も今なら、旦那様にとって自分が唯一無二だと解っているでしょうけど」
「悪かった。 気をつけるよ」
宥める様な小悪魔に素直に謝り、2人で図書館に向かいながら、問答は続いていた。
今度は、不安を内包しない世間話程度のもの。
「そういえば、小悪魔が図書館を出るなんて珍しいな」
「帰りが遅いから早く連れ戻して来いと、パチュリー様に言われたんですよ。 寂しいんじゃないですか?」
「それは嬉しい限りだが、同じ屋敷の中なのに堪え性無さ過ぎだな。 ところで、さっきのは何処から見てたんだ? 廊下にはいなかったと思うが」
「ちゃんといましたよ。 上空に」
そう言って小悪魔はぱたぱたと羽ばたいた。
薄暗い廊下の壁に映った影は大きく、ぞっとするような翼を広げていた。
気がつくと、もう図書館は目と鼻の先。
彼女は扉に手をかけると、最後に、
「今日はハロウィンですね」
呪文の様にそう唱え、大きな菓子箱の蓋を開けた――
詰まらない内容の本を半分ほど読み終えた時、区切りの悪いところで扉が開いた。
その音を合図に、栞を挟んで本を閉じ、顔を上げた。
これを読み続けるよりも、大事な事がある。
○○との会話だ。
「連れて来ましたよ」
「ご苦労様。 ○○、少し遅かったわね」
「そうでもないと思うが」
「質問だけにしては、時間がかかり過ぎだと思うけど?」
「ちょっと話し込んじゃったし、思わぬ珍客に出くわしたんだ」
数日前、レミィがハロウィンの夜はパーティーを開くと言い出した。
待っていればいつも通り、咲夜が呼びに来るのだから必要は無いのだけれど
○○はわざわざ咲夜に、本当に今夜開くのか、何時から始めるのか等を訊きに行ったのだ。
「珍客?」
「妖精だよ。 お菓子をくれとね」
○○が新しい記憶を思い起こし、薄い笑みを浮かべる。
それの何処が面白いのだろう?
「確かにメイド以外の妖精は珍客かも知れないけど、ハロウィンなんだからおかしい事じゃないでしょ」
「いや、何でハロウィンの事を知ってるのかなあ、と」
「なるほど……」
彼の言いたい事は、大体の予想がついた。
『何故、この屋敷の住人でもないのに外界の文化を知っているのか』
十中八九これだろう。
幻想郷に住まう者達には、ハロウィンは決して身近なものでは無い。
実際に、今まで紅魔館にお菓子をもらいに来る者などいなかった。
私は、○○に答えに近いヒントを与える。
「いつだったか、私達に外の世界のハロウィンの事を話したでしょ」
「ああ」
「その時、入り込んだネズミが盗み聞きしていた可能性は?」
言葉の意味に気付いた○○は、微笑を苦笑に変えた。
してやられた、といった顔だ。
「そういう事か。 すっかり失念していた」
「魔理沙は来る度にわざわざ挨拶する訳じゃない。 むしろ、顔を見せる方が少ないわよ。
彼女がその話を持ち帰って、誰かに話したのを妖精が聞いていた可能性が大きい。 レミィか咲夜が漏らした可能性も無い訳じゃ無いけど」
「その可能性は低いだろうな……。 ところで――」
疑問が解けると、○○はそれきりこの話題への関心は無くした様だ。
一応の本題、とでも言えるだろうか?
早々に、今夜の事に話の内容を転換させる。
「咲夜さんの話だと、予定通りだそうだ。 お嬢様が起きたら呼びに来るとさ」
「当然ね。 中止する理由が無いもの」
「しかし、一応魔物から身を守る日でもあるのに、この屋敷でパーティーとはな」
「何事も楽しんだ者勝ち、と言ったところかしらね。 レミィは口実になれば何でも良いのよ。 ○○も解ってるでしょ?」
「まあな」
「私達なら仮装する必要も無いですね」
「一応俺と咲夜さんは人間なんだが」
「2人ともこの館の住人なんだから、同類の様な気もするけど。 特に咲夜は」
「旦那様も。 魔女の夫なんて、それだけで十分に人間離れしてますよ」
邪魔をしない為か、黙り込んでいた小悪魔も、タイミングを見計らって会話に参加した。
2人とも、戻ってきてから立ったままだったのだが、一段楽して椅子に座る。
本棚の整理も先日済ませたばかりで、今のところ仕事は無い。
並びはいつも通り、私を間に挟み、○○がすぐ横に、寄り添う様に。
小悪魔は少し間隔を空けて、見守る様に。
タイミングはほぼ同時で、三者三様の本を開いた。
それを合図に会話が止み、静寂が訪れる。
嵐の前の静けさ、とでも言うのだろうか?
パーティーが始まる前の時間を、のんびりと過ごす。
再び読み始めた本の内容は、相も変わらず退屈なままだ。
だけど、今はむしろ、それが良い。
この屋敷では、楽しむのは夜だと相場が決まっている。
黄昏時、愛する者と共に、退屈と静寂に抱かれ、饗宴を待つ。
○○に肩を預けると、彼は僅かに身を震わせ、一瞬の微笑を浮かべた。
その横顔に、私の瞳は微かな欲望を宿す。
疑問が浮かんだ。
私は本当に、夜まで待てるだろうか?
「さてと」
変化を感じ取ったのか。
小悪魔が突然本を閉じ、背伸びをして立ち上がった。
「どうした?」
解っているのかいないのか。
とぼけた風で尋ねた○○に、彼女は笑顔で続ける。
「飽きたので少し散歩してきます。 ひょっとしたら、そのままメイド長の御手伝いに行くかもしれません。
パーティーが終わるまで、ここには戻ってこないかもしれませんね」
悪戯っぽい声音でそう言い、小悪魔は私に視線で許可を求めた。
前述した通り、今日は仕事が無いのだ。
断る通りも無い。
「分かった。 好きにすると良いわ」
「良かったな、小悪魔」
「はい。 ありがとうございます」
図書館を出て行く前、彼女は私と○○に向かい、
「ごゆっくり」
そう言い、随分と楽しそうに笑った。
言葉だけが余韻となってここに残る。
「行っちゃったな」
「そうね」
2人きりになっても、○○の態度には特に変化は無い。
私の体重を支えながら、急がずにページを駆る。
彼には今、そういう気は全く無いのだろうか?
私がめくるページには、徐々に大きくなる欲求と、苛立ちが乗せられる。
折角、小悪魔が作ってくれた甘い筈の時間に繰り広げられるのは、奇妙なポーカー。
賭けるチップも、ディーラーすらも存在しない。
無言で互いの出方を伺う。
そんな拮抗状態が延々と続いた果てに、○○が僅かに目を細めた。
ここぞとばかりに私は沈黙を破り、ハンドを公開する。
恐らく、勝負所はここしかない。
「○○。 今夜はハロウィンよね?」
こんな行為に及ぶのは、きっとハロウィンのせいだ。
たぶん、恋愛に飢えた悪霊にでも憑依されてしまったのだろう。
そう思いたくなるくらい、今は○○が欲しくて堪らない。
甘い夜の幕を、少し強引にこじ開ける。
本当に、全くその気が無かった訳じゃない。
ただ、明らかに作為的な状況に、完全にタイミングを見失っていただけだ。
「○○。 今夜はハロウィンよね?」
唐突なパチュリーの問いが、薪としてこの空間にくべられる。
抑圧された激情は、ゆっくりと、確実に燃え始めていた。
どうやら、俺のものよりも、彼女のものの方が強大な様だが。
「そうだけど、それがどうかしたか?」
俺のとぼけた問いに、パチュリーは妖艶に笑う。
既にお互いの本は読み進められる事が無く、開かれた意味を失っていた。
影から影へと、魔女が飛び移る。
2つの影が重なり、濃度を上げる。
先ほどまでは肩を預けていただけのパチュリーは、既に腕の中に居り、とろんとした瞳で先を紡いだ。
「Trick or Treat」
小さくそう告げ、彼女は俺の顔を見据える。
そんなパチュリーが余りにも可愛らしく、俺は自然と笑みを浮かべてしまった。
しかし、その要求には、言葉通りの意味では答えられない。
比喩的な意味でも、今は自分から答えるつもりは無いのだが。
たまには少し意地悪もしたくなるし、受け手に回るのも良いかと思えた。
「分かってるだろ? 持ってない」
「ここにあるでしょ? とびっきり……甘いのが」
もう我慢は出来ないとばかりに、パチュリーは少し強引に唇を重ねてくる。
静かな図書館の中に、欲望に塗れた水音が、やけに大きく聞こえた。
どれだけそうしていたのか、彼女は最後、名残惜しげにやわらかく俺の唇をかむと、ゆっくりと自分の唇を離した。
小さな痛みが、微熱としてとどまった。
長い長いキスが終わっても、互いに、熱に浮かされて頭はボーっとしている。
頬を薄紅に染めたパチュリーの視線は、何かを期待する様に、俺の瞳から逸れる事が無い。
恋愛に関しては、男よりも女の方が貪欲だ。
「これは確かに甘いけど、お菓子じゃないだろ?」
ここまでくると、どちらがお菓子をねだっているのか。
どちらが与える側なのか、そんな事はどうでも良くなっていた。
俺の言葉に満足した様子のパチュリーは、表情に恥じらいを浮かべて、甘く気だるげな声で囁く。
「じゃあ……悪戯、しちゃうね」
ほんの少しだけ、迷いを内包した指先が伸びる。
パチュリーの綺麗な指が、俺のシャツのボタンにかかった次の瞬間――
「ぎゃおー! おかしくれなきゃたーべちゃうぞー!」
「は?」
「ほえ?」
何の前触れも無く扉が開き、唐突に現れた闖入者に、俺達は随分と素っ頓狂な声を上げてしまった。
頭の中が真っ白になるというのは、まさにこの事だ。
それは、レミリアお嬢様も同じだったようだ。
俺とパチュリーの姿を確認するなり、数秒間動きを停止させると……
「ええと……じ、邪魔だった?」
物凄く気まずそうにそう言った。
だが、俺達にその言葉は届かない。
軽いパニック症状を起こしていたせいもあったが、何より……
「あ~あ。 お姉さまのせいでムード台無し。 ホント駄目だなー」
直後、上空から聞こえてきた声に気を取られた。
「フラン!? こんなところで何してるのよ!?」
「何って、暇潰し」
いつからいたのか、どの辺りから見ていたのか。
隠れて俺とパチュリーの行為を楽しんでいたらしいフランドールお嬢様が姿を現した。
お嬢様達の会話を呆然と見ていると……
「パチュリー様。 こちらにお嬢様は……あら」
今度は咲夜さんがやって来た。
案の定、俺達を見て目を丸くする。
「メ、メイド長!! 駄目です!! 今はまだ駄目です!! あ……」
それに続いて小悪魔も。
全員の動きが止まり、何とも形容し難い空気が流れる。
もう、こうなると笑うしかない。
俺は抑えようともせずに、苦笑を音にした。
冷静に考えてみよう。
ここには美鈴以外の紅魔館の主要メンバーが揃っていて、そんな中、1つの椅子の上で俺とパチュリーは抱き合っているんだ。
本当に、笑うしかないじゃないか。
「あ、貴女達」
先ほどまで微動だにしなかったパチュリーが、小刻みに震えながら、俺から身体を離す。
焦点の定まらない瞳が、未だに混乱が収まっていない事を意味していた。
「私達の邪魔は……」
そこで一泊置いて、大きく息を吸い込む。
真っ赤な顔をした彼女は――
「そこまでよ!!」
上擦った声で力いっぱい叫んだ。
俺の苦笑は伝染し、大きな笑い声が図書館内に満ちた。
Happy Halloween
Trick or Treat
今夜のパーティーは、思った以上に楽しかった。
食って、呑んで、笑って。
やっている事は毎度同じだが、それでも楽しいものは楽しい。
予想通り、招待もしていない客人が多く詰め掛け、予想以上の盛り上がりを見せる。
ただ、パチュリーだけはむくれているが。
埋め合わせは後で、しっかりとしてやるつもりだ。
「○○。 甘味が足りない」
「はいはい」
製造禁止前のアブサンに、角砂糖を1つ落とす。
パチュリーが緑の魔女を呑む様を、うっとりと眺める。
夜は、まだまだ終わらない。
むしろこれからだ。
ジャックランタンの怪しい灯りに照らされて、この後の相談といこう。
角砂糖1つでは、まだまだ足りないな?
新ろだ86
───────────────────────────────────────────────────────────
消えない虹
一話
「レミィ、しばらく紅魔館を留守にするよ」
七曜の魔女。
知識と日陰の少女。
動かない大図書館。
パチュリー・ノーレッジは親友に対して、こう切り出した。
秋の永き夜。
陽もとっぷりと暮れ落ちて、吹きわたる風の冷たさが身に染みてくるころのこと。
ようやく起き出した紅魔館の主人、レミリア・スカーレットは友人の管理する(というか、住み着いている)大図書館へと顔を出していた。図書館とは言うものの、書庫にある本はまだまだ未整理のまま、乱雑に積み重ねられているだけだ。およそ百年という歳月を経て無尽蔵に集められた文物と、その時間に付随する、重苦しささえ感じられる埃と黴の匂いが支配するところ。気質的に夜と闇に属すレミリアでさえ、あまり寄りつくことはない。
しかし、今日はその珍しい訪問の日であったようだ。
「留守? どこか用事でもあるの?」
唐突なパチュリーの物言いに、レミリアは幼い眉を顰めながら問い返す。
当然の疑問だろう。
出不精という言葉で済まされるものか、パチュリーは十日くらい平気で図書館に籠りきりになる。さらには何か月単位で紅魔館の外に出ないこともざら、らしいと聞く。
会話を交わしながらも、吸血鬼の親友は長机に向って書き物をしたまま。厚い革表紙に幾つもの紋様が刻まれている。いわゆる魔導書の類らしい。そんなことを気にする様子もなく、レミリアは書物に埋もれた机の反対側に座る。彼女用の椅子は常備されていて、脚は高く背は低い。普通のものでは顔半分が机の上に出ないためだ。
待ち構えていたかのように差し出されるティーカップとソーサー。
瀟洒な従者はいつどんなときも、主の要望に応えることができる。次の瞬間には時を操りどこかへ居なくなっているが。
一呼吸。
紅色の液体を口に含んだところで、パチュリーが再び口を開く。
「用事……まあ、そんなとこかな」
「曖昧な答え方」
「そうかな? 外界に行ってみようかと思って」
この台詞に、聞いていた者たちは驚きを隠せない。呆けたような表情のまま、レミリアは固まっている。どうやらカリスマというものは何処かに忘れて来たらしい。
「驚いた。理由を聞いてもいい?」
ここ百年は友人やっている彼女が言うのだから、相当のことなのだろう。
「探したいものがあるのよ」
内容は曖昧に、しかしきっぱりと言い切った。羽ペンを滑らせていた手を止め、運命を見通すと言われる友人の瞳を見つめている。確かに答えは曖昧。曖昧だったが、魔術の詠唱をしているときのような確信と、弾幕を避けているときのような決断力を内包した言葉。深紅と紫紺の瞳が交錯している。
その間ほんの数秒の出来事だ。
先に視線を外したのは、驚いたことにレミリアだった。
二口目の紅茶を飲み込んだところで、
「行ってくるといい。ま、わざわざ私に許可なんて取らなくても良かったのに」
と、苦笑混じりで言う。
「ありがとう、レミィ」
反対にパチュリーは、明らかに緊張が解けている。どうやら彼女の中では大事なことだったらしい。しかし、目的をはぐらかしたことから、友人にも腹のうちを見せないつもりか。外界に行って何を探すつもりなのか、とんと見当がつかなかった。
「それで……外界に行くってのは、八雲紫がはじめた外界ツアーで行くんでしょ?」
「そういうことになるね」
いつのまにかパチュリーの手には新聞があった。
題字は『文々。新聞』だ。そこにはレミリアの言う、外界ツアーの記事が載っている。
掻い摘んで説明すると、神無月に神様たちが出雲大社へと里帰りする。そのとき幻想郷から出るのに、八雲紫の隙間を通じて行く。その隙間をほかの人妖たちにも開放して、一月だけの外界バカンスを楽しもう――というものだ。
「ってことは、外界に詳しい人物が必要じゃないの?」
そうだった。
流石に外の世界の常識を知らない奴らを、そのまま放りだすのは心もとない。何をやらかすか予想がつかないし。だから、現界に詳しい――外界から来た人間を付き添いとして連れて行かねばならないという条件があるのだ。
迷い人として幻想郷を訪れ、定住してしまった人間はそこそこ数がいる。大抵の者は、半人半獣のハクタク先生に斡旋されて、人里にて能力に似合った仕事についている。しかし、他に縁があって、博麗神社やら白玉楼やら永遠亭やら守矢神社やら地霊殿やらで暮らしている者も、僅かながら存在するのだ。例えばここ、紅魔館にも。
「ええ。だから、○○を連れていくわ」
パチュリーの隣でここ数日間に整理した蔵書の帳簿をつけていた、俺、こと○○は、紅魔館の大図書館にて司書と雑用を兼ねて、住み込みで働かせてもらっている。
「俺……ですか、パチュリーさん」
「あなたしかいないじゃない。外の世界に通じている人間なんて」
「確かにそうだけど」
いまの会話からもわかる通り、俺は外界の、生粋の人間だ。年齢は……まあ、二十歳前後とでもしておく。ここらに住んでいる連中から比べると、何の能力もない一般ピープルである。それで良かったとも思うが。どうして能力を持っている奴らは、こうも曲者揃いなのか。
ちょうど小悪魔さんが紅茶を運んできたので、俺たちも手を休めることにする。
「お疲れさまなのさ」
「ありがとう、小悪魔さん」
礼を言いつつ、一口目を啜る。琥珀色の液体が揺らめきならが口の中へ流れ込んでくる。ぴりりと引き締まった渋みを香りとともに楽しむ。埃っぽい仕事柄、時々の紅茶休憩は日課のようになっていた。
「咲夜も貴方たちの分まで紅茶の用意をしとけばいいのに」
「レミィが飲んでるのと同じのは、私たち飲めないわよ」
「それもそうね」
レミリアの飲んでいる紅茶は、人間の血を混ぜた特別製らしい。血が主食である吸血鬼だが、幻想郷内での吸血は基本的に禁じられている。外界の人間の血が提供されているようだ。最近では献血が盛んなので、昔より食料の補給は楽なのではないか。
「でも、この紅茶は美味しいわ。また腕を上げたわね、小悪魔」
「ありがとうございます、なのさ」
「俺もこっちに来てから、紅茶にハマったからなぁ……」
「そういえば、ここで働きだした頃は珈琲が欲しいって、いつも言ってたのさ」
俺が幻想郷に来た理由は、それほど難しいものではない。
実際のところ、ただの偶然だ。
七曜の魔女と言われるだけあって、パチュリーは七つの属性の精霊を使役した魔術を得意とする。普通は一つの属性の精霊を支配するので精いっぱいなのだが、彼女は同時に二つ以上の精霊を意のままに操ることができる。物凄い腕前らしいのだが、魔術そのものを理解できない俺にとってはよくわからんことだ。ただ、いつも図書館内で新魔術の開発と言う名目で、怪しい実験を繰り返しているのを見ると、努力家(ただの暇つぶしかもしれない)なのだろうということはわかる。
閑話休題。
そのときもパチュリーは新たな精霊召喚の魔術を試していた。同時に俺は、たまの休日を満喫していた……はずだった。激しい衝撃と眩暈とともに視界が暗転し、ここ、紅魔館大図書館の一角に転移させられるまでは。
要するに失敗である。術式の途中で召喚対象の設定を間違えたそうだが、未だに正確な理由はわかっていない。俺が選ばれる可能性なんて、それこそ天文学的な数字であろう。宝くじに当たったようなものだと、今では開き直っている。
「○○が来てからもう半年近くになるのね」
「初めの頃の狼狽ぶりからだと、見違えるわ」
「その話はやめてくれ。一般人がいきなりあんな状況になったらビビるだろ、普通」
突然わけのわからんところに連れて来られて、混乱しているわけで。目の前にはパジャマみたいな服を着た女の子が怪しげな呪文をもにゃもにゃ唱えてるし、その後ろには明らかに生モノの羽の生えた女の子もいる(今でもパチュリーの服装は魔女に見えない)。そりゃ腰くらい抜かしても仕方ないと思いませんか? 見かねた小悪魔さんが、この館の主に会わせてくれたと思ったら、見た目十歳くらいの幼女だし。吸血鬼だし。メイド長は人間だと聞いてたけど、どうみてもDIO様です本当にありがとうございました。むきゅ~。
「それで……他の外界の人間にアテがあるの?」
ああ、そういえば外界旅行の話でしたか。半年もこっちで暮らしてると、人里の方にも少しは知り合いがいるけど、そういうことができる人間はいない。
「うーん、ないなあ」
「あったとしても、見ず知らずの人間を連れて行くなんて嫌」
なら聞くなよ。まあ、赤の他人とは見られてないとわかっただけでも良しとしておこう。
「その程度には信用してくれてると?」
「そりゃあ……そうだけど」
だんだんと小さくなる語尾。旅行へ行くこと自体は良いのだが、本当は一人旅をしたくて、俺を連れていくのは嫌だとか? 俯いてしまったパチュリーの思考は、俺にはさっぱりわからない。
パチュリーが失敗の責任を取るという形で、レミリアは俺が紅魔館で働くことを許可してくれた。
最悪、食われるという結末も用意されていたのだから、かなりマシな結果だったろう。
幻想郷で生活することについて特に問題はなかった。向こうでは季節雇用の出稼ぎ労働者だったし、親しい身内や友人もいない。仕事して、仮住まいのアパートに戻って……というだけのモノトーンな生活である。
幻想郷に迷い込む中に、けっこうな数の自殺志願者がいるらしいが、流石にそこまでではないにしても、現実に希望を見出せないという点で俺も似たようなものだった。極端な話、働いてメシが食えればどこでもよかったのだ。だからかもしれないが、早くにこちらの気風に馴染めたんじゃないかと思う。
紅魔館は吸血鬼が住んでいることもあって、活動時間は夜に集中している。俺の主な仕事は、大図書館の蔵書整理と館内の雑用。他に力仕事があれば進んで受けることにしていた。働かないレミリアはともかく、パチュリーや咲夜さん、小悪魔さんは肉体的に女の子と変わりないわけで。男手は貴重な戦力になっているようだ。
そんなこんなであっという間に半年が過ぎ、春から秋へと季節はとめどなく流れていた。文明の利器のない生活にようやく慣れ、落ち付いて今後のことに思考が回るようになったころ、パチュリーの外界旅行の話が舞い込んできたのだった。
転機かな、と思う。ここらで一度、自分が生まれ育った世界を見つめなおしたい。いずれ向こうに戻るにせよ。こちらに居つくにせよ、いま俺がやっておかねばならないことのように思う。
パチュリーの沈黙に助け舟を出すようにして、
「これも――運命と思って諦めることね」
と、レミリアは言った。
獲物を狙う狼のような含み笑いを湛えての台詞。彼女がその言葉――運命――を口にすると、洒落にならない重みが加わるから困る。幻想郷を紅色の霧で覆った事件、それより前、紅魔館が幻想郷へ来たばかりの頃に起こした吸血鬼事変。二つの首謀者であるレミリアの能力とは、ありあまる力でも身体能力でもない。運命を操る――などという、わけのわからないものである。しかし、
「あんまり簡単に言わんで下さい。俺は運命って信じてないから」
何でも運命で片付けられたらやってられない。いまさら足掻いたって、どうにもならないこともある。既に起きた事実は変えられなくて、未来は変えられる。そこに至るまでの努力すら運命だと言うのなら、自分っていう存在はなんなのだろうか。
「そうかしら? 私には見えるわよ。数多の運命の糸が絡み合う世界が」
本当か? とは口にしない。言っても詮無いことだし、説明してもらって理解できるとも思わない。
「例えば……そうね、あんたたちの運命とか」
俺とパチュリーを見比べて言う。
「どういうことだ?」
「まんまの意味よ。あんたたちの辿るはずの数奇な運命――」
「やめてくれ」
「今回の外界旅行は――」
運命を未来の出来事だとするのなら、それは不躾なものだ。ましてや、それを操ることが出来るというのなら、押し付けがましいものでもある。出来るならば聞かせて欲しくない。
「レミィ」
と、パチュリーが静かな声で友人の言葉を遮る。珍しく棘があるように聞こえたのは気のせいだったろうか。俺としては有難かった。どうもこういう話は気に食わないようだ、理由はわからないが。
「○○も。レミィの能力は呼吸と同じように存在するもの。ある者はない者のことをわからないものよ」
思考を読んだかのような彼女の言葉。
当たり前だと思っていることで相手を不快にさせる。右と左を間違うくらいの確率で、ままあることだ。常識と常識のすれ違いといったところだろう。話してみなければわからないこともある。だから、別にレミリアのことが嫌いなわけじゃない、と、レミリアに視線を向けると、彼女も肩を竦めてみせた。
「話題が逸れちゃってたな」
「そうみたいね。パチェ、続きは?」
とパチュリーに視線が集まる。
「……そう、それで、○○はどうなのか。一緒に行ってくれるのかな? もしかしたら……外界に帰れるチャンスかもしれないよ」
うって変わって、風が囁くような声で言う。
パチュリーの意図が先ほどから掴めなくて困る。俺に対するときだけ弱気になっているようだ。それが何を意味するのか、わからない。
旅行については問題ない。喜んでついていくだろう。相方がパチュリーであることに戸惑いはあるが。
実のところ、普段の生活の場で、割と近くにいるはずなのに俺とパチュリーとの会話は殆ど無い。無限に知識を求める魔女――と聞いていたので、最初の頃は外界のことに聞かれるかと構えていたが、そんなことはなかった。仕事の場合も、必要最小限のことを指示するぐらいである。だからといって嫌われているわけでもなさそう。たまたま廊下で出くわしたときも、こちらから挨拶すれば目礼くらいは交わしてくれるし。レミリアに対する場合は別として、彼女は誰にもそんな感じの態度だから。
とはいうものの、こんな形でパチュリーに指名されるのは予想外だった。
他に外界出身で適任者が紅魔館にいないとはいえ、だ。
「うーむ」
どちらにせよ俺が頷かないと、この話は立ち消えになるわけで。わからない部分は、時間が解決してくれるさ、と自分を励ましておく。こいつらが本気になれば、意思など関係なく無理やりにでも良いのだ。そういうことはしない――緊急時じゃない限り――というのは経験上わかっている。だからこそ俺はこの場所に留まっているのだから。
それに、上目使いでこちらの様子を窺っているパチュリーの表情を見ると、ジェントルな俺は断れないじゃないか。
「仕方ないな」
小さく聞こえた溜息は安堵のものなのだろうか。パチュリーは、ほっとした様子で眉尻を下げ、木の芽が綻ぶような微笑みを見せてくれた。
それほどまでに外界に行きたい理由は何なのか。知りたいと思うが、聞いても語ってくれない気がする。あまりプライベートに立ち入るのは良くないとも思う。もし語れるような心境になったとしたら、自然と零れてくるものだろう、こういうことは。
新ろだ126
───────────────────────────────────────────────────────────
どこまでも果てしなく広がる宇宙の姿が、丸窓の形に切り取られてロケットの壁に貼り付いている。
視界の半分を埋めるのは薄らと白く、優しくぼんやりと輝く青い星。
そこに住まう人々が名付けた数多の星座。尾を引いて飛んで行く彗星達。
自覚する。
夢を見ている。
頭に三角帽子を被って、お尻からコンロみたいな火を噴き続けている落書きロケットは、そんな自分を乗せて宇宙を飛び続けている。
不思議な、素敵な夢だ。
いっちょ前に備え付けられたコンピューターは静かな駆動音を響かせ、聞いたことも無い星系から発信しているらしいラジオは、緩やかな曲調の歌を流している。
そして、無重力に遊ばれてゆらゆらと部屋に浮かぶ、赤。
それをもっと良く見てみたくて、
手を――――
「……」
「……おはよう」
寝息一つ立てずに椅子にもたれて、珍しく眠っていた魔女は全く唐突に目を覚ました。
そのまま無遠慮に目の前にある顔をしげしげと眺めて「カボチャ……では無かったわね」と呟いた。
これっぽっちも腑に落ちないが、酷く失礼な事を言われたのではなかろうか。
しかし、謀らずも勝手に寝顔を拝む形になっていた事に少なからず引け目を感じた○○はその不満を飲み込み、変わりに思った事を口に出すことにした。
「パチュリーが寝てるところなんて初めて見たな」
以前、魔法使いには睡眠は必要ないとか言っていたような気がする。
「最近忙しかったから、気分的にでも休養を取ってみたの」
パチュリーは眠たげな目をしたままぼんやりと答えた。ちなみに寝起きでなくとも彼女は普段から大体こんな目つきをしている。
「意味あるのか? それ」
「病は気から」
「確かに気合が不足してそうだな。慢性的に」
パチュリーはそれには答えずにテーブルの上の本に手を伸ばす。
○○は、彼女がひとたび本に没頭しだすと完全に外界をシャットアウトしてしまうのを知っている。
「なぁ、忙しかったワケってさ」
「ロケット製作」
先に言われてしまった。
「門番から聞かなかった?」
「ワガママ君主と他数名で月旅行中らしいな」
聞きたいことはそれだけ? と、目が言っている。
窺うような視線を受けて、軽く息を吸ってから告げる。
「俺も行きたかった」
胡乱な瞳が僅かに揺れる。どうやらこの返答はそれなりに意外だったらしく、手の上の本を一時テーブルに戻してくれた。
「あなたが宇宙に興味を持っていたとは知らなかったわ」
男の子ですから。と返すと、何よそれ。と再びジト目で睨まれた。
「いつも土いじりの本ばかり借りて行くクセに」
「そっちは生活が懸かってるからな。いつも助かってるよ。ありがとう」
「私が書いた本じゃないし」
「拗ねるポイントはそこなのか」
ふと席を立ったかと思うと、彼女は近くの本棚から一冊の本を抜き出して戻ってきた。そして、そのまま手に持った本をこちらに差し出して一言だけ。
「はい、コレ」
「何だコレ」
渡された本は、やたら分厚いくせにその割に控えめな装丁を施された物だった。
「錬金術のハウツー本よ。書いたのは私」
脈絡が無い上に意味がわからないんですが。
「私が直接手渡しした時点で仕掛けは外れているから魔力の無い貴方でも問題なく読めるわ」
「はぁ」
「内容についてもヘルメス文書にも負けていないつもりよ」
「そうですか」
「宇宙に行きたいんでしょ?」
まさにその宇宙そのものを秘めているかのようなコスモ的な色の瞳でトツトツと語るパチュリー。さっきから微妙に話が通じていない気がする。誰か小悪魔を呼んできてくれ。
「錬金術の究極的な命題は魂の浄化にあると言えるわ。人の卑俗な魂を神霊のレベルにまで昇華させ、それによって遍く全ての物質を組成している第一質量を意のままに操ることができるようになる。つまり金の練成、万能薬の生成、生命の誕生、宇宙の創造すらも自らの手で実現する事が可能になる訳ね。そもそも宇宙というものを本質的な概念で捉えると」
俺の困惑なぞ知ったことかとばかりに頼もしくシカトをくれつつ、淀みなく長広舌をぶち続ける姿は、正直、かなりアレだ。
それでいて目線はしっかりこちらを捉えたまま動かないので冗談抜きで怖い。つうか持病の喘息はどうした。
「要するに、不完全を完全に。これを目指すのが錬金術なの。何か質問はある?」
これだけ熱弁を振るったにも関わらず、いたって涼しい顔をしている事についてこそツッコみたかったが、迂闊に口を開けば倍返し程度では済まなさそうなのでやめておいた。
目の前の何故か生き生きとした様子のパチュリーと、手元の本の表紙を交互に見つめて、軽く息を吐く。
「悪い。やっぱこの本、返すわ」
一瞬だけ翳ったその表情に、胸が痛む。
「そう。残念ね」
本を渡すと、既にいつもの眠そうな目つきに戻っていた。
「天地創造は俺にはちょっと荷が重い。おとなしく畑を耕してる方が性に合ってる」
床に置いていた鞄に手を突っ込んで収穫したばかりのトマトを取り出し、テーブルに置く。土産のつもりで持って来ていたのだがタイミングを逃してしまい、出しそびれてしまっていた。
突如として出現した赤い果実に、パチュリーの目が僅かに困惑の色を滲ませる。
元より月の石になんか興味は無かった。
月面に旗を立てて何かを主張したかった訳でも無い。
ただ、単純な理由だ。
「それにな、俺はパチュリーの造ったロケットに乗りたいんだ」
それだけの話だ。
机の上のトマトは、どこまでも普通のトマトだ。
赤くて、甘くて、少し酸っぱくて。
うちの畑で採れた、日の匂いのする宇宙のかけらだ。
トマトを見つめたまま動かないパチュリーが妙におかしくて、少し意地悪をしたくなった。
「どうぞ召し上がれ」
弾かれた様にトマトからこちらへ、またトマトへ。交互に視線を送るパチュリーを見て唇がつり上がるのを抑えきれない。
「あの、○○? ひょっとして」
「水洗いしてあるから大丈夫」
何が大丈夫なんだとはあえて言わない。
「……咲夜が帰ってきたらパイにしてもらいましょう。紅茶も淹れて。うん、そうしましょう。レミィも喜ぶわ」
「採れたてを食べるのが良いんじゃないか。五、六個持ってきたから、そっちを今度パイにしてもらえばいい」
「そもそも私、食事摂らなくても平気だし」
「好き嫌いは良くないな」
からかわれているのが分かっているのに無碍にも出来ないという内心の葛藤が手に取るように見えるので実に面白い。これはどっかの素兎でなくても「うささささ」と言いたくなるというものだ。
こっちがニヤニヤと笑っているのに気付くと、パチュリーは少しムッとして席を立ってしまった。
ちょっとやりすぎたか、と慌ててこっちも席を立とうとすると、パチュリーは難しい顔で眉をひそめたまま、ポツリと呟いた。
「本を戻しに行くだけだから。汁、飛んじゃうでしょ」
新ろだ198
───────────────────────────────────────────────────────────