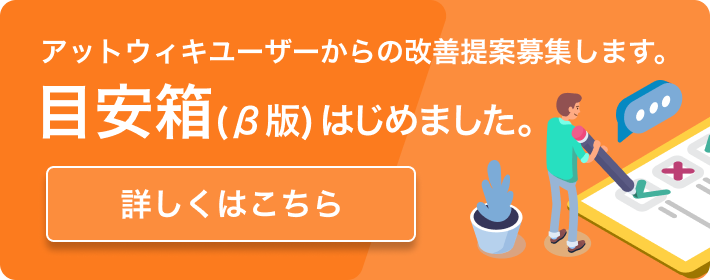先輩とファンタスティック・テクニック
「先輩! お勉強で分からないところがあるので教えてください!」
(えー……イヤだなぁ……)
「ありがとうございます! やったぁ! 先輩大好きっ!」
(えー……イヤだなぁ……)
「ありがとうございます! やったぁ! 先輩大好きっ!」
……俺はまだ了承などしていない。
俺が下唇を裏返してみせたのを、いったい誰が責められるだろう? というか責めたやつ、頼むから俺と大至
急代わってくれ!
俺が下唇を裏返してみせたのを、いったい誰が責められるだろう? というか責めたやつ、頼むから俺と大至
急代わってくれ!
「最近のお前ってほんとうに俺の話聴かないよな」
「必要ありませんもの。相思相愛、以心伝心。先輩のお心は丸裸です!」
「必要ありませんもの。相思相愛、以心伝心。先輩のお心は丸裸です!」
ちょっと照れたのか得意気な顔に朱の散った後輩はそれは可愛らしかったが、俺たちは相思相愛の仲ではない
し、彼女が分かると嘯く“俺の心”などまずもって独り善がりの妄想にすぎない。俺のほうも後輩の考えている
ことなんて知らないし、というか知りたくない。こわい。
し、彼女が分かると嘯く“俺の心”などまずもって独り善がりの妄想にすぎない。俺のほうも後輩の考えている
ことなんて知らないし、というか知りたくない。こわい。
「勉強で分からないというのは四字熟語の意味か。それとも人物の心情の読解のほうか」
「えー? 違いますよ?」
「えー? 違いますよ?」
後輩は不意打ちで俺の耳元に唇を寄せて囁いた。
「保健です。……先輩お得意の保健のお勉強です。先輩のファンタスティック・テクニック、また閑花ちゃんに
味わわせてください……」
味わわせてください……」
もしも、これと同じことを手のひらでもメガホンにして大声で教室中に言いふらすようなマネをしていたら、
さしもの俺も真剣にこの後輩との絶交を考えているところだった。俺を怒らせないぎりぎりの線で引くそのあた
りの手管には少し感心する。
“保健”とか“テクニック”とか、中学生あたりなら水とアルカリ金属のように激しく反応するかもしれない
言い回しに関しては当然無視だ。後輩にしてはオリジナリティがない。……そんなことはどうでもいいか。
さしもの俺も真剣にこの後輩との絶交を考えているところだった。俺を怒らせないぎりぎりの線で引くそのあた
りの手管には少し感心する。
“保健”とか“テクニック”とか、中学生あたりなら水とアルカリ金属のように激しく反応するかもしれない
言い回しに関しては当然無視だ。後輩にしてはオリジナリティがない。……そんなことはどうでもいいか。
「調べ学習と暗記の科目に、得意不得意もテクニックもないだろう」
「ご存じないですか? ――保健にも実技ってあるんですよ?」
「ご存じないですか? ――保健にも実技ってあるんですよ?」
面白みゼロの返答で話をぶち壊しにしようと思ったら、向こうが踏みこんできた。湿り気を帯びた吐息にぞっ
とし、俺は露骨に嫌そうな表情を作って顔を背ける。
とし、俺は露骨に嫌そうな表情を作って顔を背ける。
「よそは知らんがうちの学園にはないんだよ、一年生」
「今年度からできたかも」
「今年度からできたかも」
後輩がさらに身を乗り出す。
「どのみち、今の二年はその授業を受けていないから俺に教えられることは何もないな」
「じゃ、私が手取り足取り教えてあげます」
「お前は何しにここに来たんだ」
「さあ? 何でしたっけ。……忘れてしまいました」
「じゃ、私が手取り足取り教えてあげます」
「お前は何しにここに来たんだ」
「さあ? 何でしたっけ。……忘れてしまいました」
……なんだか、らしくないと思った。
俺たちのやり取りにはもっと、こう、何と言ったらいいのか、関係の進展について暗黙の了解があったように
思う。いや、後輩にとってはこれもまだそのちょっとした延長なのかもしれないが、“後輩が攻め、俺が躱し、
後輩がほどほどのところで退く”、そんな俺たちの関係がひどく危ういバランスの下に成り立っていたのだと、
思い知らされた気分だった。
彼女が少し退かずに粘っただけで、俺はひどく動揺していたのだ。
後輩が本気になったら、俺も本気にならざる得ない。恐らく俺か後輩かその両方が不幸になる形で破綻してし
まうだろう。
後輩は俺に対して一見やりたい放題しているように見えて、実はあれでもかなり言動に気を遣っている。
たとえば、後輩は料理ができる。
実に要領よく並行作業をこなし、家庭料理としては誰に出しても恥ずかしくないレベルの三品四品を鼻歌混じ
りに作ってみせる、それくらいの調理技能を持っている。家庭科の白壁教諭はおろか、俺やうちの母よりたぶん
うまい。
そんな具合だから、いつかの事件が落着を見てしばらく、彼女は俺に毎日の手作り弁当を作らせて欲しいとし
きりに言ってきた。
俺たちのやり取りにはもっと、こう、何と言ったらいいのか、関係の進展について暗黙の了解があったように
思う。いや、後輩にとってはこれもまだそのちょっとした延長なのかもしれないが、“後輩が攻め、俺が躱し、
後輩がほどほどのところで退く”、そんな俺たちの関係がひどく危ういバランスの下に成り立っていたのだと、
思い知らされた気分だった。
彼女が少し退かずに粘っただけで、俺はひどく動揺していたのだ。
後輩が本気になったら、俺も本気にならざる得ない。恐らく俺か後輩かその両方が不幸になる形で破綻してし
まうだろう。
後輩は俺に対して一見やりたい放題しているように見えて、実はあれでもかなり言動に気を遣っている。
たとえば、後輩は料理ができる。
実に要領よく並行作業をこなし、家庭料理としては誰に出しても恥ずかしくないレベルの三品四品を鼻歌混じ
りに作ってみせる、それくらいの調理技能を持っている。家庭科の白壁教諭はおろか、俺やうちの母よりたぶん
うまい。
そんな具合だから、いつかの事件が落着を見てしばらく、彼女は俺に毎日の手作り弁当を作らせて欲しいとし
きりに言ってきた。
『ねー先輩ー。いいでしょ? 愛妻弁当です! 愛後輩弁当! 実は先輩のお母様のお許しももら……え? い
らない? ……そう……』
『閑花ちゃんは先輩に自分をアッピールするチャンスもいただけないのですか……?』
『っよし! 分かりました! もう結婚しましょう! それが先輩にとっても一番いいと思います! 閑花ちゃ
んあったまいー!』
らない? ……そう……』
『閑花ちゃんは先輩に自分をアッピールするチャンスもいただけないのですか……?』
『っよし! 分かりました! もう結婚しましょう! それが先輩にとっても一番いいと思います! 閑花ちゃ
んあったまいー!』
全て固辞した。
そして俺が拒否する限り、彼女が不意打ち気味に“実際に弁当を作ってくる”ことはなかった。一度もだ。
もしそういうことをされていたら、受け取るべきかどうか、どういう対価を払うべきか、そんなことで俺は本
気で困惑したに違いない。
それが分かっていたから、後輩は自ら退いたのだ。まんざらただのお馬鹿さんではない。
もっともその分、調理実習の菓子類やバレンタインチョコでは箍が外れがちで、とんでもないものが繰り出さ
れることもしばしばだったが、まあそれはこの際いいだろう。
そして俺が拒否する限り、彼女が不意打ち気味に“実際に弁当を作ってくる”ことはなかった。一度もだ。
もしそういうことをされていたら、受け取るべきかどうか、どういう対価を払うべきか、そんなことで俺は本
気で困惑したに違いない。
それが分かっていたから、後輩は自ら退いたのだ。まんざらただのお馬鹿さんではない。
もっともその分、調理実習の菓子類やバレンタインチョコでは箍が外れがちで、とんでもないものが繰り出さ
れることもしばしばだったが、まあそれはこの際いいだろう。
「思い出しました」
ようやく――
ようやく、だと思った。
ようやく、だと思った。
――ごめんなさい、悪ふざけがすぎました? でもどきどきしたでしょ?
気まぐれな黒猫のように、後輩がさっと俺から離れた。掛かる吐息が消えたことに密かに安堵しながら、俺は
彼女の表情を窺う。
可憐な口元に満足げな笑み、しかし俺を捉えるその眼差しにはこちらの内心を見透かすような、どこか悪魔的
なものがあった。俺はせめてもの抵抗に、顎を引いてやる気のない半眼で圧し返す。その時にはもう、彼女はに
っこり笑って、瞼で瞳を覆い隠していた。
彼女の表情を窺う。
可憐な口元に満足げな笑み、しかし俺を捉えるその眼差しにはこちらの内心を見透かすような、どこか悪魔的
なものがあった。俺はせめてもの抵抗に、顎を引いてやる気のない半眼で圧し返す。その時にはもう、彼女はに
っこり笑って、瞼で瞳を覆い隠していた。
「保健の勉強で教えて欲しいところがあったんですが」
――もう分かりました。私がその気になれば、すぐにでも先輩を私の物に出来るんだって
それは幻聴だったのか、どうか。
後輩がその気になったら、俺もその気になるしかない。そうすれば、俺か後輩かその両方が不幸になる形で破
綻してしまうだろう。
そうは言ったが、不幸せを予言したとしても、彼女の戒めにはならない。それはそうだ。後鬼閑花の考える彼
女の幸福と、俺の考える後鬼閑花の幸福はずいぶん違っているのだから。
後輩がその気になったら、俺もその気になるしかない。そうすれば、俺か後輩かその両方が不幸になる形で破
綻してしまうだろう。
そうは言ったが、不幸せを予言したとしても、彼女の戒めにはならない。それはそうだ。後鬼閑花の考える彼
女の幸福と、俺の考える後鬼閑花の幸福はずいぶん違っているのだから。
「ここです。“防衛機制について”」
目の前に該当ページの開かれた保健の教科書が差し出される。かっこうつけた専門用語が見出しになった、俺
の大嫌いな単元だった。やりたくないことを催促されているような気になってくるのだ。嫌がらせのようなタイ
ミングである。
の大嫌いな単元だった。やりたくないことを催促されているような気になってくるのだ。嫌がらせのようなタイ
ミングである。
「私も早く防衛機制を華麗に使いこなせる女になりたいです!」
「そういうもんじゃないから」
「そういうもんじゃないから」
ふたりしていつもの調子に戻っても、俺の頭の中には“これからのこと”がずっとこびりついたままだった。
おわり
前:]] 次:[[