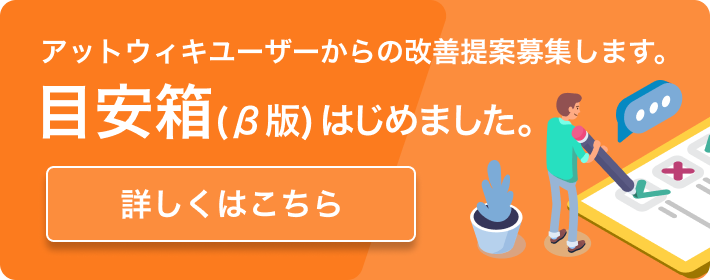ろうそくもらい
お菓子作りが好きだ。
筋道通して順序よく組み立てれば、必ず良い結果を残してくれるからだ。
まるで、聞き分けのよい理数系の大学生みたいだ。やつらは理屈を重んじる。だからこそ、対話していて心地よい。
分量、順序、時間。きちんとさえすればよいだけの話。テーブルのうえのクッキーを人つまみして、自分の腕前を確かめる。
部活動は一休み、誰もいない部室にて、しとしとと残る梅雨の忘れ形見を背中にして、放課後のひとときを貪る。
筋道通して順序よく組み立てれば、必ず良い結果を残してくれるからだ。
まるで、聞き分けのよい理数系の大学生みたいだ。やつらは理屈を重んじる。だからこそ、対話していて心地よい。
分量、順序、時間。きちんとさえすればよいだけの話。テーブルのうえのクッキーを人つまみして、自分の腕前を確かめる。
部活動は一休み、誰もいない部室にて、しとしとと残る梅雨の忘れ形見を背中にして、放課後のひとときを貪る。
今日は七月七日。全国的に七夕。
お菓子をあげることも好きだ。
自分の成果が目に見えることは、一種の快感だ。
自分の成果が目に見えることは、一種の快感だ。
お菓子についてならば、誰にも負けない自身は山尾修にはあった。
山尾修はアーチェリー部だ。七月真夏の真っ盛りだけど、やはり腕前が気になるから。だが、雨ゆえに実射練習が出来ない。
梅雨も明けたばかりだし、雨天だから。仕方ないから、弓具の手入れを丹念に行っていたのだ。
梅雨も明けたばかりだし、雨天だから。仕方ないから、弓具の手入れを丹念に行っていたのだ。
「……今度、何作ろうかな」
繊細さと大胆さ、相反する能力を必要とするアーチェリーと、お菓子作りはこじつけのように似ている。「おいしい」の一言と、
矢が的中した瞬間に、清涼感溢れる快感が突き抜けるからかもしれない。
修は手についたクッキーかすをウェットティッシュでぬぐい去った。面倒な弓具の手入れも、波に乗れば苦でもないし。
矢が的中した瞬間に、清涼感溢れる快感が突き抜けるからかもしれない。
修は手についたクッキーかすをウェットティッシュでぬぐい去った。面倒な弓具の手入れも、波に乗れば苦でもないし。
矢をつがえる際、指に引っ掛けるタグにワセリンを塗りこんでゆく。手になじませて、よき相棒へと仕立て上げるためだ。
直接指に付ける道具だから、丁寧に丁寧に、恋人へ囁くように皮を柔らかくする。タグは優しく返事をしていた。
直接指に付ける道具だから、丁寧に丁寧に、恋人へ囁くように皮を柔らかくする。タグは優しく返事をしていた。
『ローソク出ーせー出ーせーよー 出ーさーないとー かっちゃくぞー おーまーけーにー噛み付くぞー』
何の呪いか、聞き慣れない童歌が部室の入り口から流れてきた。
一人、弓具の手入れをしていた山尾修は、不審にかられながらも引き続き手入れを続ける。
こんこんと扉を叩く乾いた音が修の耳に響くから、重い腰をやれやれとあげる。
できることなら面倒なことに巻き込まれたくはないもの、奇妙な次元に飲み込まれたままなのも、なんだか落ち着かないから、
ドアノブをがちゃりと回して招かざる来訪者を出迎える。
一人、弓具の手入れをしていた山尾修は、不審にかられながらも引き続き手入れを続ける。
こんこんと扉を叩く乾いた音が修の耳に響くから、重い腰をやれやれとあげる。
できることなら面倒なことに巻き込まれたくはないもの、奇妙な次元に飲み込まれたままなのも、なんだか落ち着かないから、
ドアノブをがちゃりと回して招かざる来訪者を出迎える。
「黒猫?」
ちょこんと前足を揃えてつぶらな上目遣いを潤ませる一匹の黒猫。
首からぶら下げたiTunesと、背中に背負った、小型スピーカーが違和感を誘う。
そこから流れていた歌声は、修をの耳を奪った張本人だった。
誰に話しても一笑に伏されるのがいい落ちだ。猫がお菓子をねだりに来た。そんなおとぎ話許されるの、小学生までだよねー。
山尾修は高校二年、メルヘンのメの字も忘れた。
首からぶら下げたiTunesと、背中に背負った、小型スピーカーが違和感を誘う。
そこから流れていた歌声は、修をの耳を奪った張本人だった。
誰に話しても一笑に伏されるのがいい落ちだ。猫がお菓子をねだりに来た。そんなおとぎ話許されるの、小学生までだよねー。
山尾修は高校二年、メルヘンのメの字も忘れた。
がたっと廊下の先で音がする。
人影に黒髪がふわりと柳のようになびく。
息を殺す声が現場に残る。
すらりとした夏の制服姿が、からっと晴れた八月の廊下にひまわりの花びら散らす……夢を見る。
彼女は黒猫の差し金・黒咲あかね一年生。
人影に黒髪がふわりと柳のようになびく。
息を殺す声が現場に残る。
すらりとした夏の制服姿が、からっと晴れた八月の廊下にひまわりの花びら散らす……夢を見る。
彼女は黒猫の差し金・黒咲あかね一年生。
「クッキー先輩ですよねっ」
「……」
「ろうそくの代わりに黒猫です」
「……」
「ろうそくの代わりに黒猫です」
確か、クッキーをあげたから、それ以来クッキー先輩と呼ばれている。
もちろん、そんな呼び方をしているのは黒咲あかねぐらいだ。
もちろん、そんな呼び方をしているのは黒咲あかねぐらいだ。
「『ろうそくもらい』ですよ。ご存知ですか」
「ろうそく貰うの?いいの?」
「北の大地の習わしですっ」
「ろうそく貰うの?いいの?」
「北の大地の習わしですっ」
額に汗した修は黒猫を抱き抱えたあかねの二の腕を見つめていた。湿り気を帯びた猫は黒さを増して、黒曜石にも負けない輝きだ。
男子としては背の低い修だからか、女子としては背の高いあかねに対しては、自然と照れ隠しの目線となる。
ただ、修としては、自分が先輩だからか言い訳としては何かと好都合だった。
男子としては背の低い修だからか、女子としては背の高いあかねに対しては、自然と照れ隠しの目線となる。
ただ、修としては、自分が先輩だからか言い訳としては何かと好都合だった。
「北の大地の習わしって……黒咲さんって、もしかして北海道……」
「違いますっ。おばあちゃんちが長崎ですっ」
「違いますっ。おばあちゃんちが長崎ですっ」
肌の白いあかねだったからと思いきや、それは、あてずっぽうの流れ矢だった。
アーチェリーで的をはずすとくやしいし、このときも何故か同じぐらいくやしい。だが、ここで顔に出すのはオトナ気ないなと
先輩はぐっと奥歯をかみ締めていた。
アーチェリーで的をはずすとくやしいし、このときも何故か同じぐらいくやしい。だが、ここで顔に出すのはオトナ気ないなと
先輩はぐっと奥歯をかみ締めていた。
あかね曰く、ただの好奇心に掻き立てられてとのことだが、修も年上だ。あかねの企みに裏を見た。
なぜ、修のいるアーチェリー部を狙ってわざわざやって来たのか。
それは、一度、クッキーをあげたから。理由など、どんなものにだって存在する。
なぜ、修のいるアーチェリー部を狙ってわざわざやって来たのか。
それは、一度、クッキーをあげたから。理由など、どんなものにだって存在する。
「ろうそくもらいは、小学校の低学年ぐらいの子供たちが、各家庭にお菓子をもらいに来る行事ですっ」
「へえ。ハロウィンみたいだね」
「毎年七夕になると、こどもたちが歌を歌いながら家庭に訪れてお菓子をもらうんですっ。
『お菓子をくれないと引っ掻くぞ、噛み付くぞ』って……こども……がです」
「七夕?」
「へえ。ハロウィンみたいだね」
「毎年七夕になると、こどもたちが歌を歌いながら家庭に訪れてお菓子をもらうんですっ。
『お菓子をくれないと引っ掻くぞ、噛み付くぞ』って……こども……がです」
「七夕?」
頬を赤らめたあかねは、スカートの裾を握りしめた。
一方、修はあかねから引っ掻かれたり、噛み付かれている自分の姿を想像していた。
一方、修はあかねから引っ掻かれたり、噛み付かれている自分の姿を想像していた。
一般的に黒猫は人懐っこいらしい。人をひきつける魅力があるという。
あかねが連れてきた黒猫は校舎に迷い混んだ野良だという。
だから、役目を果たした野良猫と別れを告げた。もう、会わないかもしれない寂しさと、いつかきっと会えるという希望を胸に。
手洗い場で修とあかねは蛇口から溢れる水の音に心を留めた。
あかねが連れてきた黒猫は校舎に迷い混んだ野良だという。
だから、役目を果たした野良猫と別れを告げた。もう、会わないかもしれない寂しさと、いつかきっと会えるという希望を胸に。
手洗い場で修とあかねは蛇口から溢れる水の音に心を留めた。
「……だって、わたしはコドモですよっ。みんなは『オトナっぽいねっ』とか、言ってくれるんだけど、全然ですっ」
「そんなことないよ……、黒咲さんは」
「そんなことないよ……、黒咲さんは」
手を清める。
ざっざとぬれた手を振り切って、水を切るあかねの仕草に微かな色気を感じた修は、先輩らしい対応で黙していた。
ざっざとぬれた手を振り切って、水を切るあかねの仕草に微かな色気を感じた修は、先輩らしい対応で黙していた。
「でも、やっぱり」
#
わたしはかつて『あーちゃん』でした。
ファッション雑誌の中だけで、誰からも羨ましがれる『読モ』……読者モデルをしていました。
ファッション雑誌の中だけで、誰からも羨ましがれる『読モ』……読者モデルをしていました。
でも、あーちゃんなんて知りません。
みんなから担ぎ上げられて、ふらふらと迷いの森に投げ込まれた名もなきコドモですよ。
みんなから担ぎ上げられて、ふらふらと迷いの森に投げ込まれた名もなきコドモですよ。
あるとき、はるか遠い北の大地から撮影の為に通っていた読モ仲間の『きー子』が嬉しそうに言いました。
そのころ中学生になったばかり。コドモだと主張しても通るし、コドモじゃないんだからと駄々こねても許されるあいまいな時期。
きー子は意気揚々として、わたしに自慢しました。
そのころ中学生になったばかり。コドモだと主張しても通るし、コドモじゃないんだからと駄々こねても許されるあいまいな時期。
きー子は意気揚々として、わたしに自慢しました。
「あーちゃんさー。ろうそくもらいで、子供たちにお菓子あげるぐらいにお姉さんになったんだよねー」
「ろうそくもらい?」
「うん。小学校の低学年ぐらいの子たちが、おうちにお菓子をもらいに来る行事だよ。北海道だけなのかなー」
「ろうそくもらい?」
「うん。小学校の低学年ぐらいの子たちが、おうちにお菓子をもらいに来る行事だよ。北海道だけなのかなー」
それ、わたしです。お菓子をもらいに行く方です。
わたし、全然コドモだし。
わたし、全然コドモだし。
「やっぱ、あーちゃん……着こなしがオトナだぁ」
#
自覚はある。
自分はコドモだと思い込んでいても、誰もがみなそれを認めてくれない事実。
みどりの黒髪艶やかに、すらりと背の高いあかねが『背伸びして』子供ぶるよりか、心を許した黒猫に願いを託した方が良い。
外の雨音もすっかり止み、雲の切れ目からは天への架け橋が下りていた。希望への架け橋とも言うらしい。
自分はコドモだと思い込んでいても、誰もがみなそれを認めてくれない事実。
みどりの黒髪艶やかに、すらりと背の高いあかねが『背伸びして』子供ぶるよりか、心を許した黒猫に願いを託した方が良い。
外の雨音もすっかり止み、雲の切れ目からは天への架け橋が下りていた。希望への架け橋とも言うらしい。
「ほら。お菓子」
修があかねに手渡したクッキーは割れていた。
深々とお礼をしたあかねは、恥ずかしそうに顔を背けた。
あかねが口にしたクッキーはバターの味が程よく効き、自己主張の控えめな上品さがあった。
深々とお礼をしたあかねは、恥ずかしそうに顔を背けた。
あかねが口にしたクッキーはバターの味が程よく効き、自己主張の控えめな上品さがあった。
たった、お菓子を手に入れるだけに「ろうそくもらい」を口実に、黒猫連れてあかねはわざわざ修の元へやってきた。
背は低くとも、修は先輩だ。そんなこと、とっくに見破っている。
修はそれを思うと、背伸びとだだっこの挟間でもがくあかねが余計にコドモに見えてきたのだ。
背は低くとも、修は先輩だ。そんなこと、とっくに見破っている。
修はそれを思うと、背伸びとだだっこの挟間でもがくあかねが余計にコドモに見えてきたのだ。
「また、来ます」
振り返りざまのあかねの髪があまりにも完璧な曲線を描くので、ぎゅっと修は胸を締めつけられた。
背の高い後輩なんかに、惑わされるものかと意地を張る。
背の高い後輩なんかに、惑わされるものかと意地を張る。
「いつでもおいでよ。ヒマだし」
「来ます」
「来ます」
あかねはこどもっぽく返答すると、黒猫を抱きかかえて顔を隠した。
「来月、七日も所によって七夕ですっ。仙台とか……」
………
夏休みの真っ只中、山尾修はアーチェリー部部室で弓具の手入れをしていた。
休みだけども腕前が気になるから。すると、廊下から聞き覚えのあるわらべ歌。
休みだけども腕前が気になるから。すると、廊下から聞き覚えのあるわらべ歌。
『ローソク出ーせー出ーせーよー 出ーさーないとー かっちゃくぞー おーまーけーにー噛み付くぞー』
今日は八月七日。所により七夕。
おしまい。
前:サードアイ 次:ダブルストップ・あなざー